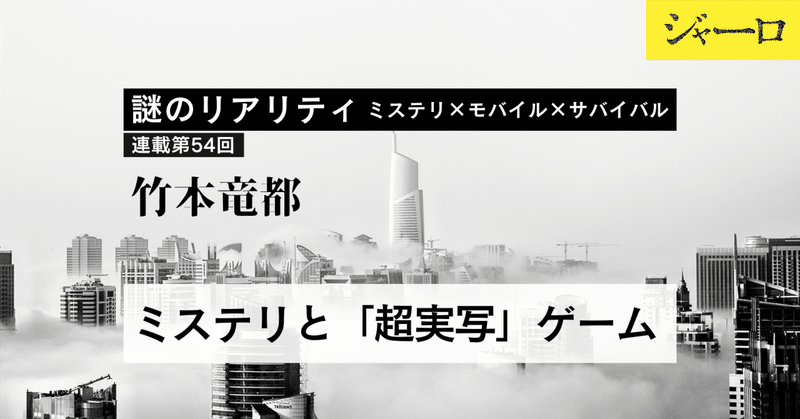
ミステリと「超実写」ゲーム|竹本竜都・謎のリアリティ【第54回】
▼前回はこちら
文=竹本竜都
サム・バーロウ
『Her Story』(2015)
『Telling Lies』(2019)
『IMMORTALITY』(2022)
多様性の加速度を増すいっぽうの社会状況に晒され、ミステリが直面する前面化した問題と潜在化した問題。重層化した「謎」を複数の視座から論ずることで、真の「リアリティ」に迫りたい
前々回の連載担当分において筆者は、レフ・マノヴィッチのいう「オールドメディア」⇔「ニューメディア」、つまりアナログで物理的・固定的なメディア⇔デジタルで可塑的・インタラクティブなメディアという分類を元に、デジタルゲームというニューメディアでありながら擬古的にオールドメディア的な装いをしようとする作品群を「クラシカルメディア」と定義し、その一例としてSquare Enix, Human Head Studios『THE QUIET MAN』を採りあげた。『THE QUIET MAN』は、格闘アクションゲームでありながら長尺の実写シーンを多く挿入し、価格も一般的な映画鑑賞料金と同額に揃えるなど、ゲームでありながら同時に「映画的」であることを強く意識した作品であった。
このような実写を多用した映画的ゲームは、デジタルゲームの歴史において一つのジャンルとして存在してきた。八〇年代に入り、レーザーディスクの登場により映像のチャプター選択・ジャンプ再生が可能になると、その機能を利用し、選択肢を選ぶことで実写映像を再生し、物語が進行するタイプのアドベンチャーゲームが登場することになる。現在に至るまで、この手の作品は、「インタラクティブシネマ」として作られ続けている。近年では、ゲームメーカーではなくネットフリックスのような映像配信サービス側も、視聴者の選択によりその後の展開が枝分かれするインタラクティブシネマを配信するなど、実写ゲームは一般化しつつあり、また映画とゲームとの垣根自体も近づいていると言えるだろう。
だが、ここで重要なのは、インタラクティブシネマは、あくまで本質的には「次にどの映像が再生されるかを選択するだけ」のアドベンチャーゲームであるという点にある。なぜこのような形態になるのかというと、ニューメディアという媒体においても、実写映像は本質的に「固定されている」からだ。実写は一度撮影・編集というプロセスを経てしまうと、その後に動的な変更を加えることができない。登場人物が分かれ道の右に行くか左に行くかをプレイヤーが選べるようにするには、右に行くパターンの映像と左に行くパターンの映像とを別個に撮影・編集しておく必要がある。これが実写によらないCG画面であれば、登場人物をプレイヤーの思うままに動かすことはずっと簡単だ。フィールドを作り、その空間の中でプレイヤーキャラクターを自由に動かせるように設定したり、他のキャラクターがランダムに動くようにしたりすることは、ゲームにおいては基礎的なプログラムだ。だが、この挙動を実写で再現することは現在に至るまでほぼ不可能に近い。これが実写の大きな制約なのだ。
このように、実写という動的に操作できない固定的なメディアを、いかにインタラクティブなものとして=ゲームとして扱いこなすかが現在に至るまで実写ゲームの主題であり続け、そのもっとも無難な回答として、インタラクティブシネマが定番のジャンルとして存在し続けている、という構図になっているわけだ。
さて一方で、この構図に抗おうとする試みも一定数存在している。例えば『THE QUIET MAN』は、選択肢を選ぶことでゲームが進行するアドベンチャーゲームではないという点では狭義のインタラクティブシネマとは言えないが、それでも映画的なゲームであろうとするために、二つの回答を試みている。
ひとつは、「過剰な映画化」だ。ハリウッドの脚本家および制作チームを起用して撮影された長尺の実写映像をあえて長大な尺で入れ込むことで半ば映画のなかにゲームを挟み込むような形でゲームとの融合度を高めようとしているのだ。
もうひとつは、「実写とCGとのシームレス化」だ。実写のキャラクターを模した3Dモデルを作成し、その操作パートをムービーシーンの終わりにシームレスで挟み込むことで、まるで実写のキャラクターをそのまま操作しているような没入感を得させることを狙っている。
だが、この二つの試みは、残念ながら共に失敗していると言わざるを得ない。長大な実写パートはひたすらに退屈で、ゲームとしてはおろか映画としてもつまらないし、3Dモデルはクオリティが低く、実写の登場人物と別人に見えてしまい没入感どころか違和感しかない。「意欲作ではあるのかもしれないが失敗作と言わざるを得ない、いわゆるクソゲー」というのが『THE QUIET MAN』に対する一般的なゲーマーの評価だろう。
ことほど左様に、実写をうまくゲームとして取り扱うことは難しい。だが一方で、『THE QUIET MAN』とはまた異なる方法論で単純なインタラクティブシネマの域を離れた実写ゲーム開発を続けている者もいる。イギリスのゲームデザイナー、サム・バーロウは、その中でも名が知られるクリエイターの一人だろう。『サイレントヒル シャッタードメモリーズ』等のリードデザイナーを務めた彼は、近年はインディーゲームディレクターとして三作品をリリースしているが、そのいずれもが、なんと実写ゲームなのだ。
第一作目であり、彼の代表作とされる『Her Story』は、警察のデータベースに保存されている、とある過去の事件に対する一人の女性への事情聴取動画の断片を見ていくことで、その事件の真相に迫るというスタイルのゲームだ。特異なのは、その動画の断片の探し方だ。データベースにはGoogleのような検索欄があり、そこに任意のキーワードを入力すると、当該のキーワードを事情聴取の対象者が発言している動画がヒットする。その動画を視聴し、そこで出てきた新たなキーワードを入力したり、あるいは思いつきで適当な単語を打ち込んだりすることで更に新たな動画を検索し、視聴することでプレイヤーは物語の断片をつなぎ合わせ、事情聴取を受けている女性は何者か、捜査されていた事件の真相とは何か、あるいはそもそもこのデータベースを検索している主人公は果たして誰で、なぜこの動画を見ようとしたのか、どうやって警察のデータベースにアクセスしたのか、というゲームそのものに関わる謎について理解していくことになる。
ここで重要なのは、一般的なインタラクティブシネマが、ゲームブックのように選択肢はあれどプレイ体験上の時系列が定まっている、直列的な構造になっているのに対し、『Her Story』は、うまくキーワードを思いつきさえすれば、最初からほぼすべての動画にアクセスできる、並列的な構造になっているという点だ。これは、前掲した実写ゲームの特徴である実写メディアの固定性に対し、単語検索というプレイヤーの自由な行動を許すゲームシステムによって可塑性を与えるという大きな意味を持つ。実写が固定的なものであるのならば、その断片の提示方法に大きな自由度を与えることで、従来のインタラクティブシネマにはなかった体験を得ることができる。この斬新なゲームシステム、そしてプレイによって明らかになる魅力的な謎、この二点において、『Her Story』は大きな評価を得た。
『Her Story』の成功を受け、バーロウが新たに制作した作品が、『Telling Lies』だ。アメリカ国家安全保障局から盗み出されたノートPCのデータベースから、四人の人物を対象としたビデオ通話を主体とする録画映像の断片を見ていくことで、その動画に隠された謎とはなにか、なぜ主人公はこのデータベースにアクセスしているのかを探っていくというスタイルになっている。というと、『Her Story』と同じような印象を受けるだろうが、実際、プレイしてみると、システムや物語構造がかなり前作と近いものになっている。大きく違うのは、『Her Story』における動画が、一人の女性への質問に対する供述を切り抜いたものであったのに対し、『Telling Lies』においては複数人によって行われたビデオ通話の録画映像であり、通話している双方の動画が別々のファイルとして保存されているという点にある。つまり、今話している人物は誰で、誰と通話しているものなのか、この時の通話相手方の動画はどれなのか、といったより複雑なタームを孕むものになっているのだ。『Telling Lies』は、『Her Story』の精神的続編と謳われたが、実際のところ、物語的な連続性があるわけではないが、ゲームシステム、あるいはプレイを牽引する謎の構造という点においては強く類似しつつ新たな試みに挑んだ、まさに続編的作品であると言える。
だが、『Telling Lies』は、その新たな試みにおいて、『THE QUIET MAN』と同じく、実写の扱いに失敗していると評価せざるを得ない。具体的には、動画が「ビデオ通話映像」であるという点が孕む問題だ。ビデオチャットは、ただ話している部分だけを切り取った供述映像と違い、「聞く時間」が存在する。つまり、人物Aの側の動画でAが喋り続けていると、そのときの通話相手である人物Bの動画では、Bは聞いているだけになる。この聞いているだけの動画には、基本的には有効な手がかりはないし、映像的にも何ら面白みはない。早送り機能はついているものの、それを使ったとしても、プレイヤーにとっては退屈であるか余計な手間がかかるか、どちらかの印象を残す。
また、人物が増え、物語が複雑になったことで、動画自体も圧倒的に長尺化した。『Her Story』における供述動画が数秒から数分の断片であったのに対し、ビデオチャットは数分から数十分のものが多々あり、その動画の中から有用なキーワードを探すためのザッピングは、プレイヤーに大きなストレスを与えるものであった。『Her Story』が実写をミニマルな形で扱ったのに対し、『Telling Lies』は実写をより複雑で拡張的な形で扱ったが、そのことが裏目となり、退屈で冗長なゲーム体験をもたらすことになってしまった。物語上の謎も二番煎じ感が否めず、『Her Story』のような新鮮な驚きが得られなかったこともあり、結果、高い評価を受けた『Her Story』と比較して、『Telling Lies』は失敗作として評価されることになっている。
だが、『Telling Lies』への低評価にもかかわらず、バーロウは新たな実写ゲームをリリースする。それが『IMMORTALITY』だ。この作品も『Her Story』『Telling Lies』に近く、並列的に動画を探し出し視聴することで物語が浮かび上がってくるシステムのゲームだが、大きな変化は、動画探索のシステムが、検索から、映像のポイントアンドクリックによるジャンプに変わったことだ。つまり、映像の中に出てくる人物や物をクリックすると、同じ人物や物が出ている別の動画にジャンプする、というシステムだ。これは、実写に対するインタラクティブ性の付与として、これまでの作品の先を行っていると評価できる(※1)。あくまで単語という文字情報によってのみリンクされていた動画と動画が、『IMMORTALITY』においてはプレイヤーが動画内のオブジェクトに直接インタラクトすることでリンクされる形になる。これは、実写ゲームとしての新たな体験をプレイヤーにもたらすものだ。
もう一点は、ゲームの物語構造だ。『IMMORTALITY』は『Telling Lies』と比しても、圧倒的に複雑な構成になっている。この作品における動画は、映画のワンカット、つまり劇映画のフィルムカメラの録画が開始され、停止するまでの一連の映像の断片である。それも、年代の違う三作もの映画のそれなのだ。まったく違う映画のワンシーンの中を行き来しながら、あるいはそれらの作品のリハーサルや台本の読み合わせ、衣裳合わせやオフショットといった動画へと飛びながら、プレイヤーはゲームの構造を理解しようと努める。そして、三作の映画の関係性や、映画制作現場の内外で何が起こっていたのかといった謎を解き明かそうとしていくことになるのだが……。
さて、一旦ここまでバーロウの三作の概要について語ってきたが、改めて言及しておかなければならない点は、この三作がいずれも「ミステリ」であること、それもいわゆる「ホワットダニット(=何が起こっているか)」ものに分類されるタイプのミステリであるという点だ。三作いずれにおいても、その開始時点においてゲームそのものの世界観はごく断片的にしか提示されない。つまり、「このゲームは何を目的としているのか」「なぜプレイヤー≒主人公はこんなことをしているのか」「今プレイヤー≒主人公が操作しているこの画面は果たして何なのか」といった謎がそれだ。これらは単にストーリー上の謎というわけではなく、プレイヤーに対するメタ的な謎の投げかけ、つまり「このゲームは果たして何なのか」というホワットを突きつけるものだ。
特に前二作である『Her Story』『Telling Lies』においては、プレイヤーはわけもわからず謎の動画を見て、また別の動画を見ていくうちに段々と手がかりが集まっていき、その結果主人公が誰で(フー)いったいなぜ(ホワイ)行動しているのかといった謎の答えを見出すようになる。そして、その謎の答えが、実は動画そのものの謎と密接していることに気づいていくのだ。その意味で、『Her Story』『Telling Lies』は「このゲームは何か」を問う本格実写ミステリゲームだということができる。
一方で、最新作である『IMMORTALITY』は、その枠からも逸脱した構造になっている。動画を視聴していっても、このホワットダニットに対して、前二作のような明確な回答が提示されることはない。それどころか、プレイしていくうちに突然未知の人物がプレイヤーに対して話しかけてくるような動画が再生されたり、すでに見たことのある動画の登場人物が別の人物に入れ替わり会話内容も全く別のものに変化してしまったりと、動画やゲームシステムそのものが何者かによって侵食されていくことになるのだ。結果としてゲームの後半は、「このゲームシステムへの侵食は一体何なのか」、という新たなホワットダニットが主題となってプレイが進行していくことになる。だが、こちらの謎もまた、明確に解き明かされることはない。どうやらこの未知の人物は作中の映画三作品で主演を務めた女性であり、三作の制作年代にかなり幅があるにもかかわらず年齢が変わっていないことや、未知の人物自身の発言からどうやら普通の人間ではなく不死(=IMMORTAL)の存在であることが推測できる、といった程度だ。
前二作のように大体の動画を見ればホワットダニットが解き明かされる、というような構造ではなく、ゲームシステム上の問題を解決したにもかかわらず謎が謎として残り続ける、という点で、『IMMORTALITY』はより難解で答えの見えない、いわば変格実写ミステリゲームであると言えるだろう。そのため本作は、万人受けという評価は得られなかったものの、よりコアな支持を得る作品となった。
最後に、ひとつ言及しておかなければならない点がある。なぜこれらの作品が、ミステリ的要素を含まなければならなかったか、という点だ。
今まで見てきたように、バーロウは実写を単に直列的で固定的な選択肢として取り扱うのではなく並列的でインタラクティブなものとして取り扱おうとしていることがわかるだろう。実写を単なる固定的な映像に留まらせずに拡張しようとする試みが、彼の作品からは見て取れる。そのために彼が選択した手法が動画の並列化であり、それらを繋げるシステムとしてのキーワード検索あるいはポイントアンドクリックが採用されていたが、これらはいずれも単なる実写映像やインタラクティブシネマを超えた、別次元のインタラクティブ性を付与するものだ。この点において、バーロウは明らかにこれまでの実写を超えた「超実写」ゲームを指向している。最新作『IMMORTALITY』の題材が実写映画という代表的実写メディアであり、さらに多数の作品の混在やプレイ中の動画の入れ替わりといった今のところ映画では実現不可能なシステムを採用することで、映画を徹底的にエミュレートしつつ映画にはない要素を付与している点からも、その指向の一端はうかがえるだろう。
だが、その超実写ゲームが単に複数の動画の集合体ではなくゲームとしての体をなすには、ゲームそのものに対して一定の物語的意味を付与しなければならない。つまり、「なぜプレイヤーはこのゲームをプレイするのか」という問いに対する答えがなくては、ゲームは魅力的なゲームとして成立し得ないのだ。そして、その問いに対するバーロウの答えは、ミステリだった。「問い」はミステリというフィルターを通すことで、「ゲームをプレイしていけば魅力的な答えが見つかるのではないか」という「謎とその答え」の探求へと変化する。それによってプレイヤーは「ゲームの謎を解くためにプレイする」というインセンティブを得ることができるのだ。そして、プレイヤーにとってその謎とその解決が魅力的であったかどうかが、ゲームの評価基準においては大きな比重を占める。その点で、三作はいずれも同じような謎を立てたが、その物語上の解決が生み出す魅力において、評価が分かれる形になった。
超実写ゲームは、必ずしもミステリである必要はない。だが、すくなくともバーロウが採用した並列的な動画の断片を探索するというシステムにおいては、その探索の理由が「物語上の謎を解くため」とするミステリの方法論がもっとも整合的だったのだろう。今後も、超実写とミステリとが結びついた作品が、どのような魅力的な形で現れるのかに期待したい。
※1 実写を利用したポイントアンドクリックゲーム自体はこれまでに多数存在するが、ここまで並列的で多数のリンクをちりばめた作品は『IMMORTALITY』の他に類を見ない。
《ジャーロ No.90 2023 SEPTEMBER掲載》
★2024年は(ほぼ!)毎日投稿【光文社 文芸編集部公式note】
ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。
お気軽にフォローしてみてください!
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
