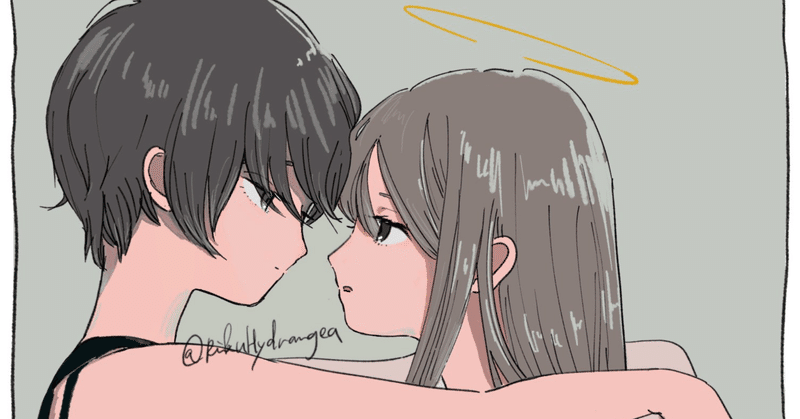
【短編小説】告白されて困ったら両想い
放課後を迎えると予想した通り、前の方の席にいた奏が長い髪を弾ませてパタパタと走り出す。わたしの机の横で立ち止まると、あからさまなモジモジを始めた。ゆったりとした白いワンピースを着ていてもよくわかる。ふくよかな胸の揺れに男子達は、おー、という低い声を上げた。
わたしは心の中で遠慮ない溜息を吐いた。奏を無視して机に入れていた教科書とノートをカバンに収めていく。
その時、奏は小声で言った。
「いじわるぅ」
「何もしてないじゃない」
怒りの目を横手に向けると、奏は甘ったるい笑顔を浮かべた。
「こっちを向いたね」
「策士か。で、授業中に散々チラ見したほどの相談は何よ?」
「ここには男子がいるから……」
恋する乙女のように頬をほんのりと染める。睫毛は長く、伏せた目は同性のわたしから見ても色っぽく感じる。同じ中学生とは思えない。きっと家のペットが乳牛で、毎朝、腰に手を当てて搾りたてを一気飲みしているのだろう。いや、その発想はさすがにおかしいぞ。
奏は不思議そうにわたしの顔を覗き込む。
「なっちゃん、笑ってる?」
「そんなこと、ない」
口元を引き締めたわたしは席を立った。また男子が、おー、と低い声を上げた。
「いちいち、うるせーんだよ。おまえら、全員ぶん殴るぞ!」
「巨人が怒った」
「マジ、祟られるわ」
「ヤベーって」
小躍りする姿で男子達は教室を飛び出していった。本当にばかばかしい。相手をして損した気分になる。
「失礼だよね。なっちゃんはカッコイイだけなのに」
「その言い方もうれしくない。夏樹さま素敵とか、凛々しいとか……こっちが恥ずかしくなるわ!」
前髪を乱暴に掻き上げた。ダボダボのTシャツにハーフパンツ姿の自分のどこに、先程の要素があるというのか。軽く錯乱したように思えた。
「はい、どうぞ」
奏は自分の左肩をクイッと上げる。身長の関係で手は握りづらい。その代わりとして肩を差し出しているようだった。
「じゃあ、行こうか」
わたしは奏の頭を掴んだ。強引に歩き出すと、ちがーう、と胸を揺さぶって足をバタバタさせる。そんな姿も愛らしく、つい目を細めてしまった。
九月中旬を秋とは認めない。降り注ぐ陽光で肌がじんわりと汗ばむ。
そこで自動販売機に立ち寄った。わたしは微糖のコーヒーで奏はミックスジュース。一級河川を望める階段に二人で座って喉を潤した。
「もういい加減、相談内容を教えてくれてもいいんじゃない」
「……それなんだけど、なっちゃんは好きな人っている?」
上目づかいで言われた。即答はできず、少し考えてみる。
「NBAの選手ではダメかな」
「アイドルもダメ。もっと身近な人で」
「同じクラスのバカ共は対象にならないし、どうだろう。ちなみに奏はどうなのよ。身近に好きな人っている?」
何げない言葉に奏は顔を赤くした。手の中の缶を意味もなく回し始める。
「……いるよ。そこで相談なんだけど」
「いるんだ。もしかして告白に迷っているとか」
「そう、どうしたらいいかな」
手の中で回す缶をじっと見つめる。長い睫毛に目が引き寄せられた。恥じらう姿まで愛らしい。
「奏の気持ち次第だと思うんだけど」
手の中で回していた缶がぴたりと止まる。奏は中身を一気に飲み干した。
「好きだと思う。相手の気持ちは全然わからないんだけど」
「フラれることに怖がっていたりする?」
「ダメなら仕方ないんだけどね。気持ち悪いと思われるのは想像するだけでちょっと辛くなって……」
奏は寂しそうな顔で笑った。わたしは小さな肩を掴んでこちらに強引に向かせる。
「奏が気持ち悪いわけないじゃん! 長い髪はツヤツヤで天使の輪っかができるし、ぱっちりした目はきれいな二重でマジ天使とか本気で思うよ。だから自信を持てばいけるって」
「告白して、相手が返事に困ったら?」
「それは両想いってことだよ。考えてみなよ。どうでもいい相手から告白されて、迷うなんてこと、絶対にないから。わたしがクラスの男子に、仮にだよ。告白されたら顔面にダンクシュートを叩き込むよ、マジで」
奏の目を見て熱弁を振るった。心の中でクラスの男子は鼻血を出して倒れ伏す。顔面ダンクで墓標のない墓場と化した。
「なっちゃんのおかげで、元気が出たかも!」
「その意気だよ!」
「今日、告白するね」
「え、今日なの? まあ、わたしが背中を押したんだけど、もう少し考えてからでもいいんじゃないかな」
小鼻を膨らませた奏にわたしは宥めるような笑みを向けた。
「早く決めないと気持ちが揺らぐかもしれないし」
「言われれば、うん、その通りだよ。わたしも応援するから」
「じゃあ、告白するね」
「うん?」
わたしは笑顔のまま小首を傾げた。
「カッコイイなっちゃんのことが前から好きでした。わたしと付き合ってください!」
「ええっ、告白の相手ってわたし!?」
「今、返事が欲しいな。もしかして困っているの?」
「そ、それは当然だって。同性だし。友達から告白されるなんて、考えたこともなかったよ」
目を合わせられない。小さな身体にわたしは気圧された。
逆に奏は勢い付いた。ふくよかな胸をわたしに押し当てて言った。
「なっちゃん、困ったら両想いってことなんだよね!」
「それは……」
自分が口にした言葉に追い詰められる。奏は頬をプルプルと震わせて見上げてきた。潤む目を逸らさず、泣きそうな顔で返事を待った。
健気な姿にわたしは無意識に奏の頭を撫でた。予想以上の震えが掌に伝わると横目になった。
「その、これからもよろしく」
「なっちゃん、大好き!」
小柄な奏に抱き締められた。顔が熱い自分にわけがわからず、わたしも好き、と朦朧とした頭で口走っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
