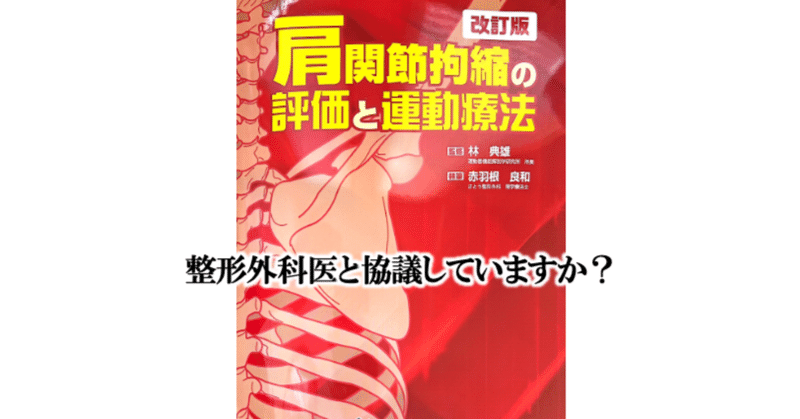
肩関節拘縮の評価と運動療法【第4弾〜関節拘縮と疼痛との関係】
みなさん、こんにちは!
運動器理学療法の革命児です。
今日も1日仕事、学校お疲れ様でした。
みなさんの貴重な時間をいただいて読んでくださる方にはいつも恩返しをしたいと思っております。
図々しいのは承知なのですが、♡をクリックしていただけると嬉しく思います。
ぜひ、押してください。
フォローも宜しくお願いします。
今回のテーマは肩関節拘縮の評価と運動療法です。
私は臨床で林先生、赤羽根先生の評価・治療を参考にしています。
その一部を紹介して、私なりに所見の解釈、そして検証作業を行い、病態を明確にしてから治療に専念しています。
第1弾です。
続いて第2弾
第3弾です。
ここからが第4弾です。
肩関節障害は、骨折や脱白などの外傷後に続発する拘縮や、肩関節周囲炎をはじめとする変性を基盤に発生した拘縮が、原因となっていることが非常に多い。
これらの拘縮は、関節包炎、腱板疎部損傷、上腕二頭筋長頭腱炎、腱板炎、肩峰下滑液包炎など、炎症後の修復反応として各組織間に癒着や療演等によって生じる。このため、その運動療法では、対象となる組織のリモデリング過程を援助することが重要となる。
また、関節拘縮に対する治療戦路としては、"安定した関節 ”の再獲得が最大の目的であり、これは各関節障害に対するリハビリテーションの共通した基本概念である。
このため、ここでは、"安定した関節 ”と“不安定な関節” の基本概念についても説明を加えたい。
その上で、関節拘縮を基盤とした関節障害の基本的な考え方について説明する。
関節拘縮と疼痛との関係
サポートお願いします🙇 活動費として使わせていただきます。
