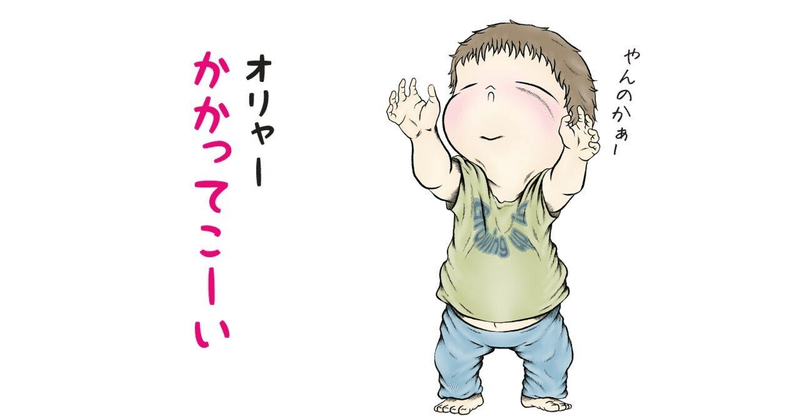
罰則・引き締め・監視強化【学校編】(4)
ところでどうしていた
ところで、しばらく前から学校の図書室には朝の時間帯に鍵がかけられていたわけで、その間、特に家から本を追加で持っていくわけでもなく、どうしていたのかと訊いたら、「友達と本を交換すれば大丈夫だった」と返ってきた。
長男自身が上限の10冊しか借りられなかったとしても(実際にはこの上限も守らなかったと思われるが)、クラスメートと交換すれば数十冊読めてしまう。
長男はあの手この手と色々と考える。それに対してさらに監視なり罰則が厳しくなるのが現実だ。長男もどんな展開になるかは大体予想がついているはずなのだが、だからといって最初から諦めるでもない。
ある学校関係者から、「ルールの破り方ばかりを身につけても・・」と言われたこともある。この言葉は重い。
誤解のないように、長男は交通ルールなどはしっかり守る。公共交通機関等で騒いではいけないといった暗黙のルールだって言われなくても守る。チームプレーのスポーツのルールだって問題なく守る。
長男を擁護するわけではないけれど、子供を管理するために作ったルールと感じられるもの、無ければないでいいではないかと思えるルールは、長男にとっては守る意義を感じにくいのだと思う。図書室に制限がかかった今も、「図書室なんて最初からいつでも自由に使えるように開けとけばいいのにね」と、仕方ないけどという風だった。
長男にも分かってほしい
今回、以下のような出来事があって図書室に鍵が掛けられてしまった。
①司書さんが長男の貸し出し手続きを免除してくださっていた
②担任の先生がこれを知って、みなと同じルールで借りましょうと言った
③長男「わかりました」と言いつつ、貸し出し手続きをせず借り続けた
④朝図書室に行くことを禁じられる
⑤禁じられても朝行って借り続けた
⑥朝図書室に鍵がかけられるようになった
⑥は学校としての判断なのだろうと思う。
長男には、「あんたが貸し出し手続きを守らなかったんだよね?」と訊くと、「お恥ずかしながら・・」と返ってきた。
この件に限ったことではないのだが、人がやめてほしいということをやるというのは、相当に人を不快にさせるのだということを長男には何度も伝えている。
また長男には、お前はこれ以上近づいたら撃つぞと言われているのに、撃つほどのことじゃないでしょうと言って、警告を無視して行動しているようなものだよと言ったこともある。
普通、撃たれたらどうしようかとか、撃つほどに相手を怒らせてはいけないと考えると思うのだが、自分ならこの場合撃たないと思ったら軽く受け止めてしまうのだと思う。舐めてるのか?と逆に人の感情を悪化させてしまう。
家庭内でもここは時々しんどい。もともとの問題が大した話でなくても、相手の気持ちをどう思っているんだ?という事を問題視したくなることがあって、たまになんでこんなにわからず屋なんだ?と思って苦しくなることがある。屁理屈が加わるともうしんどい。
ここの部分はギフテッドと切り離して長男の性格であると考えたい。一般化しては申し訳ないと思っている。
(5)につづく
