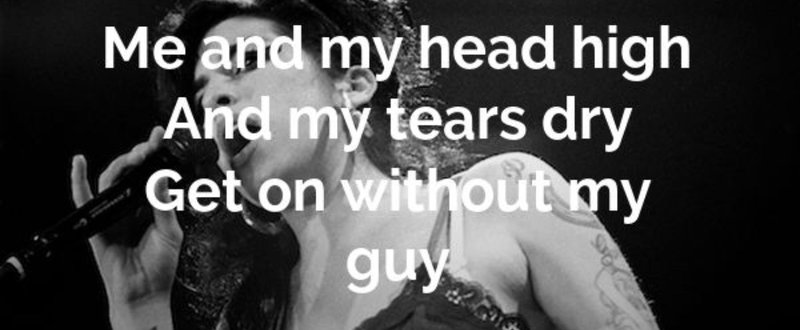
急落する恋
三橋さんは、わたしの胸鎖乳突筋を甘噛みしてから言った。
「おまえ俺の彼女になれよ」
わたしは荒い息の合間で「うん」と返事をした。その3か月後には三橋さんとは連絡が取れなくなった。
photo : Amy Winehouse "Tears dry on their own"
わたしは、女好きで有名だった三橋さんが異動してきて3か月くらいで、あっと言う間に彼の手に落ちた。その頃、三橋さんにはまだ彼女がいた。前の部署の彼の同期の女。わかっていてわたしは彼と寝た。呆れた女だ。まあしょうがない。わたしは恋多き20代だったし、三橋さんは前評判通り、めちゃくちゃ仕事ができて、しかもグッドルッキングガイだった。
それに、20代の男女が毎日、深夜まで一緒に残業していれば、まもなく朝まで2人で飲み明かすことになるし、まもなくそのまま2人で彼のマンションに帰ることにもなる。自然の摂理だ。抵抗する方がナンセンス。
その日、新橋の和民でレモンサワーを飲み干したわたしは、さっきからずっとわたしの手を握っている三橋さんに言った。
「一緒に帰りましょうよ。」
わたしも三橋さんもかなり酔っていた。
「え?まじで?いいの?」
「いいですよ。ここまで来たらそうなるでしょう。」
わたしは繋いだ右手の親指で彼の手の甲を撫でて言った。
「ほ、ほんとに?おまえ変わった子だねえ。いや願ったりかなったりだけども、俺は」
三橋さんは酔って眠そうな目を見開いて、驚いていた。
その夜を経て、行為に夢中になったのは三橋さんのほうだった。勝算があったから夜に持ち込むことにしたわけだが、わたしは一夜でほとんど欲しいものを勝ち取った。それから深夜残業のたびに、彼はオフィスでも部屋でも所構わずしたがった。エレベーターで二人になったらキスし、部署の飲み会ではわたしの隣に座り、机の下で腿の間に手を入れた。その秘密が、冒険が、わたしたちを益々燃え上がらせ、どんどん大胆にした。
一方で彼女との仲はまだ切れていなかった。それでこそ三橋さんだ。連休明け、彼はわたしにハワイ土産をくれたのだが、一緒に行ったのが彼女であるという情報は、別の筋から入手済だった。わたしは社内イントラで彼女の顔も確認し、同期ネットワークから彼女の評判も獲得し、「大した敵ではない」と結論を下していた。
ある休日の夕方、『おまえ今日なにしてんの』とメールがあった。『家で仕事です』と返すと『飯食おうよ』と返ってきた。目黒の彼の部屋に向かうと、彼は手際よくパスタを作ってくれた。岩塩とオリーヴオイルと桜えびのシンプルなパスタ。彼がピンクソルトを取り出したときわたしは一人、心の中で笑った。クレジットカードはアメックス、カフスとタイピンはブルガリ、なんだか全体的にそういう人だった。
わたしはソファでパスタを口に運びながら言った。
「希美さん今日何してんすか」
彼女のことだ。
「え?おまえ・・怖いこと言うね」
「いや、有名でしょ?三橋さんが希美さんと付き合ってるの」
「いやおまえ・・こわいよ~なんだよ~」
「はは」
「そんなことより美味いとかなんとか言えよ」
「美味しい!!すごく」
その後、代わりに皿を片付けるわたしを後ろから抱きしめた彼は、わたしをそのままベッドに引っ張っていった。まだ泡のついたわたしの両手をタオルで軽く縛って、首を噛んだ。
「おまえ俺の彼女になれよ。もう希美とは別れたよ」
ラッキー、と思った。うまくいった。わたしは甘えた声を出して、うん、と答えた。
でもその夜がわたしたちのピークだった。なぜだろう。関係が曖昧だったとき、仮想敵としての本命彼女がいるときのほうが、わたしたちはうまくいっていた。わたしたちを彩っていた背徳が、スリルが、そのネオンサインのような蛍光色が、見る間に消えていくような感覚だった。
彼もわたしも、典型的な、「手に入れるまでが楽しい」人間だった。わたしは、百人斬りの三橋さんを夢中にさせたことでもう十分満足してしまっていたし、関係を維持することは不得意中の不得意だった。始めたからには続けなければという強迫観念と、続けることに対する苦手意識から、自由奔放なわたしは突然、世に溢れる「大事にされる女になるためには」ノウハウ本から抜け出してきたかのように真面目に振舞った。
結果、2か月も経つ頃には、デートは、義務感で外形を固められただけの、中身が空洞のレプリカ彫刻のようになった。3か月で三橋さんからは完璧に返信がなくなった。その彼の非礼に耐えられなくなったわたしはある日、オフィスを去る彼を追い、会社のエントランスで捕まえて、「ちゃんと別れましょうよ」と告げた。ごめん、と彼はつぶやいて、とりあえず通りの向かいの居酒屋に入って、1時間ほど話した。
わたしは冷静だった。すこし傷ついたふりをして、彼のことが好きだったと言ってあげた。でももう終わりにしたほうがお互いのためだ、わたしは平気だと思う、と言ってあげた。実際のところは、わたしにとってはとっくに死んだ恋愛だった。正直、せいせいしたという気持ちのほうが強かった。
一方の三橋さんは。
翌日から、また以前のように、オフィスでわたしに明るく話しかけるようになった。飲み会でもまた隣に座り、軽く肩や背中に触れる程度のことはやってのけた。その様子は、鎖を解かれて翼を伸ばす鳥のようだった。ものわかりのよい元カノと、また明るく友達になれるとでも思ったのだろうか。
なんだそれ。
わたしにはさっぱり、さっぱりわからなかった。その神経が。
彼が誕生日にくれたオープンハートは、すぐに質屋に売った。4千円にしかならなかった。たった4千円。上等だ。いい気味だ。わたしは4千円できれいさっぱり清算する。終わった恋愛なんて、わたしたち女にとっては、そんなもんだ。思い知るがいい。
ああ、ステディって難しいな。懲り懲りかも。4千円を財布にしまいながらわたしは、曇った空を見上げて溜息をつくのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
