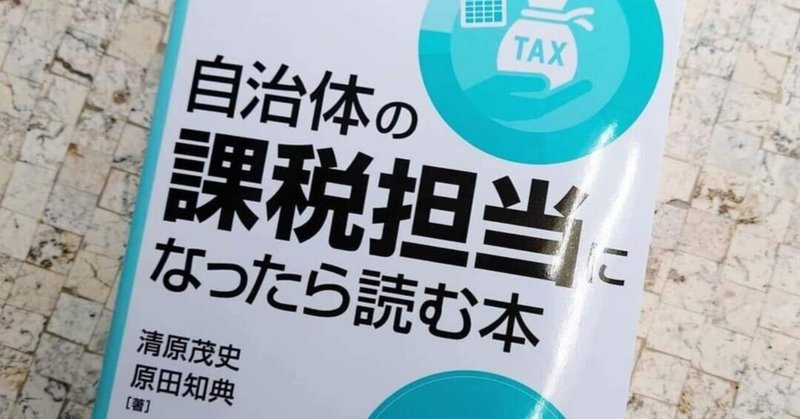
「自治体の課税担当になったら読む本」の読書感想文
1.まえがき
■今回、私が初めて著作者である筆者のお一人の原田知典さん(以下、筆者という)から献本を頂いたことから、筆者のその意思に応える、そして可能な限り私のこの本の記述に対する疑問点は事前に筆者に質問もしながら、そもそもこの本には法律事項の記述が多数ありますので、そこを税務の専門家でもない私が誤って解釈しないように気を付けて、最終的にはこの本を読んでいる人を念頭に置いて、この感想文を書くこととしましたので、「先ずは書店でこの本を手に取ってもらいたい」と思っています!
■そして、そもそもなぜこのような自治体の課税担当向けの本が今必要になっているのかについて、MBAとしては自治体における取り巻く外部環境が変化していることによるものではないかとの仮説を置きました。そのため、その要因分析として、それをMECEにロジックツリーに落として、この仮説を確からしくするために自治体の職員とコミュニケーションしながらこの感想文を書きましたので、この本の重要性・貴重性、特にMBAではあまり学ばない税務会計について、行政書士の立場として、この感想文の中で表現したいと考えているところです。
■では、残念ながら、私はこの本のメインターゲットである「自治体の課税担当」ではないことから、現在は行政書士ですが、行政に長く携わってきた国の元一職員という違った視点から、この本の論点整理をして行きます。また、政令・省令、そして関連する通知や事務連絡まで含めて、その法律等の制定には何故その法律が必要と考えられたかについての国民からコンセンサスが得られた上での明確な柱となる主旨、そして目的がまずあって作られたということは、今更、自治体の職員の方に申し上げるレベルのことではないので、あえて書きません。
■そのことから、この感想文では特に筆者が気づきやと問いを立てられている各章の最後のCOLUMNについてそれに対して私なりに意見を述べる形でこの感想文を構成して、そもそも法律の主旨・目的に意識を向かわせることが、納税義務者である住民の気持ちに寄り添うという意味においても如何に大切かについて、出来る限り筆者と同じ気持ちで書き進めたいと考えています。
→なお、私は国家公務員としての仕事での思考法は、6W3Hだったと後ほど書いていますが、その中にサイモン・シネック氏のゴールデンサークル理論も含んでいるものの、最初には現場のWhoを置いています。この感想文の最後には、結論として、自治体の課税担当は基より、全ての自治体の職員が、真剣に、そして気兼ねなく国に法律等について問い合わせる際の肝になるポイントを記述しますので、是非、参考にしていただけたらありがたいです。ですので、この感想文のターゲットはこの本を読むであろう、現場のWhoとして自治体の職員及び広く公務員等としたいと思います。
■まえがきの最後として、この本の章立てに沿って感想文を進めますので、最初に章の構成は一旦ここに書いてから、いよいよ本論に入りたいと思います。
〇本論
第1章:課税担当の世界へようこそ
第2章:地方税の基礎知識を押さえよう
第3章:住民税の課税業務は何をするの?
第4章:固定資産税の課税業務は何をするの?
第5章:一歩先に進むために+α
〇結論
第1部:筆者の言わんとする「ミッション・ビジョン・バリュー」は何か?
第2部:私のこの本での「ミッション・ビジョン・バリュー」は何か?
Ø 以上を、最初のまえがきと、最後のあとがきにサンドイッチしたのが、この感想文の全体構成となりますことを、読まれる方へのガイドとして最初に書かせていただきます。
2.本論
(1)第1章:課税担当の世界へようこそ
1-1税務はとても大切です
Ø この本に、はじめには特にはありませんので、第1章の1-1で、まず「あなたの自治体の税収はどれぐらい?」との表題で入り、具体的には令和3年度についての総務省からの出典資料の図表1で、市町村の地方税収入の分かりやすい円グラフで示されています。
Ø 勿論、カラーであればもっと分かりやすいとは思いますが、それでもマクロでの市町村の財源の状況が一目瞭然で分かりますから、そもそも自治体の財源について殆ど知識がない初めて課税担当になった方ほど、本当に全体の財源のイメージが概略つかめる資料だと思いますので、この本論は、なぜ私がこの本を書店で手に取って読んでもらいたいと書いているかの理由を書きたいと思います。
Ø ただここで、筆者から「ご自身の自治体について、以下の3点の項目は最初に確認をしておきましょう。」とありますので、
① 財政規模
② 地方税収入のおおよその金額
③ 歳入額に占める地方税収入の割合
私も、改めて自分が住んでいる白井市の現状と比較検討をする必要がありますから、白井市の市政だよりからの資料を下に張り付け、先程の図表1と比較して自分が実際に住んでいる自治体の現状分析の感想を少し記述したいと思います。
Ø令和5年度の白井市の歳入比率グラフ及び金額表


※資料:白井市「広報しろい(2023年3月15日号)」より
・この本では、市町村全体の一般財源額として61兆4,051億円となっていますが、それをまず、①の財政規模で比較すれば、白井市は213億1,291万円ですから、それからすれば3.47%程度の規模にはなります。
・次に、②の地方税収入のおよその金額としては、本ではこの52.2%である32兆705億円ですが、白井市は市税合計が、96億2,952万円となります。
・最後に③の歳入額に占める地方税収入の割合は、左の円グラフにあるように45.2%ですから、全体と比べると7%程マクロのグラフの数値より、白井市では市税が占める割合が低いこととなります。
→このデータから勝手に私が推測できることは殆どありませんが、基本的に人口が5万人を超える市で、それほど高齢化率も現状高いとは言えず、また東京のベットタウンである千葉ニュータウンに所在することから、全体のマクロでの市税の割合は高いと予想していましたが、逆に7%程低いということで、それほど市として稼げている自治体とは言えないのではないかと改めて感じたところです。
・なお、注意事項として令和2年度及び3年度は新型コロナの影響で通常の歳入割合と大きく異なる場合があるとありますが、これは令和5年度の予算という最新情報ですので、白井市の通常時にかなり近い状況だと考えられます。(参考データ:白井市の現状の人口は、約6万3千人程度、高齢化率は28.1%となっています。)
Ø 地方税収入以外の収入については、厳密に比較すると、この本とは項目が違う部分もありますので、単純に比較はできませんが、地方債は別にしても、地方交付税や国庫/都道府県支出金などは、マクロと比較しても、おおよそ同様の状況ではないかと、この数値からは推測されます。
1-2税務の役割分担及び1-3課税業務の3つの特徴
Ø この部分については、実際の自治体の担当者が自分の自治体のシステムと比較したり、また心して税制の部署に就いて貰いたいという筆者の気持ちからの事前の念のための注意事項であり、少なからず自治体のどんな部署に就いてもだと思いますので、私から感想めいたことは割愛させていただきます。
1-4課税担当で磨く3つの力、1-5課税担当が感じるやりがい及び1-6課税担当に必要な心構え
Ø ここから私の好きなポジティブシンキングでだと思いますが、まず「課税担当の仕事は自己研鑽のチャンス!」との表題で入り、その1で法令運用力、その2で説明力、その3で段取り力が磨かれるのがこの課税担当者の仕事だということですので、課税担当の皆さんも存分にそのスキルを磨く意識で日々の業務に取組むことを勧められています。
Ø また、1-5は課税担当のやりがいの大きさを特に強調されていますが、私として自治体のどの部署に就いても、これは心がけ次第で感じられると思いますので、確かに課税担当として感じる特別な感情はあるかもですが、全ての自治体職員の方、そして全ての公務員が感じてもらいたいことだと私は考えます。
Ø 最後の1-6の心構えの話は、1-3の課税業務の3つの特徴における注意事項に近い内容ではありますが、最後の「アンテナを高く張る」はこれも自治体の業務全般に言えることではあるものの、税制は毎年改正されるものであり、5年に1度は大幅な全面見直しが行われますので、昨年までの正しい知識が正しくなくなるわけですから、グローバルでの経済ニュースなども常にチェックしながら、最新の情報にバージョンアップし続ける意識が課税担当には必要だと、社会人として前向きに考えていただきたいと思います。
<COLUMN1>
→いよいよ私が特に今回の感想文の中でこだわりを持って書きたいと考えているCOLUMNですが、最初のテーマは「配属されたら最初に何をする」という表題です。
Ø 答えとしては、ここに書いてあるように、まずこの本を読むことです(笑)
勿論、その他に職場で前任者が作った引き継ぎ書やマニュアルにも目を通す必要はあるでしょうが、まずはこの本を読むことだと私も思います!
後はここにあるように、課税担当の「装備」として、12桁電卓、指サック、地図、それとセットで三角スケール、そして家屋の実地調査用のメジャーやスリッパなどが必要だということですので、早めに用意をしておくのが仕事が出来る公務員だということですね!
Ø 最後に、私なりに皆さんにアドバイスできることがあるとすれば、マニュアルは読むことにはあまり意味はなく、それを自分で作り替える、改善することに本当の意味があります。また引き継ぎ書も、異動が決まって慌てて作るのではなく、日々の自分の業務の自己点検と考えて、こちらも日頃から定期的に作り替える作業が重要です。是非、皆さんも心掛けてください。
(2)第2章:地方税の基礎知識を押さえよう
2-1税を納めるのは法律で決まっているから
Ø まず、住民の方から「なんでこんなに高い税金をはらわないといけないの?」と聞かれた時の心構えとして、「納税」は日本国民の三大義務の一つだと誰もが知っている憲法の常識から入りますが、それを法律的に説明した場合の基本的な考え方についてだと思います。
Ø ただ、住民の方が全て憲法・法律の常識から入る方ばかりではありませんから、自分の考えから入る方の方が多いと考えれば、その方にもきちんと説明して、納得してもらえる分かりやすい説明が必要だということだと思います。私としては、国税とは違い、ここにある地方税は『応益原則』という考え方、また『負担分任原則』という考え方が色濃く出ていることを知って、税制としてとても勉強になりました。
2-2税の種類と分類を押さえよう
Ø そろそろ税制の専門的な、課税担当としてのマニアックな話に入ってきますので、そちらの系統の大学の学部を卒業されている方は、その教科書を引っ張り出して一緒に比べて読むのも一考かと感じました。
Ø ただ、たぶんですが課税担当としては、常識的な税制の基本の話だと思いますので、ここは教科書的にしっかり覚えるしかないと感じました。
→ここで、ちょっと余談ですが、図表4の課税体系の中に、冒頭の国税―普通税―収得税の中に、森林環境税は入っていますが、この図表にもう一つのセットである、森林環境贈与税が入っていません。元農林水産省職員としては納得がいかないので、筆者に質問したところ、この図表は令和4年度資料を基にしているが、令和5年度資料を見ると、確かに森林環境贈与税が、国税―目的税として入っていると回答がありましたので、確かに財源的にはインパクトがある税ではありませんが、このように毎年、税制は何らかの見直しが行われていて、非常に複雑であることからも、かなり注意して勉強しておかないと専門家でも見落とす場合があると、改めて認識すべきだと思いました!
2-3課税業務の枠組みを理解しよう
Ø まず、「課税に関わる5W2H」とありますが、私は通常の仕事で、6W3Hで仕事をしてきましたら、これが多いとは感じませんが、その内容は全く違うので、税制の5W2Hだということですね!
Ø 私がここで理解に苦しんだ、難解だと感じたのは、What(課税客体(課税物件))とWhom(納税義務者)の定義の分離についてです。納税義務者は課税客体が帰属する者ですから、単純に住んでいるその人と考えると思いますが、特に課税客体が、個人住民税は具体的な「物」ではなく、住所があるという「事実」や「所得」に課税されるとありますが、住民にこれを言って、果たして「そうですね!」と納得される方は殆どいないと思いました。
→ここは、私から特に筆者に何度も質問をして議論をしましたが、個人地方税の『応益原則』と整合するようにこれを説明するのは本当に難しいと感じましたので、自治体の課税担当はしっかり理解をして、住民の方によどみなく分かりやすく説明をしてもらいたいと思いました。
Ø 他の5W2Hについては、手順の考え方として読めばそれほど理解に苦しむことではないと思いますし、最後のWhy(課税の根拠)はしっかり課税担当として勉強するのは責務だと、私も強く感じました。
2-4課税業務の関連業務を理解しよう、2-5主な市町村税を見てみよう及び2-6租税原則も知っておこう
Ø 特に最後の2-6は、そちらの系統の大学の学部を卒業されている方は、その教科書を引っ張り出して一緒に比べて読むのも一考かと思いますので、私からは割愛しますが、2-4や2-5については課税担当として常識的な知識や手順の話ですので、しっかりマニュアルのつもりでこの本を読むことをお勧めします。
<COLUMN2>
→そしてCOLUMNですが、次のテーマは「国税と地方税の違い」についてという表題です。
Ø ここでは、税の3つの役割(機能)について記述してあります、①財源調整機能、②所得再分配機能、③経済安定化機能の3つについてです。個別の機能については、このCOLUMNに詳しく書いてありますが、②と③は国税の機能とされていますので、要は地方税の機能は、①財源調整機能だということになります。
Ø そして、国税は『応能原則』が強くなり、地方税は『応益原則』に基づくということが書いてあります。つまり、地方税を理解するためには国税も合わせて知り、理解することが必要だということだと思います。
Ø 結局、最後に判断する場面で、国と税制について議論する場面も自治体の課税担当として出てくると考えられますので、その時にしっかりと議論が出来るスキルが必要だということだと思います。
→そして、いよいよ本論のメインである地方税の第3章に入ります!
(3)第3章:地方税の課税業務は何をするの?
3-1住民税の概要
Ø まず「市町村の基幹税としての住民税」という表題で、法律に住民税という定義はなないが、一般的に市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と言っているとあります。また住民税には、個人住民税と法人住民税があり、冒頭の第1章のマクロでのこの本の図表と同じく、図表11税収入の税目別割合の資料を見ても、市町村税だけで見ると、その2つの住民税が46.9%を占めており、次に固定資産税の40.6%となっていることから、この2つで全体の9割近くを占めていることとなります。
Ø ここで示されている円グラフとの比較をする必要性を私自身が感じたので、ここには第1章の1-1にあるような筆者から「ご自身の自治体について、以下の3点の項目は最初に確認をしておきましょう。」はありませんが、第1章と同様にデータの見える化をしておきたいと思います。
① 財政規模
② 地方税収入のおおよその金額
③ 地方税収収入に占める各税目の割合
Ø令和5年度の白井市の地方税比率グラフ及び金額表

※資料:白井市「令和5年度当初予算の概要」から
・この本のマクロのデータでは、住民税が46.9%を占めていますが、白井市では市民税として46.6%ですのでほぼ同じ、また固定資産税は40.6%となっていますが、白井市も42.0%ですからこちらもほぼ同じであることから、マクロでもこの2つで全体の9割近くを占めていることと、ほぼ同様の税目の比率であることが読み取れます。
→このことから、住民税や固定資産税といった地方税の歳入については、白井市はマクロでの全国的な平均構成であるとも言えるのではないかと感じました。
なお、このような定量的な分析は、比較対象との差分により物事の要因を論理的に分析することが出来ますが、今回はマクロでの全国的な平均構成とほぼ差がないということですので、自分が論文等を書くために更に深堀した要因分析をやることに大きな意味があるなら別ですが、費用対効果分析の考え方からも、ここではこれ以上の分析は行わないこととしました。
3-2住民税担当の仕事の全体像
Ø 最初に、図表17業務スケジュールで、住民税の担当が年間のどのタイミングで何をする必要があるのかの大まかな内容が、いわゆるガントチャート形式で書かれており、以後はそのスケジュールでの時系列で、主な仕事の事項の内容を細かく記述している冒頭の説明になります。
3-3誰に課税するのか
Ø 納税義務者、その1、住民票のない市町村で課税される個人、その2となりますが、その次にいよいよ住民の方には理解が難しいと感じるであろう課税客体ことが、均等割(家屋敷課税)、及び所得割について定義が書いてありますが、所得割の「所得」に課税するというのはまだ分かりますが、均等割り(家屋敷課税)の「事実」に課税するというのが私には今一つピンとこなかったのですが、実は今、自分の一般社団法人の法人住民税についての確定申告書を作成して、法人住民税は住んではいない事務所にも当然課税されます。
これは、その街でお店などの事務所を開くと市の提供する上下水道や道路などの公共サービスを利用するだろうということからの「地域の会費」(=負担分にの原則)と捉えられるのだと、法人住民税から改めて考え直したところです。
Ø ただ、次に「賦課期日」の説明があり、基本的に住民税は1月1日の時点での課税になりますので、後々にこの前後での住所に異動が生じた場合の考え方について、その後の志望のケースも含めて、筆者に何度も詳細を確認しましたが、行政書士として非常に参考になりました。
3-4いくら課税するのかについて①~⑨
Ø サブタイトルで①~⑨で課税からその所得控除の考え方まで、事細かに記述されていますので、課税担当はこれを読めば本当に熟知できると思います。そして、所得控除考え方について書いてあり、の有名な「ふるさと納税」について、このまま試算に使える数式も挿入してありますから、勿論、ここの数式を使って、ふるさと納税をやっている多くの住民の方が、自分の限度額を算出することも可能です(笑)
Ø ということで、住民の方がここの章をしっかり理解すれば、節税にも活用できるほどの内容ですので、自治体の課税担当のための本ですが、この本を住民の方が買ってこの章を読めば住民税を納める、納税義務者にとっても節税のためには特に必読の章だと思います。
3-5どのように税額を伝えるか(納税の告知)、3-6住民税がかからないケース(非課税)及び3-7税額が低くなるケース(減免)
Ø 3-5の納税の告知は課税担当者として読むべき内容ですが、一方、3-6及び3-7については、3-4の中にある所得控除と同じで、住民の方にとって節税となるケースが書いてありますので、この部分についても行政書士の私もですが、住民の方が特に読んでいた方がよい内容だと感じました。
Ø 内容の詳細については割愛しますが、特に減免については地方税法で「減免することができる」規定となっていますので、条例で定めるか定めないかについては、自治体自身が決める権利がありますから、住民の方は必要があれば、必ず市町村の課税担当に確認するべき事項になると思います。
3-8証明書の発行及び3-9よく尋ねられる住民からQ&A事例集
Ø 証明書の発行業務については、業務スケジュールの詳細な手順の説明になる、またQ&A事例集については住民の方から、地方税においてよく聞かれることを課税担当として直ぐに使えるマニュアルとして書いてあると思いますが、内容としては住民の方からよく聞かれるのは、基本的には前年と比べて税金が高くなった、また何か節税になる制度はないのかということになるかと思います。
Ø 勿論、税金が高くなったのには明確な根拠があると思いますので、課税担当はそれを住民の方が納得できるように説明するのは責務ですが、一方、節税つまり非課税や免除に該当するケースの有無については、このような税制を勉強して住民が自ら自治体に申請するのがこのような制度の基本となります。これは税制に限ったことではなく、補助事業等を含め国の制度としてそのような申請主義となっていますので、もし疑問点があるようなら、時間的にはお近くの行政書士か税理士に確認いただくのが一番素早い対応かと思います。
Ø なお、この中にやはり「ふるさと納税」に関するQ&Aが登場します。そして、やはり限度額について多く質問あるものと私も推測しますが、日本国民の中で多くの住民の方が実際に利用している制度になりますので、自治体との間に入ってその取扱いを行っている超有名な企業の名前は多くの住民の方がご存じかと思いますから、当然、住民の方はそちらに問い合わせるとは思いますが、企業の方は税制については自治体にお問い合わせくださいと回答することが多いようです。
Ø このことから、住民の方はグーグル検索の中でも色々計算できるサイトは出てきますので、その企業のHP等のサイトで、その限度額を大まかには簡単に算出できるエクセルシートも掲示されていますから、限度額についてわざわざ自治体の問い合わせる必要はないことを念のため!
では、「ふるさと納税」については、この後のCOLUMNのテーマですので、そこでしっかりと私の考えを書かせていただきます。
<COLUMN3>
→こちらのCOLUMNですが、前述したようにテーマは「ふるさと納税四方山話」についてです。
Ø この制度は2008年5月から始まったとありますが、日本国民でこの「ふるさと納税」という言葉を聞いたことがないという方はほぼ居ないと思いますので、ある意味ここを読まれた多くの方が筆者が言われていることに共感されると思います。
Ø ここに、「ふるさと納税」は応益原則や負担分任原則にそぐわない側面がある。と書いてありますが、地方税における法律的な言い回しをすればそうだと思いますが、最後に筆者から問いが投げかけられていますので、今からしっかりと私の意見を書きたいと思います!
→問いは、「皆さんは、ふるさと納税について、いかがお考えですか?」となっていますので、私の考えとしては、
・そもそも、私は自分の生まれ育った福岡県山門郡山川町(現在は市町村合併でみやま市山川町)にふるさと納税をするならいざ知らす、全国どこにでもそれが出来ますし、そもそも当初の目的は自分のふるさとの応援をするということだったと思いますが、現在は2,000円余計に地方住民税を払えば、寄付した自治体から何らのお返し(多いのは肉などの地元食材)があるのが目的になっていると強く感じていましたので、実は、私は国家公務員を退職するまで絶対にやらないと決めていました。
・ただ、多くの自治体職員の方、また地方で頑張っている旧知の仲の方と話す中で、そのような方を応援出来るケースであれば、個別に「ふるさと納税」をしようと考えて、一昨年の国家公務員を早期退職する際に、4市町村に「ふるさと納税」を初めてやりました。
・結果的にはやって良かったと思っていますが、ただここに書かれているようなもやもや感は依然として持っています。その最大の要因は、そもそもの「ふるさと納税」の創設時の目的がないがしろになって、全国の美味しい肉などの地元食材が個人住民税を2,000円多く納めるだけで手に入る、つまりそれを手に入れる手段が目的化してしまっていると感じるからです。
・勿論、中にはここに書いてあるように、今は多くの自治体がその使い道の指定が出来るようにしていますので、自分がその自治体の教育に使ってもらいたいと考えれば指定は出来ますが、そもそもなぜその自治体に?と言えば、やはりその自治体に自分が欲しい肉などの地元食材があることが前提になりますので、私としては以前としてこの制度のもやもや感は完全には晴れません。
・しかしながら、私がやって良かったと書いたのは、今回私がやった4市町村には旧知の仲の方がいると共に、その地元食材は私が実際にそこに行ってお話した生産者・当事者の物であり、そのことを心から応援したいと思って、その地元食材に「ふるさと納税」しました。勿論、使途は少子高齢化が進む日本、そして過疎化が地方ほど、未来の地元を救うのは未来の子供たちですので、そのための教育に投資をしていただきたいということを使途としたところです。
・このように、今の「ふるさと納税」制度は、創設時の目的から、手段が目的化してしまっているという大きな問題点を感じるものの、一方、過疎化に悩む地方の多くの自治体で、このことで数百億円規模の新たな財源が生まれている自治体もあると聞いていますので、私が今住んでいる人口約6万3千人程度の白井市の市税が総額で100億円行かないことからそのスケールが如何に大きいか想像してもらえると思います。そのことからも、この「ふるさと納税」が地方活性化に大きく貢献している自治体がいくつもあることは私も認識をしています。
・ただ、逆に都市部の自治体ではそのことで個人住民税が減って、大変苦しいということも現に言われていますので、以前として課題が多い制度だとは考えますので、総務省は引き続きやる気のある自治体の創意工夫や努力は活かしながら、自治体と共に制度の適切な改善を進めることを切に願います!
(4)第4章:固定資産税の課税業務は何をするの?
4-1固定資産税の概要
Ø まず「市町村の基幹税としての固定資産税」という表題で、固定資産税は固定資産の所有者に課税される、『応益原則』に基づいたものとあることが、私には住民税と比べ非常にシンプルに分かりやすいと感じました。
Ø そして、固定資産の定義として、「土地、家屋、償却資産」とこの3つが政令や省令などではなく地方税法の本分に定義されているということですから、これも明確で分かりやすいと感じます。
Ø そして、その先の固定資産税の仕組み、また固定資産税とあわせて徴収する都市計画税の項目に入ってくると、私からすれば難しくはないですが、特記する事項とすれば、毎年の年次業務加え、評価替えという3年周期の業務がそこに組み込まれているということが、第3章の地方税とは大きな違いなのかもしれません。
4-2固定資産税担当の仕事の全体像
Ø 地方税でも最初にありましたが、図表40業務スケジュールで、固定資産税の担当が年間のどのタイミングで何をする必要があるのかの大まかな内容が、地方税と同じように、いわゆるガントチャート形式で書かれています。
Ø なお、スケジュール的には地方税と比べると2か月程度早い年度業務のスタートになっているようには感じましたので引継ぎ前に実質的に業務が繁忙期に入り、4月1日に異動した方はまさに激務の中に飛び込む感じかな~とも感じますが、このように時系列でスケジュールを見える化すると、地方税のところでも感じましたが、とても分かりやすいですね!
Ø その後、ガントチートにあるように、最初に書きました納税義務者の特定及び課税客体の補足、税額の計算、納税の告知、不服申し立て対応、国への報告、そして証明書発行等とありますが、ここで行政書士として注意すべき点は、地方税は不服申し立てには行政不服審査法による審査請求しかありませんが、固定資産税には固定資産評価審査委員会に対する審査申出という制度が、それに加えてあるということは注意しておくべき点だと感じました。
4-3誰に課税するのか
Ø ここもとてもシンプルで分かりやすく、最初に納税義務者1~基本は賦課期日時点の登記名義人~とある通り、こちらも地方税と同じくその年度の1月1日時点であり、図表41固定資産の所有者にあるように基本的には登記がされているものは、登記名義人が納税義務者となるという非常に分かりやすいものです。
Ø ただ、であれば登記されていないものはどうなるのか?という疑問がわくでしょうから、それは償却資産に当たるところとが殆どだと思いますが、私も前年末までの白井市からの調査依頼に答えているように申告制になるとは思いますが、後ほど出てくるように市町村にも国での国税調査権があるように、実地調査による徴税吏員と固定資産評価補助員というのが市町村長から任命されていますので、その方がその確認のための実地調査等を実施することとなることには十分にご認識をお願いします。
Ø その後に課税客体の異動を含めて納税義務者に関しての細かい記述が続きますが、そこはこの本を読んでもらえれば分かることですので割愛します。ただ、参考で最後に不動産登記制度と所有者不明土地問題のことが書いてありますが、この問題は近年特に農業関係では農地・山林でも大きな問題となっており、そのため令和6年度から不動産登記法の改正の施行が行われ、「相続人申告登記制度」の創設や、住所等の変更登記の義務化が決まっています。ですので、私もそうですが田舎の親の家屋やそして農地を売れないのでそのまま放置している人が多数いるとは思いますが、これからは法に則って手続きしないとそのことでのペナルティが新たに生じる場合があることはこちらも認識しておくべきだと感じます。
3-4いくら課税するのかについて①~⑨
Ø サブタイトルで①~⑨で税額の算出家庭の全体像から3年に一度の評価替えまでをこちらも、事細かに記述されていますので、課税担当はこれを読めば本当に固定資産税についても熟知できると思います。
Ø 特記するとすれば、④家屋課税についてということで、ここで先程書いた実地調査による徴税吏員と固定資産評価補助員というのが市町村長から任命されていますので、その方が実地調査等を実施することとなるということでの記述がありますが、その際の家屋の定義について、外気分断性、土地への定着性及び用途性の3要素満たす建物が固定資産税の課税客体としての「家屋」で評価すべき対象となっています。
Ø 住民の方にとっては、特にここが重要で、私も農業用ビニールハウスが固定資産税の課税対象か?とよく聞かれましたが、今の補助事業で整備するような骨組みであるパイプの基礎をコンクリートで打ってしっかり固定されていてれば固定資産となると聞いていますし、キャスターが付いて動くような簡易倉庫なら別ですが、こちらもきちんと土地に固定して台風などで動かないようになっていれば固定資産に該当すると聞いていますので!
Ø 後は、⑦償却資産の課税業務で、そもそも申告制ですから実態と相違している場合も多々あるようですし、先程のビニールハウスや簡易倉庫の件もそうですが、3要件に合致しているかということで、そもそも家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものについては償却資産ではなく家屋に含めて評価するとなっていますので、ここを特に注意する必要があると感じました!
Ø また農業関係では、農業用特殊車両で自動車税が課せられていないものには償却資産となることや、そもそも耐用年数からの減価償却費の算定が、今の時代にまだ定額法でなく定率法かい!ということですので、最後の1円が残存簿価として残る点も含めて、基本的な簿記の知識も必要だと思います。
Ø そして最後に3年に一度の⑩評価替えについてですが、これは固定資産税における土地だけの制度ですので、やはり住民から見ると土地の価格と言っても、いわゆる路線価なのか、いったい何を基準として定まっているのか?それは妥当なのか?などかについて、客観的な判断軸の妥当性について争点になりそうなので、ですから地方税は不服申し立てには行政不服審査法による審査請求しかありませんが、固定資産税には固定資産評価審査委員会に対する審査申出という制度がある理由なのではないかと感じました。
4-5どのように税額を伝えるか(納税の告知)、4-6固定資産税がかからないケース(非課税)及び3-7税額が低くなるケース(減免等)
Ø 基本的にはここもしっかりこの本を読めば分かるので割愛しますが、一つ税額が低くなるケース(減免等)の等、つまり地方税ではないこの「等」って具体的には何か?と感じた方がいるかと思いますが、筆者に確認したところ、この償却資産の免税点制度、特例、租税特例が固定資産税にあるという回答があり、これもまた私には大変勉強になりました。
Ø 私としては、特に免税点制度については、住民税と違い固定資産税には免税点があることから、図表68に書いてあるようにこの課税評価額未満であれば課税されないとなっています。つまり、納税義務者の所得の多少に関わらず、この額に達してなければ固定資産税は納める必要はないという制度があることを初めて知りました。
4-8証明書の発行
Ø 証明書と共に、固定資産税には私も全く知らない名寄帳を発行する事務があると書いてありますので、書面での交付の義務は法令上課されていないが、書面の形で交付している自治体が一般的であると書いてありますので、私も時間がある時に市町村の窓口で名寄帳の交付を求めたいと思います。
Ø なお、証明書が求められるのは不動産の相続や贈与が行われる場合、不動産の所有権移転登記が行われる場合とありますが、不動産登記自体は本人か司法書士・弁護士の占有業務でしょうけど、農地もそうですが、不動産売買が行われるときに特にトラブルが発生する恐れが高いということですので、私も行政書士として相談は受けますので、この点は十二分に注意して対応したいと思います。
4-9固定資産税特有のトピック及び4-10都市計画税
Ø ここでは、固定資産税だけの固定資産評価審査委員会に対する審査申出という枠組みのための固定資産評価審査委員会制度についてその手続きが詳細に記述されていますので、不服審査をしたいと考える住民の方は読むべき所だと思います。
Ø なお、都市計画税については、固定資産税の違いについて詳しく書かれていますが、そもそも都市計画法に基づく目的税ですから、事業目的も限定されていて、通常の固定資産税より高くなる計算基準なのか!と感じますけど、全国で約8割に及ぶ都市計画法に該当されるであろう住民の方は、ここも押さえる必要があると感じました。
4-11よく尋ねられる住民からQ&A事例集
Ø 住民税と同じく、税額が急に上がったか、下がるはずの税額が下がらないということが多いようですが、固定資産税では土地の一部が道路なのに非課税となっていないというクレームあるようです。公衆用道路として住宅地の一部を利用している場合は確かに非課税になるケースもあるということなので、そのような場合の確認及び申告は忘れないようにしたいですね!
Ø では、この後のCOLUMNのテーマは、新型コロナウイルス感染症と課税業務という、まさに全ての公務員が危機的な非常時対応を求められた場面での話ですから、こちらも私の考えをしっかり書きたいと思います。
<COLUMN4>
→こちらのCOLUMNですが、前述したようにテーマは「新型コロナウイルス感染症と課税業務」についてです。
Ø 現状はここに書いてあるより進んで、マスクは基本不要になり、来月5月8日からは良好支援でもワクチン接種証明書の添付は不要となるそうです。しかし、外国人が誰もマスク付けていないのに対して、今でも大多数の日本人はマスクを着けていますので、私は室内で強制される場合を除き、外して電車にも乗っていますが、本当に同調圧力、前例踏襲から外れることに凄くデメリットを感じる人が多いのだと思います。
Ø 話が横道にそれてきましたので、COLUMNの話に戻りますが、この未曽有の危機に対して世界中の国で、そしてグローバルで緊急避難的に政策が実施され、勿論我が国でも国会でコロナへの臨時措置法が制定され、一人10万円の給付金も含めて前例のないことがいくつも行われました。
Ø ここに書いてあるのは、そのことで毎年改正される税制においても、特別な対策が数多くとられたということですが、それはそれとして、国の税制は毎年見直すこととなっていますので、今進んでいるインボイス制度や先に出てきた不動産登記制度の改正など途中での紆余曲折はありますが、既に決まった話の中で淡々と進んでいる改正も多々あります。
Ø つまり、新型コロナウイルスのような緊急避難的な対応の物もある一方で、国の将来の形を決めるための税制改正は毎年、ルールに則って粛々と行われているということです。このことから、このような税制改正はいきなり制定され施行されるわけではなく数年スパン、場合によっては20年以上の長い期間で準備から完全施行となる場合もありますので、日頃からマクロとミクロを行き来しながらグローバルの視点でアンテナを高くしておく必要があるということです。
→では、最後に私から問いとして、日本国民としての三大義務である納税のことですから、税制を身近なものとして勉強しておく必要がありますので、日頃から英語の記事も含め、自分のスキルとして身に付ける必要がある分野は、年間100冊以上の本や論文は読んでいますか?ということをCOLUMNの最後に書かせていただきます。
(5)第5章:一歩策に進むための+α
5-1地方税を読む
Ø まず「地方税を読む」となっていますが、要は日本の法律の体系を理解した上で課税担当として業務に取組む必要があるということだと思います。これは公務員である以上、必須な条件とも言えることですので、確かにここには地方税法について書いてありますが、国や自治体という枠組みにとらわれず、全ての公務員が常日頃から担当として前提条件として意識しておくべき内容だと思います。
Ø 特にp211の「法律を読むコツ2~「実質的理由」を意識する~」の表題の箇所は自治体職員として絶対に持って貰いたい、公務員ならば絶対に持っているであろうエシカルの次に大切なことだと感じました!
5-2情報を適切に扱う、5-3徴収を意識する、5-4財政を意識する、5-5知識の幅を広げる、5-6チームプレーを大切にする及び5-7業務を改善する
Ø この5-1の最後のp211からですが、5-2~5-7の項目についても、私が書き出すと、私の持論ばかりになるので差し控えますが、本当にとても筆者の想いが詰まった内容だと思います。
Ø ですから、私がここに強く共感するからと、長々と持論をここに展開する必要はなく、この本をしっかり読めば、筆者の言いたいこと、自治体の課税担当の方に伝えたいことの本質がここに書いてあると感じました!
Ø 冒頭に自治体における取り巻く外部環境が変化していると書きましたが、それは国でも同じでもっと言えば、グローバルでそうだということです。ですから日本だけが頑なに前例踏襲で今のルールを守り続けるということは困難な時代ですから、そのことをよくよく考えながら、民間で言えばマネジメントもそうですが、現代はパーパス経営の時代だとよく言われますので、公務員の組織文化もパーパスから始まり、「ミッション・ビジョン・バリュー」を再定義して変えていく必要があるということを認識して知識の幅を広げ、業務を改善し続ける必要があります!
→では、最後のCOLUMNに私の意見を少しだけ書いて、あとがきはありますが、この本の本文に対しての話は、これで終わりたいと思いますm(_ _)m
<COLUMN5>
→最後のCOLUMNですが、テーマは「“外”の世界をのぞいてみる」です。
Ø 冒頭に最近の「越境学習」、今盛んに中高で取り入れられている「アクティブラーニング」の本質的意味ことが書かれています。今の中高での「アクティブラーニング」でも目の前に答えはない、だから与えられた答えを探すための教科書ではなく、自分たち自身が今の学校という枠から出て、身近な社会課題について分け隔てなく人の話を聞いて、ダイアログをし、皆で納得解を見つけるということをやるようですが、まさしくそれの公務員版だと感じました!
Ø ですから、ここに書いてあるような「オンライン市役所」、住民税ゼミや資産税ゼミに拘らず、本当にスポーツや外国語会話、音楽、絵画など、自分が日頃やってないことに飛び込むことで、未知の分野と未知の分野が人で繋がり、早稲田大学大学院ビジネススクールの入山教授がよく言われる、新たな「知の探索」になり、最近亡くなられましたが、ハーバード大学ビジネススクールのクリステンセン教授が言われるイノベーションにも繋がるんだと、私も強く感じます。
→では、最後に筆者から「職場の“外”の世界をのぞいてみませんか?」とありますので、皆さんどんどんチャレンジしましょう!ただ、ファイナンスの世界からリスクを考えると、何も考えず、外部環境分析もしないでチャレンジするのはあまりにも無謀すぎますから、しっかりとリスクを定量化し、「天の時、地の利、人の和」を持って、自分の人生のハンドルは自分が握るつもりで未来に進みましょう!
3.結論
(1)第1部:筆者の言わんとする「ミッション・ビジョン・バリュー」は何か?
1-1前提
■まず、ミッションとは目指すべき方向性の先にある北極星、そして筆者がこの本で自治体の課税担当者に伝えたいこと、つまり目的とします。
■次に、ビジョンはこの本を読んだ公務員等が、この内容に共感、腹落ちして税制をしっかりとリカレントして住民に税制について伝えようすることを到達点とします。
■最後にバリューは、この本を読んだ全ての人が、税制についてもっと知ろうと思い、日本国民の三大義務である納税について真剣に自分事として考えるようになることにしたいと思います。
1-2ミッション
Ø 筆者が自治体の課税担当に本当に伝えたいことは、まさにp211の「法律を読むコツ2~「実質的理由」を意識する~」で筆者が言われていることだと私は強く感じました。勿論、第5章:一歩策に進むための+α自体がそうであるようなのかもしれませんが、その呼び水として問題提起の意味も含めて各章の最後に、筆者はcolumnを書いていると感じました。
Ø ただ、筆者もこの4月の異動で、6年間の長きにわたる課税担当から福祉部門の方に移られたと聞きましたので、業務としては直接的には地方税制から外れるわけですが、福祉部門でも税制のことは現場の課題として目の前に立ち塞がることがあるでしょうから、その際には今までの経験、そしてこの本を書いたことでのスキルが大きなアドバンテージになると私は感じます。
Ø 勿論、それは今まさにそこで新たな業務に取組んでいる筆者自身が感じられていることであり、皆様も良くご存じのChatGPTのようなAIがどんどん発展してくれば指示待ちで誰でもできる様な仕事をしていてもAIやロボットに置き換えられてしまい不要な人材になることが既に目の前に迫っていますので、そうならないようにするためにも必須なスキルだと思います。
1-3ビジョン
Ø この本を読んだ公務員等が、この内容に共感、腹落ちして税制をしっかりとリカレントして住民に税制について伝えようすることをビジョンとするなら、私ももちろんその仲間です(笑)
Ø 筆者の策略にはまったのかも知れませんが、勿論、行政書士として依頼があったクライアントに税制を含めてしっかりと説明し、理解を得るのが責務ですので、これから仲間として積極的に活動をして行きたいと思います。
1-4バリュー
Ø この本を読んだ全ての人が、税制についてもっと知ろうと思い、日本の国民の三大義務である納税について真剣に自分事として考えるようになることですので、これは財務省、そして国税局のミッションとも言えるかもですが、ともかくせっかくこのような地方税のことについて誰が読んでも分かりやすい本が、今書店に並んでいるわけですから、読んでみる価値は十分にあると思います。
Ø 正直言って、このような自治体の職員向けの本などは公務員関係の専門雑誌の中での話が殆どでしたので、一般の住民の方が手に取って読むような本はなかったと思います。ですから、このような本が出版され誰でも書店で手に取って読めるのですから、税制は知らないと場合によって多大なリスクとなりますので、是非手に取って、日本国民の三大義務である納税について、真剣に自分事で考える機会に恵まれたということですね!
(2)第2部:私のこの本での「ミッション・ビジョン・バリュー」は何か?
2-1前提
■まず、ミッションは目指すべき方向性の先にある北極星ですから、私としてはこの本で日本の国民が自分事で税制を常に考える社会になることを目的とします。
■次に、ビジョンはそのような日本の国民が、この内容に共感、腹落ちして税制をしっかりとリカレントをして税制について自治体の課税担当や我々行政書士に、自分の問題点を的確に伝えることが出来るようになることを到達点とします。
■最後にバリューは、この本を読んだ全ての人が、税制についてもっと知ろうと思い、日本の国民の三大義務である納税について真剣に自分事として考えるようになること、つまり筆者と同じバリューにしたいと思います。
2-2ミッション
Ø 私が、この本で日本の国民が自分事で税制を常に考える社会になることを目的としましたが、これは本当は政治家の役目であり、財務省や国税庁が目指すべきことです。本当は常日頃から国の立場でもしっかりと、このことを国民に分かりやすく訴求して理解を得るのがその責務ですから、私も行政書士として協力はしますが、是非、国の職員もこのような本を執筆してもらいたいと思います。
2-3ビジョン
Ø そのような日本の国民が、この内容に共感、腹落ちして税制をしっかりとリカレントして税制について自治体の課税担当や我々行政書士に、自分の問題点を的確に伝えることが出来るようになることですから、これこそ私がこの本の感想文で目指すべき到達点だと思っています。
Ø つまり、そのような住民の方が、自治体職員の方に限らず、今の公務員に税制について質問等をした時に、そもそも文章というもの自体が自分のためではなく相手に伝えるために書くものですから、勿論、税制に限ったことで張りませんが、相手に出来るだけ早く、的確に、そして分かりやすくで、可能ならば腹落ちして、それで相手が行動してもらえるように相手に話す必要があります。
Ø ですから、特に自治体の職員の方には感覚的でも構いませんので、組織で仕事をする上での重要度に重きを置いて考えて貰いたいのは、仕事に時間をかければかけるほど内容の精度が上がり、良い成果のものが出来るわけではない、どちらかと言えば完璧を目指して時間をかければかけるほど、途中から仕事の生産性と共に、逆に費用対効果は低下するということを意識して、若い人は特に自分の仕事は6割の出来で上司に報連相(本当は逆の相→連→報)しながら、住民の現場ニーズに対して組織として最大の費用対効果を生むように心がけて仕事をしていただければと私は考えています。
2-4バリュー
Ø この本を読んだ全ての人が、税制についてもっと知ろうと思い、日本の国民の三大義務である納税について真剣に自分事として考えるようになることという、筆者と同じバリューですから、特段改めて書くことはありませんが、まさに、それがこの本でも筆者が目指されていることだと思いますので、この感想文はそのことをそっと後押しする、行動経済学でのこの本のナッジになることを目指しています!
Ø ですから、最近、自治体職員の方が本を出すときに、その本の印税が本人の収入になる場合に職場から反対されたことで本の出版が出来なかったとか、印税を放棄したので職場からやっと承認されたと聞くことが良くありますが、そのような個人がいくらの収入を得るか得ないかの次元の話ではなく、最終的な成果としてその市町村、そしてそこの住民がその本を読めば自治体の業務にどれだけの費用対効果を生むかという視点での合理的判断をするべきだと思います。なお、決して私にこの本の売上でのバックマージンがあるわけではありませんが、この本の売り上げに貢献することが出来れば本望ですね(笑)
4.あとがき
■それでは、今回、自身初めて筆者のお一人である、神戸市役所に勤務されている原田知典さんから献本を頂きましたので、勿論、この本を読んでいる方に対して、自分なりには精一杯の感想文を書かせていただきました。
私のモットーとして、「時間はなまもの!感動もなまもの!」の意識を、最後に筆者が言われている公務員組織の“外”の世界に出るようになってもう20年以上心掛けてきたことから、この感想文も、もっと多大な時間を掛ければ分量も2倍、3倍になるし、厚みも増すでしょうけど、それは私の意図するこのこととは整合しないこととなりますので、本を頂いて読んだらおよそ1週間以内には書きあげるという時間的な自分なりの目標をまずクリアーすることとしたところです。
■それでは、どんな仕事でもまず自分自身に時間の制約を設定するのは仕事の効率性を上げるためではありますが、人生は本当に長いようで短いからです!私は今還暦を過ぎたところですが、55歳の時から霞ヶ関の農林水産省本省に勤務しながら、グロービス経営大学院に通いMBAを取得し、農林水産省を早期退職して、行政書士として起業し、フードロスをゼロにするミッションを掲げて一般社団法人フードロスゼロシステムズを設立しました。
今考えれば、このことを最低でも10年以上前にするべきだったと思いますが、では10年前にそれが出来たかと言えば、私自身の家庭を含めて絶対に出来る外部環境ではありませんでした。
ですから、今のリカレント、リスキリングが当たり前だと言われる時代ですが、アンラーニング本質である、「本当に現在に必要なのは、最終学歴ではなく、最新学習歴だ!」と皆さんもよくよく考えて、今できることに全力を尽くしてもらいたいと思います!
■その上で、最初のまえがきに書いた、自治体の職員の方が、国に法令等について尋ねる際の心がけですが、p211の「法律を読むコツ2~「実質的理由」を意識する~」でも筆者が言われているように、先ずは自分がそう判断する根拠として、該当する法律等の条項のどこにそれが書いてあるのかは前提条件として明確にしておく必要があります。
その上で、そもそも該当する根拠法の主旨・目的からして、そのことと自分の考えが整合し、そうした場合に現場の住民の方の意見を踏まえて、このように考えればそのことが適法となるという考え方を明確に整理し、できれば仲間の職員、そして家族にも説明して同意を得る説明の練習をした上で、思考をブラッシュアップして論理的・客観的に自分がやりたいことを堂々と国に提案して欲しいと思います。
その法律の主旨・目的に合致しているのであれば、細かな要件も現状は確かに最終的にはクリアーしなければいけませんが、もし今その法律で対象から漏れているとお互いに納得できれば、法律は国会で制定されるのでおいそれとは変えられませんが、次年度での改正で通知の細かな要件などを変えることは不可能ではないですから!
■では、この感想文の最後は少々哲学的な話になるかもですが、私は米国のテレビSFドラマであるスター・トレックという番組が好きで、もう50年以上前の最初の日本での深夜放映の時から見ています(苦笑)
そのことでのMBAでの経営学に繋がるマネジメントのことを書き出すと、本当に何十枚になってもこの読書感想文のあとがきが終わらなくなるので、そのシリーズの中でのスター・トレック・ヴォイジャーのある話から一つだけ!
そこでは、不死身の人類であるQ連続体という宇宙の何処でも、何時の時代でも行ける神みたいな存在の一人が出てきます。そこでのこの一人が、こんな全く進歩も何もない会話もせずに退化するだけの退屈な死のない神のような世界に居るのは死ぬ以上苦痛だとして、死を望み、勿論、Q連続体から途轍もない反論や妨害を受けますが、ヴォイジャーのジェンウェン艦長を始めとしたクルーやQ連続体の仲間の一人の協力もあり、最後は自ら死を選んでこの回は終わります。
なお、ご興味がある方のために、最新版ドラマは、アマゾンプライムで現在、新スター・トレックのピカード艦長が登場して、今放映されていますので(笑)
■それから言えば、逆に我々は生まれた以上、死ぬことだけ決まっていて、それが今日なのか、明日なのか、はたまた100年後なのかは誰にも分かりません。ですから、人は今日死んでも悔いのないように、今を全力で生きるしかないと今は思っています。
このスター・トレック・ヴォイジャーの中の自殺したQ連続体の一人も本当に悔いのない人生だったと思うために自殺をしたと考えれば、人が死ぬということはあながち悪いこと、残念なことばかりではないのではないかと私は考えます。
死ぬからこそ、人は今を全力で生きようと出来ると考えれば、人の人生は長生きだから幸せでなく、たとえ短くても悔いのない人生だと死ぬ時に思えることが本当には必要なことかも知れないと・・・
では、私にはとても、その境地、悟りは開けませんが、全力で今この本の読書感想文を書きましたので、是非、「この本をお買い求めいただき読んで」いただき、その次に、このnoteも読んでいただけたら幸甚です。
ですので、最後にこの読書感想文を読んでいただいた皆様にマネジメントの視点から言いたいことは、どんなに仕事で苦しい時でも、家族には何時も「Have funで!」
―以上―
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
