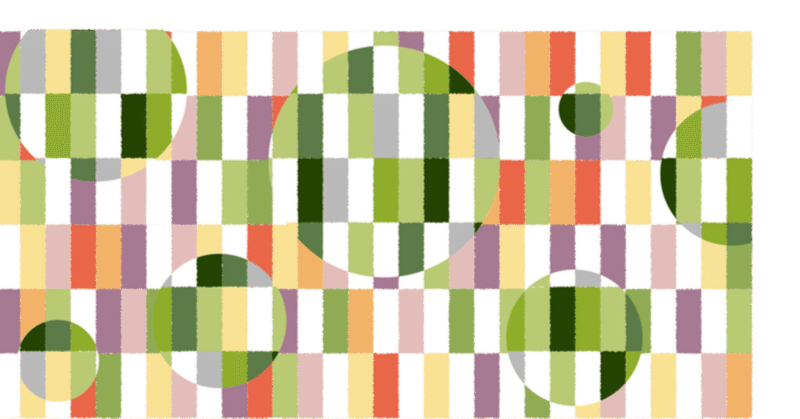
【みじかい小説No.7】おばあちゃんの押入れ
居間で本を読んでいると、どこかから声がする。
「美代、美代――。」
美代は息を呑む。
美代、美代――。
声はまだ続いている。
読みかけの本を閉じ、美代は居間を出る。
声の主は、か細い声でまだ続けている。
廊下を抜け両親の寝室を抜けると、仏間のあるおばあちゃんの寝室にたどり着く。
「美代――。」
美代は戸と開けると、勝手知ったる風に押入れの戸に手をやった。
からり、とかわいた音をさせて襖を開く。
二段に別れたその下半分に、ちょこんと正座をした祖母が鎮座している。
「見つかっちゃった。」
そう言って祖母は皺だらけの顔をさらにしわくちゃにして、ふふっと笑う。
「もう、おばあちゃんたら。」
慣れたふうに美代も言う。
よっこいしょ、と言いながら押し入れから這い出る祖母に、美代は手を貸してやる。
しわくちゃの、なんとも頼りない手を引きながら、その肩を抱きながら美代は思う。
この人にも若い頃があったのだなぁ、なんて。
そして、私もいつかこういうふうになるのかなぁ、なんて。
「美代、あげる。」
言うと祖母は、握りこぶしを開いて、飴玉を三つ、美代に差し出す。
「ありがと、おばあちゃん。」
その顔を見遣って、祖母の明子は思う。
私にもこんな頃があったなぁ、なんて。
この子はこれからどんな人生を歩むのかなぁ、なんて。
ねがはくは、この子の残りの人生が良きものでありますように――。
くしゃくしゃの手で四十になる美代の手を握りながら、その瞳の中に映る自分の姿を眺め遣る。
祖母のそんな顔を見つめ、美代は言う。
「またこんなところに隠れて。寂しかったんだよね、おばあちゃん。」
それを聞き、ひときわくしゃりと笑う祖母。
と、その時、仏間の写真立ての一つがパタリと音を立てて倒れた。
ふふ、と笑みを浮かべ、美代はそれを元に戻す。
遺影の中の祖母は、ちょうど美代と同じ年頃である。
「またね、美代――。」
どこかから声がする。
手の中に残された飴玉は、昨日仏壇に供えたものである。
「もう、ほんとに寂しがり屋なんだから。」
ふふっと笑って、美代は飴玉の一つを口に入れると、仏壇に線香をひとつ立ててかつての祖母の部屋を出ていった。
再びがらんとなった仏間では、線香から立ち上る紫煙がいつまでもふたりの不在を慰めていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
