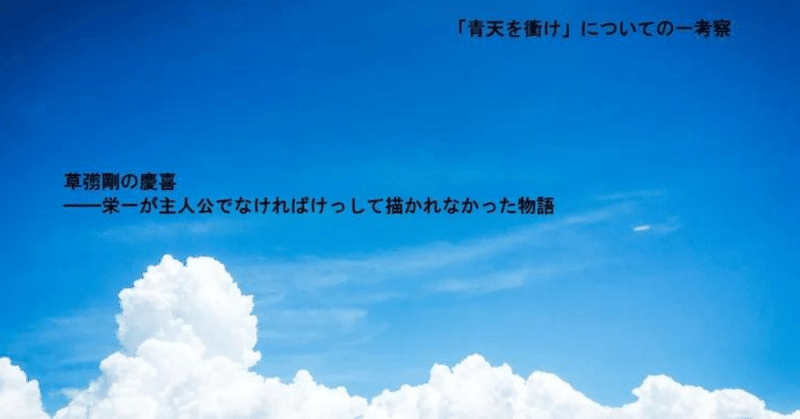
草彅剛の慶喜 ――栄一が主人公でなければけっして描かれなかった物語
傑作の呼び声高い昨年の大河ドラマ「青天を衝け」は、史上最高の「慶喜」と評される草彅剛のキャスティングなしに語ることはできない。
これまで、大河でも慶喜を演じた俳優は何人もいる、そしてさまざまな演出を施され、その人物像が描かれてきた。「二心殿」と呼ばれたというエピソードからも、一筋縄ではいかない掴みにくいキャラクターであるというイメージは定着している。「何を考えているかわからない」というミステリアスな要素は、どんな慶喜にも多かれ少なかれみいだされる。この大河では、「輝きがすぎる」という圧倒的なカリスマ性と「人の心がわからない」というコミュニケーション能力の欠如を伺わせる人物造形に、そのミステリアスな性格を反映させていた。
慶喜の性格が「わかりにくい」と言われるのはなぜか。それははっきりしている。鳥羽・伏見の敗北のあと、慶喜はなぜ戦うことなく京都から江戸へ「逃げた」のか、それが日本史上評価の分かれる謎の一つとされているからだ。そして新政府から排除され政治の表舞台から去ったあと、なぜ沈黙し歴史の証言者となることを忌避したのか、なぜ息をひそめるようにひっそりと余生を趣味に生きたのか、といった謎とも相俟って、人は慶喜の胸中をさまざまに推し量らざるをえなくなる。それだけ慶喜は、「わかりやすい」解釈を許さない、複雑な人物像として、私たちの前に立ちはだかっているのだ。
「青天を衝け」は、こうした慶喜をめぐる日本史上の謎に焦点を合わせ、その「解」の一つを説得的に呈示したという意味で画期的な意義がある。物語=フィクションのなかで、一般にはあまり知られていない渋沢栄一とのさまざまなエピソードに託して、ミステリアスでわかりにくい多面的な慶喜像をそのつど丁寧に描きながら、最後に「そうだったのか、慶喜とはそういう人だったのか」と誰もが納得する一つの明確な「慶喜像」を浮かび上がらせた。そして、そのためにこそ栄一が主人公である物語が必要であり、また慶喜を草彅剛という俳優が演じることが必然であったのだ。それはどういうことか、以下明らかにしていこう。
慶喜の独白
「青天を衝け」は渋沢栄一の一生を描いた物語である。あくまで主人公は栄一である。しかしこのドラマを観ていた誰しもが、もう一人の、きわめて重要な主人公がいる、と感じたはずだ。いうまでもなく徳川慶喜である。第1回の冒頭から、まず二人の印象的な出会いのシーンが描かれ、その後何度も回想されることからも、この二人の関係性――から紡ぎだされる「ドラマ」――を描くことがこの大河の中心的なテーマではないか、そして二人に纏わるさまざまなエピソードを丁寧に描きとるという一貫した脚本・演出によって、幕末・維新の歴史を今までの大河とはまったく異なる視点から問い直し、「明治維新」という日本の近代化の嚆矢となった出来事に一つの斬新な解釈を与えようとしているのではないか、と推察させる。だとすれば、徳川幕府の優秀な幕臣たちの目に映った激動の時代とはどのようなものであったのか、そして何よりもその中心にいた慶喜はそこで何を思い何を考えていたのか、という「問い」を避けて通ることはできない。まずこの問いの答えがドラマのなかのどこにあるのか、確認しよう。
最終回間近の第39話(「栄一と戦争」)で、晩年の慶喜は、伝記の編纂に奔走する栄一たちの熱意に応えるかたちで、慶應3年から明治元年(1867-8)、つまり大政奉還・王政復古から鳥羽・伏見の戦いにいたる幕末史のまさに渦中にいた自らの心情を、はじめて語り始める。
慶喜は慶應3年12月新政府から出された内大臣辞退と領地一部返上の命をうけ大坂城に引き上げたとき、薩摩討つべし!と半狂乱になって「出兵を許さぬなら私を制してでも薩摩を討つ」と言い出した家来たちの顔を今でも夢にみる、と回想する。慶喜は、人を戦争へと駆り立て高揚させる「欲望」が道徳や倫理よりはるかに強く、その力にはけっして抵抗できないことを思い知り、家来たちに向かって「どうにでも勝手にせよ」と言い放った。そして鳥羽・伏見の戦が始まり、「多くの命が失われ、この先は何としても、己が戦の種になることだけは避けたいと思い、光を消して、余生を送ってきた」と言う。それに対して、喜作が「そこまでのお覚悟が。それはただ逃げたのとは違いましょう。あれほど数々の誹りを受け、何もあえて口を閉ざさずとも」と絞り出すように言葉をかけると、「いいや、人には生まれついての役割がある。隠遁は私の最後の役割だったのかもしれない」と返すのだ。
この独白には、幕末から維新にかけて政治の中心にいた慶喜、その後明治の世を長く生きた慶喜の心の核にいったい何かあったのかという私たちの「謎」を一気に解き明かす一つの言葉がある。「光」だ。慶喜はまさに「光」だった。いつも何かしらものごとの「中心」にいた。慶喜から放たれる「光」がまるで道標であるかのように、人びとが引き寄せられ集まってくる、そしていつのまにか大きな歴史のうねりの「中心」へと押し上げられてしまうのだ。腹心の側近平岡円四郎との心を許したやりとりのなかで、自らを「輝きがすぎるのだ」と評したシーンは印象的だ(第16話「恩人暗殺」)。慶喜は、いつも気がつけば、歴史の(つまり政治の)ど真ん中にいることになった。そして政治とは争いであり、慶喜のまわりではたえず血腥い争いの種が尽きず、円四郎をはじめ優れた献身的な家来たちが次々に命を奪われていった。その果てに鳥羽・伏見の戦いがあったのだ。 「薩摩討つべし!」と叫びながら出兵の命を迫る家来たちに取り囲まれたとき、慶喜は権力の「中心」にいながら何ごともまったく思い通りにならない、という無力感に襲われ心底絶望と恐怖を感じたに違いない。言葉が足りなかった、失策を重ねた、後悔している、どこで間違ったのか、いやずっと間違っていたのか・・・慶喜は思い迷い苦悩し、そして決めたのだ、自分の存在から放たれる「光」――否応なく人を惹きつけ、「この人のためなら」と思わせてしまう「カリスマ性」――を消してしまおう、と。
「己が戦の種になることだけは、避けたい」という言葉は、慶喜が「平和主義者」だったから戦をしたくなかった、戦をしたくなかったから「逃げた」ということをけっして意味しない。慶喜は自分が「逃げた」ことを否定していない。慶喜に心酔する栄一や喜作たちは慶喜に着せられた「汚名」を雪ぎたい一心で伝記の編纂に注力したが、慶喜は汚名を雪がれることは「望まぬ」、「事実、私はなすすべもなく逃げたのだ」とはっきり言う。確かに歴史上誰がみても「逃げた」には違いない。しかしそれでもやはり、「ただ逃げた」のではない。数々の失策・過ちを認め、最後まで戦って死ぬことではなく速やかにその場を去って生きることを、「光を消して生きる」という困難な道を選んだのだ。生きつづけることは、時に死ぬことよりはるかに難しいということだ。
己が戦いの種になることを避けるといっても、それは簡単にできることではない。どんなに忌避しても嫌だといっても、気がつけばなぜか「中心」にいて人びとの視線を一身に浴びることになってしまう、そんな慶喜にとって「中心」からはるか遠くに身を置くことは、歴史そのものに立ち向かい抗うことに等しい。それは自分を無に帰してしまわない限り、おそらく不可能に近いことなのだ。しかし慶喜はそれを見事に成し遂げた、「光」を消して――自らを空虚にして――「隠遁」という「役割」を自分の「運命」だと定めて、それを全うした。生まれつきの圧倒的なカリスマ性を持ちながら、それをあえてないものにしようと意図し、現実にそうしたのだ。ここに、慶喜という人物の傑出した唯一無二性をみることができる。
物語の構造――栄一と慶喜
「青天を衝け」のなかで慶喜はこうした人物として描かれた。「描かれた」といったが、しかし、慶喜をこうした人物として「描く」こと――言い換えれば、私たちがドラマを観て慶喜の人生を「なるほど、そうだったのか」と理解できたということ――それ自体がきわめて稀有なことであり、それに成功したという意味で、「青天を衝け」は大河ドラマとして特異な作品になった、といえる。この成功の鍵は二つある。すでに述べたように、一つは、このドラマの主人公はあくまで渋沢栄一であるということ、もう一つは慶喜を演じたのが草彅剛という俳優だった、ということである。
逆説的だが、栄一を主人公にした物語でなければ――慶喜を主人公にした物語では――、慶喜の人物像、その心情や思いを、このように描くことはけっしてできなかった。それは、この大河ドラマで「鳥羽・伏見の戦い」がどう描かれたのかをみればわかる。私たちが提起した日本史上の「謎」は「鳥羽・伏見の戦い」をめぐるものだ。慶喜の人生にとってけっして避けては通れない重要な出来事だ。しかし驚くべきことに、この大河では「鳥羽・伏見の戦い」について具体的にはほぼ何も描かれていないのだ!1968年1月に「鳥羽・伏見の戦い」があったという歴史的事実は、渋沢栄一が慶喜の弟昭武に同行してパリ万博に行っている間に起きた出来事として、遠く日本からの「書簡」が届くというかたちで栄一にも私たちにも知らされる。このとき、大政奉還とともにその戦いの顚末を知った栄一は烈火のごとく怒り、昭武からの手紙を装い直接慶喜へ諫言する。ドラマで描かれるのはこれだけだ。(第24話「パリの御一新」)。そしてドラマの終盤になって、この伏線は慶喜の独白によって見事に回収される。 「鳥羽・伏見の戦い」という点としての歴史的事実に言及し、四十年余りの時を経て、当時を回想する慶喜の言葉を最後に据える、この物語の構造があってはじめて「謎」は解かれ、同時に慶喜の人物像にも明快な一つの解釈を与えることができたのだ。
この物語の構造は、渋沢栄一が主人公でなければ成り立たない。栄一は、幕末・維新のこの動乱の時期日本にはいなかった。だからあくまで栄一の視点からは「こう見えていた」という描写に止めることができたのだ。慶喜が主人公の物語を、この構造の下に描くこと、慶喜の人物像をこのように造形することはけっしてできない。なぜか。それは、ここでの慶喜とは、自らの「カリスマ性」を無に帰そうとした、いわば「空虚な中心」としての慶喜であるからだ。このような人物像を、ドラマのなかで積極的にキャラクターづけすることはきわめて難しい。現に生きている「何ものかであるもの」を、「空虚な中心」=端的な無として描かなければならないからだ。たとえばもし、慶喜が主人公なら、「鳥羽・伏見の戦い」に直面した慶喜の心情と行為を、積極的な内容をもつ「何か」として描かなければならない。肯定的にしろ否定的にしろ、京都から江戸へ行ったという「歴史的事実」を、それが「何であったのか」(怖くてただ逃げたのか、深謀遠慮の末の戦略だったのか・・・)を、慶喜の発する言葉とその振る舞いによって具体的に示さなければならない。大政奉還も鳥羽・伏見の戦いも、こんなふうにスルーすることは許されない。栄一が主人公であったからこそ、それが可能だったのだ。
栄一の人物像は明快だ。一つひとつの出来事について、栄一が何を考え何を感じなぜそうしたのかが台詞と所作によってあますところなく示されている。栄一が「何ものであるか」は一目瞭然だ。そのエネルギッシュで「わかりやすい」直情的・行動的な「陽」の栄一に、物語の全編にわたって「何を考えているかわからない」「人の心がわからない」抑制的な「陰」の慶喜が配されることによって、「何ものでもないもの」としての慶喜が僅かに掬いとられ、その人物像が私たちに辛うじて理解可能なものとなる。
そしてなんといっても、私たちが慶喜の人物像をこのように理解することができたのは、草彅剛という俳優の存在に拠るところが大きい。草彅剛の慶喜は、画面の中に一瞬現われるだけで、それまでの慶喜の人生のすべてが確かにそこにあると感じさせる圧倒的な存在感を放っていた。いま何を思い何を考えているのかをけっして積極的に演じてみせることがなく、ただそこに存在しているだけで、その立ち居振る舞い、静かな台詞回し、無表情の表情ともいうべき僅かな顔面の動き・・・そのすべてが、まさに慶喜その人以外の何ものでもない、と思わせてくれた。よく考えればこれは実に奇妙なことだ。「何ものでもないもの」の「圧倒的な存在感」とは!しかしこの二律背反を可能にしたものこそ、草彅剛という俳優の佇まいそのもの、あえていうなら、何もしない何も付け加えない――自らが自らであるために自らを脱け去らしめる――という「引きの演技」だったのだ。まさに圧巻、見事というほかない。
「青天を衝け」と現代社会
最後に付け加えておきたいことがある。大河ドラマは過去の歴史を扱うが、多かれ少なかれ現代社会にとって示唆的な内容を含んでいる。「青天を衝け」にはこれまでにもましてストレートで強いメッセージ性を感じた。
幕末・維新を扱った歴史ドラマは、国の行く末を憂え倒幕の志を共にする志士たちの側から描かれることが多い。したがってほとんどの場合正義は倒幕側にあり、徳川幕府はただ旧弊を踏襲し権力を温存させようとする頭の固い「悪者」にされる。私たちは教科書で習ったとおりに、江戸無血開城から明治維新を日本の近代化の成功として記憶し、新政府=薩長政権の功績を何の疑問もなく受け入れてきた。しかし「青天を衝け」を観ると、こうした歴史観は揺るがされ一気に相対化される。慶喜を頂点に幕府側の人びとのなかにも、どうすれば日本を近代的な国家にできるのかを真剣に考え徳川以後の政権について思いめぐらせていた有能な人材が多くいた、という当たり前の事実に気づかされるのだ。そしてもし慶喜が新政府の一角を占めその才能を遺憾なく発揮していれば、もし新政府が多様な意見を闘わせることのできる「オール・ジャパン」の体制であったら・・・明治から大正、昭和へと一直線に悲惨な戦争へと向かっていったその歴史の流れを変えることができたのだろうか・・・と思わずにはいられない。それが大河ドラマを楽しむ一つの醍醐味でもある。「戦争は忌むべきもの」という思いは、もちろん渋沢栄一その人の生涯を貫ぬくテーマでもあった。そもそも栄一の資本主義とは、この社会から貧困をなくし格差をなくしすべての人が幸福を享受するためにこそ実現しなければならない制度であった。それは徹頭徹尾「民」のためのものであり、民にとってもっとも忌避すべきもの、それが戦争にほかならないからだ。
この物語は「今、日の本はどうなっている?」と問う栄一に「恥ずかしくてとても言えません」と返す孫の敬三のシーンで終わる(第41話「青春はつづく」)。現代日本を生きる私たちにそのまま突き刺さる強烈な言葉だ。しかしその直後、栄一は「なぁに言ってんだ」と笑い「まだまだ励むべぇ」と畑を耕す。ここには、端的に「生きろ」――どんなことがあっても人間は生きて一人ひとりに課せられた「役割」を全うせよ――という強いメッセージが込められている。それは慶喜のラストシーン(第40話「栄一、海をこえて」)にもはっきり読みとれる。パリからの手紙に少しは答えをだすことができたか、と栄一に問いかけ、「私はあのころからずっと、いつ死ぬべきだったのかと自分に問うてきた」と言う。慶喜は「いつ死んでおれば、徳川最後の将軍の名を穢さずにすんだのか」を自分自身に問いつづけ維新後の長い長い人生を生きてきたのだ。そして最後に、「ようやく今思うよ。生きていてよかった。話しをすることができてよかった。楽しかったなぁ」、「尽未来際、共にいてくれて、感謝しておる」、そして「快なり。快なり、快なり、快なりじゃ!」と言って、じっと何かを思い浮かべるかのような、ちょっと切なく悲しげでもある微かな笑顔をみせるのだ。
「青天を衝け」という大河ドラマにおいて、争いごとを忌避して、光を消して、人生を全うした慶喜という人物像が鮮やかに実を結んだ瞬間だ。草彅剛という稀有な俳優を得て徳川慶喜という歴史上の一人の人物が「そうか、こう生きたのか」「このように生きるしかなかったのか」と心底思わせてくれたからこそ、ドラマに込められた反戦の思いも「生きろ」というメッセージも、私たちの心にストレートに届くものになった、といえるだろう。
amanatsu20220319
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
