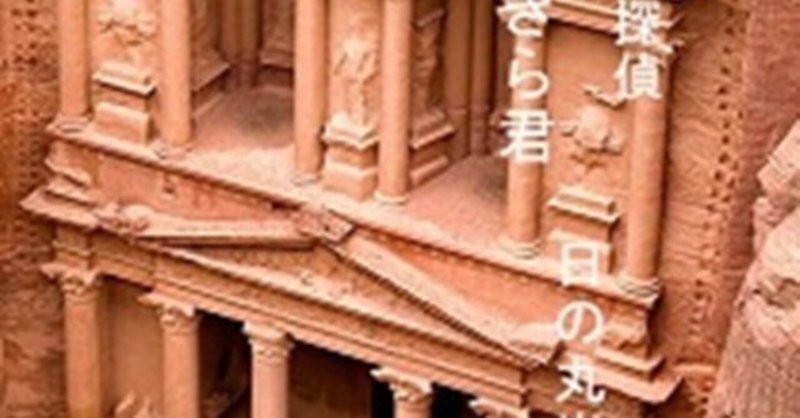
お坊ちゃま探偵 日の丸岩の秘密
はじめに
お坊ちゃま探偵シリーズ二作目となります。
お楽しみ頂けますことを願いつつ・・・。
日の丸岩
託された銅板
ペトラ遺跡
クフ王のピラミッド
モナリザの瞳
お坊ちゃま探偵 花房あきら君
日の丸岩の秘密
大空まえる
木の葉が色づいています。
山のもみじも黄色やオレンジや赤などとカラフルです。
風も冷たくなってきました。
この間の夏休みが、もう嘘のようです。
楽しい夏休みでした。
湘南海岸から一望できる烏帽子島での、伯母の米ちゃんとの冒険。
忘れられない想い出です。
あきら君は、そのことを母の夏ちゃんに話してあげました。
「あのさあ、鎌倉の古本屋で面白い本を見つけたんだよ。
日本の古来からの七不思議について書かれた本なんだけどね。
そこに後北条氏の宝について書かれたところがあってさあ、本当に冒険に行っちゃったんだよ。烏帽子島なんだけどね。
そして見つけたのが後北条氏の残した古文書だったんだよ。
それを博物館に寄贈してきたんだ。
楽しかった。」
すると、夏ちゃんは言いました。
「それは、お手柄だったねえ。
それで、米ちゃんは、何も言ってなかったかい。後北条氏の事について・・・・・。」
「うううん。
何も。」
「そうかい。
じつは、私たちは後北条氏の血を受け継いでいるのよ。」と言うのです。
夏ちゃんの話によれば、北条家の娘が嫁いで娘が生まれ、また、その娘が嫁いで生まれたのが夏ちゃんや米ちゃんたちなのだそうです。母方、母方と伝わってきていることになります。そんなこともあって、夏ちゃんは続けて言うのです。
「烏帽子島での冒険も、不思議な巡り合わせだったねえ。
ご先祖様も、きっと喜んでくださっている事でしょう。」と。
もちろん、伯母の米ちゃんも、この事は承知しているのですが、あきら君に知らせるのは、まだ早いと思って話さなかったのだそうです。
烏帽子島での冒険は、米ちゃんにとっても感慨深いものであったに違いありません。
あきら君にとっても、ご先祖様への感謝以外の何物でもないのでした。
あきら君のお父さんは、岡山科学大学の教授で、地球温暖化防止対策の研究をしています。
特に地熱発電の開発を研究テーマにしているのです。
日本は、米国、インドネシアに次ぐ世界第三位の地熱資源国なのに地熱発電では、米国、フィリピン、インドネシアなどの国々に比べて開発が遅れています。
原子力発電に頼らず、クリーンエネルギーに変えていかなければなりません。
あきら君も、そのお父さんのあとを継ごうと思っているのです。
少しでも早く地球温暖化防止対策に取り組んで二酸化炭素などの排出量の削減に努めなければ、手遅れになってしまいます。
世界各国のそれぞれの政府が国を挙げて一丸となって取り組まなければなりません。
それが今いちばん望まれていることなのです。
瀬戸の海面が輝いています。
穏やかな波が西日を反しているのです。
ここは岡山県の小さな港町、あけの。
海もあれば山もある静かな町です。
そこから望む山の頂には大きな岩が幾つかあり、そのうちの一つには大きな日の丸が彫られていて、赤い塗料が塗られています。
船から見えるように、目印となっているようなのです。
みんなには日の丸と呼ばれて親しまれていました。
あきら君たちも良く友達と一緒に遊んでいる山なのです。
山水の細い流れには砂留が間隔をあけて何段にもあり、恰好の遊び場になっています。
山の斜面には、木の茂みを利用して造った隠れ家が、あちこちにあるのです。
山から見下ろす瀬戸内海は穏やかで、大小の島々が点在しています。
漁船が航跡を残しつつ進んでいたり、島の岸辺の灯台の回りに群れて、漁をしているらしいときもあるのです。
山からの眺めは広々としていて、気持ちが晴れ晴れするので良く登ります。
一番低い所にある砂留は、二番目と共に小さいのですが、三番目のものは相当大きくて、その砂場で幼児の運動会ができるほどなのです。
あきら君は、そこから上には行ったことがありません。
だいたい、ここら辺りまでが普段の行動範囲なのです。
日の丸岩は、その更に上にあるのでした。
日の丸岩
あきら君は、近所の友達と一緒に、日の丸岩まで行くことにしたのです。
さとし君と佳代ちゃんと、もう一人、のぼる君です。
のぼる君とは同級生で、さとし君は六年生、佳代ちゃんは五年生でした。
お互いに、お弁当とおやつを入れたリュックを背負って、水筒を肩にかけ、集まります。
みんな日の丸まで行くのは初めてなのです。
いざ、山へ向かいます。
いつも通っている道です。
まだ民家がありますので、その間の細い道を通って登り始めます。
民家を通り抜けた辺りで、ときどき竹トンボや小さめな竹でっぽうなどを作るために訪れている笹薮を横目にしながら、更に進むと、第一砂留に出るのです。
そこを渡って、通りなれた細い山道を、山水の流れに沿って登ってゆきます。
すると、すぐに第二砂留の横に差し掛かりますので、更に登ってゆくのです。
茂った草木を、かき分けながら進みます。
さあ、いよいよ第三砂留です。
大きな砂留を登って、越えたところが、けっこう広い砂場になっています。
そこで一息つくのです。
ちょっと隠れ家に寄ります。
男どもは立ち小便です。
そこえゆくと佳代ちゃんは、お尻を出して、しゃがんでのおしっこです。
佳代ちゃんは平気でするのですが、男どもは、
いかにも気にしていないかのような振りをしています。
でも男どもは、何とか佳代ちゃんを自分のものにしたいのは明らかでした。
今日は隠れ家でゆっくりしているわけにはいきません。
更に上を目指すからです。
しばし、水筒のお茶を飲み、お菓子を頂きます。
「佳代ちゃん。
これ食べる。」
のぼる君が、袋に入ったポテトチップスを差し出します。
「ありがとう。
少し頂くね。」
「僕のも食べない。」
「良かったら、これも食べて。」
あきら君も、さとし君も、それぞれに、袋に入ったお菓子を差し出します。
佳代ちゃんを独り占めにはさせられません。
みんなそれぞれにけん制しあうのです。
佳代ちゃんもそれを察して気を使っています。
けっきょく、みんなで食べ合うことになったのでした。
「この、かりんとう、おいしいね。」
佳代ちゃんが言います。
「この一口羊羹も、甘くて、おいしいね。」
「この一口チョコレートも、とっても甘いね。おいしいよ。」
みんな、それぞれに、お互いのお菓子を、堪能し合ったのでした。
最後にお茶を飲んで、さあ、出発です。
一休みを楽しんだ四人は、更に上を目指します。
ここから先は、普段、あまり踏み込んだことがないのです。
それでも四人は、山水の流れに沿って進みます。
やがて、山水の流れとも別れて、ふたたび、登りにかかるのです。
そこからはシダが覆っていて、なかなか前へは進めません。
もちろん、道はないのです。
シダの茎が強く張っているので足を取られます。
上の方に、あるだろう、日の丸岩を目指して、ただ、ひたすら進むだけです。
斜面も急になってきているので、かなり手こずります。
それでも、先を進んでいる、のぼる君が大変なのであって、そのあとを一列になって付いて行っている三人は、比較的、楽なのです。
まあ、ここは、時間をかけるしかありません。
四人は、黙々と登りました。
さしものシダの茂みも、そろそろ終わりです。
あと一息。
みんなは頑張りました。
そして、一休みです。
山を回り込んでいるので、もう、砂留は見えません。
反対に、日の丸岩が見えてきているのです。
俄然、勢いづきます。
はやる気持ちを抑えて、まずは一服です。
斜面ですから座るといっても、体を確保するだけで、やっとですが、それぞれ上手に休んでいます。
「もうすこしだね。」
あきら君が言います。
「うん。
頑張ろう。」
のぼる君が応えます。
「もうちょっとだもんね。」
佳代ちゃんも頑張っています。
お茶も飲んだし、さあ、出発です。
みんなは、また、登り始めました。
なにしろ道がないので、散り積もった落ち葉が滑りやすく、大変です。
お互いに、ときどき足を取られます。
それでも、どうにか、大きな岩々から水の流れた跡らしいところまで到着したのでした。
後は、ここを慎重に登るだけです。
みんな滑りやすいので気を付けます。
とうとう日の丸岩まで、やって来たのです。
「大きな岩だね。」
「本当に大きいわね。」
「こんなに大きいとは思わなかったよ。」
「最高だね。」
みんなは口々に感想を述べます。
岩の上に登った四人ですが、まずはお弁当でしょう。
ご苦労様でした。
そのご褒美は、素晴らしい眺望です。
瀬戸内海が一望できるのです。
穏やかな海面をフェリーボートが進んでゆきます。
お弁当の味も格別でした。
そのとき、下の茂みで音がします。
「ガサガサッ、ガサガサッ!」
みんなが、何だろうと思って覗いてみると、一羽のオスの雉が出てきて、斜面を登ってゆくのです。
「まあーっ!
とっても奇麗。」
佳代ちゃんが呟きます
「ほんとだね。」
みんなは声を殺して見詰めます。
顔は赤くて羽は青いのです。
そして、キラキラ輝いています。
他の色も混ざり合っていて、何とも言えないのです。
「こんな所に、雉がいるんだね。」
みんなは、感心しています。
まもなく雉は、どこへともなく消え去ってゆきました。
一同は声もありません。
暫く余韻に浸っているのでした。
さあ、お弁当の後片付けも済ませて、探索です。
大きな岩々の一つに、大きな日の丸が彫られていて、赤い塗料が塗られています。
(これが下からも見えていて、目印になっているんだな。)と、一同は納得したのでした。
みんなで周りをよく調べてみます。
すると大きな岩々が集まっていて、その隙間がトンネルのように通れそうなのです。
「ちょっと僕が入ってみるよ。」
そう言って、あきら君が入ってみます。
中は、ちょっとした防空壕のような広さがあるのです。
みんなも入ってきました。
「すごいわね。
こんなになっているなんて・・・・・。」
佳代ちゃんが感心しています。
みんなも同感でした。
あきら君は、あちこち調べています。
しかし、光が余り入ってこないので、薄暗いのです。
みんなで調べてみました。
するとです。
壁に覗いている石の一つが抜けました。
中には銅板らしきものが入っているのです。
それを表に持ち出して調べてみました。
文字が彫り込まれています。
まさか、こんなものが見つかるなんて思ってもみなかったのです。
どうやら英語で書かれています。
「僕が預かっておくよ。
英語の先生に読んでもらおう。」
あきら君が言います。
「それがいいわね。」
「うん。
頼むよ。」
「これはいったい何でしょうね。
ワクワク、ドキドキしますね。」
そうして、みんなは帰路に就きました。
みんな期待で胸が一杯でした。
日はもう山の向こうに沈んで、辺りは薄暗くなってきています。
そうして無事に山を下ってきた一行は、一段砂留の辺りに差し掛かりました。
すると向かいの山の斜面に、灯りが連なっているのが見えるのです。
(なんだろう・・・・・。)
一同は不思議に思いました。
「きっと、狐の嫁どりだよ。
おばあちゃんが言っていたんだ。」
さとし君が言います。
確かに狐の嫁どり行列のように見えるのです。
(不思議なことがあるものだなあ。)と、みんなは思っていました。
「今日は不思議なことばかりだったね。
ひょっとしたら、狐に化かされているのかも知れないね。」
あきら君は、しみじみとした様子で言うのでした。
託された銅板
あきら君が銅板を英語の先生に読んでいただいたところでは、次のようなことが書かれていたのです。
私は船乗りです。
世界中を回っています。
私が今までに見聞きしてきた珍しいことを、皆さんに授けようと思っているのです。
どうか、隈なく調べてみてください。
きっと、ご満足いただけるものと信じています。
さあ、冒険の世界へ旅立ちましょう。
一 ペトラ遺跡
二 ツタンカーメン王墓
三 ナスカの地上絵
四 ストーンヘンジ
五 クフ王のピラミッド
六 ベルサイユ宮殿
七 モナリザ
「どうやら、この銅板は船員さんが残していったもののようです。
ひょっとしたら、岩を彫って日の丸を造った船員さんなのかもしれません。
遥かなるロマンではありませんか。
僕は、その、ご期待に応えようと思っています。」
みんなに、そう宣言したのは、他でもない、あきら君だったのです。
ペトラ遺跡
ペトラを含むヨルダンや、その周辺は降水量に乏しい乾燥地帯だそうです。
特に、ペトラの周辺は雨がほとんど降らない砂漠地帯だったようです。
砂漠気候の特徴は一日の気温差がとても大きいことで、夏の最高気温は五十度に達する日もありますが、夜には二十度近くまで気温が下がるんだそうです。
雨は冬のごく限られた期間に、ほんの少し降る程度で、基本的には一年を通して乾燥した気候なのだとか。
ペトラ遺跡を残したナバテア人は、周辺にある水源地から水道管を通して水を得ていました。年間降水量が百五十ミリ、日本の十分の一ほどの降水量しかないのですが、ペトラの市内や周辺の山には雨水をためる貯水施設が見つかっています。その数、二百以上。また、ナバテア人はペトラの外から水を引く技術も確立していました。ナバテア人は地形をうまく読み、高低差を活用して水源から水を引いています。水道管には陶器を使用しました。陶器でできた水道管はメンテナンスが必要で、数年に一度は交換しなければいけませんでした。でも、だから、降水量の少ないペトラに都市を築くことができたのです。
砂漠の中にあり、生活に不便なペトラに、なぜ古代遺跡を残すような大きな都市が造られたのでしょうか。
それは、ペトラが交易ルート上に存在していたからでした。
ペトラを中心として考えると、西に地中海沿岸のガザ、北に古代から続く中東の中心都市であるシリアのダマスカス、南に紅海の重要な港であったアカバがあります。
ペトラは貿易品を運ぶキャラバンの中継地点として繁栄したのです。
中国から運ばれた絹、東南アジアやアラビア半島南部から運ばれた香料、香辛料などを積んだキャラバンがペトラで、つかの間の休息をとりました。ペトラは西のローマ帝国と東の中国・インドを結ぶシルクロードの一翼を担っていたのです、
ペトラを支配したナバテア人は、キャラバンに、宿と保護を与える見返りに税を取りました。こうしてペトラは大都市に成長したのです。
アラビア半島南西端にあるイエメンは紅海とインド洋を結ぶ重要地点でした。
旧約聖書に登場するシバの女王はイエメン周辺を支配したと言われています。シバの女王はヘブライ王ソロモンに黄金や香料、宝石などを贈りました。イエメンを代表する香料が乳香です。乳香はカンラン科の植物から得られる樹脂で、お香や香水の原料として珍重されました。黄色透明で、火であぶると芳香を放ちます。聖書ではイエスの誕生を祝った東方三博士が献上物として持参したほどの貴重品でした。
もう一つの香料は没薬(熱帯産のカンラン科の低木コミフォラから採れるゴム樹脂)です。没薬も東方三博士の献上物の一つで、香料としての利用のほかにミイラ製造の際の防腐剤としても用いられました。アラビア半島南部や東アフリカで産出される乳香・没薬は、ペトラを通ってローマ帝国などの西方世界に持ち込まれました。
シルクロードの中継都市として、また、香料貿易の中継都市としてペトラは大いに繁栄し、この財力をもとにナバテア人は勢力を拡大しました。一方、ペトラの富は周辺諸国を魅了し、支配下に置こうと大国が動きました。ヘレニズム三王国の一つである、セレウコス朝や、現在のイスラエル周辺を支配したユダヤ人のハスモン朝、更に西方の覇権国家であるローマ帝国までペトラに進出しました。最終的にペトラはローマ帝国の属州に編入されたのです。
ナバテア人は、ペトラ周辺で活動していた遊牧民でした。紀元前千二百年頃からペトラに居住していたエドム人たちを南へ追いやったナバテア人は、ペトラを都とした王国を築きましたが、ナバテア人は文字を持っていたものの、彼らの歴史を記した書物は見つかっていません。そのため、ナバテア人のことは、ギリシア人や他の周辺諸民族の記録からたどるしかありません。紀元前四世紀、ギリシア人が残した記録が、ナバテア人についての最古の記録です。
この大国の文化は、基本的にはアラビア文化の流れを汲み、少なからずギリシア文化の影響も受けています。宗教はセム系で、アラビア語を話しアラム語を書くこの文化は、ナバテア文化と呼ばれています。ヘレニズム様式の建築や、優れた陶器製作技術を持っており、陶器の技術はエドム人から受け継いだものです。ワディ・ムーサで発見された窯は、ペトラが三世紀末まで陶器生産の中心地となっており、その後、衰退したことを証明しています。天然の砂岩に彫刻をして中心街路が造られており、岩壁の所々にくねくねとした美しい飾り文字も刻まれています。この文字はナバテア文字と呼ばれており、王国で公式に使われていました。最も古い文字は、紀元前九十六~九十五年に書かれたもので、岩壁だけでなく、石碑やコイン、陶片など、遺跡のあらゆるところに文字が書かれています。この頃から二百年の間に、書体に個性が出てきており、文字は飛躍的に発展したようです。フェニキア文字からアラム文字へと発展したのち、ナバテア文字が作られました。ローマによる王国併合ののち、ギリシア語が公用語になりましたが、一部でナバテア語が使われており、旧王領内のアラブ人に伝わり、これがアラビア文字へと発展したのです。
ナバテア人たちは馬を導入し、騎馬部隊を編成。シルクロードやアラビアからやってくるキャラバンたちの護衛をおこない、通商路の安全をはかりました。
一方、アレクサンドロス大王の死後、配下の将軍たちは大王の後継者の座をめぐって激しく争いました。有力者の一人で、マケドニアの王となるアンティゴノスは、隊商路を支配し富を蓄積したナバテア人に目を付け、ナバテア人から富を略奪しようとしますが、ナバテア人はアンティゴノスの軍を、三度にわたって撃破。独立を守りました。
紀元前百六十八年、アレタス一世はペトラを都としたナバテア王国を建国します。
アンティゴノスや、後に旧ペルシア帝国領を引き継ぐ形で成立したセレウコス朝などとは緊張関係が続きますが、ユダヤ人のハスモン朝とは友好関係を保ちました。しかし、ハスモン朝はナバテア王国の周辺にまで勢力を拡大したので、交易路を守るため、ナバテア王オボタス一世はハスモン朝と戦い勝利します。その後、ナバテア王国とハスモン朝の戦いに乗じて攻め寄せたセレウコス朝のアンティオコス十二世をナバテア王国が討ち取り、勢力を拡大しました。
ナバテア王国は紀元前一世紀頃に勢力を拡大。アレタス三世の時代にはシリアのダマスカスやエジプトのシナイ半島まで勢力下におさめ、ナバテア王国の最盛期を築きます。しかし、領土の拡大は西方の大国、ローマとの軋みを招かずにはいられません。ローマ帝国の東方で軍事活動を行っていたローマの将軍、ポンペイウスは、ユダヤ人の内戦に介入していたナバテア王国に圧力をかけ、ユダヤ問題から手を引かせます。更に、ポンペイウスがローマに返った後も中東に駐留していたローマ軍は、ナバテア王国に圧力を加え続けたため、アレタス三世は、銀三百タレントを支払って、ローマに従属しました。
一世紀になると、ペトラを通らない交易ルートが開拓され、交易の主導権はナバテア王国からパルミラ王国へと移り、ペトラとナバテア王国は衰退します。
西暦百六年、ナバテア王ラベル二世が死去すると、ペトラなどナバテア王国の主要都市はローマのアラビア・ペトラエア属州に併合されました。
三百六十三年に発生した大地震でペトラは大きな被害を受けます。その結果、衰退に歯止めがかからなくなり、歴史の表舞台から姿を消してゆきました。
十九世紀にスイス人探検家のヨハン=ルートビヒ=ブルクハルトがペトラ遺跡を再発見するまで、ペトラは永い眠りにつきます。ペトラは長期間放置された状態でしたが、降水量が少ないことも幸いして、多くの建物が残されました。
古代都市ペトラに行き着くには、幅二m、長さ千二百mもの薄暗い峡谷を抜ける必要があります。この峡谷はシークと呼ばれ、水の浸食によってつくられたもので、両側の絶壁には運河の後が見られ、主要な交通路であったことが分かります。また、壁には祈祷用の碑や彫刻、霊石などが見られ、シークには訪れる人を魂の内部へ導く、という宗教的な意味もあったと考えられています。
谷底にあたる通路は高さ九十から百八十mの地質断層の見られる絶壁に挟まれています。
岩肌は天然の赤みがかったバラ色のグラデーションで、日の当たる角度によって色が変わり、行きと帰りでは全く異なった雰囲気を見せてくれます。シークには神の像などが彫られていました。
長いシークを抜けると、岩壁の隙間から建物が見えてきます。エル=ハズネです。
赤い岩山に彫り込まれたエル=ハズネは、高さ約四十m、幅約二十五mあり、紀元前三十年~九年の間に建設されたと考えられていますが、もともと、ナバテア王の墳墓として一世紀初頭に造られたものだとも言われています。住民の間では、エジプトのファラオの宝物が隠されていると信じられていたそうですが、実際には内部に何も残されていないため、神殿として使われたものか、王の墓だったのかは分かっていません。この建物には、コリント様式やヘレニズム文化など、様々な建築様式が使われていて、当時、この地域はギリシア、エジプト、アッシリアなど、様々な地域の文化の影響を受けていたことが分かります。
エル=ハズネを抜け、ペトラの内部へ狭い谷の道を抜けると岩窟墓が数多く見られる場所に出ます。四十以上の墓が連なるこの場所は、ファサード通り(ファサードとは西洋式建物の正面部分のこと)で、通りに面した場所のため、きめ細かい彫刻などが配置され、凝ったデザインです。
ファサード通りの墓は階段状の屋根を持つなど共通のデザインで造られました。来世・天国に向けて階段を登るイメージだそうです。
ファサード通りを抜けると、ローマ時代に建設された円形劇場の遺跡に到着します。
最盛期のアレタス四世の時代に造られたもので、八千人以上が収容可能です。
ローマ式円形劇場の向かい側の山には王家の墓が造られました。壺の墓・シルクの墓・コリント式の墓の三つで、特にコリント式の墓はエル=ハズネによく似た建物です。その奥には大神殿と列柱通りが現れます。
ファサードの最終地点は山道へと続き、ここを登るとエド=ディルに着きます。
エド=ディルは標高千mに位置し、九百段以上の階段を登りきったところに現れる姿は圧巻です。エル=ハズネに似た建築様式ですが、エル=ハズネより一回り大きく、高さ約四十五m、幅約五十mあります。紀元前百六年、ペトラがローマ帝国に併合されて後、キリスト教の修道士が住んでいたことから修道院と呼ばれていますが、実際は神殿だったことが分かっています。
ここまで、ずいぶん長い記述になってしまいましたが、あきら君がペトラ遺跡のことについて調べてみたところ、この様なことが分かったのでした。
また、エル=ハズネなど、砂岩でできた岩壁に彫り込まれて造られている建物は、上から下へと彫り進められたもののようです。
内部は、あまり大きくすると、岩山の重さで押しつぶされてしまうので、その点も考えられているのだそうです。
この本の表紙がエル=ハズネです。
クフ王のピラミッド
紺碧の空に向かって建っている巨大な四角錐。人類史上まれにみる建造物であるピラミッドです。その多くの謎。いったいピラミッドとは何なのか・・・。誰が、何のために、どうやって造ったのか・・・・・。
クフ王のピラミッドは、底辺が約二百三十m、高さが約百四十六mあります。そこまで石材を積み上げたのです。それがエジプト王の葬送儀礼の執り行われた墓であることは、多くの専門家の間で意見が一致しているところであります。ピラミッドの建造が、王の生きている間に成されなければならなかったプロジェクトであったならば、クフ王の場合、その在位期間は最短で二十三年だと考えられているので、どれほどの人出が必要だったのでしょうか。
アメリカの考古学者、マーク・レーナーの行った”ピラミッド建造実験”の結果を紐解いてみましょう。
一日の労働時間を十時間と想定したならば、石を切り出す、石を運ぶ、石を削って据え付ける、との三工程に分けることができるので、一日におよそ三百二十二個の石材のブロックを切り出す必要があり、三十二人で一日八個半だとすると、千二百十二人の採石工がいればよいことになります。
採石場からピラミッドまでが約三百mあるとすれば、一個平均二トン半の石材をソリに載せて引いてゆくのに、実験によると二十人なら良いということになるので、採石場とピラミッドの往復に二時間かかるとしたら、一組二十人のチームで、一日五個の石材を供給できたことになります。したがって、二十人のチームが六十八組、計千三百六十人の引き手がいたと推測されます。
また、実験の結果、テコを使って石材を持ち上げるのに四人、石材を押して位置を調節するのに二人、石材を削って仕上げをするのに二人、これに予備の二人を加えると、ブロック一個に必要な人員は十人になります。
採石場からは一時間当たり三十四個の石材が届けられるので、それを十人が一時間で一つ据え付けるとすると、三百四十人がこの仕事に従事していたことになります。しかし、このペースを維持し続けるのは少々きついので、仮に人員を倍の四十人にしたとすれば、約六百八十人の労働者が必要だったことになります。
石材を切り出すのに千二百十二人、運ぶのに千三百六十人、削って据え付けるのに六百八十人、合計すると三千二百五十二人。
これ以外でも、石材をピラミッドの上部へ運ぶための傾斜路の建設に多くの人員が必要だったと考えられています。
道具とソリを作る大工や、切断工具を作ったり研いたりする金属細工師、水を運ぶ労働者、労働者の食事を準備する職人もいたことを考えると、クフ王のピラミッド建造に関わった人々は、二万~二万五千人にのぼった可能性が指摘されています。
ピラミッドの建造実験を行ったマーク・レーナーはクフ王の大ピラミッドがそびえるギザ台地の南東にピラミッド建造に従事した人々の街を発見しました。ここにはパンの焼き場があったことが分かっています。ゴミ捨て場の調査からは、労働者たちが、当時とても貴重だった牛肉を食べていたことも判明しました。さらに、この街の近くでは労働者の墓も見つかっています。古代エジプト人にとっては、墓を持つというのは、一つの特権でした。
これらのことから、ピラミッドの建造に携わった者は、エジプトの一般市民、ことによると、ある種の特権階級、エリートとさえ言える人々だったと推測されるのです。遺骨調査の結果から、そこには女性も含まれていたと考えられているのです。ピラミッド労働者たちは仕事を終えて街に戻り、焼き立てのパンと貴重なタンパク源である肉を食べて、ビールを飲んで一日の疲れを癒していたのです。
古代エジプト人たちは死後の世界、すなわち来世を信じていました。死者が来世で有力者になるためには、葬送儀礼や死後の供物といった、生者の世話が必要だとされていました。そのため、死者は生者に世話を求め、逆に、生者は死者が来世で力を持つことによって、家を守り、維持してゆくことを求めたのです。古代エジプト人にとって王とは神であり、全エジプトの家長であったのですから、ピラミッドを造ることは、国の事業に従事するという栄誉に浴するだけでなく、自らが属する共同体全体を、王の死したのちの新たな世界へと運ぶ準備に関わることだったのです。
ここまでが、クフ王のピラミッドに関して、あきら君が調べたものです。
ピラミッドの建造に携わったのは、決して奴隷だったのではないという、最近の研究成果がうかがえます。
モナリザの瞳
これは偶然にも、以前、あきら君が、湘南の海に浮かぶ烏帽子島の探検で発見した古文書と共にあった銅の小箱に収められていたもので、寄贈した博物館で発見されたものなのです。
まさか日本に伝わっていたとは、誰しも思いもよらないところでしたので、当時、とても話題になりました。
それが、あきら君たちが発見した銅板に記されていたとは、何という巡り合わせでしょうか・・・・・。
モナリザの瞳とは、オーストリアのハプスブルク家から伝わったキャッツアイという宝石のことなのです。
それが、いつ頃、日本に伝わったのかは、まだ調査中ですが、なぜ、後北条氏に伝わったのか、謎が謎を呼んでいます。
クリソベリルキャッツアイ(猫眼金緑石)とは、金緑石の中央を、くっきりと走る乳白色の光の帯が特徴で、黒猫の妖艶な眼差しにたとえられるものです。
伝説では、ルドルフ一世(一二七三年)が実質的なハプスブルク家初代で、こののち、何らかの経緯で、モナリザの瞳が後北条氏に伝わったもののようです。
ルドルフ一世が妃と褥を共にしてセックスの最中、何かペニスの先にあたる固いものがある。
不思議に思って指を挿入してみると、このキャッツアイがワギナの奥に入っていて、妃は殊更オーガズムを感じていたのだそうです。
それはそれは、天にも昇らん気持ちであったとか・・・・・。
この、モナリザの瞳が、別名、性の解放と呼ばれるのは、そのためのようです。
もっとも、そのようなネーミングが施されたのは、もっとのちになってからのことのようではありますが、そんなことですから、好色家の間では、人知れずキャッツアイが珍重されているのでしょう。
「以上が、このたび僕の調べた限りのところとなります。」
みんなは、よく調べたねとねぎらいの言葉を投げかけるのでした。
あきら君の感想です。
「大人の秘め事のことは、いざ知らず、古代から人間には、芸術に携わる能力が備わっていたのですね。
最初に芸術なさった方は、本当に素晴らしいと思いますが、それを多くの人々に教え、広めて行くことが、また、大切なのだと思います。
学ぶ側も、継承するとともに、それを更に発展させて行くことが大切なのでしょう。
日の丸岩の銅板によって託されたのは、そういうことだったのではないでしょうか。
僕と共に研究、調査に携わって下さった多くの皆様方に感謝いたします。
ありがとうございました。
託された課題の、ほんの一部にしか携われていませんが、今後の研究、調査を宿題とさせて頂きたいと思います。
それでは御機嫌よう。
失礼いたします。」
あきら君たちの此の度の冒険は、ひとまず終わりを迎えましたが、更なる冒険は「探偵あきら 後北条秘史」へと受け継がれてまいります。
乞う、ご期待!
おわりに
最後までお付き合いをしてくださいまして、ありがとうございました。
少しでも楽しんで頂けたならば幸いです。
また別の作品でお会いできますことを楽しみにしております。
それではごきげんよう・・・さようなら。
著者 大空まえる
えいめいワールド出版
スキやフォローやシェアなどをして頂けますと本当に励みになります。 喜んでいただけるのが何よりの幸せです。
