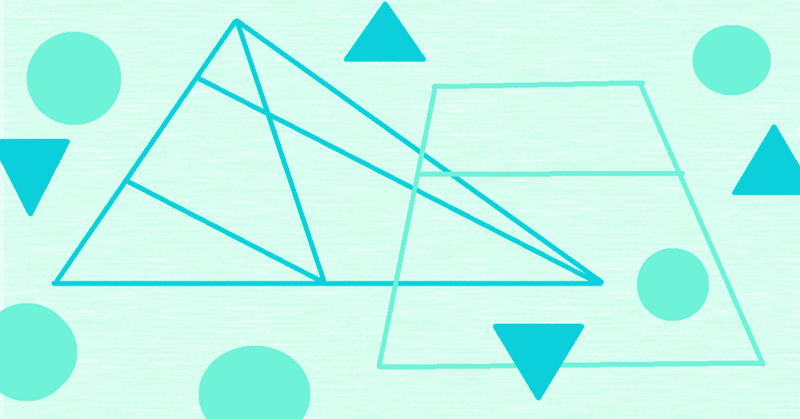
『lifetime』(1-2・2)
田崎が帰宅した頃、部屋の中は古い写真の中のように暗く、空気が停止したまま、遮光カーテンの隙間から朝日が入り込んでいた。
フローリングの床に置かれた小さな冷蔵庫の唸り声と、浴室の換気扇の音だけが田崎の耳によく届いた。
厚手のダウンジャケットを脱いで玄関脇のポールハンガーにぶら下げる。溶けた雪の雫が数滴、床に落ちて繋がった。
濡れた髪をタオルで拭くと、昨夜、出掛ける前に丁寧にセットしたセンターパートは見る影もなく消え去った。窓枠にハンガーで吊り下げたスウェットズボンに履き替えて、リビング奥の和室に敷かれた布団に潜り込む。
「おかえり」
奈緒の掠れた声がした。田崎の冷えたつま先が奈緒の暖まったふくらはぎに触れると、奈緒は小さな悲鳴をあげてから、枕に顔を押し当てたまま笑う。
「明けまして、おめでと。もう、すっかり朝だね」
ドラッグストアで三日前に買った特売のトリートメントの香りがした。触れると、奈緒の髪はまだ少し濡れている。
「ごめんね、起こした?寝たばかりでしょ」
「ううん、大丈夫。初日の出は見えた?」
暖まった布団に入ると急激に疲労が襲ってくる。山登りを終えた脚はすっかりくたびれているのに、天井を眺めていると、頭だけがやけに冴えてしまって眠れなくなるのだった。
深夜から明け方にかけて、田崎は市内の小さな山で友人二人と一緒に登山をした。今年の初日の出を山頂で見るためだった。
幸いなことに、天候は荒れることもなくものの一時間程度で登頂することができたが、しばらく運動から遠ざかっていたせいか、二十歳の田崎であっても帰りのバスに乗るころには両脚に力が入らなくなっていた。
「よくわかんないけどきっとあれはダメだったんだと思う。曇っててさ、テレビで見るのとは全然違ったから」
「もっと高い山なら良かったのかもね。ダイちゃんとミッチーは帰ったの?」
「うん、ダイちゃんはこのままヒットパレード見るって張り切ってた。たぶん、空気階段見るまで寝ないんじゃないかな。ミッチーは夜からバイトだから、今頃もう夢の中だよ」
一週間ほど前に、初日の出を山頂で拝もうと言い出したのは、花田だった。またダイちゃんがおかしなことを言い出した、と笑う堀沢は、スマートフォンで初心者でも登りやすい近郊の山を検索した。
「淳哉のアパートから結構近いじゃん。大晦日は淳哉の部屋に早くから集まってプロスピやろうよ」
田崎は堀沢からの提案に焦って首を横に振る。
「あー、大晦日はバイトが夜のシフトだから無理かも。終わり次第Switch持ってミッチーの家に行くからダイちゃんとミッチーで集まっててくれたほうがいいよ、絶対」
結局、田崎の言い分を疑う者はおらずに、昨夜───、大晦日の夜は堀沢のアパートに集合した。花田は昼過ぎからゲーム機を持って、堀沢と二人で過ごした。田崎が堀沢の部屋を訪れた時、すでに午前零時を回っており、田崎は二人から散々文句を言われたあと、山を目指して出発したのだった。
「本当に君たち三人は仲が良いんだね」
話を聞きながら、奈緒がくすくすと笑う。カーテンの隙間から差し込む陽の光は段々と強く、鋭くなっていく。
大晦日、田崎は一日中奈緒と一緒に過ごしていた。朝食に目玉焼きを焼いて食べ、テレビを見たあとスターバックスでコーヒーを飲んだ。
招き猫のタンブラーを指さすと、奈緒がお揃いで買った。ひとつを田崎に手渡して、無事に内定が出ますように、と言って手を合わせた。
「私は大学に行かなかったからね。だけど、やっぱり今の暮らしぶりを予想できてたら、大学に行ってたかもな、って時々思ってる。行っても結局同じだったかもな、とも思うけど」
「……今夜、奈緒さんも一緒に山登ってみる?」
空の招き猫のタンブラーを片手に歩く大通りは、年末特有の寂しさと高揚感が混ぜこぜになって不思議な活気を纏っている。大晦日ともなると年末セールもどこか身が入っていないように見え、売り出しと撤収が同時進行で進められているような店舗も多くあった。
ため込んだ言葉が漏れ出るような田崎の誘いを、奈緒は驚いた表情で受け止めた。田崎の鼻先に冷たいものが触れて、雪が降り出してきたことに気付く。
「淳哉くん、わたし、年が明けたらもうすぐ四十歳だよ?大学生男子の登山と同じに考えないでよ、元旦から遭難しちゃう」
奈緒は田崎の顔を覗き込むように首を傾げながら、笑顔を見せた。
「それに、ダイちゃんとミッチーだってまだわたしと会ったことないんだから、いきなりついて行ったら驚いちゃうでしょ」
奈緒の横顔が、無風の中を降りてくる大きな粒の雪の幕に遮られたせいで遠くなってしまった、と田崎は考えていた。
お揃いのタンブラーも、サイズ違いのコーヒーも、二つくっついた目玉焼きも、すべてが遠ざかってしまいそうなのはまだどこか浮ついているからなのだと、田崎は自覚していた。自分の人生をちょうどもう一度経験しているような年齢の人と恋人になるなんて考えたこともなかった。想像もしていなかった出来事が起こっている時、気持ちが追いつかずに現実味を感じられないことは田崎には時々あることだった。
どこかうわの空で歩く自分と、奈緒の横顔が抱えている不安を見比べて、離れることのないように強く奈緒の手を握る。
離れていくのは、奈緒なのか、自分なのか、わからないままに縋るような、そんな手を奈緒は柔らかく握り返した。
目を覚ますと、すでに奈緒の姿は無くなっていた。
スマートフォンを光らせると、すでに午後二時を過ぎていた。一月一日という表示の横に見慣れない西暦が並んでいて、田崎は布団から出て背筋を伸ばす。
遮光カーテンを開けると、くるぶし位まで積もった雪に様々な足跡が残されている。昨夜、脱ぎ散らかしたジーンズは折り畳まれて一人掛けの座椅子に置かれていた。
「最高だった、空気階段。出番が結構後半でさ、俺、眠気と戦うのに必死だったけど、あれを見れたらなんか良い年になりそーって思えたよ」
インスタントラーメンをすする花田は興奮気味に言った。誘われてもいないのに訪れた花田の部屋は、本や服が積まれてはいたが、不思議と乱雑な印象はなく、整頓されているように思えたのはもう三年近く通い詰めているから慣れてしまったのだろうと田崎は思う。
「ねえ、ダイちゃんは最近地元帰ってる?」
「え?いや、成人式以来帰ってないからもう一年くらい帰ってないかな。って言っても、バスで二時間だろ、地元って言ってもなんだかなぁ。それに、毎日淳哉とミッチーに会ってるんだもん、中学高校の時とあんま変わんないよ」
「俺たち、これからもずっと一緒なのかな。三十歳になっても四十歳になっても」
花田はラーメンを食べる手を止めて、しばらく考えるように黙った。
田崎と花田と堀沢の三人は、幼稚園からの幼馴染だった。同じ小学校、同じ中学校、同じ高校に通い、ずっと同じクラスで、申し合わせたようにサッカー部に所属した。
「俺さ、奇跡の途中にいるんだなって最近思ってるんだよ」
コップの中の烏龍茶を一口飲んでから、花田は言った。
「初めて出会った時から、って言っても幼稚園だから全然覚えてないくらい当たり前に一緒にいるじゃん、ずっと。クラスだって十二年間同じ。進学した大学も同じ。そんなことって普通あり得ないと思うんだよ」
思いもしなかった花田の熱量に圧倒されて、田崎は思わず身じろぎする。
「俺たち三人は奇跡的にずっと一緒なんだ。きっとこれからもずっとそうだぜ、そういう運命なんだ」
今まで一緒だったものは、きっとこれからも。花田が三人の関係をそういうふうに捉えていることが、田崎は素直に嬉しかった。田崎も、そうなればいいと思う。まるでその存在を自らの一部のように思えるような友情は、簡単には得難いものだ。
積み重ねた時間は残された時間と反比例して貴重になってゆくだろう、と田崎は想像する。大人になってから子供時代を共有することはできないのだから。
「俺も空気階段の動画見てるんだよ」
「マジ?面白いだろ?ななまがりもいいぜ。あんまりテレビで見る機会はないけどなあ」
本当はお笑いにそこまで興味はないのだけど───。
花田の思いを聞いた後であればなおさら、花田や堀沢を喜ばせたいという気持ちが強くなった。これからの十年、二十年、彼らと一緒にいるために。
奈緒の顔が頭をよぎったが、今はまだ彼らに伝えるのはやめようと田崎は思った。田崎はいま、この三人が奇跡を続けていくためには、横並びでいることが大切なのだと感じた。同じ時間をともにすること、同じものを見て笑うこと、同じ悩みをもつこと。それらが奇跡を可能にするために必要なことであり、今、二人との違いを明確にしたくなかったのだった。
冬の日は短い。午後に入ってうっかりするとあっという間に暗くなる。薄暮の部屋の中、今度の日曜日にヨガ教室に行くのについてきて欲しいと、奈緒は田崎のアパートのキッチンで玉ねぎをみじん切りにしながら言った。
田崎は奈緒の隣で手際の良さに見入ったまま、頭の中で玉ねぎをくるくる回し、なるほど、ここをこう切るからみじん切りが出来るのか、と感心しているところで、生返事を返した。
「ほら、大晦日に登山誘ってくれたじゃない?もう四十だからって言ったけど、あとから考えて思ったの。少し身体動かさないと駄目かなぁって」
「だからヨガ教室?」
「そう、おかしい?いきなりハードな運動はできないけど、初心者歓迎の教室なら続けられるかなあって思って。その教室が男性も女性も通えるらしいから、淳哉くんも一緒にどうかなって考えたんだけど、興味ない?」
腰に手を当てたまま、田崎は少し黙って考えた。頭の中ではレオタード姿の鈴木もぐらと水川かたまりが躍るCMが流れ、ヨガってあれとは違うのかな、と小さく呟く。
ただ、日曜日はアルバイトのシフトに入っている。前髪を両手で左右にかき分けると、フライパンからジャアっと玉ねぎの水分が蒸発する音が聞こえた。
「時間なかったら全然大丈夫だから。わたしも迷ってて、二人だったら心強いかもって思ったんだけど、なにも一緒に行かなくてもいいことだしね」
奈緒の視線はフライパンの中の玉ねぎに注がれていて、田崎にはその真意を推し量ることは難しかった。
「でも、奈緒さんは一緒に行きたかったよね」
「それはやっぱり、一緒だと心強いよ。だけど、淳哉くんには淳哉くんの生活があるんだから、そっちも大切にしてほしい。大学生なんて一番楽しい時期なんだからさあ」
炒められて飴色に変化した玉ねぎは一度違う皿に移された。立ち上る湯気はふわりと甘い香りを含んだまま、換気扇に吸い込まれて消えてしまった。
「奈緒さん、俺、奈緒さんのこと好きだよ」
冷蔵庫にもたれると薄い床材が軋む音が聞こえた。田崎は奈緒の後姿と、次々に小さくなっていく食材を交互に眺めていた。
華奢な腕と狭い肩幅は、小柄な奈緒を的確に現すシンボルのように見える。グレーの薄いニットが包んでいる背中に、固くひとつに結ばれた黒い髪がまっすぐに下りていた。
田崎は、奈緒がどんな仕事をしているのか、何も知らない。
出会ったのはアルバイト先である居酒屋で、声をかけたのは客である奈緒だった。その場で連絡先を交換し、他愛もないやりとりを続けた。
「一緒にいる時間が少ないのは、不安だ。どこか離れていってしまうような気がして。二人でいるっていうことは、同じが増えていくってことだよね。同じ時間を一緒に過ごせば、同じ思い出が増えていく。そうやって、究極的には二人でひとつになるってことだよね。だから、できるだけ一緒にいたいって思うんだ」
包丁をまな板に寝かせるようにそっと置くと、奈緒は振り向いて田崎の目を見る。いくらか見上げるような形になりながら、両手で田崎の人差し指を握る。
「二人だよ、淳哉くん」
テレビでは見慣れたニュース番組が喧しく声を上げ、今年予定されている出来事を大きなボードにまとめている。スポーツの国際大会、巨大な商業施設の完成、選挙───、新紙幣の発行も予定されています、とキャスターが伝える。
「二人はどこまでいっても二人。ひとつになんてなれないからね」
田崎の鼻の奥がつんと痛む。奈緒の手はしっとりと濡れたまま、冷たい水の温度を間接的に田崎の指に伝えた。
「君がどれだけ急いでもわたしの年齢に追いつけないように……違いは違いとして、誰と誰のあいだにも横たわっている。君には君の、わたしにはわたしの生活があって、それは物理的な距離だけで縮まるような単純なものじゃない。そしてそれは何も寂しいことだけでもない」
自分が都合のいいことを言っているのが、頭でわかっているからこそ田崎は余計に奈緒の言葉に首を縦に振ることができない。
奈緒にすべてを、田崎の持てる時間をすべて差し出しているわけでもないのに、離れていってしまうことへの不安を口に出してしまう。
矛盾した我儘も、年齢からくる甘えに落とし込めるはずだと見込んでいることこそ、本当の甘えだと田崎は気がついていた。
「それじゃあ、これからも一緒にいるためにはどうしたらいい?」
やはり、冷蔵庫の唸り声、浴室の換気扇の音。テレビの中の新しくなる紙幣たち。
思い返してみれば、いつも一緒の横並び、なんて思い上がりだったのかもしれない。田崎は思う。
奈緒のことではない、三人のことだ。田崎と花田と堀沢。花田は、奇跡だと語っていたけれど───
肌を灼くような陽射しと、舞い上がった土埃が、空っぽになった身体を容赦なく責め立てる。グラウンドの端に、白く四角いゴールが見える。あの夏の喧騒。ボールが砂を掠める乾いた音と、指示を出すチームメイトの声が校舎に跳ね返って重なり響く。
「先生、淳哉がやばそうです」
花田の声が、水中で聞くようにこもって遠く聞こえる。田崎は寄り集まってくる数人のスパイクを見比べていた。
腕が堀沢の肩にかけられ、田崎はグラウンドの外の芝生に横たわった。芝のひんやりとした感触と、ちくちくと刺さる感覚。濡れたタオルが額にかけられる。
「水分摂れるか?脱水になりかけてる」
堀沢が田崎の首元や指先に触れながら言った。田崎はゆっくりと身体を起こして、差し出されたペットボトルに口をつける。喉の奥を流れる冷たいスポーツドリンクが、全身の血管を通って供給されていくのが感じられるようだった。
「ごめん」
「謝るなって。今日は暑すぎるよ。俺もちょっとキツかった」
そう言うと、堀沢は芝生に並んで横になった。
「すごいよなぁ花田は。ずっと先頭で走り回って、どこからあの体力出てくるんだろ」
遠くでボールを追いかける花田の姿を、田崎と堀沢はそろって眺めた。
「俺もダイちゃんみたいに活躍したいって思ってたんだけどな」
田崎は熱くなった顔をペットボトルで冷やしながら、目を細めた。
「俺も。だけど難しいな。なんか、あいつ見てたら自分もできるかもって思っちゃうよな」
「ミッチーはレギュラーだもん、頑張れてるじゃん」
「全然敵わないよ、花田には。体力も足の速さも桁違い。おんなじ運動してきたはずなんだけどなぁ。なぁ、淳哉。今日もラーメン行く?花田、行きたがってたんだ。あ、ごめん、体調戻ってたら、でいいんだけど」
「わかった。大丈夫、いいよ」
日陰には少し風が吹いて、田崎の汚れたウェアを揺らした。堀沢は、じゃあ帰り部室でな、と言い残してグラウンドに駆けて行った。田崎はまた一口水分を口に含んでから、グラウンドの脇に立ち並ぶ白樺の葉が揺れるのを眺めていた。大きなトラックがブォンと息を吐くのを聞いた。
明日の朝にでも食べていったらいいよ、と奈緒が言って、多めに作ったハンバーグが冷蔵庫の中で眠っている。
奈緒が帰った後の部屋は、もともとの状態に戻っただけなのにやけに静かだ。そう言えば、うちの実家で出てくるハンバーグは玉ねぎを炒めないで入れるって母さんが言ってたな、と田崎は思い出していた。
明日の大学の講義の準備を始める。カバンの中に、招き猫のタンブラーを入れる。
堀沢と花田からゲームの誘いのメッセージが届く。明日は一限からだから今日はやめておくと返信すると、それぞれから「頑張れ!」とメッセージが届いた。
歯を磨いてから和室の布団に滑り込む。枕に特売のトリートメントの香りが染みついている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
