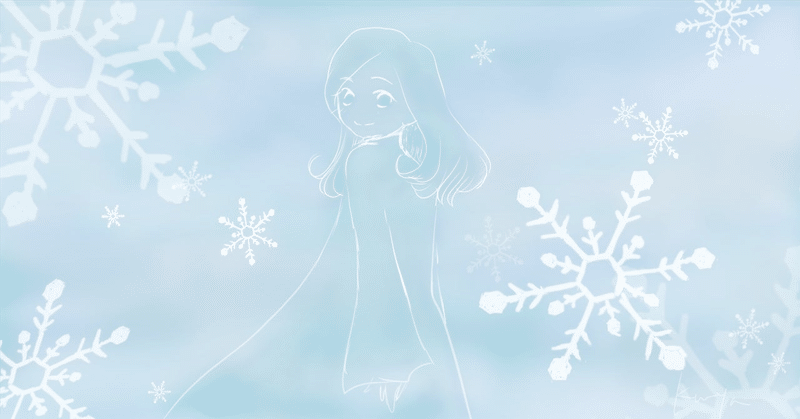
雪害(せつがい)後編
これまでのあらすじ
栞は、小瓶に入った粉骨を持参し、湯村温泉郷を訪れていた。知人の中込と遭遇した後、降りしきる雪を見つめながら亡き母と弟を思い出していた。
散骨をするべく、甲府にやってきた栞だったが、目を覚ますと盆地はまれに見ぬ大雪になっていた。
1、インフラの麻痺
雪の少ない甲府盆地を白く染め上げた大雪は人の営みを妨害していた。
どこのバス会社もタクシー会社も営業していない。
もうすでに二十件ほど電話をかけている。
散骨には、バスで行くはずだったが、大雪で運休となった。
五件目にかけたタクシー会社は大雪のせいで社員の人たちが出勤できないと電話口の人が言った。
おそらく一日か二日は営業できないだろうと話していた。
二十件もかけて無理ならば、あきらめてしまいたくなる。
宏が通った釣り場まで、到底歩いていける距離ではない。
どうして、思い出に浸って湯村温泉に泊まったの、昨日のうちにもっと近くまで行けなかったの。
雪を甘く見ていた。
手にしていたスマホをテーブル投げ出して、窓際の小瓶を見つめる。
なぜ今日でなければいけないのだ。
宏の命日でなくても散骨はできるだろう。
病床の母が言ってたことを真に受けて行動して、甲府まで来て私は馬鹿ではなかろうか。
ムシャクシャした気持ちになり、その気持ちを沈めるべく自販機でお茶を買って来ようと思い、財布を取るためバッグを覗いた。
その中から一枚の名刺が出てきた。昨日、ロビーで話した中込さんからもらった名刺だった。
2、スノボウェア
雪は止み、陽がさしている。
雪面を撫でた風が私の身を包む、冬の風の匂いの中にツンと冷たいものを感じる。
陽の光は弱く、この気温では雪は溶けないだろう。
ホテルの前で私は驚いていた。
現れた中込さんが上下スノボウェアを着ていたからだ。
昨日もらった名刺に、中込さんの電話番号が載っていたので、思い切って電話してみた。
電話に出た中込さんに事情を伝えたところ、昨日話していた四駆の車で駆けつけてくれた。
車体もタイヤもゴツゴツしていて戦車みたいに見える。ソフトな顔立ちの中込さんとは対照的だった。
「栞さんの分も持ってきましたよ」
私の分のスノボウェアも差しだしてくれた。
中込さんは戻って来た私の足元を見て、ファッションブーツでは駄目だと言ってスノボブーツを差し出した。
それに履き替えて二人してスキー客のような格好をして四駆の車に乗った。
3、嫌いな母
散骨は、渓流釣りをするような上流は無理なので、下流の公園を目指すことになった。
乗り込んだ車のフロントガラス越しに路面は見えない。
雪道には、わずかに轍(わだち)の輪郭が残っている程度だ。
運転席の中込さんはスピードを抑えて進む。
「弟さん渓流釣り好きだったんですね」
「うん、たぶん。でも山梨に来ていた本当の理由は、母の近く居るような気分に成れたからじゃないかなと思うんです。子供の頃、嫌なことがあると、すぐに母に泣きついていたような子だったから」
「じゃあ、お母さんにもうすぐ会えますね」
”もうすぐ会えますね”と言ってくれた中込さんは心根の優しい人だと思った。
「でも高校のときに親元を離れて、東京で暮らしてたわけですよね。淋しくなかったですか」
「あたし、母のことが好きじゃなかったから、べつに淋しくなかったかな。自分勝手で、フワフワしてて、男の人にだらしなくって」
私は言い足りずに付け加える。
「まだ、あたしが十代の頃、母が二番目のお父さんと別れてから、東京に居るあたしに、しばしば会いに来たんです。来るたびに違う男の人を連れて、それが、たまらなく嫌だった」
中込さんはフロントガラスを見ながら言う。
「でも栞さん偉いっすよ。自分なんて親父の墓参り、全然行ってないし」
私を慰めるような言い方だった。
4、私と母
車が川沿いの公園に着いた頃、西に傾いた陽が雲に隠れて、空は灰色になった。
駐車場に立つと陽が隠れたせいか車に乗る前よりも空気が冷たく感じられた。
ここからは歩いて行かなければならない。
雪原と化した公園は土手が高い壁のようにも見えた、雪は膝まである。
中込さんは足場の良い所を見つけては器用に土手を登って行く。
私はスノボブーツに慣れておらず、足が固定されているためか、何度も転びながら登って行く。
土手の頂までつくと今度は下り坂である。普段なら小さな子供が笑いながら駆け下りて行きそうな坂が崖のように見えた。
下りは上りと違って転ぶことすら怖い。
慎重に一歩一歩下っていくが、足を滑らせて転びそうになる。
不意に中込さんが振り向いて私を抱きとめる。
でも、私の重さに耐えきれず、抱きとめられたまま土手を転がった。
気がつくと中込さんの腕に包まれて倒れていた。
中込さんは目が合うと、驚いて私から離れる。
私は、雪を払うと、川辺を進んだ。
川岸まで辿り着く。
川の水流は北から南に流れていく。
雲から漏れる僅かな陽が南の富士山を照らしている。
ウェアのチャックを降ろして小瓶を取り出す。
さっきの転倒でも、割れていないかった。
膝をついて、小瓶の蓋を開ける。
「お母さん、良かったね」
そう呟いて私は川へ骨を流す。
小瓶からこぼれ落ちた粉骨はサラサラと音をたてて水面に落ちてゆく、全て川に吸い込まれた直後、私は自分の言葉に耳を疑った。
「お母さん」
まるで迷子の子供のような声で顔をクシャクシャにして泣き出したのである。
ドラマの演技でもでも味わったことの無いような体の底が震えるような感覚がしていた。
どうしてさっき中込さんに母が嫌いなんて強がったのだろう。
私と母の間には好きも嫌いもないのだ、好きだけど嫌い、嫌いだけど好き、それが私と母なのだ。
後ろに居る中込さんのことも気にせず、私は泣いた。
葬儀のときに一度も涙を見せなかった私なのに。
小瓶の中の粉骨が流れていった途端、母が私のもとから、すり抜けてどこかへ消えてしまったような気がして。
小瓶の中の粉骨といることで私は、母と一緒にいるような錯覚を起こしていたのだ。
もっと生きていてほしかった。
もっと一緒に暮らしたかった。
私が結婚したら旦那のことを褒めてほしかった。
子供が産まれたら、その子を抱いてほしかった。
でも死んでしまったら、そんなことすら出来ないなのだ。
北風が吹いて頬を刺す。
その北風は周囲にある木々をも揺らす、木々からこぼれ落ちた粉雪が私たち二人の身に降りかかる。
「お母さん、喜んでるんじゃないですか」
そんな中込さんの言葉に応じることもできず、
今の私は、ただひたすらに、とめどなくこぼれ落ちていく雫で降り積もった雪を濡らすことしかできなかった。
雲の切れ間から再び陽が差した頃、私は中込さんに抱えられて、その場を去った。
陽の光が私の頬を刺す。
その光は私のことを慰めるようでもあり、
弟と再会した母を喜ぶようでもあり、
降り過ぎた雪に仕返すようにも見えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
