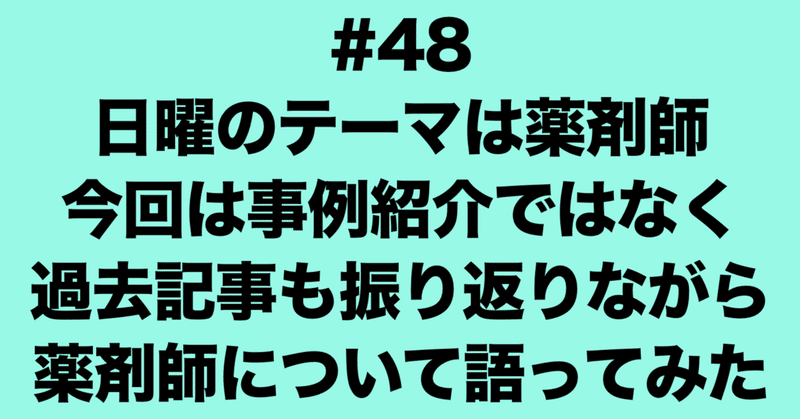
薬剤師の専門性やら、職種って何なのか、考えていることをつらつらと書いてみた
今回は事例ではなく一般論的な文章に
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
日曜日は薬剤師や仕事について語る回。
これまでは私の経験した事例をお届けしましたが、今回は私の頭の中を紹介しようと思います。
こんなこと考えているんだぁ…程度に読んでいただければ幸いです。
◼️薬剤師の専門性とは何か
アンサングシンデレラのおかげで
フジテレビのドラマ『アンサングシンデレラ』が最終回をむかえました。
原作漫画の方は引き続き連載継続しております。
漫画だけでなく、ドラマ化されたことで、今まで知られてこなかった薬剤師の一面が、多くの人に興味を持ってもらえるキッカケとなったのではないかなぁと思います。
そんな薬剤師という職種ではありますが、医療従事者の一職種でもあり、ドラマの中では『薬剤師』としての役割だけでなく『医療従事者』としての役割も描かれていたような気がします。
個人的な意見ではありますが、私自身常日頃考えていることの1つに『薬剤師であり、医療従事者でもあり、1人の人間でもあれ』という言葉があります。
この言葉を考えながら行動しているつもりですが、このように考えると同時に頭をよぎるのが、『薬剤師の専門性って何だろう』ということです。
◼️薬の影響とは何か
薬学部で学ぶこと
薬剤師の専門性を語るには、
薬学部で学ぶことを考える必要があります。
こうした考えは医師でありながら
薬局経営をされている狭間研至先生が、
常日頃おっしゃっていることです。
他の医療系の学部である、
医学部や歯学部や看護学部と違い、
薬学部で多くの時間をかけて学ぶ学問に、
薬理学・薬物動態学・製剤学があります。
そうした知識をもとに、
患者さんの身体の中に入る薬が、
患者さん自身にどのような影響を与えるのか、
思考できるのが薬剤師ではないか?
私自身はそのように考えています。
◼️患者さんへの影響を考えるには
マクロな視点とミクロな視点
ここでいう患者さんへの影響には、
薬物治療の効果や副作用といったもの以外にも、
患者さんの生活や背景や人生といったものが
含まれています。
例えば、患者さんが薬を飲むことで、
経済的にどれくらいの負担になり、
どれほどの意味合いがあるのか?
薬を飲むことで、
患者さんの体調はよくなるのか?
あるいは良くならなくても、
精神的に安定するのか?
こうした視点を評価するために、
薬に関する分野だけでも、
幅広い知識が必要になります。
冒頭の見出し的文章に書いた『マクロ』という言葉。
以前、はてなブログにも書いていました。
EBMの実践や、薬物治療学、解剖生理学や、
症候学といった汎用性の高い学問から、
腎臓病薬物療法のような、
より専門性の高い分野まで、
ありとあらゆる分野を知る必要があるのです。
そんな感じで考えながらも、
私自身まだまだだなぁと反省するばかり。
これからも精進していきたい、
と思う今日この頃です。
こんなポンコツな私ですが、もしよろしければサポートいただけると至極感激でございます😊 今後、さまざまなコンテンツを発信していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします🥺
