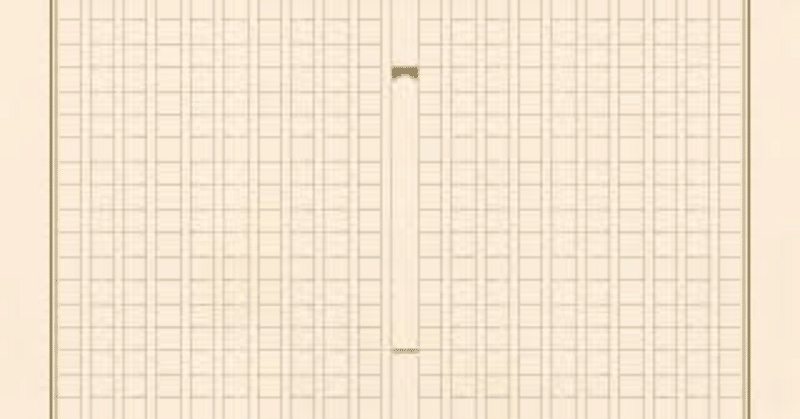
あの曲、聴きました。
僕は、その日初めて、YouTubeをダウンロードした。
そうして、勧めてもらった曲を聴いていると、心が乱されて、怖くなった。
以来、僕はその曲の再生をためらうようになった。
僕が中学2年生だった頃。隣の席の子が教えてくれた、外国人のアーティスト。
お昼休みに、ふとした会話から、ねえ、この人知ってる?って。
スマートフォンで写真を見せてくれた。もう片方の手には、お母さんが作ってくれたらしい、焼きパイシートのスティックが握られていた。
写真の中の女性は、僕の知らない人だった。
美しい人だった。その人は、己が何者かをわかっているようだった。服飾、写真の写り方。全てが計算されているように見えた。
己を主体として、世界を作り上げている人だった。
美しい人だと思った。だけど、僕はあんまり歌に興味がなかったから、記憶の表面を滑っていって、そこで終わっていた。
それから、半年経って。
半袖から長袖になって、パイシートを握っていた女の子とは席が離れた。彼女は中央の一番前に、僕は後ろの窓際になり、話す機会がなかった。
だけど、居眠りをしてしまった日。
僕は、ノートを写させてもらうために彼女に話しかけた。それが思わぬ具合に弾んで、件の歌手の話になった。
その日、僕はまっすぐ家へ帰った。
床に散らばった洗濯物や、通路を阻む、細々とした使い道のわからない収納具、小物、消耗品を避けて、部屋に入る。
そして、彼女に教えてもらった通りにYouTubeをダウンロードした。
画面いっぱいにGoogleのアカウントを作りましょう!と出てきたので、自分の情報が引っこ抜かれないか、恐る恐る入力していった。
30分後、僕の画面の中には、歌手AURORAの曲がたくさん表示されていた。
一番再生回数が多い曲を聞いてみると良い、と言われていたので、全体的に再生回数が多そうな曲を紙に書き出して、どれが一番多いのかを特定して、一曲聴いた。
曲は、雪景色と人の声から始まった。
彼女は英語で詩を歌っていた。
僕は英語がわからないから、聞き取れない。
彼女は、僕に世界を伝えるための武器を、一つ失っている状態だった。
にも関わらず、彼女の声と音楽は、ぼくの耳からスルスルと身体中を巡って、奥深くにスルリと入ってきた。そうして、「何か」に触れた。僕にはその「何か」がよくわからなかった。
だけど、彼女の歌声が僕のそれを優しく撫でたり、包んだりして、なんとなく輪郭だけはわかった。彼女の声を思い浮かべている間、僕の中には、いつも彼女がいた。僕の体の奥で、いつも見えないエネルギーを発していた。
彼女の動きの全てに、優しさがあった。
曲が終わったあと、僕はそのまま寝転んだ。
イヤホンを外して、画面を閉じて。
大の字になって寝転んだ。
疲れていた。
目元が乾燥して痛くて、頭が痛くて、頬が熱かった。
20分ほどそのまま寝転がっていた。
「何か」があった。歌声がなくなると、途端に見えなくなる「何か」。
あれはなんだったんだろう。
それがあったはずの空間に意識を向けようとしても、ボゥっとしている今は何も感じられない。
だけど、目を瞑って彼女の、AURORAの声とサウンドを思い出していると、また「何か」があることを感じ取れる。
僕は、彼女の声を頼りに、自分の中を探り始めていた。
頭の中で曲を再生すると、彼女の声が僕の中の「何か」の輪郭をなぞってくれた。
僕は、その輪郭の周りをぐるぐるとまわった。
でも、収穫はなかった。
僕の中には、何もなかった。
いや。いや、あることはあるんだ。
あることはわかっている。
だけど、言葉を当てはめられるものが何一つなかった。映像として認識することも、音として認識することもできない。触れることもできない。
形としてとらえられない。
でも、「何かが存在している」ことだけはハッキリとわかる。
気味が悪かった。
何かが、ある。
僕の中に、確かにある。
なのに、誰にも伝えられない。
見えないから、形にすることもできない。聞こえないから、音楽にすることもできない。分からないから、言葉にすることもできない。
あるのに、ない。
怖い。
こんなことは初めてだった。誰にも伝えられないことが、こんなに恐ろしいなんて。まさか、誰にも伝えられないことが、この世界に、僕の中に、存在していたなんて。
ほんとうに、ひとりみたいだ。
助けを求めたいのに、どう言えばいいのか分からない。僕が知っている言葉では、何一つ伝えられない。
僕は、恐ろしくなった。
だって、世界のほとんどは言葉で説明がついていたじゃないか。学校の授業も、テストも、成績も。会話なら、目や耳を使って、世界を捉えていた。真っ暗闇なら、手や足の感覚で、自分の位置や状況を把握できた。
だけど、ここにはなんにもない。暗くも、明るくもない。温かくも、冷たくもない。壁がない、床もない。浮いているのか、沈んでいるのか、僕は、どんな体勢なのか。
何一つ、手がかりがない。
彼女の声が「何か」の輪郭をなぞっていること以外、何も分からない。
怖い。
「確かに存在している」ということ以外、何も分からない。
これはいったい、なんなのだろう。
僕の中にはいったい、何がいるのだろう。
恐ろしい。
いつか僕は、これを、目に見える形にしたい。耳で聞こえる形にしたい。そうしなければ、僕はきっと、ずっと、ひとりぼっちだ。
ひとりぼっちは嫌だ。
ひとりぼっちのまま、誰にも知られないまま消えてしまうのは嫌だ。
彼女の声は、いったい、どこまで僕を導いてくれるのだろう。
僕は、どこまで知ることができるのだろう。
彼女は、「何か」を知っているのだろうか。
彼女が選びとったすべての音は、その「何か」から掬い上げた物なのだろうか。もしそうだとしたら、どうやってその音を聞いたんだろう。
その音が聞こえるようになるまで、怖くはなかったのかな。僕も聞きたい。見たい。
そうして、誰かと話したい。
真に、僕と話したい。
僕の中にあったもの、見つけたよって。
僕も、僕の「何か」を触って、撫でて、包めるようになりたい。
苦しかった。
何もわからないのが。
翌朝、学校へ行って、パイシートの彼女に聞いた。あの曲、聴きました。僕は、恐ろしくなりました。あなたは、どうですか
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
