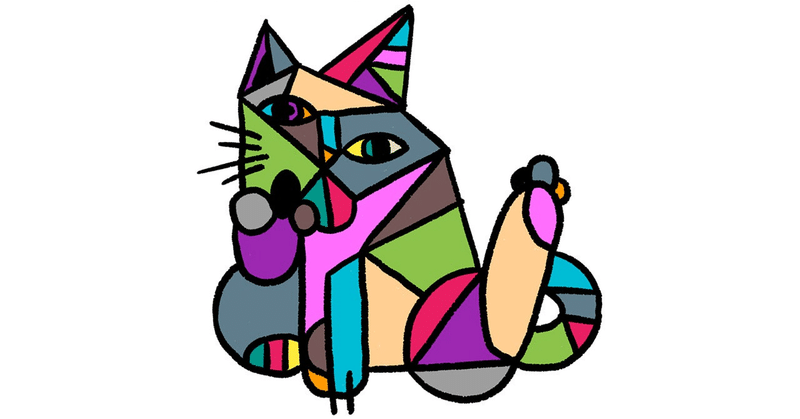
私がカメラを使って表現したいこと
はじめに(結論)
写真にのめり込み、「あ、美しい!」と思ってシャッターを押すのではなく、人に美しいと思ってもらうことを目的に、意図的に美しさを作り出すにはどうすればよいかについて、前回考察した。
これはこれで大切な検討要素で、撮りたいものが決まっていれば、写真をどんどんグレードアップできるはずだ。
一方で、そもそも自分は写真で何を伝えたいのか?という自らの軸となるテーマは、表現を突き詰める上でやっぱり必要だよね、ということも浮き彫りにさせた。
このモヤモヤに対し、これまでは避けてきた「自分の写真に対するテーマ」について深堀してみた。
結果は「カメラを通して見た世界はこんなにも面白くワクワクするものだよ」と、とにかくドヤりたい というものだった。
浅はか極まりないが、私にとってはこれが一番写真を通して人に伝えたいテーマだと確信できた。
誰にとっても参考にならない内容であるがそんなことは関係ない。
順を追って考察を記す。
私が写真を通して伝えたいテーマとは?
よく…わからない。
(この記事のこの段落を書いている時点においては)
著名な風景写真家 アンセル・アダムス(Ansel Adams)のように、
「自然保護の観点から景観を写真として残したい!」とか、
戦場カメラマンのように「悲惨な戦争というテーマを色々な切り口で撮影することで平和の重要性を訴えたい!」など、
何らかの社会問題等に対する提言 といった高尚な意識は、
申し訳ないが一切ない。
野鳥にも特段の関心は無いし、鉄ちゃんでもない。
自然風景や花は好きではあるが、では植物に対して自然と造形を深めてしまうほど好きか というと、、、ちょっと違う。
どうやら私は特定の被写体の美しさを伝えるために撮影をしているわけではないようだ。では何が楽しくて撮影をしているのだ?
やっぱりよくわからない。
だがきちんと言語化しないと前には進めない。
まずは一旦写真から一歩下がって、他のアートに対する自分の嗜好から、何かヒントを探ってみようと思う。
音楽を聞いて思うこと
私は音楽鑑賞が大好きである。
学生時代はもっぱらメタル・ハードロック系統(Slipknot様、Maliryn Manson様、rage against the machine、Slayer、Limp Bizkit、Linkin Park、AC/DC、Led Zeppelin etc凄くメジャーなやつ)にハマり、なぜかクラシックや三味線やお琴や雅楽の和楽器系にもハマり、ほんの少し洋楽のラップ(といってもEminem+αくらい)にもハマり、J-POP(女性ソロ系ばっかりだが)もちょこちょこ聞きつつ、最近はジャズも少し聞き始めた。なお、アニソンも大好きだ。要は雑食で、何でも聴く。
だが好き嫌いはかなりハッキリしている。
尖っていて、濃くて、キャッチーな音楽が好きな傾向にある。
魂の叫びのような、生々しい熱量を感じる曲が大好きで、聞いていてガツンとくるような音楽であれば、あまり聞き馴染みのないジャンルでも好きになる。歌だけでなく、超絶技巧の演奏からも、魂を感じるときは大好きになる。
なお、これは失礼かもしれないが、仮に大好きなアーティストでも、ファーストアルバムは大好きだが、サード・アルバムあたりから「枯れちまったな…」と捨て去るほど、謎のセンサーで選別をする傾向にある。
MOROHAなどは私の上記性質を説明する上ではまさに典型的な例で、日本のラップは正直物凄く苦手分野だったが、一発で虜になった。MOROHAまじで最高。普通に人気ではあるので、別に私が特殊というわけではないのだが。
さて、何が言いたいかというと、完全にオーディエンスサイドに立ったときの私は、アーティストが耳元で叫ぶくらいに「伝えたいこと」が極めて明確な作品が好きで、逆に(内容が共感できるかはさておき)そういった熱量を感じない曲は全然好きにならない。
が、しかしクリエイター側に立った時、自分の写真では何を伝えたいのか?と自問した時、かなり薄っぺらいというか、少なくとも自覚できないくらいには希薄であるという矛盾だ。
ただ、自覚なく微かな直感に従ってフラフラと歩んだ というだけで、Z9に手を出すはずがない。私はそこまで富豪ではないし、とりあえずなんでもいいものを買う というようなバカな選択しない。
はずだ。。
一旦音楽の世界を離れ、別の視点でも考えてみる。
絵画を見て思うこと
つい先日、上野の国立西洋美術館でキュビズム展に行ってきた。
別に美術にそこまでの造形があるわけではない。
最近、Youtubeで山田五郎さんの解説などを見るようになってから、ひんわりと絵画の知識がついてきて、脊髄反射で「よくわからん」とはならなくなった、くらいの状態で臨んだが、、、それでも圧倒された。
100年以上前に活躍したブラックやピカソではあるが、彼らの熱量というか、気迫みたいなものをひしと感じることが出来た。
20世紀初頭、カメラが発明され、写実的な絵画が意味を成さなくなった時代の画家が、絵画にしかできない表現方法を求め、批判されながらも挑戦的な手法で実験を重ねたアツい痕跡を感じることが出来た。
実際の絵画を見て、感動もしたが、同時に「絶対コレ描いてるとき楽しかっただろうな」みたいにも感じた。
『こんな感じで書いたら絶対一般人ついてこれないよなwwww』とほくそ笑みながら、ヒリヒリした世界の中、アトリエで突き詰めていったのではないかと、勝手ながら作成風景を妄想しながら絵画を見てちょっと笑っていた。
やっぱり音楽同様、どこか究極というか局地というか、そういったヒリヒリした情熱を感じさせるモノがお好きなようだ。
キュビズムとは描かれた時代は全く異なるが、常設展もすごかった。
17世紀や18世紀の西洋絵画が多かったが、この時代の写実主義はもうすごいし、山田五郎さんの解説など聞く限りでは、似たようなテーマを描いた宗教画であっても、画家によって「ここはめっちゃこだわります」というポイントが見え隠れしていたりと、やっぱりここにも熱量みたいなものはひしひし感じることができた。
で、お前は?
いやー、、、えっと、、、
としか返せない。いやはや、本当にお恥ずかしい限りだ。
「私にはそういった才能も、伝えたい想いもない、一般人なので!」
と言って楽になりたいし、実際に自分はアーティストでは無いので言って全然問題ないのだが、なんだか、それは逃げのような気がするし、何なら「何もない」のは嘘である気さえする。
だって本当に想いがないなら、高級なカメラを買うことはないからだ。
「iPhoneのカメラで十分」となるはずだ。
ならば、現状自覚できていない、自分が訴えかけたいテーマとはなんだろうか?
一般人とのズレから自分のテーマを逆算して導いてみる
そもそもどうしてここまでカメラにハマったのだったか。
iPhoneのカメラが使えるレベルになる以前から、私は一眼レフカメラ(エントリー機のAPS-Cセンサーのもの)に触れていたので、カメラ専用機でなければ撮れない写真があることは理解していたが、それが無くともケータイやスマホのカメラは「記録用」という領域から出ることはなく、一眼カメラの写真には「記録」以上の何かを感じていた。別物だ、という感覚はあった。
フルサイズのミラーレス一眼を買って、キットレンズだけから単焦点を買い増しして、と歩を進めるごとに、目で見ている光景から何段も落ちるケータイ/スマホのカメラの写真から、逆に目で見ている光景を超えた写真が生み出されることにワクワクしたのは紛れもない事実である。
Z9、大三元、f1/2レンズ、マクロに手を染めた直近は、もう言うまでもなくこのワクワクの直感に従った成れの果てと言える。
簡潔に言えば、目で見ている(往々にしてつまらない)情景を、一眼カメラならびに各種レンズを通して見ると一気に魅力的になる ということを知って、虜になった、ということだろう。
さぁ、どうしてこうなった?
ボディは、性能差によるAF速度や機能面での制約に煩わされたくないという理由でバージョンアップをしただけで、恐らく本質ではない。そっちではなく、センサー(APS-Cからフルサイズへの変更)やレンズ側にヒントがあるような気がする。明確に見え方が変わる点で、ワクワクの根源に近い。
私の場合は、特定の被写体の魅力を写真を通して伝えたい であったり、特定のテーマ(例えば自然保護とか)を訴えるために写真を利用したい、といった方向ではなく、あくまで「色々なカメラ/レンズを通して見た世界は、こんなにも面白い」という感動を伝えたいのではないかと思う。
だから恐らく機材が先で、その機材の表現をより強く発揮できるフィールドに持っていく というのが、やりたいことなのかもしれない。
おもしろいオモチャが手に入ったが、これを持っている人も面白さもあまり知られていなくて、なんとかしてこの面白さを伝えたい みたいな。
コレ、こんなことも出来んだぜ?凄くね?! みたいな。
なるほど、そこだったか。(自分でびっくり)
自分のテーマを自覚した上でこれまでを振り返る
少し見えてきたところで、今一度これまでの自分の撮ってきて気に入った写真を振り返り、今後撮ってみたいとワクワクするかもしれないものを導いてみようと思う。
私は自分の娘をたくさん撮るが、撮りたい瞬間も、撮ってお気に入りな写真も、どちらも「動き」のあるシーンばかりだ。
ブランコを漕いでる瞬間
こちらに走ってきている瞬間
ジャンプしている瞬間
こちらを振り返った瞬間
動いている最中に撮影したものが大好きだ。これはシャッタースピードが非常に早い一眼カメラだからこそできる芸当だ。
次に、被写界深度が極めて浅い写真。
背景が盛大にボケて、現実世界ではありえないようなドラマチックな写真になる。あれも大好きだ。最近はスマホの画像編集でもボケ感は演出できるが、ガチレンズではやはり違う。
あと、逆光やめくちゃ暗いシーンでの撮影。
レンズの性能がモロに出るもので、スマホじゃこうはいかねぇだろ、といったドヤ写真をしばしば撮る傾向にある。
さらに、マクロ。アレはもうヤバい。
望遠も楽しい。
うん、直感だけで動いてきたが、この「カメラ/レンズ遊びが楽しい」というテーマにバッチリ沿った動きをしてきたようだ。
まとめ
自分で言うのもなんだが、私は人より感受性に富む。
音楽、映画、絵画、アニメ等に触れたとき、受ける感動の大きさ、感動を享受できる範囲の広さが、少なくとも私の周りにいる"普通の"人よりは大きいと自覚している。
だが、それはそれだ。
どうもそこにヒントがあるような気がして逆にミスリードされてきたが、こと写真の撮影者側に立った時、私がやりたいことは「カメラ遊び」「レンズ遊び」であり、そこで撮った写真でキャッキャしたいのが私の本心だ。
深いテーマ?
社会問題に対する提言?
そんなもんは知らん。
私はカメラで遊びたいだけだ。それが一番楽しいしワクワクするんだから仕方ない。そのカメラ、そのレンズにしか出来ない写真を撮ってやりたいし、そこで感じたワクワクをシェアしたい。
持ってるレンズが物凄く高額だとか、ただの趣味なのにかけてるお金がすごいとか、そういうことはどうでも良い。そうではなくて、そっちではなくて、こんな奇っ怪な見たこと無い写真を撮ったこの機材、すごいだろ?!すごいよね!!と、そういうことだ。
誰でも持っているカメラで工夫して〜 だったり、そういうことでもない。
私がやりたいのは、みんな持ってるおもちゃじゃなくて、レアなオモチャで、それでしか体感できないワクワクを味わいたいし、それをシェアしたいのだ。
画像/映像データの編集は、基本的にはシラける作業だ。
あくまでもスパイスとしての役割を超えてはならない。
物理的な光学設計や本体の処理性能によって実現される光のマジックの局地にこそ、尖ったワクワクの世界があると私は思う。
全く持って、金のかかる趣味だ。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
