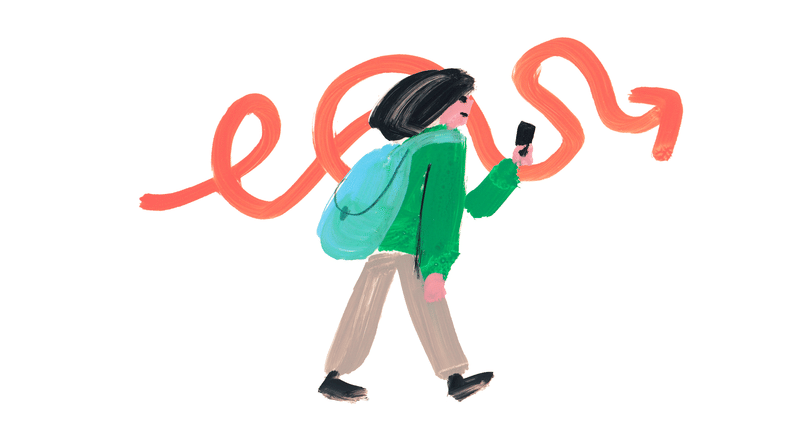
これまでとこれからと~心理療法覚書~
最初にカウンセリングを学んでから、いろんな療法に首をつっこんできました。
どれも極めたというのには程遠く、きちんと自分の療法としてものにしている方からすれば、触った程度かもしれないものも多いですが、お客さんと接する中で確かに私の中にあったものです。
今の自分を考える上で、少しふりかえることにしました。
初期Ⅰ 『聴く』
カウンセリングの勉強を開始して、実際に現場で何かするというよりは、勉強の場でのロールプレイやミニカウンセリングだったり、実際の仕事の中での、聴く場面での活用だったりした頃。
当然ながら?カール・ロジャースのクライエント中心療法から入っている。
個人的にはこれは流派とか療法というより、カウンセリングをする上での土台で、この上にいろんな療法がのっかるようなイメージで長い期間いたのでだが、最近はやはり、本当によく聴くことさえできれば何もいらないのだけれど、よく聴く難しさゆえに、他の療法が必要なのかもという気持ちに変わってきている。
初期Ⅱ 『伝える』
実際に仕事として相談を始めると、特に仕事についての相談だったこともあり、『聴く』だけではなりたたないため、どう伝えていくか、という必要性が大きな課題となってきた時期。
時代もあると思うが、認知行動療法を主とした方向へ興味が移っていった。
認知行動療法をベースとしたアサーションやソーシャルスキルトレーニング(SST)なども首をつっこんだ。
グループワークのファシリテーターなどを行うこともあり、そちらでも『伝える』重要性が大きかったのも一因と思う。
ビジネス系のファシリテーションスキルやプレゼンテーションスキルなども学んでた。
中期Ⅰ
『理解から感覚へ』
認知行動療法やアサーションはうまくいく場合はとてもいいのだが、ある程度頭で考えるのが得意な方が向いている技法で、あまり論理的に考えることが得意でない人は、そもそも利用が難しいという課題があった。
このころパールズのゲシュタルト療法に出会い、これは今でも続けている。
考えるより感じる。
いま、ここに注目する。
初めてワークを見たときには、短時間で深く入っていく様に驚いたことを今でも覚えている。
ちょうど転職の前後で、これまで以上に論理的な思考よりは感覚的な話のほうが入りやすく、精神的な疾病の重症度も高い人たちが対象となった時期と重なり、こちらへ傾倒するようになっていく。
ゲシュタルトの先生は、〇〇先生でなく、さんづけで呼ぶように言われたのも、自分にとって後に大きな意味を持っていたことがわかる。
また、この時期はボディワークやマインドフルネス、瞑想などへも興味が向かった。
中期Ⅱ
『個人から関係性へ』
今の職場に来てから、論理的な話より感覚的な話のほうが入りやすい人が増えたと中期Ⅰで書いたが、それと同時に1対1で話すだけでなく、家族や他の支援者を含めた複数での面談が増えてきたことから、家族療法を学びだした。
複数での面談の際のポイントのようなものも学んだけれど、ここで学んだ一番のことが、話の内容でなく「文脈」に注目することと、問題の「外在化」
目からうろことはまさにこのことで、問題を切り離すこと、関係性の中にみていくことで、原因を誰かにおしつけることなく、楽にものごとを進めることができることへの驚きと嬉しさがあった。
実際にうまくできるかということとは別に、対応していくのに消耗してしまう利用者に接するときの気持ちの持ちようがこの考えで劇的に変化した。
誰も悪くない。
その状況はとても私を安心させた。
あわせてこの時期はナラティブ・アプローチにも興味をもちましたが、これはどちらかというと、これまでの自分の姿勢がナラティブよりと確認した程度で終わっている。
こうしてみると、私の興味の変遷はそのまま、利用者の変遷でもあるのだとしみじみ思う。
現在 『再び聴くへ』
そして、ここ何年か私の興味の中心にあるのはオープンダイアローグとリフレクティング。
フィンランドから来たこの療法は、私に聴く力のすばらしさをもう一度実感させてくれると同時に、私の中にあったカウンセリングで生じる対等性に対する違和感も解決してくれた。
私の中ではカウンセリングや相談の際の自分と利用者の非対等性というものがずっと違和感として残っていた。
常に対等というのはありえないし、だからこそ、対等であることに、ものすごく慎重にならざるを得ないのだが、1対1の相談の場になったとき、この非対等性を生み出さないのはとても難しい。
相手のほうがよく知っているという姿勢のナラティブアプローチも、先生が先生と呼ばないようにというゲシュタルトのアプローチも、非対等性への答えのひとつだが、なかなか違和感の解消まではいかなかった。
そのジレンマに対する答えがオープンダイアローグだった。
またオープンダイアローグをしてみると本当にきちんと聴くだけでいいのだという、本来のクライアント中心療法のところに立ち戻ることができる。
きちんと聴くことの難しさに対しては、1対1の縛りを外し、聴くと話すをわけること、本人の目の前ですべてが行われるけれど、本人に向かって話さないことで、非対等性の苦しさからも解放される。
ただし、実際にやってみると、やはりきちんとリフレクティングすることの難しさは感じられる。
オープンダイアローグ発祥の地のケロプダス病院では、医師も看護師も心理職も同じようなトレーニングをきちんと受けた上で参加するというが、本人の前でいろいろな意見を伝えるというのは、簡単にできることではない。
ある意味、自分がどんな人間かを問われることでもあると感じている。
言ってみれば、公開カウンセリングなのだ。1対1のカウンセリング以上に問われる部分も大きい。
それでも私にとってとても大事な対等性をたもちながら、1対1のカウンセリング以上の結果をもたらす、オープンダイアローグに今の私は夢中である。
これから
当面の課題は一人ではできないオープンダイアローグをどう実施するか、どう一緒に入る人を作っていくか。
今の職場は、実はオープンダイアローグを活用できる場面はそれほどは多くない。というか、本来の対象者だとそれほどなくてよいのだが、私にまわされるお客さんたちは本来の対象者から外れている人が多く、オープンダイアローグが有効な人の割合が他の人よりは多いのだ。
一方で職場の体制としては今非常に厳しく、通常の3分の2しか人員がいないので、面談に複数の人が入るのはとても厳しい状況なのだ。
今のところ、他の機関の人に入ってもらい、実施することが多いが、きちんとオープンダイアローグを理解している方はほとんどいないので、うまくいかないことも多い。それでも、成果を考えると、やりたい気持ちがある。
これが続くと、場合によっては、再び仕事の場を変えることも出てくるかもしれない。
でも、それは今後のなりゆきにまかせようと思っている。
こうしてふりかえったことで、私のこれまでは聴くことから始まり、伝える、感じるを経て、今また聴くことへと向かっている。
そして、それは利用者の変遷にも大きく影響されている。
だとしたら、またこれから相手が違う層に変わると私の興味も変わるかもしれない。
自分自身の変化を楽しみながらよりよく聴けることを目指して進んでいきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
