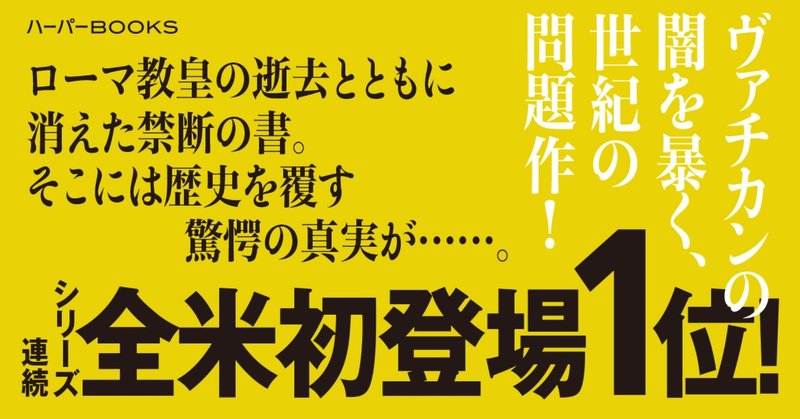
【NYT紙、WSJ紙で1位獲得の超話題作!】ダニエル・シルヴァ『教皇のスパイ』試し読み
3/17刊行、ダニエル・シルヴァ〈ガブリエル・アロン〉シリーズ最新刊『教皇のスパイ』の試し読みをお届けします!
米・Amazonレビュー1万超!〈NYタイムズ〉紙、〈ウォール・ストリート・ジャーナル〉紙でも第1位を獲得した話題作。『ダ・ヴィンチコード』好きは必見⁉
それではお楽しみください📖

『教皇のスパイ』
ダニエル・シルヴァ[著]
山本やよい[訳]
1
ローマ
電話があったのは午後十一時四十二分だった。ルイジ・ドナーティは電話に出る前にためらった。彼の電話の画面に出ていたのはアルバネーゼの番号だった。こんな時刻にアルバネーゼが電話してきた理由はひとつしか考えられない。
「いまどこだね、大司教?」
「城壁の外ですが」
「ああ、そうか。今日は木曜日だったな」
「何かあったのですか?」
「電話で詳しい話はしないほうがいいだろう。誰が聞いているかわからない」
ドナーティが夜の通りに出ると、じっとりと冷えこんでいた。いまの彼の服装は聖職者用の黒いスーツと白い立ち襟で、執務室で着る赤紫の縁どりのあるカソックではなかった。ちなみに、ドナーティのような高位聖職者たちは教皇宮殿のことを〝執務室〟と呼んでいる。ドナーティは大司教で、教皇パウロ七世に個人秘書として仕えている。背が高く、ほっそりしていて、豊かな黒髪に映画スターのような顔立ちで、六十三歳の誕生日を迎えたばかりだ。年齢を重ねても容姿にはまったく衰えがない。『ヴァニティ・フェア』誌が最近、〝魅惑のルイジ〟と題してドナーティのことを記事にした。ドナーティは中傷が渦巻く教皇庁内部でずいぶん居心地の悪い思いをさせられた。とはいえ、冷酷無比という彼にふさわしい評判のおかげで、面と向かって非難を浴びせてきた者は一人もいなかった。唯一の例外は教皇で、遠慮なくドナーティのことをからかった。
〝電話で詳しい話はしないほうがいいだろう〟
ドナーティはこの瞬間が来るのを一年以上前から覚悟していた。教皇が初めて軽い心臓発作を起こして以来ずっと。発作のことは世間に隠し通し、教皇庁の多くの者にも秘密にしてきた。しかし、なぜよりによって今夜?
通りは妙に静まりかえっていた。不意に、死のような静けさだと思った。ここはヴェネト通りから脇に入った豪邸が建ち並ぶ並木道で、聖職者が足を踏み入れるような場所ではない。イエズス会で学び、薫陶を受けた聖職者であればとくに。イエズス会は高等教育を重視し、ときとして権威に批判的な姿勢をとる修道会で、ドナーティはそのメンバーだ。〝ヴァチカン市国〟を意味するSCVのナンバープレートをつけた彼専用の公用車が、車道のすぐ脇で待っていた。運転手はコルポ・デッラ・ジェンダルメリーア─人員百三十名の市国警察─の男だ。ゆっくりした運転でローマの街を西へ向かった。
この男はまだ何も知らない……。
ドナーティは携帯電話でイタリアの主要な新聞のウェブサイトにざっと目を通した。どこもまだ何もつかんでいない。ロンドンとニューヨークの新聞も同じだった。
「ラジオをつけてくれ、ジャンニ」
「音楽でしょうか、大司教さま」
「ニュースを頼む」
今夜もまたイタリア首相サヴィアーノがたわごとを並べ立てていた。アラブ諸国とアフリカからの移民がこの国を破壊しつつあるとわめいている。イタリア人だけでは国を破壊しきれないとでもいうように。サヴィアーノはここ何カ月間も、教皇への個人謁見をヴァチカンに頼みこんでいた。ドナーティは少なからぬ喜びを胸に抱きつつ、その頼みを退けてきた。
「もう充分だ、ジャンニ」
ラジオはありがたくも沈黙した。ドナーティはドイツ製の高級車の窓から外を見た。キリストの兵士がこんな車を使うとはもってのほかだ。運転手つきのリムジンでローマの街を走るのも今夜が最後になるだろう。ドナーティは二十年近くにわたってローマ・カトリック教会の首席補佐官のような役目を果たしてきた。嵐のような日々だった─サン・ピエトロ大聖堂を狙ったテロ攻撃、古代遺物とヴァチカン美術館をめぐるスキャンダル、聖職者による性的虐待事件─だが、ドナーティはその日々を一分一秒に至るまで精一杯勤めてきた。それがいま、一瞬にして終わりを迎えることとなった。今後はふたたび、ただの聖職者だ。いまほど深い孤独を感じたことはなかった。
車はテヴェレ川を渡ってコンチリアツィオーネ通りへ曲がった。ムッソリーニがローマのスラム街をつぶして造った広い通りだ。修復で往時の輝きをとりもどした大聖堂のドームがライトアップされ、遠くに姿を見せている。ベルニーニ設計の列柱が描くカーブに沿って聖アンナの門まで行くと、スイス衛兵が手をふってヴァチカン市国の領土内へ車を通してくれた。衛兵が着ているのは夜勤用の制服だ。白い丸襟がついたブルーのチュニック、膝丈のソックス、黒いベレー帽、夜の冷気を防ぐためのケープ。衛兵の目に涙はなく、表情にも乱れはない。
この男もまだ何も知らない……。
車はゆっくりとサンタンナ通りを進んで、スイス衛兵宿舎、聖アンナ教会、ヴァチカン印刷所、ヴァチカン銀行を通り過ぎ─やがて、聖ダマシウスの中庭に続くアーチの横で停止した。ドナーティは砂利敷きの庭を歩いて横切ると、キリスト教世界でもっとも重要なエレベーターに乗りこみ、教皇宮殿の四階まで行った。片側がガラス壁、反対側にフレスコ画が描かれた柱廊を足早に歩いた。左に曲がると、その先が教皇の居室だった。
別のスイス衛兵が、こちらは正装に身を固めてドアの外に直立不動で立っていた。ドナーティは無言のまま、衛兵の横を通り過ぎて部屋に入った。木曜日─しきりに考えていた。なぜよりによって木曜日に?
教皇の書斎に目を走らせて、ドナーティは思った─十八年のあいだ、何ひとつ変わらなかった。変わったのは電話機だけだ。ドナーティの説得で、ヨハネ・パウロ二世時代の古めかしいダイヤル式電話をようやく最新型マルチライン電話に替えることができた。あとはすべて、ヨハネ・パウロ二世がこの部屋を去ったときのままだった。同じ簡素な木製デスク。同じベージュ色の椅子。同じすりきれた東洋緞通。同じ金色の時計と十字架。吸い取り紙とペンさえもヨハネ・パウロ二世が使っていたものだ。ピエトロ・ルッケージは使徒座についたばかりのころ、これまでより優しい教会、権威をふりかざすことのない教会を約束したが、それでもやはり前任者の長い影から完全に逃れることはできなかった。
ドナーティは無意識のうちに腕時計で時刻を確認した。午前零時七分。教皇が一時間半ほど読書と執筆をしようとして書斎にこもったのは、夜の八時半のことだった。普通なら、ドナーティは教皇のそばに控えるか、廊下の先にある彼自身のオフィスで待機する。しかし、今日は木曜日、週に一度だけ自由になれる夜だったので、教皇のそばにいたのは九時までだった。
〝きみが出かける前に頼みがある、ルイジ……〟
教皇は書斎の窓を覆った分厚いカーテンをあけるよう、ドナーティに頼んだ。この窓から、教皇が毎週日曜の正午にアンジェラスの祈りを唱えるのだ。ドナーティは言われたとおりにカーテンをあけた。さらに、重要な書類仕事に追われる合間に教皇がサン・ピエトロ広場を眺められるようにと、鎧戸まであけておいた。ところが、いま、カーテンはぴったり閉ざされている。ドナーティはカーテンをひいてみた。鎧戸も閉ざされていた。
デスクの上はきれいに片づき、ルッケージのいつもの散らかりようとは違っていた。中身が半分になったティーカップが置かれ、受け皿にスプーンがのっていたが、ドナーティが書斎を出たときにはそんなものはなかった。収納式スタンドの下に、書類をはさんだ紙製フォルダーがいくつか積み重ねてある。性的虐待スキャンダルによる財政面の痛手に関してフィラデルフィア大司教区から届いた報告書。来週水曜の一般謁見についてのコメント。目前に迫ったブラジル訪問のさいにおこなう説教の草稿。移民問題について教皇から全世界の司教に送る回勅のためのメモ。これを見たら、サヴィアーノ首相と彼の同調者である国内の極右勢力が激怒するのは間違いない。
しかしながら、消えている品がひとつあった。
〝かならず彼に渡してくれるね、ルイジ?〟
ドナーティはくずかごを調べた。空っぽだ。紙切れ一枚入っていない。
「何かお捜しですかな?」
ドナーティが顔を上げると、ドメニコ・アルバネーゼ枢機卿がドアのところから彼をじっと見ていた。生まれはカラブリア州、現在は教皇庁の仕事をしている。いくつか高位の役職についていて、諸宗教対話評議会議長や、ローマ・カトリック教会の文書管理と司書の役目もそこに含まれている。しかしながら、そのどれをとっても、午前零時七分に彼が教皇の居室に来たことの説明にはならない。ドメニコ・アルバネーゼはカメルレンゴ、すなわち、使徒座空位期間管理局の長官という地位にある。使徒座空位の正式宣言は彼がおこなうことになる。
「あの方はどこに?」ドナーティは尋ねた。
「神の王国におられる」アルバネーゼ枢機卿は答えた。
「で、ご遺体は?」
ドナーティはアルバネーゼのあとから短い廊下を歩き、教皇の寝室に入った。薄明かりのなかで、さらに三人の枢機卿が待っていた。マルセル・ゴベール、ホセ・マリア・ナバロ、アンジェロ・フランコーナ。ゴベールは国務省長官。つまり、世界最小の国家の実質的な首相と主席外交官を兼ねている。ナバロは教理省長官。カトリックの正統性を守護し、異端信仰を排除する役目だ。フランコーナは三人のなかでもっとも年長で、枢機卿団の首席枢機卿である。従って、次の教皇選挙のさいに進行役を務めることになる。
ドナーティに最初に声をかけたのは、スペイン貴族の出であるナバロだった。四半世紀近くローマで暮らし、聖職についているが、彼の話すイタリア語はいまもスペイン語の訛りが強い。「ルイジ、きみにとってどれほど辛いことかは、わたしにもよくわかる。われわれすべてが教皇さまの忠実なしもべであったが、いちばん愛されていたのはきみだった」
ゴベール枢機卿は猫のような顔立ちのほっそりしたパリジャンで、ナバロの月並みな慰めの言葉に深くうなずいた。寝室の隅の暗がりに立っていた三人の平信徒も同様だった。教皇の侍医を務めるオクタヴィオ・ガッロ、市国警察長官のロレンツォ・ヴィターレ、スイス衛兵隊司令官のアロイス・メッツラー大佐。到着したのはドナーティが最後だったようだ。逝去した教皇の枕辺に教会の高位聖職者たちを呼び集めるのは、本来ならカメルレンゴではなく、個人秘書ドナーティの役目だったはずだ。ドナーティは不意に、罪悪感に打ちのめされた。
しかし、ベッドに横たわった人の姿を見下ろしたとき、罪悪感は圧倒的な悲嘆に変わった。ルッケージはいまも白い法衣のままだった。ただ、スリッパは脱がされているし、帽子はどこにも見当たらない。誰かがルッケージの両手を胸の上で組ませていた。その手にロザリオが握られている。目は閉じ、顎はゆるんでいるが、表情に苦悶の跡はなかった。苦しんだ様子はまったくない。それどころか、急に目をあけた教皇に〝今夜は楽しかったかね?〟と尋ねられたとしても、ドナーティは驚かなかっただろう。
いまも白い法衣のまま……。
ルッケージが教皇となったその日から、スケジュール管理はドナーティが担当してきた。夜のスケジュールが変更されることはめったになかった。七時から八時半まで夕食。八時半から十時まで書斎で書類仕事、そのあと、教皇専用のチャペルで十五分の祈りと瞑想。たいてい十時半にはベッドに入る。英国の探偵小説をお供にするのが常で、これがルッケージの罪深き喜びだった。ベッド脇のテーブルを見ると、P・D・ジェイムズの『策謀と欲望』が置いてあり、読書用眼鏡が上にのっていた。ドナーティはしおりがはさまれたページを開いた。
〝四十五分後、リカーズ主任警部はふたたび殺人現場を訪れた……〟
ドナーティは本を閉じた。教皇の逝去から二時間近くたっている。いや、もっとだろう。冷静に尋ねた。「誰が見つけたのですか? 身のまわりのお世話をする修道女でなかったのならいいのですが」
「わたしだ」アルバネーゼ枢機卿が言った。
「教皇さまはどこにおられたのでしょう?」
「チャペルから旅立たれた。わたしが見つけたのは十時を数分まわったころだった。正確な死亡時刻となると……」アルバネーゼはがっしりした肩をすくめた。「わたしにはわかりかねる」
「なぜすぐに連絡してくれなかったのです?」
「きみを見つけようとしてあらゆる場所を捜した」
「携帯に電話してくれればよかったのに」
「したとも。何回も。だが、応答がなかった」
アルバネーゼは嘘をついている─ドナーティは思った。「ところで、あなたはチャペルへ何をしにいらしたのです?」
「取調べのような雰囲気になってきたな」アルバネーゼの視線がナバロ枢機卿のほうへちらっと移り、ふたたびドナーティに戻った。「一緒に祈ってほしいと教皇さまに頼まれて、そのお誘いに応じたのだ」
「教皇さまからじきじきに電話があったのですか?」
「わたしの居室に」アルバネーゼはうなずきながら言った。
「何時ごろでした?」
アルバネーゼは記憶から抜けてしまった詳細を思いだそうとするかのように、目を天井へ向けた。「九時十五分。いや、九時二十分ごろだった。十時過ぎにチャペルに来るようにと言われた。行ってみると……」
ドナーティはベッドに横たわった命なき人を見下ろした。「で、教皇さまはどうやってここに?」
「わたしがお運びした」
「一人で?」
「教皇さまは教会の重みをその肩で支えてこられた」アルバネーゼは言った。「だが、死を迎えると同時に羽根のように軽くなってしまわれた。きみに連絡がとれなかったため、国務省長官を呼びだし、長官がナバロ枢機卿とフランコーナ枢機卿に電話してくれた。次にドットーレ・ガッロに電話し、診断をお願いした。重い心臓発作が命とりになったそうだ。たしか二度目ではなかったかね? それとも三度目だったか?」
ドナーティは教皇の侍医に目を向けた。「診断なさったのは何時ごろでしたか、ドットーレ・ガッロ?」
「十一時十分でした」
アルバネーゼ枢機卿が軽く払いをした。「わたしの正式な報告書では少しばかり時間を修正した。ルイジ、お望みなら、教皇さまを見つけたのはきみだということにしてもいいが」
「必要ありません」
ドナーティはベッドの横に膝を突いた。生前の教皇は小さな妖精のようだった。亡くなったいまは、さらに小さくなったように見える。コンクラーベで番狂わせが起きて、当時ヴェネツィアの大司教だったルッケージが二百六十五代目の教皇に選ばれた日のことを、ドナーティは思いだした。〈嘆きの部屋〉に用意されていた仕立て済みのカソック三着のなかから、ルッケージは最小サイズを選んだ。それでもなお、父親のシャツを着た小柄な少年のように見えた。サン・ピエトロ大聖堂のバルコニーに出たときには、頭が手すりからほとんど出ていなかった。ヴァチカン担当の記者たちはルッケージに〝あっと驚きのピエトロ〟というあだ名をつけた。教会の強硬派の連中は嘲りをこめて〝アクシデント教皇〟と呼んだ。
しばらくすると、ドナーティは肩に誰かの手がかかるのを感じた。鉛のような感触だった。アルバネーゼの手に違いない。
「指輪を、大司教」
かつては、亡くなった教皇の〝漁師の指輪〟を枢機卿団が見守る前で破壊するのがカメルレンゴの役目だった。しかし、教皇の額を銀のハンマーで三回叩いて死亡を確認する儀式と同じく、指輪の破壊ももうおこなわれていない。ルッケージがほとんどはめたことのなかった指輪に、十字架を表す二本の線が深く刻まれるだけだ。しかしながら、それ以外の伝統は厳重に守られる。たとえば、教皇居室のドアはただちに施錠されて立入禁止になる。ルッケージの唯一の個人秘書だったドナーティですら、遺体が運びだされたあとはもう出入りできなくなる。
ドナーティは膝を突いたまま、ベッド脇のテーブルの引出しをあけて、ずっしりした黄金の指輪をとりだした。アルバネーゼ枢機卿に渡すと、枢機卿はそれをベルベットの小袋に入れた。厳粛な声で宣言した。「使徒座空位」
いまのところ、聖ペテロの聖座には誰もついていない。使徒憲章に従えば、空位期間中はアルバネーゼ枢機卿がローマ・カトリック教会の教皇代行者となり、新教皇が選出された時点で空位期間は終わりを告げる。名目だけの大司教に過ぎないドナーティには、この件に口出しする権利はない。それどころか、教皇が亡くなったいまでは地位も権力も失い、カメルレンゴの指示に従わざるをえない。
「公式発表はいつの予定でしょう?」ドナーティは尋ねた。
「きみが到着するまで待っていたのだ」
「草稿を拝見していいですか?」
「時間が何より大切だ。これ以上遅らせたら……」
「わかりました」ドナーティはルッケージの手に自分の手を重ねた。教皇の手はすでに冷たくなっていた。「教皇さまとしばらく二人だけにしていただきたい」
「しばらくだぞ」アルバネーゼが言った。
人々が徐々に寝室からいなくなった。最後にアルバネーゼ枢機卿が出ていこうとした。
「伺いたいことがあります、ドメニコ」
アルバネーゼはドアのところで足を止めた。「なんだね?」
「書斎のカーテンを閉めたのは誰です?」
「カーテン?」
「九時にわたしが書斎を出たときは、カーテンはあいていました。鎧戸も」
「わたしが閉めた。あんな遅い時間に明かりがついているのを、広場にいる者たちに見られてはまずいと思って」
「なるほど、そうでしたか。賢明な判断です、ドメニコ」
アルバネーゼはドアを閉めもせずに出ていった。教皇と二人だけになったドナーティは涙をこらえようとした。悲しむための時間はあとでとれる。ルッケージの耳元に顔を寄せ、冷たくなった手をそっと握った。「話してください、古き友よ」ささやきかけた。「今夜、本当は何があったのか、教えてください」
2
エルサレム─ヴェネツィア
夫にはぜひとも休暇が必要だとひそかに首相に訴えたのはキアラだった。夫はキング・サウル通りの長官室にしぶしぶ腰を落ち着けて以来、わずか半日の休暇をとったことすらない。パリで爆弾テロに巻きこまれて腰椎骨二カ所にひびが入ったあと、何日か療養に専念しただけだ。だが、休暇をとるといっても簡単にできることではない。安全な通信回線と厳重な警備が必要だ。キアラと双子もそうだ。アイリーンとラファエルはもうじき四歳の誕生日を迎える。アロン一家はつねに大きな危険にさらされているため、家族そろってイスラエル国外へ出たことは一度もない。
でも、行き先はどこがいいだろう? 遠い異国へ旅をするのは無理だ。いつなんどき国家の緊急事態が起きるかわからないから、数時間でキング・サウル通りに戻れるよう、イスラエルからそう遠くないところでなくてはならない。一家で南アフリカへサファリ旅行に出かけるのは当分無理だし、オーストラリアやガラパゴス諸島への旅行もできない。まあ、そのほうがいいだろう。ガブリエルは野生動物とどうも気が合わない。それに、キアラがいちばん避けたいのは長時間のフライトで夫を疲労困憊させることだ。〈オフィス〉長官に就任して以来、ラングレーにいるアメリカの情報機関の連中と協議をおこなうために、ガブリエルは頻繁にワシントンへ出かけている。いまの彼にもっとも必要なのは休養だ。
だが、その反面、ガブリエルは休養をすなおに楽しめるタイプではない。豊かな才能に恵まれた男だが、趣味はほとんどない。スキーもシュノーケルもだめ。ゴルフクラブやテニスラケットは、武器として使う以外に一度もふったことがない。海岸へ出かけても、寒い強風の日でないと退屈してしまう。セーリングを楽しむことはあるが、いちばんのお気に入りはイングランドの西の沖合にある波の荒い海域だ。また、リュックを背負って殺風景な荒野を歩きまわることもある。かつて〈オフィス〉の現場工作員だったキアラですら、彼の無謀なペースにつけていけるのは二キロか三キロぐらいだ。子供たちはいじけてしまうに決まっている。
こうなったら、ガブリエルが休暇先で何かできるよう、考えておくしかない。毎朝、子供たちが起きて着替えをすませ、一日を始める用意ができるまでのあいだ、ガブリエルが時間をつぶせるような小さな仕事を。彼がすでに馴染んでいる街でその仕事ができるとしたら? 絵画修復の技術を学び、見習いとして腕を磨いた街。彼とキアラが出会って恋に落ちた街。キアラはこの街の生まれで、父親は縮小しつつあるユダヤ人社会のために首席ラビとして尽力している。母親からは、子供たちを連れて遊びに来るようしつこく言われている。完璧だとキアラは思った。いわゆる一石二鳥というやつだ。
でも、いつにしよう? 八月は論外だ。気温も湿度も高すぎるし、パッケージツアー客の波の下に街が沈んでしまう。自撮りの好きな連中が、わめきたてるツアーガイドのうしろにくっついて一時間か二時間ほど街をまわり、そのあと〈カフェ・フローリアン〉でやたらと高いカプチーノを飲んで、それからクルーズ船に戻る。しかし、十一月ぐらいまで待てば、爽やかな涼しい季節になり、この街を一家がほぼ独占できる。〈オフィス〉にも、イスラエルでの日々の暮らしにも邪魔されることなく、自分たちの将来について考える機会になるだろう。長官の任期は一期だけにしてほしいとガブリエルから首相に伝えてある。その後の人生をどんなふうに送るか、どこで子供たちを育てるかを考えるのは、けっして早すぎはしない。二人ともこれ以上若くなることはないのだから。ガブリエルはとくに。
キアラはこの計画をガブリエルに内緒にしておいた。でないと、ガブリエルが長ったらしい演説を始めて、彼が一日でも職務から離れればイスラエル国が崩壊してしまう理由をあれこれ並べ立てるに決まっている。キアラはかわりに副長官のウージ・ナヴォトを味方にひきいれ、日程を選んだ。〈オフィス〉で安全な不動産の取得・管理を担当しているハウスキーピング課が滞在場所を手配してくれた。ガブリエルときわめて親しい関係にある地元警察と情報機関が警備を担当してくれることになった。
あとはガブリエルを忙しくさせておくために、何か仕事を見つければいい。十月下旬、キアラはフランチェスコ・ティエポロに電話をかけた。この街でもっとも評判の高い美術品修復会社のオーナーだ。
「ちょうどいい作品がある。メールで写真を送ろう」
三週間後、イスラエルの気むずかしい閣僚たちと侃々諤々の議論を終えてガブリエルが帰宅すると、アロン家の複数の旅行カバンに荷物が詰めてあった。
「きみ、出ていくのか?」
「いいえ」キアラは答えた。「休暇旅行に出かけるのよ。一家そろって」
「わたしは無理だ─」
「話はつけてあるから大丈夫、ダーリン」
「ウージは知ってるのか?」
キアラはうなずいた。「それから、首相もご存じよ」
「どこへ出かけるんだ? 期間は?」
キアラは質問に答えた。
「二週間ものあいだ、わたしは何をすればいい?」
キアラは夫に写真を渡した。
「二週間で仕上げられるわけがない」
「できるところまでやればいいでしょ」
「そして、あとはほかの誰かに任せろというのか?」
「世界の終わりってわけじゃないわ」
「わからないぞ、キアラ。終わりになるかもしれん」
そのアパートメントは、ヴェネツィア市街を構成する昔ながらの六つの区のうち、いちばん北のカンナレッジョ区にあり、崩壊しそうな古い大邸宅の主階を占めていた。大広間と、現代的な調理器具のそろった広いキッチンと、ミゼリコルディア小運河に面したテラスがついている。四つある寝室のうちひとつに、ハウスキーピング課によって、キング・サウル通りと連絡をとるための安全な回線が用意されていた。テントのような装置─〈オフィス〉では〝天蓋〟という隠語で呼んでいて、なかに入れば、盗聴の心配なしに電話でやりとりできる─までついている。外のフォンダメンタ・ディ・オルメジーニでは、私服姿の国家治安警察隊の人間が見張りに立っている。ガブリエルはそちらの許可をとったうえでベレッタの九ミリを携行している。キアラも同じで、射撃の腕前は彼女のほうがずっと上だ。
運河沿いの道をしばらく行くと、鉄製の橋─ヴェネツィア市内で唯一のもの─があり、向こう岸にゲットー・ヌオーヴォ広場と呼ばれる大きな広場が見える。博物館、書店、ユダヤ人コミュニティの運営に当たる複数のオフィスなどがある。広場の北端に建っているのは高齢者のための介護ホーム〈カーザ・イスラエリティカ・ディ・リポーゾ〉。そのとなりに、ヴェネツィアのユダヤ人たちを追悼する簡素な浅浮彫りの碑がある。一九四三年十二月、ユダヤ人がここに集められて強制収容所へ送られ、のちにアウシュヴィッツで殺されたのだ。重装備の警官二人が防備を強化したボックスから追悼碑を監視している。水中に沈みつつあるヴェネツィアの島々でいまも暮らしている二十五万人のうち、二十四時間態勢で警察の保護が必要なのはユダヤ人だけだ。
広場を囲むアパートメントはヴェネツィアでもっとも背の高い建物だ。中世のころ、ここの住人たちが市内のほかの場所で暮らすことを教会が禁じていたからだ。いくつかの建物の最上階には小さなシナゴーグがある。丹念に修復されたそれらのシナゴーグに、かつては下の階に住むアシュケナージ(ドイツ・ポーランド・ロシア系ユダヤ人 )やセファルディ(スペイン・ポルトガル系ユダヤ人)が通っていたのだ。広場の南側に、現在も礼拝をおこなっているシナゴーグが二カ所ある。どちらも目立たない建物で、外から見たかぎりでは、ユダヤ教の礼拝の場であることはまったくわからない。スペイン系のシナゴーグは一五八〇年にキアラの先祖が建てたもので、暖房はなく、過越祭から、大祭日─ロシュ・ハシャナ(新年祭)とヨム・キプル(贖罪日)─まで門戸を開放している。レヴァント系のシナゴーグは小さな広場の反対側にあり、冬のあいだ信者たちを迎え入れている。
ラビのヤコブ・ゾッリと妻のアレッシアはレヴァント系のシナゴーグの角を曲がった先に住んでいる。人目につかない中庭に面した小さな一軒家だ。アロン一家は月曜にヴェネツィアに到着し、数時間後、そちらで夕食をとった。ガブリエルが電話をチェックできたのはわずか四回だった。
「何か問題が起きたのでなければいいが」ラビ・ゾッリが言った。
「いつもどおりです」ガブリエルはぼそっと答えた。
「安心した」
「安心しないでください」
ラビは静かに笑った。テーブルの周囲を満足げに見まわして、二人の孫にしばし視線を向け、次に妻を、最後に娘を見つめた。ろうそくの光がキアラの目に映っていた。その目はカラメル色で金色の斑点が散っている。
「キアラがこんなに輝いて見えるのは初めてだ。きみのおかげでとても幸せに暮らしていると見える」
「本当ですか?」
「もちろん、ここに来るまでにはいろいろあっただろう」ラビは諭すように言った。「だが、いいかね、キアラは自分のことを世界でいちばん幸せな人間だと思っておる」
「いや、幸せなのはわたしのほうです」
「噂によると、キアラはきみに隠れて休暇の計画を立てたそうだな」
ガブリエルはしかめっ面になった。「ユダヤ教の律法のなかに、それを禁じる法があるはずです」
「わたしにはひとつも思いつけん」
「たぶん、それでよかったのでしょう」ガブリエルは認めた。「知らされていたら、わたしが休暇に同意したかどうか疑問ですから」
「ようやく孫たちをヴェネツィアに連れてきてくれて、こんな嬉しいことはない。だが、むずかしい時代になったものだ」ラビ・ゾッリは声をひそめた。「サヴィアーノと極右の友人たちがヨーロッパの暗黒の勢力を目ざめさせてしまった」
ジュゼッペ・サヴィアーノはイタリアの新たな首相だ。外国人嫌い、偏狭、出版の自由に懐疑的、議会民主主義や法の支配といった優雅なものには我慢がならない。親しい友人のイェルク・カウフマンも同類だ。カウフマンは頭角を現しはじめたネオファシストで、現在オーストリアの首相の座にある。フランスに目を転じると、国民連合の党首セシル・ルクレールがエリゼ宮の次の主になるだろうというもっぱらの噂だ。ドイツでは、元ネオナチのメンバーでスキンヘッドのアクセル・ブリュナー率いる国民民主党が一月の総選挙で第二党に躍進すると予想されている。どちらを向いても、極右勢力が優勢のようだ。
西ヨーロッパにおける極右勢力の台頭は、グローバリゼーション、経済不安、どんどん変化する大陸の人口動態によってさらに加速している。ムスリムは現在、ヨーロッパの人口の五パーセントを占めている。生粋のヨーロッパ人のあいだで、イスラム教は自分たちの宗教と文化のアイデンティティーを脅かす存在だと言う者が増えてきている。彼らの怒りと恨みは、これまでは抑えこまれ、世間の目から隠されてきたが、いまではインターネットという血管のなかをウイルスのごとく駆けめぐっている。ムスリムへの迫害が大幅に増えている。ユダヤ人を狙った暴行や破壊行為も同様だ。じっさい、ヨーロッパの反ユダヤ主義は第二次世界大戦以来絶えてなかったレベルに達している。
「先週またしてもリド島の墓地が荒らされた」ラビ・ゾッリは言った。「倒された墓石、鉤十字……いつものことだ。うちの信者たちは怯えている。みんなを元気づけようとするのだが、このわたしまで怯えている。移民を敵視するサヴィアーノのような政治家どもが、壜を揺すってコルク栓を吹き飛ばしてしまったのだ。やつの支持者たちは中東とアフリカからの難民に難癖をつけているが、連中がもっとも蔑んでいるのはわれわれだ。最古の歴史を持つ憎悪だな。このイタリアでは、反ユダヤ主義者であっても、眉をひそめられることはもうない。ユダヤ人への軽蔑をおおっぴらに示せるようになった。どんな結果が待っているかは火を見るより明らかだ」
「嵐はいずれ過ぎますよ」ガブリエルは言ったが、説得力はほとんどなかった。
「きみの祖父母もたぶん同じことを言っただろう。ヴェネツィアのユダヤ人たちもそう言った。きみのお母さんは生きてアウシュヴィッツを出ることができた。ヴェネツィアのユダヤ人たちはそこまで幸運ではなかった」ラビ・ゾッリは首をふった。「わたしは前にも同じ状況を目にしてきた。どんな終わりを迎えるかを知っている。どうか忘れないでくれ─想像もつかないことが起こりうるのだ。だが、暗い話でせっかくの夜を台無しにするのはやめよう。孫たちと楽しく過ごしたい」
翌朝、ガブリエルは早起きをして、フッパーというシェルターのなかでキング・サウル通りの上級スタッフと二、三時間話をした。それがすむとモーターボートを雇い、キアラと子供たちを連れてヴェネツィア市内とラグーナに浮かぶ島々の観光に出かけた。寒すぎてリド島で泳ぐことはできなかったが、子供たちはビーチで靴を脱いでカモメやアジサシを追いかけた。カンナレッジョ区に戻る途中、ヴェロネーゼの《聖人に囲まれた栄光の聖母子》を見るためにドルソドゥーロ区のサン・セバスティアーノ教会に寄った。キアラの妊娠中にガブリエルがこの絵の修復を手がけたのだ。やがて、ゲットー・ヌオーヴォ広場の秋の光が薄れはじめるころ、子供たちはにぎやかな鬼ごっこの仲間入りをし、ガブリエルとキアラは〈カーザ・イスラエリティカ・ディ・リポーゾ〉の外に置かれた木製ベンチにすわってそれを見守った。
「これ、わたしが世界でいちばん好きなベンチかもしれない」キアラが言った。「あなたが意識をとりもどして、家に連れて帰ってほしいとわたしに頼んだ日に、あなたがすわっていたベンチよ。覚えてる、ガブリエル? ヴァチカンが攻撃を受けたあとのことだった」
「どっちがひどかったのか、わたしにはわからない。ロケット推進式の手榴弾と自爆テロ犯か、それとも、きみの看護か」
「自業自得でしょ、お馬鹿さん。もう一度会うことに同意しなければよかった」
「おかげで、いま、われわれの子供が広場で遊んでいる」ガブリエルは言った。
キアラはカラビニエリが詰めているボックスにちらっと目をやった。「銃を持った男たちに見守られながらね」
翌日の水曜日、ガブリエルは午前中の電話を終えるとアパートメントを抜けだし、ニスを塗った木箱を小脇に抱えて徒歩でマドンナ・デッロールト教会へ向かった。身廊は薄暗く、足場が組んであって、側廊にある二重壁の尖塔アーチを隠していた。この教会には袖廊がないが、奥に五角形の後陣があり、そこにヤコポ・ロブスティの墓がある。ティントレットという名前のほうがよく知られている。ガブリエルがフランチェスコ・ティエポロを見つけたのはそこだった。ティエポロは熊のごとき大男で、白髪交じりのもじゃもじゃの黒い顎髯を生やしている。いつもどおり、流れるようなラインの白いチュニック姿で、首に巻いたスカーフを粋な感じに結んでいる。
ティエポロはガブリエルを強く抱きしめた。「いずれあんたがこっちに戻ってくることは、ずっとわかってたんだ」
「休暇で来ただけだよ、フランチェスコ。まあ、そう興奮しないで」
ティエポロはサン・マルコ広場の鳩の群れを追い払おうとするかのように、片手をふった。「今日は休暇だとしても、あんたはいつの日かヴェネツィアで死を迎える」そう言って、ティントレットの墓を見下ろした。「あんたを埋葬するときは、教会以外の場所にしないとだめだよな」
ティントレットは一五五二年から一五六九年にかけて、この教会のために十点の作品を描いた。そのひとつが《聖母の神殿奉献》で、身廊の右側にかかっている。四八〇×四二九センチの巨大なカンバスに描かれていて、ティントレットの傑作とされている。修復の第一段階のニス落としは完了していた。あとは絵具を塗り直すだけだ。歳月とひずみによって絵具が剥落した部分に手を入れていく。気の遠くなりそうな作業だ。ガブリエルが見た感じでは、修復師がたった一人で作業を進めたら、最長で一年ほどかかるだろう。
「ニス落としを担当した気の毒なやつは誰だい? アントニオ・ポリーティだったら嬉しいんだが」
「新人のパウリーナだ。あんたの作業を見学したいと言っていた」
「無理だと言ってくれただろうな」
「きっぱり言っといた。パウリーナからの伝言だが、どこでも好きな箇所を修復してかまわないってさ。ただし、聖母を除いて」
ガブリエルはそびえ立つカンバスの上のほうへ目を向けた。ナザレからやってきたヨアキムとアンナというユダヤ人夫婦の娘で三歳になるマリアが、エルサレム神殿の十五段の階段を祭司長のほうへためらいがちにのぼっていく。階段の下のほうに茶色い絹のローブをまとった女性がいて、階段にもたれかかっている。幼子を抱いているが、男の子か女の子かは判然としない。
「この女性にしよう」ガブリエルは言った。「それから、子供も」
「いいのか? かなり手間がかかるぞ」
ガブリエルはカンバスに目を向けて悲しげに微笑した。「この二人のために、せめてそれぐらいはしないと」
ガブリエルは教会で二時まで作業を続けた。予定より長くなってしまった。その夜は子供たちを祖父母に預け、キアラと二人で大運河の対岸のサン・ポーロ区にあるレストランで食事をした。翌日の木曜日は、午前中は子供たちを連れてゴンドラに乗り、午後は五時までティントレットの修復に没頭した。五時になるとティエポロが教会の扉に錠をおろしてしまうのだ。
キアラはアパートメントで夕食をこしらえることにした。食後はガブリエルが〝バスタイム〟と呼ばれる夜ごとのバトルを監視し、それからフッパーというシェルターにこもって祖国の小さな危機に対処した。ベッドにもぐりこんだときは午前一時近くになっていた。キアラは音を消したテレビには目もくれずに小説を読んでいた。テレビ画面に映っていたのはサン・ピエトロ大聖堂からの生中継だった。ガブリエルは音量を上げ、旧友が亡くなったことを知った。
3
カンナレッジョ区、ヴェネツィア
教皇パウロ七世の遺体は午前中の遅い時間に、教皇宮殿の三階にある広間、サーラ・クレメンティーナへ移された。翌日の昼過ぎまでそこに安置されたあと、厳かな行列と共にサン・ピエトロ大聖堂へ運ばれ、二日にわたって一般弔問を受けた。逝去した教皇を囲むようにして、鉾槍を構えた四人のスイス衛兵が警護に当たった。ヴァチカンの記者団は、教皇にもっとも近い補佐役で腹心の友でもあったルイジ・ドナーティ大司教が遺体のそばをほとんど離れなかったという事実を、新聞で大きくとりあげた。
教会の伝統が定めるところによると、教皇の葬儀は逝去後四日から六日以内にとりおこなわなくてはならない。カメルレンゴのドメニコ・アルバネーゼ枢機卿から、葬儀は翌週の火曜日、その十日後にコンクラーベを招集するとの発表があった。ヴァチカン担当の記者たちは、改革派と保守派の烈な争いになることを予想した。本命はホセ・マリア・ナバロ枢機卿で、教理省長官という地位を活かして、亡くなった教皇をも脅かすほどの勢力基盤を枢機卿団の内部に作りあげている。
ピエトロ・ルッケージがかつて大司教を務めていたヴェネツィアでは、市長が三日にわたって喪に服すことを宣言した。街じゅうの鐘が沈黙し、サン・マルコ寺院でほどほどの人数が出席して礼拝式がとりおこなわれた。それを別にすれば、ふだんどおりの日常が続いていた。高潮でサンタ・クローチェ区の一部に浸水被害。巨大なクルーズ船がジューデッカ運河の桟橋に衝突。あちこちのバーに地元民が集まり、秋の冷気を撃退するためにコーヒーやブランディを飲んでいたが、亡くなった教皇の名前が出ることはほとんどなかった。元来冷笑的なヴェネツィア人なので、几帳面にミサに出る者はほとんどいないし、ヴァチカンの聖職者たちの教えに従って暮らす者はさらに少ない。ヴェネツィアにある数多くの教会はキリスト教世界で最高の美を誇っているが、いずこも観光客がルネサンス美術に見とれる場所でしかない。
しかしながら、ガブリエルは並々ならぬ関心を抱いてローマの出来事を追っていた。教皇の葬儀当日の午前中は早めに教会へ行って修復作業に没頭した。もうじき十二時十五分というころ、誰かの足音が身廊に虚ろに響いた。ガブリエルは拡大鏡つきのバイザーを押しあげ、作業台の周囲にめぐらした防水シートを用心深く左右に分けた。カラビニエリの美術遺産保護部隊、通称〝美術班〟を指揮するチェーザレ・フェラーリ将軍が無表情にガブリエルを見つめかえした。
将軍は勝手に防水シートの奥に入ってきて、ハロゲンランプ二台の無慈悲な白いライトを浴びた巨大なカンバスを見つめた。「ティントレットのなかでは出来のいいほうだと思うが、きみの意見はどうだね?」
「ティントレットは自分の実力を証明しようとして、大きなプレッシャーの下敷きになっていた。世間ではすでに、ヴェロネーゼがティツィアーノの後継者として、ヴェネツィア最高の画家として認められていた。哀れなティントレットのもとに以前のように注文が舞いこむことはなくなっていた」
「ここはティントレットが通った教会だった」
「まさか」
「フォンダメンタ・ディ・モーリの角を曲がったところに家があったんだ」将軍は防水シートを脇にどけて身廊に入った。「この教会にはかつてベッリーニの絵がかかっていた。《聖母子》が。一九九三年に盗難にあった。以来、美術班はそれを捜しつづけている」肩越しにガブリエルをちらっと見た。「きみ、目にしてないかね?」
ガブリエルは微笑した。〈オフィス〉長官に就任するしばらく前に、世界でもっとも捜索に熱が入っていた盗難絵画をガブリエルがとりもどしたことがあった。その絵はカラヴァッジョの《聖フランシスと聖ラウレンティウスのキリストの降誕》。ガブリエルの配慮で手柄はすべて美術班のものになった。ガブリエルと家族がヴェネツィアで休暇を過ごすあいだ、二十四時間態勢の警備をつけることをフェラーリ将軍が承知した裏には、主としてこういう事情があったのだ。
「きみはのんびりと休暇を楽しむことになってるはずだ」将軍は言った。
ガブリエルは拡大鏡つきのバイザーを下ろした。「楽しんでるさ」
「何か問題は?」
「理由がわからないんだが、女性の衣装の色を再現するのに少々手こずっている」
「きみの身辺警護について尋ねたんだ」
「わたしがヴェネツィアに戻ったことは誰にも気づかれずにすんだようだ」
「そうでもないぞ」将軍は腕時計にちらっと目をやった。「ランチ休憩をとるよう勧めても、たぶんだめだろうな」
「仕事中はランチをとらないことにしている」
「知ってるとも」将軍はハロゲンランプのスイッチを切った。「覚えている」
ガブリエルはティエポロから教会の鍵を預かっていた。美術班のチーフに見守られながらアラーム装置をセットし、ドアに錠をおろした。ティントレットが住んでいた家の何軒か先にあるバーまで二人で歩いた。カウンターの奥のテレビが教皇の葬儀を中継していた。
「きみが疑問に思っているかもしれないから言っておくと」将軍が言った。「ドナーティ大司教はきみが葬儀に参列するのを望んでいた」
「だったら、なぜ招いてくれなかったんだ?」
「カメルレンゴが耳を貸そうとしなかった」
「アルバネーゼのことか?」
将軍はうなずいた。「きみがドナーティと親しくしているのが、アルバネーゼは前々から気に入らなかったようだ。ついでに、教皇と親しくしていたのも」
「わたしが参列しないほうが、たぶん正解だな。邪魔になるだけだろう」
将軍は渋い顔になった。「きみを貴賓席にすわらせるのが筋というものなのに。なにしろ、きみがいなかったら、ヴァチカンがテロ攻撃を受けたときに教皇は死んでいたはずだ」
黒いTシャツを着た二十代ぐらいの痩せこけたバーテンダーが、二人分のコーヒーを運んできた。将軍は自分のコーヒーに砂糖を入れた。カップをかきまわす手は指が二本欠けている。カモッラという犯罪結社が勢力をふるうナポリ管区の指揮をとっていたころ、手紙爆弾で指を吹き飛ばされたのだ。右目も失った。義眼を入れているが、瞳が静止したままなので、冷酷かつ無情な視線になってしまう。さすがのガブリエルもこれだけはつい避けたくなる。すべてを見通す神の目を覗きこむようなものだ。
その目はいま、テレビのほうを向いていた。カメラがゆっくりパンして、政治家、元首、世界のさまざまなセレブといった悪党どもの集団を映しだしていく。やがて、ジュゼッペ・サヴィアーノのところでカメラが止まった。
「やはり喪章もつけずに来ている」将軍はつぶやいた。
「おたく、やつの崇拝者じゃないのか?」
「サヴィアーノは美術班に気前よく予算をまわしてくれる。おかげで、われわれの関係はきわめて良好だ」
「ファシストは文化遺産が大好きだからな」
「本人はファシストじゃなくて、ポピュリストのつもりだ」
「安心した」
フェラーリの一瞬の笑みは、義眼にはなんの影響も及ぼさなかった。「サヴィアーノのような男の登場は避けがたいことだったのだ。この国の連中は、自由民主主義、欧州連合、西側諸国の同盟といった夢想的な観念を信じる心を失ってしまった。無理もない。グローバリゼーションとオートメーションのせいで、イタリアの若者の大部分はまともな職業に就くこともできない。給料のいい仕事がしたければ、英国へ行くしかない。この国に残っていたら……」将軍はカウンターの奥の若者にちらっと目を向けた。「観光客にコーヒーを運ぶことになる」声を低くした。「あるいは、イスラエルの諜報機関の工作員に」
「サヴィアーノにはそれを変える気はない」
「たぶんな。だが、首相の座にあって、力と自信をひけらかしている」
「有能さは?」
「移民の排斥を続けるかぎり、まともな文章が書けなくたって、サヴィアーノの支持者たちは気にしない」
「もし危機に直面したら? 本物の危機だぞ。右派のウェブサイトででっちあげるようなやつじゃなくて」
「例えば?」
「銀行制度が崩壊するような財政危機とか」ガブリエルは言葉を切った。「もしくは、それよりはるかに悲惨なこととか」
「わたしが一生かかって貯めた金が煙となって消えるよりも悲惨なことがどこにある?」
「疫病の世界的流行はどうだ? 新種のインフルエンザが広まり、人類はそれに対して免疫がないとか」
「疫病?」
「笑ってる場合じゃないぞ、チェーザレ。それが現実になるのは時間の問題だ」
「で、きみが言うその疫病とはどこから来るんだ?」
「衛生状態に問題のある場所で動物から人間に感染するだろう。例えば、中国の生鮮市場とか。始まりはゆっくりだ。ある地域でクラスターが発生する。だが、いまは世界じゅうが密接につながっているから、全世界に野火のごとく広がっていくだろう。疫病発生の初期段階で中国人観光客がウイルスを西ヨーロッパに持ちこむ。ウイルスが特定されるよりも前に。数週間もしないうちに、イタリアの人口の半分が、いや、たぶんもっと多くが感染するだろう。次はどうなる、チェーザレ?」
「聞かせてくれ」
「感染の広がりを抑えこむために全土を封鎖しなくてはならない。医療体制が逼迫して、もっとも若く健康な者以外はすべて見捨てざるをえなくなる。毎日数百人が死亡するだろう。いや、数千人かもしれない。感染の広がりを抑えようとして、軍隊が大規模な火葬を担当しなくてはならなくなる。それはまるで─」
「ホロコーストだ」
ガブリエルはゆっくりとうなずいた。「そういう状況になったとき、読み書きもろくにできないサヴィアーノのような無能な政治家はどんなふうに対処すると思う? 医療の専門家の意見に耳を貸すのか、それとも、自分の知識のほうが上だと考えるのか? 国民に真実を告げるのか、それとも、ワクチンと治療薬がもうじき完成すると請け合うのか?」
「中国人と移民に責任をかぶせて、自分はさらに強大な存在になるだろう」フェラーリは真剣な顔でガブリエルを見た。「知っているのにわたしに話すのを省いたことが、まだ何かあるんじゃないかね?」
「一九一八年のスペイン風邪に匹敵する流行がそろそろ起きても不思議でないことは、少しでも脳みそのある者ならわかっている。わたしもわが国の首相に、イスラエルに対する脅威のなかでとりわけ懸念されるのはパンデミックだ、と進言してきた」
「わたしの任務が盗難絵画を見つけることだけで、つくづくありがたいと思う」将軍はテレビ画面に映しだされる緋色の衣の海を見つめた。「あのなかに次の教皇がいるわけだ」
「ナバロ枢機卿が本命と言われている」
「噂に過ぎん」
「内部情報でもつかんでるのか?」
フェラーリ将軍は部屋を埋めた記者連中に話をするような調子で答えた。「次期ローマ教皇の選出に関して、カラビニエリが目を光らせるつもりはいっさいない。イタリアのほかの保安機関も情報機関も同様だ」
「冗談はやめてくれ」
将軍は低く笑った。「では、きみのほうはどうなんだ?」
「次期教皇が誰になろうと、イスラエル国にはなんの関係もないことだ」
「ところが、あるんだな」
「どういう意味だ?」
「説明はあの男にしてもらえ」フェラーリ将軍はテレビのほうを見てうなずいた。教皇パウロ七世の個人秘書を務めていたルイジ・ドナーティ大司教が画面に映しだされたところだった。「話をする時間をきみに少しだけとってもらえないかと言っていた」
「わたしに直接電話してくれればよかったのに」
「電話で話せるようなことではないそうだ」
「どんな話か、聞いてるのか?」
将軍は首を横にふった。「きわめて重大な件だということしか聞いていない。明日のランチをつきあってもらえないかと、大司教が言っている」
「場所は?」
「ローマ」
続きは本書でお楽しみください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
