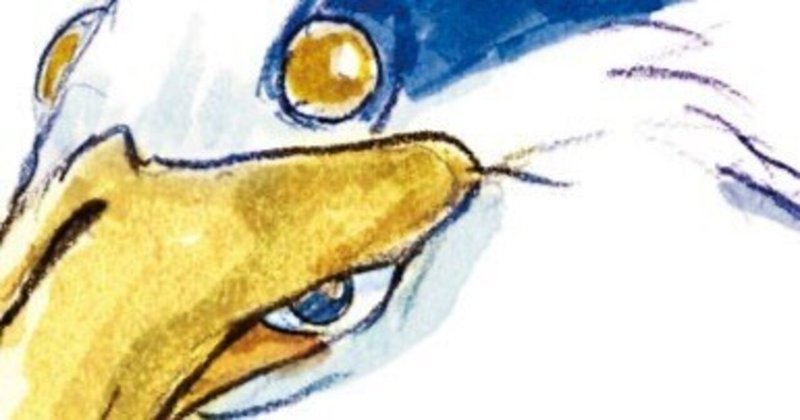
宮﨑駿『君たちはどう生きるか』の心理士的考察(感想)※ネタバレ
私にとって、ジブリの中で一番良かった作品かもしれない。登場人物の人柄や関係性についての精巧な描写・表現に、改めて感銘を受けるとともに、精神分析やユング心理学をはじめ心理学的な構成要素が観て取れて、とても味わい深かった。個人的に、心に深く響くものがあり、スクリーンの中の世界に没入し、終わった後も、涙が込み上げてくるほどだった。そういった私の個人的な思い入れが、noteを書かせるに至り、思いや考えをしたためたものとなっている。解釈であり、自身の投影を含めた感想の要素もあるところを、ご了承いただきたい。
作品の背景
ジブリは少女の主人公が多い。個性的で愛らしい少女のキャラクターは広告塔としての役割を果たす商業的な理由もあると思われるが、主人公を少女のキャラクターにするのは、精神的変化を描きやすくするためというのも大きな理由なのではないかと思う。一般的に、主人公が少年の作品は、何かに打ち勝ち成功を掴む物語になりがちだが、ジブリは少女を主人公に置くことで、繊細な感情表現を用いながら精神的成長を描き出しているように思う。
また、主人公を取り囲む人物と配置が巧妙で、頼れそうな大人でもどこかに陰の側面があり、そういった大人と真摯な姿勢で向き合う姿や、脅威となる人物を敵として憎まず受容し、共生していく姿やが描かれる。多義的な曖昧さの中で、真剣に人の多面性を取り入れて、自分を作り直してて大人になっていくプロセスが描かれていると感じる。
これまでのジブリ作品では少女を主人公として精神的成長を描いたものが多かったが、宮崎駿の引退作とされていた『風立ちぬ』の主人公が男性であるように、今回の主人公も少年である。この2作の主人公は、宮崎駿の片われなのではないかと思う。自分自身の人生や生き方をキャラクターに預けて表現し、達観し、自身の集大成としようとしたのではないだろうか。そうすると、『風立ちぬ』から10年経った今、少年の頃に戻して作品を作り、プロモーションも僅かに作品を公開したのには、そうする必要性があったのだろうと思わせられ、宮崎駿の自己表現と創作の渇望があったのかもしれないと想像を寄せる。本作は『風立ちぬ』よりもファンタジックで象徴的な表現がふんだんに用いられており、宮崎駿が、少年時代の思いを作品に昇華させ、私たちに「君たちはどう生きるのか」と投げかける作風になっているのではないかと察することもできる。
設定とテーマ
宮崎駿の子ども時代を預けられた主人公”直人”は、背格好や教室の風景などから小学生で、同級生の子どもたちのガキンチョ感や最終学年ではなさそうなことをふまえて、10〜11歳ほどだと予想する。”直人”は、幼児ではないが青年ではない、微妙な年頃の少年と考えられる。そんな年頃の”直人”が、戦時中に起きた火事で母親を失う。喪失から始まる物語である。さらに、それからたった数年で、父親は母親の妹と結婚するに至り、東京から疎開する。そこで出会う、父親の結婚相手”なつこ”との関係形成が、現実世界のシビアさとコントラストを効かせながらファンタジックに描かれていく。
家族構成も重要な要素である。父親は戦闘機の部品工場の社長、母親を由緒正しい家系の出身にすることで、戦争によるひもじい思いをする様子は描かれず、戦争の悲惨さが、作中で最も伝えたいわけではないことがわかる。そのうえで、戦中・戦後という時代が設定が、父親が母親の妹と再婚するという酷で複雑な状況を、時代的に起こり得ることとして、複雑で過酷な状況から始まる少年の精神的成長を描きやすくしている。
本作では、戦争の悲惨さではなく、少年があまりにも酷な状況の中で、母子の絆を築いていく精神世界が、深く細かく鮮明に描き出されている。
二つの母子関係
死別した母親を恋しく思う気持ちを残しながら、凛々しく振る舞う”直人”の苦しみと、母親と姿形がそっくりな得体の知れない新しい母親に警戒心を向ける様子が冒頭で描写される。そんな苦境で、”青鷺”がパラレルワールドに誘惑する。”直人”は戸惑いながら抵抗するが、実母が大人になった”直人”に向けて残した書籍『君たちはどう生きるか』を半ばまで読み、涙したことを境に、現実逃避ではなく、”なつこ”を救い現実を生きるため、主体的にパラレルワールドに歩みを進める。パラレルワールドには、火を操る自分と同じ年頃の実母”ひみ”の姿があり、助け合いを通して、母親を愛し、愛されていたことを確かめる。危険を犯して”なつこ”に会いに行き、実母との喪失体験と重ねながら甘えたい思いを叫び、本音をぶつけ合うプロセスを通じ、実母の喪の作業を経て、新たな母親とわかり合い関係を築いていく。二人の母親がオーバーラップしながら、悲しみを抱えつつ正直になって、新たな母子関係を築く様子が強く描かれる。
”なつこ”と女性性について
”なつこ”の初めての登場シーンは、”なつこ”の実家に身を寄せるべく疎開した父親と”直人”との待ち合わせに、”なつこ”が遅れてやってきたシーンである。着物姿で髪を結い、口紅を指す”なつこ”は大変美しい。”直人”は目を伏せたまま、礼儀正しく挨拶するのみだった。その後、父親は仕事に向かい、”直人”は”なつこ”と家に向かうなか、”なつこ”は唐突に「手を出して」と言って躊躇う”直人”の手をとり、自分のお腹に触れさせる。そして、「今度直人さんの弟を産むんですよ。私、それがとても嬉しいの」と顔を輝かせる。その”なつこ”の様子とは対照的に、”直人”は家に到着するまで俯いたまま、表情が見えない。”直人”にとっては衝撃的な出来事だったに違いない。”直人”が父親から新しい母親の妊娠を聞かされていない様子だったこと、父親が持参した砂糖や缶詰やタバコが詰まった大きなトランクを”なつこ”が持った際に、父親が「重いぜ」と笑って止めなかったことから、その時点でまだ”直人”の父親は懐妊を知らなかったのではないかと考えられる。夫となる人に言うよりも早く、初対面の”直人”に、父親の子を孕っていることを伝えた可能性があり、もしそうだとしたら、”なつこ”から見て姉の子どもである可愛げのない”直人”に対し、父の妻であり、”直人”の母となる地位を確立したことを主張する言動だったのではないかと考えられる。”なつこ”の実家で暮らすようになってからは、”直人”は転校先の学校でも拒否され、多勢に無勢で喧嘩に負け、自ら頭部に怪我を負って帰る。父親は、息子がやられて黙っていられないと、誰からやられたのかと何度も尋ねるが、”直人”は「一人で転んだ」と答える。父親は、一人で、学校に怒鳴り込みに行き、校長に金を叩きつけて、”直人”は通学を免れるようになった。その出来事と時を同じくして、”なつこ”はつわりが重くなり、床に伏せるようになる。周囲から見舞いを勧められ、女中に「お母様のときも大変苦しまれましたよ」と言われたことが後押しとなり、”直人”は”なつこ”の見舞いに行く。ベッドに横たわる”なつこ”は、”直人”が口を開くよりも前に、直人の傷を撫で、「こんな傷をつけさせてしまってごめんなさいね。お姉様に顔向けできないわ」と言って涙する。傷を処置したパッドがふくふくへこみ、表面がカサカサという、”直人”の耳元で聞こえる音が生々しく響き、直人は目を見開く。泣くなつこを置いて、”直人”は何も言わず、”なつこ”の部屋の机の上にあったタバコの箱をポケットに入れて、部屋を去る。一見しとやかなようで、妻であり母であることを使い、直人のセンシティブなところにづけづけと立ち入る、わかる人にはわかる嫌な女感が滲み出る、前半のなつこの印象である。
そんな”なつこ”に自ら寄りつこうとしない”直人”だったが、実母の遺した『君たちはどう生きるか』を読んで、”なつこ”を助けにパラレルワールドに入り、禁忌を犯して”産屋”に入る。”産屋”で”なつこ”を起こすと、”なつこ”は美しい顔を歪め、鬼のような形相で「どうして来たの」「あなたなんて大っ嫌い」と叫ぶ。その姿に直人はハッとして「なつこ母さん」と呼び「一緒に帰ろう」と必死に手を伸ばす。表に出せない心の奥にしまってあって感情をぶつけ合い、一度二人は気を失うが、”ひみ”の助けを得ながら、三人は現実の世界に帰ることになる。別れの時、ひみは、なつこに、「いい赤ちゃんを産みなさいね」と言い、三人は抱き合う。現世に戻ると、”なつこ”は子供のような屈託のない笑顔で笑う。それから数年後、戦争が終わって程なくして、幼い弟と家族四人で東京に戻る場面が、作品のラストシーンとなっている。その場面の”なつこ”は、登場シーンと打って変わって、ショートカットにワンピース姿で”直人”に微笑んでいた。母と子になるようになった女性と少年が、それぞれの抑圧していた感情を決死の思い出ぶつけ合い、新たに関係性を築く構成に、死と再生を思わせた。その中で、直人が成長するとともに、なつこが開放的になっていく姿が見える。
”青鷺”とは何か
”直人”をパラレルワールドに誘い、案内人を務める”青鷺”だが、取り上げずにはおれない強烈なキャラをしている。殺伐とした現実世界からファンタジーの世界に”直人”を導いてくれる救いの手かと思いきや、”直人”を侮辱し、裏切り、殺そうとまでしてくることもある。燃える炎の中で母親が”直人”に助けを求める姿を夢に見てうなされる”直人”を嘲笑い、「直人、助けてー、助けてー」と真似たり、母の姿を模ったハリボテで”直人”を誘き寄せたり、残虐な言葉で脅し襲いかかってくることもある。次の瞬間には態度を変えて、ドジを踏んだり、媚びたり、文句を言いながら力になってくれたりもする。登場場面では、動物的な”青鷺”の姿だが、徐々に嘴の中から、鋭い目や大きく醜い鼻を覗かせるようになり、着ぐるみのように中からギョロついた目の禿げた小男が姿を現す。不気味でギョッとする姿だが、物語の展開によって、ひょうきんにも目に映る奇怪な風貌である。
調べたところ、青鷺は、古代エジプトで「太陽の魂」として神聖視され、再生や蘇りの象徴だったという。日本でいうところの火の鳥、不死鳥と通じる。本作の”青鷺”が導いたパラレルワールドでも、死人や墓石、卵子を思わせるキャラクターや、皮肉にもそれを食べずには生きていけないコウノトリなど死と生を象徴するものが混在する世界になっている。媚びるかと思えば凶暴になり襲いかかってきたり、裏切るかと思えば味方する”青鷺”の二面性は、死と生が背中合わせで併存する姿を抽象化したものかもしれない。
死と再生
映画のテーマに、死と再生を思わせるのは、火のモチーフもある。火事で亡くなった実母が、火を操る少女の姿で直人の前に現れる。まるで不死鳥を想像させる。直人は"ひみ"が世界から出いく際に、火事にあって死ぬことを伝えて止めようとするが、ひみは笑顔で「火だったら平気。それに直人のお母さんになるなんて素敵じゃない」と答える。この言葉は、私の胸を震わし、涙が流れた。死は終わりではなく、繋がれていくと伝わるものだった。そして、無意識下で、母を救えなかったという罪悪感や自分を置いて死んで置いてかれた母に拒絶されたよう感じられている”直人”にとって、ただ母が苦しんで居なくなったわけではないと思える救われる言葉だったのではないかと思う。冒険は、実母の喪の作業のためのプロセスでもあったと思う。
最後に
私は宮崎駿やジブリについて特に詳しいわけではないし、精神分析が専門ではない。そのため、詳しい方からしてみれば、もしかしたら浅はかに思われる部分があるかもしれない。しかし、作品に感銘を受けて、感想や考えをまとめたくて、個人的な趣味で書いた文章であるため、「そういう考えもあるのかー」と思って面白がってもらえたら幸いである。感想や考察の相違があれば、コメント欄などでお寄せいただけると嬉しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
