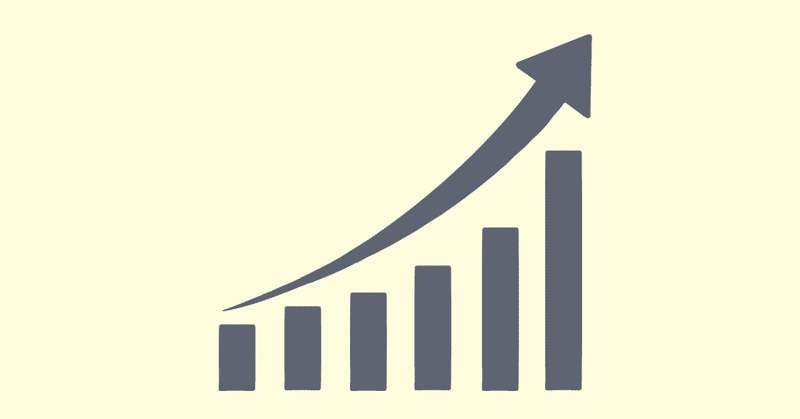
今さら新聞各紙元旦号読み比べまとめ2024Part2【2024.5.10】
「2024年、日本は停滞から抜け出す好機にある」―。そんな前向きな書き出しにひかれた、日経新聞の1面の連載企画「昭和99年 ニッポン反転」。読んでみたら、日本が抱える課題解決の難しさを痛感させられた。
「昭和のシステムは(中略)時代と合わなくなった」「昭和の慣習が邪魔だ」と、99年目を迎えた「昭和」的なるものを糾弾。高度経済成長で獲得した安定を維持するために変革を避けてきた結果、停滞を招いたと解く。
続いて「日本経済、停滞の理由」について尋ねた街頭アンケートのうち、「野心をもとう」「少子化 改革意識のうすさ」「若者に投資しよう」「年功序列で安泰の文化」などの声が並んだ。それに呼応するように、変化を受け入れ、若い人の力を結集して世界に打って出て、「成長する国に若返ることができる」と、1面記事は意気揚々とした筆致で締めくくられていた。
関係記事は、3面、特集6、7面へと大展開。3面で国内外の識者が現状打破について語り、6面ではバブル経済後の官民の取り組みを当時の「霞ヶ関」次官3人が証言していた。それによると、2000年代初めに歳出削減で一定の効果を出せたものの、その後の行財政改革は頓挫、製造業を優先してデジタル化に遅れを取ったという。
記事では「痛みを避け目先の支援に傾いていく」などのくだりがあった。私は政経分野には疎いのだが、徹頭徹尾、数合わせの「上から目線」の論調だと感じた。例えば、大企業に対する法人税減免などの優遇策や、非正規雇用の増大、消費増税など、市井の人たちが被った「痛み」についても言及されていない。
代わりに目を奪ったのは、7面の右肩下がりの 折れ線グラフだった。 世界のGDP(国内総生産)に占める日本の割合を示すもので、1994年の17.8%を最高に低落傾向にあり、2024年には3.9%に落ち込むと予想されている。
「いいか、これからの日本は高度経済成長の坂を駆け上がったのとは逆に、一気に坂を下っていくだろう。一度、いい思いをした人間は、簡単には行いを改めることはできない。だから、日本の未来は真っ暗だ」
大企業のシステムエンジニアで、中小企業診断士でもあった亡き父は、1980年代半ばに日本の暗い未来を予言していた。
「コスパ重視 長引いた不調」という記事では、「節約志向を前に企業は値上げに慎重になった。収益を伸ばせない企業が賃上げをためらうという悪循環に陥った」とあった。このタッチもどちらかというと企業側の論理に立っている。人々が節約にいそしむのは、生活防衛だ。そうせざるを得ない、厳しい暮らしがある。そのことをどれだけ意識しているのだろうか。
前向きな見出しがかえって空回りしているような印象を受けた。日本の夜明けは遠い。
*すてきな画像は、みんなのフォトギャラリーからtokyojackさんの作品をお借りしました。ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
