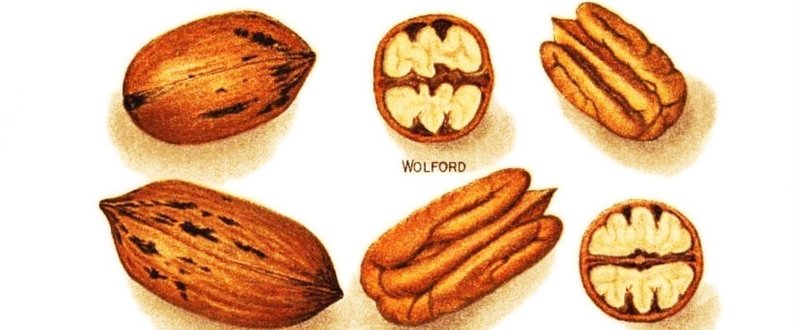
試し読み!12月17日発売「ブルームワゴン」第六話
第六話 「どうかわたしの願いを叶えて下さい」
彼女は赤ん坊を抱いてその部屋を飛び出した。途中でリネン室と書かれたドアの前を通り掛かったので、そこに忍び込んでバスタオルとシーツを盗み出し赤ん坊を包んでやった。彼女は転がるようにして階段を使って一階まで下り、産院の裏玄関から外に飛び出すと一目散に山を下った。彼女は看護師や医師に、「あなたが産んだ赤ん坊はもう死んだ」などという嘘をついた理由や、自分の産んだ赤ん坊があんなひどい目に遭っている理由について訊きたいなどとはまったく考えなかった。とにかく一刻も早く産院から離れなくてはとだけ思っていた。赤ん坊の体には明らかに、何か間違った、おぞましいことが行われていた。
彼女は山道で何度も転び、土や草で膝や掌をすりむき、木の根に顔を打たれ、折れて木から千切れそうになっていた細い枝の先で眼球を傷つけそうになった。強い風と雨があらゆる方角から滅茶苦茶に吹きつけてきて、休みなく走っているためただでさえ苦しい呼吸を更にしづらいものにした。土は雨を飲んでどろどろで、彼女が履いていた入院患者用のスリッパはすぐに泥だらけになって重たくなり、知らない間に脱げてなくなってしまった。彼女は薄手の寝間着一枚という恰好だったので、それは彼女が外に飛び出して間もなくびしょ濡れになり、走っている間にあちこちに裂け目が入ってボロボロになった。
彼女は裸足で、彼女の体をかろうじて覆っている、水を吸って重たいただの布と化した寝間着姿でずっと走り続けた。しかし山を下っている途中、産院の人間に彼女が赤ん坊と一緒に逃げたことを気づかれてしまったことを知った。連中は犬を放ったようだった。彼女の荒い呼吸と、雨がそこらじゅうのものを激しく叩く音と風の重たい唸りとの隙間に、犬の鋭い鳴き声が混じっていた。
「犬は赤ん坊の匂いを記憶しているのだろうか? わたしの匂いを記憶しているのだろうか? ひょっとしたら、子供を産んだばかりの女には特別な匂いがあって、犬はそれを覚えるように訓練されているのかもしれない」
嵐の中を必死になって逃げる間、そんな疑問が頭に浮かんだが、すぐに彼女はそんな疑問など投げ捨てて、無事に山を下りることだけを考えた。そして彼女は何とか産院の連中にも犬にも見つからず、赤ん坊と一緒に家に帰ることができた。
「わたしはまず赤ん坊から濡れたバスタオルやシーツを剥ぎ取り、よく体を拭いてやると乾いた服を着せました。わたしも着替えて赤ん坊を胸にぴったりくっつけて抱きしめ、手で体をこすり続けました。わたしたちはベッドに入り、布団を被りました。そのころには赤ん坊の顔色は、健康な赤ん坊が持つ色に戻っていました。わたしはやがて眠ってしまった赤ん坊を見て、ようやく安心することができました。でもわたしはすぐにあることに思い当たりました。考えてみればわたしは赤ん坊の泣き声を一度も聞いていないのです。産院を飛び出したときも、山を下りているときも、べッドに寝かせたときも、目や口を閉じたり開けたりはしますが、一度も声を上げないのです。
わたしは窓の外を見てみました。何か音が聞こえたような気がしたのです。するとそこに誰かが潜んでいることが分かりました。地面の近くに、時々黄色い丸い光が見えました。それは産院の連中でした。わたしは急いで赤ん坊を抱き上げ、そばにあったわたしの服で包んで裏口から外に逃げ出しました。背後から、犬の鳴き声と、その犬の闘争心を煽るような男の声が聞こえました。わたしは走りました。わたしはすでに疲れ切っていて、体中が痛み、足は重く、今にも倒れてしまいそうでしたが、わたしが足を止めたら終わりでした。
走っている途中で、営業時間を過ぎてシャッターを下ろした商店の前を通りました。商店の前には青いビニールシートをかけて留められている沢山の木箱がありました。わたしはそのうちのひとつの木箱の中に赤ん坊を入れるともう一度ビニールシートをかけました。そのとき、犬の鳴き声がこれまでになく大きく、すぐ後ろから聞こえてきました。振り返って見るとそこに人間の姿はありませんでした。何頭もの黒い体の大きな犬が、わたしに向かって一斉に走ってくるところでした。わたしは赤ん坊を隠した木箱から離れることだけを考えて、ただまっすぐに走りました。
気がついたときには、わたしは地面に倒され、犬の脚に押さえつけられていました。わたしの体のあらゆる場所に犬たちが食らいついていました。わたしは激しい痛みに引き裂かれそうでした。犬の荒い息遣いと、強い興奮が伝わってきて、やがて濃い血の匂いがしてきました。遠くで男の声がして、犬たちに何か命じている様子でした。でも犬たちは彼らの主人の言うことをまったく聞きませんでした。
わたしはそこで気を失ったようでした。目覚めたとき、わたしは水たまりの中に転がっていました。わたしの体から出た血が水たまりを黒っぽい色に変えていました。どこからか明かりが差していたのでそのことが分かりました。わたしは目だけを動かして上を見ました。雨はやみ、雲の切れ間から月がのぞいているのが見えました。わたしの足は、犬たちの牙で破れた雑巾のようになっていました。不思議と痛みはもう感じませんでした。でもどうやっても立ち上がれないので、わたしはみみずのように、這って道路を進み、とうとう赤ん坊を隠した木箱まで辿り着きました。赤ん坊は無事でした。かすり傷ひとつ負っていませんでした。そのときにわたしは思い出したのです。この近くに、見えないとされているものが見え、聞こえないとされているものが聞こえ、わたしたちには思いもつかない知恵を授けてくれる人たちがいることをです。そしてわたしはここまできました」
そのとき女性に変化が起こった。着ていたコートにじわじわと黒い染みが広がり始め、それはコートを汚すだけ汚すと袖口から伝って床に落ちた。彼女の頭を隠していたフードも濃い色に変わった。彼女の顔には夥しい数の切り傷が現れ、裂けた皮膚の間から血にまみれたピンク色の肉や黄色い脂肪が飛び出した。彼女の耳は取れかけていて、喉の近くには丸い大きな穴がいくつも開き、そこから多くの血が流れていた。
部屋の中は、瞬く間に血の臭いに包まれた。「もう限界なんだ」ヨークの父親は言った。「体を自分に繋ぎとめておける最後の瞬間が近づいている」
彼女はソファの背もたれに体を預けていることさえできなくなった。コートは崩れて前に倒れ、ソファから滑り落ちた。にぶい音を立てて床に落ちた体からは、凄まじい臭気が立ち上っていた。
「どうかわたしの願いを叶えて下さい。どうかわたしの代わりにこの子を育ててやって下さい。わたしは沢山の罪を犯しましたがこの子はまだこの世に生まれたばかりなのです。あなたがたの慈悲の心をわたしからの娘への贈り物にしたいのです」
それはもう声ではなかった。ヨークの両親には分かる電気信号のようなものだった。腐肉のようになっている体からついに離れなくてはならなくなった若い母親が、必死になって送っている声によく似た何かだった。
第七話へつづく(毎週水曜日更新)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
