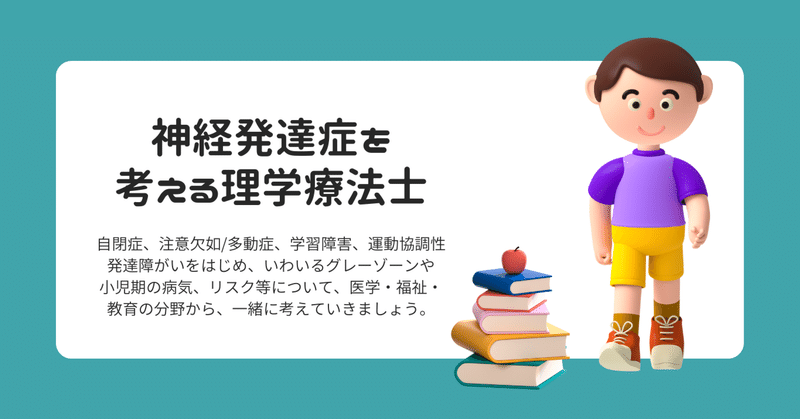
グレーゾーン
たとえば、高齢者における認知症の診断を受ける人をブラックとすれば、軽度認知障害(いわいるMCI)と呼ばれる認知症までは障害の程度が重くないが、正常な範囲よりは認知機能が低下している方たちのことを、いわいるグレーと呼べるだろう。
軽度認知障害は、何も対応をしなければ認知症に移行する確率が高まる。適切な治療、または認知トレーニング、食生活、生活リズム、運動習慣などを改善させていけば、認知機能の低下の進行を止めることができる可能性がある。
では、発達障害グレーゾーンに関してはどうだろう。
明確な診断はついていないが、なんらかの障害特性を抱え、生きづらさを抱える子供たち。
また近年では、発達障害の大人についても取り上げられることが多くなってきている。
グレーゾーンの子たちが、急に重度の知的障害に進行することは想定しづらいという点では、認知症患者で言うところのブラックに移行していくということはないにしても、グレーがホワイトになることはおそらく難しい。
発達障害の特性をいくつか抱えながら、社会の中で生きづらさを抱えるグレーゾーンの子供たちは、全くのブラックというわけでもなく、全くのホワイトというわけでもない、まさに中間点にいる存在。
いつも、中間点の存在の支援は、十分ではない場合がある。
そして、難しい。
知的障害や、身体障害、重度心身障害の支援が簡単だ、といっているのではない。
理解を得るための知見、支援方法、手技、場所、法整備が進みやすいのが、ブラックやホワイトの領域に関してである。
グレーはいつも、後回しだ。
グレーゾーンとしてひとくくりにされる子供たちの抱える困難さは、まさに十人十色であって、正解がなく、開かれた課題だらけだ。
ある程度の医学的・心理学的手法は役に立つ。
不安に対する暴露(エクスポージャー)療法。
不適応行動に対する応用行動分析的アプローチ。
怒りに対する認知行動療法。
しゃべり下手に対するコミュニケーショントレーニング。
ただし、不安があるから暴露療法をすればいいというわけではない。
しゃべり下手だから、コミュニケーションのトレーニングをすればいいというわけではない。
なぜ不安になるのか。
自閉特性の、こだわりや完璧主義、対人関係の難しさからくるものか。
失敗体験が多く、成功した経験が少ないからか。
未来を先読みしたり深読みしたりする思考のクセからくる認知の歪みなのか。
さまざまな可能性の中から、原因相当性の高いものに対して、その原因を取り除く、あるいは軽減させるようにしていくようにしなければならない。
なぜ、なぜ、なぜと深く考えていくことも重要だが、多角的観点から物事をとらえることも重要である。
そのためには、さまざまな知識が必要で、その知識の幅は、特定の分野に固まりすぎると、全人間的に支援をしなければならない子供の発達に関しては、不利益になる場合がある。
医療職だからと言って、保育、教育分野の勉強を怠ってはいないか。
社会保障、福祉制度、サービスなどの勉強を怠ってはいないか。
経営、サービスにかかる費用、会計、事務、安全管理などの勉強を怠ってはいないか。
さまざまなことに目を向け、知識や技術を習得、収集しながら、グレーゾーンの子供たちの支援にあたっていきたいと考える、今日この頃。
たくさんの知識に出会うためには、たくさんの人と話すこと。
たくさんの本に出会うこと。
たくさんの価値観に出会うこと、であると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
