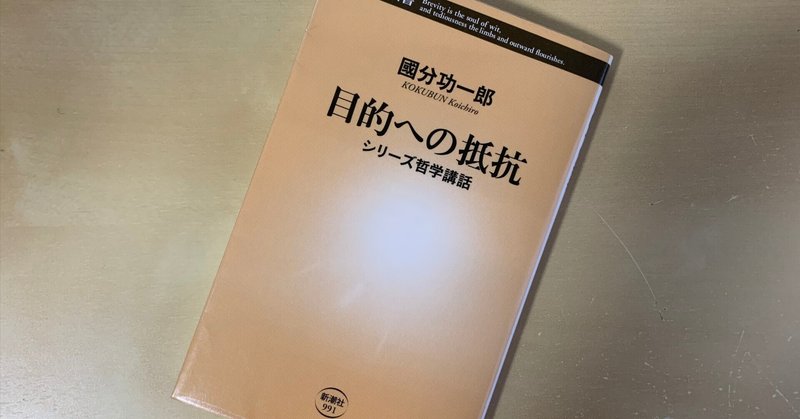
ブックレビュー「目的への抵抗」
(通常ブックレビューは私のプライベートnoteであるKeith Kakehashi名義に掲載していますが、本レビューはHIRAKUコンサルタンシーサービシズの業務にも関連しますので重複して掲載しました。)
前回の「暇と退屈の倫理学」に続いて今回は國分功一郎による「目的への抵抗」である。
本書はコロナ禍の2020年10月にオンラインで開催された「東大TV-高校生と大学生のための金曜特別講座」と、2022年8月に著者が自主的に開催した特別授業である「不要不急と民主主義」が出発点である。
著者が「はじめに」に指摘している通り、「暇と退屈の倫理学」と比べると学生向けだけに砕けた口調で語られているので読みやすい。また途中にそれぞれの講座での質疑応答の部分があり、補足説明的な役割とともに優秀な学生とのライブリーな対話を垣間見ることが出来る。
第一部 哲学の役割
本書の第一部は、哲学者ジョルジョ・アガンベンが2020年2月に発表した論考が題材となっている。アガンベンは『コロナウイルスの拡大を防ぐという理由で実施されている緊急措置は、「平常心を失った、非合理的で、まったく根拠のないものである」』と指摘している。特に「厳しい移動制限」が行なわれていることを鋭く批判した。
多くの人が「緊急事態」なのだから移動制限も仕方が無いと思う中で、「自由を守るために自由を制限しなければならない-そんな矛盾が受け入れられるだろうか」という問題提起である。
アガンベンは最初の論考の補足説明を同3月に発表、その三つの論点は次の通りである。
三つの論点(1)-生存のみに価値を置く社会
三つの論点(2)-死者の権利
三つの論点(3)-移動の自由の制限
特に三番目の移動の自由の制限が問題で、移動の自由さえあれば様々な抑圧から逃げることができる、それを制限するということに哲学者として「チクリと刺す蛇」の役割を演じている。
彼の論点には「生の経験の単一性」、すなわち「身体的な生の経験と精神的な生の経験はつねに、互いに分離できないしかたで一つにまとまっていたが、私たちはそれを、一方の純粋に生物学的な実体と、他方の情感的・文化的な生とに分離してしまった」という考え方がある。
もう一つは行政権力が緊急政令によって、権力分立という民主主義の原則を事実上の廃止に追い込み、もはや立法権の代わりとなりつつある点を問題視している。これはヴァイマル期をへてヒトラーに全権委任した歴史を最悪の事態として学んだ教訓を忘れてはいないか、ということでもある。
もちろんコロナ禍で一時的に医療ひっ迫のため行動制限することはやむをえなかっただろう。ただそれを無制限に許容したり、批判を抑え込んでいたとしたらそれは危険な兆しだといえるのではないか、という指摘である。
今になったら「確かにそうだな」と思える論点ではあるが、あの時期にアガンベンのように「チクリと刺す蛇」の役割を演じられる人がどれほど日本社会にいたのだろうか。欧州の論客にとっての自由への渇望と日本社会のそれの大きなギャップを強く感じた。
第二部 不要不急と民主主義-目的、手段、遊び
第二部は第一部の補足的な扱いで、「不要不急」と判断する目的とはそもそも何だったのかについて「暇と退屈の倫理学」を振り返りながら説明していく。
そこでの問題点は「現代社会はあらゆるものを目的に還元し、目的からはみ出るものを認めようとしない社会になりつつあるのではないか」という点である。
「暇と退屈の倫理学」における消費と浪費・贅沢、本書における必要と不要、これらの排除の理論は目的からはみ出るものを認めないことで共通している(前者でいわゆる「清貧」の考え方は排他的だった)。「毎日カロリーメイトだけ食べたって、別に十分生きていけるよ」という資本主義の囁きと同じだ。
そしてハンナ・アーレントを引用し、目的という概念にはそもそも手段を正当化するという要素が含まれている、と指摘する。そしてそれは「どんな無駄をも排し、常に目的を意識して行動する」(=何かのためでない行為を認めない)ことを前提とする全体主義(いかなる場合でもそれ自体のために或る事柄を行うことの絶対にない人間の世界)につながる、という。
まとめ
移動の自由にしても、目的による正当化にしろ、資本主義はその効率性の追求から我々に強いてきたものだ、という点は企業勤めであった身としてまさに実感するところだ。そもそも日本の企業は就社による移動(=転職)の自由を事実上制限し、強制的に転勤を強いていた訳だし、目的のためにブラックな運営やリストラを正当化する企業は山ほどある。そして多くの人はそれが明白であっても許容してきた。
数年前までその片棒を担いできた自分自身ではあるが、個人で事業を行なっている今は企業勤めの制約は無い。嫌な仕事なら断れば良い訳だし、まさに仕事のための仕事だ(楽しむための仕事)と言ってもいいだろう。
そして移動の自由にしても、目的による正当化にしろ、労働市場が売り手市場になり、企業が選ばれる側に立つようになった今、見直しが始まっている(転勤制限や副業解禁、エンゲージメントや人的資本開示などがその一例)。そういった動きに鈍感であったり、横並びでしか変革できない企業はますます選ばれなくなっていくだろう。
個人の立場から言うと、目的に没頭して暇を持て余す余裕の無い人、すなわち目的の奴隷になる人は、どこかで余裕なきゲームに破綻するか、手段と目的を取り違え、いつまで経っても終わることのない消費を繰り返し、思考を強制するものを受け入れる余地が無くなるだろう。ここでいう消費はモノだけでなく、仕事への生き甲斐(消費概念の労働への持ち込み)も余暇(非生産活動への消費)も含まれる。
筆者が「暇と退屈の倫理学」で指摘した通り、人は奴隷状態に陥るなら、思考を強制するものを受け取れない。退屈を時折感じつつも、物を享受する生活のなかでは、思考を強制するものを受け取る余裕をもつ。そして退屈と向き合いながら生きることができるようになると、他人に関わる事柄を思考することができるようになるのだ。
そして退屈と向き合う生を生きていけるようになった人間は、おそらく、自分ではなく、他人に関わる事柄を思考することができるようになる。それは<暇と退屈の倫理学>の次なる課題を呼び起こすだろう。すなわち、どうすれば皆が暇になれるか、皆に暇を許す社会が訪れるかという問いだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
