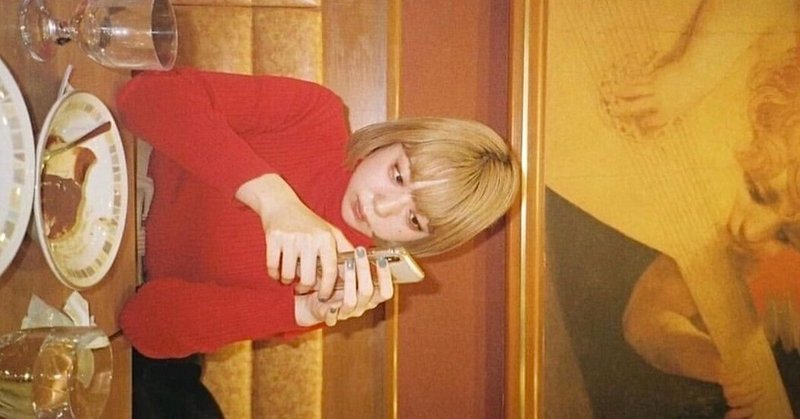
わたしと盛岡と、ヘラルボニー
はじめまして。
はじめまして。わたし、4月からヘラルボニーに入社しました
石井 菜実(いしい なつみ)です。
社会人1年目、初めての春を迎えました。
今日はヘラルボニーに出会った日のこと、わたしの生まれた街のこと、そして、自分のことを話したいと思います。
ヘラルボニーとの出会い
出会いはいつも突然やってくる。
なんて事のない1日の、なんて事のない瞬間。
たったひとつの出会いや選択が運命を変えてしまうことがある。
2022年1月14日
ヘラルボニーと出会った日のことは鮮明に覚えています。
いつものようにinstagramのストーリーを流し見していると、ヘラルボニーでインターンシップをしている知り合いが、急遽イベントの手伝いを募集しているのを偶然見つけました。
「ヘラルボニーで明日、1日手伝いできる方いませんか」
その会社の名前はなんとなく知っていました。
障害のある人の絵をハンカチとかスカーフにして最近じわじわと話題になっている会社、
そのくらいの、本当にふわっと知っているくらい。
でもなぜか、この彗星のごとく現れたこの募集を見たときなんとも言えない胸騒ぎがしたのを覚えています。
強く波打つようにざわざわと、大きく、はっきりと。
直感的に「これは、やらなきゃ」
と思いました。やりたいとかやってみたいとかじゃなくて、やらなきゃ。
猛烈に突き動かされるようなその感覚に驚きながら、急いで知り合いにメッセージを送りました。
今考えると、図々しいくらいのその直感は結構当たっていたのだと思います。
車内
結局緊張して一睡もできないまま、1月14日の当日を迎えました。
会場は沿岸の陸前高田という街で、内陸の盛岡から向かうと片道2時間ほどかかる場所にあります。(岩手県は本当に広くて大きいのです)
その移動の車内で、副代表の文登さんと社員の丹野さんとたくさんお話をしました。ぶっちゃけもっとイケイケの怖い人が来るのではないかと思っていたので(!)お二人の優しい話し方とフラットな雰囲気にとてもびっくりしたのを覚えています。他愛もない雑談は楽しかったし、ヘラルボニーのことをほとんどなにも知らなかったわたしには全てが新鮮なものでした。
わたしは母が福祉関係の仕事をしていますが、
福祉の勉強をまったくといっていいほどしてきませんでした。
正直、興味が湧いたことすらありませんでした。
福祉=良い事・人助けというイメージしかなく、母のように人生をかけて福祉に携わっている人をそばで見ているとなおさら、そういうものに関わるほど自分が良い人間だと思わなかったからです。物心ついたときから、そういう世界に関わる人はいわばつねに他人のために働き続ける愛と正義感があるのだと思っていました。
そう、生まれてこのかた福祉のことを考えたことがありませんでした。
ましてや福祉業界でのビジネスなんて、そんなことは聞いたこともありませんでした。
思えば、街中で障害がある人が働いている景色を22年間生きてきて見たことがありません。
この世にたくさんいる障害のある人たちのなかで自分の力でお金を稼げる人はどのくらいいるんだろう。
そんなことを考えて怖くなったのを覚えています。
そして、ヘラルボニーの考えは、なんて素敵なんだろうと衝撃を受けたのです。
車窓を流れる一面の雪景色を眺めながら、生まれて初めての出会いに胸が高鳴った感覚を今も鮮明に覚えています。
「異彩」
その言葉の意味は作品を目の当たりにしてすぐに分かりました。
会場に並べられたたくさんの作品。
感情が揺さぶられるような激しく大胆なタッチ、生きているように躍動する線、目の覚めるような色使い…。
気づけば吸い込まれるように見入っていました。意味や制作背景を聞かなくても、理屈抜きで体の深い部分が震えるような、本能的に惹かれてしまうような。
力強く、ときにはやさしく語りかけてくるようなひとつひとつの作品たちには、到底言葉では表現できないほどの躍動する魅力があります。初めての出会いにわたしは呆然としました。
彼らの感じている感覚や世界はこんなに鮮やかに彩られている。
ただ、目の前の作品がひたすらにかっこよかった。感動した。
それだけの理由で、帰ってからも障害のある作家さんの描いたアートの記事や動画を漁り続けました。
ビリビリビリ、ドカーン!うっとり。圧倒。
ダイレクトに感性が揺さぶられるような、その力強さ。
クセになるようなその魅力に、なんだかすっかりやられてしまいました。
そして次の日、陸前高田から2日経ってますます身体中をほとばしっていた気持ちをnoteに書き綴り、双子の代表である崇弥さん・文登さんにインスタグラムのDMで送ったのです(唐突)

(燃えるような勢いに任せて書いたnoteの文章。今見返すとかなり恥ずかしいのですが、このときの気持ちを文章に残しておいたのは本当によかったなと今になって思います。)
わたしのこと、盛岡
またまた唐突に話が変わります。ここからはちょっと自分語りです。
わたしは、とてもきれいな街で生まれ育ちました。
澄んだ川が街を流れ、秋には鮭が上る。晴れた日は大きくそびえ立つ岩手山がくっきりとのぞみ、一年を通して美しい夕焼けに包み込まれる人口30万人ほどの街です。
えびす様のようなこの赤ちゃんがわたし。

(予定日から大遅刻で生まれ、あまり泣きもせず、当時からとにかくぼけーっと過ごしていたらしく、生まれた時から今に通づるものがあるなと思います)
ここからの18年、盛岡でのびのびと生まれ育ちます。
今でこそいいところを語り出せばキリがないくらい盛岡が好きですが、高校のときまではそんなにここが好きではありませんでした。都会みたいにすごく新しいものはないし、遊ぶといえば町外れの大型イオンだし、アーティストはライブに来てくれないし、盆地だから超寒いし、それでいて暑いし…みたいなフラストレーションと都会への憧れを募らせる日々。
生まれてから今日までのわたしの全部を知っているこの街。
ここで生きているわたししか自分自身も知りませんでした。

変わった子ども
わたしは小さい頃からよく変わった子と言われながら生きてきました。
保育園のときから体を動かすのが好きではなく、みんながかけっこやジャングルジムで遊ぶなか、園庭の隅でミミズを掘ったり、花壇でオシロイバナの種を拾ったり、砂場でキラキラした粒をずっと集めたりして過ごしました。
小学校に入ってからもそれは相変わらずで、というかむしろエスカレートして。全く褒められたことではありませんが宿題は躊躇なく丸めてポイするタイプだったし、徒競走は5等だし跳び箱は飛べないし、マラソン大会でもびりっけつ。他にも学校を苦手だと思う瞬間はたくさんあったし、集団生活で何かを強いられてそのプログラムの中で順位をつけられることはわたしにとってかなり苦痛でした。学校生活のなかでどんどん自信は失われていく。ものすごくはずかしかったし、いわゆる優等生の子たちを毎日羨ましく思っていました。
通っていた学童保育や家の中では工作をしたり、自分で漫画や物語を書いて過ごしたり、地域の人が寄付してくれた本を夢中になって読み漁ったりしました。ひとりで黙々と好きなことをする時間だけが、誰にも邪魔されない唯一の支えと癒しでした。
小学生の頃は特に、箱のような学校が嫌いでした。
朝目が覚めると泣いてしまうこともあったし、
仮病を使って休むこともありました。
でも、両親はわたしの得意な絵や歌、詩、ちょっと変わった趣味を認めてくれた。
だからなおさら言えませんでした。
『なっちゃん、学校はたのしい?』「うん、楽しいよ」
『よかった、何かあったらいつでも相談してね』「わかった」
そう言われるとなおさら、苦しい気持ちを打ち明けられませんでした。
盛岡、脱出。
高校まで、その箱の中に閉じ込められたような感覚は続きました。楽しい時間もたくさんあったけど、常にうっすらと苦しさがある。どこにいても居場所がない。それはわたしが無意識に自分にかけていた呪いだったのかもしれません。とにかく一度この街から逃げだして自分らしく生きてみたい。いや、今までの自分らしくなく、生きてみたい。環境を大きく変えたいと思い、両親の反対を押し切って進学先を仙台の大学に決めました。
大学生活
大学生になって、驚いたことがありました。
服や化粧品への関心に周りが興味を持ってくれるようになってくれたことです。
まわりのおしゃれが好きな友達と学校帰りに買い物をしたり、実家で厳しく決められていた門限を気にせず夜まで遊べたり。お金を貯めれば大好きな温泉に好きなだけ行ける。
高校生の時からやっていたTwitterでの発信にもさらに力を入れてみると、多くの人が目を向けてくれました。
今までただひとりで好きだったこと、周りには言えなかったこと。
環境を変えたら、それなりに時間はかかったけれど精神的にとても自由な状態で生きられるようになり
現実世界の友達はもちろん、SNSを通じて日本全国に、同じように楽しめる友達ができました。
それが、本当に本当に嬉しかった。
自分を認めてくれる人がいることをたくさんの人が教えてくれました。
これでいいんだ
「これでいいんだ」
大学4年生になって、やっとそんな風に肩の力が抜けた気がします。
じつに21年の呪縛から解き放たれたようなすっきりとした気持ちでした。
帰省して、盛岡の街を散歩したときのこと。
本当に不思議なことに、見慣れていた景色がすごく鮮やかに見えました。川沿いの景色も、喫茶店も、冷たい空気と秋の高い空も。18年ここに住んでいたはずなのに、知らない街のように感じるくらい。小説でよくある描写のようなこういうのって本当にあるんだなとちょっと驚きながら歩きました。
今の自分で、もう一度この街で生きてみたいと思ったんです。
そんなとき、1月に送っていたあのnoteを読んでくださった文登さんから
入社のお誘いをいただくのでした。(InstagramのDMというのが超今っぽいポイント)

腰を抜かすほど驚くと同時に、とても嬉しかったです。
そんなこんなで入社が決まり、本当に盛岡に帰って来ることになりました。
いいじゃん、盛岡
そして今!盛岡を大好きだと思える大きな理由がもうひとつできました。
ヘラルボニーギャラリーがあること。
そう、他でもないこの街にはヘラルボニーがあるのです。


素敵でしょー!
よく晴れた日のギャラリーを撮影。目の覚めるような美しさに惚れ惚れします。
実際に来てみると、この写真よりもっといいです。
お近くの方もそうでない方も、ぜひお越しくださいませ(社員エントリーでも抜かりなく宣伝)
「ちがいに、リスペクトを」
「ちがいに、リスペクトを」
わたしはヘラルボニーの価値観のひとつであるこの言葉が大好きです。
ちがいって、すごい
人とのちがいを恨めしく思ってきたわたしが
最近やっと、胸を張ってそう言えるようになりました。
そう、ちがうって当たり前だけど当たり前に素晴らしいのです。
わたしにそれを教えてくれたアーティストさんたちの作品が放つ、異彩
それを日々、光のように感じています。
出会いはいつも突然やってくる。
なんて事のない1日の、なんて事のない瞬間。
たったひとつの出会いや選択が運命を変えてしまうことがある。
わたしはあの1月14日があったから、今こうして入社エントリーを書いています。
キーボードをカタカタ打ちながらやっぱり不思議でしょうがないけれど、運命かもと思っています。
あのとき10分起きるのが遅かったら、あの道を通っていなかったら、今全く違うことをしていたかもしれない。そんなことをたまにふと考えます。
入社してあっという間に3週間が経ちました。
ヘラルボニーの描く未来。その可能性のためならわたしも一生懸命やってみよう!と思い奮闘する毎日です。
胸の高鳴りは止まりません。
進んでいこう、このワクワクを抱きしめて。
明日からも、日々は続く。

石井 菜実
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
