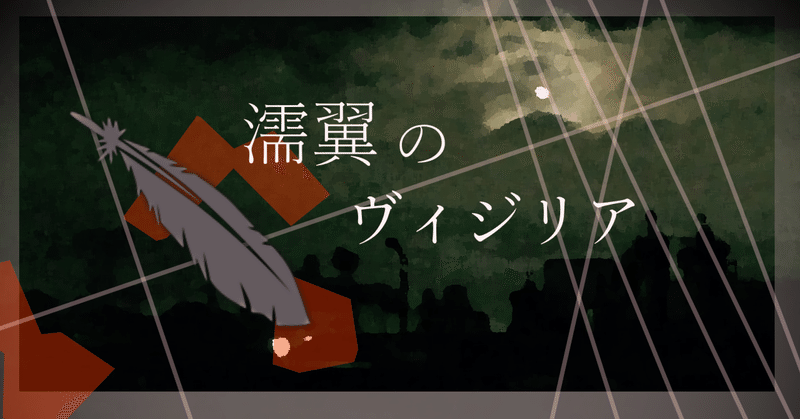
【小説】濡翼のヴィジリア【第三話】
あんなに夜を徹したというのに、朝になると自然に目が覚めるのは、仙鳥としての習性なのかもしれない。あるいは従軍時代の習慣か。
あれだけ耳障りだったラッパの音が、ときおり恋しくなる。
レナータはまだ眠っているようだった。
霧で煙った町並みを横目に、ドアの前に置かれた新聞を手に取る。第一面には頬まで裂けた口で悲鳴を上げる娼婦と、ナイフを振りかぶる暴漢の版画が刷ってあった。
「資本主義だねえ」
新聞版画というものはひどくコストがかさむものだ。それだけの価値が『突き刺し魔』のニュースにはある。どうせ記事には素人の憶測しか書いてないので、訃報欄だけ見てさっさと食卓のすみっこに放り投げた。
洗面所で寝間着を脱ぐあいだに、居間の方でレナータが起きた気配があった。
「朝食ならカウンターにある!」
ウィルドが声を張りあげると、足を引きずるような音が返ってきた。
水道局がまたサボったらしく、シャワーからは冷水しか出なかった。濡らしたタオルで身体を拭きつつ、ウィルドは逆立った首の羽毛を抜いた。ゴミ箱を開けてみると、昨日すでに同じことをしたレナータの赤い羽が何枚か入っていた。
「誰かいらっしゃったんですか」
食卓につくと、レナータがマーマレードを塗りたくったポガチャを頬張りながら言った。
ウィルドもマーガリンを乗せた切れ端を噛んでうなずく。
「クレイヴン伯爵だ。ボーア戦争のときからの知り合いでね。どうしてだい?」
「流しのコップが多かったもので。それに空き瓶も。……伯爵?」
「警察の新顧問だよ。家で不幸が続くもんだから、早々にハンガリーに渡って家督を継ぎなさったそうだ。伯爵といっても領地は片田舎に小麦畑がひとつふたつって程度だが……」
「ああ、最近よくある名誉爵位ってやつですか」
「我々の出資者でもあるし、異種族への理解も深い方だ。挨拶くらいしたまえよ?」
「考えときます」
レナータは顔をしかめながら席を立った。
彼女がシャワーを浴び終える頃になって、ちょうど出勤の時間になった。ジャケットを羽織ってソフト帽をかぶる。軽くて落ち着かないので、今日はポケットに嗅ぎタバコの箱も忍ばせておいた。レナータが服に香水を振るあいだにアパルトマンの外に出て、路上のタクシーを呼び止める。
「法院まで」
降りてきた御者に伝えると、彼は物珍しそうにウィルドの顔を見た。
「また誰か死んだのかい」
「チップを追加するから、その口を閉じてくれと言ったら?」
「情報ってのは端金より価値があるって言うぜ」
ウィルドはため息をついて、自宅の玄関をうかがった。レナータはまだ出てこない。
「……クロイツ通りの娼館だ。妖精がひとり殺された」
「それだけか」
「ああ、それだけ」
「まったくいいご身分だな」
御者はグローブを外して、手の甲に浮いた汗をぬぐった。日焼けした顔がわずかに歪む。
「有名人に殺されたってだけで世間は同情しやがる。あの辺りじゃ人死になんて日常茶飯事だろうがよ」
「人間じゃない。妖精だ」
「まあ、俺は区別も差別もしないことにしてるんだ。男、女、人間、妖精、化け物ども……どいつも大した価値がねェからな」
「すばらしい博愛だな」
「だろ? シティボーイでね」
ちょうどレナータがカンテラを抱えて出てきた。御者はグローブをはめ直して、うやうやしくタクシーのドアを開ける。彼女が会釈すると、繋がれた馬がいななきを返した。
流石に馬車を動かすときになると、御者は黙って手綱を繰っていた。
いけ好かない野郎だが、こういう飾り気のなさは悪くない。
「伯爵はなんと?」
タクシーが広場を通り過ぎたとき、レナータが唐突に言った。
ウィルドが見つめ返すと、彼女は窓から外を見たまま、「さっきの話です」と呟いた。
「だって用もなく訪問を受ける鳥でも無いでしょう、あなた」
「ん……ああ。警察で劇場にガサ入れをするから、援護に参加してくれという話だった」
「勝手なもんですね」
レナータはカンテラの口金を指で叩いた。
窓の外では人々が路面電車の駅に並んでいる。
前国王がクーデターで死んだのが十年前。トルコ人ばっかり贔屓していた総督府の方針もずいぶんと変わり、今では地方から来た妖精がだいぶ増えた。
「まったく、こっちは裁判所の独立部隊だっていうのに」
「言い訳が欲しいんだろう。『不正は無かった、法院の連中も見ていたのだからな』、とな」
「告げ口が恐いならその場の全員ブチ殺せばいいじゃないですか」
「レナータ君、今は二十世紀だよ」
だから何です? と言いたげにレナータはカンテラをこすった。
彼女のつやつやとした眼帯を眺めるうちに、タクシーが法院に着いた。御者が客室のドアを開けると、この時期に特有の乾いた夏風が吹き込んできた。
「ありがとう」
ウィルドがチップを渡すあいだに、レナータはさっさと法院に入っていく。
近くの屋台で揚げポテトとレモネードを買いながら、ウィルドは建物を見上げた。
法院は元々礼拝堂だったそうだ。帝国からの独立のときに用済みになったのを、総督がごちゃごちゃと増改築してしまったのだとか。
つい二百年前まではここで異教徒を縛り首にしていたのが、今は裁判所付の警察もどきがすし詰めになっている。首吊り台も片付けられて、美しい金百合の花壇になっている始末だ。
「おはようございます」
地下の仕事場に潜ると、本が積まれたデスクからドイツ訛りのあいさつが飛んできた。書記官のアリッサが、肉球の付いた指で万年筆をくるくると回してくる。
「留学の件は良かったのかい?」
ウィルドの机にはさっそく事件の資料が置いてあった。コートを壁に掛けながら、一番上のファイルをめくる。各紙の報道内容に、検視報告書。目新しいものは無い。
「あの話は断りました。こちらの方が中身のあるものが読めますもの」
昨日まで資料棚に置いてあった大学のアテネ像が消えていた。この娘、今日からしばらくは仕事に集中するつもりらしい。あるいは国にはもう二度と戻らないつもりか。
「なるほど。死して骨を貴ばれるより、むしろ泥中に尾を引きずらん……と言いたいわけだ」
「はい?」
「東洋のことわざさね」
ウィルドは読書眼鏡をかけて、ちらりとアリッサを見た。
「向こうじゃ死んだカメの甲羅を占いに使うらしい。だが生きてるカメの方が面白いとか、そんな感じの意味だった――」
「また変な本を読まれましたね」
「それで、きみも事件の資料には目を通したんだろう?」
「まあ、はい。被害者はハンガリーのビザで渡航していました。期限は切れていましたが」
「就労ビザか?」
「通過ビザの方ですね」
アリッサは顔をしかめた。「マフィアのやり口ですよ。団体で申請して、通りすがりの国で移民をぽろぽろと落としていくんです。目的地に着いた頃には誰も残っちゃいない」
「例の店も、監視が付いていたようだが」
二冊目のファイルには政府のエンブレムが捺印してあった。要注意団体のリストだ。
「以前、クーデターを計画した協会がたむろしていたそうです。ほら、前国王の……」
「ああ。覚えているよ。揚羽連盟とか」
軍人くずれや企業の出世コースから外れた奴ら、熱意だけの大学教授や行き場の無い青年のたまり場だった。長く協会設立ブームが続いていると、どうしてもしょうもない連中が出てくる。
「被害者は四人目、妖精はこれで二人だね」
ウィルドは席を立ち、コルクボードの地図にピンを追加した。
一人目は駅の荷下ろし係だった。二人目は牛乳配達員で、三人目と四人目は娼婦。
「ここ二件は事件現場がかぶっているが……」
「模倣犯の可能性は?」
「いや、同一人物の犯行だ。刺すときの構えがぴったり一致していた」
むむ、とアリッサはうなってぴんぴんとヒゲをしごいた。今朝は珍しく毛づくろいする余裕があったようで、三角形の耳がつやつやと灰色に光っている。
「犯人はどこかの労働者でしょうか」
「フェンシングを習得するのはむしろ事務方だな。それも暇な金持ちの。あとは退役軍人あたりか……専門に訓練したやつかもしれないが、それにしては身長が低すぎる」
「金持ちが自分で殺すとも思えないのですが」
「本人には狩りのつもりなのかもしれん」
ウィルドはペンを持って、「金持ち?」と地図に書きつける。
それから少し考えたあとで、「女?」と付け足した。
「女性ですか」
「娼館の桶が使われてなかったんだ」
ウィルドはくちばしをこつこつと叩いた。
「ぬいぐるみみたいに抱くだけで終わって、剣で壁ごとつらぬいた。酒場のマスターの証言は?」
「あ、はい。ここに……」
ぱらぱらと別のファイルがめくられる。警察から寄越してもらったコピーだ。
「かすれた声の背が低い男。着込んでいて顔の造作は分からなかった、と」
「声はタバコやヘリウムガスでいくらでも細工できるし、夏場に着込むのは体型を悟らせないためだろう。やはり私は女だと思うね」
「靴のサイズが出れば多少は分かりますが……四件目ともなると警察連中も慣れたもんですね」
「いつものことだ。慣れ始めたころには手遅れになっている」
ウィルドはレモネードの瓶を傾けながら考える。
殺人という作業には多大な労力を要する。ゆえに戦場の新兵には上官の号令が不可欠となり、街中のシリアルキラーはストレスから逃れようと自作の美学にすがる。
今回の犯人は、移民から妖精の娼婦へとターゲットを移した。
そこに法則は見当たらないが、気まぐれで片付けるには手口が一貫しすぎている。
「……正教じゃないな、犯人?」
「警察は過激化した保守派の線で捜査しているそうです」
アリッサもウィルドの隣に立って、地図のピンを撫ぜた。刺してあるメモはドイツ語だ。
「これまでのところ、被害者の勤め先はすべてラテン記法の文書を採用しています。新市街の警備を強化するという件については?」
「クレイヴン顧問どのからじきじきに伝えられたよ」
「いつもながらあのイギリス人は口が軽くて助かりますね」
このドイツ娘はときどき、あけすけに正直すぎると思う。
「まあ、今度のガサ入れは劇場だ。キリル文字の看板が入った店に『突き刺し魔』は現れんだろう。我々にはいい休み時間というわけさ」
ウィルドが別件の資料を引き出すと、アリッサは席を立って「飲み物を」と言った。
「レモネードは二本買ってあるよ?」
「コーヒーが欲しいんです。ちょっと占いがしたい気分なもので」
「あ、そうかい……」
彼女がトルコ式コーヒーの粉で運勢を見るあいだに、ウィルドは判事に送る資料をふたつばかりやっつけた。三件目からはアリッサも本腰を入れてきて、なんとか定時までに本日のノルマが片付いた。
万引き、強盗、痴話げんか。『突き刺し魔』がいなくたって、この町はただでさえ騒動で溢れている。御者が言った通りだ。違いは注目されるか、されないか。それだけ。
「忙しい一日でしたね」
そう伸びを打ったアリッサに、ウィルドは苦笑を返した。
「いつものように、な」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
