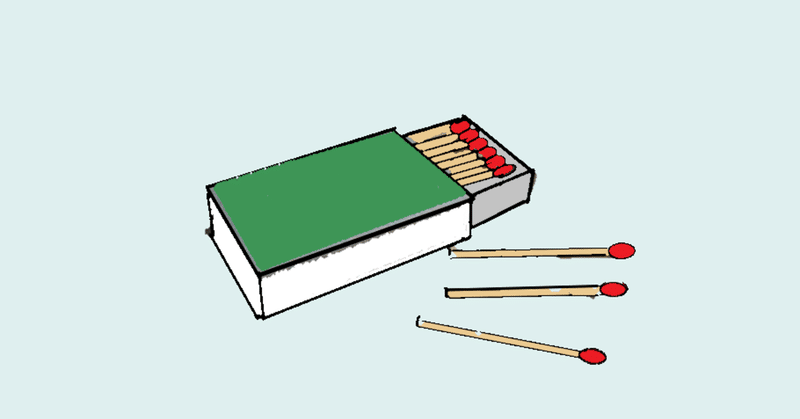
らぶりー④(終)
ドライブの日から一週間、オミからの連絡はなかった。
こちらから送らないから返ってこないのだ、とスマートフォンのスリープモードを解除して、何度も指を泳がせて、再び画面が暗くなるまで待つことを繰り返した。言葉を探しているわけではなかったし、ましてや言うべきことが分かっているわけでは決してなかった。それをするたびに胸のあたりで走る鈍い痛みのようなものを求めての自傷行為でしかない。
想いを言葉にできないのならば直接行動すればいいのだとは思うのだが、マイの足は動かない。正確に言えば決意した一歩目から動けなくなる。自分から相手を追うのは、ハルに対してマイができなかったことじゃないか。
そうしたわけで『会えない?』とLINEのメッセージ欄に書くのも、マイにとっては決死の思いだった。書き終わってから送信ボタンを押す代わりに消してしまおうかとも思ったが、やめにした。ただ、脳裏によぎったものに従って『会いたい?』と文章だけ変えた。クエスチョンマークが不恰好に感じられた。
ナミさんはどんな風に誘ったのだろう、それとも誘われたのだろうか。マイは見たこともない女性の姿を想像したが、その隣にいたのはどうしてかハルだった。
送信して程なく返事がきた。握ったままだったスマートフォンにかぶりつくように顔を寄せる。
『会えない』
マイは深呼吸をした。どう返そうか考えているうちにオミがメッセージを追加した。
『入院してる』
「は?」
どういうこと、と聞くと『階段で転んじゃって派手に足折った』と返信がくる。ギプスが巻かれた右脚の写真も送られてきた。いかにもなんでもなさそうな調子だったが、これは文章から感情や表情がこぼれ落ちてしまっている類のものではないだろう。オミは恐らく、全て素のままだ。マイは深いため息を吐いた。
――義理で来てくれるわけか?
『お見舞い行く』と打ちかけたところでオミの声が聞こえた気がして、指が止まった。何もかもマイ自身で作り出したものだとは重々承知はしていたけれど、固まってしまう。例の細い煙草を加えながら、皮肉気に笑うオミの顔が、瞳が、スマートフォンの画面の向こうに鮮明に見えた。
声にならない音を喉のあたりで鳴らしながらマイは『一応』と言いたくもない枕詞を置いてオミから病院の場所をどうにか聞き出した。少し離れた土地の大学病院だった。物理的な距離よりも、心理的な距離として遠かった。車があっても行ける気がしないくらい。
こうする、こうしたいも何も言わずにやり取りを終える。枕に顔を伏せた。
そうしたわけだから翌日、エリコに「そういえば例の人とどうなったの」と水を向けられた時にはマイは明るい声色で「終わっちゃったっぽい」と答えていた。
平日夜の繁華街だった。仕事終わりの先輩を労えと自分で言って、エリコがマイを呼び出してきたのだ。こういう風にぐいぐい引っ張っていく人についていってしまう人間なんだな、と自身に情けなさを感じながらもやはり嬉しく、マイは久々の気分転換にと誘いに乗った。対面で話すのは久々ということでお互いの近況を話しているうちに、先ほどの質問がエリコの口から出てきた、という流れだった。
エリコは「ぽいってなんやねん」とのけぞった。昔からよくやっていたオーバージェスチャーだが、びしりと決めたスーツ姿でやられるとやたら滑稽に見え、マイは思わず噴き出してしまった。サラリーマンのコスプレをするように髪型を変えていたハルとは違い、エリコは髪色も髪型も大学生の頃と大して変わらなかったが、それ故にこうしたちょっとしたところでの差異がマイには目立って見えた。少し、眩しくさえある。
「掘り下げていいやつ?」
「全然いいですよ」
体勢を立て直しながらエリコが問いかけてきたのにマイは笑いながら返す。しかし、エリコの言葉は「じゃあねえ……」以降は続かなかった。しばらくマイの顔を見つめた後、誤魔化すように大声でビールを注文する。店員が離れるとエリコは「そういえばさ」と話題を切り替えた。
気を遣われた、という悔しさがマイの中に湧き上がる。自分の顔にどんな表情が浮かんでいるのか、最早マイには分からなかった。
取り止めもない話を取り止めもなく続けているうちにラストオーダーの時間がやってきた。エリコが「奢ってあげましょう」と言いながら伝票を持って立ち上がる。マイは「ありがとうございます」と怪しい呂律で言いながら荷物を持ってレジへ向かう。追いついた時は既にエリコは鞄に財布をしまっていた。
「おっ、いいねこれ。可愛い」
エリコがレジ台上のマッチ箱をつまみあげる。この居酒屋オリジナルのキャラクターなのだろう、猫がポップな絵柄でジャケットに描かれたものだった。
「そんなのもらってどうするんですか」
煙草吸うわけでもないのに、とマイが続けるとエリコは「吸うよ?」と懐から箱を取り出した。白地に真ん中に赤い丸が書かれたデザイン、マイの知らない銘柄だ。
「吸ってましたっけ」
「社会人になってからね」
ストレスで、と冗談っぽく笑ったあと「職場の先輩がヘビースモーカーで、その影響」と続ける。
「結局こういうの、周囲からの影響だよね」
店を出て、駅へ向かって歩く。気温は低いはずだが、マイの体は熱いくらいだった。飲みすぎたな、と反省しながらエリコの話へうんうんと頷く。
「友達、喫煙者誰もいないからさ」
「まあ、今は、そうですよね」
酔いのせいだろう。マイはそう口走っていた。
「今は?」
「ナミさんは吸ってたんでしょ」
マイがそう言うとエリコは立ち止まった。
「いや、吸ってなかったけど」
「えっ」
構わず足を進めていたマイも、ここで歩みを止めた。
「むしろ煙草は嫌いだったかな、あの子。なんでまた」
「でも……」
言いながら、マイは自分の身体が急に冷めていくのを感じていた。オミの声が頭の中で聞こえる。今度は、ちゃんと本人が言っていたやつ。
――俺さ、寂しがりやなんだよね。
「あの馬鹿……」
マイの口から、言うべき言葉が漏れた。
何の話か分かっていないエリコへ、マイは手を差し出した。
「エリ先輩、車、持ってましたよね?」
「持ってるけど……」
「貸してくれません?」
エリコは「乗るの?」とまだまだ上気した顔色のマイの顔を指す。マイは首を振った。
「今日じゃありません」
翌日の午後、マイは病院の駐車場にエリコの車を入れていた。ハンドルに片手を当てながら気持ちを整えたあと車を降りて、嫌になるほど真っ白な建物の中に入っていく。面会受付で、芹生孝臣という初めてまともに口にする名前をスタッフへ告げて、エレベーターに乗った。
病室は三階のエレベーターホール近くの四人部屋だった。オミのベッドは右奥らしい、と名札の位置を確認する。ドア越しにも聞こえてくる会話の声に気圧されそうになったがどうにか堪えて、踏み入った。
他のベッドの病人と見舞客には目もくれず、逆にあちらからも一瞥もされずに、マイはずんずんと進んでカーテンを開けた。いた。
ギプスを布団の上に投げ出すように座って、窓の外を見ていた。その脚と、セットされていない髪が風に揺れて普段より艶やかに見えた他は、いつも通りのオミだった。当たり前だ。最後に会ってから一週間ちょっとだ。
オミが振り返る。
「あのさ」
オミの表情を見てしまう前にマイは先制攻撃をする。抱えた紙袋へ手を突っ込んだ。手渡す。
オミは一瞬、それが何か分からなかったようだ。「ああ」と呟いて掌の上で弄ぶ。土埃でフィルムが薄汚れた、メビウスの箱。
「お供えとかじゃないならこれ、不法投棄だから」
オミが顔を上げた。
プレゼントをもらった子供みたいに、緩みきっていた。マイはため息をつく。今日は、自分が今どんな顔をしているのか分かった。
「ごめん」
オミは箱をマイの手へ押し戻した。
「じゃあ、ちゃんとしたところへ捨てといてよ。吸わないから」
「禁煙だから?」
オミは、嬉しそうに首を振る。
窓の外から冬の風が急に強く吹き込んできて、オミとマイの体を通り越し、背後、騒がしいドア横のベッドの方へ抜けていった。
「二人きりだから」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
