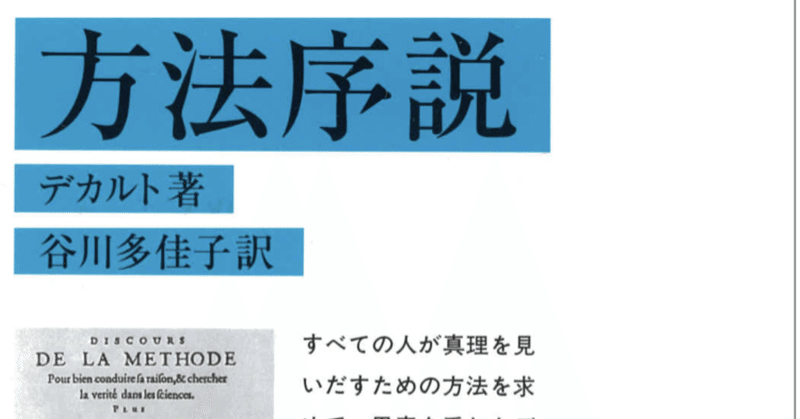
最近読んで面白かった本。『方法序説』デカルト
「我思う、故に我あり」で有名なデカルトの本を読んだ。
1行でまとめるなら、
「合理性について書かれた不合理な本」
って感じか。アツくて面白い本だった。
中でも面白い点が2つあった。
1つはもちろん「我思う、故に我あり」という真理に関する部分。
もう1つは、その真理に到達するためにデカルトが行った修行パート。
まずは修行パートから触れていく。
デカルト修行編
疑いようのない原理を打ち立るっていう難事に取り掛かる前に、まずそれに耐えうる自分を作ろうということで、修行パートが始まる。
修行に際して、デカルトはいくつかのルールを設定して、それに従うことにした。
真理を探究できる様になるまでは、暫定的な真理に身を委ねていようっていう判断だ。
デカルトってラジカルな完璧主義人間のイメージだったけど、意外と地に足ついてて面白い。最初からベストを目指すと絶対コケるから、まずはベターな選択を。
もしくは、一歩目で山頂を踏むのは不可能なので、そんなことを考えるより、まずはとにかく一歩進むために足を踏み出す。(#1)
#1 一歩目で山頂を〜
かつて、そんな様なことを教授に小1時間かけて説かれた覚えがある。「タカギ君、」と。
先生、教えは全く身に付かなかったけれど、僕は元気にやっています。
ルールは以下の通り。
1.「自分の国の法律と慣習に従う」
自分の周りにいる人が従っている穏当な意見に従うのが丸い。
2.「どんなに疑わしい意見でも、一度それと決めたら一貫して従う」
森で迷っても、一直線に進めば抜け出せる。望んだ場所には着かなくとも、とりあえずどこかには行き着く。
3.「世界を変えるよりも自分の欲望を変えるよう努める」
これ仏教的だよな。
ここで大事なのは、あくまでこれらはいつか棄却する予定の、暫定的な格率だということ。
従うことが主目的ではなく、あくまで原理を探る準備として従っている。
そして彼は旅に出て、さまざまな事柄について反省をしていった。
しかし、だからといってわたしは、疑うためだけに疑い、つねに非決定的でいようとする懐疑論者たちを真似たわけではない。それどころか、わたしの計画は、自ら確信を得ること、緩い土や砂を取りのけて、岩や粘土を見つけ出すことだけを目ざしていたからだ。
確実なものを見つけるために全てを疑う。これかっこいいよな。こういう逆説的なモチベーションの主人公大好き!(#2)
#2 そういうモチベーションの主人公の例
・ドラマ『TRICK』の山田
父を殺した本物の霊能力者を探し出すために、自称霊能力者達のインチキを暴く。まるっとお見通しだ!
・小説『アメリカ最後の実験』の主人公
音楽がただのゲームではないと信じたいがために、あえてゲームとして音楽を行い、それが通用しない世界を探す。
我思う、故に我あり
「『我思う、故に我あり』って結論じゃなかったのか!」というのがこの本を読んで1番の驚きだった。
てっきりラストに「我思う〜」っていうタイトルをズバンと出して終わる、『ゼログラビティ』(#3)的な構成なんだと思っていた。
#3 『ゼログラビティ』(原題:Gravity)
崩壊する宇宙ステーションから脱出するSF映画。ラストで主人公が地上に降り立った後、映画全体の総括として「Gravity」というタイトルを出して終わる。
これは無重力の宇宙の話をしているようで、実はずっと重力の話をしていたんだという、クソかっこいい終わり方。
最後にタイトルを出す映画だーい好き!
(そしてその構成を台無しにする『ゼログラビティ』という邦題😡)
しかし、「我思う〜」は結論じゃなくて、足がかりだった。
デカルトが「我思う〜」からどうやって理論を展開するかっていうと、「我思う〜」がなぜ成立しているのかを考え、その成立条件を真理の条件にした。
その推論を短くまとめると次の様になる。
◇
「我思う、故に我あり」が真理たりうる根拠は「それが明確に正しいと分かるから」っていう一点しかない。
↓
じゃあこの世の全ての真理の判別方法は、それが明確に正しいと理性によって分かることだ!
◇
つまり、真理の条件は、それが論理的に正しいこと。
論理的に正しいことが真理である、って意見がラジカルなものであるとされた時代ってすげーな。
そして、結論はともかく、何じゃその推論はって思うけど、こんな無茶が通るのはデカルトが信じていた公理が前提になっているから。
その公理とは、全てにおいて完全な神が存在しているということ。
しかし、デカルトは神の実在を前提に真理の定義を決めた一方で、その真理の定義から神の実在を証明している。これは循環論法になっている。(#4)
#4 循環論法
ループしちゃって意味をなさない論理。
「論理的に考えて神は存在する。そして神は論理の正しさを担保している」←これは論理として成立してない。
論理的に成立していないのは一旦置いておいて、このデカルトの思考にはかなり親しみを感じた。
本人は至って合理的な思考だと思っていても、そのベースには信仰という思考以前の型が置かれている。
とても人間らしくて良いと思う。

全てに意味なんてないんだから、合理的に何かを成そうとするときにはまず、意味のないところに意味を見出す不合理が必要になる。(#5)
デカルトの場合、それは神への信仰だった。そしてその不合理をなんとか合理化しようとした結果、循環論法という形で不合理が噴出してしまった。
というような感想を抱いた。
論理について説いた、現代の合理的思考の礎みたいな本なのに、その論理は不合理によって生み出されている。これめちゃめちゃ面白くない?
人間!って感じのする熱い本だった。
#5 全てに意味なんてない〜
例えば生き方について考えると、「合理的に、無駄を省いて、完全に正しい道だけを生きていきたい」という人は、即座に死ぬしかない。
まず自分のやりたいことは何かということを決めてからじゃないと、合理的な進み方もクソもないからだ。
そして、やりたいことを決める際には合理性は役に立たない。なぜなら、社会的に成功したいだとか、幸せになりたいだとか、そういう価値基準自体には正解不正解はないからだ。
合理性は価値基準の内部にしか存在しない。
余談
この本を読んだのと同じ頃に
・『世界はなぜ存在しないのか』
・『世界は関係で出来ている』
という、それぞれ哲学者と物理学者が書いた本を読んでいた。
一見対照的なことを言ってる2冊だけど、どちらも遡れば、合理的思考の礎を作ったこの本に行き着くんだな、と感慨深く思った。
「この3冊を同じタイミングで読めてラッキー!」って感じ。
↓『なぜ世界は存在しないのか』の感想
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
