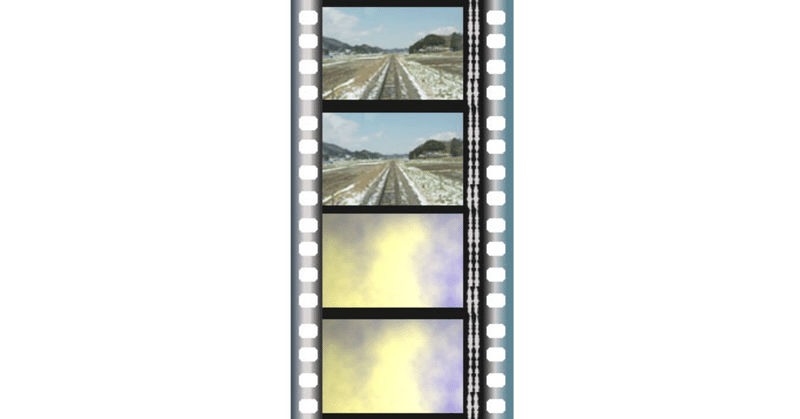
1980年の映画監督No.11
2.天国と地獄③
以前、この「眠れる美女」を制作しようとした時は、アカマツがプロデューサーで、ビーグル犬と蓄音機が目印の音響設備の老舗が出資を決めていたが頓挫した。すでに、アカマツは東京にはいない。その後、自身のプロダクションもふるわず、たたんでしまった。“カントク”と同郷である福岡県の北に位置するI市に、家族もろとも引き込むことをアカマツは決意した。山田は、アカマツの多摩川沿いの公団住宅の自宅を引き払う時に手伝いに行ったが、“カントク”は会うこともなかった。しかし、どういうつもりか、100万円を銀行の封筒に入れ、山田に持たせた。アカマツは黙って受け取った。幼なじみの俺にこれっぽっちか、と思ったのか、照れたように口元を緩めただけで、何も発することはなかった。ありがたくないはずはないが、意外に驚く表情もないので、当たり前とでも思ったのかもしれない。
今回のプロデューサーのコガさんは、出資する会社を探し、資金面を固めたが、現場を仕切れるプロデューサーではない。“カントク”は、はなっからアカマツに任せようなどと思ってもいなかった。あるいは、呼び戻せば、アカマツは喜び勇んで出て来ただろう。しかし、“カントク”はそんなことはしない。すでに、縁も、気持ちもなくなった相手に再び手を差し伸べることはない。
“カントク”が、旧知の美術監督に相談すると、シロイの名前が上がった。日活製作部出身で、今は制作プロダクションを持っている。アカマツと変わらず、下請けの制作会社だが、請けている作品はヒット作ばかりだ。シロイにヒット作は請け負いの制作会社には金銭的な恩恵はもたらさないものの、制作プロデューサーとして名を上げ、人脈も映画会社首脳陣や振興の製作会社のエグゼクティブプロデューサーと呼ばれる人たちからは絶大な信頼を得ていた。面識はないが、シロイさんにやってもらえるなら、と“カントク”はコガさんを斥候に口説きにいかせた。シロイは首を縦には振らなかった。あまり、自分のハタケではない人脈と現場にはかかわりたくないのだ。ヒット作を量産できる制作体制は自分の身内で固めることにある。多くがはじめてのスタッフの現場を仕切っていられるほど暇ではないのだ。しかし、何度かコガさんが頭を下げて頼むと、受けてくれた。根はヒトがいい。コガさんという実直な人柄につい首を縦に振ってしまったのだ。しかし、わずかではあるが、ほとんど個人で企画から制作まで立ち上げる“カントク”のやり方も、この機会に見ておくのも悪くない、と感じたかもしれない。
そのシロイが、最もよくわからない、やったこともない映画制作の方法論を“カントク”に見せつけられる。エキストラに労力をかけてどうしようというのか。素人を使えば、それだけ現場のリスクは上がる。太ももの女子大生のこと。現場をまかされている以上、勝手なことをされても困る。シロイの本音だ。出来ればやめてもらいたい。“カントク”はシロイに止められればやめたかもしれない。結局、自分の首を絞めかねないからだ。しかし、シロイはこんな条件を出した。親御さんに会って、OKをもらうように。
あるいは、許可が下りないことを期待して、歪曲にそう“カントク”に言ったのかもしれないが、“カントク”は親に許可をもらうなど考えてもいなかった。
現場いっさいを任せた制作プロデューサーのシロイさんに”カントク”はそう言われ、女子大生の両親に会うことを決心した。この頃は、まだ威勢もあるし身なりもちょっとしたブランド品できめていたシロイは、“カントク”一人じゃ心細いだろうから、山田お前も行け、と促した。
太ももは、何度か、何日にも渡って“カントク”が確認するも、OKした。裸だろうが何だろうか出てみたい、と言っている。見上げた女子大生だ、と“カントク”は感想をもらした。山田は、あまり深く考えていないだけではないか、と訝しがった。
18歳とはいえ、親の許可がない限り現場プロデューサーとしては承服できないのだ。本人を口説く以上に緊張し、気が重かった。
父親は絵に描いたような会社勤めの人でだった。その時、山田は土下座でもしてお願いしたような記憶があるが、それは違った。そのような心境だったのだろうか。“カントク”と並んでソファーに腰掛け、父親が正面に、母親は奥のダイニングテーブルに当の本人と並んで座っていた。
「本人がどうしてもやりたいというものを…」と、父親はポツリと言う。我々にちゃぶ台をひっくり返すわけでもなく、もちろん怒鳴り散らして塩をまくでもなく、穏やかに、きわめて紳士的に、対応した。できれば、娘にそんな映画になど出てはほしくない、そう思っても、無碍に反対するわけにもいかず、といったところか。いや、もしや女優にでもなってしまうのか、などと淡い期待もあったかもしれない。そこが返って気の毒である。女優などにはなれません。“カントク”の趣味みたいなものです。気に入った子を脱がせたいだけなんです。結婚を申し込むより容易く、罪深いと言わねばなりません。映画という大義名分と、その実態があやふやな、産業のような芸術のような文化のような性産業のような、そんなものを振りかざしていて、遊びのような、猥褻な、不埒な、隠遁な、犯罪のようなことを平気でします。その証拠に現場プロデューサーのシロイさんは、素人に出てもらったほうがタダでいいかもな、と最初は反対していたものの金銭的観点から少し期待していたのだ。
気の毒な父親から了解をもらい”カントク”は意気揚々だっただろうか。いや、なんとも居心地の悪さを感じてはいた。が、あの子でいきたい、という強い思いに変わりはなかった。
撮影の当日。山田は、早朝の住宅街の一角に車を止めていた。凝視していたバックミラーに太ももの姿が写った。パンツ姿だった。考えてみると山田は彼女の太ももを見た記憶がない。女子大生は車の助手席に座るなり、白い息をふぅーと吐き出しこう言った。
「やっぱりできなくなりました」
予想はしていた。
念のため確認をする。
「できないって、映画に出ることですか?」
「はい」
「どうしてですか?」
「彼がダメだって」
彼氏がいたのか、と山田は愕然とした。不覚であった。父親だろうが母親だろうが、“カントク”は説得することはたやすかった。しかし彼氏の存在を消し去り何食わぬ顔で出演を許諾していた太ももの存在に、ここへきて彼氏がひょっこり顔を出してきた。今の短大生に彼氏がいないわけはない。彼氏にも相談したのか、と一言聞いていればこんなこんなことにはならなかった。太ももも彼氏を甘く見ていたのだ。自分がやりたいことに同意してくれるはずであるとでも思ったのか、あるいは彼には内緒で出演してしまうつもりでいたのか。昨夜は、彼と言い合いにでもなったか、少し眼を腫らし、寝不足気味の表情を見せた。
“カントク”が直接女子大生迎えに来なかった理由はここにある。ホテルにまで足を踏み入れたというのに、やっぱできません。と断られているのと同じことである。その場に“カントク”が居合わせた時のショックは計り知れない。もっとも撮影真っ最中に監督自ら出演者を迎えに行く時間などないが。
太ももの太ももが自分には見えなかったのだ、と山田は思った。
山田は深追いはしない。黙って太ももを車から降ろす。凍り付くような外気に体をすくめ心細そそうに立つ太ももにどこにそんな魅力があったのだろうかと思う。逃がした魚にもはや未練はない。
帰り際、現場に報告の電話を入れた。もしものための保険。どうあれその日の撮影ができるように代わりの女性は用意してある。脱ぐための女優が型通り脱いで撮影は進められる。“カントク”の意に沿わない撮影が進行するのだ。
“カントク”の恋は終わったのである。無聊を慰め、撮影に没頭しているだろうか。
山田が戻ってきた撮影現場は、今の時代珍しくアフレコだ。撮影中に俳優の声や音は録らない。撮影後にアフター・レコーディング(アフレコ)して声を録る方が安く上がると現場プロデューサーのシロイの決定である。そのためキャメラが回る音も消音する必要がなく費用は抑えられるというのだろう。
“カントク”は、準備期間ではいざ知らず、撮影に入ってしまうと画にこだわってはいられない。こだわりすぎて撮影が延びることは、自分の首を絞めることになるからだ。
かつては、西の重鎮の映画に憧れ、1本目の痴漢の青年を題材にした作品では、そっくりそのまま西の重鎮のお抱えのスタッフを付けようとし、キャメラマンと編集マンは、その通り踏襲できたものだった。
しかし、今は画にこだわりはない。ないことはないだろうが、自分から声を発してその類いを示すことはない。
むしろ裸だ、と言わんばかりの演出を多く言及した。それは歳とともにその傾向を強くしたというわけではない。時代がそうであった。映像的なことより、映画の仕掛けにこだわりが出てきたと言えるかもしれない。
撮影に入る直前にシナリオにはないレズシーンを入れたい、と“カントク”は言い出した。館の女将とその使用人の若い女の、である。シナリオにはないので、その出演者二人には、撮影前には伝えていたが、どうも納得が言っていない。それを飲み込ませるために、撮影は止まっていた。
本当にレズシーンが必要なんだろうか、とスタッフも俳優陣も思っている。それを演じる当の二人は尚更だ。
膠着状態の現場で、山田はステージの外にいたキャメラマンに午前中の撮影について聞いた。
「指を口の中に入れたり出したりしてさ、なんかポルノになっているよ。これ文芸映画じゃないの?」
口元のアップを撮るとき、添い寝の老人がもてあそぶ様子を、“カントク”が自分の指を女優の口に入れたり出したりして撮影したのだ。それをキャメラマンがぼやいたのだ。裸体を引いた絵で撮りたくないのだ。気に入らない裸をみせるよりアップでごまかしているのだ。ついでに、ムシャクシャするから、指でも出し入れして欲求を解消しているのだ。
本来は太ももで撮りたかった“カントク”は代役での撮影になげやりになったようだ。その穴埋めに午後はレズシーンで気分を盛り上げたいところだったが、俳優もスタッフも唐突なレズシーンに懐疑的で、なによりも俳優が乗れないため、一時撮影は中断してしまったというわけである。
とはいえ、中途半端なレズシーンを何とか撮り終えtwこの日の撮影は終了した。
さて、「眠れる美女」だが、文芸映画といえども、“カントク”は撮影に当たっては、過激な戦略を用意していた。その頃流行っていたヘアを堂々と見せること。
“カントク”は、当時流行った映画「氷の微笑」を非常な興奮を持って見ていた。椅子に座った主演女優が足を組み直すところである。はっきりとは見えないものの、下着を身につけていない股間をカメラに収めたのである。対峙する主演男優を挑発した行為なのだが、あれを狙いとして演出することと、その撮影を受け入れる主演女優に“カントク”はまいってしまったのである。
“カントク”は、「眠れる美女」制作にあたっては、このヘアに挑戦し、当然その映画の上映を阻む映倫と、とことんやり合うことを声高に語っていた。
撮影でも随所にヘアを撮っていた。
「大丈夫なの? こんなに撮っちゃって」とキャメラマンは常に懐疑的であった。
「バンバン撮っちゃって下さい!」
しかし、“カントク”は、ある種ジレンマに落ちると簡単に公言を撤回する。映画が出来上がった後のこと。映倫が首を縦にふるはずはないのである。映倫マークがないことには映画が上映できない。映倫の息のかからない興行協会以外で過激に上映するという手もある。現にそれも“カントク”は公言していた。いわゆるテント上映みたいなことである。しかし、出資しているテレビ局との契約、また興行を行うことを前提としてビデオグラム契約をむすんでいる大手映画会社のビデオ事業部。これらの会社とは劇場で公開する映画という契約を結んである。そこに背くことはできない、と“カントク”は早々に映倫の言いなりになったのである。あるいは、2社を説得して、映倫の息のかからない上映を行うこともできたかもしれない。テレビ局にしても、ビデオ事業部にしても、話題になれば、それだけ収益に繋がるかもしれない、という打算は働くからだ。ビデオ事業部の次長は、ヘアを出す、と“カントク”が制作前に言ってたから、けっこうなビデオグラム化権料を支払ったのに、と憤慨していたほどだ。
しかし、“カントク”はそうはしなかった。痴漢をする青年を題材にした1本目の監督作品は、形は違えど、そういう過激な発想が話題を呼びヒットしたのである。今回、“カントク”がそうできない理由は、金の重み、であった。テレビ局、ビデオ事業部と並んで自分のプロダクションからも出資をしている。それを回収しなくてはならない。その重み。これが決定的であった。あの”カントク”が、すでに攻めの姿勢を崩してしまっていた。
ヘアが映るショットを全て切ってしまい映倫マークをもらった川端康成原作の映画「眠れる美女」はその年冬があけようとする頃調布の日活スタジオセンターで仕上げを行った。ヘアを映さないショットを撮るなら、あのようなサイズ、画角で撮らなかったであろう。キャメラマンも苦々しく思い、編集マンも苦労したはずだ。山田は、イタリア映画で戦時中の検閲でラブシーンがことごとくカットされ、後年、映写技師がラブシーンだけを繋げて、感動的なシーンを作り上げた映画があるが、カットしたヘアだけをつなげれば、それに劣らぬ秀逸な一編が出来そうだと思ったが、カットしたヘアショットを編集助手からこっそりもらうことはしなかった。
調布駅のロータリーの車の中。山田は朝のニュースで地下鉄に原因不明のガス漏れが発生し乗客が次々に救出されていることをラジオから聞いた。プロデューサーのコガさんさんを迎えに来ていたが、コガさんさんは行徳の方から地下鉄を利用して調布に来る。ガス漏れと報道していたその官公庁がひしめく地下鉄の駅を越えて来ることになる。が、コガさんさんは1本か2本遅い電車に乗っていたため難を逃れた。やがて、それは日本を震撼させるような事件になっていったが、山田たちは仕上げに追われることとなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
