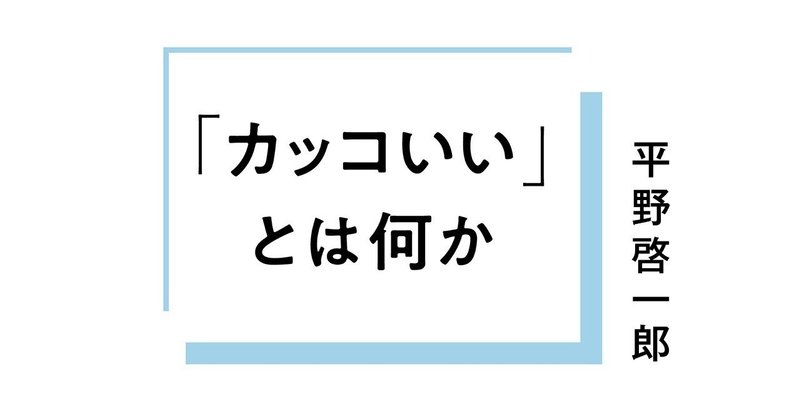
新書『「カッコいい」とは何か』|第3章「しびれる」という体感|4何が「カッコいい」のか?
一旦、それに「しびれる」経験をしたあとで、反復的にその「カッコいい」ものに触れ続けることによって、恐らくは生理的興奮の回路が出来、ますますのめり込んでいくのだろう。それが、ファンになる、ということかもしれない――。平野啓一郎が、小説を除いて、ここ十年間で最も書きたかった『「カッコいい」とは何か』。7月16日発売に先駆けて、序章、終章、そして平野が最も重要と位置付ける第3章、4章を限定公開。 「カッコいい」を考えることは、「いかに生きるべきか」を考えることだ。
※平野啓一郎が序章で述べる通りの順で配信させていただきます。
「全体のまとめである第10章にまずは目を通し、本書の肝となる第3章、第4章を理解してもらえれば、議論の見通しが良くなるだろう。」
4.何が「カッコいい」のか?
「経験する自己」の生理的興奮
さて、「しびれ」と「美の多様性」を巡るこうした議論は、当然のことながら、「カッコいい」について考える上でも、重要な示唆を与えてくれる。
私たちは、一体、クリスティアーノ・ロナウドとマイルス・デイヴィスとスポーツカーには、同じように「カッコいい」と表現されるべき共通点があるのかと問うてきたが、それは、この生理的興奮に他ならない。
ピカピカのスポーツカーを見た一九六〇年代の少年も、武道館の矢沢永吉のコンサートに行ったファンも、いずれも、鳥肌が立ち、「しびれていた」のである。
そして、かつては「カッコいい」と思っていたのに、今ではもうそう思わない人や車は、体で感じるものがなくなったという意味である。
「こんまりメソッド」でアメリカで大ブレイクした〝片づけコンサルタント〟近藤麻理恵は、自宅に溢れ返っているものを捨てるかどうか迷った時に、それを手にして「ときめく」かどうかを重視しているが、これはまさに体感主義に他ならない。
小難しい理屈ばかりの現代アートに、「これのどこが芸術なのか⁉」と腹を立てるのは、それを前にしてもまったく「しびれない」時である。また、お勉強の成果を並べ立てるだけの批評家の言葉にイライラさせられるのは、彼らの芸術体験の根本に、こうした生理的興奮が欠落していて、新しい表現をまったく受け止められていない時である。
しかし、美の場合と同様に、個々の「経験する自己」の生理的興奮は、実は、「カッコいい」という言葉に一元管理されるべきものではなく、「物語る自己」は、もっと違った情動と解釈すべきだったのかもしれない。
イギリスのHR/HMの一源流であるブラック・サバスというバンドは、当初は別の名前だったが、デビュー前にホラー映画『ブラック・サバス』(一九六四年、マリオ・バーヴァ監督)を見て、人に恐怖感を与えるロックという斬新なコンセプトを思いついた、という有名な逸話がある。
実際、《ブラック・サバス》(一九七〇年)という、バンド名と同名の曲は、暗く虚ろな不協和音と重低音のリフ、サタンに追われる恐怖を綴った歌詞が一体となって、何とも言えない、ゾッとするような雰囲気を醸し出している。
ブラック・サバスは大ブレイクしたが、しかし、なぜ恐い音楽が、「カッコいい」と熱烈に支持されるのかは、合理的には理解し辛いところがある。
この時、「経験する自己」の生理的反応は、一種の不安や恐怖だったのかもしれない。つまり、「吊り橋効果」で、観客を緊張させ、ドキドキさせていたのである。しかし、当の観客は、ライヴが終わったあと、他のキャッチーな曲やライヴハウスという環境、そもそもロックを聴いているという前提、メンバーのルックス、周囲の熱狂などから、その生理的興奮を、「カッコいい」音楽を聴いたからだと解釈し、あるいは彼らのファンになったからだと理解したのかもしれない。
「カッコいい」存在とは、私たちに「しびれ」を体感させてくれる人や物である、という本章冒頭の定義に立ち戻ってほしい。
勿論、楽曲自体が「ダサい」のでは、そのバンドも、ただ気持ち悪い人たちだと思われて終わりであり、実際、「吊り橋実験」も、途中にいる女性が魅力的ではない時には逆効果になるという。
ロックは、単純な音楽だと見做されがちで、実際に、譜面に起こせば、ジャズやクラシックの複雑さの比ではない。
しかし、いかに人に刺激的な快感を催させるか、という意味では、舞台の視覚的効果から会場の雰囲気、収容人数、ミュージシャンたちの振る舞い、言動、楽器の音色、ビートの勢い、ヴォーカルの生々しい肉声、メロディ・ライン、頭に染みついて離れないリフ、……など、様々な要素が緊密に結びあった非常に複雑な音楽である。重要なのは、その一体感であり、これは、ヒップホップでも、テクノでも、ファンクでも同様だろう。
ここで、「美」や「崇高」といった一八世紀以来の美学的概念と、二〇世紀の「カッコよさ」との関係を、改めて整理しておこう。
これまで本書では、美や崇高と「カッコよさ」とを、同列的に、対比的に論じてきた。しかし、実際私たちは、美しいものに鳥肌が立つこともあれば、崇高なものに戦慄することもある。それどころか、敏捷さ、華麗さ、大胆さ、率直さ、巨大さ、恐ろしさ、色気、……等、美術やスポーツ、対人関係の様々な経験を通じて、鳥肌が立つような生理的興奮を引き起こされている。
この「しびれ」の多様性こそが、それをもたらす「カッコいい」存在を多様化させているわけだが、だとすれば、「カッコいい」は、美や崇高の上位概念ということになる。逆に言えば、美や崇高は、今し方列挙した「しびれ」の複数的な要因の一つとして位置づけられている、ということである。
かつて私たちは、マイケル・ジョーダンの超人的なダンクシュートの「美しさ」に「しびれた」。そして、その生理的興奮をもたらしてくれた彼を(また、彼のプレーを)「カッコいい」と感じたのである。
理想像はあとからわかる
理想的なものを賛美する、という意味では、「カッコいい」も「恰好が良い」も同様である。
しかし、「恰好が良い」ものは、事前にその理想像が前提とされており、それとどの程度、合致しているかが問われる。和菓子職人の師匠の例を出したが、高級レストランで、そつのない振る舞いが出来るだとか、流暢な英語で外国人と会話を交わせる、といった日常的な振る舞いも、この「恰好が良い」であり、今日ではこれも「カッコいい」という言葉によって言い換えられている。
しかし、「カッコいい」ものの場合は、必ずしもそうではなく、非日常体験として、むしろ理想像は結果として、あとからわかるということがしばしば起こる。これが一九六〇年代以降に加わった新たな意味である。
日本やイギリスで、初めてロックの洗礼を受けた若者たちは、事前にこういう音楽が聴きたいという理想像を決して有しておらず、説明を求めても誰も答えられなかっただろうが、一聴して、「これこそ自分が求めていた音楽だ!」と発見したのである。だからこそ、幾らマーケティング・リサーチをしても、真に「しびれる」ような「カッコいい」ものは生み出されない。消費者自体が、それを知らないからである。
初めてラジオでエルヴィス・プレスリーを聴いた時のことを、ローリング・ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズはこう証言している。
「ある晩、ベッドで眠っているはずの時間に小さなラジオでラジオ・ルクセンブルクを聴いていた時、俺の中で爆発が起きた。《ハートブレイク・ホテル》だ。気絶しそうな衝撃。初めての感覚だ。こんな音、聴いたことがない。エルヴィスという名前さえ知らなかったが、俺の人生、まるでこの出会いを待っていたかのようだった。」(9)
今聴けば、決して激しい曲ではないが、その新しさの衝撃を全身で受け止めた感じが生々しく伝わってくる。
この何が何だかわからない未知のものに驚愕し、鳥肌を立てて夢中になる、という戦後のロック世代の体感主義は、一九世紀のボードレールのワーグナー体験と重なる。
こうした「カッコいい」存在は、何らかの理想を体現しているが、それは私たちがアプリオリに知っているものではなく、その人物なり事物なりが、出会いの「電気ショック」を通じて、初めて私たちに教えてくれる理想である。だからこそ、新しいものを受け容れられる一方で、実のところ、「物語る自己」は、それを状況的にわかりやすいものに勝手に結びつけてしまっている、という懸念もある。
そして、一旦、それに「しびれる」経験をしたあとで、反復的にその「カッコいい」ものに触れ続けることによって、恐らくは生理的興奮の回路が出来、ますますのめり込んでいくのだろう。それが、ファンになる、ということかもしれない。
私たちの多くは、十代の頃に衝撃とともに受け止めた音楽の趣味からなかなか離れられないが、それはこの回路に捕らわれているからではあるまいか。
人格か、エピソードか
勿論、仰ぎ見るようなスターだけでなく、「カッコいい」存在は身の回りにもいる。
中学生くらいの頃には、私も同級生の女子が、「三年二組の○○君、カッコいい!」などと噂し合っているのを耳にし、羨ましく思ったものだが、「カッコいい」男子がいるという評判は、当然のことながら、昼休みや放課後に、彼女たちに、彼を見に行かせることになる。
この時、実際に話題になっているのは、まずは「カッコいい」というより、「格好が良い」ということではあるまいか? つまり、足が長いだの、目鼻立ちがハッキリしているだのといった理想的な容貌が思い浮かべられていて、ハンサムと言い換えてもイケメンと言い換えてもいいのかもしれない。
しかし、そのサッカー部なり野球部なりの少年が、部活の練習で、見事なシュートを決めるのを目の当たりにした少女は、胸を高鳴らせながら「カッコいい!」と感じ、そのドキドキを、「これって恋?」と解釈するかもしれない。
彼がそんな運動神経の持ち主だとは、彼女は想像していなかっただろう。それでも、キース・リチャーズのように、「わたしの人生は、まるでこの出会いを待っていたみたい!」と、彼を理想のタイプと見做すことはあり得る。しかし、「吊り橋理論」によるならば、それは一種の誤解なのかもしれない。
実際に、私たちが誰かを好きになるきっかけは、相手の人格や外観というより、こうしたエピソードの中にある体感なのかもしれない。私の『透明な迷宮』という短篇は、この主題を扱ったものである。
しかし、一旦憧れが芽吹き、「これって恋?」と感じてしまったあとでは、幾ら「アンタがドキドキしたのは、シュートの華麗さであって、彼に対する恋心じゃないと思うよ。」などと説明されようとも、もう決して後戻りは出来ないのである。
脚注
(9)『キース・リチャーズ自伝 ライフ』(キース・リチャーズ 棚橋志行訳)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
