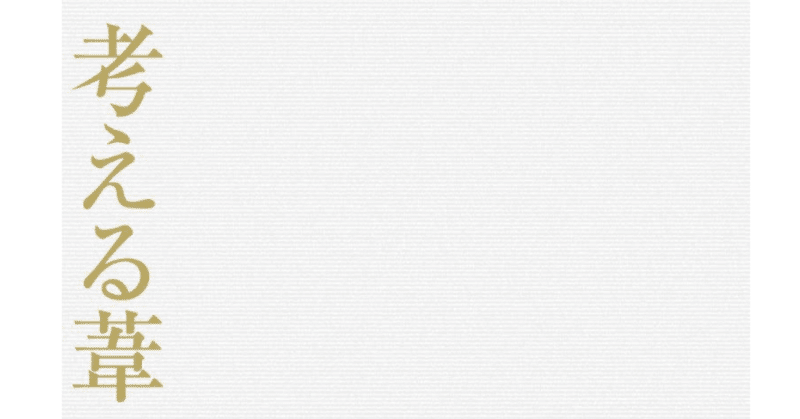
考える葦|I-20|〝我が事〟としての政治思想史
平野啓一郎の論考集『考える葦』(2018年9月発売 / キノブックス)より、『西洋政治思想史講義 ーー 精神史的考察』(著:小野紀明)の書評を公開しています。
主に、2014年〜2018年(それより古いものも)、第4期にあたる『透明な迷宮」『マチネの終わりに』『ある男』が書かれた時期の批評・エッセイを集めた論考集。平野啓一郎の思考の軌跡が読める一冊です。
(2018年9月発売 / キノブックス)
Ⅰ : 文学・思想
Ⅱ: 自作及び文壇・出版業界への言及
Ⅲ:美術、音楽、デザイン、映画その他
Ⅳ:時事問題とエッセイ
自己について語ろうと、広大無辺な言葉の世界を見渡すと、他人にとっては不可欠だが、自分には一向に関係がない単語というのが、当然のことながら、数多目につく。
たとえば、「挫折を知らない」という決まり文句の揶揄がある。「挫折」というのが、どの程度の 体験を指すのかは人それぞれだろうが、重要なのは、当人が、己を語る上で、その一語を不可欠と感じるかどうかである。
この選別は、非常に厳密なものではないかと思う。私は折々、新聞や雑誌のインタヴューを受け るが、記者の中には、私の発言をまとめる際に、つい自分の語彙を混ぜ込んでしまう人がいる。そうすると、ほとんど身体的な、非常な違和感を覚える。 自分の中に絶対に存在しない語彙というのはあるもので、ありきたりであるにも拘らず、自分の 言葉としては、生まれてこの方、一度も使ったことがない単語というのは、案外、少なくない。誰 かの言葉が、どうしようもなく浮薄に感じられる時には、やはりそれが、その人の実存とは何ら必 然的な関係を有さない場合だろう。
十代の頃、私は、自分の人生は、「恩師」という言葉と、きっと無縁のまま終わるだろうという 予感を抱いていた。
高校まで、私も色々な教師に世話になったが、親の世代の人たちが、敬愛の念を籠めて、小学校の担任のことなどを「恩師」と呼んだりする感覚が、私にはついになかった。大体、学校教育には反抗的だったし、せいぜいのところ、シブシブといった態度だった。好きな教師もいたが、多読だったので、感情を揺さぶられるような言葉の体験は、遠い彼方の、遠い時代の誰かが書いた本の中 にこそあると思い込んでいた。
そのくせ私は、「恩師」というこの古風な言葉に、なんとなく憧れを抱いていた。私は、オスカ ー・ワイルドが、ジョン・ラスキンに『幸福な王子』を献本する際に添えた手紙の次のような文言 を覚えている。西村孝次が、新潮文庫のあとがきに引用している。
わたくしのオックスフォード時代のもっともなつかしい思い出は、先生との散歩と会話であ り、先生から教わりましたのは、すべてすぐれたものばかりでした。どうしてそれ以外であ りえたでしょうか? 先生にはどこか予言者の、司祭の、詩人の風があり、先生にたいして 神々は他の誰にも与えなかった雄弁を与えられました、......
もちろん、まさか自分をワイルドに擬えるわけでもなく、オックスフォードに行きたい(!)などとは考えもしなかったが、しかし、大学というところに行けば、こういう「恩師」との出会いが あるのだろうかと、漠然と想像してみたりした。
ーー が、矛盾だらけの私は、結局、法律には何の興味もないまま、京都大学の法学部に進学する ことになった。理由は色々だが、いずれにせよ、実定法の教授が、自分の「恩師」になるだろうと いうことは、端から期待もしていなかった。
入学後の二年間を、私はほとんど授業にも顔を出さず、だらしなく過ごした。三回生になって、いよいよ専門科目の履修が始まり、その一覧表の中に見つけたのが、小野紀明先生の「西洋政治思想史」の授業だった。
私は、相変わらず法律に興味がなく、政治への関心も希薄だったが、思想史というのは面白そう だった。丁度、ミルチャ・エリアーデの宗教史にのめり込んでいた頃で、他方で、小説家になりたいという思いを抱きながら、批評家たちが、あんまり喧しく「文学は終わった」だの「近代文学が 終わった」だのと言うので、本当にそうなのかと、自分なりに文学史を辿るような読書をし始めた頃だった。現代思想ブームもいよいよ爛熟期を迎えていて、その手の本も多少読んでいたが、自分 の血となり肉となるという感覚からはほど遠かった。しかし、思想史を学べば、なにかもうちょっとわかるようになるのではないかという気がした。
小野紀明先生の西洋政治思想史の授業は、二年間かけて、ホメロス期のギリシア哲学からポスト モダニズムに至るまでを網羅するという、壮大な内容だった。私が授業に出るようになった一九九 六年は、その後半を扱う年で、初日に取り上げられたのは、ニーチェだった。
その日の午後、広い法経第四教室で行われた講義を、私は今でも昨日のことのように覚えている。
教壇に立たれた先生は、今期から新たに受講する学生のために、冒頭でまず、古代ギリシアが経験した自然と法との乖離という西洋精神史の根源的な危機について話をされた。私は、教室の一番後ろの席で、頰杖をつきながらノートを取っていたが、次第にやんごとなき出来事に直面しているような心地がしてきて、やがて『悲劇の誕生』へと話が移り、講義が終わる頃には、一種のショ ック状態で、その場から動けなくなっていた。
「なんか、めっちゃアツい講義やったな。」
珍しく大学に顔を出して、ぼうっとしている私に、クラスメイトが笑って声を掛けた。私は多分、 ああとか、うんとか、何か適当な返事をした。
私は、どうして自分が、古代ギリシア人たちが、一つの世界観の崩壊に直面して感じていた困難 を、まるで我が事のように、こんなにも身に染みて体感できるのか、ふしぎだった。そして、考え込んでしまった。
私は以来、二年間、ほとんど欠かすことなく講義に出席して、初回に感じた衝撃をその度に新た にした。そして、このたび一冊の本にまとめられた、先生の『西洋政治思想史講義││精神史的考 察』を読み返しながら、この講義が、私がものを考える上でいかに豊かな土壌となったのか、そし て、今以ていかに私の思考を先へと推し進めてくれるのかをしみじみと感じた。
小野先生は、とある歴史的状況下に置かれた一人の思想家が、彼の時代の何に最も強く抵抗し、 何に拘ったのかを最大限強調し、それを核として議論を組み立てられた。ジャン=ジャック・ルソ ーの櫛事件のような極めて私的な体験が、どのようにして一つの世界観に影を落としているのか、 ハイデガーの『存在と時間』が、またどのようにして当時のドイツの青年たちの人生を見舞ったか を、時に繊細に、時に緊迫感を以て語られた。
個々の思想家の思想は、徹底して彼に固有のものでありながら、しかも同時に時代精神の産物であり、思想史の流れの中の一部だった。絶対的でありながら、例外なく相対化された。
小野先生の講義には、何か、私たちが日常の中で浸りきっている空気を一変させるような迫力があった。
決して大柄ではないが、話が熱を帯びてゆく時の、背中を丸く強ばらせて、眉間を険しくし、問いかけるように首を傾けながらまっすぐに学生を見つめる姿には、息を吞むような存在感があった。
非常によく通る、少しざらついたハリのある声で、「君たちは普段、当たり前のようにそう思って生活しているかもしれないけれど、違いますよ。ニーチェに言わせるなら、そんなのは、......」 と、講義中、何度となく学生に向かって語りかけた。
私が受講していた頃は、先生も四十代の後半で、その一挙手一投足、言葉の一つ一つに活力が漲っていた。名物講義として有名になった、黒板を叩いたり、教壇を足で踏みならしたりするパフォーマンスは、その著作の強調箇所に打たれた傍点そのままに、私たちの硬直化した通念に衝撃を与 え、最も先鋭的な思想を、最も生々しい身体感覚に直結させた。
その真剣さ、深刻さ、爽快な論理的明晰さと思いつめた暗い情熱、アイロニカルなユーモア、世俗に通じた柔軟な共感、禁欲的な公平さ、そして、圧倒的な博識、ーー そのすべてが、当時蔓延し ていた浮薄な現代思想ブームとは真反対であり、私を含め、学生たちから熱烈に支持されていた。
ジョージ・スタイナーは、『師弟のまじわり』(高田康成訳)の中で、教育者としてのニーチェに 言及しながら、次のように語っている。
......ニーチェは、「一人の《ツーフマイスター》」に出会うという幸運が大切だと言う。このドイツ語は外国語に訳すことが難しい。強いて訳せば「振る舞いの師」ほどの意味であり、 知性だけでなく、身体的にも教育は深く関わることを示唆する。偉大な師は、「人を新たに 作り変えて一つの小宇宙となす」のである。
私は、小野先生の政治思想史の講義に出る度に、本当にいつも、「生きる」ということは何なの かを真剣に考えさせられた。それは稀有な体験だった。
非常に多くの、私とは金輪際無縁であった思想家の言葉が、自らの実存について語るために不可 欠の言葉となった。私はその後、ゼミ生としても先生の指導を受けたが、振り返るとそれは、「わ たくしの京都大学時代のもっともなつかしい思い出」となっている。
講義で、そのワイルドを取り上げられた時、先生は、「内面の不道徳な本質を隠蔽する「仮面」 を肯定して、表層の感覚的美にとどまろうとするワイルドの唯美主義」が、古代ギリシア以来の西 洋思想史の中でいかに特異だったかを論じつつ、同時にそのワイルドが『幸福な王子』の作者であ ることをも指摘して、ワイルドの魅力は、その両者の間で矛盾しながら揺れ続けていることだ、と強調されていた。私自身は、後に『サロメ』の翻訳を手懸けながら、まさしくそのナイーヴさの故に、ルソー的な「透明」な関係になどとても耐えられない、正直なワイルドという人物を改めて理 解した。
小野先生のハイデガー論は、転回によって、その思想が、現存在中心主義の〈決断〉から、存在 中心主義の〈放下〉へと移行したという旧来の解釈に対して、「ダス・ゼルプストとダス・マンの 両義性の思想は、最初期からハイデガーに一貫していたこと、しかし彼が政治的関与を深めた時には二項対立的捉え方をしてしまったこと、その反省の上にケーレ以降の彼は両義性の立場を一層深 めたこと」の緻密な論証を試みたところに特色がある。
文学にも深く通じ、ワイルドの解釈を一例として顕著に窺われる先生の「両義性」に対する深く繊細な認識は、長い時間を掛けて醸成された、一種の気質的思想であるように私には思われる。自 分は飽くまで思想史の研究者であり、思想家ではないという潔癖な職業倫理を墨守されている先生 は、そうした認識を拒否されるだろう。実際、それが先生のハイデガー解釈を導いたとは決して言 わない。しかし、西洋政治思想史の長い歴史の果てに出現したハイデガーの思想の中でも、先生が、 誰にも増して注意深く、その「両義性」を見ていたことに、私は必然性を感じる。
グローバル化が一気に進んだ今日、西洋社会の理解は、改めて私たちにとっての緊急の課題とな っている。
政治という営みの出来以来、彼らは何を思考し、どう生きてきたか?
本書は、それを〝我が事〞のように追体験するための一条の道である。
(「図書」2015年5月号)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
