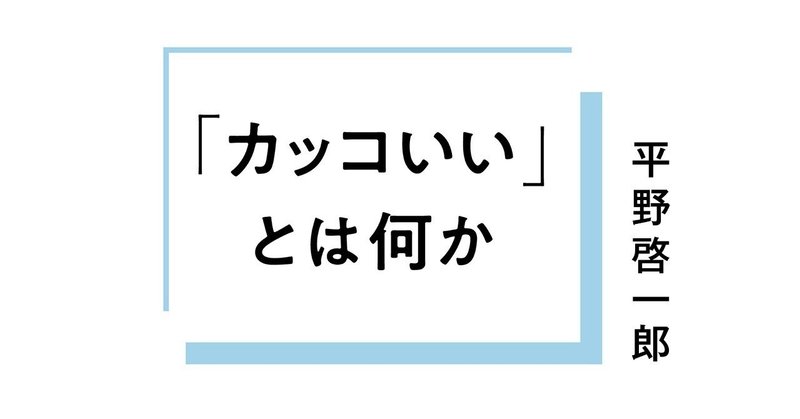
新書『「カッコいい」とは何か』|第3章「しびれる」という体感|1生理的興奮としての「しびれ」
「カッコいい」という判断は、本人にとって、絶対に疑い得ない根拠を持つこととなる。「しびれる」というのは、飢くまで一つの表現だが、とにかく、そんなような何かが、もし体を駆け巡らないならば、それは、人がどれほど崇めようと、自分にとっては、「カッコいい」対象ではないのである――。平野啓一郎が、小説を除いて、ここ十年間で最も書きたかった『「カッコいい」とは何か』。7月16日発売に先駆けて、序章、終章、そして平野が最も重要と位置付ける第3章、4章を限定公開。 「カッコいい」を考えることは、「いかに生きるべきか」を考えることだ。
※平野啓一郎が序章で述べる通りの順で配信させていただきます。
「全体のまとめである第10章にまずは目を通し、本書の肝となる第3章、第4章を理解してもらえれば、議論の見通しが良くなるだろう。」
1.生理的興奮としての「しびれ」
人を虜にする
ここからいよいよ、本書の最も重要なテーマである「しびれる」という体感について、更に議論を深めていきたい。
「カッコいい」にあって、「恰好が良い」にないものの一つは、あの「しびれる」ような強烈な生理的興奮である。これは非日常的な快感であり、一種、麻薬のように人に作用し、虜にする。
そこで、改めて「カッコいい」を次のように定義し直しておこう。
「カッコいい」存在とは、私たちに「しびれ」を体感させてくれる人や物である。
この定義によって、私たちは、フェラーリと大谷翔平とマイケル・ジャクソンを同一線上で比較することが可能となるのである。
私たちは、「カッコいい」人に憧れ、夢中になり、政治的にも思想的にも大きな影響を被るが、だからこそ、社会はそれを警戒する。ロクでもない人間が、その「カッコよさ」で人をたぶらかしてはたまらないからである。
「カッコいい」は、大抵、軽薄で、表面的なチャラチャラした価値のように見做されてきたが、そんなふうに不当に貶められてきたのも、実は、政治的な意図が働いていたのかもしれない。というのも、「カッコいい」存在は、マスメディアを介したその絶大な影響力故に、反対の立場に立つものを脅かすからである。
体制に従順であれば、大いに利用価値があるが、反体制的であれば危険視もされる。
アメリカでは、ヴェトナム反戦運動に加わり、「ラヴ・アンド・ピース」を訴えていたジョン・レノンが、一九七四年には国外退去を命じられている(結局、取り下げられたが)。ロック・ミュージシャンは、「カッコいい」かもしれないが、それは上っ面で、中身は空っぽの〝お花畑〟だ、という批判は、こうした実力行使とは違ったかたちで、その影響力を削ごうとするものだろう。
また青少年の健全育成という名目で、同じくアメリカでは、八〇年代に保守派が、若者に〝有害〟なレコードにシールを貼り、注意喚起を行う活動を目的としたPMRCなる団体を設立し、物議を醸した。ロックだけでなく、ヒップホップもそのターゲットとなり、例えば、マイアミ・ベースの2ライヴ・クルーは、リズムマシンを使ったエレクトリックなパーティ・サウンドで《As Nasty As They Wanna Be》を大ヒットさせたが、タイトル通りの卑猥過ぎる歌詞が問題視され、彼らのアルバムは「猥褻物」として規制され、当人たちのみならず、レコードを販売した店の店員まで逮捕されるなど、表現の自由を巡る大問題に発展した。
〝危険な魅力〟への警戒
誰がどう考えても、「カッコよさ」は、二〇世紀後半の最も重要な価値だったにも拘らず、それが今日までまともな議論の対象とされてこなかったのは、統治の上で、それがコントロールの難しい、危険な魅力だったからかもしれない。丁度、プラトンが、人々の目を真理からそらせてしまう芸術を、公的領域から追放しようとしたように。選挙キャンペーンの分析などを見ても、「カッコいい」にはなるほど、理知的な判断力を歪めてしまう、という懸念もあるだろう。
些か穿った見方だが、アートの世界でこの概念が軽んじられ、低級なものと見做されてきたのも、「美」によって得られる快が、「カッコよさ」から得られる快の強烈さに負けてしまうからかもしれない。
私は、「美」を愛しているが、客観的に見れば、二〇世紀後半は、「美」は「カッコよさ」に影響力の点で大敗している。音楽に於いても、美術に於いても、由緒正しい「美」にとって、新興勢力の「カッコよさ」は、社会の支配的な地位を奪おうとする脅威であり、その意味では、大衆からの支持が得られ難かった二〇世紀前半のアヴァンギャルド運動の方が、まだしも手なずけやすかっただろう。
今日、「美」は既に、芸術の最高理念ですらなく、実際には、六〇年代に登場したポップアート然り、「カッコいい」は、様々な形でこのジャンルに紛れ込んでいる。
そして、芸術家像という意味では、マイケル・ジャクソンのような〝キング・オヴ・ポップ〟だけでなく、ジャズとクラシック、それぞれの世界で二〇世紀後半に〝帝王〟と称されたマイルス・デイヴィス、ヘルベルト・フォン・カラヤンは、いずれも、スポーツカーを乗り回し、華麗な恋愛遍歴を重ね、ファッショナブルで理知的な「カッコいい」存在であることを強く意識していたのだった。それは間違いなく、彼らのカリスマ化に寄与している。
実のところ、その作品に関しても、カラヤンがベルリン・フィルを指揮したベートーヴェンの交響曲第三番《英雄》(一九七七年)などは、「カッコいい」という表現が最も的確な演奏ではあるまいか?
私たちの「カッコいい」人への支持は熱烈で、嘘偽りがなく、拍手や歓声は、心の底からの感動に衝き動かされている。
なぜそう言い切れるのか? それは、作為的なことではなく、体が自然と反応しているからである。私たちは誰も、演技で鳥肌を立たせることは出来ないのである。
「マジでカッコいい!」とか「超カッコいい!」といった感嘆の表現には、刺激的な体感が伴っている。決して単に、「あるものとあるものとがうまく調和する・対応する」ことを冷静に、理屈や知識で判断しているだけではない。
これこそが、「カッコいい」について考える上でのすべての基礎である。
この体感の故に、「カッコいい」という判断は、本人にとって、絶対に疑い得ない根拠を持つこととなる。「しびれる」というのは、飢くまで一つの表現だが、とにかく、そんなような何かが、もし体を駆け巡らないならば、それは、人がどれほど崇めようと、自分にとっては、「カッコいい」対象ではないのである。
そして、そこから発して、対象を好きになり、対象に憧れ、対象のようになりたいと感じ、対象のように振る舞って、自分でその鳥肌が立つ感覚を追体験したいと欲望する。あるいは、その「カッコいい」ものを所有し、年中、「見れば見るほどカッコいい。……」と、「しびれ」ていたくなる。それを身につけていることで、自分も人から「カッコいい」と目されることを期待する。
端的に言って、「カッコいい」ものは、魅力的であり、人気があるのである。
リストに熱狂
ヨーロッパで、音楽家がそんな存在となったのは、一九世紀中頃である。
〝ヴァイオリンの魔神〟パガニーニを嚆矢とし、彼に憧れ、〝ピアノのパガニーニ〟たらんとしたのが、ご存じ、リストである。
「彼(リスト)がサロンに入ってくると、まるで電気ショックが走ったようだった。婦人たちは、ほぼ全員が立ちあがり、どの顔にも陽が射しているようだった」
童話作家のアンデルセンの証言である。
「電気ショック」という表現の通り、まさしくみんなリストに「しびれて」いたことがよくわかる。そして、彼女たちは失神したのである。それは、会場の換気が悪く、コルセットを締め過ぎていたせいでもあろうが、同時代のシューマンやショパンのコンサートでも、そんなにバタバタ人が倒れていたというわけではなかったから、リストはやはり、格別に「カッコよかった」のである。
「彼の前にひざまずき、指先にキスさせてもらえるよう許しを請う女性がいるかと思えば、別の女性は、彼の紅茶のカップにあった飲み残しを、自分の香水瓶に注いだという。あるロシアの淑女たちは、船で旅立つリストを見送るためだけに、大型汽船を楽団付きでチャーターしたという。」
凄まじい逸話だが、これは、一九五〇年代にエルヴィス・プレスリーのコンサートで見られるようになった光景と瓜二つであり、その後のスーパースターとファンたちとの関係の言わば原型である。
三島由紀夫は、初来日したビートルズの武道館公演を聴きに行って、その会場の熱狂に皮肉交じりに驚嘆しているが、『裸体と衣裳』(一九五九年)の中では、テレビでロカビリーを見たあと、
「ロッカビリー歌手をタックルするファンの狂態から、現代のオルフェウスとオルフェウスを八つ裂きにするバッカスの巫女たちとのモダン・バレエの台本を誰か書かないものか。」
と、斜に構えつつ、洒落たことを書いている。
勿論、リストは本物の音楽家であり、超絶技巧のピアニストだった。素晴らしい曲もたくさん書いている。しかし、この時代のリスト・ブームには、純粋に美しい音楽を鑑賞する、というだけでは説明のつかない、「カッコよさ」への激しい熱狂が感じられる。
リストは、一八三九年一一月のウィーン公演から一八四七年九月のエリザベトグラードでの引退公演まで、なんと、八年間にわたり、二百六十の都市で千回にも及ぶコンサートを催し、大成功を収めている。飛行機も車もなく、汽車も極一部に通っていただけのあの時代に、三日に一度はコンサートをしていたことになるが、その驚異的な観客動員力には、やはり、彼が「カッコよかった」ことも大いに手伝っていただろう。ヨーロッパ中に、「電気ショック」が走ったのである。
第二次世界大戦後、「カッコよさ」の威力は、マスメディアを通じて更に途轍もなく巨大化した。
当然、商品の広告は、「カッコよさ」を武器とする。なぜなら、「カッコいい」ものは、体が反応する快感を与えてくれるので、どうしても見たくなり、また欲しくなるからである。
そして、宣伝に「カッコよさ」が有効であるならば、グラフィック・デザイナーやCMプランナー、商業写真家には、「カッコいい」表現が求められ、当然に、そのイメージにピッタリの「カッコいい」人が起用される。つまり、「カッコいい」ことはお金になるのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
