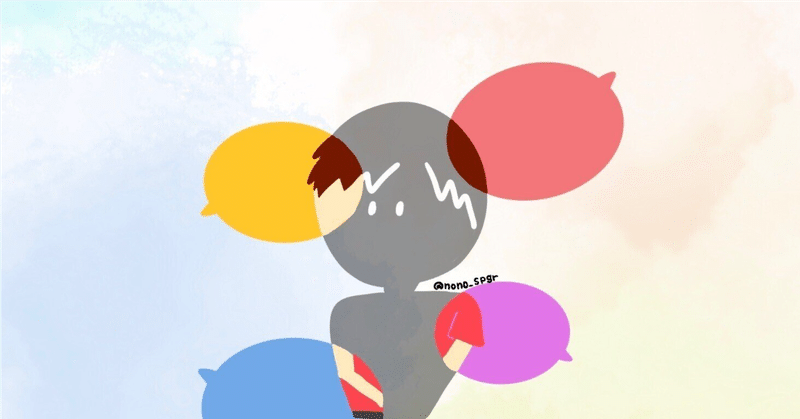
子どもを「褒める教育」は正しいのか?
最近、「褒める教育」というのが流行っているというか、
注目を浴びています。
それだけ、親や先生が子どもたちや生徒たちを褒めない、という考えがあるからのことでしょう。
ちょっとできたことが「当然」「当たり前」と捉えると、
褒める前に次を期待したりします。
ちょっとの努力や成功も、「当たり前」と捉えなければ、
自然と、褒める気持ちが湧いてきそうですよね✨
一方、叱られてばかりの子どもたちは、
「どうせまた怒られる」
「まただ」
「はいはい、どうせ自分はダメですよ!」
というビリーフが作られ、
ますます叱られるような言動を取ることがあります。
大人からすると「叱られたくないなら、変わりなさい!」という意味で
叱るのだと思いますが、ゴーレム効果が働いちゃうんですね。
結局、親も先生もイライラ、子どももイライラ。
何も変わらない。
だからこそ、
逆の視点から「叱るのではなく褒めよう!」が出てきたんだと思います。
その結果、
褒めてばかりいると、子どもは褒められるのが当たり前になって、
褒められる価値を無くしていくかもしれません。
「なんで褒めないの!」
「褒めてくれない人は嫌い。。。」
になるかもしれない。
大人は
「褒めなきゃ!」
「叱ってはいけない!」
「もっともっと褒めなきゃ!」
「あー、でもまた叱っちゃった・・・」
のように、褒めるというHowのばかりに意識が行きすぎて
大人である自尊心が傷つけられたりすることも出てきます。
「褒めることが正解」「叱ることが不正解」
そんな「正解」「不正解」に固執する必要はないと思います。
まず「叱る理由」に向き合ってみましょう。
「注意しないといけない」時は必ずあります。
優しく注意するのか、強い姿勢で注意するのか、
自分に気づいて欲しいから、と放置することもあるかもしれませんが、
やはり気づかせるきっかけは作る必要はあります。
時には「強い姿勢で注意をする」ことも必要かもしれません。
「褒めることも、叱ることも大事」
「どっちもあり!」
「どちらにもメリット、デメリットある」
もっと俯瞰してみる。肩肘張らなくていい。
大事なことは、
流行りに流されず、感情に任せず、
しっかり子どもの目を見て正直な想いを言語化して
対話することなんじゃないかなぁと思うのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
