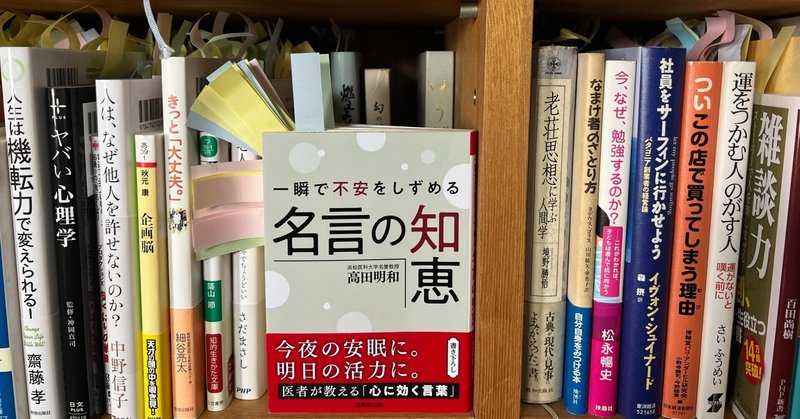
よい運を続けるためには
今日のおすすめの一冊は、高田明和氏の『名言の知恵』(成美堂出版)です。その中から『「困ったことは起こらない」を口癖に』という題でブログを書きました。
本書の中に「よい運を続けるためには」という心に響く一節がありました。
仏教では、慈悲に基づく言動や思いは宇宙の貯金通帳に善業、つまり徳として蓄えられ、それはよい運になるとされています。一方、他人の生命や心を傷つけるような 「思いや言動は、悪業という借金になります。
借金は返さなければいけませんから、そ の人は悪運に見舞われることになるのです。 この貸し借りは、普通は現世で決着がつくのですが、前世の影響を受ける場合もあります。 この考え方で大切なのは、運が悪い時には苦しい努力をするので徳を積んでいることになるという点です。
私たちは、自分がどれくらいの善業を持つか知りません。そのために不幸が続くと嘆くのです。 しかし、悪業の借金を返しているのだと考えたほうがいいと思います。イギリスの看護婦ナイチンゲールは「病気は健康に向かう道だ」と言っています。 病気という不運に見舞われた時にも努力をやめず、時を待つことが大事です。
ここで大事なことがあります。よい運を続けるのは並たいていではないことです。徳を損なわないように細心の注意を払わなければなりません。私は幸い恵まれた晩年を送っていると思いますが、徳を損なわない生活を心がけています。本を書いたりする時も、徳を損なわないように注意しています。
私はすぐれた先人が、徳を損なうまいと薄氷を踏むように生きた意味がよくわ かります。そうしないと運を逃してしまうのです。 最近、知人や著名人の晩年を見る機会が多いのですが、人生は最後まですべて因縁 ではないかと思うことがしばしばです。
「禍福は糾える縄の如し」という言葉がありますが、禍が起きた後は、必ず幸がやってくるし、幸のあとには禍が起こる、ということです。しかしながら、幸福を長続きさせる方法があります。それが、福が来たとき、自分が少し損をして生きることです。
幸田露伴は「幸福三説」を唱えました。三説とは、「惜福」「分福」「植福」の三つです。惜福とは自分に来た運を使い尽くさないで、天に預けておくことです。「分福」とは、自分に来た運を人に分けることです。「植福」とは、未来のために、幸福の種まきをすることです。
つまり、この三つは自分が少し損をして生きるということです。運がいいときも、有頂天にならず、傲慢にならず、偉そうにせず、自己中心的にならず、自分だけが楽しもうとしないことです。謙虚に、人のために生きることです。すると、幸福も長く続くのだと思います。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
