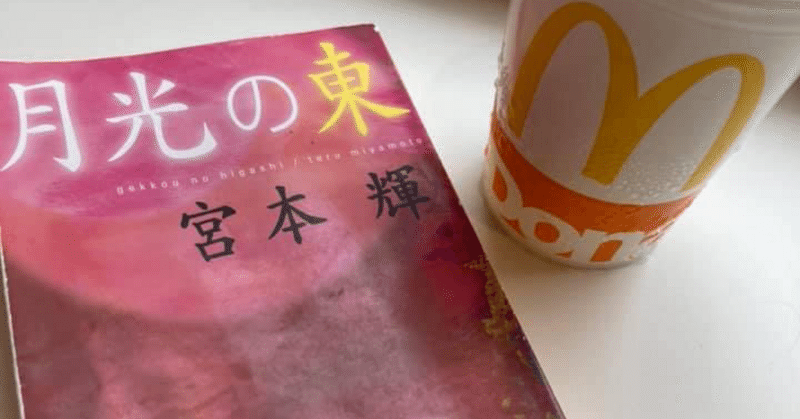
📕宮本輝「月光の東」を書き手として読んでみた時
🥀宮本輝「月光の東」
「十三歳のときの私の恋は、いまもまだつづいていると思うのも本心ですし、加古慎二郎への嫉妬も本心ですし、よねかを癒せる男になりたいのも本心なんです。
誰もが、みなそうであるにちがいありません。人は誰もが無数の本心を持っている」
〜宮本輝「月光の東」より
パキスタンのカラチで首を吊って自殺をしてしまった友人の影には「よねか」という幼馴染の女性の影がちらついていた。
この物語は、多くの男性を虜にしながらも自らの心をすり減らしてゆく「米花(よねか)」という類い稀な美貌の持ち主と、彼女に振り回される男たちを描いた人間ドラマである。
ストーリーはカラチで首吊り自殺をしてしまった男、加古慎二郎の幼馴染である杉井が語り手になる章と、加古の妻、加古美須寿が語り手となる章がパラレルに進んでゆく。
読み始めて前半の印象は、よねかが残した「月光の東」という暗号のような言葉と、加古慎二郎の自殺の真相が謎かけとなり、ミステリー感覚で読み進めていたが、結局最後までどちらの謎もはっきりと明かされることなく終わってしまう。
ミステリーとして読めば、もやもや感が残ったままで消化不良になってしまいそうな物語。しかし、巻末の解説にも書かれていたように、この物語の主題は、多くの男を虜にしながらも破滅していく「よねか」という女性の生き様を、夫が自殺をして破滅しそうになりながらも再生していく、加古美須寿と対比させながら描くことにある。
そう考えると語り手のひとりである杉井は、主役でもなんでもなく、よねかに振り回された多くの男性の中の一人、という位置付けに過ぎない。
特筆すべきなのは、主役というべき「よねか」視点で書かれている章が一切ないところだ。あくまでも、ふたりの語り手が第三者から聞いた、いわゆる伝聞形式で「よねか」が描かれている。
その表現方法が、よねかという女性のミステリアスな部分をより鮮やかに読み手に印象付ける。語り手とよねかの間に、一枚の壁を作ることで、不確かで、朧げで、まるで現実の世界を生きていないようなよねかという女性を描き出すことに成功している。
対照的に描かれている加古美須寿は、そのものが語り手であり、日記を使った告白形式を用いることにより、現実を生きる女性像として極めてリアルに描かれている。
例えて言えば、加古美須寿を昼を照らす太陽の光だとしたら、よねかそのものが、夜を煌々と照らす月の光だと言える。加古美須寿の存在が、よねかの存在感を増幅させているのである。
クリームコロッケや、ひまわり、骨董品、チョモランマトレッキング、競馬。物語に奥行きを与える小道具の使い方も抜群に巧い。
書き手の立場として読めば、多くのものを学ぶことができる宮本輝の作品。この「月光の東」からも多くのことを学ぶことができました。
余談ですが、僕の初めての海外旅行はトルコでした。当時、成田からイスタンブール行きの直行便はなく、パキスタン航空を使い、カラチ経由南回りで半日以上かけて行ったことを思い出します。
カラチでトランジットのため一泊したので、初めて異国の地を踏んだのはトルコではなく、パキスタンということになります。カラチ空港に降り立ったのは現地時間で確か午後八時ごろでした。空港の前には、観光客をホテルやタクシーに勧誘する現地の人が蠢いていて、めちゃくちゃ怖かった記憶があります(笑)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
