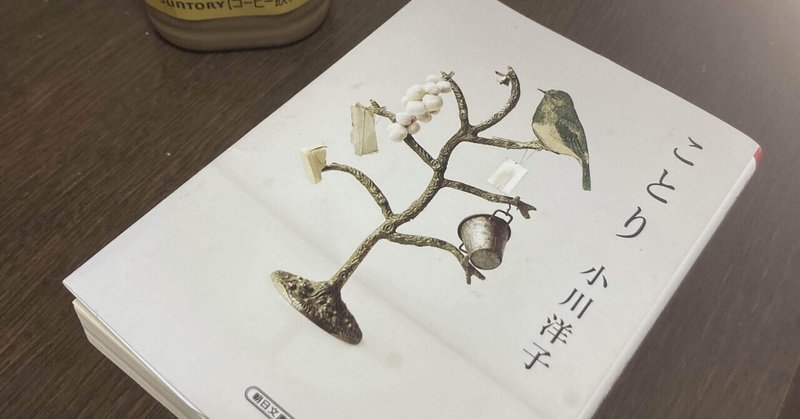
📕小川洋子「ことり」読了後の雑感❶
「鳥籠は小鳥を閉じ込めるための籠ではありません。小鳥に相応しい小さな自由を与えるための籠です」〜小川洋子「ことり」より
※※※※※※
⭐️静かに進行してゆく物語前半3分の2と、そこで散りばめられている無数の伏線
この作品の主人公は、子供たちから「ことりの小父さん」とよばれている男性。なぜ、「ことりの小父さん」とよばれているかといえば、毎日のように幼稚園の園庭に設置されている鳥小屋の掃除をしているから。そして、この小父さんにはお兄さんがいました。お兄さんは「人間の言葉は話せないけれど小鳥と話ができる」人でした。
この物語の前半は、「ことりの小父さん」とお兄さんとの触れ合いを中心に進んでいきます。お兄さんの話す言葉は常人には理解不能だったけれど、なぜか弟である小父さんには理解できた。そして自然とお兄さんの影響を受けて、小父さんは小鳥に関心を持つようになります。
さて、小鳥と会話ができるお兄さんは心臓麻痺で幼稚園の前で死んでしまう。これがちょうど真ん中あたり。圧倒的にキャラが濃かったこのお兄さんが死んでしまったところで、正直、少し読むのがかったるくなってしまったというのが事実。
しかし、そこは流石の小川洋子さん。
お兄さんの死後、足繁く通うようになった図書館の女性司書の登場で物語は再度熱を帯びてきます。小父さんの女性司書に対する淡い恋心を小川洋子さんは圧倒的な描写力で表現する。【カメラ目線は常に「ことりの小父さん」に固定されているの】で、その描写は、「ことりの小父さんから図書館司書のお姉さん」に向かってということになる。
小川洋子さんのすごいところは、【第三者の目を通して今そこにいない人を描写する力】。ここでいう第三者とはいうまでもなく「ことりの小父さん」で、今そこにいない人というのは「図書館司書のお姉さん」になります。歳の離れた若い女性に恋心を抱く小父さんの気持ちを表現する時、小川洋子さんは一切の説明を省き、描写で表現をする。それは、恋をした小父さんの仕草であったり、庭に集まる小鳥の様子であったり、お姉さんの動作、ものいいを回想する様子であったり。
つまり、図書館司書のお姉さんはそこにいないけれど、キャラが際立ってくる。これが【登場人物不在時のキャラ立ての極意】。
そして、図書館司書のお姉さんとのエピソードまでに、数多くの伏線が散りばめられているのが、「ことり」の小説構造を読み解く上での大きなポイントになります。それは、長い間小父さんを苦しめている頭痛であったり、図書館で読んだ本の内容であったり、お兄さんが心臓麻痺で倒れてしまった時にできた幼稚園の前にあるフェンスの窪みであったり、、、そんな数多くの伏線を孕みながら物語は後半戦へ。
⭐️圧倒的な伏線回収力と慈愛に満ちた物語後半三分の一
トルストイの「戦争と平和」を読んだ時、エピソード描写力に圧倒されました。その時痛切に感じたのは、圧倒的な描写力とは、【その場面だけの描写ではなく、複数のエピソードを有機的に繋げていくことのできる描写】であるということ。複数のエピソードが有機的に繋がり、おおきなうねりとなって物語は怒涛のように進んでいく。それが「戦争と平和」でした。
小川洋子さんの「ことり」ではその片鱗が見えます。もちろん「戦争と平和」ほど壮大ではないけれど、虫箱を持った老人の登場以降は、【前半3分の2で散りばめた伏線を回収しながら、それまでのエピソードを利用して物語を自然に盛り上げていきます】。その頂点は、最後、ことりの小父さんを看取ることになったメジロとのエピソード。いやはや、物語は至って静かなのに、圧巻でした。
⭐️小説はストーリーではなく描写力
正直、ストーリーとして面白いかと言われたら多分、面白くはありません(笑)
でも、読者に強い印象を残す物語であることは確か。なぜ、ストーリーはさして面白くないのに、印象には残るのか?
小説を書き、小説を読むことにおいて避けて通れないその命題に対する答えをこの作品は提示してくれているような気がします。
「小説はストーリーではなく描写力」であることをはっきりおっしゃっている小川洋子さんの面目躍如的な長編だと思いました。
他にも書きたいことはあるけれど、、今日はこの辺で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
