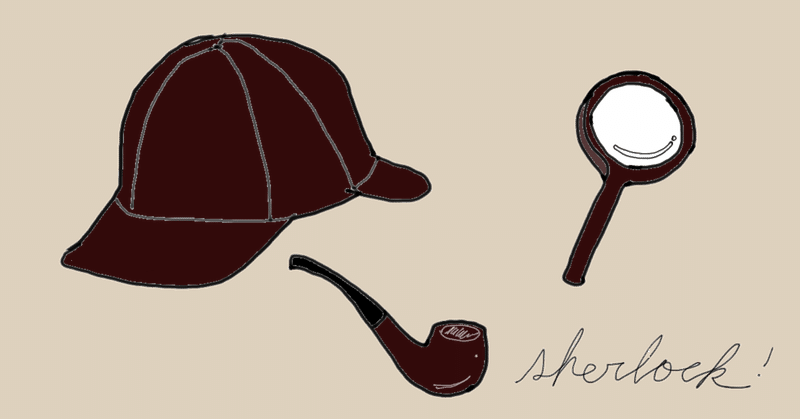
認知の歪みはなぜややこしいのか?
認知の歪みについてのnoteを読んでいただき、たくさんのいいねをありがとうございました。
『認知の歪み』がどのようなものかを簡単にまとめたのですが、前回のまとめは認知の歪みが実際のやりとりの中で何を引き起こしやすい(≒問題の火種になりやすい)のかが中心でした。
しかし、実際のやりとりの中では、火種だった問題が連なるように広がり、結果として本来以上に認知が歪められてしまうことがしばしばあります。なぜなのでしょうか?
これは人間が生物として生きていく際に、集団や社会の中で生きていくことが必須であることにも起因します。
①Bio-Psycho-Socialモデル
もともとはEngelが提唱した概念ですが、現在のココロに関する医学、心理学の概念の中に広く用いられるようになりました。私もクライアントさんと状況の確認をする際や問題がどのように生じやすいのかをお話しする際に良くこの概念を使います。
Bio…生物学的な要因。本人の気質や発達特性、身体的な特徴、虐待に伴うトラウマなど本人の”内側”にある要因です。
Psycho…心理学的な要因。認知の歪みはここに入ります。他の人とのやりとりの際に生じる”関係性”に基づく要因です。
Social…社会的な要因。社会生活の中で生じる問題(学校、職場、業務内容、コミュニティとの関係など)による要因です。
それぞれの要因はお互いに影響を与え合って、様相を複雑にします。
複雑に絡まり合った糸を解すように整理していくこと(クライアントさんから”因数分解みたい”と言われることもあります)で、問題がなぜ大きくなってしまったのかを理解しやすくなります。
②なぜ”因数分解”するのか?
わざわざややこしい問題をなぜ分解する必要があるのでしょうか。
それは”できること”を性格に選べるようになることが目的です。
精神科や心療内科でお薬を処方され、服薬している方は世の中にたくさんいます。いわゆる精神科系のお薬はほぼ全て”脳”という臓器に働くものです。
人間の認知には脳の構造が大きく関わっていますが、不安になりやすい、気分が落ち込みやすい、注意が散りやすい、気になったら止まらないなど、脳の機能の問題に起因する認知の特徴はお薬で和らぐことがあります。
しかし薬はそもそもBioの部分にしか効果がありません。Bioの特徴が和らいだとしても、その人が獲得してしまったPsychoの問題はお薬ではあまり改善しないことが多いのです。
Psychoの問題は学習や経験を積むことで”修正”することはある程度可能です。自分を俯瞰的に見るようになることで、歪んだ認知に囚われなくなることで、Psychoの問題は改善していきます。
Socialについては周囲との環境調整を行うことが必要です。今の本人の問題が、どうしてこうなっているのかを理解することで葛藤を減らすことはできるのですが、拗れている場合はなかなか難しいところがあるように思います。
③SNSなどで見る”何でこうなる?”への因数分解
なんで女性の人権がーって話する時に他人の家庭持ち出して奴隷扱いだとか性欲処理機とか言っちゃうんやろ。
— せんり🦍ネットゴリラ (@Lnnt6iol7GyOCWf) November 7, 2021
その奥さんがどう思ってるかもわからないのに。幸せに暮らしてるかもしれないのに。私勝手に他人にそんな風に言われたら嫌だわ。
旦那が大好きやし、仕事や家事は家族の生活のために頑張りたいし、好きやから笑いかけたいしセックスもしたい。やらされてる事じゃないよ。
— せんり🦍ネットゴリラ (@Lnnt6iol7GyOCWf) November 9, 2021
でもDV受けてる時は全部苦痛だった。全部上手くやらないと叩かれてたし。やからね、辛いのは相手との関係性が問題なんやと私は思ってる。
友人が感じた、とても彼女らしい疑問や感想。
少しこれを因数分解してみます。
Bio…この場合は”性”が一番の生物学的要因だと思われます。そしてそれに基づく体の特徴(男性より力が弱いことが多い)もこの中に入ります。
Psycho…相手との関係性に基づく要因です。この場合は相手との関係(素敵な夫との関係、以前に受けた交際相手からのDVなど)が中心です。
Social…社会の中で生じていることの要因です。この場合は”性欲処理器”などの言葉を用いた男性や配偶者の女性への攻撃的な発言が多いことへの違和感というのが近いように思います。
彼女が気づいているとおり、仕事、家事、笑顔を向けたり、愛し合ったりすることは相手との関係が良好であれば”最高に楽しいこと”。相手が最悪の相手であれば”傷つくこと”になります。
それに気がついている人からすれば、いわゆるフェミニストのような人が他の家庭の夫婦の関係に関して”性欲処理器”のような言葉を用いたり、男に知らしめるためにボイコットを呼びかけるような行為は違和感でしかなく、嫌悪感を感じるのは理解できます。
生活の中で幸せを見つけるコツのようなものになりますが、問題がありそうな要因の中で、何かひとつでもうまくいくものを探し出すことが重要だと思っています。
合うお薬が見つかること、問題点の整理を手伝ってくれる人や認知の歪みを責めないけれど伝えてくれる人がいること、支えてくれる仲間を作ること。その中で自分らしく生きることが探せると良いのだと思っています。
前述の友人はDVなどの辛い経験を彼女の力で乗り越え、今の幸せな生活を満喫しているので、問題点を自然に整理できる女性になったのだと思います。
そして全ての領域はつながっていますが、無理やり繋げ過ぎないことも大事なこと。
④無理やり繋げ過ぎないこと
認知の歪みの話の中で、行き過ぎた一般化、レッテル貼り、感情の理由づけなどをお話しました。
最近のSNSなどでは本人の内側の問題や特定の誰かとの問題を全て歪めた認知を通じて”社会の問題”にまとめようとする傾向があるように感じます。
自分自身が受けた性被害やトラウマについて、傷が癒えない状況が続き、似たような境遇の人のケアにあたることで代償しようとする人もいれば、”男性優位の腐った社会が悪い”と社会活動に没入していく人もいます。
攻撃を受けた男性側も”フェミニストは攻撃的”と主語が広がり過ぎてしまい、社会自体が分断されていく状況が作られます。
歪んだ認知(行き過ぎた一般化やレッテル貼り)が原因で、世の中の男性全て(女性全て)が敵になってしまう状況はBioの問題やPsychoの問題に蓋をして、Socialの問題が”全ての元凶”であると無理やり繋げて判断してしまうことで、火種だったものが炎上していく様を良く見かけます。
でも実は、これはとても危険なことでもあるのです。本来は向かい合って癒すべきであるトラウマやそれに基づく認知の歪みには全く手をつけていない状況ということですから。
選挙で野党が大敗し、ジェンダー問題に取り組むと宣言した女性候補が落選し、Socialへの希望が損なわれたことで、不安や絶望感、怒りなど負の感情が惹起され、より攻撃的な言動が目立つようになったと考えることもできるのです。抱えるトラウマが刺激されることで、本来なら不要な攻撃性を爆発させ、諍いや周囲との軋轢が生じ、孤独感を高めていく危険は低くないと思います。
⑤最後に
人づきあい全般を社会スキルと呼びますが、社会スキルが担保されるためには最低限の感情コントロールが必要になります。剥き出しの感情をぶつけ合うことは相手との関係が相当密なものでも苦しいものです。特にSNSなどで短い活字が中心のやりとりになると、言いたいことの本意が伝わりにくく、拡大解釈されたりすることもしばしばですから、余計にうまくいかないものです。文章を整理する力の有無だけでなく、怒りなどの感情に任せて打った長文は言わなくてもいい攻撃的な言葉を用いてしまうこともあるので、公開する前にしばらく時間を置いて、何度も読み直すことをお勧めしたいくらいです。
感情コントロールをするに当たっても、トラウマ処理が現在進行形の場合は些細な刺激でトラウマが刺激され、強い不快感情が呼び起こされます。だからこそ、自分の抱えるトラウマを正しく癒せることはとても重要なのだと思うのです。
敵意を自分の属性に向けられた時、私も怒りを感じます。自分の大事な友人が傷つけられたりしたら尚更。
でも相手の中にある認知の歪みやトラウマなどに思いを馳せながら、どのポイントが問題だと思っているのかを冷静にやりとりできる相手であれば、ある程度の妥結点を見つけることは可能だとも思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
