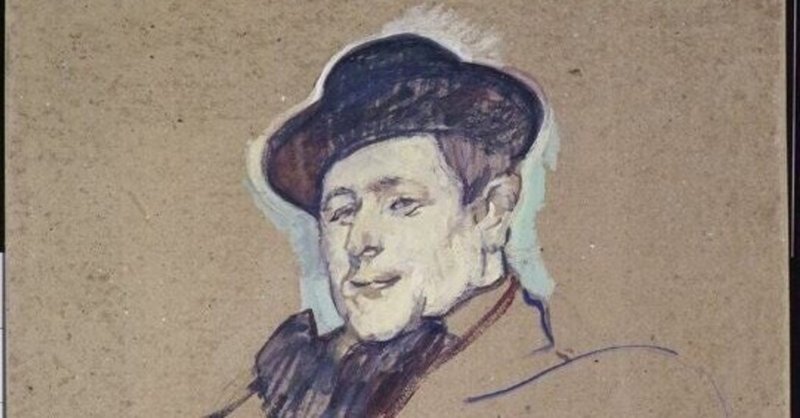
中島義道著〖『純粋理性批判』を嚙み砕く〗読書メモ
P92
これまでドイツ語の”Natur”を時折「自然本性」と訳してきましたが、それはこの言葉には日本語の「自然」という意味と「本性」という意味とが重なっているからです。カントはここでこのことを語っている。
「付加的(形式的)に解される場合」は「ある物の諸規定〔性質〕が原因性という内的原理に従って結合されたもの」であって、これは日本語の「本性」という意味に対応します。(あえて言えば「内的自然」)。
そして、「自主的(質料的)に解される場合」は「現象の総括」であり「自存する全体」であって、日本語の「自然」という意味に対応する(あえていえば「外的自然」)というわけです。
P125
篠田訳では、「争いそのものをひき起こす方法」となっていますが、この場合"veranlassen"というドイツ語を「ひき起こす」と訳すのは正確ではない。争いをあらためて「ひき起こす」審判者がいましょうか?ここは「誘導する」くらいに訳さねばならないと思います。
【感想:ここは、中島氏の言う通りだと思う。この著書は、約10年前から読んでいるが、こうして篠田氏のダメ出しが満載されているので、篠田訳の文庫本も持っていたが、どうしても読む気持ちになれなかった。中山元訳の「純粋理性批判」電子版を購入して読んでみた。1巻目はカントの原文と解説両方読んでみて、解説が平易で理解しやすかったため、2巻目以降7巻目までは、とりあえず解説文だけを読み通した。「実践理性批判」の2巻も同様に読んだ。その上で、この本を手にしてみると、以前はチンプンカンプンだったのが、理解できるようになっていた。】
P148
カントによれば、すべての物は矛盾対当に従うのに、「世界が時間的に無限か有限か」に関する第一アンチノミーにおいては、矛盾対当ではなく反対対当が成立するから、世界は観念なのでした。
ここには、「物自体ではない=観念である」という隠された等式が前提されています。カントにおいては、思考の対象である限りのもの(物自体)はすべて矛盾対当に従わなければならず、そこにおいては互いに相手を反駁しても自分を正当化できない反対対当など成立するはずがない。
しかし、現に示したように、われわれの住む世界においては「世界は時間的に無限であるか有限であるか」という問いに関して反対対当の形をとるアンチノミーが生じているのだから、世界は物自体であるはずがなく、まるごと観念(現象)でなければならない、ざっとこういう論法になります。
P149
超越論的観念論を無条件(無前提)で正当化することはできません(もちろんいかなる哲学理論も無条件で正当化できないのですが)
さしあたり面白みのない結論を下しますと、カントの認識論が二百三十年にわたって風雪に耐えて生き延びているのは、それ自体として論理に破綻がないからではありません。
見方によっては破綻だらけの認識論ながら、「世界」とは何か、「時間」とは何か、真摯に思索していれば必ずぶち当たるアポリア(行き詰り)を小手先で回避せず、それとまともに格闘しているその姿に永遠の価値があるからだと思います。
【感想:同感です。ビッグバン説には現代物理科学界では、異論もある。宇宙は、膨張が止まり、収縮していき、究極の収縮点で、また爆発して膨張を始めるという具合に繰り返しているという説もある。まるで、仏教の世界だ。
ようするに、カントの時代から、量子力学も含めて、科学は大幅に進歩したとはいえ、「時間と世界」については、いまだに、謎のままである。先ほどの、膨張から収縮への転換に関してだが、最先端の天文科学によると、宇宙は膨張速度が弱まるどころか、加速して膨張しているという観測結果が得られている。
それは、何故かということだが、宇宙に散らばっている、解明不可能状態にある、暗黒物質、暗黒エネルギーではないかという説である。「暗黒」とは、まるでスリラー小説かと、おちょくった名称だが、これが真面目な科学用語だというから、科学も、もはや、居直っている感じだ。
以前は、真空は、空っぽだから、真空中には物質は含まれていないと見なされていたが、なんと、ぎっしりと物質で詰まっているということが解明されているから、この暗黒も、いずれかは解明されるであろう。こうして、未知の世界に格闘している姿に価値があるのだろう。余談だが、暗黒は真空のことではと研究されていたことがあり、計算すると莫大なエネルギーとなってしまうという矛盾が出たということだった。】
P181
もし世界が時間的に無限であるとすれば、「現在の時点に達するまでに」自然数の総体に呼応して時間単位が無限回経過したことになりますが、このことはありえないがゆえに「無限の時間が過ぎ去ったということはありえない」わけです。
先の箇所で論じられた無限なもの=最大量が無限の数学的概念に、無限の全体=無限性が無限の超越論的概念に相当し、これでようやく、両者の区別が鮮明になりました。【注:自然数の全体=数学的概念、自然数全体をたどる操作をふくめること=超越論的概念】
P187
カントによれば、あくまでも空間のほうが諸物に先立っていなければならない、なぜなら、カントにおいて「形式」とは、ア・プリオリすなわち経験(現象)に先立つことを含意しているからです。
P192
無が世界における有限な空間部分を取り囲む(条件づける)ことはできないのですが、逆に世界における任意の空間部分Rmが無を取り囲む(条件づける)ことは論理的にありえる。なぜなら、今度は(無でなくて)有が無を取り囲む(条件づける)ことになるからです。
【感想:現代物理科学では、プランク距離(約10のマイナス33乗cm)という超ミクロな距離以下となると分解不可で、時間も空間も無となる領域があることが知られており、この領域付近では、まさに有が無を取り囲んでいる状態にあるといえる。ちなみに、素粒子同志を衝突させて、仮にプランク距離以下に分解されたとすると、莫大なエネルギーが発生する危険性あると言われている。つまり、宇宙の始まりのようなビッグバンが発生するというわけだ。】
P224
空間は無限分割可能でも物体は不可能であるという結論も可能です
【感想:空間は無限分割可能とは言えない。ミクロで見れば、空間も種々の物質から構成されているのである。すると、カントは空間は時間と同様に概念と示されているが、時間はともかくとして(量子重力理論によると、時間も物質化した理論である。だからプランク距離以下の領域での時間は分割不可能となる)、空間は概念ではなく、実体となるのでは?
上記のようにプランク距離以下の領域となると、明らかに分割不可能となる。従って、P221で「トリックとは、合成物という物体の話をすぐに空間の話に移し変えて」とあるが、これは、トリックではなくて、カントが記載通りで良いということになる。
すると、カントはプランク距離以下の領域を認識していたのかとなるが、そもそもカントの時代は、ニュートンの世界であり、量子論の世界ではないので、単なる偶然ということになる。
概念という言語なのだが、世界となると、確かに概念といえるが、身体を取り囲んでいる程度の空間ならば、目に見えないだけで、概念というよりも、実際に、素粒子でぎっしりと詰まっているわけだから、物質となる。
これとは別に、重力は確かに身体でも感じるのに、最新の物理科学の世界でも重力子なるものは実証実験上でも観察されていないというから不思議だ。
一方、ループ量子重力理論では時間も空間も量子化されていて、それ以上分割できない最小単位を想定している。それがプランク長さ(約10のマイナス33乗cm)となる。】
P240~P241
「しかし、点は空間の部分ではない、なぜなら、点とは位置だけで広がりのない存在者であって、それをいかに寄せ集めても空間的な広がりはゼロだからです。
といって、無限個集めたら一定の広がりに至るわけでもない。無限の点から成る空間はどれほどの大きさでしょうか?
もし空間が無限の点から成っているとすれば、一立方ミリメートルの空間(R1)も、一立方メートルの空間(R2)も、一立方キロメートルの空間(R3)も、(中略)しかも一方では、明らかにR1はR2の部分であり、R2はR3の部分であるのに、他方では、R1とR2とR3とは同じ無限の点から成っていることになり、部分と全体が等しくなるという矛盾です」
よって、そもそも「空間は単純な点という無限な点という無限の部分から成っている」という初めの命題が間違っているのであって、いかなる空間も点から「成っている」のではなく、空間における点とは一定の空間を無限分割する限界(Grenze)として意味づけられているのです。
【感想:空間における点とは一定の空間を無限分割する限界を”プランク距離の領域内の点”とすると、「空間は単純な点という無限な点という無限の部分から成っている」という初めの命題は正しいといえるのでは。
「R1とR2とR3とは同じ無限の点から成っていることになり、部分と全体が等しくなるという矛盾です」とR1、R2,R3・・・・と各点が無限にという捉え方に違和感がある。
一定の容器の中に存在している空気には素粒子という点が無限個含まれているが、この容器を無限の空間に拡大したとすると、命題の通りとなる。また、R1,R2,R3・・・・については、身体を囲い込む空間をR1、またそれを囲い込む空間をR2・・・・・と累進的に無限に広がり重なっていくということであれば、理解できるが、「R1,R2,R3とは同じ無限の点から成り立っていることになり」となっているため、理解できない。】
P261
(A)神は(人間の行為を含み)すべての現象を決定する。
(B)悪の原因は、神ではなく(悪魔でもなく)人間である。
これは単純な外見をしていますが、なかなか「解決」が困難なものです。(中略)そして、こうした神学的決定論がニュートンによる万有引力の発見あたりから、自然科学的な決定論にバトンを渡す。ここでも、先の対立とほぼ同じ対立が成立しています。
(A’)自然法則は(人間の法則を含み)すべてを決定する。
(B')人間の行為は自由である。
そして、カントの第三アンチノミーも自然科学的決定論をそのまま承認するアンチテーゼの立場と、それに対抗して自由を認めるテーゼの立場という対立になっているわけです。ですから、自由は決定論という大枠の中で論じられているのです。
【感想:ニーチェは、一般の自由論の潜む中立性の中から奴隷のロジックを暴き出しており、ベルグソンは、自由を定義するいかなる試みもはじめから自由を所有物とする中立性を前提としていて、サルトルは、「人間は自由の刑に処せられている」、「余計なものであるがゆえに人間は自由」、「死はわれわれの自由を根拠としてあらわれるのではないから、死は、あらゆる意味を人生から除きさることはできない」、「アンガジュマンが行われるやいなや、私は私の自由と同時に他人の自由を望まないではいられなくなる。他人の自由をも同様に目的とするのでなければ私は私の自由を目的とすることはできない」と、考えている。】
P283
自由論はなぜ経験的事実(自然因果性)から目を逸らし、初めから超越論的事実(自由による因果性)に照準を定めるかというと、自由を肯定したい者(テーゼの立場)は、人間の悪い行為を非難しその責任を追及する論拠が欲しいからでもあり、この要求を充たすには自然科学的(心理学的)事実を離れて別のレベルに達しなければならないことを知っているからです。
いかなる自然科学的事実が提示されようと、それにもかかわらず自由を保全しなければならない、それには自然科学的事実より「強い」事実が必要です。
P286~P287
自由が支配する可想界と自然法則のもとにある現象界という二つの世界を文字通りに設定するのではなく、「一つの行為に関する二つの異なった関心(理論的関心と実践的関心)に基づく二つのとらえ方」とみなすほうがずっと真実に近いことがわかります。
つまり、Kが殺人行為を実行した場合、その殺人行為に至るまでの(Kの生い立ちや性格などを含めた)自然因果性をたどるという理論的関心と、Kの責任を追及するという実践的関心がともに矛盾なく成立しうるのです。
P289
「椅子から立ち上がる」例は、「世界の経過の絶対的に第一の始まりが可能だ」ということをいささかも証明するものではありません。
P290~P291
さかのぼって決意の瞬間に「そうしないこともできたはずだ」という新たな意味を与えても、ある行為Hが実現されたあとで、それと並んで実現されなかった行為H’を「架空の行為」として加えているだけなのですから(それはまったく実現されなかったですから)、このH’はいささかも自然因果性を「攪乱する」ことはない。(中略)「〈椅子から立ち上がる〉というこの出来事に関しては、規定する自然原因はこうした決意と行為よりも前にすでに終わっているからである」
この文章を素直に読めば、決意の直前まで自然因果性が作用しているが、決意の瞬間それはいわば停止していて、そうした自然因果性の停止状態において、われわれはまったく自由に椅子から立ち上がることを決意できる。ということになりましょう。とすると、これが自然因果性を「攪乱する」ことではなくてなんでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
