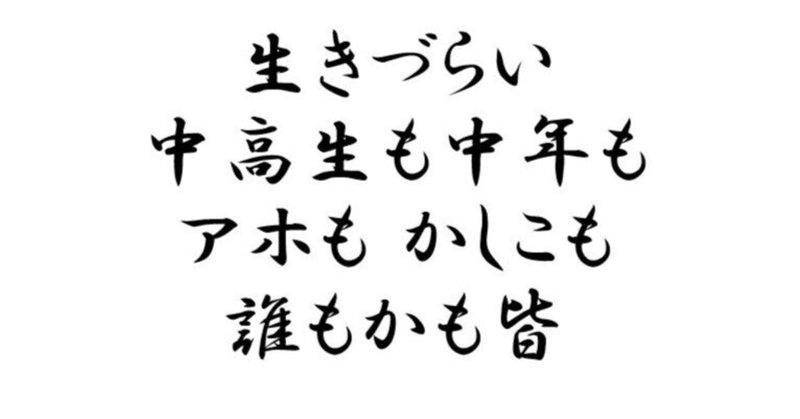
【現代文】捨てるなよ 確定するまで 君の紙
高校時代の鬼教師による読書感想文の宿題。その8作目の粗筋は、私の記述によると次のようなものだった。
「秋の夕暮れ、炉辺に坐って回想にふけるチップス先生の胸に、ブルックフィールド中学での六十余年の楽しい思い出が去来する。ゲイブル山で知り合って結婚した妻キャサリンの助言に支えられて生きたこと。彼女を亡くしてから落ちこんだものの、仕事を続けて教師としての腕をみがいたこと。そして、いつの間にか彼はブルックフィールドの顔となっていた。また、教育の能率性や学校経営の向上ばかりを重んじる新校長ロールストンとの対立もあった。退職しても、学校に近いウィケット夫人の家に住み、大戦の緊張した日々の中、学校に出向いて助ける日々もあった。そして、老教師チップス先生は、愉快だった学園生活の思い出を胸に、深い眠りに沈んだのであった。」・・・「読みはじめ」は「92年9月27日」、「読みおわり」は「92年10月1日」、「延べ時間」は「5時間」――チップス先生の胸にも六十余年の思い出が去来していたが、私の胸にもこの「5時間」が恰も六十余年であったかのように長く感じられた思い出が去来する。
大井競馬場が公営競技で日本初となる夜間開催をスタートしたのは私が小学生の時で、高校生にもなると、すでに「トゥインクルレース」の名は夏の風物詩として定着していた。おそらく平日の開催日だったと思う。渋谷の老舗料飲店で鶏の料理人をしていた父が、土日に休みを取れた筈がない。そうだ、そうだ、間違いない。携帯電話など巷に出回る前の時代のこと。部活の練習が無い日を選び、学校を終えた私は、それこそ昼から営業している父の勤めていた店で父と待ち合わせをした記憶がある。
父はこの店へ頻繁に私を呼んでいた。だいたい自分が休みの日まで待ち合わせ場所に使っていたくらいなのだから――。自営業や職人というのは「親の働く姿」を我が子に生で見せてやることが出来る。私は、父が焼いたハツやつくね、父が仕込んだ鳥鍋、父が包丁を入れた鳥刺しを幾度食べたことだろう。父のような秀逸な技能にも恵まれず、かといって利潤を追求する民間企業の会社員にも性格的に向いていない私だが、それでもサラリーマンとして何とかこの歳まで耐えてこられたのは、「労働の基本姿勢」たるものを父の背中から学んだおかげかもしれない。父は「社会人」としては落第生だったが、「仕事人」としての腕となると、それはそれはウルトラ級のエリートだった。世間は「脱サラして焼鳥屋を始めた」みたいな話題に豊富だが、焼き鳥というのは「串打ち三年、焼き一生」と謂われ、とても素人が簡単に手を出せる領域に非ず。中高生の頃から「お前は成績が悪くねえんだから、なるべく大きな会社のサラリーマンになれ。」と父も言っていたが、なるほど私には料理人なんぞ無理なのだと悟ったものだった。鶏を丸一羽から捌き、串を打つまでの時間たるや、スロー再生の解説を要するほど魔術的であり、「手際が良い」という表現はこの人の為にあると思われるような器用さであった。鳥の肉の繊維と焼き上がりを踏まえ、人間の舌が最大限に美味しさをキャッチできるよう計算し尽くす「匠」が、本日は馬の気持ちを読もうとしている。
少なくとも9月までは確実に夏服だったので、店で制服のズボンと革靴はそのままに、上半身だけ些か年寄り臭い色柄のポロシャツなんかに着替え、深く帽子を被れば、それだけで高校生の雰囲気を“消臭”させることが出来た。脱ぎ捨てた校章入りのYシャツと一緒に、教科書もノートも筆箱も細々とした文具も、そして勿論「生徒手帳」も鞄に詰め込む。それを渋谷駅のコインロッカーに放り込むや否や、この嘘みたいに仲の良い父子――ギャンブル好きの父親と思春期の息子――は、遅くとも日没直後の第7レースからの投票を目指そうと競馬場へ急ぐ。
但し、例外的に1つだけ鞄に仕舞わず手元に携行したのが、感想文の提出締切に間に合わせるべく出来れば9月中には読み終えたかった文庫本だった。きっと敬愛する二宮金次郎先生が薪を背負い歩きながら読書の時間を惜しまなかった故事を見習い、レース予想の合間に僅かでもページ数を稼ごうとしたのだろう。今にして思えば何という無謀な高校生だったことか。
埠頭が近い所為もあるだろう、秋分を過ぎてなお残暑を引き摺った生温い夜風にも2~3割は秋の気配が混じるようになり、「爽やか」というのが秋の季語であることを噛みしめる。ただでさえ眠らない東京の街灯りに馬場の照明が加わって夕暮れの後も瞑色を保ったままの星空、その下で文字通り砂色に照らされたダートを勢いよく駆け抜ける騎手と馬たち――この光景を眺めているだけでも高揚する。「天高く馬肥える秋」と言うが、食欲が増すのは人間も同じ。瓶ビールのお供は名物の「モツ煮込み」。やや大雑把に刻まれた白葱を合わせ味噌の汁に潜らせ、崩れた豆腐ともども掻き込む。小鉢が半分になったタイミングで七味唐辛子の出番となる。今にして思えば何という早熟な高校生だったことか。
ところで、この年の春、大井では発売と払戻を完全自動化した「馬場内新投票所」が設置され、もうその機材に触れるだけでバルセロナ五輪に匹敵するほどの興奮を覚えたものだった。そう、国鉄の民営化が、私が小学5年となった4月の出来事で、高校生にもなると、もはや23区の鉄道駅では有人改札口が“絶滅危惧種”と化していた。しかし、ギャンブル場のほうは、平成になっても暫くの間、人を介した投票窓口が常識だったのである。
――余談だが、投票所といえば独りでに偲ばれるのが締切前のメロディーだ。とりわけ京王閣競輪場では、締切3分前になると「カチューシャ」が流れ出し、そのテンポに乗って透明板の向こう側のオバさんの動きも慌しくなるといった情況が目に焼き付いている。このロシア民謡の代表曲を耳にする度、私は30年以上経った今でも「リンゴの花」より先に「ピストレーサーの回転」を連想してしまう程だ。しかも、つい条件反射的に選手入場曲の定番「WAY TO VICTORY」まで続けて口ずさんでしまう。誠に血が騒ぐこの2曲は「両A面シングル」のようなものなのだ。
締切1分前になると踏切の警報を二倍速にしたような焦燥感と危機感を煽る音に変わり、1分前と告げつつ実際にはこの音が5分は延長されたりして、その間にオッズが激変したりもする。この如何にも如何わしい恣意的な香りも含め、競輪には競輪の趣があった。それに比べると、競馬場はまだ運営もBGMも上品な部類に属していたと断言できよう。
因みに余談を重ねると、父に連れられて川崎にも花月園にも“遠征”に出かけたのを機に、敢闘門を輝かせる「WAY TO VICTORY」が全国統一の曲だったのに対し、締切前のメロディーは競輪場によって異なることを学んだ。合唱コンクールに准えるならば、課題曲と自由曲との関係である。でも、我々の本拠地はあくまでも京王閣――人生から色を失ったモノトーンの遊び人達の頭上に容赦なく鳴り響く「カチューシャ」と、鍛え上げられた勝負前の漢達の導火線に容赦なく着火する「WAY TO VICTORY」、今はもう聴かれなくなったこのカップリングこそ、私にとっては強烈で刺激的な珠玉の名曲セットだったのだ。
因みに余談に余談を重ねると、京王閣の「閣」とは一体何のことだろう?小学校も6年生になると、こうした知的好奇心が芽生えるようになる。国語辞典の上では「見晴台」とか「御殿」とかいった意味のようだが、当然ながら「ああ、そうか、競輪場も眺めが良いからな」と納得して終わることは無く、この土地の過去を紐解きたくなる。父が「花月園は大昔に遊園地だったんだ」という大ヒントをくれる。区立図書館で「三多摩地域の郷土史」みたいな本を引っ張り出し、難しい漢字や詳らかな年表に苦戦しながら調べると、「京王閣」というのは京王電気軌道の経営していた遊園地で「関東の宝塚」と称される賑わいだったことを知る。新宿育ちの母は京王相模原線がもともと砂利の運搬路線だったことを教えてくれた。どうやら当時は未開発の郊外に娯楽施設を作るのが流行りだったようである。「花月園」も遊園地が先、それが廃業した跡地に競輪場という順序だが、実は「西武園」は逆のパターンで、かつては「村山競輪場」という土地の名を冠していた周囲に後から遊園地が出来たのだそうだ。それに「西武園」の場合は、花月園や京王閣のような「親子の代替わり」則ち「先代の遊園地を潰して、二代目からは競輪場として出直します」といったケースではなく、「夫婦の二人三脚」則ち「遊園地と結婚した“村山さん”は“西武園競輪場”と苗字を変更後も共働きで頑張っている」といったケースで現在に至っている。尚、小学生の私は、あの「東村山音頭」の歌詞に真っ先に登場する風光明媚な「多摩湖」に「遠足」ではなく「社会科見学」で訪れたのだが、それは彼の“本名”が「村山貯水池」という水道局管理の人造湖だからである。
花月園は「西の宝塚・東の花月園」と称されていたそうだが、さっきから出てくる「宝塚」の凄さについては、小学生の私がイメージできるわけが無い。但し、渋谷育ちの人間で五島慶太の名を知らぬ者は居ない故、「西の小林・東の五島」という言葉から、小林という鉄道王が相当に天才的だったことは何となく想像できた。16年後に転勤で関西へ移り住み何年かを経て、池田市の小林一三記念館へ足を運んだ際には、初めて甲子園のスタンドへ足を運んだ折と同じくらい爆発的な感動に全身が束縛された。「甲子園」は球場が先、競輪場が後だが、場所は球場からやや離れ、そもそも「鳴尾競輪場」という名だった。あの競輪史上最悪の暴動「鳴尾事件」の舞台であり、子供だった私は関西人が全員ヤクザみたいなものだと信じ込んでいた。先に球場、後で競輪場のパターンは「後楽園」も同じだが、後楽園はそもそも徳川家の屋敷だったのだから、本当に競輪場の場所に「貴人の住む所」という意味での「閣」があったというパターンだ。甲子園の名の由来が甲子(きのえね)年の建設という縁起担ぎだったのに対し、後楽園のそれは「天下の憂いに先だって憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」という水戸黄門の信条によるものだった。後楽園競輪場は私の生まれる前には閉鎖され、この跡地が東京ドームへと生まれ変わったのは、まさに私が京王閣の研究に夢中だった小6の時分――大袈裟だけど、自転車の車輪の如き“輪廻転生”が、我が思考回路の中に繰り広げられる。
少年は京王閣の歴史を夏休みの自由研究として発表したかったのだが、子供心にも躊躇われ、多摩川の全長138キロを羽田から小河内ダムまで歩いて遡る観察記録を制作することとした。流域の様子を絵地図と文章に残しながら進むので1日10キロが限界。それでも14日で完了する。多摩川なら、歩くのを何処で中断しても、付近に鉄道が通っているので、最寄り駅から帰宅でき、また別の日にその駅まで鉄道で向かえば再開ができる。ウチは貧乏暇なしである。家族で海や山になど出かけられないのだから、宿泊不要で観察旅行ができるという点にも着目した。そこで最も気合を入れたのが、京王閣のある京王多摩川駅付近のエリア解説という次第だ。川を遡ったと見せかけて、同時に歴史を遡った成果を披露したのである。
――話が自転車に脱線したが、場面を馬の夜間競走に戻すとしよう。父は私に「浮世」という科目を教えてくれた先生だったし、私も父から強引に誘われるがまま純粋に「オトナの遠足」を楽しんでいた。地方競馬は中央競馬よりも田舎臭くてレベルが劣るようなイメージがあるだろうけど、私からすれば大井は府中よりもキラキラした存在だった。むろん賭博の場なので基本的には猥雑なのだけど、都心からも近い大井には何処となく洒落た空気感すら漂っていた。その風情とレース展開に夢中になっているうち、手に汗と共に「予想紙」こそ強く握りしめても、ポケットに突っ込んだ「文庫本」を何かの拍子に落としたことなどには気付ける筈も無い。
メインレースが20時過ぎ、最終が21時近くだった。平日開催は帰路がそこまで混雑することも無かったため、順調にモノレールに飛び乗れば、浜松町で乗り換え、22時には渋谷に戻ることが出来た。新潮文庫のオーソドックスなタイトルは大抵どの本屋さんにもあり、当時は22時半まで営業していた書店が近所にあったので、どうにか命を取り留めた。いくら世の中広しと雖も、ナイター競馬で遺失した課題図書を求めに父親と来店した高校生は、さすがに私くらいのもんだったろう。当時は薄いタイプが本体価格で272円、消費税が3%だったから280円だった。当然ながら私の読み方は、的中配当金と同様「“ふた”ひゃくはちじゅうえん」である。
私にとって「文学作品に触れる」という行為の多くは「暇潰しの道楽」というよりも「感想文を書くための準備」に近い性格を帯びていた。従って、引用したい箇所や気になったフレーズには傍線や印を入れたり、ストーリーにリンクする自分自身の体験談や持論等々を簡単にページの端へ書き留めたりと、即ち本の中身を汚しながら読み進めていく癖が身に染み付いていた。だから、落とし物の代償は「本そのもの」よりも「残したメモ」のほうが大きく、途中までは粗筋を知っているにも拘らず、本の中身を再び汚していく目的で最初から読み直さなければならない。この作業負担が痛手極まりなく、レースで損した小遣いよりも高い授業料だったと追想する。
さて、こうした顛末から、活字に目を通した正味時間は読書記録の通り「5時間」だったのだろうけれど、事実上読破までに掛けた疲労感は途轍もなかった。本作品がヒルトン著・菊池重三郎訳の『チップス先生さようなら』であることは言うまでもない。粗筋に引き続き、私の感想文は次のようなものだった。
「私は老教師チップス先生を心から尊敬することができました。というのも、私は彼のように、学業そのものよりも人間性の育成を重んじる考え方に賛成で、そして何よりも彼の悠悠自適な生き方にあこがれているからです。
彼の生き方には、どこか言葉では表せないような『味』があります。それは、キャサリンと知り合ってから、より奥深くなったと思います。彼の生真面目な性格は、彼女の急進的な考えによって、がらりと変わりました。授業ではシャレもとびました。そのような厳しさと優しさに満ちあふれた人間に自分もなりたいと思いました。また、彼は誰よりもブルックフィールドを愛し、誇りをもっていました。学生たちもそれに答えるようにチップス先生を愛していました。私はこのような絆をうらやましく思います。
また、彼が同じガウンをいつまでも着ているように、古いものを大切にする心を忘れてはならないと思います。時代がいくら流れても、手本にすべき古い時代の教えはたくさんあります。それを守っていくのも、私たちのつとめではないでしょうか。」
・・・六十余年もの経験を誇る老教師の人生に向かって「言葉では表せないような『味』」だの「奥深くなった」だのと論っている割に、何と味わいと奥深さに乏しい感想文だろう。「貴様は何のために校舎から厩舎へ直行したのか、その盆暗頭で少しは考えなさい」と高校1年だった私を叱咤していると、やがて逆に「昔の私」の文章から「今の私」が習得すべきものを発見する展開となる。目に見える文字に起こせていなかったというだけで、私はトゥインクルレースの体験をしっかり活かそうと努めていたのだった。その魂が行間から滲み出ているではないか。
まず序盤では「私は『父』を心から尊敬することができました。というのも、私は彼のように、学業そのものよりも人間性の育成を重んじる考え方に賛成で、そして何よりも彼の悠悠自適な生き方にあこがれているからです。」と吐露する。次に中盤に入ると「彼は誰よりも『大井』を愛し、誇りをもっていました。『息子』もそれに答えるように『父親』を愛していました。」と吐露する。こうなると終盤に「時代がいくら流れても、手本にすべき古い時代の教えはたくさんあります。『モツ煮込み』『有人投票所』『カチューシャ』それを守っていくのも、私たちのつとめではないでしょうか。」と結んでいるのが、殆ど違和感なく消化できる。爽やかな秋風に吹かれて私はこう主張していたのだ。本音のところチップス先生に憧れてなど居なかったのだ。それでも感想文としての体裁を何とか整えなければ格好がつかないから、「先生」を「父」と読み替えたのである。表面的な意味は一切変えること無く、「生真面目な老教師」を「不真面目な反面教師」へ置き換えてしまうなんて、なかなかの芸当ではないか。あの頃の父の年齢に追い付いた現在の私は、この拙くて短い感想文を以上のように解釈している。悔しいかな「たかが宿題の紙切れだろうとも、何かの節目に人生を振り返る教科書になり得る」という鬼の教えは、馬券よりも高確率で見事的中していたわけだった。
そういえば、「モツ煮込み」と同じくらい場内の食堂で名物だったのが、昔ながらの「醤油ラーメン」だ。今もメニューに残っているのだろうか、鶏がらスープに鳴門と焼海苔をトッピングした典型的な東京の中華そば――アレが京都の店には皆無に等しい故、時折ではあるが無性に食したくなる・・・つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
