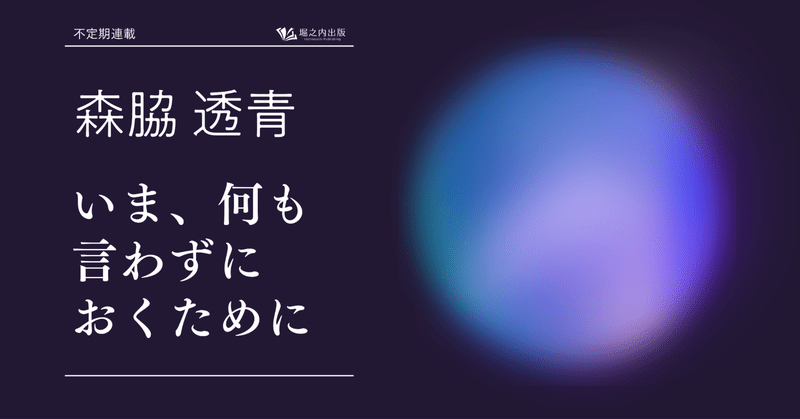
【いま、何も言わずにおくために】#001:意味の考古学 前編|森脇透青
※こちらのnoteは森脇透青さんの不定期連載「いま、何も言わずにおくために」第一回の前編です。他の記事はこちらから。
はじめに
いま、私たちの身の回りにはフィクションおよびフィクションに関する言説が溢れている。それに触れずに生きることはもはや困難である。そのフィクションの濁流こそが現代を特徴づけていると言ってもいい。
このnote連載で私は、現代において「フィクション」が持つ機能と意味を、さまざまなアーティスト、批評家、研究者たちとの対話を通じて探究していこうと思う。この第一回では連載全体の前置きあるいは基調報告のようなものとして、私の立場を簡単に示しておきたい(noteの仕様上、脚註は最後にまとめてある)。フィクションをめぐって、いま何が問題となるのか?
先に言ってしまえば、私は、いま「批評」の課題は、フィクションをめぐる状況全体を批判的に考察することにあると考えている。それは同時に、現代の社会状況を理解し、言語化し、その批判の可能性を探ることでもあるだろう。フィクションを通じて時代に対する批判を加えること、そして「時代」に抗う作品にこそ可能性を見いだすこと。それこそが「批評」の「伝統的」な試みである。だが、私はこうした「批評」を開始するにあたって、他者との対話という形式を選ぶことにした。それは私の試みをたんに独りよがりな理論としてではなく、具体的かつ実践的なものとして、創作や批評の現場と結びつけながら提示するための一種の「実験」なのである。
私自身についても自己紹介程度に触れておく。東日本大震災後、私は日本において「批評」と呼ばれてきた営為を発見し、惹かれ、それ以来「批評」の読者であり続けてきた。「小林秀雄以来」としばしば言われる日本の「批評」とは、人文学の一種でありながら、大学的な専門知の外部に立ち、さまざまな領域を横切りながら人々に語りかけようとする、「奇妙に思弁的な散文」である[1]。それはおそらく、公共的な「哲学」というものを現代に至るまで持つことができないこの国において、「哲学」の代わりに、その代わりを埋めるもの(「代補」)として機能してきたのだ。
あのとき、無知で粗野なひとりの高校生が「批評」に惹かれたのは、その内容以上に、その存在そのものの謎、その不安定さのせいだったのだろう。私には、「批評」という営為が何かよくわからなかったし、当たり前のものとはとても思えなかった。目的も動機もよくわからず、とりたてて磐石な基盤も持たない、このような営為がなぜ日本に存在しつづけ、それなりの数の読者を獲得しているのか、私にはそれが不思議でたまらなかった。
他方、大学の哲学科にたまたま入学してしまった私は近現代の西洋哲学を学び、院に進むころにはジャック・デリダというフランスの哲学者の思想を研究上の専門として選ぶことになった(現在、デリダに関する博士論文を執筆中である)。そしておそらくデリダという哲学者は、「西洋哲学」という伝統的営みそのものに大きな違和感と魅力を感じて、生涯にわたってそれにとり憑かれてしまったひとである。彼は「哲学」に対する違和感を捨てられない哲学者だった。私がデリダにそれなりの親近感を覚えて集中的に読んできたのは、そのせいかもしれない。
要するに私はたぶんこの十年ほど、人間が何かを考え言葉を発するということそのものについて考えていた。だが私のなかでその思考はいつも、日本と西洋(「批評」と西洋哲学)、大学の「内」と「外」(アカデミズムとジャーナリズム)、理論と実践といった領域に引き裂かれて、つねに二重のものになってしまうのだった。私にとって、読み、書き、語る行為がシンプル(単一)なものであったことはない。このステートメントは、そうした深刻な二重性を私なりに整理したものでもあるかもしれない。
1. 批評の民営化
認めていただけると思うのですが、この「何も言わずにおくこと」は絶対安全な試みなどではないのです。
批評の時代である。それは、この国において「批評」と名指されてきた独特の言説がかつてなく権力を持ち、人々に支持されているということを意味しているのではない。大上段に構えた知識人たちがテクストを読み、現実に即して発言し、時代を批判し、価値を創造し、大衆を導くような、旧来の大文字の〈批評〉のモデルを、私たちはもはや想像することさえできない。そうではなく、いまや誰もが批評をなしうるし、実際に批評をなしているからこそ、批評の時代を語ることができるのだ。あるいは、それは批評の「民営化」と呼ぶべき事態である。
そもそもなぜ(大文字の)〈批評〉が、かつて必要とされていたのだろうか。誰もが知っているように、神なき資本制民主主義の制度においては、「価値」は本質的な多様性に満ち溢れている。価値は決定不可能=「人それぞれ」である。作品「それ自体」の価値など存在しない以上、この社会では「いいもの」も「わるいもの」も等価な「商品」として現出する。〈批評〉は、どの近代社会においても、そのような商品の「渦」的混乱と競争のただなかで善悪あるいは好悪の規範を仮構し、大衆たちが作品を消費するための趣味判断の指針を示すものとして機能してきたのだ。
言説を流通させる手段が少なかった時代には、一定の批評家たちのみが言説の流通ルートを寡占し、読者はそれを通じて作品にアクセスし、その価値を測量するしかなかったかもしれない(ゆえに批評家はその権威主義的欺瞞を揶揄されもした)。しかしいまや、読者たちはみずから語ることができる。規範は必要ない。誰もが批評をしているし、誰もが自身の消費の基準をみずから作り出すことができる。誰もが小さな批評家なのだ。この時代、人々に向かって判断の指針を示すような〈批評〉は、もはや不要なのかもしれない。
2. ふたたび意味という病
意味に憑かれるという病は「近代」から始まったのではなく、むしろ「近代」を生み出したのである。
驚くべきことに、いま、ひとびとはある作品の中にすぐさま意味(sense)を読み取り、「理解する」(make sense)ことができる。批評の時代とは、意味の時代である。特定のシーンから現実の出来事の寓意を読み取ったり、特定のセリフの「背後」——深層——に作者からのメッセージを見つけ出したり、あるいは読み手自身の人生に引きつけて理解することは、いま、一般にひろく行われている(この事態は、むしろ、リテラシーの向上と受け止めるべきなのかもしれない)。あるいは、よりリベラルな読者は、ある作品の中に「差別」と「反差別」の意味の力学を見つけ出し、進歩的な点と反動的な点のバランスを指摘して点数をつけることもできるだろう。
こうした行為は、かつてのように大文字の〈批評家〉たちに占有された試みではない。意味のおかげで、小さな批評家たちは流行の小説や放映中の映画や開催中の美術館展示や、売り出し中のアイドルや配信者について何かを語りあう「おしゃべり」(Gerede)に熱狂することができる。現代において「作品」は、語られるために存在しているのである。
作品は、いかにそれが二次的な言説を生み出すか、つまり「場所(プラットフォーム)」としていかに機能するかによってその商品価値——費用対効果および耐用年数——を測られている。作品それ自体の価値が先にあってその後に批評的言説が続くのではない。言説——「おしゃべり 」——の端的な量と流通速度が、当の作品の価値そのものなのである。このとき、消費者たちが実際に享受しているのは、外在的に自律した作品の価値ではなく、作品に紐づいた自身の消費行動そのもの(見ること、語ること、共有すること、投稿すること……)なのだ[2]。
対象が宮崎駿だろうが庵野秀明だろうが村上春樹だろうが芥川賞作家だろうが、それを受け取るひとびとが右翼だろうが左翼だろうがノンポリだろうが同じことだ。また、「解釈」が最終的に「作者の意図」に付き従うものであろうが、それを無視した「独自の」読解であろうが同じことだ。内容のレベルや立場、倫理的/非倫理的、批判的/肯定的の区別にかかわりなく、形式的にはいずれも、すべて意味にすぎない。
矢継ぎ早に供給されてくる「新作」について人々がいちいち考察をめぐらせ、語り合い、共同体を形成したり、あるいは右や左に分化して対立したりすることができるのは、意味のおかげである。言い換えれば、かつてなくひとは意味というこの基礎概念に安住している。あるシーン、あるシークエンス、あるキャラクター、ある発話といった、フィクション内に現象する任意の表現的要素を意味に「変換」することは、今日、きわめてスムーズに行われている。「変換」の作業は、次々と目の前に運ばれてくる商品のバーコードを読み取るレジのスキャナーに似ている。それは驚くべき速度と機械的な能率で行われる。
この「変換」の出来事ののち、解釈をめぐる闘争が生じる。そしてこの解釈の闘争においては、意味そのものが問われることはない。つまり、「解釈違い」は重々承知されているにしても、「解釈」という行為そのものを疑う者はいない。意味は、他人(「友」であれ「敵」であれ)とコミュニケーションするための場=媒介(メディア)として機能している。
闘争はどのようなものであれ、コミュニケーションの様態のひとつである。表面的な政治的対立や「分断」とは無関係に、日々交流は問題なく行われているのだ。しかし、私たちのコミュニケーションの基礎に居座る意味は、決して所与のものでも自明のものでもない。
自身が読み取り・語っている意味そのものの安定した自律性を疑わず、いまだに他者と共通のコードでわかり合えると思い込む者たち。ここにはおそるべき共犯性と癒着がある。小さな批評家たちは、「任意の表現的要素」と意味のあいだに、また自己と他者のあいだに大きくまたがっている渓谷のような隔たりを、自身が飛び越えていることに気づかない(あるいはその渓谷に落ち込みつつあることにも)。それゆえに、小さな批評家たち(スキャナーの群れ)は自身のセンサーにあらかじめプログラムされた意味をただ反復することに甘んじるのだ。
もちろん、このような意味への安住は、たとえばSNS上で匿名のうちに語る読者たちだけに適応可能なのではない。当然だが、私の目的は大衆たちを告発することにはない。最近のメディアに自身の署名つきで文章を掲載する「批評家」たちもまた、充分意味に安住しているように見える[3]。
だから、いま「批評」がさしあたり課題とすべきなのは、特定の意味を雄弁に語ることではない。私たちはむしろ、健全に感染し充満していく意味の発生を問うべきなのである。〈批評〉の民営化とは、意味という病(柄谷行人)がもはや「病」とは看做されなくなった状態である。だとすればいかにも健康そうに見えるこの相貌を「病」として診断するところから、新たな「批評」が始まらねばならない。この「批評」が「大文字」のそれなのか「小文字」のそれなのか、それは今のところは考えずにおこう。
3. 「言おうとすること」の時代
私の関心は、今のところはその意味の次元において何かを語ることの方ではなく、いかにも融通無下に流通しつづける意味の起源を辿ることにこそある。言うまでもないことだが、意味の発生へ向かうこの思考は、「あらゆる意味は等価」だとか、「読みは人それぞれで自由」だとか、「解釈は多義的だ」と言った相対主義とはなんの関係もない。解釈の多義性などたかが知れている。そうした相対主義は、「ポスト・モダン」や「テクスト論」という卑俗かつローカルなレッテルのもとで語られてきた。私たちの営みはそれと異なる。私自身は少なくとも、意味のあいだに特定の優劣が存在することを疑っていない。あらゆる価値を「宙吊り」にすることは問題にならない。どういうことか。
意味の意味について熟考した哲学者であるジャック・デリダは、現象学者フッサールにおける「意味」(Bedeutung)の概念を「言おうとすること」(le vouloir-dire, want-to-sayに相当)とあえてフランス語訳した(『声と現象』1967年)。この翻訳を通じて、デリダは一見中立的に見える伝統的な「意味」の概念が、つねに「言おうとする」主体の意志に紐づけられていること、主体の権能のうちにあることを暴こうとする。
この時期のデリダの著作で繰り返し批判的に考察されるのは、哲学者たちがこの「言おうとすること」、つまりは主体—意志—意味—言語—対象といった連続性を疑わず、それに不当な権威を与えてきたことである。こうした伝統的な解釈において、言語とは、主体が自身の意志する意味内容を託す透明で便利な媒体にすぎない。デリダはそれに反旗を翻しつつ、言語ないし媒介機能一般を、より複雑な(場合によってはより創造的な)運動——差延——として考えなおす[4]。
たとえば批評家の蓮實重彦は70年代にはすでに、こうしたデリダの企図を充分察知していた。彼は『声と現象』を念頭におきながら、デリダの別の著作『グラマトロジーについて』(1967年)について以下のように総括している。
『グラマトロジーについて』の全編は、何もいわずにおくことの華麗なる実践なのである。〔…〕何もいわずにおくことは、「何かをいおうとすること」と、そのいわんとする「意味」の解読とが絶対的な「書物」の時代、最後の「レクチュールのレッスン」なのだ。
※強調は蓮實自身による
ここで蓮實が述べる「何もいわずにおくこと」は、まさに意味しないことに向かっていく運動を指している。実際、批評の時代=意味の時代とは、誰もが何かを「言おうとする」時代であり、その病的な強迫が最大限のものとして押し寄せてくる時代である。ぜひとも何かを言わねばならない、それこそが現代の強迫なのだ。
それは小さな批評家たちだけにかぎった話ではない。「クリエイター」たちもまたこの病に感染している。たとえば、現代のアーティストたちや文学者たちは、「作品」制作以上にステートメントの公表——作品の意味、作品が「言おうとすること」の自己解題、「作風」の自己説明——に、言い換えれば「自己PR」に力を入れているように見える。このような状況では、個々の作品は(どれほど多義的な解釈を喚起し称揚するように見えても)基本的にはステートメントに、さらにはその作家の諸属性に従属する一部品にすぎない。このとき「物」は意味に従属しているにすぎないのである。
だが、私たちが意味の時代を、つまりは誰もが何かを「言おうとする」この時代を警戒するとしても、その目的はまったくの無意味の静けさのなかに沈黙することではない。結論から言えば、意味のざわめきから逃避した安息の場所など存在しない。蓮實が適切にも指摘しているように、デリダの「何もいわずにおく」実践は、沈黙や逃避ではないし、また「無意味さ」——それはいまだ意味の相関物でしかない——を特権化する思考でもない。私たちはむしろ、「何もいわずに」、しかし同時に雄弁に語り倒してみせたいとすら考えている。それでは、何も言わずにおくことは、いったい何を言おうとしているのか。
【後編に続く】
註
[1]「新しい情報の提供があるわけでもなく、新しい価値判断があるわけでもない、ましてや学問的研究の積み重ねがあるわけでもない、なにか特定の題材を設定しては、それについてただひたすらに思考を展開し、そしてこれいった結論もなく終わる、奇妙に思弁的な散文」(東浩紀「批評という病」、『ゲンロン4』所収)
[2]このような指摘自体はよくあるものである。他方でこの自己言及的なシステムには、きわめて精神分析的な構造を見てとることもできるだろう。自身が享受しているものが実際には「自身の消費行動そのもの」である、というナルシシズム的な退行と悪循環を隠蔽するために、人々は消費の対象が自身から隔絶した「外部」に存在することを演出する(たとえば「推し」)。自己の内部にしかない対象を自身には到達しえない不可侵の「超越」であるかのように見せかける見えすいた計略(「尊い」)は、実際には内的に閉じている自家撞着の働き(自己愛)を否認し、それを外部との関係(対象愛)に偽装する働きにすぎない。たとえば「推し」に「認知」されることが時たま不気味なアレルギー反応を起こすのは、その超越的対象が実際には自我の内部にしか存在していないことが暴かれる危険に自我が接しているからなのである。このとき、現実存在としての「推し」は、自我の内部にある「推し」の観念に対する脅威、つまりは閉じた自己愛構造を破壊するかもしれない脅威として現象する(なお誤解のないように言っておくが、精神分析は自己愛を糾弾するための道具ではないし、私の意図もそこにはない)。
[3]たとえば典型的な症例として、映画批評家の伊藤弘了の『万引き家族』についての評を見てみよう。ここで伊藤は是枝裕和の作品中に繰り返し「入浴」のシーンが現れることを、ひとまずテマティックな手続きで確認する。だが、最終的に伊藤はこの入浴のシーンを「血のつながり」のない「家族」を表現するメタファー(水は血より濃い)として、是枝作品全体に通底する核心的な「意味」として論じる。ここには、画面上で反復されるシーンにかんする発見が、すぐさま——無難で誰も傷つけることのない——凡庸な「意味」へと変換され癒着する事態を見ることができる。この読解の帰結そのものに異議を唱えることは本稿の課題ではない。しかし伊藤はここで、同型のシーンの反復という自身の発見を即座に「意味」に変換することになんの躊躇いも覚えてはいないし、またそれゆえか、「家族」という危険な主題にもなんら警戒を示さない(それは是枝の作品の魅力を伝えているのか、それとも単に——伊藤のいう「教養」があればわかるはずだが——どこにでもありふれている「血のつながらない家族」の美談的凡庸さを露呈させているだけなのか?)。伊藤の批評は、そのように何かを「言おうとして」しまう強迫を避けられず、そのことによって象徴主義に落ち込むのである。この「意味」への警戒の薄さによって、伊藤の読解は映画上の運動を——「意味」以前の運動として——取り出すテマティスムの禁欲的な試みから、イメージの背景に潜む「意味」を疑うことのない平凡なイコノロジーへと退却する。私はここでテマティスムを最も有効な最終理論として肯定したいのではなく、その分析と主張、読解と意味づけのあいだに伊藤がなんらの緊張も覚えていないことを、その批評的欠陥として指摘しているのだ。しかしいずれにせよ、良くも悪しくも、伊藤の図像解釈学的批評を、観衆の目の前でパズルを解いてみせるスペクタクル以上のものとして評価することはできない。
[4]「私が試みているのは、言うこと、および「言おうとすること」の問いが提起されるような空間を(その空間において)書くことです。私は問いを、すなわち「言おうとすること」とは(何か)、という問いを書くことを試みています。したがって必然的に、そのような空間のなかで、このような問いに導かれて、エクリチュールは文字通り「何も言おうとしない」のです。それはエクリチュールが不条理だからではありません」(デリダ「含蓄的絡み合い」、『ポジシオン』所収:本稿でのデリダからの引用はフランス語から直接翻訳しているため、日本語訳とは文面が異なる)。
なお、こうした60年代デリダの取り組み及び「差延」の概念について、私は森脇透青ほか『ジャック・デリダ「差延」を読む』(読書人、2023年)のなかで一通り解説している。
【後編に続く】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
