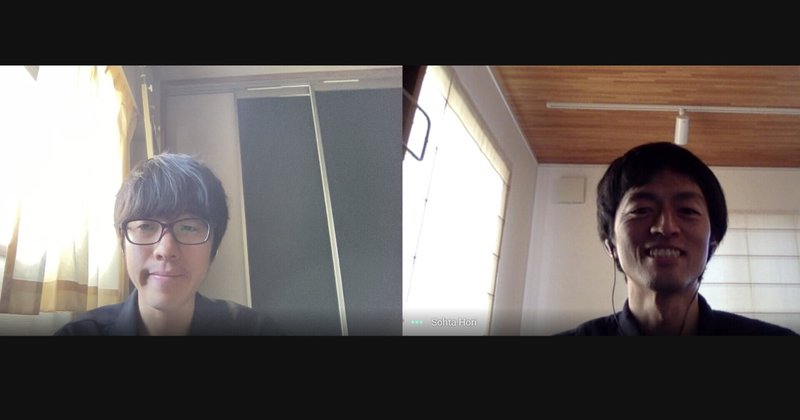
MATCHA・青木さんとの雑談 #オンライン朝活
「堀さんが人事をしているので、人事の話をすると思っていた(だけど、あまりしなかった)」
と青木さんが語ったように、僕も「経営者としての青木さんや、MATCHAにまつわる組織論」についての話をするだろうと思っていた。
*
青木さんが今年から始めたオンライン朝活、有難いことに一緒に対話する機会をいただいた。朝8〜9時、Google Meetで話をするというもの。
青木さん曰く「オンライン朝活は、ノーアジェンダで好きなことを話す場」。そのスタンスはまさに言葉通りで。前日にGoogle MeetのURLを教えてもらうだけで決め事は一切なし。当日の朝8時、ゆるりと「初めまして」から始まった。
*
ノーアジェンダだったとしても、お互い「大人」なわけだし、どのような話題が展開されるかは多少なりとも想像がつくものだと思う。
だけど最初の5分間ほど、アイスブレイク(という感じもしなかったな)的な導入を交わしながらも、残りの55分間、どういう話をしていくか全く読むことができなかった。
僕らが完全に初対面だったことを差し引いても、予定調和が求められていなかったのは事実だったと思う。そのときに直感する空気感を、青木さんが大事にしようとしていたのではないか。
加えて、青木さんの人柄も大きい。
喩えるならば、近所に構えるお寺や神社のような存在感。どうぞどうぞと歓待する感じではなく、おおやけに門戸が開かれているような。あちらこちらと巡る他者の想いに呼応するように、青木さんが絶妙なボールを返してくれる。
自然体で、自在な関係性を紡いでいく。それが青木さんの大事にする「余白」の在り方なのかもしれない。
*
振り返ってみれば、1時間の「雑談」はあっという間に終わった。
ジブリと瀬戸内芸術祭という、異なるプロジェクトの共通点の話が起点になって、お互いが大事にしている「余白」についての話へ。
「余白」という言葉は近年それほど珍しい言葉ではなくなって、わりと価値観として「余白のある生活」というものが大衆化されていると思っていて。でも、だからこそ、僕はもうちょっと余白の正体を感じたかったし、青木さんの口から余白の定義(らしきもの)を聴きたいと思った。
・青木さん曰く余白には3種類ある。組織に関する余白、他者に関する余白、自分自身に対する余白
・自分自身に対する余白は、突き詰めていくと「自分らしさ」になる
・余白とはspaceなのかmarginなのか
・時間のことを指しているのか、思考の在り方を指しているのか
・余白があると何が有意義なのか
・本当は余白がある人生なんだけど「余白がない」と感じることはありそう
・いわゆるメモ帳(ページ全てが書き込める媒体)は、余白的なのか
・余白って、ありすぎると疲れてしまうよね
・教科書の片隅にあるスペースがちょうど良いかも
・教科書の片隅に落書きってするよね
・教科書への落書きって、自分らしさを象徴しているものかもね
・余白を「組み立てる」ということ
・たった0.1%の余白だったとしても場合によっては「十分である」と言える
・てことは適切な余白というのは人それぞれで相対的なもの?
こんな風にするすると色々なアイデアが出てきた。話がひと段落したときに、おそらく、青木さんと僕とでは着地点が違っていたように思う。
無理に合意をする必要はなくて。お互いが今後更に思考していく上で「着想を得た」という感覚に近いのかもしれない。(僕が青木さんの思考に影響を与えたということではなく、対話そのものが着想を得るために有効な手段なのだろうと推測している)
*
「自分(青木さん)にタグをつけるとしたら何か?」という問いも、面白かった。こんな風に自然と他己評価を求められるのも、青木さんの、しなやかな強さだ。
普段noteなどで青木さんの考えや行動に触れているとは言え、対話するのは掛け値なしに意義のある時間だった。
聴き手としてのClubhouseというメディア(あえて「メディア」という言い方をする)は、使い方によっては価値のある情報を得られるかもしれない。だけど感覚的には「受ける」というスタンスだけでは、その先に転用する内発的な推進力を持ちづらいようにも感じる。
対話で求められる役割は、受け手(耳)と送り手(口)の両方だ。
インプットとアウトプットを即興で繰り返すことで、頭の中は次々に躍動していく。読後感が清々しいだけでなく「この刺激をもとに何をしていこうか」を考えるきっかけになると気付いた。
本当に楽しかった。
自分でも、こういう機会を作っていけたらと思う。
青木さん、本当にありがとうございました!
記事をお読みいただき、ありがとうございます。 サポートいただくのも嬉しいですが、noteを感想付きでシェアいただけるのも感激してしまいます。
