シク教研究の成果 ー保坂俊司
シク教研究の成果

シク教の聖地ゴールデン・テンプル(ハリ・マンディル・サヒブ)
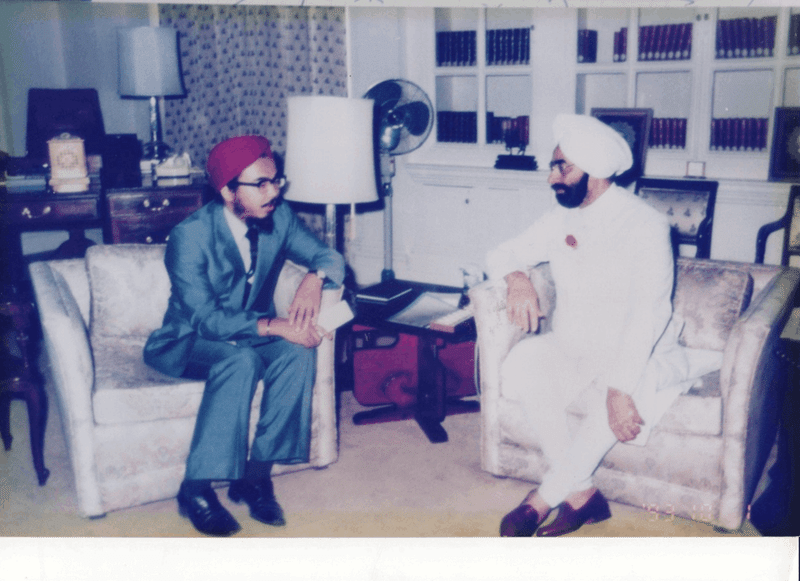
ラシュパティ・ババンにて、第七代インド大統領ザイル・シン閣下
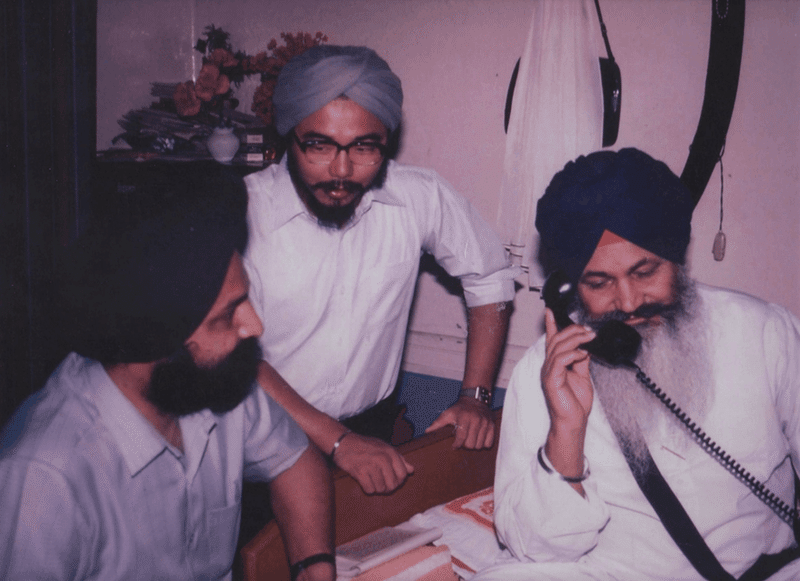
シク教教団総本部SGPCの総裁ロンゴランワレ師と
シク教の研究
科研研究を含む
融和・共生思想の研究
寛容思想をキーワードとして
インドと日本の宗教融和思想の研究
初期シク教グル・アマルダスの融和思想
第一部
今や余り意識されないが、20~30年ほど前までの国際社会では、米ソ冷戦構造、つまりイデオロギー(政治思想・体制)対立が、極めて深刻であった。しかし、1991年のソ連邦の崩壊と共に、再び宗教間の対立紛争が、世界各地で引き起こされるようになった。この古くて新しい対立構造である宗教間の対立は、過激原理主義思想を暴力的に展開する一部のイスラム教徒による無差別的なテロリズムにより、国際社会の新たな不安定要因として強烈に印象付けられた。
確かに、2001年の9.11事件(ニューヨークの貿易センタービルヘの航空機による大規模テロなど)は世界中を震撼させた、イスラム教やイスラム教徒へのないナスイメージが形成された。しかし、たとえ一部であろうとも、イスラム教徒をこのようなテロリズムへと駆らせる要因を作った側の反省や、自己分析は余り聞こえてこず、彼らの理不尽さや凶悪さばかりに報道が偏る傾向もあり、イスラムと非イスラム間の対立は、収まるどころか却って大きくなっている。特に2014年のIS(イスラム)国の出現とその後の混乱は、その独善的な異教徒や他宗派信者への過酷な扱いかたに加え、イスラム原理主義の現代的な展開としての可能性を示したことで、大きな驚きを引き起こした。
勿論、筆者は過激なイスラム原理主義者というより、イスラムの理想を自己流に解釈して自己の欲望を、宗教的正統性を装うって満足させようとする一部のイスラム原理主義者達の言い分や、その行動を肯定するものではない。しかし、彼らが執拗にあおった他宗教、あるいは他宗派への敵意の根源に、他者への寛容の精神の欠如があったことは否定できないであろう。本来的には、寛容と慈愛そして、平和を説く宗教とイスラム教の教えを自認するイスラム教徒の中から、彼らの媼過激な行動を取る集団を生み出した諸々の背景を描き出す必要がある。つまり、イスラム国に代表される異教徒、異宗派への不寛容なイスラム解釈が、歓喜を以て受け入れられた、その背景の分析が必要である、ということである。そうでないと、イスラム内におけるこの新しい宗教運動、教理解釈の持つ意味が明らかとならず、今後とも多くの混乱や犠牲が生まれることが予想されるからである。少なくとも、宗教の名の下に、あるいは正義の名の下に、多くの命が犠牲になることのないような社会の構築を目指すことが重要であろう。それは、勿論イスラム過激のみならず、これを攻撃する欧米の側にも云えることである。彼らが、中東を中心に広くイスラム圏で行ってきた現代の十字軍とも言われるような軍事行動への反省を含めて検討は、真摯に行われてしかるべきであろう。
勿論、本成果報告書において、そのようなことを直接扱うわけではない。本報告書で扱うのは、宗教や民族の対立において特に強調される他者への憎悪や敵意の軽減や解消の可能性、さらにそれを包括的に寛容思想と認識し、その寛容思想の考察である。具体的には、度重なる異民族、異教徒の略奪や、過酷な支配に苦しみつつも、他宗教・異民族との平和的共生、それは後に検討するような近代的な平和ではなく、相利共生関係の構築を通じて精神レベル、宗教レベルからの相互理解と尊重、そして相利共生関係の平和思想であり、この思想を可能にする寛容思想の検討である。そしてこの寛容思想を異教徒間、具体的にはヒンドゥー教とイスラム教間の対立を超えることを目指し16世紀初頭にうまれたシク教における寛容思想の検討である。加えて、その宗教的な理想を現実社会において実現すべく、独自の教団そして最終的には独立国家において、シク教的な平和社会の実現へ展開するその寛容思想の検討となる。その際に、シク教という宗教や思想が、殆どしられていない日本に於いて、彼らの思想的な意義を理解すること、またインド宗教思想史上に、シク教の存在を位置づけることもが必要である点をふまえて、シク教思想形成に至るまでのヒンドゥー教、イスラム教の思想的な流れを鳥瞰的検討もおこなった。
21世紀にシク教を研究する意義
21世紀のグローバル社会における国際社会の課題は、異なる価値観を持つ人々との共存、それも単なる共生ではなく相利共生関係を基本とする共生思想の構築が不可欠である。そこで、この相利共生思想の基本として、寛容思想をキーワードとして、特に異教との共生が今後問題となるであろうイスラム教と非イスラム、中でも彼らが偶像崇拝者(カーフィル)として、忌避する仏教、ヒンドゥー教、神道などとの共生の可能性を考える上でも、中世インドにおいて、軍事的にも、宗教的にも厳しいイスラムと、カーフィルの典型でもあうヒンドゥー教との共生、そして融和的な共生の可能性を開いたシク教の存在は、注目すべき点がある。
勿論、その理想はやがて多くの社会的な試練に余って大きく損なわれてゆくのであるが、とはいえ、異なる宗教の共生を唯一の神(ワイグル)ヘの信仰によって、その暴力性や最大限に限定する努力を行い、シク教を中心に諸宗教の共生社会が形成されるその過程を実際歴史的におうことで、我々は大きな教訓を得ることになる。
というのも、インド中世においては、イスラムとの共生の実践が、現実になされ結果としてヒンドウー・イスラム文明とも云える共生文明が実際に展開し、特にその象徴的な存在としてヒンドゥー・イスラム融合宗教とも云えるシク教という世界に展開する宗教が生まれたのである。
このシク教を生み出したヒンドゥー・イスラム融合文明は、イスラムと全く宗教的な関係を持たない、というよりイスラムが尤も忌み嫌う多神教(カーフィル)との融和関係が構築された、という点で21世紀における国際社会における宗教共存関係を形成する為の大きな可能性の存在を我々に示唆するものである。
さて、以上のような意義を踏まえてシク教の寛容思想検討とその現実社会への具体的な展開に関して検討することになるが、具体的な検討のまえに、本テーマを検討する上でキーワードとなる言葉の検討から具体的な検討を始めたい。というのも、意見明白に思われる言葉も、異文化、異宗教、さらには異文明の検討に於いては、その言葉の持つブレや曖昧さが、明確な検討に時として悪影響を及ぼす危惧があるからである。
そこで、言葉への先入観を捨てて、より普遍的な意味へを把握すべく文明と宗教に関する報告者の基本的考えを簡単に述べておきたい。この点で重要な視点は、布告者が宗教を単なる信仰の体系というような狭い意味で取られないという点である。真s婦負者は、高名な丸山真男の講義録しばしば振れているように、文明の祖型、あるいは意外といっても良いであろうが、プロトタイプとして宗教が大きな役割を果たす、という視点かを考えている。いわば宗教文明論なのである。そこで、重要な者が、文明の構造を筆禍于を通じて、サライは人類尾発展史を通じて考察するという比較文明学という学問である。以下ではこの点から論考を始めたい。。
比較文明という発想
先ず、文明の概念化から検討しよう。「比較文明学」は、巨視的な視点を持ち、かつ人類の知的営為を総合的に研究する事を目指してきた学問であり、文明学は、人間の営為をその生存形態の発展史という統一的な視点で捉え、これを総合的に考察する学問である。この学問によれば、人類は嘗て5つの大規模な革命的な変化を経験し、今また規模は小さいながら新たな革命時期を迎えているということになります。その5つとは、比較文明学の泰斗伊東俊太郎(1935~)によれば、先ず、猿人から二足歩行の人類が生まれた「人類革命」にはじまります。最新の研究でその起源は、おおよそ500万年前の東アフリカでのことである。その後、第二の革命として「農耕革命」が、今から約1万1千年前に中東ではじまり、我々の生活に大きな変化をもた。この「農業革命」により人類は、自ら食糧の獲得(生産)を管理できるようになり、生産技術の工夫を重ねることで、食糧に大きな余剰を生み出すことが出来る。
そ の結果、今から約4500年前には、中近東において「都市革命」という段階を迎えることにとなりました。この第三の革命である「都市革命」を、第35代アメリカ大統領故ケネディー大統領の言葉を借用して表現すれば、「都市革命は、人類による、人類のための、人類の生活空間の創出である」。この「都市革命」により、人類は自然の圧倒的な影響下から脱し、人類にとって快適な生活環境を手に入れることが可能となった。この「都市革命」の結果生まれた都市生活では、「この世界を合理的統一的に思索し、そのなかにおける人間の位置を自覚しようとする」(伊東2009)知的な営みが生まれたそれが第四の「精神革命」と呼ばれる段階であり、この段階では高度宗教や哲学が誕生することになる。
この「精神革命」は、おおよそ紀元前八世紀から同四世紀の間に掛けて中国、インド、イスラエル、そしてギリシアに発生した。そして、最新の第五段階として「科学革命」が、17世紀のキリスト教の伝統が息づく西欧において、いわばその宗教勢力と対峙する形で生まれた。この「科学革命」の中に、18世紀後半に生まれた「産業革命」があり、そしてこの「産業革命」の最先端に、「情報革命」によって生まれた高度情報化社会であり、これを情報文明の時代と表現するのである。これが比較文明学の理解である。
人類文明史を鳥瞰する
続いて、比較文明を理解する上で重要な、文明概念であるが、その前に文明とはどのように定義できるのであろうか。この問題に応えるのは、実はそう簡単ではない。というのも、「文明」という言葉とその概念は、「十七世紀の西欧という特殊な地域に於いてのみ生起した」(伊東、2009)科学革命と呼ばれる西洋近代文明下に生まれた科学的思考を基礎としている点で、地域や時代の限定を持つ、特殊性ある知のあり方で、それは決して万能な知のあり方ではなく、時には欠点にもなるの知のあり方なのである。つまり、科学革命によって生み出された科学文明は、理性や合理性を強調するあまり、自己中心、人間中心主義に陥りやすく、他者や自然との共生が疎かにされる傾向があるということである。
もちろん、この科学革命は「歴史的意義は直ちに全世界史的な意味をもった」(前掲書)ものであり、グローバルに共有された思考法である。しかし、その限界を理解しておく必要がある。例えば、最近の科学技術の暴走による環境破壊が、地球環境の危機を生み出したことは、科学文明の問題点の現れである。
いずれにしても文明という概念は、科学革命と呼ばれる時代に優勢となった思考法によるものです。それは対象を抽象化し、特定の単位に置き換える事で、客観化し分析するという科学思想を基礎としている。こうすることで、人類史という対象を客観的に理解することが可能となり、それぞれ異なる地域や時代、あるいは社会が、一つの価値観で認識できるようになった。
その結果、人類史を分かりやすく理解するために文明という概念が生み出された。特に、農業革命を経て生まれた都市という、人類特有の生活空間の形成以後、人類の生活スタイルは激変する。これが先に示した都市革命であるが、この都市革命によって人類の生活形態は、多様化した。そこで、この都市化以降の段階を特に文明期と呼び、それぞれの特徴を冠して○○文明と呼ぶようになった。そこでこの人類の進化を、分かりやすく比喩的に表現すてみると、人類はその発生時から力を合わせてビルを作り上げてきたと表現できることとなる。
この人類のビル建築作業は、都市を中心とする文明期に入ると一層発展し多様化する。すでの紹介したように、「都市とは、人間による、人間のための、生活空間」と云うことであるため、この都市空間で人間は、自然からの制約から自由となり、人間の生活の快適さを求め知恵を巡らし、都市生活の充実のためにあくなき探求を試みてきた。その結果、人類が築いた文明の高層ビル化が一層進み、また複雑化した。そして、文明概念もそれぞれの階層やフロアーの特徴を表現するキーワードとして、多種多様に用いられることになった。いずれにしても文明とは、政治や経済、宗教や各種技術を体系的に結びつけ、ひとくくりにして理解するための言葉である。
。 さて人類文明という高層ビルは、幾層もの階層からなり、更にその階層は、幾層ものフロアー〈文明〉からなり、それぞれのフロアーには、またいくつもの異なる部屋(文化)がある、というイメージとなる。
このようにイメージした上で、我々が現在生活しているのがこの人類文明という高層ビルの最上階である、という位置づけることができる。そして、それぞれの階層やフロアーが形成されるときには、大小の価値の変化〈革命〉が必然的にともなうのである。その結果、形態の異なる階層やフロアーが形成される。つまり、この人類文明という高層ビルは、その建築開始以来、常に大小の革命〈進化〉を経験しつつ高層化してきた。特に情報文明の階層は、IT 革命により一層の展開が期待されている。更に云えば、同じフロアーに住む、つまり時代と空間を同じくする同じフロアーの人々(同時代人)とも、密接な関係によって結ばれており、我々は、この歴史性と社会性との両者の接点上に形成されたフロアーに住んでいるということである。
故に私達は次のフロアーの建設者として、よりよいフロアーを造り、これを次世代に継承してゆく義務を負っている。ここに、過去、現在未来を直線的に繋ぐ意識と、同時代の人々との相利共生関係を形成すべき義務が生じている。少なくとも、これらと良好な関係を結ぶことが、次世代への義務という発想が、比較文明論的には重視される。そして、それらを繋ぐのが情報であり、その情報の継続性と体系性の維持が極めて重要となる。
この理解の上で、高度情報化社会、つまり情報文明の階層にいる我々は、AI時代のフロアーを、いままさに建設しようとしているのである。ところがこのAIフロアーの全貌が、まだ見えず、そのなかで人々は、我先に利益を争い、互いに疑心暗鬼となり、がむしゃらな自己主張や技術開発に血道を上げている状態である。そのために、近視眼的、あるいは利己的な動機による暴走により、全体のバランスを欠いたいわば違法建築ビル化しかねず、最悪人類文明の高層ビル自体が崩壊の危機に直面してしまうのである。そうなると大変である。
そこで、改めて人類史を冷静に考える必要が出てくる。ではどうすればいいのか?そこで、人類史を鳥瞰する視点、いわば人類文明という高層ビル全体を見る視点が必要となる。
第二部 方法論と用語の検討
文明の発展と宗教
さて、ではこれまで人類文明という高層ビルの発展を支えてきた要素は何であろうか。もちろん人類の飽くなき豊かさなどへの欲望という生物としての根源的な部分もあるが、それでは動物レベルの行動原理で有り、文明の持つ体系性や継続性は、ここからはでてきません。つまり、人類文明という高層ビルにはならないのです。文明が高層ビル化するためには、先にも触れたように継続性と総合力、そして将来へのビジョンのような時間的、空間的に繋がる知的な体系性が不可欠である。
その点で、宗教、特に所謂世界の三大宗教と呼ばれる普遍宗教のような巨大宗教が、人類文明の高層ビル化に果たしてきた役割は、決して小さくない。というのも、宗教は以下で考察するように、統一した情報を時代、空間を超えて継続して発信してきた人類史上殆ど唯一の存在だからである。但し、日本においては、明治以降の近代化の過程で、宗教ヘの認識が否定的になるように情報操作してきたために、一般の日本人は「宗教」という言葉に、負のイメージを抱いてる。しかし、グローバル時代と呼ばれる現在においては、この認識は大きな負の遺産であり、日本人が真にグローバル社会を理解するためには、宗教の存在を正しく理解する必要がある。というのも、人類の文明史を考える時はもちろん、グローバル化した国際社会の情況を理解するために、宗教への理解は不可欠だからである。以下の図は、文明を構成する政治や経済などの要素と宗教の関係を示したものである。
この図の特徴は、科学革命以降主流となった宗教と政治、経済などを分離し、文明を理解することを目指してきた近代文明の修正を含むもので、グローバル時代における国際社会理解には重要な点を含んでいる。
というのも、グローバル時代を迎え、世界各地の文化や宗教が急激に交わり、政治的にも文化的にも多極化してくると、科学文明の基本的立場である宗教と政治、経済などの世俗社会の要素を分離して理解しなければならない、という文明理解が立ちゆかなくなったかである。。
情報文明時代の文明構成図
特に、世界に18億人ともいわれる信者をもつイスラム教、及びその文明の台頭は、近代文明における宗教の位置づけに対する根本的な修正の必要性を引き起こした。周知のようにイスラム教は、中世時代には世界を席巻する高度な文明を発展させましたが、近代以降はキリスト教とその文明にその地位を奪われ、凋落したが、それでも独自の文明形態を築きた。一方、キリスト教の影響が強い西欧社会で生じた科学文明は、近代以降地球規模で拡大し、人類の文明のスタンダードとして共有され今に至ってる。
ところが、近代文明とは異なる文明概念を持つイスラム教の台頭で、従来の枠組みの不完全性が顕在化してきた。また文明と自然の関係認識には、大きな問題点があることが浮き彫りになりになった。というのも、科学文明の基礎である科学革命では、中世以来の教会中心の世界観から、人間理性を解放することを目指した。その結果、人類文明を大きく発展させた。しかし、その一方で宗教の重要性がやや軽んじられることになり、従来宗教が果たしてきた倫理観や道徳の存在が、希薄化した。また人間と自然との関係も、対立的に捉えられるようになった。
その結果、人類は地球規模で繁栄する一方、自然破壊により環境問題が深刻となった。またイスラム文明のように文明の中心に宗教を位置づける社会への正確な理解も難しくなり、世界各地で宗教間、さらには文明間の衝突が深刻化しつつある。(ハンチントン、1997)逆にいえば、科学革命以降形成されてきた科学文明における宗教の位置づけを、図のよう修正することで、現代社会が直面する問題解決の道筋が開ける可能性がある、ということである。特に、AIなど情報文明の優れたツールを用いることで、従来不可能であったことが次々に実現できる時代となっていますので、文明における宗教の重要性を再評価することで、現代社会が直面する問題解決を飛躍的に進歩させることも期待できる。
そのためにも、科学革命以降矮小化してきた宗教の存在を再評価し、その存在を人類文明のさらなる発展に役立てることが、情報文明下の大きな課題ではないでしょうか。というのも、先にも触れましたが、宗教は文明の体系性や継続性に大きな役割を果たしてきた歴史があるからである。
日本と世界の「宗教」ギャップ
日本人は一般に、「宗教」に「無頓着」あるいは「無関心である」と云われている。そして、「無宗教」であること、あるいはそのように自己認識することを、あるべき姿あるいは所謂科学的合理主義精神(日本では「宗教」に対置された)こそあるべき姿であり、近代的な(西洋文化を模倣する態度としての、「科学」的と呼ばれる態度に顕著)理想的な生活態度であり望ましいものと教えられてきた。その反対に「宗教」に頼ることには、なにか後ろめたさを漠然と感じる傾向がある。(1)
しばしば話題になることだが、日本人は自らを「無宗教」と云う。ところが、実際には、無宗教と名乗る割りには至る所に寺院や神社があり、宗教的な行事やそれに則した生活も決して少なくない。にもかかわらず、日本人はそこに「宗教」性を見出そうとも、また認めようともしない。というよりそれを「宗教」と認識すること、あるいはそこに「宗教性」を見出すことを恐れているかの如くであり、少なくとも無関係を装っている。そして、この日本文化に内在するねじれ現象が、外国人をして日本および日本人を不可解な国民と思わしめているし、日本人自身の宗教理解を大きく歪めているのである(そして、それは逆に言えば、日本人の宗教に対する意識が、世界的な認識との間に大きなズレがあるということである)。
これは、日本人が一般に用いる「宗教」という言葉によってイメージする、つまり「宗教」という言葉(記号)が表現する意味と、他の諸国で用いられ、日本語に翻訳する場合には、「宗教」という記号によって置き換えられる言葉の意味するところには、大きな意味の不一致があるということである(しかも、問題はこの点があまりに 基本的なものであり、普通には意識されたり、指摘されない点である)。
我々は、言葉によって知識を得、言葉によって思考し、言葉によって対象を認識し、言葉によって意思を伝達する等、我々の生活全般に、言葉が果たす役割は甚だ大きく、その重要性について疑問を抱くものは稀であろう。しかし、この重要な言葉について、つまり、思考を組み立てる材料としての、あるいは意志や思想や要求を伝達する道具としての言葉について、我々はどれほど厳密に用いているであろうか。自明のものとしてそれらを用いることに慣れすぎてはいないだろうか。少なくとも、学問的な研究をしようとする時に、材料や道具の吟味にどれほどの注意を払っているであろうか。
このことは、根本的な問題であるが、意外に無意識に過ごされているのではないだろうか。勿論、日常生活における用法においては、このような問題に厳密な態度で望む必要性はまったく無いであろうが、こと学問上、つまり本書でいう「宗教」(当然それは仏教の研究の準備である)について学問的なアプローチを行なおうとすれば、やはり「宗教」という言葉を厳密に用いる、あるいは少なくともその用法を一応規定しておかねばならないのではないか、というのが筆者の考えである。なぜなら、後に示すように、日本人の「宗教」観は、余りに特殊であるからである。
それにはやはり「宗教」という言葉の成立史について概観しておく必要がある。それは、後にいう宗教学的な宗教の定義という問題以前の「宗教」という、日本語の中の日常語と化した言葉の分析からはじめなければならないであろう。
そうでなければ、いくら「宗教」について議論しても、その議論は根本的な所で噛み合わないものとなってしまうであろう。特に「宗教」のように、長い歴史と幾多の意味上の変遷とそれが同次元に混在する言葉については、その言葉の成立史と意味概念の一応の把握は不可欠であろう。そこで、日本近代において「宗教」という言葉それ自体とその意味体系=文化が、どのように形成されてきたかを検討してみよう。その上で、宗教の一つである仏教のインド車かいでの消滅という、大きいテーマであり、かつ微妙なテーマについて検討することとしたい。
「宗教」という言葉の三つの源流
一般にいわれる宗教の語源に関する研究を整理すれば、「宗教」という言葉が持つ意味の起源には先ず、二つの流れが考えられることとなる。
その第一は、仏教語としての用法ならびに意味であり、これは中村元博士や川田熊太郎先生によって詳しく研究された。そして、第二は西洋のreligio or religionの訳語としてのそれである。
しかし、筆者はこれだけでは不十分だと考えている。筆者は、現在の日本人の精紳を形成している言葉、ここでいう「宗教」のもつ文化的な特殊を、日本人である我々が先ず認識することで、他の地域の「宗教」との相違を修正するということを行いたいのである。そのためには、明治以後の日本社会において「宗教」がどのように認識され、どのように機能してきたか、という単なる語源解釈学の域をこえたいわば社会科学的側面からの「宗教」へのアプローチが必要であり、その視点からの「宗教」という言葉の意味の検討が不可欠である、と考えている。
つまり、現在われわれが無意識的に用いている「宗教」という言葉が、明治・大正・昭和期において極めて政治的・イデオロギー的に形成されたことを重視し、その形成史や文化的な背景を明らかにする必要がある。これにより形成された意味、つまりイデオロギー的に「宗教」という言葉に付与されたものが、第三の意味である。
このいわばイデオロギーとしての「宗教」という言葉の歴史の確認と、その限界性の自己認識及び修正が、如何なる意味においても日本人の宗教研究には不可欠である。つまり日本人に共有される日本独自のイデオロギー的な宗教観から自由となり、客観的に宗教を論じなければならないのである。すかし,この方向から研究は従来あまり意識されてこなかった。
その意味で「宗教」の研究には、第一・第二に加え、第三をも含めて総合的に検討する必要がある。ただし、この点に関しては他の機会に既に検討したので、ここでは第三の点について簡単に言及する。
近代日本における宗教と政治の連関
明治政権の基盤は、日本の民族宗教としての神道を全面的に打ち出した、新しい形の神道、つまり平田神道を中心とした神道イデオロギー(これを国体神道、国家神道などと呼ぶ)を基礎としていた。それは明治維新(一新)という一種の革命(神道革命)下において形成され、後に西欧の絶対王権を真似て形成されたからである、とされたものである。(4)
明治政府の正当性を強調すべく行なわれた近代的な神道(所謂国体神道、あるいは国家神道)の実質的な国教化とは、キリスト教の国民一般への浸透の防止、あるいは圧倒的な強さをもって押し寄せてくる近代ヨーロッパ文化への民族的な危機意識から生じた、という点は決して疎かに出来ない点である。
そしてこの外圧、あるいは普遍的で圧倒的な文明の来襲への自己防衛的な運動としての民族意識、あるいは民族宗教の強調は、後述するようにインド仏教の衰亡時と文明史的には非常に類似した現象として捕らえることが出来るのである。
この神道の特殊化政策の上にイデオロギーとしての「宗教」の日本近代独自の意味が形成されたのである。つまり、日本近代の特徴である民族主義を基盤とする神道の特殊化は、神道以外の「宗教」の矮小化と表裏の関係であった。
この点は福沢諭吉など当時の知識階級による以下のような言葉によって明確となる。
余輩は、神仏の事に付き甚だ不案内なれども、識者の言を聞けば、神道は決して宗教
に非すと言へり。(中略)神道は唯現世に在って、過去の神霊を祭り、その徳に報じて現世の人の幸福を祈り、専ら生者の為にするのみなれば、決して宗教には非ざるが如し。……中略……今より(明治十四年頃)更に神仏の区別して、日本の宗教は仏法なり、神道は宗教にあらず。
そして、その真意は、
蓋シ夫レ我ガ 皇上ノ祖先ヲ祭祀敬宗スルヲ以ッテ宗教トナサバ、畏コクモ我ガ歴世皇帝ノ聖霊ヲ、彼ノ幽冥不測ナル、信ズル者ハ之ヲ信ジ信ゼザル者ハ却テ之ヲ嘲弄スル諸宗法教ノ神等ニオナジトスル乎、我ガ穆々タル、皇上ヲ、他諸宗教ノ法主宗主等ニ比セントスル乎。何忌憚ナキノ甚シ。・・・・彼ノ神道ヲ以テ宗教トナスノ誤謬ヲ釐正アラバ則チ国体維持ノ裨補ニ幾カラン歟。
というものであった。
このイデオロギー的な神道非宗教論とも云うべき立場が、「国民教育」という教育(すなわち布教)政策を通じて、初等・中等教育の中に組み込まれる。このことは、「宗教」という言葉の概念を著しく複雑なというより歪んだものとしてしまった。
つまり、神道を「宗教」ではないとしたために、「宗教」という言葉が本来含むべき要素が、その言葉から切り離されたのである。それは、以下のような当時の「宗教」観を観れば明らかである。
人の幼稚なるや、自主独立の力なくして専ら父母若くは他の長老に依りて生長するを
得、智識上に於ても亦此の如く、脳力の孱弱なるものは、偏に他力を頼み、却て自力
の他力に勝ることを知らざるなり、宗教的信仰を脱却すること能はざるものは、児童
の未だ母乳を廃すること能はざる薬が如く其自埼の不足を表白するものなり。(7)
という意見が、当時において盛んに述べられた。
ここには「宗教」は、幼稚な人間の信ずる対象、あるいは知的未熟者の頼るものであり、知性の発達とともに、やがて乗り越えられなければならないもの、というような認識が横溢している。事実。井上は、「所がどうしても成立宗教(仏教・キリスト教)として説きまするというと迷信が付随してくる」(7)として、神道以外の「宗教」には、迷信や自己の立場に固執する見解が多く「国民教育」にとって有害である、としてこれを排除しようとする。
ただし、神道は宗教ではないので迷信も不合理も存在しないという立場である。ここでいう国民教育とは、「次の時代の国民を健全に養成しようと云う目的を有す」(9)という国家(当時は国家そのものが宗教的帰依の対象であった、といっても過言ではない。
このレトリックによれば、政治の宗教からの独立、あるいは直接的な関係性は、理論的に排除できつつ、神道を非宗教と位置づけることで明治政府のイデオロギー的存在である神道は保護できるというレトリックが可能となる。これはヨーロッパ近代の政教分離主義(世俗政治からのキリスト教会支配の排除)に一見類似しているが、その実全く別のものである。しかも、国(臣)民には、政治と宗教の独自性を教え込んだために、文化的にはこのレトリックに気付き難い構造となっている。
しかも、国家神道、あるいは皇国・神国思想をイデオロギーとして戦った第二次世界大戦の完敗を期に、明治以来の神聖一致政治への極度の反省(?)からか、宗教への極度の不信感が共有され、その結果と思われるが、日本人は宗教が政治などの要素と結びつくという文明論には当然ともいえる問題に関心を持ちにくい、あるいはそれを避けて通るという傾向を持つにいたたのである。これは研究者であっても例外ではないであろう。それ故、日本の宗教研究における文明論的な視点は、これらの偏向の是正、少なくとも確認からはじめなければならない、と筆者は考えている。
以上、簡単ではあるが、「宗教」という言葉の歴史を検討し、日本人の持つ「宗教」イ
メージを検討した。これによって現代の日本人の「宗教」観がかなり特殊なものである
ことが、ある程度明確になったのではないだろうか。
仮に前述のような「宗教」観で、世界の諸宗教にアプローチするとすれば、その対象との間に引き起こされるギャップは無視しえないものとなり、その意味で注意を要する点であろう。
また、本章においては明治以来の宗教政策についてかなり批判的なスタンスをとったが、
それは必ずしも、これらの政策への非難を意味しない。なぜならその政策のために日本の
近代化は未曽有の発展を遂げたのであるから。
要は、その政策も完全のものではなく、時代とともに修正されるべきであり、そのため
にはその政策あるいは文化のもつ一種の弱点を冷徹に分析する必要がある。ということで
ある。自文化に誇りと愛情を持ちつつも、それに溺れず時代の要請によって新たなる文
化の創造への準備段階として、自己批判(反省)は不可欠である。
以上簡単ではあるが、「宗教」という言葉の歴史を検討し、日本人の持つ「宗教」イ
メージを検討した。これによって、現代の日本人の「宗教」観がかなり特殊なものである
ことがある程度明確になったのではないだろうか。仮に前述のような「宗教」観で、世
界の諸宗教にアプローチするとすれば、その対象との間に引き起こされるギャップは無視
しえないものとなり、その意味で注意を要する点であろう。
宗教と文化・文明の関わり
近代文明を受け入れたわれわれ日本人においては、「宗教は個々人の内面を規定するものであり、国家や社会全体が特定の宗教、特に特定の宗教教団やセクトに肩入れしてはならないというルールを基本」とすることが、当然のことと考えられている。いわゆる政教分離の原則である。この政教分離の原則は、いわば近代文明、正確には近代キリスト教文明における普遍的な原則と考えられている。
近代西洋文明が到達したこの原則は、一般には世俗革命と呼ばれる現象の政治的展開とされる。この世俗革命とは、キリスト教教会による人間生活の完全支配の体系から、日常生活の分野を分離独立させる運動として、ルター等の宗教改革を契に引き起こされた。そして、西洋社会は、永い混乱の末に教会支配から独立した文化・文明形態を構築することに成功した。これがいわゆる近代西洋文明である。
この近代西洋文明(それは近代ヨーロッパキリスト教文明)の特徴は、世俗化という名のもとに、宗教から政治や経済の領域を分離し、それぞれの社会的な要素を独立させたことにある。その結果、宗教の社会的な役割は縮小し、主に文化や個々人の精神の中にのみその存在を許されるようになった。そして、この宗教からの日常世界の独立、つまり宗教(西欧の場合は、教会)による、日常社会の支配からの独立、これを成し遂げたのが近代社会、近代文明なのである。そして、この世俗化された近代社会、近代文明こそが人類の理想の形態と言う認識を作り上げたのである。
このように近代西洋文明は、その形成過程において文化の中心をなす宗教の影響力を矮小化し、一種の普遍性を身につけていたのである。
結果として、西洋近代文明は、宗教性を極力矮小化した故に、文明移転がよりスムースにできるようになり、その結果18世紀以来世界各地に伝播したのである。
しかし、この西洋近代文明における宗教と文化・文明のあり方が、唯一のものでもなければ、理想的なものであるというわけでもないことは当然である。特に、非西洋文明地域や近代文明発生以前の文明時代を考える時、この点は重要となる。何故なら、非西欧文明地域や時代の人々は、宗教と文化・文明を分離するというような近代的合理性はもっていなかったからである。この一見あたりまえのことを忘れると、近代人の常識で、過去の歴史を捌くという誤りを犯すこととなる。
一方、近代西洋文明に対して、非近代西洋文明のモデルを最も判り易く我々に示してくれているのが、イスラム文明である。この文明は、西洋社会のように世俗革命を経験しておらず、その意味で前近代的モデルである。
このイスラムを含めた非近代西洋文明世界は、極端に言えば文化と宗教は未分化であり、一体である。それ故に前述の文明からの文化の剥離は起こりにくい。例えば、この傾向が最も顕著な、つまり宗教的価値があらゆる日常生活の価値に強い統制力を持つイスラム文明では、文明移転はそのまま他の文明における文化の部分までも変換、あるいは排除せずには成立しない文明形態である。したがって、イスラムの伝播は、イコール他の宗教文明の排除という結果必然的に齎す。それが暴力的か平和的かは別として。
一方、同じように宗教と世俗社会が密接不可分に見える仏教においては、宗教の世俗社会への影響力は限定的であり、その意味で文明における文化剥離が起き易い形態といえる。このような違いはみられるが、非西洋近代文明以外の世界では、宗教と文化、さらに宗教と文明は密接に関係している。
もちろん、それは宗教が政治や経済,当然のこととして文化に深い影響を与えることと同時に、政治・経済の問題が、宗教的な紛争や対立の要因となる、ということを意味する。
一方、図1に象徴される近代的合理主義理解では、政治・経済の問題は、それぞれ別々に処理され、宗教に結び付けられることはまれとなる。ただし、現実にはこのような理性的な対応を取ることは難しく、結果として宗教的な感情対立を持ち込むことは避けられない。
そこで図3として提示するモデルがある。それは宗教と社会を過剰に分離した図1と、逆に宗教が過剰に社会を圧迫する図2の折衷的なモデルである。勿論折衷という意味は単なる妥協の産物というものではなく、両者の不備を補うモデルということである。このモデアルによれば、宗教と社会の関係が密接不可分に理解されることなる。
それ故に、宗教問題と理解されるものは実は政治的な問題であると冷静に分離できることとなるし、逆に政治的、社会的問題が宗教と関連付けて理解されるというダイナミズムも体系的に理解できることとなる。(18)
同様に、宗教によってそれらの紛争が調停されたり、平和が形成されたりということも理解しやすくなるのである。しかも、社会と宗教とを密接に結びつけることで、社会改革と宗教の関連もスムースに説明できるのである。つまり、社会的な不満により宗教を変えるなどという運動の真意が理解できるというわけである。
インドにおける宗教観
以上、簡単に宗教という言葉の形成史をたどり、現在日本人が共有する「宗教」という言葉の背後に潜む重大な欠陥、少なくとも深刻な問題点を指摘した。その上で、文明と宗教の理解モデアルについて簡単に検討した。
次に、インドにおいて「宗教」の社会的位置づけについて、簡単に検討しよう。いわゆる近代的な世俗化とは無縁であったインドにおいては、当然ながら宗教と其の他の要素は一体化している。つまり、宗教的な理想モデルが、日常社会においても常に追求されたのである。それは今日においてさえも「ヒンドゥー教は西洋流の宗教ではない」とか、「ヒンドゥー教は生活そのもの」といったインド人の宗教意識によって明らかであるが、以下やや詳しく検討しよう。
現代の辞書を見るとインドにおける「宗教」という言葉に当るものは、ダルマ(dharma)である。ただし、この点に関してはインド哲学者の中村元博士が検討しているように、恐らく西洋の言葉であるreligionの翻訳語としてこの言葉をあてたものであろう。Dharmaは、ネパール、ブータン、スリランカ、ビルマ、タイ(パキスタン)などでも「宗教」の訳語として、あるいは正しい宗教を意味する言葉として用いられている、という。(19)さて、ダルマは本来「持(タモ)つ」という意味であり、「人を人として持(たも)つ」ものを意味するという。だから「人の道」という意味合ともなり、漢訳仏典では「法」と訳された。つまりダルマは人の道であるから、倫理(義務)的なものであり得るし、「法(秩序・習慣)的なもの」でもあり得る。しかし、このようなダルマの意味が成立するためには、これらの規則性(のり)を成立させる究極の根底、根源が不可欠である。それがダルマの真の意味である、といっても良いであろう。それは人間を含めた世界を根源的に支える、あるいは貫く理法ということである。そしてこの理法(法則:定理)に気づき、日常生活において実践することが、悟りということである。
このようにインドにおける諸々の宗教は、この理法であるダルマをとらえ、これを言語化するとともに、この理法を現実の社会において顕現することをめざしていると認識される。とうのもインドにおいてこの理法(ダルマ)は、根源的な真実(satya:サトヤ)と同義であると考えられているのである。そして人間の目標は、この真実との一体化、あるいはそれを獲得することである、とされる。インドではウパニシャッドに代表されるように、この真実在(普遍原理)であるブラフマンと個我(個別原理)が、究極的には一つ、つまり異なることがない(梵我一如)とするのである。
そして、この梵我一如に象徴される絶対的・超越的なるものへの達成・獲得が、インド宗教の基本モチーフとなっている。それは仏教とて例外ではない。しかも、この普遍原理と個別原理との一体化は、個別原理の個別性を成り立たせる個我(自我、各種の限定要因)の死滅によって可能とするのが、インドの宗教の特徴である。そのためにあみだされたのが、自己を省みること(内省)であり、自我を抑制する(内制)であり、それらを行うための各種の瞑想法である。インドの宗教はこの瞑想の実践と瞑想のための環境つくり、そして瞑想体験そのものを含めて宗教と呼ぶのである。
従って、インドの宗教は、一つの価値形態によって独占されることは無いし、またそのように考えることもない。つまり、唯一絶対的創造神による世界の創世という一元的な価値体系を中心とする近代西洋文明のうえに形成された現在の宗教観、いわゆる科学的宗教学(science of religion)によって提示された宗教観では、いわゆる多神教世界の宗教を実情に合った形で認識することには限界がある、と筆者は考えている。
というのも、ヒンドゥー教のようにゴータマ・ブッダはもとより、イスラムの神アッラーさえ、神の化身として自らの宗教に取り込んでしまう宗教に対して、現在の宗教観はこれを包摂しきれていないのである。このあたりの反省も不可欠である。
以上のように、・イスラームという一神教的宗教をモデルとして形成された現在の宗教観は、樹木で喩えれば針葉樹のようなものである。一方多神とされるヒンドゥー教や仏教は言わば、地下茎が複雑に入り組んでいる竹林であり、その地下茎から伸びる竹茎の一本一本がヒンドゥー教や仏教という宗教として位置づけられる。確かに、竹一本一本は針葉樹のように独立した存在といえる部分を持つが、しかし、その根本は互いに共有され個々の株が独立して存在する針葉樹とは大きく異なる。
故に、インドの諸宗教は、ユダヤ・キリスト・イスラムのように宗教形態として峻別されるのではなく、その差異は非常に小さいということを先ず、認識しておくべきである。勿論、独立的な面が強調されるユダヤ・キリスト・イスラームの宗教でも、厳密にいえば神や聖典の共有は多く、一般に考えられているよりは、共通点は大きいことは忘れてはならない。ただし、今回は、この点に関しては指摘のみにとどめる。
以上で方法論的な部分は終了し的な検討に移る。
具体的亜検討の前に、言葉の検討を先ず行っておこう。
言葉の検討の必要性
先ず第一部では、「寛容」と言う言葉に注目する。その理由は、それが他者認識、あるいは他者との関係を象徴的に示す言葉であると同時に、この寛容の思想の広がりは、単なる宗教レベルにとどまらず、宗教あるいは社会集団間の他者認識、具体的には政治思想などとも深く関わり、昨今の宗教を無視しては考えられない国際紛争の背景分析に何らかの情報を供することが期待できるからである。
ところで宗教の本質は、これを信ずるものに心の平安や社会の安定、つまり人間が幸福と感じる物質的、心理的要素を提供することを目指すことに求めることができる、と云えないであろうか。あるいは少なくとも信者は、自ら信奉する宗教、それがいわゆる民族宗教であろうが普遍宗教であろうが、全ての宗教は、そのような信徒の願いをたとえ部分的にせよ叶えてくれると信じている。
尤も、民族宗教の多くは共同体祭祀から出発しており、それらの宗教は基本的に内向きである。つまり、その他者認識においては自らを是として、他者を非とし、さらには野蛮人とするなど、本質的に他者の存在をその宗教構造の成立要因と認めないか、その埒外において消極的に認める程度にとどまっていた。つまり、民族宗教は自民族主義であり、それは血統や地域性を基準に、閉じられた構造を持つ。
ところが、これら民族宗教の地域性、民族性を超えて全ての人間、少なくとも信者の平安と幸福を志向するのがいわゆる普遍宗教である。この拡大志向、外向き開放的な教えが、地域や民族を超えて、これらの宗教が全世界に伝播定着した理由と考えられる。その意味で、いわゆる普遍宗教と呼ばれる仏教・キリスト教・イスラム教の3教は、ともに世界中の地域や民族の壁を越えて信奉されることとなっている。
ところで普遍宗教は、民族宗教を土台とした後発の宗教であり、普遍宗教が生まれたときにはすでに既存の宗教が、存在しており、さらに普遍宗教は他地域への布教によって拡大する宗教である以上、宿命的に他者(異教徒。原則的に以下同じ)の存在を前提とする。
しかも、その異教徒を自らの教えに改宗させなければ、自らの存在意義を示せない、発揮できないというアンビバレントな宿命を持つ。それ故に、普遍宗教においては既存の宗教との軋轢は、不可避的である、といえる。逆に言えば、他者への働きかけは普遍宗教の宿命である。故に、その他者をどのように認識するか、また他者とどのような関係を結ぶかは、それぞれの普遍宗教の宗教的な特徴が端的に現れる部分である、ということがいえる。
「寛容」の意味が持つ問題点
急激なグローバル化によって、現在社会において異なる価値観に対する寛容、特に宗教的な寛容は「一見して、人類共通の価値としての位置を占めている。それは、平和、正義、人権、デモクラシーといった価値と類似して、一種の人類的な普遍性をおびてきていると言っても過言ではないであろう」 と言う認識が、ますます強くなっている。
確かに近代社会において、異宗教間の共存に関して「寛容(tolerance本小論ではtolerationも含めるが、便宜上toleranceに統一して表記する。以下同じ)」という言葉を用いて、価値観や制度、さらには宗教を異にする人々の平和的な共存関係を可能にする思想を寛容思想として表現し、これを近代社会の理想的な姿と認識することが一般的となっている。(* )特に、宗教の平和的な共存を促進する立場を表現する場合に、寛容という言葉は、当然のごとく用いられる。つまり、宗教間の対立や紛争などの反対概念、或いはその状態を表現する言葉として、寛容という言葉は用いられていると言うことができよう。
しかし、多くの先学が指摘するように、寛容という言葉が示す思想内容は多義的であり、その基本的な理解さえ一定していない。 なぜなら、この寛容という言葉の意味形成においては、以下で検討するような社会背景が深く影響しているからであり、現在一般に用いられている寛容という言葉は、この複雑な社会背景によって形成された多義的寛容の意味内容への不十分な理解から生じる危うさを孕んでいるように思われるのである。例えば、インド思想研究者の間で議論されているハッカー(P.Hacker)の「ヒンドゥー教は寛容の宗教ではなく、包摂(Inkulsivismus)の宗教である」という問題提起に対して、インド学者が様々に議論しているが、彼らが基準とする寛容思想についての統一的な理解は、未だ為されていないようである。 そのために、この提示した問題への議論もうまくかみ合っていないように思われる。つまり、例えばインド哲学者のハッカー氏は、西洋人の視点からインドの寛容思想を包攝主義と表現し、寛容思想とは異なるものとして批判的に論じているが、その背後にある自らの寛容思想の背景、つまり本小論で簡単であるが検討したような西欧近代の特殊な寛容思想の限界性には余り注意を払っていない。(
勿論、本小論でこの統一的な寛容思想の基準を提示しようとするものではないことは言うまでもないが、寛容思想研究に不可欠であるが、余り注目されていない以下の二つの点を先ず簡単に検討しておきたい。
本研究は、寛容という言葉が持つ近代西洋文明的な意味背景を検討することでその限界性を明らかにし、その上でインドにおいて展開された宗教共存(寛容)思想との比較研究を通じて寛容という言葉に新たな可能性を付与する事を目指す。少なくともその展望を示したい。つまり本小論は、現在の寛容(tolerance)思想が暗黙の前提としている西洋近代(キリスト教)文明的な意味世界の限界性を超える新しい寛容思想構築のための基礎作業の一つとなることを目指す、研究ということである。つまりそのために非ヨーロッパ的伝統、特にその形成に大きな影響力を持つキリスト教とは異なる宗教伝統を持つ仏教などのインド思想の知恵を探ること、また日本人としてこの問題に対して日本文化の視点から考察を加えたい。少なくとも、寛容や共生を考える時、そもそも寛容とは何か、という問いに、日本語としての意味に加え、西洋の意味、更に他の宗教や国の文化における意味の比較研究は不可欠である。なぜなら、これらは全く同一ではないにしても、同質の意味を持ち地つつ、掃除に異なる意味を含んでいる。そして、不和や紛争を引き起こすのは、この異なる部分、文化や地域性など、異なる部分を中心とする寛容理解から引き起こされるおとが、少なくないからである。
そこで、先ず筆者は日本語で物事を考え、表現する日本人として、この寛容思想を検討する前に、日本語の寛容と云う言葉について若干の検討を加えたい。
日本語における寛容の特性
先ず、寛容という言葉に関して現在一般に用いられる言葉の意味を考えよう代表的な国語辞典である『広辞苑』(「1・寛大で、よく人をゆるしいれること。とがめだてせぬこと。2・善を行うことは困難であるという自覚から、他人の罪過を厳しく責めぬこと。キリスト教の重要な徳目。3・異端的な少数意見発表の自由を認め、そうした意見の人を差別待遇しないこと」と言うことになる。
この『広辞苑』の僅かな説明からも寛容という言葉の背景が明確になる。特に、この言葉がキリスト教と深い関係がある、ということが推測される。この点に関しては、後に触れることとし、まず言葉の全体のイメージを考えよう。因みに1の意味は、漢字の意味から来るイメージにも通じるものである。この場合の寛と言う漢字は、「宀と莧とに従う。宀は廟。莧は眉に呪飾を加えた巫女。廟中の巫女が緩歌漫舞して祈るさまをいう。」(『字統』)という。つまり、中国の文明において最も重視される祖先祭祀において、祖先の廟の前で行われる巫女のゆったりとした歌舞に関することを意味しているという訳である。この時には、踊る方も、またそれを見る方も穏やかで、ゆったりとした気持ちになる分けで、憎しみ愛や争いなどの状況とは対極にあることとなる。
また同書によれば、容は祈祷の際に用いた容器のことで、入れ物の意味だから、寛容とは「大らかな心をもって、他人の言動などをよく受け入れる心持ちのこと」と言うほどの意味となろうか。いわば「度量の大きさ」ということである。但し、漢語の熟語としての寛容という用法は、余り一般的な用例ではなかったと言われる。(1)ではなぜ、この寛容が、toleranceの訳語として採用されたのであろうか?そこに日本語としての寛容という言葉の特殊な歴史があり、それ故にtoleranceと寛容と云う言葉の意味の誤差もここから生まれる、と筆者は考えている。
こそでまず寛容という言葉が、いつ頃からトレランス(tolerance)あるいはトレレション(toleration)の訳語の歴史を簡単にたどってみよう。
これを知る手がかりとしては、最初の英和辞典として知られるヘボンの『和英語林集成』(初版:慶応3年)等が参考になる。参考のために系列語を含めて紹介すると同辞書では 、tolerable「かなり」「ずいぶん」「こらえられる」 tolerate「ゆるす」「かんにんする」 toleration「ゆるし」「めんきょ」(以上はすべてローマ字表記であるが、便宜上仮名表記にした。)となっている。この時toleranceという言葉は採用されていない点も注目される。
次に日本人初の英和辞典『和訳英辞書』(明治二年)、所謂『薩摩辞書』では、tolerance は「堪忍」「免許」tolerant「堪忍である」となっており、 toleration「堪忍」「免許」となっている。これら明治初期の翻訳は、tolerance所謂寛容とはやや異なる意味、後に明らかにするようにtolerance本来の意味を確実に表現していることが注目される。つまり英語のtolerance以下その関連語の語源は、ラテン語のtolerantiaであり、このtolerantiaは、 ラテン語のtrelo「耐える」・「我慢する」・「持ちこたえる」から派生した言葉であるとされる。だから『和英語林集成』や『薩摩辞書』はtoleranceの訳に、「堪忍」あるいは「許可」というような言葉を当てたのであろう。
しかし、前述のように現在の寛容という言葉には、このtoleranceが持つ「堪忍」、「認可」、「耐える」というニュアンスは感じられない。
それはどうしてであろうか?そもそもいつごろからこの寛容という言葉が、tolerranceの訳語して採用されたのであろうか。現在のところその時期は特定できないが、多様と言うより混乱状態であった翻訳語を学術用語として確定させることに大きな役割を果たした井上哲次郎等編纂の『哲学字彙』(明治16年)では、「寛容」「容任」「任由」としており、以後今日に至るまで、toleranceの訳語は、原則これに従っている。
何れにしてもトレランスの訳として「寛容」を第一義として当てはめた井上の訳語では、トレランス本来の意味である「堪忍」、「怒りを抑えて、人の過ちを許す」という意味とは多少意味構造が異なるように思われる。
つまり、井上等が採用し、学術用語として定着した「寛容」という翻訳では、トレランスという言葉が本来持つ、以下のような意味を明確に表現することが難しいように思われる。つまりもともと「辛抱(する)」「耐(える)」あるいは「許し」を意味する言葉であるtoleranceに、なぜ井上は寛容とう訳を与えたのであろう。
と云うのも、この言葉の持つ意味構造は、ある者が他者に向かい一方的に地位や権利、信仰など自由を与える、あるいは許すという片務的で、しかも上から下への垂直的な関係によって成り立つ構造を持っている。確かに、一方が精神的に大きな器を持っていれば、あるいは耐える心を持っていれば、この「寛容」の関係は、最低限成り立つというものである。つまりトレランスは、他者への働きかけにおいて最小限の関心、時には他者の存在を等閑視しても成立可能な状態を意味する言葉なのである。
だから、トレランスの主体は「私」であり、その私が、相手の存在等に「耐える」、あるいは「許す(者)」ということになり、この私に依って「許す」「耐える」状態がtoleranceと云う言葉で表現される意味世界である。
ところが、このトレランスを寛容と訳しては、トレランス本来が持つ基本的意味である「堪忍」「許可」「辛抱」「耐が、表現されていない。つまり、井上の訳語では、本来のトレランスが持つ「許し(の寛容思想)」の側面が希薄化してしまう。つまり寛容という訳語では、トレランス(tolerance)の持つ意味世界、特にキリスト教との関係が曖昧になる。その意味で、原語と翻訳には微妙な差異を生じ、と云う意味で問題があるということである。勿論、井上はそれを承知で、従来の宗教的なイメージを髣髴させる「救い。寛恕、慈悲」等ではなく、敢えて、あまり知られていない寛容という漢字を付け変えたのである。そこには日本近代における近代化、即ち西洋キリスト教文明化の過程における独自の事情があったのである。そして、そのある種のイデオロギー的な意図が、今日の日本語の思索を混乱に陥れる原因の一つとなっている、と筆者は考えている。
実はこの点を明らかにすることは、寛容と云う言葉を用いて思索する我々日本人には、大変重要なことである、と筆者は考える。
そこで、日本語の寛容に関して検討する前に、西欧におけるトレランスの意味について検討したい。その際にはtoleranceの持つ宗教的、あるいは歴史的な意味の検討も必要となる。
そこでまずキリスト教同様にキリスト教と同様の宗教構造を持ち、「許しの寛容思想」的な発想を持つイスラムの寛容についても簡単に紹介しておこう。というのも、両者は同じセム族の宗教であり、ユダヤ教から発生した兄弟宗教であり、その宗教構造が相似形だからである。つまりイスラムを概観すると、このtoleranceが本来持つ意味構造がより明確になるからである。
イスラムにおける寛容思想の構造
イスラム(イスラム教と表記する時よりもより広く文明レヴェルの広がりを想定している)思想における寛容では、samuha(samha)という言葉が先ずあげられる。このサムハという言葉は、「・・に許す。に権力を与える。」という動詞であり、そこから派生するさまざまな言葉には、samAha「許す」「容赦する」「寛大に振舞う。」からtasAmaha「寛容である」「善意を示す」という言葉がある。また、同じく辞書的意味での寛容とされるkarramaは「尊敬する。栄誉を与える。」という動詞であり、それがkarumaでは「寛大である。気前がいい。」となる。
これらの言葉の意味を形成する背景は全て一方向性、それも高所にいるもの、あるいは優位に立つものが、目下の弱者に対して一方的に与える形の恩恵として、これらの言葉が更生されていることがわかる。つまり、直線的で、一方的な許しの構造ということになる。このイスラムの寛容の構造をさらに典型的にあらわしているのが、『コーラン』二-109節の「彼らを許してみのがせ」という部分に用いられる‘afwa「救済する。許す。免ずる。」あるいはghafara「許す」であろう。これらの言葉は、大体においてイスラムにおける寛容性、つまり他者との関係において良好な関係を保つことを表す語として用いられる。
しかも、このラビア語には、イスラムの寛容の立場が明確に現れている。つまり’afwaには、「相手の存在を全く忘れて心から忘却してしまうこと」と言う含意があり、またghfaraには「何事もなかったように包み隠す。」つまり「全てを飲み込んでそのまま許す。」という発想がある。これらはtolerance的な寛容に通低する構造を持つものである。だから’afawa にしてもghafaraにしても、その近接語にafara「塵で覆う」ghaZZay「覆う、包む、隠す」があるのである。
これを前述のような立場から解釈すると、イスラムにおける寛容思想のスタンスは、他者、特に彼らが忌避する異教徒(カーフィル)であろうとも、その存在を見て見ぬ振りをして、その生存や存在を見逃す。つまり「塵(砂の方が近いか?日本的ならば雪が)一切のものをそのままに多い尽くして、あたかも見えなくするように、他者の存在をないものとして許す。」(***『コーラン』の注釈日本語)ということとなる。
これが実質的なイスラム教の寛容の立場を表すものと理解されるが、その典型に全てを遍く許す「大寛恕者ghafala(アラーの99ある名称の一つ)」の存在が強調される。
このように、典型的なセム的一神教であるイスラム教の他者認識は、常に、一方的に「許す」「耐える」という「許しの構造」を中心とする片務的かつ垂直的他者認識の構造になっている。この構造は、前述のtoleranceにも共通する構造といえるであろう。
いずれにしても、インドにおいて繰り広がられたイスラム教徒のインド支配においても、常にイスラム教徒の軍事的あるいは文化的優位を前提として、ヒンドゥー教徒や他の宗教に対する所謂寛容が議論されたのである。 つまり、イスラムにおいても「許しの寛容」と言える構造によって、異教徒ヒンドゥー教徒との「寛容の共存関係」が形成される構造なっているのである。ところで、なぜセム族の宗教下では、寛容が宗教と結びつくのであろうか?(***それは、セム族の宗教特有の厳格な一神教の構造、筆者は特にこれを(排他的)一神教として、所謂汎神論的な一神構造と区別している。詳しくは拙著参照。)
そこで以下では、「許しの寛容」の構造が最も明確に現れており、かつ日本語の寛容という言葉の意味を理解するうえで重要な西欧近代の寛容と云う思想について極簡単に検討しよう。
「近代的寛容思想」とその宗教性
実は、トレランスいう言葉は、近代社会において生み出された次のような状態を支える理念として形成された言葉で、極めて西欧近代(キリスト教)文明の思考伝統の所産であるということである(勿論、古くからある言葉であるが、本小論で問題としている、タエル赦しや免許と云う意味)。というのも西欧近代社会において寛容が注目されるようになった背景には「十六世紀の宗教改革の結果としてカトリック普遍主義が崩壊するとともに、多くの同時代人が宗教的な寛容を重要な課題または争点として認識するようになった」 という事実である。(*実は、カトリックと改革派系、例えばピューリタンやイギリス国教会派との対立、紛争の時代には、トレランスは極めて悪意のある意味で用いられていた、という)
更に言えば「まず宗派間の対立感情が頂点に達する宗教戦争の時代には、寛容は信仰の弱さの表現として否定的に考えられたが、やがて宗教戦争から平和に移行する段階になると、寛容はいわば必要悪として暫時的にではあるが肯定され、信仰の問題というよりも国家理性を優先する立場からカトリックとプロテスタントの平和共存が実現される。」 という事実である。この時トレランスという言葉で表されたものが、プロテスタンとカトリックというキリスト教内の異なる宗派間の平和共存の思想つまり寛容の思想である。しかし、この時強調された寛容思想は、後に検討するように必ずしも積極的な徳目としてではなく、むしろ「異端信仰という罪悪または誤謬を排除することのできない場合に、やむをえずそれを容認する行為であり、社会の安寧のため、また慈悲の精神から、多少とも見下した態度で、蒙昧な隣人を許容する行為」 であった。つまり、当時の寛容思想は必要悪であり、しかも信仰の面からは悪徳とまでは言えないにしても、決して推奨されるべきものではないということである。いわば、宗教レベルでは決着のつけられない問題を、信仰以外の領域から社会不安の沈静化のために生み出されたのが「近代的寛容」思想の原点であった、ということである。
このいわば「近代的寛容」思想 は、信仰レベルの問題を棚上げした形で、つまり国家理性というような極めて近代的で、且つ世俗世界レベルで議論されているという点を特徴とする。つまり、近代的寛容思想は、法や哲学といった近代理性のレベルで議論されたもので、宗教レベルの問題としては、これを本格的には扱わないということに特徴があるということができよう。次にこの近代理性における寛容の類型を簡単に整理してみよう。
この点を深沢氏によるギ・ソバン説の紹介によれば、近代的寛容は大きく三つに分類できるという。第一類型は一種の棲み分け的寛容の状態であり、「アウグスブルグ宗教平和令」などに代表される。第二類型は法令における異宗派共存への寛容である。これはナント王令(1598)やイギリスの寛容令(1689)に代表されるものである。そして第三類型として法律の制定をともなわない実質的な寛容で、オランダの場合となる。(オランダに関しては、桜田美津夫『物語オランダの歴史』(中公文庫2017年第二章四五~九六頁において興味深い記述がある。)
以上の三分類は何れも世俗世界における異宗派、具体的にはカトリックとプロテスタンとの間の共存の関係を世俗の領域で作り出したもので、その思想的な背景は近代的な理性主義に負うところが大きい。
それ故に近代的寛容思想は、近代的概念としての「個人」という概念が基本となってはいるが、その個々人の内面にまで踏み込む事はない。そのために、近代的寛容思想なりその社会倫理を突き詰めると「『ポスト・モダン的』無関心の同義語へと堕落」 しかねない孤立主義に陥る可能性を持つのである。つまり、インド思想のように本来的に他者の内面の考察に向かわなかった西洋思想、特にキリスト教的発想では、異宗派間の平和的な共存は、日常生活レベルにおける共存、つまりが世俗領域における平和的な共生が実現することが第一義的であり、それ以上の他者への関わりを持つことを想定しない、というよりタブー視する社会である。これは宗教学者で寛容思想の研究を行ったメンシングの発想で表現すれば、内面的不寛容の外面的寛容ということになる。
このように近代の「寛容」は、その出発点として宗教的なレべルにおける異なる信仰への相互理解という精神面の部分を棚上げして、あるいは信仰の深刻な対立を回避するための方策として、世俗制度の側から宗教世界の対立を回避するための妥協案として提示されたものという側面が強い。だからこそ、信仰の自由や法(世俗の法における)平等ということがセットになっているのである。
世俗概念としての寛容思想
このような理由で近代西洋文明においては、「政教分離、信仰の自由(寛容)、さらに自然権・市民権としての良心の自由」がセットで主張され、その実現こそ近代化であり、人類共通の目標である、と長く考えられてきた。そして、この思想の形成に功績が大きかったのが、哲学者・啓蒙主義者などである。(ラッセル『西洋哲学史』)彼らによって信仰の自由とほぼ同義語の「近代的寛容」は、世俗の知恵(道徳や倫理の領域)において美徳として理想化されることとなる。そこでは人間の内面や宗教性に関しては、触れないことが前提となる。(「前述のオランダ史」など)一方、この寛容を哲学思想的のみならず法制思想や法度的にも整備したのがJ.ロックであった。彼は「『神の法が終わる所に為政者の権限が始まる』とする帰結が生ずるのである。それ故に、ロックの帰結からは、神の法により決定されぬ一切の偶性的事項は世俗の権限に服することが可能となり・・・。全ての法が沈黙するにおいては、ついに『良心と誓約[より生ずる]命令』のみが従われることとなる。(種谷春洋112ページ)」と主張し、さらにここから個人の良心では解決できない領域では、「公権力をそなえた優越的人格」が肯定され、この優越的な人格者としての国家が最終的に「神の法から生じた善悪の事物は勿論、それらの伴わぬ偶性的事物をも、臣民に対して付課し得ることとなる」(同)ということで、国家という神に代わる世俗世界の絶対権威の必要性が説かれる。ここでロックは、宗教の領域にまで国家の権限、つまり世俗の力が宗教世界の価値判断にまで及ぶという極めて近代的な主張を行う。
そして、このロックが、この国家法の優越性の上で主張してのが、法の下での信仰の自由であり、それを支える「寛容」思想である。だからこそ、個々人の信仰と「寛容」はセットとなるのである。
ただし、ロック自身は、カトリック信仰をこの「寛容」の対象には加えていないのである。彼は、イギリスにあって国教会とピューリタン相互の信仰の自由を法制度として保証し、そのために不可欠な信仰の自由と他者の信仰を許す、あるいは「信仰的には許せなくとも社会生活上はこれを堪え忍び、その存在を許す」ことを「寛容」の精神として、これを、市民社会を支える美徳としたのである。そして、このロックの思想を更に具体的な制度として確立したのが、アメリカ合衆国憲法の起草者であるジェファソンであった。彼はヴァージニア権利宣言において信仰の自由、つまり「宗教行事を為すことについての完全な寛容(tolerance)」(同315)を定めていたとされる。
しかし、これらも結果的には世俗法のレベルにおける寛容なのである。そこで、改めてトレランスの意味を考えると「耐える。我慢する、大目に見る、・・・」というような意味の真意が理解できる。つまり、キリスト教における救いの正統性を巡って、それこそ血で血を洗う悲惨な対決を経て、漸く信仰の違いを不問にして、つまりその領域には踏み込まない、見て見ぬふりをするという視点を保つこと、即ち寛容(tolerance)精神であり、その思想が寛容思想なのである。そして、その状態を保つことが、一種の理性が働いている状態となるのであろう。従って、彼らの共通の関心は信仰ではなく、寧ろ世俗生活における富の共有、特にその獲得に向かうこととなる。(*ウエ―バーの「Pと資本主義の理論)などは、これを指している、と思われる。」
以上のように、トレランスとい言葉は、厳格な一神教であるキリスト教において、信仰を異にしつつも、同じ生活空間で共存しなければならなかった香取生教徒とプロテスタント教徒のギリギリの共存の状態を表わす言葉であったと思われる。
故に、この状態を表わす言葉は、ほぼ同様意味であるが、宗教性の強いクレメンス(ラテン語は.クレーメーンス:clEmEns)ではなく、いやいやながらでも共生し、互いに信仰を不問する社会をトレランスという言葉を用いてた表わしたのであろう。というのも、前述のようにトレランスは、動詞トレオー(toleO)「支えることができる。重みを支える。良く耐える。大目に見る。忍ぶ。我慢する。」から造られた言葉であり、「堪忍」「免許」というような一方向的な、あるいは「許し与える寛容思想」を表すのに適しているのである。
一方ラテン語のクレーメーンスは、より宗教的というか精神的であり、キリスト教の精神を表す上でしばしば用いられて言葉である。その意味は「やさしい。親切。おだやか。」女性名詞のクレーメンチアは「優しいこと。寛大。慈悲。仁愛」という一種の内面的な美徳、更に云えば宗教的な価値観を多く含んだ意味となる。故に、クレメンスには信仰レベルの意味が強く、信仰を異とするカトリックとプロテスタンの人々の平和的共存の思想を表現するには、余りに宗教的伝統と拘わる言葉と言えるであろう。
つまりトレランスとクレメンスと比較してみると、その違いは歴然となる。勿論、トレランスは、その後も意味を変化させ、より普遍的な思想へと成長してゆく。しかし、ハッカーが指摘したように、近代精神に培われたトレランスとインドなどの東洋の「寛容」思想が、基本的に似て非なるものであることは、以上のことからも推測が着くであろう。
何れにしても近代の寛容思想が、基本的にキリスト教内の宗派対立の超克として生み出された思想、つまりキリスト教内の正統性争いという神学上非常に深刻な問題の一つの回答として、つまり基本的には同じ価値観を共有する宗教内の共存という限定された前提から生まれたのに対して、インドのそれはまさに異質なもの同士の共存関係を見いだそうとするという意味で、より根源的なレヴベルからの思索が不可欠であった。それはインド宗教世界においてヴェーダの権威を否定した仏教においてもしかりであるが、イスラムという全く宗教形態を異にするものとの共存の思想を展開したという意味で、ナーナクの試みはまさに信仰を共有する事はないが故にその正統性を巡り争うことはない、しかし、現実の社会生活において相容れない生活様式、具体的には道徳レベルにおける対立が不可避的関係間での寛容が不可欠となる。
つまり、西洋でも会えて宗教(この場合は宗派であるが)的領域に踏み込まない世俗領域に敢えて限定した状況をtoleranceと表現し、その世俗性を明確に意識して翻訳したのが、井上の寛容という見慣れない、漢字の組み合わせということになる。(*****漢字圏の伝統は、余り一般的ではなかったようである。)
日本語の寛容
改めて、寛容のという言葉に関して、おさらいも含めて検討してみよう。
既に見たように、現在我々が用いている漢字熟語である寛容という言葉は、西欧の(tolerance)の翻訳語として定着した。そして、その功労者が、井上哲次郎であり、その編著の『哲学字彙』(明治14年)であったらしい。というのも、それ以前の辞書では、toleranceは「免許」・「堪忍」などと訳されていた。(明治2年刊の『薩摩辞書』)(つまり、日本語の「寛容」という言葉の背後には、「堪忍」あるいは「許可」と言うような意味、後に検討するtoleranceと同様な、精神構造が前提となっていることが分かる。
つまり、英語のtoleranceの語源であるラテン語のtolerantiaは、trelo「耐える」・「我慢する」・「持ちこたえる」から派生したことばである。だから『薩摩辞書』はtoleranceの訳に、「堪忍」あるいは「許可」という言葉を当てたのである。
しかし、この「寛容」思想には決定的な欠点、少なくも限界がある。なぜならこの寛容という関係が成立するのは、一方が「辛抱する」「耐える」あるいは「許す」ことで成立するからである。つまり一方が、精神的に大きな器を持っていれば、耐える心をもっていれば、この寛容の関係は成り立つからである。つまりその言葉の主語にあたる「耐える者」「許す者」側によって、寛容という関係は一方的に、形成されるあるいは与えられる意味空間で成立するものとなるからである。
ところが、「辛抱させる」「耐えさせる」側の方からの、同じような働きかけはこの言葉には見出せないし、またそれは前提とされない。つまりこの言葉の中では、他者の存在は、自らと同等に意識されることは、求められていないのである。分かり易くいえば「耐える」・「我慢する」あるいは「許す」レベルの寛容は、相手と自らと同等と考えたり、相手を理解しようとする必要は必ずしも無く、ただ場や意味空間を共有することを他者に許す、あるいはそのような状態に絶えるということで十分なこととなる。その意味でこの寛容は、相手の存在に無関心、無理解でも成立する種類の寛容である。)
この種の寛容は、一方が他方に与える寛容、許す寛容ということに結果として止まることとなる。これは寛容に関して研究をしたドイツの宗教学者メンシングが、分類した3つの不寛容性のうちの「内容的不寛容の外的寛容」に当たる。 つまり、現象としては寛容に見えるが、それを支える条件が変われば、即座に寛容から不寛容へと移行するようなレベルのものである。
筆者はこの段階の寛容を「冷たい寛容」、「無関心の寛容」と名づけている。そして、いわゆるセム的一神教の寛容思想は、このように他者の存在を前提としない寛容思想であると、分類することができる。
そこで、典型的なセム族の宗教であるイスラム教における寛容について、先ず簡単に検討してみたい。「寛容」と日本語に訳される言葉、あるいはその周辺の言葉を検討し、その背景について検討してみよう。
冷たい寛容思想の構造
前述の諸々の言葉を、この3つの概念に当てはめると、以下の様になるであろう。つまりアラビア語にいうところの「寛容」のsamuha(samha)「・・に許す。に権力を与える。」からはじまり「tasAmaha寛容である。善意を示す。」も、また、同じく辞書的意味での寛容とされるkarrama「尊敬する。栄誉を与える。」やkaruma「寛大である。気前がいい。」も、 ‘afwa「救済する。許す。。免ずる。」あるいはghafara「許す」も「耐える寛容」であり、冷たい寛容と云うことになる。
しかし、この一方的な寛容には当然限界がある。というのも一方的な忍耐の関係が永久に続くということは、理念的には兎も角、現実的にはありえず、堅実的には必ずこの構図は破綻する。そしてそのときは、正義の戦い(ジハードや十字軍)という自己正当化、自己絶対化の思想が、この許しの構造から生み出される。
それは歴史的に繰り広げられたジハード(古くは異教徒征伐とほぼ同義語であった)による仏教徒やヒンドゥー教徒への激しい戦闘、殺戮、弾圧行為にも見出せる。この点に関しては、マフムード(967―1030)の事例を出すまでもなく、イスラム教徒のヒンドゥー教徒やその彼等が多神教徒と呼ぶ異教徒に対する激しい軍事行動、容赦の無い支配体制は有名である。彼等は、多神教を攻めることを聖戦と呼び、これに宗教的な正当性を付与していた。
もちろん、同様なメンタリテーは、同じくセム族的一神教であるキリスト教にも見出せる。筆者は、その典型を十字軍に見出せると考えている。十字軍も同様に、一方的な宗教的正義をかざして、異教徒や異端を宗教的な正義のなにおいて討伐する、という発想であり、そこには「冷たい寛容」さえ、見出せなかった。
いずれにしても、「冷たい寛容」には、セム的一神教の思想、筆者はこれを単なる一神教ではなく、排他的な一神教と呼ぶことにしているが、この排他的一神教の思想から導き出される寛容は、自己の絶対性優位性を前提とする寛容思想となりがちとなる。
つまり、これが排他的一神教から導き出される寛容思想の限界である。そして、このセム的な「冷たい寛容」の思想が、今日の寛容の語義となり、また世界の秩序を作っていると言う点に、現在の国際紛争の一端がある、と筆者は考える。それは、イスラム・ゲリラと推定される犯罪人によって引き起こされた「9・11事件」、つまりワールドトレード・センター、ワシントンのペンタゴン(国防省)ビルへの、旅客機による自爆事件の直後の、ブッシュ大統領のイスラム教への戦いは「現在の十字軍(正義の戦い)である。正義のアメリカに味方するか、敵にみかたするか・・・」という発言にも見出せる。
一方、このような自己の絶対化、少なくとも自己の視点の正当性を主張する立場からの寛容思想、とは異なる寛容の形態もある。
暖かい寛容思想の構造
一方、直線的で付加逆的な許しの関係ではなく、可逆的・相互交換的、あるいは循環的な許しの構造が、その一方で見出せる。その典型がインド思想、なかんずく仏教であるが、これを「温かい寛容」と名付ければ、その典型は仏教の慈悲の思想にあるが、同様の思想は、ギリシアにも見出せる。
既に検討したように、ギリシア語の寛容の精神を意味する’epieike’iea という言葉にも、仏教の寛容と同等な意味を見出すことが出来る(『岩波哲学思想辞典』)。この言葉は、epi(場所を意味する)とeikeia に分離できる。このeikeia*はeikos *(同じように)eikazw(等しくする、同じようにする)という言葉と通じており、epieike’ieaの意味は、「場所を同じくする」、「他者に場所を譲る」、「道を譲る」というような意味があるとされる。
つまり、この言葉には「自己を他者の立場に置き換えて相対化し、自他の区別を超えてより高次の一体感をもつ」、簡単に言えば「他者を自己と同等に考える」という極めて深い自他同一の原理、あるいは自他の区別を超えた普遍的な思想の深みが表されているのである。
そしてこの精神こそ、インド思想、特に仏教における無我説(ana’tman)や大乗仏教における空(sn’yata’)の思想に通ずる普遍的な精神ということが出来るのである。(詳しくは後に検討する)ここに我々は、ギリシアとインド、特に仏教との間に強い共通性を見出すことができる。しかし、ギリシアでは、インドほどにはこの精神性を発達させなかったようである。少なくとも、その思想は後代の宗教世界には受け継がれなかった様である。しかし、インド特に仏教においては、この思想が宗教的な中核隣、独自の展開を見せている。本小論では、その宗教思想的展開を概略し、更にその仏教が文明形成の基礎であり、更に現在にまで深い影響を与えている日本文明における寛容思想に関して、鳥瞰することを目指している。(話が迂遠になってしまったが、今後もこの点は深く広く展開したい。)
仏教では、「自己の立場の相対化」から、さらに「自他の彼岸における自他融和の一体的立場」という「絶対的寛容(本小論でいう温かい寛容)」の精神を築くことを宗教的な目的の中心に置いている。ところが、メンシングは仏教の寛容思想を、神秘主義的寛容主義と表現している。ところが現実委は、神秘的寛容主義は観念的な寛容思想であり、現実的な展開に乏しいという評価が、この分類の背後には存在するような印象を持つ。しかし、仏教のそれは後述するように極めて実践的な展開をしたものであり、メンシングのような評価よりは、相互性の寛容
いずれにしても本小論でいう「温かい寛容」(以下特に明記しない場合は、寛容と略記)とは、「自らを絶対視せず、他者の存在を尊重し、相互理解、相互補助の上の自他の対等の関係」と言う謙虚な心持や、思想を基とする、ということにしたい。
つまり、他者の存在を単に空間的な意味で許すのみならず、隣人として、あるいは同じ人間(仏教で言えば一切衆生ということにあるが)と認識し相手を自分と対等にみなす(自他同置、自他同地)と言う構造である。それは、その背後に所謂輪廻思想があり、全ての生命の本質的同質性、連続性という基本構造構造(「一切衆生?仏性」、「山川草木*仏性))がある。その結果として他者の尊重であると同時に、自己の相対化(所謂無我・空)、自我の抑制( 忍辱 )であり、そこには必然的に忍耐や我慢(六波羅蜜の徳目)と言うものが付随する。とすれば、仏教的な寛容と言う言葉の示す精神は、世界共通のものとなる。
このように仏教の寛容とは、他者の立場にたって自らの行為や言動を反省し、他者と同じ場や意識を共有すると言うこと、さらには自らに向ける意識を他者にも振り向けるということにより結ばれる関係性(慈悲)によって成立する寛容となる。同様に、自己の謙虚さのみならず他所においても、同様の譲歩、歩み寄りを求めるということでもある。
この精神を共有した上で始めて、「寛恕」「堪忍」「許可」というような言葉によって表される状態が生み出されるのでなければならない。そうでなければ、それは便宜的な寛容(本小論にいう冷たい寛容)となる。以下でシク教の寛容思想の源流に繋がる仏教や、更にインド思想、さらにはイスラムの思想についても、この点をさらに検討しよう。
仏教の寛容思想
仏教の寛容思想は、このように自己の相対化(無我・空)、他者と自己の一体性にある。その思想的根拠は、開祖ゴータマ・ブッダによって与えられた。仏教の寛容思想を支える精神構造について検討しよう。仏教思想、特にゴータマ・ブッダの教えの根本は、自己の絶対化を行わない、ということに尽きよう。勿論、その場合の自己とは、自己が拠り所とする神や理論や立場、あるいは肉体等々、自己を形成する全ての要素のことである。
特に、人間は自己の拠り所とする言説に執着しがちである。言葉を替えれば自己の信奉する信条や主義、あるいは自分の信仰する神を絶対視しがちである。しかし、そのことが人間のあらゆる対立の根本原因の一つである、と釈尊は教える。
(世の学者;あるいは宗教家達は)めいめいの見解に固執して、互いに異なった執見を
いただいて争い、(みずから真理への)熟達者であると称して、さまざまに論じる。(『スッタニパータ』878
しかも、これらの学者・宗教家達は、自説のみが正しく、他者の言っていることは虚偽で ある、というのである。
かれらはこのように異なった執見をいただいて論争し、「論敵は愚者であって、真理
に達した人ではない」という。こらの人々はみな「自分こそ真理に達した人である」と
語っているが、これらのうちで、どの説が真実なのであろうか。
もし、論敵の教えを承認しない人が愚者であって、低級な者であり、智慧の劣った者
であるならば、これらの人々はすべて(各自の)偏見に固執しているのであるか、彼
らはすべて愚者であり、ごく智慧の劣った者であるということになる。
これをさらに具体的に言えば、
もしも、他人が自分を(愚者だと)呼ぶがゆえに、愚劣となるのであれば、その(呼ぶ人)
自身は(相手と)ともに愚劣な者となる。また、もし自分でヴェーダの達 人・賢者と
称し得るのであれば、もろもろの(道の人)のうち愚者はひとりも存在しないこととなる。
(同890)
つまり、
ある人々が「真理である、真実である」というところのその(見解)をば、他の人々
が「虚偽である、虚妄である」という。このようにかれらは異なった執見をいだいて
論争する。なにゆえにもろもろの(道の人)は同一の事を語らないのであろうか」(同
883)
このようにゴータマ・ブッダは、自説のみを絶対視し、他の説を退けるその姿勢が、争いや対立を引き起こす原因である、と教えるのである。
つまり、人々は自説に執着し、それ故に他者を排除しようとし、お互いに争う故に、紛争は引き起こされる、と言うわけである。
かれらは自分の道を堅くたもって論じているが、ここに他の何人を愚者であると見る
ことができようか。他(の説を)、「愚かである」、「不浄な教えである」と説くならば、
かれはみずから確執をもたらすであろう。
一方的に決定した立場に立ってみずから考え量りつつ、さらにかれは世の中でなすに
いたる。一切の断定を捨てたならば、人は世の中で確執を起こすことがない」(同
894)
従って、我々はこの争いを超えるための努力として、一切の断定、あるいは自己のみが正しいという自己の絶対化という執着を超えねばならないのである。
このようにゴータマ・ブッダは、自己の絶対性を放棄することによって初めて、真の寛容が生まれ、自他同置の寛容の関係が生まれるとする。次に、この寛容思想に関して、シク教に連なるインド思想を鳥瞰してみよう。
・ インドの根本思想としての寛容思想の伝統を以下で鳥瞰する。シク教に連なる寛容思想の形成に関してキリスト教精神下に生まれた近代合理主義精神の限界が強く認識されつつある昨今、インドの精神文化に対する評価、特にその多神教的、つまり多元的世界観が、キリスト教的な思想や文明へのある種の「癒し」の思想として、意外なところから期待されているということの一例を紹介しよう。
「でもわたくしは、人間の河のあることを知ったわ。その河の流れる向こうに何があるか。まだ知らないけど。でもやっと過去の多くの過ちを通じて、自分の何が欲したかったのか,少しだけわかったような気もする」・・・中略。『信じられることは、それぞれの人が、それぞれの辛さを背負って深い河で祈っているこの光景です』と美津子は心の口調はいつの間にか祈りの調子に変わっている。『そのひとたちを包んで、河が流れていることです。人間の河。人間の深い河の悲しみ。そのなかにわたしもまじっています。』
「ひょっとすると、ガンジス河のせいですわ。この河は人間のどんなことでも包み込
み・・・。わたくしたちをそんなきにさせますもの」
これは、故遠藤周作の最晩年の小説『深い河』の一節である。
敬虔なクリスチャン(カトリック教徒)として知られる遠藤氏が精神的、さらには文明的な癒しを求めて、最後に行き着いたところがこのインド的な世界であった。つまりインドが未だに維持している精神世界への一種の回帰であった、という点に示唆的なものを感じるのは筆者だけであろうか。
遠藤氏は、この作品で人間の存在の意味について、近代的な自我意識、あるいは個の存在を前提とする近代精神の地平にあるものを探ろうとしている。つまり近代以前においては、ほとんど何処の地域にも存在した転生思想への回帰である。
しかし、それに確信をもてるほど遠藤氏を含めて近代人である我々は、無辜の精神を持ち合わせていない。そこで未だに「輪廻転生」の精神文化が息づく、インドへの魂の巡礼が行われると言う筋書きである。
『深い河』では、主人公である中年女性の美津子と、ドロップアウトしたキリスト教のカトリックの神学者であり神父である大津という、恐らく遠藤の投影であろう男性等を通じて展開される魂の遍歴と覚醒が問題とされた。彼等は人間の存在の意味、生存の過程で不可避的に生み出される罪の意識にさいなまれ続ける。その結果、インドに何かを求めてやってきて、ある種の癒しを得る。その過程で交わされた言葉が、前引用の言葉である。
一体西洋文明に憧れ、敬虔なカトリック信徒として生きた遠藤氏が何故、最晩年において彼の人生の集大成、あるいは終着点においてインドを舞台に選んだのであろうか。インドには一体何があるのであろう?この問いを考えることは、キリスト教を核として形成された近代西洋文明の限界が意識され始めた現在において、特にその精神的な荒廃の原因の明確化と処方箋の形成に貢献し得るものを内包しているのではないだろうか、という期待感を抱かせる。つまり、近代西洋合理主義思想、あるいはその文明が歴史の過程で捨て去った大事な何かを、インド社会は維持している、あるいはインド思想はわれわれにその失った大切なものを呼び起こしてくれる、と彼は感じたのであろう。
近代精神の背後にあるものとインド的なるもの
20世紀の後半より、バラ色の近代文明観、特に科学文明への絶対的な信頼観が、環境問題、原子力関係施設における度重なる事故等々の発生で、急速に減退した。それにともない、精神の荒廃や混迷が世界に蔓延しつつある。現在社会はこの現象に有効な対処法を見つけることが未だできず、混迷の度合いは深まりつつある。そのような時期であるからこそ,逆に我々は歴史に学び、新たな精神の復興を目指さねばならない。しかも、それは単なる自己や自分が属する社会の「癒し(安定)」というレベルに止まるのではなく、新しい文明形成のための、つまり新文明論に益するものではなくてならない、と筆者は考えるのである。
このように近代精神を根底か反省し、それに修正を加えようとするとき、それを可能にする視点は、一神教(的思考:つまり一つの主義や原理のみを正しいとし他を排除する思考)、個人主義、自我の独立等々近代西洋文明を支える精神構造とは、別の独自な道を歩んできたインド文化の検討が極めて有効である、と考えられる。
少なくとも、インド思想の検討を通じて、近代精神の行き詰まり解消のヒントを見出すことは可能ではないか。なぜならインドは以下において検討するように、近代キリスト教文明によって形成された合理主義的な精神文化以前の精神文化を未だに保ちつづけつつ、高度な文明を形成している数少ない地域であるからであり、しかもそれは数千さらには数万年にも及ぶ人類の文化史の歴史に培われた精神の古層文化に通底する深みと広がりを我々に提示するものである。
多様性と寛容という二つの精神
もちろん、インド文化は古代以来の精神を素朴に保存していると言うような文化ではないことは言うまでもない。周知のように,インド文化は他の地域には見られない独自の精神文化を高度に発展させてきた地域であり、その存在はイスラムの大学者イブンハルドゥーン(1332~1406)の「神は、哲学をインドに、手先の器用さを中国に、政治をビザンツに、そしてイスラムを我々に授けてくださった」という表現や、近代以降の西洋の学者達,特にショーペンハウエル等に深い感動と大きな影響を与えたことでも、その偉大さを垣間見ることができよう。
では、一体インドの精神文化の偉大さは何処に見出すことができるのであろうか。端的に言えば、それは「多様なる文化の存続を認める寛容の精神にある」となる。例えば、インドを表現する時「多様性の国」という枕詞がよく用いられる。事実、インド社会は宗教、言語、人種、民族、等々ありとあらゆる価値基準を設定したとき、その何れの要素もインドに見出すことができるほどに多様である。一見秩序に見えるインド社会であるが、その認識は必ずしも正しくない。
ただし、近代的な合理主義、特に、現象界における物質的な存在に中心を置く科学的な合理主義、これが近代西洋文明の特徴であるが、に止まる限り、インドの精神文化の本質や価値を正しく評価することは難しい。そして、この点に気付くこと、あるいは反省を加えることに、インドの精神文化を検討する意味があるのである。
というのもインドには「多様性の中の統一」という認識があり、その多様性と統一と言う言葉の表現する次元は、全く異なる2つの世界を意味している。つまり、インド哲学では、現象世界の多様性、個物の世界の多様性と、その背後にある世界、つまり個物の存在の背後にある普遍的法則性、それをインド思想では真実(サティヤ)などと呼ぶ(特に仏教ではダルマと呼ぶが)。つまり、インド思想ではいわゆる二元論的な世界観(仏教的に言えば真俗二諦説)をとる。しかし、この2つの世界は実は究極的には一つであるとする。つまり、現象的に多様な世界を作るが、その背後は一つの法則性(神でもいいが)が存在するということである。ここに、インド的な多様性を許しつつ、究極において一者に収斂するという存在論(筆者はこれを多現的一元論と表現する)が成立する。これはインドの正統思想であるウパニシャッドでは、梵我一如という。この理論に従うなら、個物を個物たらしめる個性、そしてその違いが動かしがたい事実、あるいはさらに前提として形成された近代西洋文明、つまりその人間観においては個人主義、世界観においてはデカルトよって提唱された唯物的近代科学文明とは対極のインド精神の特徴を見ることができる。つまり、唯物論的な要素還元主義、分析主義に対して、総合主義、相互連関主義(これを仏教では縁起の思想という)である。
つまり、西洋近代文明の特徴としての分析思考、要素還元主義の行き着くところが、現実社会においての民族やイデオロギー、さらには宗教対立の大きな原因の一つであり、環境破壊の最大の原因であるという考えは、決してとっぴなものではないのである。そこにはライプニッツのモナド論に典型的に見られるように、人間社会を含めた事物の認識において個の存在を前提とするが故の文化、文明の必然的な帰結が見出せる。そして、さらにそのような思想を生み出した西洋文明の中核をなすキリスト教的な、というよりそのキリスト教やその兄弟宗教であるユダヤ、イスラムに共通するセム族の宗教に特有な排他主義と選民思想に行き着くことができる。
このような排他的選民主義、つまり自己の存在や立場の絶対化を基調とする思考、そしてそれを核とした文化.文明、この延長線上に本小論で言う「冷たい寛容」の精神はあり、これと対極にある「温かい寛容」の文化、文明が、インド文化、文明、特に仏教のそれである。
インド的寛容性の起源
前述のようなインドの寛容精神の起源については明確に設定することは出来ない。しかし、インダス文明においてすでに顕著に見られる特徴であることは疑いえない事実である。つまり、「世界の四大文明」に数えられるインダス文明において、他の三文明と異なる点は、この文明には強力な武力を行使する王権が存在しなかった、ということである。(26)
つまり、古代社会において王権の存在は、すなわち祭祀王の形態を執ることが一般的であり、それ故に王は絶対化され、その結果宗教や思想が権力によって統合、あるいは強制される傾向にあった。そして、その王の権威を支えるに不可欠な要素として、軍事力が存在した。一般に古代の王の権威は、戦争に勝つこと、敵を打ち負かすことにおいてより発揮されるもの、証明されるものとされた。
しかし、インダス文明ではそのような思想的統制も、当然権力による弾圧も無かったと言われている。というのも、東西約2000キロ弱、南北約1700キロに及ぶ広大なこの文明圏の何処を見ても他の文明のような武器が多数出土せず、また巨大な権力の存在を象徴する宮殿も見つかっていないのである。
それでもこの文明が一つの統一化されたシステムを持っていたことは、各地の遺跡から発掘される均一な度量衡や、未だ解読はされていないがインダス文字の存在で明らかである。つまり、インダス文明は経済的な統合という緩やかな統合システムによって支えられ、それ以外の分野では自由と寛容な平和な社会が形成されていたのだと考えられる。というのも、インドダス文明の遺品の多くに、子供のおもちゃやサイコロなどの遊び道具が多いことなどからも、その文明の特徴を垣間見ることができる。但し、その思想などは、文字が解読されていない現在では詳しいことは不明である。
この文明が急速に衰退した理由は明確ではないが、一般には紀元前15世紀以降、インド亜大陸に侵入、定着したコーカロイド系の遊牧民のアーリア人による征服が原因ではなかったか、といわれている。
いずれにしても、以後のインド精神史上に、このインダス文明の存在は表面的には明確に顕れることは無かった。が、しかし、この文明の精神は決して消え去ったわけではない。特に、父系制社会を基本とするアーリア人の文化が、以後のインド精神史の中心を形成してはいるが、絶対的な多数派を形成する在来の人々との人種的、文化的な融合は穏やかではあるが、けっして絶えることなく続き今日に至っている。
つまり、インド精神史は、インダス文明以来の古代的精神文化とアーリア文化との融合と統一と言うダイナミズムによって、今日に至る伝統を形成したのである。(図 参照)
それ故に、インド精神は、異質なるものへの寛容性や融和、融合という方向が顕著なのである。つまり、インド起源の思想、あるいは宗教は、ユダヤ・キリスト・イスラム(これらを合わせてセム族の宗教と呼ぶ)教のように、自己を絶対化し他者の存在意義を認めなかったり、あるいは排除したりという排他性、独善的傾向をもたないというところに、その特徴があるのである。その淵源は、実にこのインダス文明まで遡ることができるというわけである。つまり、寛容思想は、言わばインド文化における文化的な伝統、あるいは智慧ということができる。それ故に、この伝統は、排他性や選民思想が極めて強いイスラム教においてさえ、彼等のインド定着後には徐々に寛容の宗教へと変化していったことでも、知ることができる。
インド的思惟と多神信仰
宗教学的にインドの伝統的な宗教は、多神教と位置づけられるヒンドゥー教や、その位置づけが難しい仏教でも、共に多くの神の存在を認める。そして数ある神々の中でも、女神への信仰は特に、ヒンドゥー教に顕著であり、民衆レベルにおいて根強く信仰されている。この女神信仰は、いわばヒンドゥー教の特徴の一つにさえ考えられている。
いわゆる女神信仰は、狩猟採集の時代(3万年ほど前)の遺跡などから「OOのヴィーナス」と呼ばれる神像が発見されることから、かなり古い時代から存在したとされる。それは女性の持つ生殖能力への畏敬念、そしてその能力の汎用化と言うべき食糧(獣から木の実など)の増殖(このころは、栽培していなかったので、自然の繁殖力の増加を、女性の生殖力に投影した。)力が、崇拝対象となった、とされる。
この傾向は、農業革命と呼ばれる農耕の始まりと共に、一層顕著となった。農耕文明は、世界各地に豊饒を願う儀礼を産み、女神(地母神)信仰を中心とする宗教世界を形成した。中近東一帯の遺跡から発掘されるアナヒター女神をはじめとする女神信仰は、農耕文明と深く結びついて、世界各地に見出せる。
この女神信仰の特徴は、後に出現する倫理宗教、特に、キリスト教やイスラム教と異なり、現実世界を一定の教理で説明するというようなドグマを持たず、自然を畏怖、崇拝し、自然への感謝を儀礼化するという謙虚さがあった。また、自然を理性的に体系化し、自らの宗教観で一元化しようとする合理化を行わなかったために、自然の多様性をありのままに受け入れる、という寛容さ、多様性、そして柔軟さをもっていた。
その傾向は世界各地の古代社会においてその原初形態を見出すことができるが、インドにおいても同様であった。但し、現代に至るまでこの古代的な信仰形態を残していて、しかも高度な宗教性や文化形態を維持しいてるのは、ほとんどヒンドゥー教のみである、ということができるであろう。
つまり、他の地域、特に、中近東以西では、後に排他性、父系制的傾向の強いキリスト教やイスラム教の支配を受け、このような古代信仰の形式は、異教として弾圧の対象となり、ほとんどその痕跡を残さぬまで破壊されたからである。もっとも、その地母神信仰の痕跡はキリスト教では12~3世紀になってマリア崇拝として一部ではあるが復活した。カトリックでは変則的であるが女神信仰が、今日まで続いているのはこのような理由による。従って、キリスト教でもカトリックは比較的異教や異端に寛容性を示す可能性がある。
しかし、セム的な原理への回帰、キリスト教の原初形態への希求を目指したプロテスタント派や、イスラム教においてはこのような信仰形態は否定された。したがって、このような宗教や宗派が隆盛している地域では、古代以来の多神教の典型である女神信仰はほとんど途絶えている。これらの地域では、前述のように倫理宗教、救済宗教と呼ばれる合理的主義の支配する父性宗教が、有史以来の感性的な女神崇拝に代表される宗教を駆逐した。
ところが、インド社会においては古代以来の多神教、その象徴ともいうべき女神(地母神)信仰が脈々と受け継がれているのである。もちろん、この女神信仰は、密儀や秘儀といった呪術儀礼をともなうために、非論理性、前理性的な傾向をもつものとなっている。が、しかし、人間の理性的な合理的な理解や道徳的な行動が、自然の全てを説明しえない以上、このような一見非合理な部分を持つ女神信仰の存在意義は小さくないであろう。
少なくとも、この信仰形態には、理性と云う名の近代人の都合(思い上がり)によって形成された科学至上主義、言い換えればそれを生み出した人間至上主義文明の欠点を補う、生命体重視の思想種としての人間の発生以来連綿と引き継がれてきた人間の本性を見据えた思想が基本にあると思われる。つまり、人間を特別なものとせず他の生物と同等あるいは連続的な存在と認識する輪廻思想や、徒に自然(この場合は、人間以外のあらゆる存在のこととする)と対峙するのではなく、自らもその一部として謙虚に、そして調和的に生きようとする姿勢などである。この自他を区別しない、あるいは自他という二律背反的な認識そのものを超える思想こそ、寛容の基本的な精神というべきものである。
ウパニシャッドの寛容思想
さて、インド文化の多様性を支える信仰形態が多神教、特に女神信仰として特徴付けられるとすれば、それを思想的に裏付けるのは、ウパニシャッドに代表される神秘主義思想である。(43)ウパニシャッドの思想はインド思想の根本をなすものであり、しかもその思想はいわゆるセム的な単一思考ではなく、多元的で多様な思想の融合体と呼ぶにふさわしい複雑さを持ちつつも、ショーペンハウワ―など近代西洋合理主義思想の限界を見据えた哲学者に深い感動と、新たな人類の知的可能性を実感させた哲学的な力を持っている。
いわゆるインドの神秘主義思想は、世界に広がる神秘主義思想の源流の一つといわれ、その系譜には西洋思想、特にキリスト教の思想的な基盤をなすグノーシス主義・新プラトン主義の思想形成に、大きな影響を与えたとされる。
また、インド国内では紀元前7-6世紀ころから始まるウパニシャッドを中心とする思想の革新運動と時を同じくして、仏教、ジャイナ教、アージヴァイカ教などが生まれ後世に大きな影響を残したことは、よく知られる事実である。
さて、このウパニシャッドの思想的な特徴は、人類最古の哲学文献と呼ばれるように、宇宙の生成や人間存在の意義等々の形而上学的な問題への真摯な探求にある。特に、非人格的な一元的な抽象原理の想定は、現象世界における多様性を肯定しつつ、普遍世界、真実世界における一元的な統一を可能とし、インド思想に共通する「多様なるものの統一」を理論的に可能ならしめた。
試みに、その一例を示すならば、
ブラフマンは実にこの一切(宇宙全体)である。・・・中略。一切の行為を内包し、一切の欲求を有し、一切の香をもち、一切の味を具え、一切に遍満し、無言にして、超然としているもの、これが心臓にあたるわたしのアートマンであり、ブラフマンである。
これがいわゆる梵我一如の思想である。このようにウパニシャッドの思想は、現象界の多様性を認め、それらの差異を前提としつつ、なおかつその背後に一つの絶対的な原理を認めるという意味で、極めて特徴的な思想である。それは同じく絶対原理を想定するも、その原理を具体的な人格や言葉として限定するがために、現実社会の各要素の違いによって争いの絶えない、セム族の宗教との違いを考えれば、ウパニシャッド思想の特質は、21世紀の世界的な思想原理構築に大きな役割を担うことは十分期待される。(*互いに絶対善=正義を主張して暴力の応酬を繰り返すアメリカのブッシュ大統領とアル・カイーダのウサマ・ビン・ラディン氏の暴力の応酬を見れば明らかである)
いずれにしても梵我一如の思想は、ヒンドゥー教のみならず仏教やジャイナ教等々のインド的な宗教の根本思想と強い共通性をなしている。
このウパニシャッド的な思考である現象世界における多様性の背後に一つの真実(原理)を想定するという考え方は、仏教を通じて東ユーラシアに現在でも根付いている。しかし、ウパニシャッドと仏教思想には大きな違いがある。それはウパニシャッドがどちらかというと、有神論的なものにその関心があったのに対して、仏教特にその創始者ゴータマ・ブッタはその基本に人間の根源的な平等性を置いた点で、より普遍性を持っている。
仏教の根本思想: 対立を越える思想
すでに検討したように寛容とは「自らと異質なる信仰や考えを持つものを自らと同一視する(筆者はこれを「自他同置、あるいは自他堂地と表現する」」つまり「他者を自らのごとくにみなしそれを尊重する」という基本的な精神が不可欠である。しかし、具体的にこれを実行するとなるとなかなか難しい問題がある。
本稿では、仏教、特にその創始者であるゴータマ・ブッタの思想と、それを現実の政治のなかで実践したアショーカ王の思想や業績を鳥瞰し、仏教における「寛容」の思想について検討する。
以下では、仏教の寛容思想を支える精神構造について検討しよう。まず仏教思想、特にゴータマ・ブッダの教えの根本はどこに求められるか、といえば筆者は、神や自己の存在の絶対化を行わない、ということに尽きるのではないかと考えている。勿論、その場合の自己とは、自己が拠り所とする神や理論や立場、あるいは肉体等々人間存在を形成する全ての要素のことである。
仏教的に云えば、人間は自己の拠り所とする言説に執着しがちである。言葉を替えれば自己の信奉する信条や主義、あるいは自分の信仰する神を絶対視しがちである。しかし、そのことが人間のあらゆる対立の根本原因の一つである、と釈尊は教える。釈尊は、この点を
(世の学者;あるいは宗教家達は)めいめいの見解に固執して、互いに異なった執見を
いただいて争い、(みずから真理への)熟達者であると称して、さまざまに論じる。(『スッタニパータ』878
と表現している。
しかも、これらの学者・宗教家達は、自説のみが正しく、他者の言っていることは虚偽で ある、というのである。
かれらはこのように異なった執見をいただいて論争し、「論敵は愚者であって、真理
に達した人ではない」という。これらの人々はみな「自分こそ真理に達した人である」
と 語っているが、これらのうちで、どの説が真実なのであろうか。
もし、論敵の教えを承認しない人が愚者であって、低級な者であり、智慧の劣った者
であるならば、これらの人々はすべて(各自の)偏見に固執しているのであるか、彼
らはすべて愚者であり、ごく智慧の劣った者であるということになる。
これをさらに具体的に言えば、
もしも、他人が自分を(愚者だと)呼ぶがゆえに、愚劣となるのであれば、その(呼ぶ人)
自身は(相手と)ともに愚劣な者となる。また、もし自分でヴェーダの達 人・賢者と
称し得るのであれば、もろもろの(道の人)のうち愚者はひとりも存在しないこととなる。
(同890)
つまり、
ある人々が「真理である、真実である」というところのその(見解)をば、他の人々
が「虚偽である、虚妄である」という。このようにかれらは異なった執見をいだいて
論争する。なにゆえにもろもろの(道の人)は同一の事を語らないのであろうか」(同
883)
このようにゴータマ・ブッダは、自説のみを絶対視し、他の説を退けるその姿勢が、争いや対立を引き起こす原因である、と教えるのである。
つまり、人々は自説に執着し、それ故に他者を排除しようとし、お互いに争う故に、紛争は引き起こされる、と言うわけである。
かれらは自分の道を堅くたもって論じているが、ここに他の何人を愚者であると見る
ことができようか。他(の説を)、「愚かである」、「不浄な教えである」と説くならば、
かれはみずから確執をもたらすであろう。
一方的に決定した立場に立ってみずから考え量りつつ、さらにかれは世の中でなすに
いたる。一切の断定を捨てたならば、人は世の中で確執を起こすことがない」(同
894)
従って、我々はこの争いを超えるための努力として、一切の断定、あるいは自己のみが正しいという自己の絶対化という執着を超えねばならないのである。
自我の超越としての無我の思想
ゴータマ・ブッダは、そのためには自我というものに対する執着を超えねばならない、と教えるのである。
つまり、人間は執着するが故に争い生ずる、その執着の対象のうちで最も身近で、わかり易い身体を例にとって、ゴータマ・ブッダはこれへの執着を超えろと教える。
「…神々ならぬ世の人は非我なるを我と思いなし、名称と形態に執着している」(同756)
つまり、人々は身体を尊び、それを重視し、それに執着するが、その事が実は迷いのもとである、というのである。さらに、
洞窟(ここでは身体のこと)のうちにとどまり、執着し、多くの(煩悩)に覆われ、
迷妄のうちに沈没している人、このような人は、じつに(遠ざかり離れること=厭離)
から遠く隔たっている。じつに世の中にありながら欲望を捨て去ることは、容易ではな
い」(同772)
というわけである。
また、ここでは、肉体を洞窟と表現して、空虚なものというイメージを我々に与えるが、これは身体を蔑ろにしろと教えているのではない。そうではなくて、身体と生命の本質を同一視し、これに執着することを戒めたのである。従って、ブッダは、執着を離れての身体そのものを尊ぶことを否定しなかった、というよりむしろ身体を尊んだのである。なぜなら「だれでも、身体によって善行をなし、言葉によって善行をなし、心によって善行をなすならば、かれらの自己は護られているのです。」と考えられているからである。つまり、身体への必要以上の執着持たなければ、身体は全ての行為の源であるが故に、尊いのであり、愛しいもの(PITY)である、と教えている。
どの方向に心でさがし求めてみても、自分よりもさらに愛しいものをどこにも見出さな
かった。そのように、他の人々にとって、それぞれの自己が愛しいのである。それゆえ
に、自己を愛する人は、他人を傷つけてはならない。
このように、自己を愛し尊ぶが故に、自己と同様に自己を尊ぶ他の人々の自己も己と同様に尊べ、というのが仏教の根本的な教えである。ここに、前述のepiekeiaと同様な思想、寛容の精神が明確化されているのである。
このように見るとゴータマ・ブッダの教えは、実に合理的であることが分かる。つまり、他者に寛容になる、あるいはなれるということは、自己を絶対視する、あるいは自分のことだけを考えるという我執の立場を超える、ということであるが、それは自己を否定することでも、軽視することでもなく、むしろ尊重し、愛おしむことを基本とする、ということである。
なぜなら、「この世で自己こそ自分の主である。」であるが故に、「自分の身をよくととのえてこそ徳行を達成」できるからである。つまり「この世では、自己こそ自分の主である。他人がどうして(自己)の主であろうか。賢者は、自分の身をよく整えて、全ての苦しみから脱れる。」(同)ことができるようになるからである。
以上のように、ゴータマ・ブッダは、物事への執着を断つこととと、自らの心身を大切に思うこと、愛おしく思うことの大切さを教える。なぜなら、それが故に人々は他者の痛みや、喜びを我がものとおもえるのであり、それがある故に寛容の精神が形成され得ると考えたからである。この他者への思いやりは仏教では、慈悲という言葉で表現される。(54)
慈悲の思想と寛容
前述のように、我々が他者を尊び、慈しむことができるのは、自己を慈しむ心があって初めて成立するものである。しかし同時に我々はこの愛しい自己に執着しても、またならないのである。
それは何故であろうか。ここに仏教独自の生命観が存在するのである。つまり、仏教では、一切の息生きとし生けるもの全てが、皆尊い存在である、と考えるからである。
いかなる生物生類であっても、怯えているものでも強剛なものでも、ことごとく、長
いものでも、大きなものでも、中くらいのものでも、短いものでも、微細なものでも、
粗大なものでも、目に見えるものでも、見えないものでも、遠くに住むものでも、近
くに住むものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲するものでも、
一切の生きとし生けるものは、幸せであれ。…・・中略。また全世界に対して無量の慈
しみを起こすべし」
なぜなら「この世には無駄なものは何も存在しない」のである。ここから「われわれは万人の友である。万人の仲間である。一切の生きとし生けるものの同情者である。
慈しみのこころを修めて、つねに無傷害を楽しむ。ということが出てくる。
つまり、「一切の生きとし生けるものにあわれみをもたらすこの耕作をなして、バラモンも王族も庶民もシュードラも清められる」という、慈悲の基本姿勢が明確化される。
以上のように慈悲を考えれば、当然生命の尊重、つまり非暴力・不殺生に行き着くであろう。つまり、暴力や争いがなく、互いに尊重し合い、助け合いながら社会を形成している状態、それは社会的に癒しを生む状態、あるいは癒されている状態、ということが出来る。
その意味で、社会的に癒されて状態とは、真の平和の状態ということが出来よう。
仏教における平和とは
インド哲学の碩学中村元博士は、「西洋人の考える平和とは、戦争がなくなって人々が快楽を楽しむことである。ところがインド人によると、静かなやすらぎの境地が平和なのである。」と指摘される。
つまり、単純化すれば西洋的な平和は、戦争という暴力行為が無く、人々が日常の生活を送くれる状態、これを平和というということになる。すなくとも、心のあり方までは問題としていない。言わば表面的な、あるいは形式的な平和の規定である。ただし、心のあり方がまったく問題にされていないわけでは必ずしもない。
一方、インドのほうはむしろ人間の内面が重視されることになる。宗教的に満たされた状態ということであろう。当然、仏教でも社会的な争いのない状態、苦しみのない状態が、その心の平穏を創る前提である考えていたはずである。
従って両者の統合こそ、つまり個々人の内面から社会という集団全体に至るまで、一貫して争いが無く、人々が満たされている状態こそ、真の意味での平和な状態、ということにある。しかし、そのような状態、つまり癒された社会の状態が、本当に実現できるのであろうか?
筆者は、この社会的な平和を実現しようとして現実の政治を仏教の教えに基づいて行ったのが、インドのアショーカ王であり、日本の聖徳太子や天武天皇であったと考えている。
さて、国家的な平和の状態については、後に検討するとして、個人的な平和の状態について、仏教ではどう考えるのであろうか。その点で注目されるのが、仏教の根本的な教えである不傷害・不殺生である。仏教では不傷害ということは、慈悲の実践として大変重要な徳目である。それは、
殺そうと闘争する人々を見よ。武器を執って打とうとしたことから恐怖が生じたのである。わたくしがぞっとしてそれを厭い離れたその衝撃を述べよう。水の少ないところにいる魚にように、人々が慄えているのを見て、また人々が相互に抗争しているのを見て、わたくしに恐怖が起こった。(『スッタニパータ』936)
というゴータマ・ブッダの言葉からも伺える。
だからこそ、実践修行者は生きとし生けるものを害さない人(ahimsaka)で無ければならないのである。しかもそれは、精神的にも、肉体的にも、言い換えれば言葉による暴力である罵言なども、また肉体の殺傷や捕縛というようなものも一切行わないものでなければならない。
そして、
あらゆる生きものに対して暴力を加えることなく、あらゆる生きもののいずれをも悩ますことなく、また子を欲するなかれ。況や朋友をや。犀の角のように一人歩め。(『スッタニパータ』35)
と、いうことになる。
勿論、これでは個人のみの心の平安ということになるので、社会構成者である個々人の徳目としては、不十分である。ゴータマ・ブッタの時代では、このようなことも赦されていたが、やがて積極的に他者への働きかけが重視され、他者への働きかけが重視されることとなった。つまり、
それゆえに、自分の友にも敵にも(平等に)慈しみの心を起こすべし。慈しみの心をもって、(全世界)をあまねく充満すべし。これはもろもろの目ざめた人の教えである」
というわけである。
このように仏教では、敵味方の区別無く、平等に慈悲をたれ、思いやるという姿勢によって社会的な平和を形成しようとしたのである。
それゆえに、全ての対立を超えて互いに理解し合い、慈しみあった社会の建設が不可欠である。そこで争わず、皆が仲良く過ごすための社会の思想として宥和・寛容の思想が不可欠となる。というのも現実問題として、平和な社会は、諸思想・宗教の対立の超越、つまり宥和・寛容の思想によって実現するからである。
仏教における寛容思想再考
仏教では、以上のように、他者を自らと同等と理解し、尊重し相って生きることを教えた。それゆえに異質なるものを排除せず、また自説、あるいは自分の宗教を頼りに、他説や他の宗教を排除しない、という姿勢を主張した。
見たり、学んだり、考えたりしたどんなことについてでも、賢者は一切の事件に対して敵対することがない。かれは負担をはなれて解放されている。かれははからいをなすことなく、快楽に耽ることなく、求めることもない。(『スッタニパータ』914)
つまり、すでに見たように仏教では、争いのもとである
聖者はこの世でもろもろの束縛を捨て去って、議論が起こった時も、党派に組することがない。かれは不安な人々のうちにあっても安らけく、泰然として、執着することがない。同921)
のである。 しかも、仏教では単に争わないのみならず、
あたかも(母が)愛しき一人児に対して善き婦人であるように、いたるところで一切の生きとし生けるものにたいして、善き人であれ」(『テールーガタータ』、33)
あるいは、
究極の理想に通じた人が、この平安の境地に達してなすべきことは、
われは万人の友である。万人のなかまである。一切の生きとし生けるものの同情者である。慈しみのこころを修めて、常に無傷害を楽しむ」(『テーラガータ』648)
となる。
このような心を社会の構成員一人一人が持つことで、宥和した真に平和な社会が築けるとゴータマ・ブッダは教えるのである。
このゴータマ・ブッダにおいて示された理想は、マウリヤ朝の第3アショーカ王によって現実社会で実践されたのである。
アショーカ王と仏教的寛容思想の実践
如何なる意味でも理想は、それが如何に素晴らしいものであっても、現実の世界に生かされてこそ意味がある。それは宗教においてはなおさら重要なことである。にもかかわらず、一般に仏教に関しては出家主義的、脱世俗的傾向が強く、現実の政治や経済といった世俗生活に、仏教の理想は反映出来ない、あるいはなし難いと考えられている。(64)
しかし、そのような考えは政治と宗教が一体不可分な関係にあるセム的な宗教、つまり、ユダヤ・キリスト・イスラムの各宗教との比較、あるいはキリスト教の教えを核として形成された近代西洋文明下の政治と宗教の分析視点からのものであり、必ずしもインドや中国・日本という非セム的宗教圏を分析して得られたものではない。
従って、今回検討するインドや日本社会を分析するには、これらの地域に即した方法論が不可欠であろう。筆者は、この点について他のところで論じたことがあるので、詳しいことはそれに譲り、結論のみをいうならば、仏教においては、セム的な政治・経済への直接的な関係とは異なるが、現実社会と強い結びつきを当然持ていたし、またそれが社会のなかに強い影響をもっていた、ことは議論の余地はない。
以下においては、この点をインドのアショーカ王の善政と我が国の古代の帝王達において検証したい。
アショーカ王と仏教理念
アショーカ王については、日本でもよく知られている。しかし、その王の政治哲学や、善政の内容となるとそれほど知られているわけではない。特に近代以降の日本では、廃仏毀釈や明治政府の敬神排仏思想教育もあって、仏教と社会との結びつきは、葬送儀礼にほぼ限定されるか、一種の例外として、新興仏教教団において強く主張されるに止まっているのが現状である。
しかし、当然ながら仏教が、人々の幸福を目指して教えを説き、これを実践しようとすれば、社会的な活動は不可避であり、当然ながら政治的な活動をともなうことは当然である。つまり、仏教の精神を社会生活に生かす、より具体的には仏教の教えをもって政策として生かすということである。
この点が特に顕著に表れているのがアショーカ王である。アショーカ王に関して、中村元博士が「人類の過去の歴史を回顧するならば、われわれは幾多の偉大なる帝王の姿を思い浮かべることができる。かれらは広大な地域を征服し、巨大な帝国を組織し、多数の奴隷を使用して大土木工事を完成し、壮大華麗な宮殿に映画の日夜を送った。かれらは偉大であった。しかし、アショーカ王のように崇高な宗教的精神を懐いて大帝国の統治にあたった人は、恐らくほかに殆どいなかったのであろう。」(68)と述べておられるように、アショーカ王は仏教の理想を現実社会に反映し、善政をしいた王であった。彼の思想やその実践についての検討は後に詳説するが、アショーカ王と程同じ時代に、アショーカ王と同様、巨大な国家を築いた秦の始皇帝との比較を行うと、その特徴は更に顕著となる。
つまり、宗教的な理想に燃えて、善政に心がけ国家経営を行ったアショーカ王と武力と征服欲によって中国を平らげはしたものの、その後は死を恐れ、疑心暗鬼のうちに一生を終えたのあの秦の始皇帝とは、まさに対極関係にあるのである。
以下においては、アショーカ王の政治に仏教の理想が如何に反映しているかについて、検討する。
アショーカ王の宗教的寛容
アショーカ王は西暦前ほぼ268年から232年の間、インドを統治したマウリヤ朝の王である。彼の詳しい伝説については、ここで触れる紙幅の余裕はないが、彼の存在は仏教圏においては護教の聖王として知られている。
しかし、世界各地に見出せるような狂信的な宗教者ではなかった。つまりアショーカ王は仏教のみを許し、他を弾圧するような偏狭な宗教政策をとらなかったのである。
中村元博士によれば、アショーカ王は熱烈な仏教信者であったが、決して諸宗教を排斥する事は無かったし、むしろジャイナ教・バラモン教。アージーヴァーカ教をも保護し、育成したのである。つまり、アショーカ王は
(神々に愛された温容ある王)は、一切の宗派の者があらゆるところにおいて住することを願う。彼らはすべて克己(自制)と身心の清浄とを願っているからである。ところで(世間の)人々は、種々の欲求をもち、種々の貪欲をもっているが、彼らは(克己自制と身心の清浄との)すべてを行うべきである。(摩崖勅令7章)72
このようにアショーカ王は、すべての宗教・宗派の活動を許し、それを援助し、彼等が自らの宗教に専心できるように計らったのである。そこにはアショーカ王の次のような宗教に関しての確信があったのである。
しかし(神々に愛せられた王)が思うに、すべての宗派の本質を増大せしめようとすることのように、かくもすぐれた施与または崇敬は(他に)存在しない」(摩崖勅令12章)
つまり、全ての宗教を保護し、全ての宗教が互いに争うことなく、社会に浸透しより良い社会を作
る、という強い意志である。
勿論、アショーカ王はすべての宗教が無秩序に行動してもよいと言っているのではない。そこに
は自ずから制限がある。それは
(神々に愛された温容ある王)は、出家者と在家者との一切の宗教を施与によって崇敬し、また種々の崇敬をもって崇敬する。
しかし(神々に愛された王)が思うに、すべての宗派の本質を増大させようとすることに、かくも優れた施与または崇敬は(他に)存在しない。
(すべての宗派の)本質の増大は多種の方法によって起こるけれども、その根本となるものは、言語をつつしむこと、すなわち不適切な機会においてもっぱら自己の宗教を賞揚し、非難してはならないこと、あるいはそれぞれの機会において温和であるべきである。
そうであるからこそ(各自は互いに)それぞれのしかたによって他の宗教を尊重すべきである。もし(互いに)このようにするならば、みずからの宗教を増進させるとともに、他の宗教をも助けるのである。
このようにしないときは、みずからの宗教を害する。なんとなれば、まったくみずからの宗教に対する熱烈な進行により、「願わくば自分の宗教を輝かそう」と念じて、みずからの宗教をのみ賞揚し、あるいは他の宗教を批難するものは、こうするために、かえって一層強くみずからの宗教を損なうのである。ゆえにもっぱら互いに法を聴き合い、またそれを敬信するために(すべて)一致して和合することこそ善である。けだし(神々に愛されし王)の希望することは、願わくばすべての宗教が博学でその教義の善きものとなれかし、ということだからである。(摩崖勅令12章。)
このように、アショーカ王は法勅によって述べているのである。
そしてアショーカ王の理想は、法勅として、各地に発布され、教法大官などの官吏によって実行
に移されたのである。その結果、
彼ら(教法大官)は、一切の宗派のあいだにおいて法を確立させるためには、また法を増進
させるために、あるいはギリシア人、カンボージャ人、ガンダーラ人、ラティカ人、ピティカ人、ま
たは、他のすべての西方の隣邦人の中で法の実践に専心している者の利益・幸せのために活動する。(摩崖勅令5章)
これこそ、まさにゴータマ・ブッダが示し、アショーカ王が政治の場において実現しようとした仏の
寛容の精神である。
アショーカ王の政治政策:法の普及と実践
仏教の理想を現実の社会に生かそうとするアショーカ王にとって、現実の生活もまた仏教の理想
貫かれていなければならなかった。では、その理想とは何か。それは慈悲の政治ということである。
そして、それを実践するためのものが、アショーカ王が「法(dharma」)」と呼ぶものである。この法
は、人間の有るべき姿、理想としての規範を意味するものであり、それ故に全ての人々によって実
践されるべき徳目を含んでいるとされる。
そして、それ故にそれぞれの人が、それぞれの立場で現実社会において実践することが要求
されるわけである。彼は言う「法とは善である。」(石柱第二)、つまり、 法は善であるが故に実践されなければならない、とするのである。それでは法とは具体的に何を言うのであろうか?「曰く、(法とは)汚れの少ないことと、衆多(数多い)の美徳と、あわれみと施与と真実と(身心の)清浄とである」石柱勅令2
さらに、
この法の敢行と法の実践とは、あわれみと施与と真実と(身心の)清浄と柔和と善良とである」(石柱7章)
そして、「神々に愛される王は、一切の生類に対して傷害をなさず、克己あり、こころが平静で、平
和なることを願う」(岩石13章)のであり、これは王のみならず全ての人々に奨励された。つまり
けだし、たとえ莫大な布施をなさない人にとっても、克己抑制、身心の清浄、報恩の念、堅固な信仰は、実に常に(力あるものとして)残る」(岩石勅令7)
このように、彼は一切の生きとし生けるものの生命を尊重し、自らの身を律して、民衆の福利のため
に、一生を捧げたのである。
宗教的理想の実現としての「法」
周知のように、アショーカ王は、みずからの悲惨な戦争体験から、仏教に深く帰依し争いのない平
和な国家を建設すべく(仏)法に基づく統治を目指したのである。
既述のように、アショーカ王の法とは「現世ならびに彼岸の世界に関する利益安楽は、法に対す
る最上の敬慕、最上の考 察、最上の敬信、最上の努力なくば、正しく行うことが難しい」(石柱第章)ものであるけれども、しかし、それを実践すれば「たとい身分のひくい者であっても、精勤すれば、広大なる天界に到達 する を得るであろう」(小摩崖第一)というものと考えられた。
従って、法の実践は誰でも、どこでもできるものであるが故に、全ての人がこれを実践することが、善とみなされ、またそう要求もされた。
つまり、王自ら「われは(わが)精励に関しても、また政務に関しても、満ち足りたと思うことがない。」(小 6章)のであった。つまり、彼は常に「全世界の利益」を願い、そのために自らも日夜努力した
のであった。彼は言う
過去長期の間、未だかつて(いかなる王といえども)、どんな時にでも政務を裁可し、あるいは上奏を聞くということは無かった。ゆえにいま、われ次のごとく命ずる。すなわち、われが食事中であっても、後宮にいても、内房にいても、飼獣寮にいた時も……上奏官は人民に関する政務をわれに奏聞すべきである。しからば、われはいずこにあっても、人民に関する政務を裁くであろう。
と。
彼は仏教の教えによる、つまり法による理想国家の建設を目指し不断の努力を惜しまなかったのである。しかも、この法は王のみならず
身分の低いものでも、身分の高貴な者であっても、ともに励してつとめるように、といって、また
わたくしの辺境の人々でもこれを熟知するように、といって、そうしてこの精励が永く存続しうる
ように、と発せられたのである。(小岩石詔勅1)
このように、善なる法が王から民衆に至るまで実践されれば、平和な社会が形成されることとなる。
この善なる法による社会統治は、
この(法による)勝利は、ここ、すなわち(神々に愛された王)の領土においても、また六百ヨージャナに至るまでのすべての辺境の人々のあいだにおいてもーーそこにはアンティヨーカという名のヨーナ人の王がいる。さらにそのテンティヨーカ王を越えたところにトゥラマヤ王とアンティキニ王とマーカ王とアリカスダ王という名の四人の王がいる。・・・中略。さらに(神々に愛された王)の使節のいまだ赴かないところにあっても、人々は(神々に愛された王)の法と実行と規定と法の教えとを聞いて法に随順しつつあり、また将来にも法に随順するであろう。このようなことによって得られた勝利は、全面的な勝利である。そして全面的な勝利は喜びの感情をひき起こす。いまや法による勝利において喜びが得られたのである。しかしその喜びも実は軽いものにすぎない。彼岸に関することもそ大いなる果報をもたらすものである、と(神々に愛された王)は考える。(摩崖勅令13章)
であり、その故に各地に広がった。
つまり、彼の法、それは「不殺生」・「不傷害」・「精勤」・「他者への思いやり」等々であるが、この仏教的な徳目の実践により、国が安定し、国庫は富栄えたのである。それ故この法による統治は、その領土を越えて世界に広まっていったのである。
しかも、それはアショーカ王の富や名声のためではなく、あくまでも一切衆生のため、人民のためであった。アショーカ王はいう
一切の人々は我が子である。あたかもわが諸皇子のために、彼らがこの世およびかの世のすべての利益・幸せを得ることを(親であるわたくしが)願うのと同じく、またすべての人々に対してわたくしはこれを願う。
おもうに未だ服従しないもろもろの辺境は、「王はわれわれに対して何を欲するので
あろうか?」と思うことであろう。しからば、次のことこそ実に辺境人に対してわが願うことである。すなわち「(神々に愛された王)はこのように望む …・諸々の辺境人がわたしを怖れることなく、私を信頼し、わたしから幸せのみを受け、苦悩を受けることがないように」ということを彼らに了解させ、また「(神々に愛された王)は、恕しうることはすべてわれわれのために恕してくれる」ということをりょうかいさせるである。そうして彼らがわが(教え)によって法を行って、この世に関する(利益・幸せ)を得るにいたるようにさせよう。(別刻岩石勅令第2章)
このようにアショーカ王は、仏教精神をもって、帝国を治めたのである。
また、仏教的な精神に則り、彼は生きとし生けるものの幸福を実現させるため、つまり慈悲の政治政策を以下のように講じたのである。
このようなアショーカ王の政治姿勢は、宗教的な理想を修家集団の中で実現したゴータマ・ブッダに対して、現実社界においてこれを実現しようとした点で、シク教の第三代グルのアマルダスとの共通点を見ることが出来る。
生命尊重の政治の実践
では、アショーカ王は如何なる方法で、仏教尾宗教的な理想を現実的に社会展開したのであろう。まず不傷害・不殺生であるが、彼は「生類を屠殺しないことは善である」(勅令3章)との仏教的精神から、「ここ(自分の領土内)では、いかなる生きものをも殺して犠牲に供してはならない。また祭宴を行ってはならない。」(第一法 勅)とした。そして、単に生類の殺害を禁止したのみならず、
(神々に愛された温容ある王)の領土のうちではいたるところに、・・…中略。他の諸王の国内の いたるところに、(神々に愛された温容ある王)の二種の療病院が建てられた。すなわち、人々のための療病院と家畜のための療病院とである。そして、人に効があり、獣に効があるいかなる
薬草でもすべて、それの存在しない地方へはどこであろうとも、そこへそれらを輸送し栽培させ
た。また木の根や果実の存在しないところでは、どこであろうとも、そこへそれらを輸送し栽培さ
せた。また道の傍らには井戸を掘らせ、樹木を植えさせた。…それは家畜や人々が受用するた
めである。(摩勅令2崖章)
というように、それぞれの生命を貴び最大限の努力おも行ったのである。
それは「一切の生きとし生けるものに対して、傷害をなさず、克己あり、心が平静で柔和であることを願うからである。」(第13章)という彼の信念に発しているのである。
彼はこれらの信念を具体化したものを「法」と呼び、この「法」を実践することを自らの使命としたのである。そして、この法を自らの実践し、また人々に知らしめるために「すなわちひとびとがこのように実践遵奉し、また、(この理法が)永久に存続するように、ということを目指して(この法は、岩や石などに)刻まれた」(第2章)
以上のようなアショーカ王の政策は、国内における罪人の死刑の廃止にまで及んだといわれている。遥か後インド訪れた中国僧の玄奘三蔵は、アショーカ王の子孫が治める一小国の事例として、「そこでは、アショーカ王以来、今日に至るまで罪人への死刑が廃止されいる」(73)と伝えている。
この不傷害・不殺生の思想は、やがてインドの他の宗教にも受け継がれ、今日に至っている。特に、インドの中世から近世への移行期にあたる15世紀以降、インド西北部のガンダーラ地域を含むパンジャブにおいて大きな勢力を確立したシク教教団は、仏教思想と強い共通性のある独自の思想と社会が形成された。以下においては、その初期のシク教教団において、創始者ナーナクと並び重要な役割を果たした第三代グル・アマルダスに関して、その思想や活動に関して検討する。
第三部シク教思想の二大源流
シク教とインド文化
16世紀の初頭、西北インドに出現したシク教について、一般には「シク教は、ヒンドゥー教とイスラム教の折衷宗教」という説明がなされている。
このような説明が必ずしも正しいものでないことは、本書において漸次紹介していくこととするが、一方でこのシク教に対する評価は、シク教の一面を適確に表現していることもまた事実である。なぜならシク教は、ヒンドゥー教とイスラム教の相方を母体として成立した宗教だからである。
本書では、「シク教は、ヒンドゥー教とイスラム教を融合した宗教」と位置付け、この点を主に思想面から立証しようとするものである。したがって、シク教思想を考察する前段階として、まずシク教を生みだしたヒンドゥー教、特にその中でもいわゆる民衆主体の宗教運動としてシク教思想成立に大きな影響力のあったバクティ運動とその思想について、検討を行うことにする。
その後、イスラムのスーフィズムを検討する。
さらに、これら異なる宗教に代表される価値観を、宥和統合した思想的な背景としての典型的な思考について、ウパニシャッド思想との関連を検討する。
2―バクティズムの概観
バクティの概念
このバクティ(bhakti)という言葉は、一般には神に「捧げる信愛(その意味は神への情熱的帰依)」と訳される。語源的には「帰依すること」、または「帰依する対象を愛すること」を意味する動詞語根bhajから派生した語である。宗教的に解釈すれば、神への帰依のみならず神そのものを愛する対象とするということである。これと同時に、神もまた、そのような信仰を捧げる人間をこよなく愛するという期待がこの思想の背後にあることは、バクティズムにおいてしばしば神と人間の存在を夫婦に譬えることからもあきらかである。
そこで、「バクティズム」の一応の定義を試みるならば、「完全に自己を投げ出して神を愛することであり、神の愛を引き出すこと」ということになるのではないだろうか。
少なくともバクティズムの思想(以下バクティと省略して記載)は、神に対する人間の愛、またはその逆に神の人間に対する愛という相互作用的な関係の上になりたつようである。ただし、
本報告では、バクティそのものを本格的に研究することは本来の目的ではなく、シク教あるいはシク教の創始者ナーナクの思想理解のためのバクティの検討が主眼である。したがって、きわめて限定的なバクティ紹介であることを予め断わっておく。
インド神秘主義思想の概観
インドの神秘主義思想は多様である。その形態も複雑であるが、まずこれを分類するときに、宗教によって区分すれば、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、シク教、という云わばインド・オリジナルの集団と、イスラム教、キリスト教、ゾロアスター教(所謂パルシー)に分けられる。
また時代的に区分すると、アーリア人の侵入からウパニシャッド時代まで、つまり紀元前13世紀前後から紀元前8-6世紀頃までの呪術性の強い祭儀主義・祭式万能的神秘主義とも言える時代である。さらに紀元前5世紀以降大きなうねりとなった「梵我一如(究極的な真理である大我と個別存在である小我との究極的一致)」を説く、本格的な神秘主義思想を展開したウパニシャッド思想。また、特に、瞑想を中心として存在の背後にあるとされる理法(ダルマ)との一致(悟り)を目指す紀元前4世紀―紀元後8世紀まで続いた仏教の時代。そして現在のヒンドゥー教の中核をなす神への強い帰依と奉仕を説くバクティ思想運動の時代が紀元後8世紀以降現在まで続く。勿論、その間には、後8世紀から12世紀を中心に、ヒンドゥー教・仏教などのヒンドゥー教系宗教を再統合させるのに大きく寄与したタントリズム(密儀的神秘主義運動)もあった。
一方、8世紀以降インドに進攻してきたイスラム教は、12世紀以来イスラム神秘主義のスーフィズムの伝播と共に、急速にインド社会に定着し、ヒンドゥー・イスラム融合文化を作り上げてゆく。その頂点にムガル朝アクバル帝やその孫のダラー・シコウーがいる。
この外に、ペルシャのイスラム化にともないインドに難民としてやってきたゾロアスター教徒や、紀元1世紀から2世紀の初頭、胡椒貿易のために遣って来たユダヤ教徒やキリスト教の存在もある。特に、キリスト教は、16世紀にはイエズス会の伝道やヨーロッパのアジア進出、さらには同地の植民地化などによって、インド社会に大きな影響を与えた。特に、19世紀のインド思想の改革者の多く、例えばブラフマ教会のラーム・モハーン・ローイやアーリヤサマージュのダーヤナンダ・サラスヴァティー、あるいはタゴールなどは、自らの深い宗教体験を元として、ヒンドゥー教とヨーロッパ近代思想(キリスト教を中心とする)の融合が試みられている。
また、非暴力主義で知られるガンディーの思想は、ヒンドゥー教を根本思想としながらも、ジャイナ、仏教、イスラム教、キリスト教の融合思想が見出せる。彼は「神を否定するものはいても真理を否定するものはいない、として真理こそ神であり」真理の獲得「真理の把持(satya’graha)こそ、人間の目指すものであるとし、その前にはヒンドゥーもイスラムも無いと主張した。そして、この「真理の把持」の実践がアヒンサー(不殺生・非暴力)であるとした。
彼の行動と思想は、世界に大きな衝撃と感動を齎したが、マハトマ・ガンディーは現在の偉大な神秘主義思想家と呼べるであろう。
ウパニシャッド以前の神秘主義思想
インド思想、インド神秘主義思想の検討には、所謂歴史時代以前のインダス文明から検討する必要がある。と言うのも、道文明は強力な軍隊の存在を示す武器も殆ど見つからないにも拘らず、東西1000キロ南北1500キロにも及ぶ広大な地域を、武力や権力によるのではなく、むしろ宗教的な権威によって治めていたと、推測されているからである。つまり、この文明には、強い思想性を持った統一した宗教が想定されいるのである。そして、殆どのインド思想に見られる特徴である、現象世界の背後にある見えざる存在に特別な意味を付加する思想(一種の神秘主義思想)は、このあたりを一つの源としていると思われる。
いずれにしても、祭祀王の像と推定されるモヘンジョダロ出土の祭祀王像は、目を半眼に開き明らかに深い瞑想状態を思わせるもので、瞑想によって得られる呪力(神通力)によって、世界や人をコントロールできるとする考えが、彼らの宗教権威を支えていたのであろう。インドの宗教伝統においては、瞑想によって獲得される呪力を重視する傾向は非常に強く、それは現在においても無視し得ないものである。
しかし、このようなインダス文明は、アーリア人のインド侵入、定着と時を同じくするように衰退し歴史の表舞台から姿を消す。そしてインド亜大陸は、インダス文明を支えたドラヴィダ人等に代わり、アーリア人が支配することとなった。 このアーリア人は西洋人と同じ祖先に由来する人種であり、その現住地に着いては決定されていないが、北海北方のクルガン文化地域ではないか、と推定されている。(中村インド史110)
遊牧の民であった彼等は、ヒンドゥークシュ山脈を越えて西北インドに入り、インド・アーリアンと呼ばれた。彼らのインド侵入は、紀元前13世紀末頃であったとされる。(中村インド史106)以後、アーリア人の支配はパンジャブからガンジス河方面へと東漸し、現在のベナレス(ヴァラナシ)付近には紀元前8世紀頃には到達したとされる。この時代から自由思想のウパニシャッド運動が胎動するのも決して偶然ではないであろう。
つまり政治的、軍事的にはアーリア人が優勢であったが、文化的、人口の多さでは先住民であるドラヴィダ人が圧倒的に多かったはずであるから、アーリア人の信仰とドラヴィダ人の信仰は、必然的に融合していったのであろう。その結果生まれたのが、ウパニシャッドや仏教といった瞑想を重視する新しい思想・宗教運動であったと思われる。そして、それは所謂神秘主義思想であり、瞑想を中心とする精神集中の行によって導かれたものである。
もっとも、呪術や苦行によって特殊な能力が得られるという伝統は、ヴェーダ時代の末期にはかなり神道下とされる。所謂シュラマナと呼ばれる、森林や村村を経巡る遊行者も紀元前8世紀頃にはかなりの数が存在した。
彼等は、長髪で粗末な衣服を身にまとっていたと推定される。彼等は森林や村村を遊行して修行を積んだようである。彼等は、心を一点に集中し、精神統一することで特殊な呪力を身に付けることができると考えた。
つまり、その初期には覚醒作用のあるソーマによって得られたと神人合一体験と陶酔体験と、内省による呪力の獲得を目指すインダス文明的な伝統の融合が、この時代以降徐々に統合に向ったのである。
ウパニシャッドの形成
この動きは文献的には、ヴェーダに続き、ブラフマーナ(梵書)・アラニカヤ(森林)文献、そしてウパニシャッドに到達する。そしてそれは、呪術的な神秘主義から神人合一を目指す体系化された神秘主義思想形成の過程でもある。
さてウパニシャッド(upanisad)という言葉は、ヴェーダ聖典の末尾であり、その意味でヴェーダの尻尾(vedanta)とも呼ばれる。このウパニシャッドという言葉は、「近く」を表す接尾辞(upa)と「下に、元に」を表す(ni)そして、「坐する」を表す動詞√sadからの合成語であると一般に考えられている。つまり、ウパニシャッドは、弟子が先生の側に坐って直接教えを受けるということを意味した、とされる。
それは、公の講義や見解以外に、私的な解釈や意見、つまり師から弟子への秘儀の伝承を伴い、結果として「秘密の意義」・「秘説」という意味となり、さらにそれらが記録された書物(『奥義書』)の意味ともなった。
このウパニシャッドは自由思想であり、一種の改革思想であった。それは伝統的な宗教界が、祭式や呪術を中心に極めて保守的に凝り固まっていたからである。そのような宗教・思想界に自由な思想や宗教的あり方を示したのがこのウパニシャッドであった。特に、その初期にはヤージュナバルキア仙などが、理性的な思想を展開した。
また、ウパニシャッド思想では伝統に縛られない自由な発想から、個人の行の可能性が著しく増大した。つまり祭式によって得られる呪力に救いを求める構造から、個々人の宗教的な行、特に苦行によって得られる呪力が注目された。そしてその呪力の探求において、世界を構成する根本原理と一体化することで得られる究極的な智慧の獲得が目指された。
つまりウパニシャッドの文献群を貫くモチーフは、「人間と宇宙を支配する支配者または原理は何か」ということであり(前田専学『ウパニシャッド』)、インドではこの原理を知ることで人間は、その原理と一体化でき、それによってこの原理を自由に操ることが出来ると考えていた。
もちろんこの一元的原理の探求は『リグ・ヴェーダ』時代から存在した。もっとももそれは『リグ・ヴェーダ』の比較的新しい部分に見られるものである。(『リグ・ヴェーダ』第10巻121讃歌など:松浪121)いずれにしても、インド人たちは、比較的早くから神々(現象世界を表象する)の存在の背後、あるいは基底に、最高原理を想定していたのである。
この思想は、ブラフマーナ(梵書)文献やアラニカヤ(森林)書の時代、つまりアーリア人がヴェーダの時代からさらに東へ移動し、ヤムナー河流域(クレクシェトラ)に到達し定着した時代(西暦で言うならば紀元前**頃から**頃までにあたる)に展開されたものである。この時代を代表する思想は、創造主、あるいは万物の根元としてプラジャパティである。
そして、さらにこの一元的な原理を求める思想は、祭祀との関わりを強めながらより一層、抽象的な概念へと展開していった。その典型が、抽象原理としてのブラフマンである。このブラフマンという言葉の語源は不明とされるが、『リグ・ヴェーダ』では念誦する言葉を意味した。(中村『ウパニシャッド』147)それは、神聖で霊力に満ちたヴェーダ聖典の「ことば」、つまりヴェーダ聖典の讃歌・祭詞・呪詞のことば、祭儀に用いられる呪術的なことばを意味し、さらに転じてそこに宿る神秘力を意味した。(同)そして、後にはヴェーダ聖典の知識を意味し、さらにヴェーダのことばに宿っている不思議な呪力、霊力を意味することとなった。
それは、次のように表現される。
彼(インドラ)は、それをブラフマンによって鎮静した。それゆえに「ブラフマンはインドラである」と(人は)いうのである。(松波『ウパニシャッド』148)
一度ブラフマンが世界原理として立てられると、ブラフマンは種々なる原理や神々と同一視され、しかも根源的な存在、原理的な側面を一層深めていった。そして、後にこのブラフマンの探求がウパニシャッド思想の重要な課題となる。
このブラフマンと同様に重要な存在に、個我と訳されるアートマンがある。このアートマンの語源については諸説あるが、要は「気息」・「呼吸」を意味することばである。さらにアートマンは、個人の生命または神聖な個人性を授ける原理または実体であると考えられた。(中村179)その後、アートマンは「身体」・「生気」などの意味に展開し、最終的には「自己自身」という意味となった。さらに自己の存在理由の探求、つまり自己の存在の根源的な根拠を明らかにしようとする知的な動きに発展してゆくのである。
やがて両者が、同一視されるようになる。(これが後に検討するウパーサナの思想である。)つまり「このブラフマンは、前も無く、後ろもなく、内もなく、外もない。ブラフマンはこのアートマンであって、一切のものを知覚する。」(中村149)のであり、さらに「それは自己(アートマン)を知った、―――(われはブラフマンである)と」(ブリハッド四-四-25中村186)という理論である。ここに、梵我一如(「ブラフマンはこのアートマンである」(187)のウパニシャッド的神秘主義思想が成立するのである。
このようにウパニシャッドは、ヴェーダ以来の祭式万能主義から、個々人の知的な活動を通じて宇宙の根本原理との一体感(モークシャ)を得ることを目指した思想運動であった。それは言葉を替えれば、個々人の努力によって悟りを得る、救済を得ることができるとする思想の革新運動であったといえる。つまり、個々人の努力によって、人間は神と一体化することが出来、それがインド人の求めた救済であった、と言うことである。
もっともウパニシャッドは一時期の思想運動ではなく、インド思想・宗教における一つの流れでもあり、内容や構成さらにはその成立年代などが広汎である。つまりその数が膨大であり、その成立期間さえも紀元前8世紀頃から紀元後16世紀のイスラム教の原理を説く『アラー・ウパニシャッド』(前田専学:ブリタニカ)ものまである、とされる。
* ウパニッシャッドの構成
ウパニシャッド文献は、大きく新旧に分類される。そして、古くから知られる古ウパニシャッドとしては、13あるいは14が知られている。さらにまた、この古ウパニシャッドは、中村元博士の研究によると初中後期の三期に分類される。そして、初期は第1、第2、第3に分類される。初期の第一期の成立期間は、紀元前800年頃とされ、初期の第3期がほぼゴータマ・ブッダの生存時代となる。この初期を代表するウパニシャッドが『チャンドーギャ・ウパニシャッド』や『タイッティリーヤ:ウパニシャッド』である。中期はゴータマ・ブッダ以後となっており、大体紀元前四世紀の中ごろ以降となる。
この中期のウパニシャッドの代表に『カータカ・ウパニシャッド』・『シヴェーターシヴァタラ・ウパニシャッド』がある。ウパニシャッドとヨーガが密接に結びつくようになるのは、この時代からである。
そして、後期は、紀元前200年ころから紀元後200年ころまでとなる。後期ウパニシャッドの代表は、『マイトリ・ウパニシャッド』などである。そして、この時代に『ヨーガ・スートラ』の原型も生れたようである。少なくともヨーガが一つの学派あるいは集団として認められる存在となったのはこの時期とされる。さらに新ウパニシャッド文献は紀元後に制作された一群のもので、そのなかには純粋ヴェーダンタ的なウパニシャッドの他に、ヨーガを説くウパニシャッドや仏教的な視点からのウパニシャッドも存在する。(中村ウパニシャッド25以後)これを図式すれば、次のようになる。(図が入る)
梵我一如(普遍との合一体験)と神秘主義
人間の内面への探求を通じて自我を超克し、神や法というような絶対的存在との合一を目指すウパニシャッドが展開する神秘主義思想は、人間精神への絶対的な信頼と深い理解とが不可欠であった。従って、インドにおいてもその道筋は,決して一様ではなかった。特に、遊牧民の信仰形態が色濃い『リグ・ヴェーダ』の素朴な現実肯定と多神教的信仰、そして何より呪術的な宗教観,特に祭式(祭儀)中心の世界観においては、人間の内面探求というようなヨーガの思想はほとんど表面に現れなかった。
その意味で、後世においてインド神秘主義思想の中心となるヨーガの伝統は、呪術や祭儀を中心とするバラモン階級以外の思想伝統をその起源とするとされる説が有力視される。この点を、日本におけるウパニシャッド研究の草分け的存在である佐保田博士は、ブラフマン信仰は、咒力原理の中核をなすものであり、一方の主体存在であるアートマンを立てる思想とは,本来別系統の思想であると指摘する。(『ウパニシャッドからヨーガ』44ページ)しかし、やがてこの呪術的な思考から梵我一如の思想が確立されるようになる。
この梵我一如思想形成に大きな役割を果たしたのは、ウパーサナ(同置・崇信・念想)の思想である。ウパーサナという言葉は、本来「尊崇する」・「礼拝する」という意味の言葉を起源とする言葉である。
この言葉は、梵書時代から初期のウパニシャッドに至って盛んに用いられるようになり、『チャンーンドギア・ウパニシャッド』には「オーム(神性を表す聖なる音)というこの一語を、高唱として崇信すべきである」と言う表現が見られる。これは、「オーム」という言葉を「その他のヴェーダなどを唱えることに代替する。」あるいは「置き換える。」更にいえば「同じとみなすことができる」と言う意味となってゆく。この思想自体は、極めて呪術的な思想であるが、このウパーサナの思想は、異質なるもの同士を結びつけるためには有効な思想であった。
このウパーサナ思想を基礎として「アートマンとブラフマン」の同置、つまり梵我一如の思想も可能となった。これがウパニシャッドの神秘主義思想の原点となる。宇宙原理とされるブラフマンと個別原理、つまり個々人に内在する原理が究極的には一致するという思想がここに形成され、内なる原理に向かうことを目指してきたヨーガの伝統が、祭式を中心とする『リグ・ヴェーダ』以来の伝統に結びつく道が開かれたのである。
しかもこの思想によって、個々人の存在が絶対普遍原理であるブラフマンと直結できるという思想は、死の恐怖の克服、あるいは再度の死(当時のインド人は、輪廻転生により死は何度でもやってくると考えていた)への恐怖の克服としての解脱の道を理論的に保証したのである。これは伝統的に祭式の力によって可能となると考えられていたものである。
しかしヨーガを基とする解脱観は、特定のバラモンのみが執行できる祭式ではなく、誰でも実行できる修行によって得られる、と主張した。特に、ヨーガの修行によって獲得される特殊な神秘体験が、解脱と同置(ウパーサナ)されるようになり、ヨーガの修行は一層重視されるようになった。
この神秘体験を得るための修行は,ウパニシャッドにおいては、初めタパス(その主なものは難行・荒行であった)と呼ばれる特殊な修行法であったが、後にはそれらを部分的に含めながらもヨーガが主流となる。(53ページ)ヨーガは、タパスと異なり難行・荒行による肉体の酷使よりも、精神統一や意識の集中(瞑想)が積極的になされ、人間の内面への探求とその分析、そして更にそれによって得られる神秘体験(モークシャ)が重視された。その典型がゴータマ・ブッダ以来の仏教ヨーガである。
具体的なヨーガの修行法は、調息や制感を基礎とする瞑想とそれを支える日常的な所作であった。佐保田博士に依ればヨーガでは、意識をより一層統一し更なる高い境地に自らを高めるために、意識統一(凝念・静慮)と、統一したことすら忘れてしまうような精神状態(三昧)が主張されたのである。
つまり前者はある一点に意識を集中するために精神統一することであり、この場合は集中する主体と、集中される対象との区別が存在するので、主客の区別は克服されない。一方後者は、まさに主客が渾然一体となっている状態である。
そして、この意識専注の対象として、ウパニシャッドにおいては、その中に全てを含むとされる聖音オーム(*)があった。また、観想(瞑想)そのものを表す言葉も、ウパーサナからディヤーナに移り変わり一層深化していった。また,ディヤーナ同様、非アーリア思想を起源とするサマーディー(三昧)もウパニシャッドにおける神秘主義思想の発展と共に、盛んに用いられるようになり、一層神秘体験は深められた。
その結果、何者にも捕らわれない真実の自己であるアートマンが、宇宙の根本原理であるブラフマンと同一であるという神秘体験を得ることが覚り、つまりモークシャであると考えられるようになった。
神秘体験とヨーガと仏教
ここに人間は、ヨーガと通じての瞑想に拠って覚りの道、覚りの智慧を獲得できると考えるようになった。この智慧を獲得すれば、内在する真実(アートマン)を汚れた肉体から解放することができる。つまり、解脱ができると考えられるようになったのである。そして、この智慧による解脱の達成をいち早く強調したのが、仏教の開祖ゴータマ・ブッダである。
ゴータ・マブッタには瞑想を通じて解脱を得る主張した。彼は「みごとにとかれたことばは、きいてそれをりかいすれば、精となる。聞きかつ知ったことは精神の安定を修すると、精になる。人が性急であってふらついているならば、かれには智慧も学識も増大することがない。聖者の説きたもう真理を喜んでいる人々は、ことばでも、こころでも、行いでも、最上である。かれらは平安と柔和と瞑想とのうちに安立し、学識と智慧との真髄に達したのである。(スッタニパータ330」
ウパニシャッドの初期の時代には、瞑想(ヨーガ)を通じて得られる神秘体験を基本とした智慧による解脱の道は、ウパニシャッドを支えた正統バラモン階級の中心ではなく、むしろ仏教のような異端(非正統)集団に受け入れられたのである。
とうのも正統派では、解脱の可能性はあくまでも祭式によって生まれるのであり、個々人の行によっては生まれ得ないものと考えられていたからである。その点で、個々人の行を重視し、祭式の効用を否定する仏教においては、ヨーガに依って得られる神秘体験が、重視されたからである。
このようにゴータマ・ブッダに依って見出されたヨーガによる覚りの道は、祭式や苦行というような呪術的から、個々人の救済を個人の努力に解放したという意味で宗教改革、偉大な精神の解放であった。
仏教はまさにヨーガを中心据えたインドの宗教改革の一大潮流となったのである。つまり、瞑想によって体得した智慧(法との合一体験:つまり悟りを通じて獲得されるとする)崇拝の仏教は、祭式と呪術を中心とするヒンドゥー教に対して、新しい道、それは初期のウパニシャッドの理想とした道、即ち神秘主義的思想、を主張したのであった。
*叙事詩などに見るヨーガ
瞑想による神秘体験を重視する仏教以外にも、古代の瞑想修行のありようを知るための文献はいくつか見出すことが出来る。例えば、古代インドの政治経済書として知られる『アルタシャー・スートラ』、その成立は紀元後3世紀頃(その原型はさらに古い)とされるが、同書によれば哲学派としてのヨーガ学派の名が、サーンキヤ学派、ローカーヤタ学派と並び示されている。
ヨーガ学派はサーンキャ・ヨーガと呼ばれるように、サーンキャ学派の影響を受けて学派としては成立しているので、サーンキャ学派の成立とされる紀元前四世紀以降、紀元後三世紀の間に成立したことになる。
この頃のヨーガに関する記述は、叙事詩『マハーバーラタ』・『ラーマヤナ』などに見られる。これらヒンドゥー教関係の叙事詩の中では、ヴィシュヌ神以上に、シヴァ神がヨーガと深く関係を持つと考えられている。後代のハタ・ヨーガの伝統では、シヴァ神がハタ・ヨーガの創始者と見られている。インド最大の叙事詩の一つ『マハーバーラタ』では、その12編においてヨーガのことが詳しく述べられている。『マハーバーラタ』の中でも最も親しまれている『バガヴァット・ギータ』(以下『ギータ』と略)において、ヨーガの第一義は、瞑想による涅槃の獲得を目指す。
欲望と怒りとを離れ、心を制御した修行者にとって、自己を識得した者にとって、梵である涅槃は近くにある。外的接触を外に遠ざけ、目を両眉の間に注ぎ、鼻孔を通る上向の息と、下向きの息とを均等にして、感官、思考器官、理性を制御し、欲望、恐怖、怒りを離れ、解脱に専念する聖者として、常に知る者は既に解脱している。祭祀と苦行を享受する者、全世界の偉大な支配者、生きとし生けるものの友である予を、認識して人は安息に達する。(5-26~29)
と言う具合である。
また、『ギータ』におけるヨーガの瞑想に関する具体的な記述は、
自ら自己を高みに引き上げ、自己を沈下せしめてはならない。自己こそ己れの友であり、自己こそ己の敵であるから。自ら自己を制したものは、自己は己の友である。じかし自己に目覚めていない者は、自己自身が敵の如くに反抗するであろう。自己を制し、やすらぎを得た人の、最高我は瞑想の中におかれている。
(ヨーガの)実修者は人里離れたところに、独り在り、心身を制御して、願望をさり、所有を離れ、常に自己を修錬すべきである。清らかな場所に、自らのため、高すぎず低きにすぎず、布、皮、クシャ草で覆われたしっかりとした座を設え、そこに坐し、意力を一点に集め、心と感官のはたらきを制御し、自己を浄化するために、ヨーガを行うべきである。
体躯、頭、頚を直立・不動に、保ちつつ、端然として動かず、自己の鼻頭を凝視して、そして諸方に目をやることなく、心を安静にし、恐怖を離れ、禁欲の誓いを遵守して、意力を統御し、予を心に念じ、予に専向し、修錬して坐すべきである。かく常に自己を修錬し、意力を制御した実修者は、涅槃をその極致とする、予に内在する安息に達する。(6-5~15)
あるいは
身体からの解放に先立ち、すでにこの世で欲望、怒りから生ずる激情を、克服しうる者は、修練した人、幸福な人である。内部に幸福あり、内部に喜びあり、実に内部に光ある者、その実修者は、梵に合一して、梵である涅槃に達する。疑惑を断ちきり、自己を制御し、すべての生物の福利を喜ぶ、罪のほろびた聖仙たちは、梵である涅槃を体得する。(5-23~25)
となっている。
しかし、『ギータ』においては、同時に瞑想のヨーガから、道徳的な徳目の「実修」・「完成」のために専念することが、ヨーガであるという「カルマ・ヨーガ」の教えが、むしろ中心思想として説かれている。このカルマ・ヨーガの教えとは、自ら与えられた職業や地位においてその全力をつくすことが、究極の道につながる。つまり、日常の場における行為こそが、悟りの道、救済の道であると言うものである。
正統哲学と神秘主義
インド思想の根本である神や超越的存在との合一体験は、ヨーガ(精神集中)を通じて行われた。このヨーガは、様々な学派、宗教と結びついて思想的に発展する。譬えば、ヒンドゥー教の正統哲学であるヴェーダンタ学派と結びついたジュニャーナ・ヨーガでは、絶対者ブラフマンとの合一、つまり解脱を目指すものとなっている。つまり、この派では人生における最高の目的を解脱に置くが、その解脱とは具体的にアートマンとブラフマンの合一だとする。
この点を偉大なるヴェーダンタ思想家シャンカラは、瞑想などの修行を通じて「(輪廻の根源としての無明)を取り除くものは明智(vidya’)である。」として、その明智を得る手段としての瞑想行を奨励する。この明智を通じて、神人合一の解脱ができるとする。つまり、シャンカラの思想はもまた、ウパニシャッド以来の伝統とされる瞑想体験を通じて獲得された「梵我一如」の真実を基礎としているのである。その意味で、シャンカラの思想も明確な神秘主義思想ということが出来る。それは彼が主張した不二一元論(Advaita)思想に明らかである。
つまりシャンカラのよれば世俗的な論理からすれば異相あるいは相矛盾する関係にある存在、あるいは現象、その典型がアートマンとブラフマンであるが、その相違は絶対的な境地、あるいは視点から見れば同一のものである、という思想を展開した。
一方、純粋精神(プルシャ)と根本原質(プラクリティ)との完全分離を理想とする二元論のサーンキャ学派の思想を基とするサーンキヤ学派は、ヴェーダンタ思想とは異なる論理であるが、やはり瞑想を行うことで、解脱、つまり神人合一できるとした。サーンキャの理論によれば迷いの世界は、二つの原理が無明(衝動)によって均衡が破られ、両者の係わり合いが生じた結果生まれるとされる。一端関係しあった2つの原理は様々な要素を生み出し、変化に富んだ世界を生み出すこととなる。そして人間自身もその変化の結果生まれたものであり、その変化の中で惑わされ苦しむこととなる。
そこで、その苦しみから、迷いから解脱するために純粋精神と根本原質の結びつきを鎮めることが必要となる。それができるのはヨーガであり、ヨーガによって獲得された完全なる智によって2つの元素の完全分離の状態、つまり静寂な状態(理想状態)の回復となる。これがサーンキャ学派の神秘思想である。
その他の学派もみな神(時に、最高原理)人合一解脱を目指点で、同様に神秘主義思想である。
タントリズムと神秘思想
さて、インド思想において思弁・理性的で、自己修養つまり修行を重視したウパニシャッド的思考に比べて紀元後6世紀頃から台頭してきたタントリズムの運動は、これと正反対の運動であった。まず、「タントラ」とは、そのサンスクリットの語根は「延ばす」・「持続する」を表す√tanである。ここからタントラとは「知識を広げるもの」あるいは「知識を維持するもの」と言う意味が生じ、タントラ特有の象徴主義的傾向を表すものとなる。
このタントラ仏教は、反苦行(修行)的・反思弁的傾向、つまり易行を説く。そして、高度な思弁や困難な苦行や修行の代わりに、具体的な図像などの象徴を用い悟りが得られるとした。しかし、このタントリズムでは、「易行道」とはいえ目的対象とそれを象徴するシンボル、そしてそのシンボルと自己を結びつけるために、ヨーガの実践が不可欠とされた。このタンとリズムでは、むしろヨーガの実践は、従来に増して重要な意味を持つようになった。
つまり、精緻に体系化されたヒンドゥー教諸派の哲学体系や仏教の教理は、知的対象としては興味深いものであるが、しかし、本来の宗教性という面から見れば、それは形骸化した知識の集積であり、ほとばしるような宗教的な情熱を失せさせることはあっても、掻き起こすことは希である。云わばヒンドゥー教も仏教も共にスコラ哲学の隘路に入ったわけである。そのような時代に勢力を持ったのが、タントリズムである。仏教ではタントリズムのことを秘密仏教(日本では密教)と呼ぶ(詳しくは**参照)
タントリズムにおいては象徴操作を通じて複雑な思想体系や儀礼が、観念的に処理されるために、今まで以上に深い宗教的な瞑想体験を必要とした。そのために、タントリズムにおいてはヒンドゥー教も仏教もヨーガの瞑想を重視した。それ故にヨーガは、一層多様化し、ヨーガの思想もまた行法も複雑化していった。
特に、10世紀頃活躍したゴラク・ナータは、ヨーガを単なる観念論的な瞑想世界から解き放ち、つまり精神世界の行としてのヨーガから、身心一体のヨーガ、具体的には多様な坐法を考案し生前解脱を目指したハタヨーガを普及させた。
以後、ハタヨーガの流れはインド医学とも融合し、独自のヨーガ理論を構築した。その指南書には『ハタヨーガプラディピカ(ハタヨーガの光)』がある。現在インドから発して世界各地に普及しているヨーガは、この系統である。
いずれにしてもヨーガは、インドに於いては神秘体験を獲得するために全ての宗教、それは外来宗教のイスラム教やキリスト教においても共有された修行法であった。
ただし、タントラにおけるヨーガの瞑想は、単なる沈思黙考ではなく、日本で言えば口称念仏や、お踊りのような忘我の状態を導くものまでその範疇に含めることとなった。
ここに従来は、祭式と苦行のヒンドゥー教の諸哲学と論理的、理性的な仏教思想という流れに対して、宗教的な熱狂、没我(法楽)を宗教の中心に置くタントリズムの特徴がある。
しかも、このタントリズムはヒンドゥー教や仏教という枠を超えて共有され、結果としてヒンドゥー教と仏教の境界を希薄化させ、ついにインド仏教の消滅の一因となった。
これ以後のインドの神秘主義思想は熱狂的な合一体験を情熱的に表現する熱狂型に移行してゆく。
インド思想がこのような転換を迎えた背景には、インドへのイスラム教の侵攻という要素が大きかったと思われる。なぜなら、タントリズムと同様インド中世思想を貫くの大きな思想運動に、バクティ運動が有り、そのバクティ運動は、イスラム教のインド侵攻との係わりが少なくないからである。
以下では、シク教の思想的検討、特に自らもバクタであったアマルダスの思想研究に不可欠なバクティに関してやや詳しく検討する。
バクティ運動の出発
南インドに興った新しい信仰としてのバクティは、五、六世紀ころから漸次盛んとなり民衆の間に広まっていった。特に南インドのタミル地方では、タミル語の発達とともにアールワ―ルと呼ばれる宗教詩人たちによって、民衆の間に浸透していった。アールワ―ルたちは、その出身が下層階級だったこともあり、ことさらに身分制度に係ることもなかったし、複雑な祭祀に拘泥することもなかった。ただ、彼は、信仰への情熱だけを歌にして各地を遊行して歩いた。彼らが、ヒンドゥー教変革の口火をきったことはほぼ間違いない。
この新興の教えは、讃歌を通してヴィシュヌ神を中心とする信仰を全インドに徐々にであるが拡大していった。しかし、まだ哲学的理論を展開するまでには発展しておらず、漸くそれがなされたのは、ラーマ―ヌジャ(1017―1137)を始めとするサンスクリット学者であったとされる。「絶対帰依的バクティの強調は、神の下での平等の主張と並んで、遠くアールワ―ルたちの宗教に由来する」といわれるようなバクティの伝統を引き継いだラーマ―ヌジャは、一方では正統のヴェーダンタ哲学の研鑽を積み、制限不二論を唱えた聖者である。彼は『ヴィーダ』や『ギータ―』などの聖典に注釈を施し、伝統的な『ヴェーダ』の宗教とアールワ―ルに代表されるバクティ運動に理論的根拠を与えた。それによれば、「最高神は無数の美徳を有し、全世界に存在し、あらゆるものを創造する。それは、ブラフマンと呼ばれ、イーシュヴァラと呼ばれ、ヴィシュヌと呼ばれる。それは純粋・無形・不倫である(中略)神は人類にたいし、愛と憐憫にみちており、化身としてのラーマにバクティを捧げることによって、恩寵があたえられる」とされて、ラーマへのバクティがブラフマンにもイーシュヴァラにも通ずるとされたのである。
この結果、バラモン階級でもなく高度な哲学的思考を持たぬ一般の民衆にも、バクティ運動が正統ヒンドゥー教信仰と矛盾しないことが示されたこととなった。もっとも、このラーマ―ヌジャの教団は、この後十四世紀に非常に象徴的な分裂をしてしまう。それは、ラーマ―ヌジャの教えが内包していた矛盾、つまり伝統的な側面である保守的正統バラモン思想と、改革的なバクティの思想むとが互いに相容れず独立したのである。それは、保守で伝統を重んずるヴァダガライ派と、社会的にも急進派で民衆の指示を多く取り付けたテーンガライ派とである。
なぜ両者に分裂したかは、ラーマ―ヌジャの主張を概括してみると明らかである。彼は寺院を建て、さまざまな祭式を定め、多くの経典に注釈するという伝統的バラモンの生活を送り、カースト制度を一応認めたという。なぜなら、彼の主張する祭式を実行7するためには、専門の修行が必要となり、自ずと上層階級に限定されてしまうのである。しかし、一方で、下層階級を救うためにも最大限の努力をしたとされ、彼らの救われる道はプラパッティ、すなわち神の庇護をひたすら願うことであると教えたという。さらに、彼は、婦女子の教育に力を入れ、宗教的にも社会的にも男女平等を唱えたのであった。このように不撤底ながらもラーマ―ヌジャの教えは、バクティの諸々の特徴をすでに持っていた。そして、バクティズムの発展過程で両者の差異が決定的となったのであろう。だからこそ、この分裂が象徴的なのである。
つまり、バクティズムと一言で表される思想も実に幅の広いものであり、カビール(1440―1518)やシク教の創始者であるナーナク(1469―1548)に継承される急進的な一派と、クリシュナ信仰などの保守的バクティとではその後の展開がまったく異なるのである。本章で扱うバクティは、主に前者のバクティの流れにあるものであることを、明記しておかねばならない。
バクティ運動の根底
バクティ運動の起源は明確ではないが、少なくとも7世紀ころから南インドのタミル地方を中心に活躍したヴィシュヌ派の宗教詩人アルヴァール達と深い関係がある、とされる。彼らは、神を直接的に知り、神への思念に没入する者というその名のとおり、宗教的熱狂によって神への賛歌を吟唱しつつ寺院を巡り歩いた。彼らは、神への宗教的献身愛(バクティ)から来る情熱にあふれ神との合一を希った。彼らの思想は、ヴェーダンタや仏教というような従来の宗教が求めた智慧による神(仏)との合一というよりも、イスラムのスーフィー的な、熱狂的忘我による神人一致という傾向が強い。その意味で両者をあえて区別すれば、冷静な神秘主義というよりは、熱狂的な神秘主義ということが出来るであろう。
しかし、このバクティ運動は徐々に全インドに広がっていた。なぜなら「バクティにとって主な障害になるものは、ほかでもない無知ではなく不信心である。この教えは、唯神の愛を信じ信愛の情を捧げるのみ」というように極めて単純な教えを展開した。しかも、バクティでは、従来のように無数の神を念じて宗教儀礼を行う必要は無く、特定の一者へのバクティが「最高神は無数の美徳を有し、全世界に存在し、あらゆるものを創造する。それはブラフマンと呼ばれ、イーシュヴァラと呼ばれ、・・・・・愛と憐憫に満ちており、化身としてのラーマにバクティを捧げれば、全ての神の恩寵を得られる」と説くのである。この運動を論理化した思想家の内、特にラーマヌジャ(1017-1137)が有名である。彼はベーダンタ哲学のブラフマンとヴィシュヌ神(その化身ナーラーヤナ)と神学的にも論証した。
しかし、ラーマヌジャは民衆信仰と正統哲学の融合を図りながらも、完全には融合的無かった。彼の思想はさらにマドヴァ(1238-1317)やニムバールカ(14世紀?)を通じて一層、宗教性を帯びるようになった。つまり解脱とは神のごとくなることであり、それは神の恩寵によって初めて可能となるが、そのためには神への絶対帰依による、としバクティを強調した。
さらにラーマーナンダ(14世紀末から15世紀はじめ)は、南インド発のバクティを北インドにおいて普及させた。彼以降中・北インドでも神との忘我的な合一を求めるバクティ信仰がインド宗教界において大きな動きとなった。
つまり理性的な云わば神人合一思想に代わって熱狂的なバクティによる神秘体験がインドでも主流となったのである。その流れからカビールやナーナクなどの中世神秘思想家が多数排出した。(詳しくは*参照)つまり、イスラムのスーフィーとヒンドゥー教の接点は、このバクティ運動にあったのである。両者の近似性が云わばイスラムへの橋渡しとなった、ということはしばしば指摘される。
バクティの根本思想
前述のとおりバクティは、「信愛」と同時に「神への熱烈な帰依」という意味も持っている。信愛と表現すると意味がはっきりしないので、ここではまず「一神に対する愛に基づく信、真心からの絶対的帰依を意味する」ということとしたい。それは、バクティの広発範な意味の中で、特に人から神へ働きかける行為や気持ち(これは信仰というべきかもしれないが)を表しているのである。
バクティ運動で主張する信仰形態、つまりその実践としての、神に信と愛とを捧げその庇護を求めてひたすら祈るという行為は、いずれの宗教においても必要不可欠な要素である。したがって、とりたててバクティ独自の行為ではないように思えようが、バラモン階級に宗教が独占されていた時期に、信仰第一主義の宗教形態を主張することは、宗教の民衆への解放ということにおいて革命的なことであった、ということは意外に認識されていない。バクティの主張する信仰重視の易行道的宗教形態のお蔭で、専門の修行を必要としない、いわば庶民の宗教参加が可能となったのである。このことは「従前の時代においては祭祀の体系が細かに確立し、司祭者が神々との仲介者であったが、このバクティの運動では礼拝個人が神に直面し、直接に神と交渉を持つようになった」と指摘されるように、バクティはインド民衆に神への直接的信仰の門戸を開いたという点で、インド宗教史上革命的な宗教運動であった。つまり、「この運動全体は、バラモンたちの硬直した儀礼宗教と、無感情という理想にたいする、情感溢れるさけびであった」ということができよう。
これを裏付けるのは「バクティには知性は必要のないものである。バクティにとって主なる障害は、他でもない無知ではなく不信心なのである。だから瞑想や精神の制御などによって智恵を獲得しようなどということは諦めねばならない。この教えは、ただ神の愛を信じ信愛の情を捧げるのみである」と示されることや「バクティは行作ではない。何故なら随愛と定義されるバクティは努力に基づかないからである」という指摘から窮うことができよう。そのバクティの基本は、つぎのようにいわれている。
1、 神の完全無欠の愛を信じること。
2、 神にすべての情熱を捧げること。
3、 神に信と愛とを捧げること。
4、 神の意思に従うこと。
5、 人間の魂を尊び、神は彼に信愛を捧げるものに恩寵(神から人や動物その他の物に向けられた愛)を垂れるということを、ひたすら信じること。
このように、祭式よりも信仰を強調する教えが民衆の間に広まったことは、その教えの簡潔さと実践の行いやすさ、つまり易行性がヒンドゥー教信仰に新しい形態を与え、民衆主体の信仰形態が生まれたことを意味する。
つぎに神からの愛、つまり恩寵についても少し考察せねばならない。
ヒンドゥー教(以下、バラモン教も含むものとする)において神から恩寵を垂れるという考えがいつごろから一般化したのかは不明であるが、ヒンドゥー教の神観念によると、「(ブラフマンは)ヴェーダ聖典またはそれをうけた神聖な知識のことであった。さらに転じてそのうちに内在する神秘力をも意味していた。ヴェーダ聖典のうちのブラーフマナ(祭儀書)文献においては、祭祀とは人が人格的存在としての神に供物を捧げて神々を喜ばせることによって恩恵を受けるというよりも、むしろヴェーダのことばを用いて秘密の呪力によって神や人間を強制し駆使することであった。しからば、非人格的なヴェーダ聖典の言葉のほうが神々よりも優位にたつ」ということになる。つまり、神は恩寵を与えるどころか傀儡である。
このような神観念では、神の絶大な力によって与えられる恩寵、特にキリスト教やイスラム教のいうような意味での恩寵という考えは成り立たないのではないだろうか。なぜなら、「ブラーフマナに現れたバラモンたちは、もはや神々に奉仕する敬虔で従順な司祭者ではなくて、その呪力によって神々をも駆使する呪術者である」というのが、ヒンドゥー教における神観念だからである。
これが、ヒンドゥー教の神観念の代表的な形態であろうことは間違いなかろう。そしてそれは恐らく最もインド的な神観念であろう。
その観念が大きく転換したのが、紀元後一世紀ころ成立した『バガヴァッド・ギーダー』の説く神への信愛思想である。その『バガヴァッド・ギーダー』は、もし人が信愛を以て一葉・一花・一果もしくは一掬の水をわれに供することあらば、敬虔なる心ある人の信仰心をもって供したるものをわれは受納す。
われは一切の生類にたいして平等なり、われに憎むべきものなく、また愛すべきものもなし。されど信仰をもってわれを拝するものあれば、かれらはわれの中にあり、またわれもかれの中にあり。
と言明している。
この『バガヴァッド・ギーダー』を通して、バクティの思想は形成されたと一般にはいわれる。
しかし、それが大きな運動になるのは、特に十二世紀からのイスラム教徒(以下ムスリムと略す)のインド侵攻の時期を契機としてであった。少なくとも西北インドにおいてはそのようにいえる。
ラーマ―ナンダのバクティ思想
さて、つぎに挙げなければならないのが、ラーマ―ヌジャ派のラーマ―ナンダ(14世紀末―15世紀初)である。北インドのイラハーバードの出身である彼は、聖地ベナレスにきてラーマ―派を信仰し、その感化で北インドにラーマ―派が流行したという。このラーマーナンダの思想は、カビールに引き継がれ、ナーナクやその後のグルたちの思想に大きな影響を与えた。
さて、まず彼の主張した点を、今度のバクティ思想の研究に便宜を図るためにも、箇条書で整理してみよう(なお、これは土井久弥・黒田恒夫両氏の整理したもの等による)。
1―階級の差別を認めず、ヴィシュヌを祟拝するものをすべて同等とした。神の恩寵は上下貴賤の区別なく、すべての者が等しく受けられるとした。
2―神の信徒の罪に対して、父の子に対するような愛情を持っていて、信徒の罪には目もくれない。
3―サンスクリット語を用いず俗語・方言を採用した。
4―ヒンドゥー教徒・ムスリムを比較的区別せず両者を弟子として認めた。
5―必ずしも偶像の祟拝を禁じなかったといわれる。
さて、ここで極めて注目すべき主張を我々はみる。
まず、1、で階級を否定していることは特別新しいことではないが、恩寵が強調されていることである。バクティ本来の姿からして別段驚くべきことではないともいえようが、それ自体の恩想よりも、それを得るために説かれたという条件に着目したい。これについても前出の土井・黒田論文によると、
a―師(グル)の与えた呪文を繰り返し繰り返し唱える。
b―神に対して家僕の感情をもって仕える。そのためには自己の欠点をみいだし、慢心をさり、あらゆる疑問を解き、常に正しい行いをする優れた師の庇護の下にいたる。
c―志を同じくする信徒を尊敬し、彼らに奉仕する。
このようにまとめられる。
彼のこのような思想展開には、後にシク教に顕著に現れるグル祟拝や倫理観の強調、そして同朋集団の尊重といったことがすでに示されている。つまり、シク教でも、グルの言葉のみが救いの道であるとか、真理の行いが最も尊いなどといわれるようになる。一例を挙げるならば、もしも、人が幾百万もの善行を積み、慈悲を垂れ、人助けをしようとも、この共同体に加わり、神の御名を唱えぬ限り決して十分とはいえない。
と述べるように、シク教徒にとって心を同じくする人々の集団に所属し、互いに助け合うことは、宗教上の救済にも関わる大問題であった。いずれにしても、すでにラーマ―ヌジャの思想の中にシク教に通じる思想があるのである。
また、2、で示したように、父性を強調しているとすれば、これはインドの神々というよりイスラム教の神のイメージが連想され、両者の関係を直接表現するものとして興味深いことであるが、直接資料に当たっての論述ではないので、今後の問題としておきたい。
3、で示したような土着語を使って表すことは、すでに述べたように、バクティ思想家に共通にみられることであった。
4、で示したことも極めて重要である。シク教の根本思想は、後に示すように、ナーナクの「この世にヒンドゥー教もイスラム教もない」という一文にあるからである。
しかし、ラーマナンダの教えは、カビールやナーナクのそれとまったく同じではなかった。彼は、「下層の者をも弟子となることを許したとはいえ、種姓制度そのものを覆したわけではなく、宗教の立場からその制限を寛大にしただけであった」といわれるように、その改革はあくまで宗教上のものであり、彼の思想の中には社会改革と宗教的改革の結合という考え方はなかったように思われる。この点が、カビールやナーナクと大きく異なるところである。
6、 で示したように、ラーマナンダは神像に対する信仰を否定しなかったが、カビールやナーナクはこれに反対した。
以上のことからもラーマナンダの思想は、シク教の思想を考える上で重要であることが理解されるが、それは彼の活躍した時代と場所がナーナクのそれに極めて類似していることによる。それについて「ラ―マナンダの活躍していた当時の北インド一帯は既にムスリムの支配下に入ってから年代も経ち、或る種の回印共存の状態にあった」との指摘がなされていることからも、なんらかの共通点があるのでないだろうか。歴史的にも、このような回印(イスラーム・ヒンドゥー)両教の融合の機運は、かなり広くかつ早くから生まれていた。それについて「十一世紀ハタヨーガの一派は、北インド一帯に広がり、彼らの根拠地であるぺシャワ―ルを中心に広く中央アジアやイランに広がった」と指摘されるように、インド思想、特にヨーガの思想はスーフィズムの思想に、大きな影響を与えたようである(スーフィーの項参照)。
これは、「十四世紀には、マハラシュトラ、グジャラート、パンジャブ、ヒンドゥスタン、ベンガルの宗教的指導者は慎重に、保守的派閥の要素を退け、ヒンドゥーとムスリムの信仰の接点を持ち込もうとした。同時にムスリムもスーフィーの主張、イスラム文学者や詩人などがヒンドゥー教の行と教理とイスラム教の同化を説く傾向がつよく、バクティと同じように、両者を適合させるという主旨のもと、ヒンドゥー教の神々を祟拝した」とされる通りである。おそらくこのような運動は、時代の趨勢としてあちこちでまた日常的に試みられたことであろう。特に、インド各地の土俗神をなんでも取り入れてきたヒンドゥー教の神観念からすれば、イスラム教の神アッラーが一つ神様の列に加わったと考えればよいわけであり、理論的には両者の融合は不可能ではなかったと思われる。もっとも初期には、イスラム教徒の軍事的征服に対する反感や恐怖から、このような運動が定着し民衆に支援されるには結果的にかなりの時間が必要であり、後述のような時代まで持ち越されたのであろう。同様な動きは、イスラム教徒の中にもみられた。
シク教とスーフィズム
イスラム教が本格的に定着しはじめた12世紀以降のインド社会の諸相を考案するには、イスラム教とその文化との関連について、ほとんど関係を持たなかったごとくに認識されてきた。
このような学的傾向を生む要因の一つには、1947年以来、インド共和国と東・西パキスタンとに分離したため、インド思想研究にイスラム教要素の欠落が生じることになったことも大きかったと思われる。いずれにしても、インド・イスラム研究は、今後のインド思想研究に託された重大なテーマである。
本書では、この点を考慮しつつ、シク教思想に直接関係のあるスーフィズムの概念を簡単に考察することにした。
イスラム教徒のインド侵攻は、早くも第二代カリフ・ウマル(在位六三四―六四四)時代の六三六年に行われた。その後も西インド地方にはしばしば侵入し、掠奪や奴隷捕縛を行った。もっとも、この時代の侵攻は総じて単発的で、一過性のものであった。しかし、このような侵略政策もウマイヤ朝のワリード一世(在位七百五―七一五)の東方経営策の転換によって大きな転機を迎えた。インドは七一一年についに本格的で、永続的なムスリムの侵入を受けることとなった。この時西インドは、弱冠十七歳のムハンマド・ビン・カーセム(六八五―七一三)率いるムスリム軍によって占領され、その結果、この地にあった仏教のほとんどがイスラム教に改宗という形で消滅し、ヒンドゥー教も大きな危機に直面した。
西北インドのこの激変について、タール砂漠に隔てられていたとはいえ、インド本国のヒンドゥー教徒たちは、どのようにうけとめたであろうか。それを直接知ることは難しいが、八世紀から十世紀にかけてヒンドゥー文化は黄金期を迎えたという歴史的事実からして、ヒンドゥー教徒内に少なからぬムスリムへの対抗意識と、ヒンドゥー教およびその文化の擁護意識の昂掦を引き起こしたことは容易に想像がつく。つまり、西インドへのムスリムの侵攻が、ヒンドゥー・ナショナリズムを台頭させ、ヒンドゥー教およびその文化を組織化、一元化させ、かつてないほどに活性化させたということであろう。これはつまりヒンドゥー教徒が、ムスリムの攻撃によって、統一を欠いたヒンドゥー教およびその社会を擁護するために結束したということであろう。この気運に理論的な裏付けを与えたのが、八世紀に出現し、ヒンドゥー教を今日の姿に大成したとされるシャンカラ(七〇〇―七五〇)である。彼は優れた学者であると同時に、インド全土を歩いて布教した典型的なヒンドゥー教の聖者であった。さらに、ヒンドゥー教がこの時期に新しい展開をしたことは、プラーナ聖典と呼ばれる民衆信仰を代表するようなヒンドゥー聖典や各種のタントラが、この時代を中心に多数書かれていたことなどからも明らかであろう。つまり、「ムスリム教徒の軍隊が侵入し、従来の宗教を圧迫したが、その結果としてヒンドゥー教の独自性が新に意識されるようになった。そうしてまたイスラム教の影響によってヒンドゥー教のうちにも一神教的傾向が強くなった。また時代の経過と共に、ヒンドゥー教とイスラム教を調和させようとする努力もみられるようになった」と指摘がなされる通りの社会が出現したのである。
しかし、十二世紀以後、中央アジアからトルコ系のムスリムによる侵略が始まると状況は大きく変わった。というものも、八世紀における西インドからのイスラム教徒の侵攻は結局インダス河流城に留まり、ムスリムの直接的な軍事的侵略はヒンドゥー文化の中心地であるガンジス河流域に及ばなかったために、ヒンドゥー教徒は、前述の通りヒンドゥー文化を発展させることができた。しかし、こんどは直接イスラムの文化に隷属することとなったのである。しかも、征服者であるルコ系のイスラム教徒は、軍事力とヒンドゥー文化への非妥協的な態度によって、ヒンドゥー教徒を圧倒したのである。
もちろん、やがてはこの両者は融合し新しい文化を部分的にしろ生みだすことになる。しかし、宗教や思想は、建築などのように明確な形で客観的に観察し証明しにくいために、両者の影響関係は明確にできない。しかし、イスラム文化の影響がインドの文化の隅々まで行き渡っていることを考えれば、イスラム思想のヒンドゥー教思想に対する影響を否定する根拠はどこにもない。
ヒンドゥー教対イスラム教の確執
12世紀以降のインド社会が、トルコ人の征服によって、前述の通りヒンドゥー教の信仰にも大きな変化をもたらした。その代表的な信仰形態が、いわゆるバクティズムであると筆者は考えている。少なくとも十二世紀以後、バクティ運動を西北インドで熱狂的な宗教運動に発展せしめた大きな理由は、ムスリムの西北インド支配にあったといってよい。これと関連して、ヒンドゥー教の中にイスラム教の一神教的信仰形態と類似する人格神に対する信仰形態が出現したことは注目されねばならないのではないだろうか。
もちろん、バクティズムにおける唯一神ヴィシュヌと、イスラム教のアッラーとは大いに異なる。というのも、アッラーは「人間をはじめとする万物を創造し、それらを完全に支配・統禦するイスラムの神が、全知全能の人格神にして唯一の神である。」であるのに対して、ヴィシュヌは古くは「リグ・ヴェーダに讃歌がみられるといい、太陽の光照作用を神格化したもの」とされ、クリシュナやラーマ等の化身を持ち、さらに「他の信仰を否定する排他性は持たず、むしろあらゆる神格をアッラーすら含めてその中に包摂しうる神である」と表現される。つまり、ヴィシュヌは多くの化身(avatāra 権化、権現)という形で信仰されたのであり、その中でも特に、ラーマとクリシュナが重要とされる。つまり、一神とはいっても実際に多神を排していることになる。特に、クリシュナは同じくヴィシュヌの化身であるヴァースデーヴァと同様、実在の人物であったとされる。彼は「マッツラー地方を中心として一神教を創唱し、唯一神をヴァガヴァット(Bhagavat)すなわち崇拝せらるべきものと称し、この性善博愛なる神にたいして信者は信愛(bhakti)を捧げ、その恩寵により、死後は唯一最高神の天界に赴き神の御下にて法悦にしたり」と説いたとされるが、この彼が化身としてヴィシュヌ信仰の中に取り入れられたことは「イスラムにおいて神と人間とは相互に隔絶し、文字通り両面をなすもの」とする、イスラム教の神とは明らかに異なる
ことがわかる。
しかし、それら相違する一方で、化身を崇拝したにしろ、観念的な唯一の神に信愛を捧げるというような信仰形態が、彼らの中に力を持っていたことは大きな意味を持つ。そしてそれは、どちらか一方からの借り物というより、複数の宗教が融合する時にみられる宗教形態の一つとみることのほうが、妥当ともいえるのではないだろうか。
もっとも、普遍的宗教を持ち出されなくとも、ヒンドゥー教とイスラム教の接点はすでに遥か以前から存在した。それはつぎに述べるように、イスラム教側にしろヒンドゥー教側にしろどちらも正統派の信仰ではなく、バクティやスーフィズムといった民衆信仰(これらは信仰という精神性を重視したために、比較的に互いの宗教を認めやすかったのであるが)の内にみいだすことができる。
では、スーフィズム思想の歴史とインド的な展開について概観しよう。
イスラム教とスーフィズム
。
インド化するイスラム
インド亜大陸は、一地域としては、世界第一のイスラム教徒(以下原則ムスリムと表記)人口を誇る。世界におけるムスリム人口が、16億前後である現在、パキスタンの約1億8千万、インド共和国の1億3千万、そしてバングラデーシュの1億5千万と、全世界のムスリム人口の3割弱が、インド当亜大陸に住んでいる。この事実は、非常に重いものがある。
因みに、その起源は711年のムハマド・カーセム(694~715頃)による西インド攻略軍の3000人の軍人を始めとするのである。(注1.『チャチュナーマ』Fathanamah-i Sind)以後、インドのムスリム人口は、移民、改宗、自然増の3要素により増加の一途をたどって来た。そしてその傾向は、現在も続いている。しかし、その間、一本調子で、インドのムスリム人口は増えたわけではない。後に簡単に触れるが、インドにおけるムスリムの増加は、初期の軍事的支配と捕虜や敗者等の改宗、から、征服者によるヒンドゥー教徒や仏教徒等への弾圧と、イスラムの中央アジアなどからの移民政策などによる増加、さらにインド特有のカースト制度の厳しい差別からの解放を願った集団改宗、そして何より自然の人口増加がある。やや詳しく云うと、先ず正式な妻を4人まで持つことが許され、さらに「右手の所有物」と呼ばれる制限なしの奴隷女などが生んだ子供の全てが、自動的にムスリムとなるという独自の婚姻制度がある。
しかし、この中で本稿が問題としたいのは、ムスリム人口の増加において、軍事的には優勢であったが、宗教的には圧倒的少数のインドにあって、軍事力、政治力、暴力ではなく、宗教的な感化力を以て多くの異教徒のインド人、特に民衆レベルへのイスラム教の浸透、つまりインドへのイスラム教の布教、定着に大きな貢献をした、イスラム神秘主義者達の思想について、その諸宗教の共生・融和思想について検討したい。
というのも後に言及するように、インド人、特に民衆レベル(カースト的には、バイシャ、シュードラ、そして仏教など非ヒンドゥー教徒)の改宗に関して、
スーフィー達躍が非常に大きかったと言われているのである。
そこで、インド亜大陸のイスラム化という視点から、このスーフィズムの歴史について、鳥瞰してみたい。
スーフィーの概要
イスラム神秘主義を表す言葉は、一般にスーフィズムと呼ばれ、日本でもイスラムへの関心の深まりと共に、その名称が用いられるようになってきた。しかし、スーフィズムという呼び名は、いわば俗称である。というより寧ろ、ヨーロッパのイスラム研究者が、イスラム教徒の中に後述するように「神との合一をひたすら願い、日々祈りを捧げる人々」を指してこのように命名したものといわれる。事実、イスラム世界ではスーフィーよりも同じ言葉から派生した「タサッウフ(Tas"awwuf))という言葉が一般的である。
さて、スーフィズムとタサッウフの双方の言葉の元となっているのが、アラビア語で羊毛を表す「スーフ(s”u~f)」である。しかし、この語源を、ネルデケに拠って解明されるまで、スーフィーの語源は、「清純」を表すアラビア語に求めたり、中東から地中海地域の文化をリードし続けてきたギリシアの伝統を踏まえて、ギリシア語の「ソフォス(神智者)」を意味する「ソフォス」に求めたりしていた。つまり、前者では、スーフィーは心清らかな修行者となり、後者では神を知る者などという意味に解釈したのである。
しかし、これが古来禁欲主義者の間で、現世放棄や隠遁者、苦行者のシンボルとして纏われてきた粗末な羊毛(s”u~f)でることが言語学的に確定されると、スーフィーたちのイメージは、より現実に近いものとなっていった。つまり、スーフィーとは、現世的な欲求を捨て、ひたすら神への畏怖を基に、ひたすら祈り、禁欲する人々であり、彼等は「アッラーを自ら体験あるいは感得することを目指して、事物の外面より内面に注視しようとする人「つまり、彼等は「世俗的要素をすっかり捨てさり、いわば素裸になって神に面し、肉欲・情欲の誘惑を退け、そうした努力により神のうちに帰一し合一して魂の救済を体験しようとする」人々である。
このように表現すると難しいことになるが、スーフィー達の主張は、日本人には極めて
馴染み易い。というのも、規則や教理解釈に厳格なイスラムの中にあって、スーフィー達は、精神性を重視し、異教徒特にヒンドゥー教徒や仏教徒とも近似した思想基盤を持ち、脱形式、脱教条主義を基調とする、極めて柔軟性に富んだ思想を形成したからである。その故にと思われるが、彼らの思想は、ヒンドゥー教世界のみならず、中国における禅思想、例えば、における寒山拾得、日本人に馴染み有る一休の風狂にも通ずるものである。このスーフィーの説く魂の浄化の階梯は、例えば『華厳経』や唯識思想の説く救いへの道に近似している。いずれにしても、彼等は形式や教義、伝統文化に囚われず、常に真実在である超越的なる者(イスラムでは、アッラー。仏教では仏)への合一、一体化を目指しひたすら修行に専念する。(修行論についは、後に検討する。) いずれにしてもスーフィズムは、個々人の宗教体験、これをファナー消滅、合一などというが、これらを仏教的或いはインド的に云えば悟り体験と言ってもいいであろうと、筆者は考える。ただし、現実には、スーフィズム研究は、スーフィー達の思想のみならず、その集団、つまり社会的な動きまで含めた広い領域を持つ概念となっている。というのも、イスラムの宗教的特徴である政教一元の故に、清貧なスーフィーのイメージとは異なり、時の専制独裁政治や恐怖政治を生み出す運動ともなったのである。
以下に於いては、イスラムの神秘主義であるスーフィズム理解のために、まずその歴史を概観する。
スーフィズムの歴史
イスラムに於いては、ローマ・カトリックに典型的に見られるような、教義や教団の正統性を判断できる権威、つまり体系的な教会のシステムは持ち得ない。つまり、イスラムには、正統と異端と言う二項対立的は、教理的には存在しない。故に、イスラム教学に於いてあるのは、個々人が信ずる教説を信ずる集団とそうでない集団、あるいは多数派か、少数派かである。さらに言えば、ムスリムか非ムスリムか、さらには背教者か、という選択の問題だけである。
しかし、現実にはイスラムといえどもカトリックにおけるような宗派、教派、流派に対する弾圧は、しばしば見られた。そして、その最大の対象が、所謂スーフィーであった。
特に、スーフィーは、後述するように、伝統的、常識的、言い換えれば保守的、形式的信仰生活を大きく逸脱する言行、つまり教条主義的な解釈、あるいは体制批判的な言動をとるために、しばしば権力者や体制側から弾圧を受けた。
しかし、それでもスーフィーが消えうせなかったのは、スーフィー達が持つ純粋な宗教的情熱や、彼らの直向きな神への祈りの姿が、多くのムスリムの宗教心に大いに訴えるものがあったからである。
そもそも、スーフィーの如く、神秘的な体験を通じて神と合一できる、あるいはそうしようとするということは、預言者ムハンマドの「預言者の封印(kh’atama;最後の預言者の意味)」(『コーラン』33~40)と言う徳性に抵触すると考えられる。しかし、その一方で、「世界を創造し」(『コーラン』)、「人間を創った神」(同76-2他)、この人間から隔絶した神が、「汝の首の血管よりも近くにおわします」(同50-16)
そもそも、ムハンマドが神の啓示を受けたその行為そのものが、ヒラーの洞窟に於ける禁欲修行の最中であったことを考えれば、そしてムハンマドの言行(スンナ)が、ムスリムの模範として認識されるのであれば、スーフィーの如き主張は、否定されるものではない。
『コーラン』も「これ、すっぽりと衣ひっかぶったそこな者、夜は起きて(勤行に勤めよ)僅かの時間を除いて。(あとは)ずっとクルアーンをゆるやかに読誦しておれ。まこと夜間の勤行は、その歩みまことに強く・・・。主の御名を唱え、ただひたすらお仕え申せ。」(同73・1~8)と述べており、夜間の一心不乱の神の念想や神の御名の読誦をムスリムの行として「さあ、クルアーンを読みなさい。無理にならぬ程度でいいから」(同20ー1)と『コーラン』の読誦を課している。これなどは、スーフィーのジグルの基本と言うことができよう。
このように、スーフィーの起源は、ムハンマド自身に求めることが可能である。そこで、イスラム神秘主義思想の根源ともいえるムハンマドについて簡単に整理してみよう。
ムハンマドの人生
イスラムの開教者ムハンマドは、中継貿易で栄えていたメッカの豪族クライッシュ族の一員として西暦570年頃生まれた。しかし、彼が生まれる前に父親のアブドッラーは亡くなり、ムハンマドは父権制の色濃い部族社会において、決定的に不利な条件下に生を享けた。
しかし、メッカの有力者であった祖父ムッタリブの庇護の下、その幼少期は一先ず平穏であった。しかし、6歳の時に母と死別し、孤児となった。その後、頼りの祖父アブドルムッタリブもその2年後に亡くなり、彼は殆ど天涯孤独の身となった。そして彼は、アラブの習慣に従い伯父アブー・タリーブの庇護の下に入る。彼はそこで孤児として、決して恵まれたとはいえない鬱屈した青春時代を送ったと思われる。
しかし、転機が訪れた、彼の誠実さを聞き知った女性実業家のハデージャからの求婚である。彼女はムハンマドより15歳年上の40才であった。そして、この結婚によってムハンマドは、資産と精神的安定と、家庭の温かみを始めて味わったようである。また、教育を受ける機会を逸した彼が、キリスト教などの教養を身に着ける切掛けとなったのもこのハデージャとの結婚であった、と言われる。
結婚によって安定した生活を得たムハンマドは、40才頃から、祖父がそうしたように、当時の習慣に従って、メッカ近郊の人里はなれたヒラーの洞窟で、瞑想や祈祷を行うようになった。
この洞窟は、天井が高く、また中にベットを置くことも出来るほどの広さであった。ムハンマドは、この洞窟にラマダン月の一月間籠もり懺悔や悔悛、そして断食を行い、瞑想や祈祷に専念することを数年来の行としていた、とされる。(注前掲載の生涯を参照)
そして運命610年のラマダン月カディールの夜、彼に神(厳密には、アッラーはその尊称)からの啓示が下る。その啓示については、幾つかの説が有るが一般には、
誦め、「創造主なる主の御名において。
いとも小さい凝血から人間を創りなし給う。」
誦め、「汝の主はこよなく有難いお方。筆もつすべを教え給う」と。
はてさて人間は不遜なもの、己ひとりで他には要らぬと思い込む。旅路の果ては主のみもと、とは知らないか。(注『コーラン』96-1-8)
あるいは、
これ、外衣にすっぽりくるまったそこな者(ムハンマドは最初啓示が下りそうになると、恐れて外衣を頭からかぶったという)、さ、起きて警告せい。己が主はこれを讃えまつれ。己が衣はこれを浄めよ。穢れはこれをさけよ。褒美ほしさ親切にするな。(辛いことでも)主の御為に堪え忍べ。いよいよ喇叭が吹き鳴らされる時、まこと、その日は苦しい日、信仰のない人々にはなみ大抵の日ではない。(『コーラン』74-1-10)
だとされる。
これらの啓示が下された初期のムハンマドの姿は、ひたすら神を念ずる後代のスーフィーの原型ともいえる敬虔さ、直向さに満ち溢れている。ムハンマドはアッラーからの直接の啓示を受け[たと当時は、信じていたらしい]預言者として神の命令(啓示)の伝達(普及)に全身全霊を捧げたのである。
ところが、周知のようにその宣教は、苦難の道であった。彼は保守派層から激しい弾圧を加えられることとなったからである。しかし、如何なる苦難にも、神を忘れず、神の心を人々に伝える。この一途な使命感、宗教心こそがムハンマドを支え、そして彼に続くスーフィー達の基本であった。
勿論、預言者とスーフィーとでは、イスラム教における神学的な位置付けは、大きく異なる。しかし、スーフィーの基本は、ムハンマドは当然、最後(カティム)の預言者とは認めるが、しかし、彼等自身も小規模ながらムハンマド同様に、神あるいは天使からの霊感を得ている、と考えていた。
この故にスーフィーは、イスラム世界にとっていわば諸刃の剣的存在ともなる。つまり、最後の預言者としてのムハンマド亡き後、人々は神(アッラー)の意志を直接聞く手段を失った、とイスラムでは規定する。なぜならムハンマドはそれまで人間世界に使わされた幾多の預言者(注:10)の打ち止め、つまり彼以後、人間には神の意志を伝える預言者は現れない、言葉を代えれば人間は神(アッラー)の意思を知るすべを失ったとするのである。故に、ムハンマドを預言者の封印、即ち最後の預言者と呼ぶのである。
この教えは、イスラム教におけるムハンマドの地位やその啓示を絶対なもの、不動、不変のものとするには、都合が良かった。が、しかし、その一方で宗教的には、その教えの硬直化、形骸化、形式化、そして教団の保守化、堕落を生むことともなった。
つまり、イスラムの正統思想には、ムスリムの宗教心を常に活性化させるような神と直結しているという意識が、内面の部分で再確認できない構造となってしまったのである。これでは宗教としては、硬直化せざるを得ない。つまり、人々は部分的ではあっても神の言葉、神の意志を何ならかの方法で知る事を望んだのである。
この二律背反的な要求の解決、つまり宗教が常にその生命力を維持するためには不可欠な宗教的エネルギーの再生手段の模索は、スーフィーと呼ばれるイスラム神秘主義者の出現によって具体化された。
スーフィズムの「悟り」構造
スーフィーたちは、一般の信徒以上にムハンマドその人の宗教的行いに、自らをオーバラーップさせる。つまり、多くの苦難に耐え忍びアッラーの道に邁進したムハンマド、神を恐れ、身を慎みひたすら神にわが身を捧げたムハンマド、その人の生き方そのものへ自らを投影する。
つまり、一般のムスリムが定められた戒律に従って行動するとすれば、スーフィーは一歩進んで、ムハンマドの生き方そのものに焦点を定める。故にスーフィーの口から出る言葉には、部分的にしろ神であるアッラーの言葉が含まれる可能性がある。これを最も象徴的に表し後述するアル・ハラージュ(略857~925)の「Ana ‘I-Haqq(我は真実なり。あるいは我は神なり)」という言葉であろう。
一般にアッラーは、宇宙や自然、そして人間を創造した神として、人間から超絶、隔絶
しているとされるが、その一方で神がお創りになった世界、勿論人間も「神を内在するもの」という認識も可能となる。ここにムハンマドに端を発するスーフィーの神学的な可能性が生まれる。従って、ムスリムは、この神への絶対服従を旨とするが、その一方でアッラーは「我らは人間を創造した者。・・我らは人間各自の首の血管よりも近い」(『コーラン』50-15)あるいは、「アッラーは人間とその間にも介在し給うと心得よ」(同8-2)とされ、常に人の内、あるいは「アッラーが信者の側についていて下さる」(同8-19)という啓示も同時に示されている、というわけである。
いずれにしても、奇跡としての啓示を授かったムハンマドの存在は、超日常的な体験、つまり神との合一、少なくとも交信体験によって支えられている。そして、正統神学ではこれをムハンマドのみに認めるが、スーフィー達は自らにもその可能性、勿論ごく一部であるが、彼らが神との何らかの交信ができる可能性を認めているのである。
ここにスーフィーの宗教的な意味が有る。つまりスーフィーは、硬直しがちな律法主義的なイスラム世界に、新鮮な宗教的情熱を吹き込む役割を果たすのである。しかし、その一方で小型ムハンマド的存在となり、既存のイスラム教団を根底から脅かす宗教運動を引きこすエネルギーを持ち、しばしばこれが政治運動に利用され、イスラム政治世界をダイナミックに変貌させる原動力にもなった。
いずれにしても、正統イスラムとスーフィーという2つの流れが、イスラム教世界に存在し、両者の存在があい合わさって、イスラム教の歴史を形成してきたのである。そして、その原型はムハンマドに求めることが出来るのである。さらに付け加えるならば、スーフィズムにも大きく2つの地域的な特徴がある。一つは西アジアから西が主流のスーフィズムであり、今一方は本小論で扱う東部、つまり中央アジアからインド、東南アジアに広がるスーフィーである。
以上で、イスラム神秘主義思想の第一原因ともいえるムハンマドの紹介を終えて、次に彼らを生み出したアラビアの思想的背景についても若干触れておこう。
ムハンマド以前のアラビアに於ける神秘主義思想
ムハンマドが生まれたメッカは、東西貿易の中継地点として栄えたオアシス都市であったが、その歴史さほど古いものではなく、また中継貿易都市ではあったが文明と呼べるほどの大規模な文化活動を支えるほどの人口も規模もなかった。後に、イランの人々がイスラムの改宗した時「神はなぜ預言者を、メッカに差し遣わされたのか」と嘆いたとされるのも、このような理由である。勿論、メッカはその周辺の遊牧民の間では古くから聖地として有名であった。つまり、そこには「ザムザムの泉」と呼ばれる泉があり、古くからオアシスとして商隊の立ち寄り所、そして聖地とみなされていた。従って、メッカには多くの部族が、それぞれに自らの神々を祭っていた。
そして、砂漠と荒野の地アラビアにおいては、さまざまな信仰が混在していたが、その中に原始的な神懸り信仰があった。一般にイスラム化する以前のこの時代をジャヒリーヤ(無道あるいは無明時代)と呼ぶ。この時代のアラビアでは、太陽崇拝、樹木崇拝、精霊崇拝など多くの宗教形態が存在した。
しかも、一般にこの時代の神々は、ジン(妖霊)と呼ばれ人間に憑依すると考えられた神的存在と区別が曖昧なほどの存在であった。従って、人々は神々をイスラム教の如く絶対者とは看做さなかった。また、各部族はそれぞれにトーテム神を持ちそれぞれ神像などで表され、それがメッカのカーバ神殿に安置されたのである。後に、ムハンマドが破壊したのは、これらである。
これらの神々、例えばアル=ウッザ女神は、イスラム化する以前メッカのクライッシュ族が信仰した女神であったし、アル=ラート女神やマナー女神は、大いに信仰されていた。これらの神々は、しばしば人間と交霊する神であり、人々はこれらの神を礼賛する賛歌として、詩を尊んだ
特に、格調高い詩には霊性が宿ると考えられ尊重された。『コーラン』の章句の素晴らしさが、神の啓示の印、つまり人知の及ばない完璧な詩句と説明されるのも、このあたりの伝統による、とされる。
いずれにしても、厳しいアラビアの大地で暮らす遊牧民、あるいは商隊による通商に活路を見出すアラブ人にとって神の存在は不可欠であるが、しかし、ムハンマドの出現まで、彼等は素朴な、雑多な信仰が混在していた。
だからこそ、ジャヒリーヤ時代の信仰のさなかにあったムハンマド自身、最初期の啓示が降ったとき、このジンの神懸りではないかと自ら疑った、という伝説が残っている。
このジンや神々の存在は、ムハンマドによってイスラム世界から排除されてゆくが、しかし、神々や神的存在(ジン)と人間との関係の近さというアラブ人の伝統が、後にスーフィー思想の発展等に、少なからぬ寄与をしたことは十分考えられる。
しかし、一般にはスーフィーの基盤は、前出のムハンマドの存在とイスラム以前に中近東を中心として広く行われていたキリスト教の神秘主義、グノーシス主義、さらには深プラトン主義、さらにはペルシャのゾロアスター教、そしてインドの仏教、ヴェーダンタ哲学などが少なからぬ影響を与えたとされる。(注14)
いわば、スーフィー思想の展開には、これら世界中の思想・宗教が流れ込んでいた中近東の状況が存在した。これをインド・イスラムに関していえば、後に検討する、中央アジアの特殊な文明背景があった。
スーフィズムの起源
イスラム神秘主義の起源は、前述のように第一義的には、ムハンマドの宗教体験そのものに、起源を求めることが出来るが、しかし、ムハンマドは、文字の読み書きが出来なかったといわれるように思想的に深い知識、特に思想構成に重要な論理性は持ち合わせていなかった。それは、彼が預言者、つまり神の言葉の伝達者という位置付けを考えれば、不要なものであった。
勿論、だからといってムハンマドに宗教に対する知識がなかったわけではない。彼は、若い時から叔父に連れられてキリスト教やゾロアスター教徒のいるシリアなどに出かけており、それらの宗教への伝聞知識はかなり持っていた、とされる。また、彼の妻ハデェージャの従兄弟のワラカはキリスト教徒であり、ムハンマドに大きな影響を与えたという。
周知のようにキリスト教には、当初より禁欲主義的な傾向があり、それに付随して神秘主義を受け入れ易い土壌があった。つまり、キリストの生き方には、本人の資質を問題としない典型的な啓示宗教であるユダヤ教とは異なり、修行による悟りを基本とする仏教などとの類似する体験例えば、40日間荒野を彷徨し自己を見つめた、とされる行為などがある。(注15)また、当時の近東地域には、ゾロアスター教、マニ教は、仏教やインド宗教の影響が濃いとされる新プラトン主義など、所謂神秘主義思想を展開する諸宗教、学派が、大きな勢力を持っていた。
また、キリスト教は、これらの思想運動を吸収し、グノーシス派のような神秘主義的傾向の強い集団も生み出した。例えば、現在のキリスト教の主流を為す三位一体の思想構造は、アウグスティヌスによって提唱されたとされるが、彼は19歳ころまでマニ教徒として成長したのである。しかし、このマニ教に関して、深い研究はまだまだこれからであり、その思想構造の影響関係ははっきりとはしない。しかし、一般的に考えれば、アウグスティヌスの思想形成には、マニ教の持つ思想構造が基礎であったという事は動かし難く、この三位一体の思想構造は、実は、マニ教の創始者より200年程早く中央アジアで隆盛した大乗仏教の「空の思想」との関連が指摘できると筆者は考える。
と云うのも「空」の思想は、後に、マニと略同時代の仏教思想家である竜樹(2世紀頃)によって書かれた不朽の名著、大乗の根本経典とされる『中論』に纏められたのであるが、此の思想とマニの思想、そして三位一体持つ既存の思想の超越の論理に共通性が見いだせる様に思われる。と云うのも、竜樹はともかく大乗仏教の思想、発展を支えた学者の多くは、中央アジアや西北インドで活躍した人々であり、またマニー( 216~276 )にしても、その初期の活躍の場は、中央アジアであった。
筆者は、彼らの背後にある中央アジアに特徴的な宗教の融合と統一的解釈による再編成の思想的メカニズムが、これ等の改革的宗教、あるいは新しい宗教の発展に大きく関わったのではないか、と考えている。
試みに、「空」思想の特徴である「八不中道」と「三位一体」の思想構造を比較してみると。八不とは、あらゆる存在は実体がなく、それ故に絶対的な存在はない。しかしでは、何もないのか、と云えばそうではなく中道と称するいずれにも偏らない中心が絶対性を否定された個々の存在を基礎として生み出される。つまり、世界は、唯一絶対の原理や存在にという一つに支えられたものには依らないが、しかし、それらの多くに支えられて存在するという発想である。この理論が成立すれば、ゾロアスター教、仏教、キリスト教或いはユダヤ教という3つの異なる宗教を融合一体化することを目指したマニの思想は成立可能である。
一方、三位一体とは、一般には神と子と精霊とされるが、古代において3は、単なる数詞の3のみならず象徴的に多数を現すことがあった。つまり、ギリシア語やサンスクリット語では、単数、両数、複数とあり、3以上が複数であり、現在の様に2以上を複数とするものではない発想があった。故に、一、両数、多数が、実は一つである、と云う風に考えれば、まさに三位一体とは、「沢山の存在が、一つに収斂する。と同時に、一者が多数に分割する」というようにも解釈できる。この理論に整合性を持たせるには、個々の事例の絶対性の否定的超越が不可欠であると同時に、唯一の統一性が生み出されるという排中律を越える絶対性を限定とする理論が不可欠である。これは、インド思想では「梵我一如」の発想や仏教の「一即多、多即一」の思想に通底する既存の概念の一種の弁証法的超越と総合の思想運動と云えるのではないか、と筆者は考えている。
マニ教で育ったアウグスティヌスであれば、三位一体という発想は、十分出てくるし、またキリスト教同様に、あるいはそれ以上に地中海全体に広まったマニ教に親しんだ人々には、このような考えは違和感はなかったはずである。ここにも中央アジアの普遍思想との関係を見出すことはできるであろう。
但し、事項で紹介するグノーシスとの関係は、今後の課題である。
ゾロアスター教とグノーシス
ゾロアスター教については、ゾロアスター(紀元前650年頃―580年頃あるいは前12世紀の生まれとする)によって開かれた二元論の宗教で、鳥葬を行うことで日本でも知られるが、その思想や世界思想やその文化、さらには宗教に与えた影響の大きさを理解するまでには至っていない。しかし、ゾロアスター教の存在は、思想、宗教研究においては極めて重要である。
特に、ゾロアスター教の善と悪の対立抗争によって世界が成り立っているとする二元論的世界観や審判思想、そして終末論は、ユダヤ教、キリスト教や仏教特に大乗仏教の思想形成、そしてイスラム教に大きな影響を与えた。また、善神アフラ・マズダー(叡知の主)への帰依そして、それに伴う善なる行いは、善なる神が、悪神(アングラ・マインユ)と戦うための糧となる、と考える。つまり、人間は常に神とその行為によって繋がっていると考えられていた。故に、人間は、善を成すもの、即ち道徳的・倫理的でなければならない、と教えた。
この故に、ゾロアスター教は倫理宗教(仏教・キリスト教・イスラム教など)の源とも言われる。というのも実質的な人類最初の帝国といえるアケネメス・ペルシャの国教として、東はインダス河流域から西はギリシア国境地域(現在のトルコ)さらにエジプトとい
う広大な地域を支配する原理となり、それ故にゾロアスター教は、世界各地に大きな影響を与えることとなった。と同時に、同帝国には、世界各地からさまざまな宗教や文化が流入し、高度な文化が生み出された。
一般に、ゾロアスター教は宗教に寛容であり、各地の信仰を尊重した。それ故に、アケネメス・ペルシャの領域においては、宗教的、文化的な折衷や融合が起きた。この傾向は、アレクサンダー以降のギリシア人の帝国さらには、アルケサス朝(前3世紀-後2世紀)にかけても所謂オリエント地域の精神伝統であった。一般にこの寛容な精神風土をヘレニズムと呼ぶ。
つまり、ヘレニズムとは、古代イランとギリシアの精神風土の融和の賜物ということであり、また同地域の伝統でもあった。というのも古代オリエントは、さまざまな民族が入り混じり、それぞれに固有の宗教を信奉し、多様な文化を形成してきた地域であったが、その中心がメソポタミアの伝統も合わせて持っていたペルシャ人とギリシア人、そしてユダヤ人であった。この様な多様な宗教や文化の共存や融和には、既存の価値観を超える新しい、そして創造的な思想や宗教解釈が不可欠である。その傾向の中から生まれた思想にグノーシスがある。
このグノーシス主義は、紀元前後の地中海東部地域に発生し、2-3世紀ころから地中海世界から中近東にまで拡大した思想運動である。この運動は、従来キリスト教の枠内での運動と考えられていたが、現在では1945年に「ナグ・マハディ文書」の発見により、この運動が、キリスト教とは起源を異にするユダヤ教周辺から生まれたものである、という理解になっている。いずれにしても、このグノーシス運動の最も成功した例が、マニ教として知られる運動である。このグノーシスという名前はギリシア語で「知覚(gno’sis)」を意味する言葉で、このギリシア語のグノーシスの持つ意味が、そのままグノーシス主義運動特有の教義となっている。先ずグノーシス運動では、宇宙も人間も神的・超越的本質と物質的・肉体的実体との二つの要素からなるとする、二元論をとる。しかも人間には、プネウマと呼ばれる神的実在が、部分的に存在するとする。そして、救済とはこの神的断片であるプネウマが集められて、神的存在に帰一することとされる。そして、そのためには自己の神的本質を知覚する必要がある、と教える。つまり、グノーシスにおいては、人間には隠された知識つまりプネウマ(善、すなわち真の神から降りてきた聖霊・救済の源、仏教でいう仏性に当たる)があり、人間は修行によってこれを復活させることが出来ると教えた。
ここにマニ教が、ゾロアスター教、仏教(主に大乗仏教)、そしてユダヤ教、あるいはキリスト教を融合、統一した宗教と呼ばれる所以がある。
一方、これらより早くインド北部や中央アジアに、諸宗教融合思想を説く、大乗仏教が生まれた。この事実は、ヘレニズムやグノーシスと云う西洋人主体の世界観にさらに、中央アジアの存在つまり、東方ペルシャからインドのガンダーラ、そして中国の西域一帯の思想運動と比較しつつ考察する必要があろう。
勿論、現在ではほとんど知られていない所謂メソポタミア、つまり現在のイラクやシリア近辺の思想や、エジプトの思想等との関係も今後は考えねばならないであろう。
いずれにしても、グノーシス主義では、全ての人間は修行を通じて救済が得られるとするもので、特にマニ教は、この教えを世界中、特に、修行による救いという発想の乏しい西方地域に広めた宗教である。但し、中近東のグノーシス主義は、遅くても7世紀にはキリスト教やソロアスター教、更には、これらを受け継いだイスラム教の中に吸収され消滅した。
マニ教とイスラム
マニ教では、世界は光と闇という対立する二つの原理からなるとする点では、ゾロアスター教的であるが、光は霊的であり、闇は物質的と位置付け、ギリシア思想の影響も色濃いとされる。しかし、基本的な構図は、グノーシス思想に一般的に見られるように、人間に内在する光の要素の回復のために倫理的生活を行わなければならない、とする。マニはそのために五戒を定め、一日4-7回神への祈祷を行う事を一般信徒にも課した。また、厳しい菜食主義と断食の奨励を行った。これらは仏教やヒンドゥー教との共通性を髣髴させるが、このような禁欲主義思想は、マニがインド(インダス河流域とされる)を若い時に訪れたことと関係がある、とされるマニ教ではこのように、人間の倫理的な行為、つまり光の要素の回復が、光の本質浄化に役立ち、世界が救われると説く。
このマニ教は、中近東ではキリスト教と勢力を争い、やがてキリスト教やイスラム教に吸収されてゆくが、それらの宗教への思想的、文化的影響は小さくなかった。しかし、同地域が他の宗教の痕跡を壊滅させる排他性の強いセム的宗教であることが影響しているのであろうが、遺跡や古文書などもほとんど散逸してしまっているようであり、その研究は遺跡の発掘、文献の収集など基礎的な調査レヴェルからの為されねばならないようである。)
このような複雑な宗教関係の中で、イスラム教は生まれ、またスーフィズムも形成されたのである。
スーフィズムに見られる東西の相違について
ところで、現代の西洋人研究者の研究では、イスラム神秘家をスーフィーと呼ぶ、その名称の起こりとなった毛織の粗衣も、キリスト教の起源であるとされる。勿論、それ以前にこのような風習があったことは、当然であろう。何故なら、宗教者が毛皮や毛を纏うという習慣は世界各地にあり、寧ろ古代信仰における呪術(類感呪術)を起点としていると考えるべきであろう。
また、スーフィーが専ら行う沈黙や連祷 (ズィグル)、その他の禁欲的な修行も、教の神秘主義や禁欲主義の伝統を受け継いだとされるが、これもそれ同様である。特に、中央アジアからインドでは、寧ろインド的な伝統からの強い影響を考える必要があろう。
と云うのも、スーフィズム特に、中央アジア以東のそれにはインド思想、特に「梵我一如」(つまり究極的一者と個別存在の本質的同質性を主張する)ヴェーダンタ思想の影響を認めることは、決して難しいことではない。事実、インドの高名なスーフィー学者リズビー(A.Rizbi)は、この点を強く主張する。イスラム文明に多くのインド的な要素が取り入れられている事、その象徴がアラビア数字であるが、このことだけでも素直に考えれば、リズビーの指摘は肯定できるであろう。
事実イブン=ンハルドーン(1332~1406 )は、「神はインドに哲学を御与えになった」(注23)と表現しているほどに、その思想的な高さ、影響力を評価している。因みに、中国には技術力という事である。しかし、ここで、指摘したい事は、スーフィズムにも、地域性が当然認められることである。
つまり、民衆への布教や、民間信仰との接触の多かったスーフィー達の宗教環境に起因すると言っても過言ではいであろうが、主に西側、つまりシリアからスペインまでの地中海沿岸における地域、それらは同じセム的一神教という土壌を持つライバル地域である。それ故に、スーフィー達も布教対象、あるいは信者達に見合った言説となる。つまり、例えば他宗教への寛容という視点でも、そもそも同一の神を仰ぐという前提を共有するセム族の宗教である、という前提が成立するために、ヒンドゥー教や仏教の様な完全にカーフィル(異教徒・不信心者)との共生とは異なる、ということである。この故に、筆者は、スーフィー運動を東西に分けて考察する必要がある、と考えている。
一方、中央アジアからインド、更には東南アジアにおけるイスラムを囲む環境は、全く異なっていた。つまり、アラーが、そしてムハンマドが忌み嫌った多神教徒、偶像崇拝の徒(ムシャラフ)たちである。それ故に、彼らとの共生は、神学上最大の問題解決が不可欠であった。
いずれにしても、西方圏のスーフィーと東方圏、ここでは中央アジアからインド、東南アジアへ伝播したスーフィー達には、基本は同じであってもその言説には、かなりの違いがあったというべきであろう。この点は今後明らかにされるべきであるが、現時点では、その指摘にとどめておきたい。いずれにしても、12世紀以降インドへの影響力を増したスーフィズムは、主に中央アジア出身のスーフィー達であり、筆者は中東のスーフィーと中央アジアのスーフィーは、その言説にかなりの違いがあるのではないか、と考えている。スーフィーの思想的な深まりに、11世紀初頭に偉大なる万能天才アル=ビルーニー( 973~1048 )が、サンスクリット語から翻訳した『ヨーガ・スートラ』の存在が、無視し得ないという指摘がしばしばなされる。(
しかし、スーフィズムの初期段階に於いて、スーフィズムの思想形成に大きな影響を与えた人物として、あるハラ―ジュ(ほぼ西暦857年-ほぼ同922年)の存在を忘れるわけにはいかない。特に、インドへのイスラムの定着に大きな影響力があった故に、以下で紹介するが、その前に中央アジアにおけるイスラム侵攻直前から数世紀前後の当該地域の思想・宗教の状況について、概観しておきたい。
中央アジア文明という視点
中央アジアは、日本人にも関心高い地域である。シルクロードを通じて、東西の文明が行き交ったロマンあふれる文明交流の大動脈である。この文明交流の歴史的ロマンに惹かれる日本人は少なくない。
しかし、この地域を文明の大動脈と表現することは、一つの大きな要素を見失わせる、あるいはそれに気づかない視点によるものでもある。もちろん、中国と西洋地域の文明交流の為の大動脈であったことは歴史的な事実であり、当該地域の世界史上に果たした大きな役割である。しかし、その一方で動脈という表現には問題があるように思われる。つまりこの認識には、東西の文明を伝えるための主要道路ではあるが、単なる通過点的な位置付となっていないか、という事である。
現在の様に、自動車やトラックなどで文物が運ばれる時代、さらには飛行機で一瞬にして行き来できる時代ならともかく、嘗てのシルクロードは、厳しい道のりを数か月さらには数年をかけて行き来したのである。その間に、多くのオアシスを通過し、異国の商人や文物が、このオワシスで直接交わることが極自然であったはずであるし、また、シルクロードには、巨大なオアシス、筆者はこれをメガオアシスと呼ぶことにしているが、あった。例えば有名なサマルカンドやブハラなどは紀元前後に於いて、数万・数十万の人口を誇る大都市であった(注28)*現在は、サマルカンド市街地約60万人、ブハラが約30万人)。これだけの住民が居住するメガオアシスにおいては、単なる人・物の通過点的なオワシスのイメージではとらえきれない文明融合の役割があるのではないか、という事である。
例えば、ザラフシャン河の流域に位置するブハラとサマルカンドでは、4~500キロメートルほどの距離があり、その途中にはいくつかのキャラバンサライが存在する。そのような地点には、水飲み場や宿場町的な場所が設けられていた。これらは確かに、従来のオアシス都市のイメージに当てはまる。しかし、サマルカンドやブハラ、あるいはタシケントなどのメガオアシスは、単なる通過点、休息所では終わらない、文明を輸合し、新しい文明の形を各地に発信する能力を持っていたと考えられる。
かつて、中央アジアからアフガニスタンを旅した梅棹忠夫は、東洋・西洋文明と云う従来の文明理解に対して、中洋文明という視点を提唱し、文明論に新しい視点を提供した。その結果、従来東洋と西洋という枠組みで人類文明を理解しようとする近代西欧中心の視点に対して、イスラム文明の独立という視点を提供することとなった。この視点により文明論は、人類史的により正確な文明理解の視点を、獲得することが出来た。しかし、この中洋の理論には、まだ東西中心という世界史観、文明論に対する異議申し立て的なものであり、真にこの中洋と表現する地域を、文明額的に位置づけるまでには至っていないようである。また、現在はこの地域がイスラム地域であるために、
当該地域の研究は、主にイスラム関係者が中心となり、人類文明におけるイスラムと云う様な視点よりも、イスラー中心に文明を論じるというイスラー的な発想で、他の文明との対比に今後の課題となっているように思われる。あるいは民族移動の視点から論じられるが、文明論的な視点は未だ十分開拓されていないようである。
中央アジアと文明のダイナミズム
中央アジア地域の独自性を文明論的に評価しようとする視点は、未だに発展途上である。いずれにしても、さまざまな新しい論点がより良い文明理解の為、文明学構築のために不可欠であることは論を待たないわけであり、筆者の中央アジア文明の文明創生力を独立させる視点も、その一つの試みと位置付けている。
と云うのも、従来の文明論では、先ず4大文明がオリジナルな文明として中心に据えられる。そして、そのオリジナル文明の周辺に、これ等の文明のいわば模倣型の小さな文明が生じているという構造となっている。これらを恒星と周辺の衛星に譬えるトインビーのモデルが最も基本的である。この理論は文明論の基本であるが、しかし、このモデルは静的な文明理解のモデルであり、4つの中心文明(恒星)同士の影響関係や、それらを取り巻く小文明(衛星)同士の影響関係については、余り関心が払われていない。成立して日の浅い文明学に於いては致し方のない点であろう。この静的な文明の構造把握に対して動的な視点を導入し、互いの文明の影響に着目した、つまり文明間の動的な関係、ダイナミズムに注目し新たな文明理解のモデルを提示したのが、伊東俊太郎博士である。伊東博士は、文明の影響関係に着目する文明圏モデルを考案した。
筆者はいわば、このモデルを中央アジアに適用し、さらに中央アジアが単なる巨大な恒星文明間の交流の通過地点という評価から、より積極的に当該地域に流入してきた諸文明の融合、そしてその結果として生まれた諸文明が総合され、その結果新たに生成された融合型文明が、各地に広がっていったという文明の形態があると考えている。勿論、それらは相互作用を持つのであり、またオリジナルの文明の部分的な接合、キメラ的な部分があるが、一方でそれが化学反応して、新たな化合物が生じるように、各文明・文化が当該地域で、濃厚に接し、影響しあい、新たな形を生み出した、という視点である。この時に、4大文明など恒星型文明の一部の要素を、元の要素から剥奪、或いは剥離させて、他の要素と結びつける事が行われる。この作業が、中央アジアの様な地域では、ごく自然に為されると考えている。そして、それは、それぞれのオリジナル文明地域では、生み出すことが難しい、文明的革命というべきものである、と筆者は考えている。
そして、本稿で検討する中央アジア、具体的には、トランスオクシアナからガンダーラ地域が、まさにこの総合と創生が為された地域である。そして、この文明のいわば最初の精華とも言えるものが、大乗仏教であると、筆者は考えている。
文明交流のダイナミズムと大乗仏教文明
さて、思想研究では、文献や遺跡から、論理的推論により一定の結論を導き出すことが出来る。しかし現実社会では、合理性と云う直線的な理解が、可能とばかりとはなっていない。ある現象の形成には、幾つもの要因が様々な条件で融合し、徐々に文化や文明と呼ばれる現象の固定化がなされるのである。そのようなことは自明であるとの認識は、容易であるが、しかし、中央アジアに起こった複雑な文明融合現象を、より正確に捉える、少なくとも重視するという視点は、従来の仏教学研究には、決して生かされているわけではない。と云うのも、このような文明融合の理論的背景は、比較文明学という新しい学問によって主張された視点であり、その成果は日本では伊東俊太郎博士に代表される新しい学問スタイルであるからである。
この比較的新しい学問形態である比較文明学は、未だ形成過程の学問であるが、その特徴は、原初還元主義的な発想よりむしろ、現象の相互連関性に重点が置かれるとともに、時間的、空間的世界認識に於いて巨視的であり、また動的であるという点を特徴とする。この点が、従来の仏教学に於いて主流の厳密な直接証拠とも云うべき文献を重視する仏教研究と異なるものである。
勿論、従来の厳密な仏教学的な視点を否定するものではなく、寧ろその成果の応用範囲を拡大するという事になるであろう。
譬えて言えば、細部の研究を積み重ねる仏教学を経済学の領域に譬えればミクロ経済学が、それにあたるであろう。そして比較文明学は、一国や世界経済の動向をフィールドとするマクロ経済にあたろう。両者は対立するものではなく、領域や手法において相補的なのである。あらに言えば、比較文明は、直接的な証拠の少ない領域に於いて、他の地域や時代の同様な現象を以て比較検討しつつ対象を明らかにするいわば、直接証拠のない事件を間接証拠の積み上げによって、明らかにしようとするような視点を持つ。
いずれにしても、文化・文明の交流と云う動的な視点と政治経済文化などを総合的に捉えようとする体系的な視点を持つ比較文明論の視点は、大乗仏教のような多様な文明を背景に生み出された宗教文明の考察には、有効な視点である、と筆者は考えている。
ところで、大乗仏教の位置づけという点になると、日本人はどうしても客観性にやや陰りが出るように思われる。そこで、比較宗教学的な立場から、客観的に大乗仏教という宗教を概観してみよう。(29)
いわゆる大乗仏教は、仏教の中の一分派と認識されている。つまり、小乗徒彼らが蔑視する伝統仏教、これを上座部と言うが、に対して、大きな乗り物(大乗:マハー・ヤーナ)と称して、自らの言説、教理や戒律などの宗教性を正統とする、新興の仏教宗派である。それは、丁度1500年後に、カトリックに対して、生まれたプロテスタント運動と構造的にも、また言説についても、類似するところがある。
この大乗仏教の中で、特に注目されるのが、菩薩思想と浄土思想であり、諸宗教共存をうたう華厳思想であり、それらを正当化するための「空」の思想である。それは、オリジナルの文明から齎された各要素を、元々の文明から切り離すための、つまり文化剥離のための基礎作業であり、理論付けである。そして、空の理論によって切り離された要素は、新たな思想の下、再構築されて、各地に広まってゆくというイメージである。
例えば、大乗仏教の救済論(悟り論)において主張されているものが、従来のものとどれくらい異なるか、簡単に検討してみよう。
そもそもインド伝統仏教における悟りの構造は、自己の努力による救いという構造であった。是は永いインドの伝統の中で形成された修行論を前提としている。しかし、大乗になると、この原則半ば放棄される。つまり自己の努力は当然であるが、同時に他者の救済への関与が、強く主張されることとなる。是が回向ということであり、それは慈悲に支えられた行為である、となる。これが所謂菩薩思想である。この思想は人道的には実にすばらしい思想であるが、インド的にはインド思想の枠組みをある意味で否定するものである。つまり、すべの行為の結果は自らに依り、自らに帰る。いわゆる因果応報の「業思想」である。ここには、一部たりとも、他者の関与はありえない。是が原始仏教の考えである。しかし、大乗仏教は、菩薩に新しい概念を付与し、この枠組みを越えたのである。まさに、文化剥離と創生がここでなされたのである。
そして、大乗仏教の菩薩思想においては、修行者としての従来の菩薩、つまり伝統仏教におけるブッダの悟り前の姿を指す菩薩が、実は悟りを完成しつつも、すべての信者を救いに導き終わらぬうちは成仏(悟りを完成状態)にはいらないという、不思議な理論で、伝統的仏教の救済論である修行論と西方的救済論である神的存在による救いの対立を乗り越えようとしたのである。そして、その典型が観音菩薩である。さらには浄土教の阿弥陀仏や後に密教へと進むビルシャナ仏、大日如来などである。
いずれにしても、これらには、思想的に大きな飛躍があり、明らかにインド文明を基礎としてきた上座部仏教の発想とは異なるものがある。いずれにしても、このように考えれば、菩薩思想を形成した背景が、インドのみならずペルシャや中近東の諸文明、宗教の要素の融合である、ということが自然に受け止められるのではないだろうか?
これらの大乗仏教の仏達の出現は、まさに融合と超越の成果ということが出来るであろう。その為に、個々の文明や宗教からの剥離れ、また新たな統合がなされたのだと、筆者は考える。その為に、前述の「空」の思想、そして新たな救済思想を支える慈悲や回向という従来殆ど意識されてこなかった思想が生み出されたのではないか、と筆者は考える。
以試みに浄土教の思想の出現に関して、簡単に以下に於いて、この点を検討してみよう。
宗教融合創成運動としての浄土教
周知に様に、浄土教が属する大乗仏教は、仏教の開祖ゴータマ・シッダルタ(釈尊、釈迦牟尼。以下では原則ブッダと表記する)の開いた仏教の延長線上にありながら、その伝統的な信仰形態の革新を目指した新宗教運動であった。しかも、大乗仏教と一般呼ばれる、この仏教の革新・改革運動は多様であり、大乗仏教とはいわばこの諸運動の総称であることになる。
そして、我々が大乗仏教と一律に呼ぶ多様な運動の一つの結果が、浄土教であろうと思われる。恐らく歴史的には、様々な文化・文明を背景に持つ、人々の豊かな(雑多な)宗教運動の結果生まれた多様な信仰形態を、総称して大乗仏教運動と呼ぶようになった、ということであろう。
いずれにしても、中央アジアのメガオアシスでの文明融合現象の結果として、幾つもの異質な宗教が、一つに重なり合った信仰形態により生まれたのが、浄土信仰であったということになるのではないだろうか。それ故に、その主尊においてもその呼称に多様性があることになっているのかもしれない。
つまり、アミターバ( Amita’bha )やアミタユス( amita’yus )などがそれである。一般には、阿弥陀仏は唯一で、それを幾つにも呼び現すと云う様に考えるが、これは歴史の河口から見たものではないだろうか。つまり、大きな河が、河口では一本の川となるが、もともとは沢山の川や小川の集合体であるように、阿弥陀信仰も多様な流れの思想や、宗教運動を併呑して、一つの信仰形態に成長した運動であったと考えることである。すると幾つもの類似した名称は、本来は別々の名で呼ばれた仏のことであり、それが統合されて主な名前が決まり、従来の名は、別名としてそのまま温存されたということになる。つまり、本流の名が前面に出るが、支流の名前もそのまま残ったというわけである。
このように考えれば、阿弥陀仏の名称の起源もそれぞれのものが実際に存在したものであり、それが統合されて一つになったと考えられよう。また、逆に、一つになった阿弥陀仏の名称を取り入れて、土着化させて名称を生みだすという逆の現象も当然存在したであろう。それが長い歴史と複雑な文明交流のなかで入り混じった結果が現在の浄土教である、ということになろう。それは中国、日本においても刻々と変化した宗教としての浄土教を見れば、想像がつくことである。
いずれにしても現在大乗仏教研究で起源の問題においてネックとなっている主仏の名称などの問題は、他の宗教との比較を行う事で、直接的な検証以外にも研究できる様に思われる。
つまり、浄土教と云う大河の流れの多様な源流や、その総合体としての我々が知る浄土教の成立については、時代と地域を固定的に限定し検討するのみならず、それらが混ざり合い独自の姿に変貌するという動的なものをも視野に入れねばならないであろう。
つまり、従来の研究の様に多様な要素を固定化し、固有の源流を捜すという視点のみならず、思想や文化の化学変化を肯定的に捉えることも必要であろうということである。
つまり、浄土教のような西北インドから中央アジアのメガオアシスとしで生まれた宗教思想や運動には、発生に於いて、西北インド特有の多様性があり、またその浄土教が発展したバクトリアやトランスオクシアナの文化について考察する必要がある、という事である。何故ならこの地を計有して大乗仏教も浄土教の多くが、東ユーラシアに伝播していったのであるから。
従来の研究は、浄土教の起源をインドかその他(ペルシャ)などと各要素を独立変数の様にとらえて、どのどちらかに帰趨させようとする傾向があり、その手段として、言語学や文献学、あるいは考古学等の成果を中心に説が展開された。そのために、インド派と非インド派起源が並立し、対抗関係にありそれぞれの陣営が納得する解釈が生まれ難かった。
しかし、事実として浄土教思想は、西北インドから中央アジアにおいて少なくとも、成長し、東アジアへ東漸していったのである。そして僅インド内地へも広がっていったのである。故に、浄土教という新仏教運動は、西北インドから中央アジア、所謂ガンダーラ地域からバクトリア、トランスオクシアナの民族やその文化、と云うより文明の産物と考なのである。故に彼らの文明的な背景を考慮してゆくことが不可欠である。
いずれにしても、浄土信仰の主仏である阿弥陀仏の語源は、浄土思想の権威であり、高名な文献学者の藤田博士の研究に明らかなように、一定しておらず、従って、阿弥陀仏という言葉を中心に検討した時には、その信仰の源流を明らかにすることは、前述の通り語源の定義により、その語源もインド文献、あるいはイラン、西方諸語と別れて行く、そして、その決定は難しいということになる。いずれにしても、この様な学問的な着状況は、方法論を帰ることで乗り越える事が出来ると思われる。何故なら、阿弥陀仏もそれを中心に形成される浄土信仰も、現実に中央アジアから中国、日本と東漸してきたのであり、事実として存在しているからである、その歴史をより的確に説明できる方法を探すことで、仏教理解が深めることが、学問の最終的な目的だと筆者は考えるからである。
その意味で、浄土教と云う大乗仏教の一宗教運動を、その内側からのみ検討すのではなく、大乗仏教とほぼ同じ地域で大きな宗教運動となった、イスラム神秘主義運動の中のチシュチー派とやや地域は東にずれるが、大乗仏教が隆盛したガンダーラに近接するパンジャブ地方に、15世紀末に生まれたシク教との比較研究は、同地域が持つ文化的、さらには文明的基礎を共有する教大宗教として、その比較研究は、意味のあることであろうし、その成果を逆に個々の宗教の研究にフィールドバックすることもまた、研究や理解の助けになるはずである。(注34)
いずれにしても、これらの宗教運動は、自然環境や民族というあまり変化しない要因を共有しつつ仏教、イスラム、そしてシク教という宗教運度の展開がなされたからである。
この三つの宗教運動を比較することで、浄土教の発生あるいは形成に関する同地域特有の事情を推測できるのではないかと、筆者は考える次第である。
以上が大乗仏教の発生に関する中央アジア文明から、大乗仏教の浄土教思想の発生或いは展開を鳥瞰したものである。この様に、中央アジアでは諸文明が融合し会い、新しい文明の形を生みだすという現象が見いだせた。そして、同様の運動が、今度はイスラムを中心に行われたのではないか、というのが次のスーフィー思想の検討である。
初期スーフィズムと中央アジア
最初期のスーフィーのインド進出については不明な点が多いが、主記イスラム神秘主義者の一人であるハラージュは、インドとスーフィズムを結ぶ重要な存在である。9世紀から10世紀頃のスーフィズムは、まだ思想的には未確定の状態であったが、ハラージュはそのスーフィズム思想の形成に大きな役割を果たした。(注35)彼は、ペルシャ各地を巡礼した後に、897-902年にかけて、西部インドや中央アジアなど、ヒンドゥー教徒や仏教徒の優勢地域を巡錫し、思想的に大きな影響を受けたとされる。特にハラージュは有名な「Ana ‘I-Haqq(我は真実なり。あるいは我は神なり)」という言葉を発し、初期のイスラム世界のみならず、イスラム思想に計り知れない衝撃を与えた。当時のイスラム聖者たちは、その言葉の余りに大胆難ことに驚き、撤回せねば、命を奪うと迫ったが、頑として自らの説を曲げず、ついには死刑となりさらに、その遺体は灰になるまで徹底的に焼き尽くされたのである。一般にイスラム世界では、いかなる罪人も生命を奪われたのちは神の裁きを待つべく、その後は所定の作法で葬られるのであるが、しかし、ハラ―ジュの思想は、神の裁きを待つまでもなく、地獄の業火に焼かれる刑を受けたのである。
一般に、ハラージュがこのような思想に行き着いた背景には、グノーシスの影響があるといわれるが、同時にインド思想、つまり「梵我一如」を説くウパニシャットもしくは、修行により仏になるという仏教思想などの影響があったと考えられている。特に、彼が逗留した西インドのムルタンや、仏教などが盛んであった中央アジアの諸都市に於いて受けた思想的な影響は、注目されていいのではないだろうか。何故なら、グノーシスの影響を受けたスーフィーは、彼以後も多々いるが、彼のようにイスラムの宗教タブーを乗り越えてしまったものは、知られていない。やはり、彼がインド的な思想の支配する地域を訪れ、宗教的な影響を受けたということがその理由であろうということは、無理のない推論であろう。
いずれにしても、スーフィズム思想の形成には、その初期段階でインドや中央アジアの融合思想が関わっていたのである。そして、その故であろうか、スーフィズムが中央アジアで盛んとなり、さらにその後の、インドへのイスラムの定着に、スーフィー聖者たちがおおきく貢献でいたのは、彼らの言説や行動がインド古来の宗教思想と共通する点があり、インドの民衆たちがイスラムの教説を受け入れやすかったからであろう、と言われる。
尤も、このような神人合一思想を展開した彼は、イスラムの正統派から糾弾され絞首刑となり、その死体はイスラムでは異例中の異例である火葬、というより罪の深さを確定するために焼き棄てられた。
しかし、彼の思想は確実にスーフィーに受け継がれ、特にインドに於いて、インドのイスラム化に大きな貢献をした。特に、彼の思想は後に消化する、アクバル帝のムガル宮廷に於いて受け入れられ隆盛した。(注36)
スーフィズムの思想のメカニズム
さて、すでに概観したように、スーフィズムの発生並びに発展には、様々な歴史的要素が関係している。しかし、その基本にはムハンマドの啓示体験、つまり神との霊的直接交流というイスラム教の根源、というより多くの宗教に見出せる人間精神の深み、霊的なものへの希求という普遍的な思いを根源としている。故に、スーフィズムがイスラム教においてしばしば異端的な位置付けによって弾圧されることはあって、その存在が人々の信仰から消え去ることがなかったのもこのためであろう。
だからこそスーフィーは、世界の至るところに類似の思想を見出したし、またイスラムの正統思想が形式化し、社会的に硬直化したとき、これを溢れんばかりの情熱と宗教鄭な使命感によって改めようと、イスラム信仰回復運動、あらには社会改革運動の中心となることもあった。
それ故にスーフィーの存在は、伝統的、保守的さらには神学的立場と対立する。というのもそれらは、往々にして教条主義的で、字義の表面的な解釈に拘泥する立場であるのに対して、スーフィーは自由で奔放な言動にその思想が象徴的に表現されるために、しばしば保守派と対立する。(注37)
スーフィーは、自己の束縛を越え、根源的で超越的一者、つまりイスラムで言えばアッラーとの合一体験からイスラムを再解釈できるという超理性(ここでの理性は、言語化され固定化した知識)の立場である。
故に、固定的にスーフィズムの思想を定義することは難しい。しかし、スーフィズムの特徴は、禁欲や神への衷心よりの祈りと言った一種の修行(これをターリカ:道と呼ぶ)を宗教体に強調することである。勿論、このターリカ(道)も多様であり、融通無礙であるが、究極的には全て神との合一を目指したもの、という点で禅の精神に通じている。つまり、それは禅において「悟りである山の頂上は一つであるが、そこに至る道は無数に有る」と表現される精神に通ていする思想である。
スーフィーの辿る合一(悟り)の階梯
著名なスーフィズムの研究者A.ニコルソンはその著The Mystics of Islam日本語訳中村雄二郎『イスラムの神秘主義』)においてスーフィーを「自分自身を『旅人(サーリク)と称し、実在との合一という終着地点への『道』にそって、ゆっくりと『階梯』を前進する。』(39)と位置付け、そのスーフィズムの特徴についてニコルソンは、現存するスーフィズムのおそらく最古の包括的な論考とされる著名なスーフィーであるアブー=ナスル・サッラージュ(988没)の『閃光の書』を検討し、次のようにスーフィーの説明をする。
ニコルソンによると、同書においては精神的な修行の「階梯」を七段階でしめす。その七段階とは、改悛、禁欲、放棄、清貧、忍耐、神への信頼、満足である。これらは、修行、つまり人間の主体的な努力によって為しえるものである。
しかし、その一方で、人間の努力では、どうにもならない神の御心に拠って特別に得られるとされる「心的状態」(アハール)をも体験しなければ、真のスーフィーの悟りとも言うべき、神との合一は得られないとする。
つまり、スーフィー思想においては、その究極的な目的である合一体験は、自らの努力であり「階梯」と、神からの恩寵とも言うべき「心的状態」との双方の体験の上に成り立つとする。スーフィーがこの2つの要素をスーフィーの悟り体験(ファナー)獲得の、条件としたことは、イスラム正統神学との融和の結果とも言える。というのも、イスラムのように天啓宗教においては、神と人間との距離は隔絶しており、人間の努力によって神に近付くというようなことは不可能とされる。それ故に、神からの啓示、つまり一方的な命令(預言)が、神の慈悲心の表れが不可欠となる。その時に、神の命令を人間に伝えるのが、預言者ということである。
従って預言者は、神から選ばれた存在であり、人間の努力によってなれるものではない、のである。しかし、そうするとイスラムのように、ムハンマドを最後の預言者(カアッテマ)とすると、神との交流は永遠に絶たれることとなる。しかし、それでは宗教的な情熱は枯渇し、宗教のエネルギーは衰退する。そのような矛盾を解決するために、シーフィー達が考え出したレトリックが、この神の恩寵ともいえる「心的状態」と人間の努力である「階梯」というわけである。
つまり、この両者が完璧にそろった者はムハンマド以外にはないが、しかし、スーフィーたちは、不完全であっても神の恩寵を得たものは、啓示に順ずるメッセージを得られる。つまり、スーフィーの道の完成は可能とされると考える。その時、スーフィーの智は「霊知」と「真理」という一段高いレベルとなる。これを知者あるいは「霊知者」と呼ぶ。
次に、この霊知者になるための道の要素について検討しよう。
ファナーと発心の比較
スーフィーにおいても、ファナー体験をするには先ず現状否定、つまりキリスト教でいう回心、仏教で言えば発心が必要である。それをスーフィーでは改悛という。
スーフィーではこの改悛は、人間の主体的な動機によるのではなく、神の恩寵によるとされる。それ故に、スーフィーの道は誰にでも開かれていない、という意味で特権であり、またそれ故に彼等の宗教的な情熱は駆り立てられる。
この改悛は深い自己否定、罪の自覚から始まるとされる。つまり「フジュウィ―リーは言う『悔い改めた者は神を愛する者であり、神を愛するものは神を観照する。観照において罪を想うことは、それが神と観照者の間のヴェールとなるのでよくない』と。」(注39)という。しかも、悔い改めることは一心に神を見つめること、つまり観照することとする。そして、観照とは自己を捨てることでもある。つまり「閃光の書」の改悛の門には「汝らここに入る者はすべて、自我を捨てよ」(注40)というわけである。この認識は、仏教においても、キリスト教に於いても見出せる発想である。
因みに仏教においてスーフィズムと近似的な発想を持つ禅に於いても、自我の束縛からの解放は、基本である。この点を道元(1200-1255)は、同様な境地を「自己をはこびて萬法を修証するを迷いとす、萬法すすみて自己を修証するは悟りなり。」(注41)などと表現している。
つまり、ファナーを得るための修行には、先ず自己中心的な見解、言い換えれば日常的な価値観を捨て去ることからはじまるのである。
そこには、すべてを神に投げ出す。つり自我を放下して初めて理解できる世界観が有る。それは、『閃光の書』の「私は多くの罪を犯しました、もし私が神に向って悔い改めたなら、神は慈悲深く私の方を向いてくださるでしょうか」と。「いいえ」とかの呪は答えた、「でも、神があなたの方に向き給うならば、あなたは神の方に向くでしょう」(注42)
という、言葉によっても、また「諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと覚知することをもちいず。しかあれどもも証仏なり、仏を証してもてゆく。」(注43)となる。
この両者は、まさに自らの計らい、自己を中心とする意識、行動を捨て去る、脱することによって初めて神あるいは仏、つまり真理の状態が表われる、あるいはそれと一体化するという世界観である。このような思想を一般に神秘主義思想あるいは宗教と呼ぶのである。
スーフィーの修行観
従って当然であるが、この様な行為は独善であってはならない。そこに良き師(導師:)の導きの必要がある。
スーフィーでは、導師に就かず独弧として修行するものは「悪魔を導師とする者」とも言われ、敬遠される。それは魂の導きが独善であってはならない、という前提が有るからである。この点は、インドの諸宗教に於いても同様で、特に神秘体験を重視する仏教やヨーガ、特に禅仏教にはこの傾向が強い。
スーフィーとして修行の道に入るためにどれほどの厳しい修行、言い換えれば師の絶対服従が要求されたかといえば、「我は神なり」と宣言して、火あぶりとなったハラージとも関係のあったとされるスーフィー、アブー・バクル・シブリー(不詳10世紀の人)が、バクダードの有名なスーフィーシュナイド (~910頃没) に入門を請うと、ジュナイドは、高級官僚として知事まで務めたシブリーに先ず、行商人、そして乞食を数年間させ、世俗の時代のプライドや思いを徹底的に捨てさせた。しかも、他者の下僕となることを条件に入門を赦したのである。その結果彼は「私は神の被造物の中で最も卑しいものだと思います。」という境地に達することが出来、一人前のスーフィーとみなされた、とされる。
このようにスーフィーの悟りの道は、これほどまでに厳しい覚悟を必要とされるのである。
同様な視点は仏教に於いても認められる。特に、禅においては菩提達磨に入門を志願した恵能は、これを断られると決心の強さを表すために、自らの手を切り落とし菩提達磨に差し出した、というような極端な話も伝わっている。この種の逸話は沢山あるが、その所以は、「仏祖の大道、かならず無上の行持あり、道環して断絶せず。発心、修行、菩薩、涅槃、しばらくの閒あらず、行持道なり。このゆえに、みずからの強為にあらず、他の強為にもあらず、行持道なり。」(注44)として、我々が悟りを開けるのは、その方法が代々継承されてきたからである、とする。つまり禅者が悟りを開けるのは「諸仏諸祖の行持によりて、われらが行事見成し、われらが大道通達するなり」(同)ということになる。
それ故に師匠に仕える必要が有り、そのためには世俗の地位や名誉や、既存の価値観は捨てねばならないとされる。禅の有名な書物『碧眼録』にも「垂示云、機不離位、堕在毒海(我師が仰るには、世俗の関係や地位を離れなければ、悟りには到達できないどころか、迷いの海に沈むことになる。)」(第二五則)などという言葉がる。
スーフィーの生活
この師匠の教えは主に、清貧と禁欲、そして祈りと精神集中によってなされるとする。特に、スーフィーは宗教生活、つまり祈りの生活に専念するために、日常の雑事から極力距離を置く事を目指した。つまり、全てを神に捧げ尽くすことを目指すスーフィーにとって、日常生活に最低限のもの以外は、不必要なのである。
インドで有名なスーフィーであるクトゥブ・ウッデーンは在る時、スーフィーのファリド・ウッデーンが、裸同然の清貧生活を送っていたにも拘らず、砂漠の民に不可欠な戸枠を捨てきれずに持っているのを見て「汝は、まだ神の御心に近付いていない!」と喝破しました。すでにスーフィーとして高名であったファリドは、自らの非を恥じてクトゥブの弟子なり、修行を完成させた。この様にスーフィーにとっては、物質的な財はおろか精神的なもの、つまり願いや希望さえも持たない完全に「貧しい者」(ファキール)や「乞食者」(デルヴィーシュ)になること、またそう呼ばれることは名誉なことが理想とされた。
この様な清貧の思想は、仏教では開祖ゴータマ・ブッダをはじめ戒律で定められた生活となっている。しかし、実際には、名利を求める宗教家が少なくなかった。だからこそ中国の名僧臨済義玄などは、有名になり人々が所住の寺に押し寄せて来る度に、それを嫌い所住の寺を転々としたし、空海や道元は都を離れて寂しい山中に庵を開いた。
特に空海は『三教指帰』において、社会的出世の道を捨てて出家すること、つまり乞食僧として生きてゆく決意を表現しているが、その生活はまさにスーフィーそのものである。
修行の方法
自らの努力によって神との合一の階段を登ることが出来るとするスーフィーにとって修行は、重大な関心事である。しかし、仏教やヒンドゥー教のように苦行や修行体系をd伝統的に形成してきた宗教と異なり、イスラムにおいては如何にスーフィーといえども苦行や荒行を公然と主張することはまれであった。その代わり、ズィグルと呼ばれる称名念仏的な行が奨励された。
つまり一心不乱に神御名を唱える事を通じて、神に近付こうというのである。それゆえに、しばしばこのズィグルを通じて忘我の状態を体験し、神との合一の疑似体験とすることがスーフィーの間で行われる。彼等の行がどれほどであったかを知るエピソードとして、初期のスーフィーで有名なサフル・イブン=アブディラー(896年没)の話が伝わっている。彼は弟子に「アッラー、アッラー」と一日中唱えよと教えた。弟子がそうする事を覚えると、こんどは睡眠中にもそれが口から出るようにせよと命じた。ある時、その弟子の頭上に材木が落ちると、滴り落ちる血の中に「アッラー、アッラー」と書かれていた、という。
仏教ではこれほどの熱狂的な表現は伝えられていないが、平安時代の空也上人(903-972)は、「市の聖」あるいは「弥陀聖」と呼ばれ常に念仏を行いながら、人々の救済を粉骨砕身した。空也上人は、口に弥陀の妙号を称えながら民衆救済を行ったとされるが、その宗教性の高さ、阿弥陀仏への帰依の深さを現した有名な空也像と通底するものがある。つまり、波羅蜜寺には、その姿を象徴的に表現したとされる、鎌倉時代の明光運慶の子康勝作で、空也上人の口から阿弥陀仏が現れる上人像がある。この空也上人像の口から7体の阿弥陀仏が現れる姿は、先のスーフィー達の表現が誇張でなく、一種の宗教的な領域を現したものであることを現している。
この様に、神の名を一心に唱える称名行は、イスラムのみならず仏教にも、キリスト教にも共通する修行である。そして、その目的は、ひとえに神への思念の集中である。
スーフィズムにおいて精神集中が、宗教的完成への階梯を上る最重要手段と位置付けられた背景には、インド思想やグノーシスからの影響が考えられるが、フーフィーの特徴として、音楽や舞踏を介 してこれを達成することが出来るとする点がある。彼等は音楽や舞踊を単なる儀式としてではなく、修行の一環、しかもそれらを通じて神を直接に体験できるとした。
スーフィズムの行の一つとして、音楽をスーフィーの修行体系の中に、本格的に導入する道を開いたのは、イスラム史上最大の思想家であり、偉大なスーフィーの哲学者アルーガザリー(1058-1111)である。彼は、サマーとよばれる音楽的な修行法を重視した。つまり、スーフィーは、音楽を聴きながら、奏でながら、徐々に精神を集中させ神との合一が出来るとし、その修行を重視した。是は、インドの宗教者に於いてもみられる傾向である。また、日本の日蓮宗なども同様な形態をとる。
彼は「スーフィーとは、特に神への道を歩むものであり、その生き方は最善のものであり・・・。スーフィーが動くのも止まるのも、その内も外も、すべては神の啓示の光明から得られたものであり、地上には啓示の光明のほかに光源は何もないのである。」(中村広治郎『ガザーリーの祈祷論』大明堂
一方、一部のスーフィーの中で行われていたセマーと呼ばれる祈祷の舞に高い評価を与えたのが13世紀の偉大なスーフィーであり、詩人であるメヴァラーナー・ルーミー(1207- )であった。彼は托鉢僧の影響を受けセマーに没頭し、セマ―を通じて法悦、つまり神と合一体験を、セマーの内に体験したのである。彼はセマーを自らの友人や支援者、弟子の内に広めた。
ルーミーのセマーを一つの教団に組織化したのは息子ヴェレドであった。彼の教団をルーミーの名を冠してネヴァラーナー教団と呼ぶ。この教団では、音楽にあわせて旋回し忘我の状態に至る。彼等は何時間、時には幾日も踊り続けるという。
ルーミーの影響も与り、本来は異端とされる音楽や舞踏を重視するスーフィー思想、あるいはその修行法は、大きなうねりとなり東はインドから西はスペインまで瞬く間に拡大した。12―13世紀以降のイスラム勢力の拡大に、スーフィーの役割は大きかったが、特に、インド亜大陸に於けるイスラムの拡大とスーフィー、それも音楽や踊りを介してとトランスに導くカッワーリーの果たした役割は無視しえない。
インドでは13世紀以降、チシュチィーやスフラワルディーといったスーフィー教団が、カッワーリーなどの修行法を用いて多くのインド人の心を捉えた。以来、カッワーリーは、現在に至るまで幅広く民衆の宗教性を支える修行であり、さらに娯楽としても実演されている。また、シク教に於いても、この風習は取り入れられている。(注保坂)
この様な音楽と舞踊とが一体となり、トランス状態に導く修行の仕方は、仏教の踊念仏と共通するものである。踊念仏は、一遍上人が仏教を分り易く民衆に広めるために、編み出した修行の一種である。彼は激しい念仏踊りによって、忘我の状態となり、阿弥陀仏の救いが得られるとした。多くの信者が念仏踊りの内に失神したとされる。
神人合一体験(ファナー)と融和思想
神との合一体験、それはいわば忘我の状態(トランス)であり、この忘我の状態の内に神との邂逅や一体感を得るという神秘体験のことをスーフィーは、ファナー(消滅)と呼ぶ。この神秘体験は、本来言葉によって表現することは出来ないとされる。
しかし、同時に言葉でなければこの体験は表現できないのも事実である。少なくとも、言葉は、この神秘体験を表現できる最も有効な手段である。故に、多くの神秘主義思想に共通に見られる現象であるが、スーフィーのファナー体験も象徴的な表現によることとなる。また、時には逆説的、否定的表現なども多用される。というのも、彼らの体験した世界は、「目に見えない絶妙は、伝統的権威によってではなく、神的光により事物を把握できるまでに神の恩寵を享受した人々のみによって、理解される。」(ガザーリー・39)であるからである。
しかも、彼らがファナーの状態にあるときは「彼らの眼には、一者以外何もみえないし、また自己自身すら見えない。彼らはタウヒードに没入しており、そのため自己自身さえ気付かない。・・・。自己自身から死滅してるのである。)」
という状態にいる。
このファナーの状態は「いまや神がその僕)の心の世話役となり、叡智の光で心を照らし出すに至る。神が僕の心の世話を引き受け、{神の}恵みがその上に満ち溢れ、光が差し込んでくると、心が開き、神の国の神秘が顕示される」という具合である。
さらにガザーリーはファナーの状態を、神を表す焚き火とスーフィーを表す 蛾の比喩で表現する。つまり火の回りに集まり旋回する、最後に焚き火に飛び込み、一蹴の内に燃え、焚き火の一部となるように、スーフィーも神の中に消滅し、神と合一できるとするのである。
この様に、ファナーの状態は一切の束縛を超えた世界である。
仏教でも、悟りの境地は「言語道断」であり、これを表現することは竜樹の『中論』に展開される八否の論理や、臨済の「仏に逢えば仏を殺し、祖師に逢えば祖師を殺し、・・」(臨 済 録97)などに顕著に現れている。
君はそれに対応するものが何も存在しない名前を知っていますか。
君は「ば」「ら」という文字から、ばらを摘み取った事がありますか。
君は神にも名をつける。それなら行って、君が名づけた実在を探し出してきなさい!
水の中にではなく、大空に月を探し求めなさい!・・・中略。
君が単なる名前や文字を超えた所に登りたいと願うなら、直ちに自我から自由になりなさい。自我の全て除く際から身を清めなさい。
そうすれば君は自分自身の輝く本質を見るだろう。(ニコルソン91)
このようにスーフィーたちは、その深い思索とあふれんばかりの信仰心、そして巧みな言葉で、ファナー体験を表現し、珠玉の箴言集、あるいは詩集を世に送り出した。つまり、ファナー体験から生まれた境地は、深遠にして、広大、自由にして柔軟なス―フィー思想を生み出し、それは多くの優れた文学作品、特に詩集を生みだすこととなったのである。
ルーミーはその典型ということが出来る。
しかし、スーフィーの思想は、単に文学作品のみに現れたわけではない。それは絵画や芸術、建築さらには現実政治にまで広く展開されたのである。つまり、この思想は、スーフィー文化とでも呼べるような包括的な文明現象にまで拡大してゆくのである。こうなると、本小国者で問題とする、宗教の差異の超越として、寛容思想の根底があらわとなり、またバクティ思想に通底する思想的な地平が明らかとなる。
次に具体的な例をインドのムガル朝に見てみよう。
インドおけるスーフィズムの展開
インドへのイスラムの正式伝播は、711年と早かった。ヒンドゥー教と仏教の地インドへのイスラム伝播は、やはり武力による軍事的な支配からはじまった。その後、11世紀から本格化するアフガン勢力の熾烈な殺戮や宗教弾圧によって、イスラム徒とヒンドゥー教徒との間の溝はなかなか埋まらなかった。しかし、12世紀頃からインドに 進出してきたスーフィー達の地道な努力が、本来開放的で、融和的なヒンドゥー教徒の心を開くこととなり、両者の間には徐々にではあるが、融和・共存の風潮が生まれた。
大多数のスーフィーは、特定の政治権力と結びつく事を嫌い、信仰と宗教生活を共にする少数団を形成し、ひたむきにファナーを目指して修行に打ち込んだ。彼等の集団をターリカと呼ぶ。
このターリカは、シェイフなどの精神的指導者を中心に形成され、その組織も極めて弾力的であった。また、その中にはヒンドゥー教の苦行や修行者さえも加わり、また逆にヒンドゥー教の修行者の集団にスーフィーが加わることもまれではなかった。
インドへのスーフィー達の布教活動は、主に中央アジア出身者によって支えられた。彼らの存在は、歴史に名を残さないような民衆レべルの聖者たちによって静かに、しかし、着実に行われた。そのような草の根運動的なスーフィズムのインドへの展開で注目されるのが、チィシュティー派の存在は重要である。
このチィシュティーは、アフガニスタンの現在の地名でいえばチィシュト(Chisht)に本境地を置く、謂わばインド独自のスーフィー教団である。このチィシュトは、かつて仏教徒の町であったが、それがユダヤ教徒に、さらにマニ教徒の、さらにイスラムへとその居住者の宗教が変わった土地である。しかも、この地は、イラン文化圏とインドとの中間点に位置し、それ故にイスラム化したのちにも、異教的な雰囲気が色濃く残っていた土地であった。ここの生まれたスーフィー教団ガ、チィシュティー教団である。この教団の起源は古く、9世紀頃からその存在が知られているが、その存在が、一躍注目されるようになったのは、高名なババ・ファリド(Shikh Faridu’d-Din:1173 ~1276)による目覚ましい活動にある。ファリドの祖先は、アフガニスタンのカブールの出身であったが、戦火を避けて移住したラホール近郊で生まれた。彼の母は、ファリドの思想形成に大きな影響を与えたが、その最たるものは、苦行と清貧ということであったとされる。彼の母の伝記はつまびらかではないが、激しい苦行や清貧の思想に、インドのゴーガ行者の教えに通じるものがあるという指摘は、多くのイスラム研究者も認めるところである。(ff。97)このファリドの後継者と言われるニザムウッディーン( 1238~1325 )は、ヒンドゥーの聖者と広く交流し、その影響を強く受けたとされる。その一方で、彼らはヒンドゥー教徒への働きかけを積極的に行い、イスラムとヒンドゥーという二つの宗教の教条主義的な対立を越えて両者の宗教の違いを認めつつ、究極的には異なることがない、あるいは目指すものは変わらない、という意識を醸成するまでに至った。14世紀の初頭のことである。彼らの後継者は、このヒンドゥー教との共生の思想とも言うべき運動を推し進め、両者の対立を越える道を模索した。勿論、彼らスーフィーといえどもイスラムの優位性を越える事は出来なかったが、しかし、これを越えて両者の融和的な共生思想を説くものが現れた。
その代表がカビールやナーナク(1469-1538?)らである。彼らは、イスラムからは偉大なスーフィーの師(シェイクやピール)と呼ばれ、ヒンドゥー教徒からはグルと呼ばれる存在である。
この様なヒンドゥー・イスラム融和文化は、スーフィーによるイスラムからのヒンドゥー教への理解と歩み寄り、そしてヒンドゥー教徒本来の寛容さが融和した結果である。そして、それを政治的にもバックアップしたのが、ムガル王朝第3代皇帝のアクバル以下、その子孫達である。
アクバルは、カビールやナーナクから遅れること数十年にして、ムガル王朝第3代の皇帝となった。彼は独自のヒンドゥー・イスラム融和思想、それをさらに進めた融合思想を展開した。またアクバルは、この視点を、単なる抽象論に終わらせることなく、現実の政治・社会政策に展開し、既存の諸宗教をイスラムと同等視した寛容政策を展開した。
既述のように、インドには宗教的差異を超える神秘主義思想の伝統が、その底流に存在し、その伝統はイスラム教徒の世界においても、無理なく受け入れられた。特に、自らもスーフィーとして宗教的な体験を持っていたアクバル帝は、その宗教思潮を積極的に宗教的にも、また政治的、文化的にも展開した。
その結果、ヒンドゥー・イスラム融合文明と言いえるような諸宗教・文化融合が、アクバルからダーラーまでの約百年間、ムガル宮廷を中心に花開いた。そこでは、イスラムとヒンドゥー・キリスト・ユダヤ・パールシー(イラン)の各宗教が、同等に扱われ融和・融合する文化が花開いた。
スフィーであるアクバル帝と宮廷文化
アマルダスとの関係でシク教の思想や歴史においても重要であるアクバルは、自らもスーフィーとして活動する神秘主義者であった。勿論、彼自身最初からスーフィーではなく、それ故に一般のイスラム王の如く、その最初期においては諸宗教の融和を必ずしも重視していなかった。しかし、1560年代から徐々にその気運は高まった。彼はシェーイーク・サリム=チシュチーから強い影響を受けスーフィーとして諸宗教の寛容へと大きく変貌して行く。
1570年代の中ごろより、彼の宗教政策は、権威化し、教条的な正統イスラムを廃して、宗教的寛容を目指すスーフィー的傾向をもつ。先ず、アクバルは1575年に教条主義的なイスラムの聖職者達を排除して、信仰の家
を建設した。
また、 アクバル帝は1579年にはイスラム至上主義者への反省を込めて、諸宗教融和を旗印としたディーニ=イラーヒー(神聖宗教)を始めた。これは1575年以来続いていた信仰の家における諸宗教の対論を通じてのアクバル帝がたどり着いた結論であった。
アクバルはこの「信仰の家」においては、「この神聖なる場所は、霊性の構築のために供され、この地に神聖なる智の柱が高々と出現した。」と表現される如く、アクバル帝を中心に
彼の寛容さと神の影を明らめる(帝の)寛容さによって、ここにはスーフィー、哲学者、法学者、法律家、スンニー派、シーア派、(ヒンドゥーの)バラモン、ジャイナ教徒、チャールバーカ、キリスト教、ユダヤ教、サービー、ゾロアスター教徒などが、この厳な集りにおいて一同に会して議論を行った。(アクアルナーマ)
という宗教的雰囲気が形成された。
このアクバル帝の諸宗教の融和思想やその政策については、さまざまな批判もなされている。しかし、彼の融和思想が単なる思い付きや政治的なテクニックによって導き出されたものでないことは、幾つものエピソードによっても明らかとなる。
例えば、アクバルは1567年シク教の第三代グルアマル・ダス(1479-1574)を訪問する。当時、結成間もない弱小教団であったシク教であるが、アマル・ダスは、面会の条件として、アクバル帝にシク教のシンボルであるランガル(共同食堂)で食事をとることを示す。この共同食堂とは、年齢、職業、階級、性別さらには宗教を問わずシク教の教えに共感する者が、先ず食事を共にするというシク教の教えに由来するが、実際には差別社会であるインドに於いては、革命的な事であった。
この申し出を聞いたアクバルの臣下は激怒したがアクバル帝は、一弱小教団の教主ではあるが、その神秘主義思想家として名をなしていたアマル・ダスの言葉に従い、伝えられるところでは、乞食達と同席し、ランガルにおいて粗末な食事を執ったと言われている。しかもアム場ルは、アマル・ダスの思想に共鳴し、彼に現在のアムリッサル一帯を与えたのである。それがシク教団の躍進にも繋がったのである。
また、彼が建設した首都ファーテープル=シークリーには、彼の諸宗教、文化融合という理想が具体的な形となって現れている。彼が建設した宮殿には、イスラム建築の象徴とも言えるボドームやアーチはほとんど用いられず、ヒンドゥー教や仏教の建築様式である木組みを思わせる柱やはり、さらには傾斜した屋根などが、全て石を素材に作られている。また、ディワネー・カース(貴族謁見の間)には、諸宗教・文化の融合を象徴する柱が建設された。建物の中央に建つ一本の柱には、イスラム・ペルシャ・キリスト・ヒンドゥーの各宗教文化を象徴する模様や形が彫りこまれ、それが巨大逆円錐形のヒンドゥー様式の待ちうけ式の梁で支えられる形となっている。皇帝はこの上で帰属を睥睨して謁見した。
アクバルの諸宗教の融合政策、融合文化は、彼の墓所であるシカンドラに於いて見事に証言されている。この建物には、世界各地の意匠がふんだんに使われ、それらが見事に調和している。
このように、アクバルは身分の上下、宗教の如何を問わず道を求めるのに真摯であり、全ての宗教に寛容であり、また異なる思想に対しても謙虚に耳を傾ける思想家でもあった。彼は当代一流のスーフィーとして、ヒンドゥー・イスラム融和・融合思想の流れを享け、さらにそれを一歩進めようとしたのである。
ダーラーのヒンドゥー・イスラム融合思想
ダーラーの思想については、日本においては、アクバル帝のそれ以上に知られるところが少ない。しかし、彼はムガル王朝を代表するスーフィーであった。しかも彼はシャー・ジャハーンの皇太子として、実際の政府を執りその中に寛容の精神を反映させた。また、彼は文化事業にも熱心であり、例えば、彼がサンスクリット語からペルシャ語に翻訳させたウパニシャッド文献、これは『ウプネカット』と呼ばれ、後にラテン語訳されてヨーロッパの知識人に大きな影響を与えたことは、よく知られたことである。これのみならず、ダーラーは、スーフィーとしてイスラムに固執せず、諸宗教思想に極めて柔軟に対応した。特に、彼はヒンドゥー教の諸聖典の翻訳事業などを通じて、神秘主義思想を極めた。特にヒンドゥー教の聖者バーバー・ラールの感化を受けてある意味でバクタとしての立場から、ヒンドゥー・イスラム両教の融和を思想的に試みたのが、彼の代表作である『二つの海の交わるところ(マジマルーダフリン)』である。
ダーラー自身が書いた本書の前文には、この経緯を、
(ダーラーは)真実の中の真実を覚り、スーフィーの真の宗旨(教えの根本)の素晴らしさに目覚め、偉大なる深遠なるスーフィーの英知を悟った後に、(ダーラー)はインドの(存在の)一元論者達の教義を知ろうと強く願った。(ダーラー)は学者達と交流し、インドの宗教における神の聖性について議論を繰り返した。彼等インドの学者は、宗教的な訓練と知性と洞察において最高に完成された境地に到達したもの達である。そして、(ダーラー)は、彼等(インドの宗教者)が捜し求め、獲得した真実について、言葉以外には、その違いを見出すことができなかった。その結果、2つの宗教(集団)の考えを集め、諸テーマを集め。真実を求める人に基本的で、有益な知識を供給する一冊子とし、これを名づけて『二つの海の交わるところ』とした。
と、ダーラーは記述している。
これは、「この世界が神の顕現であり、人間は神の本質のミクロコスムである」というウパニシャッド的な世界観に強い共感を示すのである。その上さらに、彼等は調息や聖音などの思念を説き、生前解脱さえ認めるのである。
これらのことを通じてダーラーは、イスラム教とヒンドゥー教との共存が、社会的、文化的はおろか宗教的にも可能である、と言う考えに至るのである。このとこは、イスラムの寛容性を最大限引き出したインド・スーフィーの知的営みの極致と言うことができよう。
インド・イスラムの近代化
インドのイスラム化は、前述のように主に異教への寛容・融和思想を説くスーフィー達の努力によるところが大きかった。その結果、ムガル王朝ではヒンドゥー・イスラム融和思想が優勢となっていたが、その一方で絶対少数であったムスリム人口も増大し、ムスリム純化の意識が高まりを見せてきた。その発端にスィルヒンディーがあり、さらにシャー・ワリーウッラー(1703-1763)が登場し大きなうねりを形成する。彼は偶然にもアラビア半島において極端なイスラム純化運動を展開したアブドル・ワッハーブ(1703-87)と同様の運動を展開した。尤も彼の運動自体は、直ちにインド・イスラム全体に大きな影響を及ぼすまでには至らなかったが、彼の浄化運動は、子弟に受け継がれ、シク教やイギリス政権への攘夷運動に発展した。しかし、その過激さの余り程なく弾圧される。しかし、その思想は、遥か後のインド・パキスタン分離独立時のパキスタン建国の思想に影響を与えた。
ワリーウッラーに由来する攘夷運動の挫折やセポイの乱(1857-1858)失敗のは、高度な西洋文明へのムスリムの覚醒を齎した。その代表がサイイド・アフマド・ハーン(1817-1897)であった。彼はムスリムの近代化のためにあらゆる方面に大きな貢献をしたが、説くに後にアリガール大学となる「ムハメダン・アングロ・オリエンタル・カレッジ」を設立し、ムスリム子弟に近代的な教育の場を提供したことは、その後のインド・イスラムの発展に大きく寄与した。
しかし、アフマド・ハーンの提唱する開明主義的運動に対して、伝統を重視しつつ近代的な精神をイスラムに取り込んだイクバル・ハーン(1873-1938)の存在は、重要である。彼はミュンヘン大学から学位を取得する程の高い学識を持った教養人であったが、決して西洋文明に傾倒せず、これをイスラムの近代精神形成に利用できた稀有な思想家であった。また、彼はムスリムのインドからの分離独立運動を積極的に進め、パキスタン独立の父ジンナーに大きな影響を与えた。
1947年多大な犠牲を払ってヒンドゥー教徒を多数派とするインド共和国とイスラムを絶対多数とする東西パキスタンは分離独立した。その後、1971年には東パキスタンが、バングラデーシュとして独立する。
また、イスラム国として独立したパキスタンと世俗主義国家として独立したインド共和国においては、そこに住むムスリムの意識は多少異なっている。特に、パキスタンは軍事政権が長く続き、その間にイスラム復古主義が推進された。一方、インド共和国内に留まったムスリムはヒンドゥー教との協調を重視する傾向にある。
しかし、インドもパキスタンも領土問題やアフガニスタン紛争など国際情勢に翻弄されており、その思想的な混乱も小さくない。
さて、シク教の成立時代の背景に関しても、多生触れてみよう。シク教の伝承では、ナーナクはむガス創始者であるバーブルとまみえているとされるが、これが歴史的事実かは不明である。しかしナーナクは、このサマルカンドからの征服者の軍隊に蹂躙される西北インドに在って、凄惨な状況に直面したことは、事実である。なぜなら、シク教の聖典『グラント・サーヒブ』には、そのことが直接述べられているからである。
そして、新来のムスリムの支配者への恐怖は、アマルダスの時代にも半ば共通するものがある。勿論、アマルダスの時代は、第3代アクバル帝の宥和政策が実を結びつつあった時代であるが。
そこで、先ず大まかな時代背景につて整理しよう。
第四部 シク教成立の時代背景
アラビア半島におけるイスラムの拡大は、人類史レベルでの大変革をもたらしたが、殊インドにおいても例外ではない。と云うよりもインドにおいては、アーリアン人のインド侵攻と定住にも勝るとも劣らない大きな衝撃を文化レベルから文明全域に及ぼした。このインドへのイスラムの侵攻は、歴史的に海路・陸路の二つのルートから為された。先ず海路は、古来以来の中東との交易路を経由してインダス河下流域やマラバール地域にイスラムは、多く商人の活動により、そして時にムハマドカーシム(697 -716)のような聖戦を主張する軍事行動によってもたらされた。(7)さらに、その陸路も二通り存在した。つまり最初期においてはイランから海岸線をたどり、マクラーンを経由してインダス河河口地域に至るものであり、これらは当初軍事的な色彩を強く持っていたが、やがて交易中心に細々と維持されたルートである。一方、10世紀以降本格化し、13世紀にはインドの心臓部とも言えるヤムナー河中流域のデリー地域に、ムスリム政権を成立させることとなった中央アジアからアフガニスタン経由のトルコ系ムスリム達のルートであった。彼らは、アフガニスタンのカイバル峠やボラーン峠など数少ないインドと中央アジアを結ぶ峠経由のルートを経由した。
ムガル朝の創始者バーブルは、この中央アジアからアフガニスタンを経由してインドに侵攻し、中北部のインドを支配し、ムガル王朝建設の基礎を築いた覇王であることは、周知の事実である。本小論で、バーブルに至るまでのインド・イスラムの歴史を詳説することはできないが、インドへのイスラムの侵攻と定着という歴史的な事実を主に武力によって大規模に展開したのは、この中央アジアから南下するルートを辿ってやってきたムスリムであったことは、インドにおけるイスラム観を考える上で重要なことである。特に、中央アジア経由のイスラムのインド伝播は、他の地域へのイスラム伝播以上に、軍事的つまり暴力的な色彩が強く、その代表的な存在がガズナ朝(977―1186)の存在であり、その象徴的な存在としてマフムード(在位998―1030)の存在である。彼の軍事行動は、イスラムの側からは快挙として、驚きと羨望を以て称賛され、インドにおける略奪により手に入れた莫大な財宝や奴隷によってガズナ朝の首都ガズナの繁栄は西のバクダッドと並び称されたとも言われるほどであった。事実、ガズナの宮廷にはアルビールニー(1030年ころ)など当代一流の文人・知識人があつまり、高度なイスラム文化が花開いた。一方、被征服者側のインドにおいて、彼の凄惨な殺戮や寺院などの聖地の破壊と掠奪は、長く「歴史的不正」として長く記憶され続けた。
周知の如く、その後のインド北部は恒常的にアフガンから南下するトルコ系ムスリムの定着と支配が、バーブルによりムガル王朝の建設へと連続続いてゆくこととなるが、バーブルの検討の前に、ナーナクなど北インドの非ムスリムにとってマフムード以上にムスリム侵略者への恐怖感を脳裏に刻み込ませたのが、バーブルの祖先でもあるティムール(在位1370―1405)のインド侵攻であった。彼のインド侵略は過酷を極め、ティムルの掠奪と破壊を受けたトゥグルグ王朝の首都デリー(彼はムスリムであっても容赦はなかった。)は、長く廃墟となったといわれている。(侵略は1398―1399にまたがって為された。)この時のティムルの攻撃の記憶は、インド人のトルコ系ムスリム、さらにはイスラムへの基本認識として消える事がなかったということが言えよう。
後に紹介するようにナーナクが、バーブルの侵略軍を「死神(ヤマ)」と表現したのは、このようなチムールに代表されるトルコ系ムスリムのインド侵略の過酷さを表現していると考えてもいいのではないだろうか。あるいはバーブルがチムールの後裔であるという事実が、バーブルへの認識と重なったのかもしれない。
もちろん、すべてのムスリムの王が殺戮や掠奪をほしいままにしたわけではない。しかし、インドの富への憧れと多神教徒の跋扈するインドへの聖戦という宗教的な情熱が融合し、多くのムスリムのインド侵略が正統化され、また実施されたことは疑いえない事実である。
もちろん一般に、インドへのイスラムの定着は、スーフィーなどの活躍により平和裏に行われてことは否定できない事実である。が、しかしその一方で宗教的な熱狂が、経済的欲求や領土的欲求など様々な世俗の欲望と混然一体化し易いイスラム独自のタウヒード(聖俗一元)の思想構造により、多くの軍事活動が引き起こされたことは、バーブルの場合も例外ではない。歴史学はバーブルなど権力者の史料を多用するので、「犠牲者3―4万人」などとさらりと書かれても、余りコメントされることはない。しかし、実際に犠牲となる側からの、それも庶民の側からのこのような悲惨な現実への意見は、あまり表に出ない。その意味で、市井の人であったナーナクのバーブルに対する言及は、まさに同時代史のしかも庶民側からのムスリム支配者への偽らざる感情であるという意味で貴重であろう。また、そのような侵略行為の積み重ねにより、中央アジア経由で否応なく齎された異質な文明の形が、やがて新しいインド文明へと成長してゆく過程すらも、ナーナクの思想から読み取れるのである。
インド中世における宗教と社会背景
多少前項の内容と重複するが、ナーナクのバーブル観の検討には、インドへのイスラムの侵攻定着から考える必要がある。つまり8世紀初頭のムハンマド・カーシムによるシンド征服にはじまった、イスラムのインド定着は、一時中断した後、11世紀のガズニー朝のマフムード(在位998-1030)による執拗なまでのインド略奪に象徴されるように、軍事的な侵略が主にカイバル峠経由で侵入するトルコ系のイスラム教徒により繰り返される。そして、その対象は肥沃なパンジャブ地であり、そこはかつて仏教が栄えた土地でもあった。その意味で、当時のヒンドゥー教徒やその他の非イスラムの人々とムスリムにおける相互の宗教認識は友好的なものとはなかった。
特に、トルコ系イスラムの人々は、軍事的な優位を背景に支配者として君臨し、ヒンドゥー教徒などの存在をカーフィル(邪教・多神教徒)として、聖戦を波状的に繰り返したために、両者の関係は悪化していた。というのも、デリー・スルタン王朝の興亡に象徴されるように、インドに侵攻した主にトルコ系イスラムの為政者たちは、インド人との精神的な交流に至る以前に、中央アジアから次から次へと押し寄せてくる新たなトルコ系ムスリム軍によって打倒され、インド文化との融和関係を育むまでに文化的な成長を為し得なかったのである。つまり、社会的な混乱や動揺が続き、本格的なイスラム教徒とヒンドゥー教徒との共存共栄の可能性の模索は、政治レベルではなされることはほとんどなかった。この点で、11世紀初頭のインド社会の現状をムスリムの目からみたムスリムの大学者アル=ビールーニー(973-1050頃)はその著書『インド誌』において、ヒンドゥー教とムスリムとが相容れない理由を「〔インド人とムスリムが相互に理解しがたい理由として〕またつぎのことがある。彼らは信仰において我々と全くと言っていいほど異なる。われわれは彼らの信仰をまったく認めないし、彼らも我々のそれを認めない。・・・中略・・(非インド)そのような者たちは『ムルージュ』(=ムレッチャ)と呼ばれるが、それは不純な者であり、婚姻や友誼でそれらと接触したり、同席したり飲食をともにすることは認められない。それは穢れだからである。・・・・(中略)彼らは彼らに属さない者を、たとえその者が彼らの中に入ることを欲したり、彼らの信仰に傾倒したりしても、絶対に受け入れようとしないのである。このことが〔ムスリムとインド人のあいだの〕すべての接触を不可能とし、溝をより大きくする原因となっている。・・・中略・・われわれと彼らのしきたりや習慣はまったく異なる。〔それゆえ〕彼らはわれわれの存在や、服装、外見を、子どもたちを怖がらせるのに使ったり、はてはわれわれを正義の対極にあるところの悪魔に結びつけたりするほどなのだ。・・・・(中略)それはわれわれとインド人のあいだにあるのでなく、どこの国でもよく見られることであるのだ」(小谷汪之編『南アジア史2』(世界史大系)山川出版社、2007年))という状況であった。
アル=ビールーニーは、11世紀の西北インドにおいてムスリムと非ムスリムの間には、このような宗教間の対立関係が存在し、その対立が両宗教の信仰の差もさることながら、「しきたりや習慣」にあるとしている。つまり、これは日常生活における生活倫理規範が、両者の接触を難しくしていたことを意味している。もちろん、アルビールーニーがいうように、このような対立はどこにもみだせることではある。
しかし、このヒンドゥー・イスラム両教対立を埋めることは容易なことではなかった。それはイスラム特有のタウヒード(聖俗一元)の構造による日常倫理と宗教倫理の同心円状構造による。一方、ヒンドゥー教徒の側も宗教と日常生活の未分化あるいは楕円構造による重層性により、両者の対立は単なる日常倫理レベル、つまり生活習慣レベルのそれに留まらず、いわば絶対異空間ともいえる信仰レヴェル、宗教倫理の領域における対立に直結していたからである。しかも、インド土着の信仰は、彼らの目には「ジャヒリーヤ」であり、大征服の時代以来ムスリムの敵対者であった「啓典の民」であるユダヤ・キリスト教両教徒とは、その位置づけが異なるのである。しかも、このインドの多神教徒は、反イスラム勢力としては、宗教的にも、文化的にもその水準がイスラムに決して劣らない水準であった。そのためにより一層両者の対立は深刻であった。同時にヒンドゥー教側も彼らを「ムレッチャ」と呼びさげすんでいた。
というのも、すでに触れたようにイスラムの生活倫理は、シャリアーに依って『コーラン』を核として不易のものであり、同様にヒンドゥー教においても日常倫理であるダルマは、宗教性と密接不可分であり、日常レベルの対立は、非妥協的な宗教レベルに持ち込まれる傾向をもつ。それ故に、インドにおいてヒンドゥー・イスラムの対立は、日常生活を巻き込んだ、というより日常生活の場において宗教対立という形で顕在化する故に、深刻であったそのために、西北インドから中インドにかけて瞬く間にムスリムによる政治的な支配が実現したにも拘らず、インド人の改宗は、あまり進まなかった。
というのも、多神教徒へのイスラムの布教あるいは、彼らの懲罰というイスラムへの宗教的な使命感とインドの豊かさへの経済的な欲求の相乗効果で、インドに侵攻したトルコ系ムスリムの支配者も、年月が過ぎると多数派のヒンドゥー教徒の存在と妥協し、彼らの寛容主義を発揮して変則ながらも平和的な共生社会を形成する。ところが、そのような先発ムスリムに対して、後発のトルコ系ムスリムたちはインド侵攻の期を窺い、彼らの弱体化に乗じて新しい王権を形成し、再びヒンドゥー・イスラムの緊張関係が引き起こされる。このように侵略と混乱、そしてつかの間の平和の繰り返しが、中央アジアからのトルコ系ムスリムのインド侵攻が本格化する10世紀以降、バーブルのインド侵攻に至るまでのインド、特に北部インドにおけるパターンであった。しかし、そのような中でもインドっ民衆は、イスラムの文化文明をインドのそれと融合あるいは共存のためにたゆまぬ努力を行っていたのである。つまり政治的な混乱とは別に民衆レベルでは、スーフィー達が積極的に布教をおこない徐々にではあるが成果を上げていた。
彼らは、教条主義的なイスラム解釈を控えシャリアーの実践以上に、スーフィー独自の救いを重視した。この救いとは、魂の救済(ファナー)の獲得である。この究極的な目標であるファナーを目指すスーフィーの教えは、インド宗教思想との共通点が多く、両者の融合に大きな役割をはたした。特に、日常生活倫理(世俗倫理)において大きな相違点があったヒンドゥー・イスラム両教徒における日常倫理の違いを、イスラムの神とヒンドゥー教における究極的な真実(神)と相違がないという思想にまで高めた、ダーラシュコー(1615-1658)を頂点とするインド・スーフィーの果たした役割は大きい。
このイスラム神秘主義者とヒンドゥー教の神秘主義者たちの思想交流の伝統の中に、シク教の開祖ナーナク)が位置づけられる。彼らに共通することは、ヒンドゥー・イスラム両教どちらもの教条主義も否定し、自らの神秘的宗教体験を通じて、もろもろの宗教の究極的な一致を説いた点である。
ナーナクの時代背景
シク教の開祖ナーナクは、前述のようなインドにおけるヒンドゥー・イスラムの対立構図の中で、両教の融和統合を目指して勢力的に活動した思想家、宗教家である。ナーナクはパキスタンのラホール近郊のタルワンディーに、クシャトリアが土着し、商人となったカットリ階級に属する商人の子として生まれた。(16)彼の家は、代々徴税官を務める地主であり、また小規模な商店経営者として地域の支配階層に属していた。当時のパンジャブは、比較的安定した社会状況にあり、ナーナクも、父の跡を継ぎ徴税官として、イスラムの支配者に使えつつ、小規模地主、あらに商店主として地域社会のリーダーとして細々とした世事にリーダーシップを発揮することを求められていた。その為に、ナーナクはペルシャ語、アラビア語をはじめ支配者の宗教や言葉を幼少期に学び、さらにヒンドゥー教徒としてサンスクリット語やウパニシャッドなどの基礎的な学習や家の長男として家庭祭祀に関することを学んだとされる。 つまり、ナーナクは、当時のインドにおいては最もイスラム文化の影響の強いパンジャブ地方において双方の宗教的、文化的教養の基礎を学んでいたのである。もちろんそれは、彼がヒンドゥー・イスラム両教の緊張関係の只中にいたということでもある。(17)
このような宗教の相違から発生する緊迫感に支配された社会にあって、ナーナクは、ヒンドゥー教とイスラム教両教の対立克服を目指して、つまり社会的な安定と個々人の精神の安念を保てる社会の構築を願い、生涯を捧げた宗教家である。ナーナクは30歳頃に神秘体験を持ち、以後ほぼ20年間にわたる巡礼と宗教対話の旅を行った。この巡礼はナーナクの思想性を明確に表すものとして注目されるものである。つまり、ナーナクは一般の巡礼者が自らの宗教の聖地を巡る、その宗教的な利益を得ようとするに対して、彼はヒンドゥー教の聖地はもとより、仏教、ジャイナ教、そしてメッカなどのイスラムの聖地巡礼(第4回巡礼)まで行ったのである。(18)
しかも夫々の聖地において実行される儀礼や作法に対して、その矛盾を指摘し宗教関係者を困惑させたことが知られている。例えばヒンドゥー教の聖地ベナレスのガートにおいて次のようなエピソードが伝えられている。
ある朝バラモンたちと朝の沐浴をしていた時のことである。彼は、朝日に向かって水を掬い、これをかける儀礼をおこなっているバラモンにその意味を問うた。するとバラモンは「朝日に聖なるガンジスの水をかけているのだ」と答えた。それを聞いたナーナクは、いきなり朝日に背を向けて水を掬ってかける仕草を行った。不審に思ったバラモンがその意味を問うと、「パンジャブの私の畑に水をかけているのです。あなたが、この水は朝日にまで届くと仰ったので、私は朝日にまで届くことは望みませんが、せめて私の畑くらいまでは届けたいと思いました」といったという話が伝わっている。
同種の逸話は、メッカ巡礼時にも伝わっている。つまりナーナクがメッカ巡礼を行った時、彼はカーバ神殿に足を向けて休んでいた。これを神への冒涜として咎めたものに対して、ナーナクは『コーラン』には神は遍在するとあるではありませんか、一体私はどこに足を向けて休んだらいいのでしょうか、と問うたというのである。
これらのエピソードはシク教徒が、ナーナクの教えを説明するときに好んで用いるものであるが、まさにヒンドゥー・イスラム両教へのナーナクの基本的なスタンスを象徴するものとして興味深い。つまり、ナーナクはこの巡礼を通じて多くの宗教家と対話し、独自の思想とその思想を構築するまでになったのである。
ナーナクは長い巡礼を終了すると故郷のパンジャブに1520年頃に戻り、ラヴィ河の河畔に、自らの宗教的理想を実現のための村カタルプルを建設した。ナーナクは、彼の目から見て形骸化した既存の宗教の弊害を克服する手段として、自らの宗教的理想を体現すべく理想郷としてのカタルプルを建設したのである。それは宗教的な理想と現実生活が一体化した空間、つまり宗教と日常倫理とを一致させることを目指した理想空間であった。ナーナクここで真理に基づいた生活を実現しようとしたのである。このナーナクの宗教生活即現実生活、日常生活即宗教生活の理想空間の建設には、ナーナク独自の思想に支えられていた。そのような生活に着いたばかりのナーナクの前に現れたのが、チムールの子孫であり、中央アジアからの侵略者バーブルであった。
ナーナクとバーブルの接点
一方ムガル王朝の創始者で、ナーナクにとって残忍な侵略者であったバールとはいかなる人物であったのか。その生い立ちを
野間英二博士の研究から簡単に紹介しよう。(
バーブルの出生は、中央アジアが生んだ二大英雄であるチンギスハーンとチムールの血統継ぐものであった。特に母親のクトゥルグ・ニガール・ハニームはチンギスハーンの後裔であった。そのためにバーブルは父の所領である中央アジアのフェルガナに1483年に生を受けた。しかしチムール朝の王子として生まれたバーブルであったが、その生活は安定していたわけではない。なぜなら彼が成長したころには、チムール朝は衰退から滅亡へと向かっていたからである。そのような閉塞状態に見切りをつけて、新天地として侵略の対象になったのがインドであった。
バーブルのインドへの遠征は諸説ある者の野間博士の詳細な研究によれば1505年を皮切りに1507年、1518年、1520年1524年そして1525-26年の合計6回ほどあったとされる。その中でナーナクがその遠征軍に遭遇した可能性は、1524年の遠征か1525年の遠征ということになる。しかし、1524年のインド侵攻は現在のパキスタン北部に集中しており、ナーナクの住むパンジャブの中心地には至っていないために、バーブルの軍隊とナーナクが接したのは、1525年―6年のこととなろう。野間氏訳の『バーブルナーマ』の記述によればバーブルは「カブールからヒンドゥースターンめざしてカブールを出発したのがイスラム歴932年サファル月一日金曜日(西暦1525年11月17日)であった。
その後バーブルは1525年12月15日にラホールを陥落させる。その足で、パーニパットに進軍する。そしてパーニパットでの戦いが1526年4月20日からはじまったが、その間にバーブルがパンジャブ一帯を転戦した・おそらくこの間に、ナーナクの住むカルタルプルの近くにもバーブル軍はやってきたのであろう。バーブルの1526年の2月頃の記述には、ヒマラヤ山麓の美しい村々を急襲し、民衆を拉致し、財宝を略奪した旨の記述がある。このような掠奪と支配の遠征軍を指揮しつつ、バーブルはデリー・アグラへと転戦し、最終的にロディー王朝のイブラヒームを打ち取り、ムガル王朝の創設を宣言するに至る。しかし、その混乱は置立ちには収まらず、結果としてムガル第三代のアクバル(1542~1605)帝の偉業を待つことになる。
ナーナクのバーブル観
このようなバーブル軍の侵略に対して、前述の如くナーナクは、恐らくその末端の兵卒に関してあろうが、直接見聞きしている。そして、ようやくインドに平和をもたらしたロディー王朝の消滅と新たな支配者バーブルに対して、次のような言及を行う。
ホラサーン(khurAsAn)の支配者(khasamAn)〈であるバーブル〉は、インドを震え上がらせた。
〈創造主である〉あなたは、自らインド人に罪(を与えるのではなく、ムガル(mugAlu)を死神(jama)としてお送りになった。
中略
宝石のような国の破滅がこれらの犬(ホラさん)によってもたらされた。(『グラント・サーヒブ』274ページ)
さらに
縄が首に巻かれ、真珠の首飾りの糸は切られた。
富も若さも、今は彼らにとってあだとなった。
無慈悲な死神たち(dUTA)に(彼らを史の世界に)連れ去るように、命令が下される。
彼のご機嫌をとらなければ、人々は罪を受ける。
この時、支配者たちは彼らの楽しみや喜びを失う。
バーブルの支配(bAbaruvANI)が、宣言された時、の〈パターン族、つまりロディー王朝の〉王子たち(kuiru)は食事もとることができなかった。
中略
ムガルとパタン人(ロディー王朝)の間に死闘が繰り広げられ、刀がひりまわされる。ムガルは大砲をうちパタン人は像軍で戦う。(同296~7ページ)
このようにナーナクは、10世紀以降恒常的に繰り広げられてきた中央アジアからの侵略者と同じく侵略者であったが、今はインドの支配者となった者たちとの戦闘を表現している。
ここには、庶民の力ではどうにもならない軍隊同士の熾烈な戦いとそれによって引き起こされる惨状への深い悲しみと、さらにそのような苦しみを体験せねばならないわが身の不幸を、神の罰として受け入れようとするナーナクの姿がある。
しかし、繰り返される戦闘と侵略、同時に彼らがもたらす新しい文化・文明は、結果としてインドに新しい文化・文明形態をもたらすのである。特に、ムガル王朝のように長期に安定した王朝の出現は、インドに新しいヒンドゥー・イスラム融合文明の成立をもたらしたのであった。その代償は計り知れないものであったにしろ、ムガル王朝の繁栄によってもたらされたものも、また大きかったのである。ナーナクはこのような過酷な社会状況にも屈せず、中央アジアから絶えず齎されるイスラムの侵攻や文明を本質的なレヴェルにおいて受け入れ、両者の融合を試みたのである。
ナーナクの目指したもの
バーブルによって引き起こされた新たな混乱と、それに伴うナーナクは独自の神秘体験と前述のような長い巡礼を通じて練り上げた思想によって独自の宗教観を完成させたそれが、神は唯一にして、真実を名とする。姿なく、遍在するという言葉に凝縮されている。彼は教条主義的で硬直したヒンドゥ―・イスラム両教の宗教解釈を離れて、既存のヒンドゥー教やイスラムの形態を非難し、両教の究極的一致を主張する。
パンディットは何も知らない。聖典に書いてあるのに、・・・・・
真のムスリムと呼ばれるのは難しい(musakalu)。真にムスリムと呼ばれるためには、唯一者(muhAva)を信仰し、富を捨て、自我を燃やす尽くすことが必要である。真のムスリムは預言者を信仰し、生(jIvan’a)死(marun’a)への疑念を持たぬ人、神の意志(rajAi)に服従し、創造神(kartA)を拝せば、自我はおのずと打ち砕かれる。Guru Gurnth SAhibu p.14
このようにナーナクは唯一なる神を強調し、それへの帰依を強調することで、宗教的差異を超える一体性を強調する。そのことで、日常生活レベルにおいて繰り広げられた宗教的な差異を発端とする対立や抗争の原因を超えることができると考えた。
つまり、ナーナクが目指した理想社会は、ナーナクの前に繰り広げられるヒンドゥ―・イスラムの宗教的対立、あるいはそれを口実として繰り広げられる為政者の抗争に対する宗教者としての良心の叫びであり、警告でもあった。ナーナクは、これらの宗教対立に対して、つまり異なる価値の対立に対して、インド思想特有の融合思想、つまりウパニシャッド的な思想で、これらの対立を乗り越えようとした。そしてそれは、インドにおいて涵養されたイスラム・神秘主義思想との共通性の発見あるいは協調思想でもあった。ナーナクにおいては、現前の過酷な現実の背後にある真実存在、つまり神の名においてイスラムの存在徒の融和と共存が可能であると主張しているのである。ここにナーナク思想の独自性、そして強靭さと其れを生み出すインド思想の伝統、さらにはイスラム神秘主義思想との共通性が見いだせる。歴史的にみても、中央アジアからの侵入者が齎す混乱は、インド社会に置いては、ウパニシャッド的な思想によって融和・統合されてきた歴史がある。(24)
さらにナーナクが他の宗教者と一線を画する存在として注目できるのは、彼が単なる抽象的な宗教理念を述べる神学者ではなく、実際に自らの理想を社会に実現しようとする社会改革者であった点である。
だからこそナーナクは、教条的な抽象的な教理解釈による協議論争やそれによって引き起こされる不毛とも言える宗教紛争から遠く身を置き、語るプルという小さな村において彼の目指す理想的生活を行実践したのである。彼の現実主義思想のゆえに彼は、実生活を重視し、それ故に他者への奉仕や協力を重視した。その究極の言葉が「真理は尊い、しかし、真理に根ざした行いはさらに尊い」(GGS.p.8)あるいは「心の純粋な(hirudA sudhu)グルの真の弟子(gurumukhi)の奉仕(seva)は、神に受け入れらる(thAi)」(ibid.p.28)というスタンスである。このことで、修道的な宗教にありがち他者への無関心を戒め、他者への奉仕(sewa)も修行の一部である、と教える。
だからこそナーナクは、個々人の行為の発現の場としての共同体(san’gat)の存在を重要する。つまりナーナクの教の根本は、観念的信仰を現実の行為で表現する、つまり倫理的な行為の重視というプラグマチックな者となる。この点をナーナクの後継者でシク教団第5代のグル・アルジャン(1563-1606) は、「真理の集団(sAch sn’ghati)≪シク教団≫おいては、人間の心は清らかNirmai となり、死の連鎖( jam kI dhAma)から切り離される」(GGS.p.44)表現している。
さらに彼はこの共同体が何故そのような力を持ち得るのかについて、サンガトの構成員は、神を宿すものとして、互いに尊い存在であるが故に、彼への奉仕は神に奉仕するとみなされ、尊いものとされると教えている。
唯一なる神(ekk)は、真の友達であり、母であり、父である。
我が魂(jIu)と肉体(pin’d’A)をお与えくださった唯一なる神(ekk)である。
唯一なる神(ekk)は家にあって、外(bAhari)になく、彼自身あらゆる
処に遍在する。GGS.p.45
しかも、この引用が示すようにシク教の教えでは、神はヒンドゥーの神々も、イスラムの神も、実は真実の神の多面的な側面を見ているに過ぎず、本当の神は唯一でありしかも、目に見える様な形もなく、偏在する神であるとするのである。ナーナクは、このように現実の世界の多様性を認めつつ、その背後にある一者に着目することで、ウパニシャッド的な思想を基礎に、現実の対立を超える融和思想を人々に広めていった。その教えが、やがてパンジャブ一帯のジャット農民などに受け入れられて、シク教団として成長してゆく。
バーブルが創設したムガル王朝は、その後インド社会に長く君臨し、インド史には例外的な長期安定社会を実現させ、他のイスラム諸国にはない非イスラム教との平和的な共存社会を実現した。一方、ナーナクによって開かれたシク教は、同じようにヒンドゥ―・イスラムの差異を超えた新しい宗教のあり方を唱えて、パンジャブ一帯に大きな勢力を張った。偶然とはいえ近世以降のインド社会に大きな影響を持った二人が、パンジャブにおいて遭遇したという事実は、歴史の事実として興味深い。
まとめ
以上簡単に、ナーナクの存在を中心としながらも、中央アジアからのインド社会への文化的文明的衝撃の一端を紹介した。そして、歴史的に中央アジアからの侵略者により掠奪と破壊、さらには過酷な支配にさらされながらも、ヒンドゥー側も、またイスラム側も互いに他者の存在を認め合う関係を作り上げ、豊かなインド文化・文明を形成していった。特に、ナーナクの様なインド庶民は、イスラムの過酷な支配に対して、宗教的な敵意を持つのではなく、それを自らの罪として受け入れ、これを乗り越えてゆこうとする強靭なしかも、しなやかな思想を展開したという点は、インド思想の伝統であるウパニシャッド思想影響であろう。インドの歴史は常に、このような異質なるもののとの融和・統合の歴史であり、其の異質なるものの多くが、中央アジア経由でもたらされたという点で、中央アジアの存在は、インド文明の展開のダイナミズムを誘発する最大の動力因であり続けてきたと言えるのではないだろうか。
そして、その後継者として、ナーナクの理想を現実社会において実現しようと奮闘したのが、第三代グルのアマルダスその人であった。
シク教思想とその展開
以上のような歴史的、宗教的な流れの中にシク教は生まれたのである。以下においては、このシク教の展開を具体的に論いることとなる。但し、シク教の創始者ナーナクの思想に関しては、既に報告者は発表しているので、以下に置いてはナーナクからアマルダスに焦点を絞り検討する。
ナーナクからアマルダスへ
さて、アショーカ王によって推進された異なる価値観を持つ者との相利共生型融和思想は、その後どのような展開をみたのであろうか?その直接の後継思想は、仏教の発展的な展開である大乗仏教出る、という事が出来るであろう。この大乗仏教の特徴は、アショーカ王時代の仏教、いわゆる原始仏教あるいは根本仏教
展開して、正統仏教ともいえる上座部仏教である。しかし、この仏教は、インド的な要素が強く、思想的な普遍性ハモっていたが、現実的な思想や、その実践として生活規範などにおいてインド的価値観が強く、他地域ヘの展開にはかなりの難点があった。その点をクリアーしたのがいわゆる大乗仏教と呼ばれる仏教である。
この大乗仏教は、インドと非インドの宗教を融和、統合した新しい仏教の形態である、という事が出来る。というのも、大乗仏教の隆盛した地域は、先ずインドと西方文明との窓口、つまり多様な文明形態がインド文明と出会う地域である西北インド、日本人に馴染みのある名前でいえばガンダーラ等で有り、当該地域における文明の多様性は、第二の文明の発生地域とさえ言われる程に、多様である。その多様性を思想的に融和し、宗教的に統合しようとしたのがいわゆる我々が大乗仏教と呼ぶ仏教の新しい形態である、と筆者は考えている。
つまいり大乗仏教は、インド的な宗教要素に、イランやギリシアなどの文明(宗教を格とする)を融和させ、依り普遍性の高い宗教としての仏教へと飛躍させた者と云うことが出来るであろう。この点に関しては、先行研究も少なくなく、本小論では指摘にとどめる。
本小論では、更に大乗仏教の後に、同様の地域において生まれた新しい普遍思想としてのシク教の思想とその教団に関して、簡単に検討する。というのも、時代こそ1500年の差があるが、シク教は大乗仏教の最初期の隆盛地(派生に関しては異説があり定かではないが、その最初期の隆盛地に関しては、西北インドであり、それは今日のパンジャブであり、カシミールである。そして、シク教の発生と隆盛も、このパンジャブとカシミールにまたがった地域である。
これは決して偶然のことではない、と文明論的には云うことが出来る。つまり、パンジャブという地域は、ヒンドゥークシュ山脈とシュレイマン山脈を境としてペルアヤや中東地域の文明と隔絶され、僅かにカイバルなどの少数の峠と繋がっているのである。
故に、この峠を通じて新しい文明や異民族がインド亜大陸に流入し、またインド大陸から中央アジアやペルシア方面に流出したのである。そして、この幾つかの峠を中心に文明の交流がなされ、文明の融合が繰り返されてきたのである。このような状況の中で、16世紀から17世紀に欠けて生まれたのシク教である。このシク教は、融合の当事者は仏教とギリシアではなく、ヒンドゥー教を中心に仏教とイスラムとの間で行われた文明融合の結果生まれたのである。
特にシク教の場合は、融合の相手となるのが、排他的一神教であるイスラム教で有り、現実的な野心が宗教的情熱と直結する椅子アム今日であったために、その融和共生には、厳しい試練が立ちはだかっており、それは8世紀以降、当該地域がイスラムの度重なる親友と略奪、そして支配を体験したために、大乗仏教のように大きな成果として世界的な発展は出来なかった。しかし、その試みは、イスラムと非イスラムの融和共生思想、及び共生社会構築の実現出あり、またその可能性を世界に知らしめるものであった。その意味で、シク教には大乗仏教との共通性が、思想的にもまた文明論的にも見いだせる。
このシク教の思想の提唱者は、初代グルであるナーナクであるが、ナーナクのこのヒンドゥ-・イスラム融和思想の実現としての、理想郷の建設とその拡大には、ナーナク以上に、その後継者である第3代グルのアマルダスの存在が不可欠である。
つまり、ナーナクの理想を現実社会において実現する為に、アマルダス在位(1151~74:生誕は1479)の存在は非常に大きかったのである。それは恰も仏教におけるブッダとアショーカ王の関係と言い得るのではないだろうか。
アマルダスの社会的功績
アマルダスに関しては、日本では殆ど知られていない。また、彼の人生に関しても殆ど知られていない。それは、シク教研究に於いても然りである。というのも、彼は九十五才という中世印度というより現在でも非常に長命であって、シク教教団の基礎を築いたが、しかし、その入信は六十才で前後であり、それまでの人生に関しては。殆ど記録がない。つまり、それまでの彼の人生は極普通の庶民であった、とされる。ただ、自らはシヴァ教徒であり、しばしばパンジャブを通過して、カシミールに巡礼したといわれている。その巡礼の途中に第二代グルのアンガド(1539~1552)のシク教コロニーが有り、彼は六十才を過ぎてからアンガドに師事し、十数年仕え、第3代グルを継承した。その後の活躍は、シク教団の基礎を築くものであった。
彼の業績の中で現代的な意味で特記すべきものは、女性の地位向上を明確に、教団の中で組織化したことである。特にイスラム教やその文化の影響の強かったパンジャブにおいて、その主要な生活スタイルであるパルダー(女性隔離)制度を否定し、現代的に云えば男女同権を主張した。それは社会的のみならず、宗教的に実行され、シク教団に於いては女性の宗教指導者の存在が認められた。更に、同様な女性差別の典型であるヒンドゥー教のサティー(妻殉死:夫が無くなり寡婦となった妻を夫の遺骸と共に荼毘に付す。つまり焼き殺す風習。イスラム教徒の侵略以前は、夫婦愛の比喩的表現と見做されていた。しかし、イスラムの侵入を期に、サティーは盛んとなった。特に、パンジャブはじめ中インド一体のイスラム教徒との関わりが強い地域では、宗教的な相違を強調する為に行われた。というのも、イスラム教では離婚・再婚は極普通のことであった。ところが、ヒンドゥー教では、夫婦愛を強調し、女性の純粋性を賛美し、イスラム文化との相違として誇った。そのために、寡婦はサティーされたわけである。
しかし、現実は寡婦という社会的な不安定要因を美名のもとに排除するということであったとされる。一方、妻を失った夫は、サティーされることはなく、再婚はふつうであった。この矛盾をアマルダスは否定し、サティー禁止、再婚の奨励をシク教徒に定めた。
更にアマルダスは、シク教団の宗教義務としてランガル(施食堂、自由食堂制度)を定めた。このランガルの制度は、元々インドの布施の習慣と、イスラムの施食の習慣を基礎としているが、これらの対象が宗教的に限定されているのに対して、如何なる宗教、階級にも開かれた施食である、という点が大きく異なる。この制度は、現在でもシク教団の宗教的な義務として、世界中で行われており、シク教のフリーキッチンとして、つとに有名である。ランガルに必要な膨大な経費は、全てシク教徒の寄付である。
シク教教団がこのような事業を展開出来るのは、教団組織が確立されているからである。シク教教団の維持には、ナーナクの時代は共同生活であり、自給自足であった故に大きなもんだとならなかったが、アマルダス時代には、社会背景の異なる多くの信徒が集まり、そ統率は組織化しなければならなかった。そこで、アマルダスはムガル王朝政府の行政組織とされるミシュルを模倣し、22のマンジュ-(manjis).を定めた。このマンジューでは、教団の維持費(一種の宗教税)が、徴収され、また後にシク教団の聖地となるアムリッサルのハリマンデル(通称ゴールデン・テンプル)建設や、その他の寺院(グルドワラ)建設に役立てられた。
また、彼は、ナーナクの宗教的な理想を現実社会に実現するために、積極的に説教し、多くの信者を獲得した。彼の教えの基本は、ナーナク思想をより具体的、且つ分かりやすく展開したことである。
アマルダスの思想的特徴
アマルダスの思想的特長は、ナーナク思想をより具体的に展開したことである。つまり、神の前の平等、つまり宗教的な平等を、男女平等に展開し、あらゆる人間に食事を提供し、時には衣服や宿泊施設まで提供する。アマルダスはこのようにナーナクの理想を小さいながらもパンジャブの地において実現したのである。それはナーナク以来の人間の平等と共働生活による思想社会の実現を具体化した社会存在であった。
このアマルダスの思想は、我々は、全ての人を等しく尊重し、尊敬の心でもって自由食堂において接待しなければならない。なぜなら自由食堂への奉仕はここの信者の徳と神の恵みを増大することになるからである。しかし、それは莫大な犠牲が必要なのではなく、ほんの少しの奉仕によって生まれるnodeある。(75)という表現に表れている。
彼の全ての人間の平等であるという信念は、彼のもとを訪れたムガル朝第三代皇帝アクバル(1542~1605)との会見でも遺憾なく発揮された。ムガル帝国の若き皇帝アクバルは、アマルダスに興味を持ち彼のもとを訪れ、教団への多額の寄付を申し出、接見を求めた。しかし、アマルダスはこの権力者にランガルでの食事を条件として求めた。そこでは貴賤を問わずあらゆる人々が一同に会しており、アクバル帝もその中で食事をし、アマルダスに接見したのである。
アマルダスは時の絶対的な権力者であるアクバル帝にさえ、その宗教的な義務を履行させた、というわけである。その思想的・宗教的な信念に感服したアクバル帝も優れた為政者で有り、また宗教的実践者であった、ということができる。
何れにしてもアマルダスの教えの基本は、安定的な社会の構築であった。というのも、ナーナクからアマルダスにいたる15~6世紀の西北インドは、アクバルの祖父であるバーブルのインド侵略とその定着による社会的な混乱と、10世紀以来続いた長期的なイスラムの侵略が、最終段階に入る時期で有り、当該地域は宗教と民族、さらにはインド特有のカースト間の対立や断絶が激しい紛争屋厳しい対立、相互不信が支配しており、人々は相互に反目し、社会的反目や相互不信による社会不安は払拭されることがなかった。その一方で、当該地域はインド亜大陸と中央アジアを結ぶ経済活動の大動脈で有り、 特にパンジャブ地域は、不安定とはいえイスラム支配が定着し、宗教・政治・文化はもとより経済活動も西アジアのイスラム圏と密接な関係が築かれ、旺盛であった。そのために、当該地域に商人階層(シク教ではカットリ;katri)と呼ばれる階層が社会的にも大きな力を持っていた。同時に、パンジャブは土壌も豊かな平原地域であり徐々に安定してきたイスラム支配下で、彼らの生産力もまた社会的な地位も、彼らの財力の増大と共に向上していった。
そのような社会経済的な変化を背景に、新しい宗教が生まれる機運が調っていた。他の機会に触れたが、マウルヤ王朝以来の政治的統一をもたらしたムガル王朝の成立時と、シク教教団の成立発展は、ほぼ対応するのである。特に、ムガル王朝の実質的な完成車であるアクバル帝( )とシク教のアマルダスは時代的にも対応し、実際に交流もあったのである。
特に、アマルダスの在位時代になると、アクバル帝の支配も安定し、イスラム教徒の支配下とはいえ、彼の思想的な背景もあるが、政治的な安定に加え、文化的、さらには宗教的な共生関係への関心や要求も徐々に意識されていた。(*~~)
そのような中でのナーナクからアマルダスへと3代のグル達の思想、宗教活動が展開されたのである。
シク教教団(グル・サンガ;後にはカルサ)を支えるジャットと並ぶ勢力となる。
アマルダスの出現の背景
+
シク教の教えの特徴は、、ヒンドゥー教、特に庶民に信仰が行き届いていたシヴァ信仰やバクティ信仰を基礎に、地理的、歴史的な経緯によりイスラムとの共生、それも積極的な共存の未知を歩まざるを得なかったという背景により説明することが出来る。既にインド思想とインド・イスラムの思想的な流れを概観したが、これら異なる系統の宗教とその思想が、シク教という小規模ではあるが新しい宗教教団によって融和統合の道が開かれたのである。
そして、思想的な基礎を築いたのがシク教の開祖ナーナクで有り、それを受け継ぎ発展の基礎を作ったのが二代目グルのアンガドで有り、教団としての独立性の基礎を確立し、実際にシク教団の拡大路線を確立したのが第三代グルのアマルダスである。 彼の思想的な特徴は、ナーナクの理想主義的な思想を、更に現実社会において展開した点にある。具体的には、より一般的な体臭に向けて分かりやすく、しかも具体的な表現を用いてこれを展開した。そのために、彼小競り合いに巻き込まれてゆく、そしてそのたびにシク教団は、内的な組織固めと思想的な独自性の道を歩んで行くことになる。
以下においては、アマルダスの思想が最も明確に現れているとされる「ラーグ・バイロ-」『グラント・サーヒブ』からの試訳を示しつつ検討する。
アマルダスは、ナーナク同様イスラムの暴力的な支配とヒンドゥー社会の理不尽な各種の差別に対しての一種の宗教・社会改革として、シク教団を創設し、成長させていった。
彼は後に見るように、決して宗教エリートを対象とした思想展開や布教を目的としなかった。アマルダスにとって重要なことは、彼と同様に極平均亜的なインド庶民であり、イスラム教徒であった。
アマルダスにとって日々の生活に汗を流す庶民の理不尽な状況の解決こそ最重要の課題であり、目的であった。そのために、彼は宗教的な障壁を取り除く他面い、また相互に支え合う共同体の構築の為に、無料の施食制度(ランガ)を作り、これをシク教の思想的な特徴を象徴するものとしたのである。
このランガルは現在世界中に伝播しているシク教徒の間で実践されている。報告者も、35年以上前に、アムリッサルのハリマンデルでほぼ一年間に亘りセーワ(奉仕)を受けた。つまり、今でもアマルダスの精神が、シク教の中心的な核として生きているのである。
シク教団への道
弾圧と独立
ナーナクによるカルタルプルでの理想郷団の創設は、シク教教団の原点であることは事実であるが、現代に続くシク教団(sanght)の基礎を確立し、更にヒンドゥー教段でもなく、またイスラムのウンマからも独立した集団としてのシク教ガンガの設立は、アマルダスの功績である。その象徴的事例は、アマルダスが現在のシク教団の中心で有り、再考の聖所であるハリマンデアル、通称ゴールデンテンプルに、シク教団の根拠地と定めたことである。
というのも、アマルダスの時代になるとシク教団は、教団組織も確立し、また独自の宗教儀礼や活動を行うことにより、特に周辺地域のヒンドゥー教社会から排斥される事例が惹起したからである。
既にしばしば紹介したように、アマルダスは、人間の平等を教えの中心に置くナーナク以来の伝統に、さらに女性の地位の保全や向上を定め、特に女性を亡き夫と共に荼毘に付すサティーの禁止、さらには寡婦の再婚の奨励など、当時のヒンドゥー教社会の宗教的な象徴行為を否定したのである。更に、身近なところでは、ヒンドゥー教の一派であるヴィシュヌ派、当時ヴィシュヌ派はインド北部一帯に大きな勢力を持ち、その熱心な信徒の中には、自ら料理した食事以外は口にしない、というような厳しい戒律を守る者が少なくなかった。アマルダスは一種の宗教改革者でも有り、このような習慣に強く反対した宗教指導者であった。アマルダスが、確立したランガル制度は、食餌規定が厳しいヴィシュヌ派の習慣の否定、ということでもあった。
しかし、これらの宗教的な独自性の確立は、一方で周辺社会との軋轢を生み出した。特に、シク教団が大きくなり纏まった土地の取得が不可欠となった時に、その問題は具現化した。つまり、シク独自の社会芦生団形成のためのいわばシンボルとしての聖地の取得においての問題である。土地の招集者あるいは、その所属する社会の腸であるバラモンやカットリ階級の指導者は、アマルダスの教えが、ヒンドゥー教を侮辱しているとして、また土地取得に絡み不正をはたらいているとして聖不二提訴するのである。
この時、彼らは「カーストの否定、聖なる文字であるサンスクリットの廃止」などシク教の主張が、ヒンドゥー教の侮辱であると歌えたのである。
その裁判は、皇帝アクバルの
独自の文字の創設とその意義
ここで我々は、なぜサンスクリット語をやめて民衆の言葉であるパンジャビー語を用いて宗教的な教えを説くということが、ヒンドゥー教の伝統をそこねることになるのか、まあそうすることがなぜシク教の独立と関係があるのか、について検討する必要がある。
記述のように、サンスクリット語を聖なる言葉、宗教原語としてきたヒンドゥー教を基礎としつつも、全く宗教的な背景を異にするイスラム教とその文化に深影響を受けている。故に、更に、シク教徒の多くがカットリやジャットという庶民階層で占められており、サンスクリットを自在に操りその権威を主張できる宗教指導者階級出あるバラモンの存在が殆ど考慮されない社会であった。そのような環境に於いてシク教は、独自の言葉で教えを語り又記録するという宗教的な独立を、言葉の独立と重ね合わせたのである。
その点で以下のようなエピソードが伝わっている。
アマルダスがヒンドゥー教の聖地ハリドワルヘの巡礼中、彼は居合わせたバラモンと以下のような議論を交した。
バラモンが、何故あなたは聖なる言葉のサンスクリット語で話さないで、パンジャビー語のような俗語ではなすのか?
アマルダスは、確かに、灌漑用水の水は素晴らしいですが、しかし、限られた土地にしか引き込めません。しかし、雨水は全ての田畑を潤します。ですから、シク教のグル(宗教指導者)は、グルキ文字を用いて、カーストや社会階層、さらには男女の区別なく、シク教徒の文字であるグルムキが読める全ての人の心(という畑)を潤すことを目指すのです。
バラモンが、しかし、「雨水は、既に地上に十分供給されいるのではないですか。」と問うと
アマルダスはあなたは雨水は、地上に溢れているというが、しかし、地上に雨水は全く足りていない。ただ、雨雲の下に降るだけだ。
このように、特定の人や集団にだけ理解される、つまり宗教的な利益をももたらすサンスクリト語は、シク教が目指す宗教の言葉としては不向きである、という主張である。
更に、バラモンが宗教的な教えは、術の人間には必要はない。特に女性やシュードラなどの低いカーストの人間には不要である。
アマルダスは人間の性やカースト、そして社会的な地位などの差異は、確かにありますがそれをお作りになったのは神ではありませんか。そして、我々は輪廻という多くの生と死を繰り返しているのです。そこにどのような差異があるのでしょうか?全ては神の世界の内にあるのです。そして、その真実を知ることはあらゆる人に必要なのです。全ての人に等しくしらせる必要があるのです。故に、民衆の言葉であるパンジャビーで、神の真実(意志)を語るのです。
真実の神の教えは、グルの言葉に表れる。我々はグルの言葉で、救われる。
このような議論がなされ、多くの民衆がシク教の教えに共感し、シク教へと改宗してゆ
くのである。
さて、ここで、名瀬市苦境は、独自の文字を持とうとしたのか、という点にを検討してみよう。
周知のように、ヒンドゥー教系の宗教では、独自の文字を持たなかった。彼らは、文字による記録という概念を持たず、語りの伝承により、極めて性格に宗教性点を継承してきた。しかし、正確には不明であるが、紀元前数世紀には、アラム語系の文字を西方から輸入し、現実世界の記録などに用いていたようである。その最も実証可能なものは、アショーカ王の勅令であり、紀元前3世紀である。
更に宗教分野では、宗教的に独立を果たした仏教がサンスクリットではなく俗語であるパーリ語とその文字で表したのが、確かな事例である。ではなぜ、仏教は独自のサンスクリットではなく、パーリ語によって教えを説いたのであろうか?また、なぜ、仏教の改革派である大乗仏教では、あえて仏教の伝統を否定して、ヒンドゥー教の聖なる言葉であるサンスクリット語に先祖返りしたのであろうか?実は、シク教が独自の文字や言葉により自らの宗教教理の独立を考えたことは、宗教の独立性を考える上で重要である。
この点は、仏教の教団独立の手法との共通点が見いだせるである。
つまり、バラモン教の禍一家右派的存在として生まれた仏教、少なくとも仏教教団が拡大して行くにつれて仏教教団への批判や弾圧は強くなる。この時に妥協すれば仏教は一バラモン教の宗教運動として吸収されてし待ったであろう。しかし、仏教は独自の教団を形成史、宗教的な独立を目指す方向に発展してゆく、そのために、あるいはそれ故にか、バラモン教の宗教的な権威に依拠しない、民衆の宗教としての自覚としてパーリ語による教えお説くことを選択肢と云うことが出来よう。しかし、この点は、従来余り仏教学の世界では問題にされなかったし、シク教においても今後の問題である。
アマルダスの試訳
以下においては、アマルダスの思想が最も簡潔に表されているとされる聖典『グラント・サーヒブ』(1128ページ~11``)に所蔵の「ラグ・バイルロー」から抜粋して彼の思想の特徴を検討する。
唯一の神あるのみ。真のグル(サッチグル)の恵みにより、神は理解される。
誰も自らのカーストを誇ってはならない。
真実の神(ブラフマー神)を知るものだけがブラフマンである。
無知なるもの達よ、カーストを誇ってはならない。カースト誇ることは、罪を増すだけである。
人々は四つのカーストがあるという。しかし、全ては神の意志の表れである。
この世界は、一塊の土から(神によって)造られた。
そして最後に人間が、その世界に造られた。
全ての人間は、五つの要素が、合わさって造られている。
誰も一つとして欠くものはないし、また一つとして多いものはない。(全ては平等に
造られた。)
ナーナクは仰った。この人間の魂は、人々の行いでけがされる。真実のグルの下でしか、解放は得られない。
ヨーガ行者、在家者、知識階級、宗教者、これら全ての人々は、自惚れの闇に寝入っている。彼らは煩悩の富に酔いしれている。(グルの教えに)目覚めたもののみ、
救われる。
真のグルの教えに従うもののみ、救いはある。真のグルの教えに従う者のみ、五つ悪を製することが出来る。
彼は、真実を知り救いに目覚めた者、彼は迷いを捨て、他を傷つけないもの、彼こそ唯一の神の教えに目覚めた者、他者にこびへつらわす、真実に目覚めた者、四つのカーストの則悪から離れた者、彼は生と死から解放される。
ナーナクは云う。真実の知恵に目覚めるとは、病んだ目に目薬をさすようなものである。
神への信心を持つ者は、神の祝福を得て、その恵みを得る。不平を宿す者よ。この世の全ては神の意志の表れで有り、神の意志に即している。この世は神の現れである。神は、この世を即座に破壊し、即座に再生する。
グルのお恵みにより、私は最高の恵みを得ることが出来る。
ナーナクは云う。神はこの世の破壊者で有り、創造者である。
人々よ、迷いの世界に止まってはならない。
私は神の花嫁。私の婿は創造主の神。
神は彼の飾りとして私をお作りになった。それが、神の意志のであり、私は神と共にある。私の身も心も神と共にある。どうして他に心を向けられようか。神は全てにおわします。
沈黙の行にふけるヨーガ行者は、未だに迷いから覚めていない。沈黙こそが彼の迷い(ドゥビヤ)である。彼の迷いを鎮めるならば、彼は神と共にある。
グルの導きに従うものは、真実を知る(悟る)ものである。
本質に導かれる者は、真実を知る(悟る)ものである。
唯一の神を知る者は、真実を知る(悟る)ものである。
心に、神を思う者は、彼は神にまみえ、神の恩寵を得る。
神の御心で全てが生まれ、神の御心で全ては調和する。
おお、神よこの世はあなたによって維持される。
この世の破壊者である神は、瞬時に破壊し、再び創造する。
神の愛により、神はこの世を造る。
神の恩寵により、私は再興の恵みを得る。
ナーナクは云う、神はこの世の破壊者で有り、再生者である。
故に、迷いの世界に止まるな。
私は花嫁で有り、花婿は神。
彼がそのようにお作りになった故に、私は神に従う。
神が臨むとき、私は神と共にある。
私の身も心も神に捧げる。
どうして他の者に捧げられようか、神は全てに親鳥になる。
グルの恵みゆでに、心に神を宿すことが出来る。
五つの歌を歌うとき、神にまみえることが出来る。
ナーナクは云う。神にまみえる者は、神と一つになるものである。
瞑想する聖者は、未だ迷いに止なる沈黙こそ、迷いである。彼は神を持たない。
神の御心を求めよ。さすれば九つの宝を得る。
創造主である神は。この世を愛するが故に、この世をお作りなる。
エゴのよってこの世に関わる者、彼は迷の世界に止まる。
この心から、全ての肉体と迷いの心が生まれる(輪廻が始まる)。
心からの瞑想する者のみ、神と一体となる。
グルの導きで、良い行いをする者のみ、神の恵みを得る。
迷いの心に止まる者は、神の心を知ることがない。
汚れのない心、執着のない心に神は宿る。
ナーナクは云う。この道理を知る者、彼は神と一つとなる。
救いの道は、神の導きのみ。
それは、迷いの海の渡し船。
グルの導きで瞑想する者は、神の傍らに立つ。
汚れに満ちた瞑想では、この海は渡れない。グルの導きのみ
迷いの海を渡る。
神を真実者は、神のよって音調を得る。ハリ、ハリ(クリシュナ)は、音調への道
グルの導きで、神を知り、神を心に宿す。
一切の者は、神により救われている。
神に救われている者は、神に祝福された者。
グルによって、神の恩寵は示される。
神を愛する者は、神の御名を愛す。
彼らは自らと友を救う。
神の導きなき者は、地獄に向かう。
彼らには悲しみと苦しみのみある。
神の恵みはサンカ(聖者の一種)や彼らの友をも救う。
彼らは神を熱烈に愛する人々。
我らに恵みをもたらす神よ、グルの導きにより私はあなたの皆を呼び続ける。
神にまみえたグルの導きで神への心からの愛を得る。
神は自らの御座所にまします。グルの導きで、神は、我らの心に止まる。
神は全てをご存じ。
神の御名を心にとどめよ。ナーナク。
暗黒時代は、神の名を身勝手に呼ぶ。
グルの恵みがなければ、汚れに被われる。
神の祝福を得ることは難しい。
只、グルのお導きによる。
一人で神を求める者は、救われない。
それは、グルの導きのみ可能となる。
神の意志を受け入れた者のみ、
グルの言葉を信じる者は、神の救いの証しを得る。
全能の神に仕えは、善の中身の力を得る。
グルの導きで神の愛生えられる。
鉄の時代に在っては、人々は置くの儀式に縛られる。
不幸なこの時期には、儀礼は無意味である。
この闇の時代に神の名(ラーム:を称えることは)最も有益である。
グルの教え(グルムキ)により、一葉真実を得る。
真の救いを求める者に神の恵みはもたらされる。
純粋な人は、いつも神を念じている。
グルの導きで、神の教えに忠実な者は、神の救いを得る。
暗闇の時代こそ、信仰の種をまく時である。
手当たり次第に、神を拝む時(儀礼をする)ではない。
グルの恵みにより、心に神は宿る。
バイロ
神は唯一にして、グルの導きによって、神は知られる。
世捨て人は、二元論の迷いに陥っている。煩悩の炎に焼かれている。
彼らは志と再生を繰り返し、真に休まるところがない。彼らの命はむなしく潰える。
私の神への愛は、神の恵みをもたらす。
この世をお作りになった神よ。慢心から生まれる病は、神の導き以外には、も
たらされない。
聖者達は、聖典を読が、神の導き無しには、真の意味を理解できない。
全ての人々は、欲望とこの世への執着により神を忘れる。
導きの師よ。あなたの心と、人々の心を神に結びつけよ。彼らの心に神の恵み
と、彼らの心に平安(ムク)が得られる。
グルの教えを信づる者は、第四段階に止まる。彼らは在家のままで、貴いグル
の導きにより、彼らは在家に有りながら、煩悩(アープ)を克服する。
ブラフマン、ビシュヌ、シヴァをお作りになった唯一の神は、信徒等の奉仕を喜ぶ。
神は、唯一の真実野上、彼は生も死も超える。
利己主義は二元論の病である。この世に拘る病である。
真実を知ること、それは神の心であるグルの言葉に従うことで、取り除くことが出来る。
神と神の言葉であるグルの教えに従うことで、病は取り除かれる。彼らは神に祝福され、病は取り除かれる。
この世に執着する者全てに、死はやってくる。彼らは死の運搬人、しかし、シクの教えを心に持ち従う者に、シノ神は近づけない。
グルを通じて神の教えを知らぬ者、どうして真実の世界にたどり着けようか。
彼はグルの教えに気づかず、むなしく死に至る。
神に祝福されたナーナクの言葉で、彼らは神に結びつく。
彼らは、神の恩寵を望む者は、グルの教えにより平和を獲得する。
人々は、痛みの中で生まれ、痛みの中で罰せられ、痛みの中で生きる。
彼は生まれる前からとらわれており、糞尿の中で苦しむ。
人々の命を台無しにする忌まわしい利己主義。彼らは神の教えもグルの導きも否定する。
グルの教えは全ての病を根こそぎ癒やす。
グルの教えのみ、神の真実に導く。
神の現し身であるグルの教えに従う者は、救いを得る。
グルにまみえたものは、神の恩寵を得る。真実の生活は、最も貴い。
憂い亡き者とは、神に従い、神を愛し、グルの言葉に従う者。
神の導きに従う者が汚れを得ても、真実の教えにより、解消出来る。
神の教えを信じ、心に神を宿す者こそ、真実の人。日夜身も心も神に捧げ生活する者は、悲しみに襲われることがない。
神に仕えよ、神に仕えよ、神に仕える(信仰する)事以外に、救いはない。
神の意志に従うことで、恵みはもたらされる。
無心否者は、富を失いつつも、利益を求める。どうして利益を得られよう。
死の神は彼らのすようにあり、彼らは全てを失う。
欲に駆られた傲慢な者、彼らは日夜歩き回り、彼らの煩悩の病は癒えることはない。
聖典を読んでも、彼らは争い、益々混乱に陥り、神の救いから離れてゆく。
グルの教えにより、最高の真実に目覚め、神の恩寵を得る。
グルの教えに従う者は、裁きの法廷において祝福を得る。
利己主義者は望みを失う。彼らは神の愛を失う。
空気では腹は充たされない。渇望の火が彼を焼き尽くす。
幸福とは、神の本質を知ること、神の教えに従い二元論から自由になること。
神の妙薬を得た者は幸福である。心に神の愛が溢れ、二元論から自由となり、充た
される。
この世の創造主で有り超越者である神は、人々と仕事を結びつけた。(全ての人に死後を与えた。)
グルの教えは真実の神の知恵と真実の神の光が一つになったもの
神は真実中の真実
全てのものは、神から生まれた。
ナーナクは云う、真実の教えが救いに繋がると、神は示された。
神の境地、神の教えに充たされた人間は幸福の中にある。鉄の境地、彼らは神の教えに充たされず、邪鬼となる。
銀の境地、銅の境地、煩悩は沈黙する。
暗黒の境地、人々は神の恵みを神への帰依で獲得する。
全ての境地において、純粋な人は、神が唯一であること、神ヘの帰依以外にすくはないことを知る。
グルの教えに帰依する者の心に、神は恵みとして現れる。
神を信じきる者は、子孫共々救われる。
神は利益を与え、神の言葉は災難を焼き尽くす。
高貴な者とは、心に神を宿る者、彼の心は、神の宿りである。
神は、神の邸宅、庭園、宮殿を誤字比と共に見せられて、
神の全て最高・最善のものとして受け入れた。
グルの教えによって心に望むことは、神と一つとなる。
グルの導きで、神をしれば、その時信者は節を得る。
神の否は心の支えとなる。
グルの恵みにより私は最高の境地に至る。
神は、救いの自薦者である。
唯一の神は全てに宿る。しかし、グルの教え以外では、それを知ることは出来
ない。グルの導きより、神は現れ、そして私は日夜神を讃える。
心の平安をもたらすのは神のみ。他なら神から、心の平安はもたらされる。
真のグルへの無心の奉仕で、後悔から自由となる。
真の神に仕えものは、幸福を得、苦しみは追いつかない。
ナーナクは、神を念じて清められ、彼の心は最高の魂と一致する。
神なくしては、この世は乱れ、争いとなる。
神の救いの紋への知識のない私には、生と死が繰り返され、生と悲しみは繰り返しやってくる。
神の庇護の下にある私の魂には、神の御名は甘露である。グルの教えにより、信徒は、魂案亜海を横断できる(三途の川を渡れる、)
凡夫の心は、宗教的な装飾に迷い、彼の心は、迷いと性欲と、噴霧とおごりに満ちている。彼等の心はこの上なく激しい渇きと飢えに満ちており、彼はいずこともなくさまよい歩く。
彼は、グルの教えによって死に、そして、再び蘇り、神の救いを獲得する。
彼らのこころは、癒やしとし平安に充たされる。彼らは神を心に宿す。
ナーナクよ。神の恩寵により、かみを一心に祈る。その時人は神の恵みを一つとなる。
世俗の富と愛に溺れる者は、苦しみをえ、その苦しみに煩わされる。
飽くなき金銭を求める強欲という病は、彼の心に救う。そして彼は神への祈りを奪われる。
この世の富へのとらわれは、おぞましい。彼は、神の御名を夢にだに見ず彼への信仰を起こすこともない。
彼は畜生の如く振る舞い、神の愛を理解する事がない。愚かな行いは、彼を虚偽の世界に導く。
真実の神にまみえれば、この世の苦しみから救われる。
神を心に宿す者は、神の祝福を得る。
グルの導きにより、人々の心の迷いは消え失せる。
創造主にして、維持者である神は、自ら正しい道を示す。
ナーナク、神はグルを、神の名を称える(称名)ことにより祝福する。
私の心には、この世を造り、また維持する神がある。
誤った神への信仰は、彼を死に導く。
救いは、真の神の導きだけ。
神は常に私とある。
グルの導きに従う者は、子供でさえも救われる。しかし、そうでないものは、恐怖に駆られる。
母親は、最愛の息子を育む。
我が子の神の祝福と良き人生があるようと、
人々よ、聴きなさい、神こそ真の母親。
神の名への帰依(称名)をやめるな。グルは、この真実を示された。
プラハルド等悪魔達は、人々を迷いに導く。
裁きの場に於いて、彼らを惑わす。
しかし、裁きの場に於いてプラハルド(に従う者達)の救いの劇が始まる。
剣を手にして、偉丈夫にハルナカシュ神は云う。おまえのすくの神はどこか、
ブラハルドは、恐れおののく、すると即座に神が現れる。
ハルナカシュ神は、即座にきびすを反し、ブラハルトは救われる。
神は、プラハドに従う無辜名人々を救う。
グルの教えで、欲望に曇った心は、救われる。
心に清らかさを保つ者は、悲しみから救われる。
全ての時に、神は神を信ずる者をお救いになる。
悪魔の子孫であるプラハトは、ヒンドゥー教の教えのむなしさを知る。
グルの教えのみ、神の下に導く。
昼夜を問わず、神の名を称え、神を思い瞑想することで、迷いの世界から
救われる。
真理を得た者は、神が心に宿る。愚か者は、真の神の導きは得られない。
だから,彼らはむなしく生涯を終える。
悪しき神は、グルを誹謗し、卑しめる。
二元論を知らないプラハ土神は、神の名を諦めない、彼は他者を恐れない。
高貴な神は、信心深い人々の救い主。死の神を近づける。
神は御自ら音調と共に,グルを祝福する。
ナーナク、ハルナクシャは、きびすを返し、盲目の神は,裁きの場を知らぬ。
これは、アマルダスの教えの代表的な作品の一つである。この中で、報告者は、アマルダスの用いる神の未詳は,彼が60才を過ぎてシク教に改心するまでの知識であるバクティ信仰の影響が有り、ラームやゴーパルという名称が登場する。勿論、サット・グルというシク教独自の神明や、フーカムといういすらむ的な名称も時に用いられる。
また聖者に関しても,ヒンドウー教や仏教における宗教的完成者とされるムニが用いられる。更に,翻訳では時に神の恩寵、あるいは称名と訳したが、ラーム・ナームが問い言葉がしばしば登場する。俺は、日本仏教の唱名念仏思想に近く、時代的にもかなり禁じ姓があるという点で、面白い。勿論、唱名念仏の起源は印度に有り、特異仏教を通じて、中央アジアからに中国、日本へともたらされ、徳治に発達した麺が有賀、それにしても、神の御名を称えることが,神の恩寵であり,神への奉仕で有り、神を喜ばすことである,という発想は、法然や親鸞などとの共通性を感じて教に深い。
また、アマルダスの思想で二元論の否定と超越に関しても、重要なテーマになっている。この二元論はインド哲学的な二元論、つまりアートマンとブラフ万というような世界認識における根源的な原理を問題としているのではなく、現実的な意味での二元論の超越である。その最大な対象は、異なる宗教の超越というテーマである。既にしばしば言及したように、アマルダスにおける二元論(デュアー)は、16~7世紀のパンジャブにおける紛対立紛争の源であった。
このヒンドゥー・イスラムという二つの相異なる宗教の対立のちょうえる、あるいは解消こそ二元論のである。
この『バイロ』を読むと、アマルダスの教えの簡潔さと,時にイスラム的な唯一絶対神的な神観念があり、一方でヒンドゥー教的汎神論があり、まさにヒンドゥー・イスラム融合の姿勢が見事に反映されている。
更に、ナーナク以来お伝統でもあるが、シク教では観念的な真理を重視するのではなく、常に現実世界における神の教えの有効性、いわゆるシク教独自の宗教的な倫理的行動とその社会的価値の連動を何より重視した点が、現代に至るシク教徒の倫理観に少なからぬ影響をもたらした。
現在インドのシク教徒
さて、話は多少前後するが、シク教徒が抱える問題を理解するためにも、まず彼らの日常生活について検討しておこう。シク教はその独特の装俗で有名であるが、その人口はインドの全人口のわずか二パーセント(1400万人程度)である。また、シク教のほぼ70パーセントはパンジャブ州に集中している。このパンジャブ州のなかでも特に、ゴールデン・テンプルのあるアムリッサルは、1947年のインド・パキスタンの分離独立以後、かつての宗教都市から政治都市としても重要になってきている。
シク教の聖地であるアムリッサルには、他の地域ではほとんど儀式用になってしまった伝統的な風俗が今でも生きている。この町を歩くと手に手に剣や旧式な鉄砲などを提げたシク教徒に出会う。
それは、タクシーの運転手だったり、商店主であったり、医者であったりするが、この町での生活においては、多くのシク教徒が片時も放すことなく武器やシク教徒のシンボルたるキルパンという小刀を携帯している。彼らはキルパンを携帯することを宗教上の義務としている。そのためインド共和国憲法は、彼らがこれを携帯することを公式に認めている。
だから、ハイジャックの多い昨今も、シク教徒に限って飛行機の機内に武器(キルパン)を携帯してもよいことになっている。(もっとも最近では、本物の武器は機長預かりとして、機内ではその模造品を渡すようになったとも聞いている。)一時、インド政府がハイジャック防止のために、キルパンの機内持ち込みを禁止しようとして、大きな社会問題と化したことさえある。彼らのこの問題に対する関わり方は、一つにはキルパンが持つシンボルとしての宗教的意味、そしてシク教の歴史とそれを支えるジャット族と呼ばれる人々の長い苦闘の歴史への理解が必要である。それについては、後に触れることとする。
シク教徒の誇り
独立自尊の気風の強いシク教徒が最も誇りとしているのが、19世紀に打ち建てたシク教王国の存在である。彼らは、最後まで英国支配に対抗してインドにおける最後の独立国として、イギリスに抵抗した。このためシク教は、ヒンドゥー教の守護者という位置を与えられることとなった。しかし、シク教徒側では、このようなヒンドゥー教徒の認識を歓迎しない。シク教側は、これによってヒンドゥー教によるヒンドゥー教内のサブ・カースト化、つまりヒンドゥー教へのシク教の吸収ということを恐れているからである。なぜなら、多数派のヒンドゥー教になしくずし的に同化されれば、シク教の宗教的な自立はなくなるからである。古来、ヒンドゥー教は、多くの宗教を併呑して今日のような多目的、多元的な宗教に発展したのであるから、シク教徒の警戒も故なしとはしない。事実、インド共和国憲法の第25条の2項には「シク教と仏教・ジャイナ教はヒンドゥー教の一部とみなす」という条項がある。今日、シク教の政治団体はこの条項を改正するよう運動している。その運動の過激な発展形態の一つが、今日のパンジャブなのである。
インド・パキスタンの分離独立とシク教
英領インドと呼ばれていた地域が、正式に独立したのは1947年のことである。この時、英領インドはインド共和国と東西パキスタン(パキスタン・イスラーム共和国成立は1956年)に分かれて、それぞれ別々に独立した。その理由はよく知られているように、ヒンドゥー教とイスラム教の宗教対立であった。そしてその原因は、イギリス政府が高まる独立運動を抑えるために、ヒンドゥー・イスラーム両教の対立をことあるごとに利用したためといわれる。しかし、ここで忘れてはならないのがシク教徒の存在である。シク教徒は、かつてのパンジャブ全土を実質的に支配しており、イギリスは当初ヒンドゥー・イスラーム・シクの三つの国を作ることを考えていたという。しかし、ヒンドゥー・イスラーム両教の対立が激化し、結果的に少数派のシク教徒はヒンドゥー教側に吸収されることになってしまった。その結果、パキスタン側にはシク教徒がかつて持っていた領土の3分の2、人口の約6割が割り当てられてしまった。彼らはほとんど着のみ着のままで、インド共和国側に難民としてやってきた。その数約六百万人(三百万人との説もある)だったという。この時、パキスタン側のヒンドゥー教徒とインド側のイスラム教徒は互いに移民したが、その数たるや一千万人に達するといわれている。これほどの規模の人間が、政治的な理由で移民させられるということ自体尋常ではない。しかし、この時、多くのシク教徒は永く住み慣れた地を追われた。また、インドに帰属することを嫌ったシク教徒は、アメリカ・カナダ・香港・シンガポールなどに移住した。これがもとで、シク教が世界に広がることとなった。
さて、シク教は、インド・パキスタン分離独立というきわめて政治的な対立の犠牲によって国土の三分の二を失い、人口の六割を難民にしてしまった。はたしてシク教徒はその犠牲によって何かを得たのであろうか。
「ヒンドゥー教徒はヒンドゥー教の国家を手に入れ、イスラム教徒はパキスタンというイスラム教国家を手に入れた。しかも、元来貧しい人たちが多かった彼らは、この分離独立によって返って豊かになったものさえ多い。」ところが、「地主階級あるいは上級の商人として活躍していたシク教徒は、国を失い、財産を失った。しかも、この分離独立によって、国土も失ったのである。彼らの多くに残されたものは難民としての試練だけであった」と、シク教の歴史家が書くように、シク教にはなんらメリットはなかった。少なくとも、多くのシク教徒はこのように考えている。
この辺りの歴史が理解されていないと、今日のパンジャブ問題は、単なるシク教徒の一方的な我がままと認識されてしまう危険性がある。特に、一般の報道はこのような分析に偏り、その結果、シク教徒が悪者になってしまいがちである。彼らの感情の奥底に潜んでいるこのような不満を考慮に入れなければ、いくら彼らの行動を分析したところで、最後は過激派、あるいは狂信者という月並みなレッテルを貼っておわってしまうのである。
もっとも今日のインド人の多くは、シク教徒の歴史的な不満を理解しようとはせず、また解決しようとも考えていない。なぜなら、彼らはヒンドゥー教の利益は、ヒンドゥー教の一部であるシク教の利益だと一方的に考えているからである。ここに、インドの文化的特徴であるヒンドゥー教至上主義、ヒンドゥー・ナショナリズムの一端がうかがえる。著者は前述したように、インド文化をヒンドゥー教至上主義、いわばヒンドゥー・ナショナリズムと、アンチ・ヒンドゥー教勢力との相剋によって織りなされた巨大な模様である、と考えている。つまり、シク教をアンチ・ヒンドゥー教勢力として位置付けることにより、彼らの反政府運動も、インド文化史上の問題として一般化が可能となる。
独立後のシク教徒
独立後、シク教徒は時を移さずして、分離独立時に失った利権の回復を中央政府に要求する運動に着手した。そのためにアカリダルという政党を結成した。しかし、それを支えるシク教社会の衰退から、この運動が社会運動として力を持つには、十年ほどの準備期間を要した。やがてシク教徒の生活も安定期に入り、彼らにも漸くまとまった政治運動ができるようになった。この運動は、シク教徒が多数派を占めるパンジャブ州(パンジャブ語圏を意味する)の自治権の獲得(1966)、という形で一応の結実をみた。
もっとも、これには次のような経緯があった。シク教徒が自治権を要求し運動していた時、第一次印・巴戦争が勃発した。時の総理はガンディー女史であった。彼女は、優秀なシク教徒の軍事的協力を得るために、シク教徒の要求を受け入れた。結果的に戦いはインド側の勝利に終わった。ところが、ガンディー首相は、シク教徒との約束を棚上げしてしまったといわれている。その象徴が、インドで最も豊かな州の一つであるパンジャブ州の州政府専用の建物がなく、隣のハリアナ州の政府の建物の一角に間借りするという状況が、つい最近まで続いていたことである。このようなわけで、シク教徒からみると、当時のインド政府のシク教徒に対する対応は、決して満足のいくものではなかったのである。その後もさまざまな問題が中央政府とシク教徒の間で繰り広げられ、1972年10月12日のカリスタン独立宣言が、アメリカの「ニューヨーク・タイムズ」紙上で宣言され、インド政府を慌てさせることとなった。もっともこの宣言は海外在住のシク教徒によってなされたもので、インド国内のシク教徒にはあまり支持されなかった。ところが、ここに一人の男が出現した。それが若きカリスマ、ビンドランワレである。
若きカリスマの登場
私がこのビンドランワレという男と初めて出会ったのは、1982年の夏のことであった。ゴールデン・テンプルの聖なる沐浴場をぐるりと取り巻く廻廊を歩いていると、身の丈六尺を越す大男が何人もの取り巻きに囲まれて歩いてきた。彼らは皆それぞれに武器を持ち、辺りに気を配っていた。彼がインド政府から指名手配されていたシク教独立運動の過激派の首領であることはすぐにわかった。その時の印象は異様な目付きをした、何か狂気を漂わせている男というものであった。事実、彼の名によって多くのテロ事件が引き起こされ、実際に私が世話になった人も何人か殺された。もっとも、実際に彼がどれほどそれらの事件に関与していたかは不明である。しかし、インドのマスコミは彼をさかんに悪人扱いしていた。彼らがビンドランワレを非難すればするほど、シク教側は彼を神の如く崇めることとなった。まさに彼は宗教的カリスマの典型であった。とにかく、マスコミの異常とも思えるシク教批判は、そうでなくとも窮地に立たされていたシク教徒を過剰に刺激したことは事実である。多数派ヒンドゥー教徒の社会的・政治的圧迫に、宗教的熱情と護教精神による以外に対抗の術を持たなかったこの時期のシク教徒は、教世主あるいはヒーローを待ち望んでいたのである。その結果ビンドランワレという男が、カリスマに仕立てあげられたといってよいであろう。
私が彼に最後に会ったのは、彼が政府軍との銃撃戦で亡くなる一週間前だった。その時彼はもう完全にカリスマとして人々に崇められていた。彼の前には、インドでは珍しい百ルピー札など高額の御布施が山となっており、彼の顔を拝もうとインド各地から信者が何千人も集まってきていた。
これらの人の前で、静かにしかし力強く説法する彼には、すでにテロ組織の首領であった時のトゲトゲしさはなかった。毎日毎日何万人もの信者を前にして、彼はとうとうとシク教王国建設の必然性や、シク教信仰の重要性を説いていた。その姿は完全に宗教者のそれであった。しかし、彼の周りには武器が山と積まれ、寺の周りでは政府軍の部隊が彼を狙撃しようと待機していた。ただならぬ雰囲気がゴールデン・テンプルの周りには漂っていた。
その後の展開は前述の通りである。あの美しかったゴールデン・テンプルの建物の多くは銃撃戦で破壊され、何千もの一般人もそれと一緒に犠牲となった。
このような経過をたどって、シク教徒の復讐劇であるインデラ・ガンディー首相暗殺事件は実行されたのである。しかし、1991年現在も、シク教徒による独立運動は依然続いており、収拾の目処はたっていない。一体シク教徒はなぜこのように執拗に、独立と反政府運動に執念を燃やすのであろうか。それは、シク教の思想と歴史伝統、さらにはインド全体のそれを知らずには理解できないことである。
以上が、科学研究費を用いての研究の成果である。勿論、この報告書は、科研の研究を体系化するために、以前の研究と有機的に連続させて書き下ろした。
執筆:保坂俊司
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
