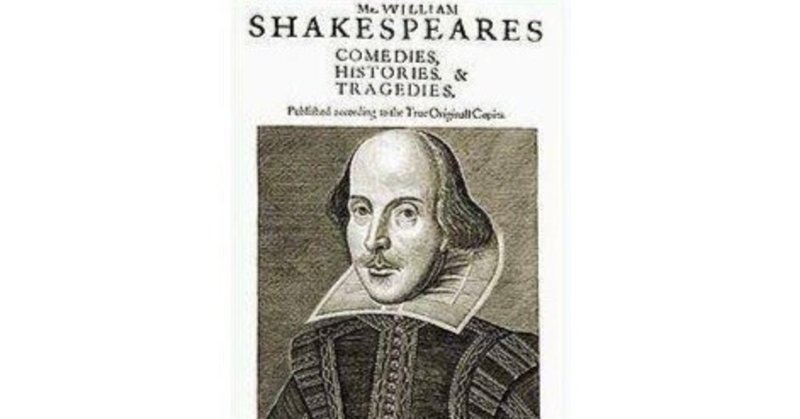
「ハムレット」読書感想文
わが町の公民館読書会があり、今回ぼくが当番で課題本を選んでその感想を話し合う司会役となる。課題本はなんと「ハムレット」だ。シェイクスピアをこの歳になるまで読んだことがなく、今年の春に友人と二人で「テンペスト」の読書会をやって戯曲に目覚めたので、今回本丸の「ハムレット」を読もうと思ったのだった。誰もが名前だけは知っているハムレットとはどういう人物なのか?意外と知られていないかと思って課題本にしたのだが、読んでみると巷に流れている優柔不断のキャラクターとは全く違う意志の強い、悪と戦う戦士の像が浮かび上がった。実際に舞台の最後でハムレットの遺体は抱きかかえられ、大砲の音とともに戦士として称えられる。ただしその戦いは陰謀を暴くために狂気を装い、真実を暴くためには狂気と道化という想像力の力を必要としたところが、シェイクスピアの劇の面目躍如たるところだ。それはまさにシェイクスピアの生きた時代が、イタリアから始まるルネサンスというヨーロッパ文芸復興(実は教会に対する革命運動)の時代だったからである。以上のような落ちで読書会ができればいいかなと思った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
先日ハムレットを読んだがその感想を読書会のメンバーの前で話したら、期待していた反応が返ってこなかったので、あれ何でなのだろうと心にしこりが残ったことがおそらくこれを書く動機になっているのだと思う。ハムレットってあまりにも有名で、シェイクスピアの劇としておそらく何万回と演じられてきているから、今更ぼくがどうこう言っても客観的に何かが残るということはありえないのだけれど、ぼくの発見が何かの刺激を産んでSNS上で誰かがハムレットを読んでみたくなるとすると、それはそれでちょっといいことじゃないかと思う。けれどもそれはぼくがハムレットを読んで得た発見がうまく文章に展開されてのことだし、発見と思っていることの価値は全く保障されないものだ。
発見というのはハムレットがヨーロッパ中世を終わらせる、ルネサンス運動のシンボル的な英雄の一人ということだ。もちろんマルティン・ルターなどが中世のキリスト教会支配を改革する歴史上の功労者ということに違いないのだけれど、ギリシャ・ローマ的な人間精神に還る芸術家の創作行為の連鎖がヨーロッパの当時の人々に与えた「教育的価値」は、革命運動と称されてもいいくらいだと思っているぼくとしては、ハムレットをその一員に加えたくてしようがなくなったのだ。シェイクスピアはハムレットに狂気と道化を演じさせて、自分の叔父が前王の父を毒殺して母を妃にするという権謀術策によって得た腐敗した支配体制を、「内側から」「悟られることなく」崩す戦術を取らせた。いわば不正に王となった叔父を不安に落とし入れ自らの延命策に逆襲されるように、ハムレットを行動させたのだった。剣の先に毒を塗って試合をさせたり、ワインに毒を入れて試合中に飲ませようとしたりした「不正」が暴かれて、衆目一致するところとなり「崩壊」を迎えることになる。シェイクスピアは復讐の正当性が衆目一致するところとならなければ、単に反逆テロにしかならないことを知っていた。また顧問官のポローニアス家(オフィーリアは娘、試合の相手のレアーティーズは息子)を自分の復讐に巻き込んでしまったことの責任を引き受けて自らも死に赴かせている。
そしてデンマーク王族はみんな死ぬことによって親族関係にあるノルウェー王国に引き継がれて、一つの時代が終わる。ハムレットはルネサンス的英雄としてぼくは描ききれているだろうか?もっと狂気を装った言葉による攻撃やら、劇中劇の俳優に語らせる戦術などを述べて論証したいところだが、とても力が及ばないとこの辺でキーボードの手を置くことにする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
