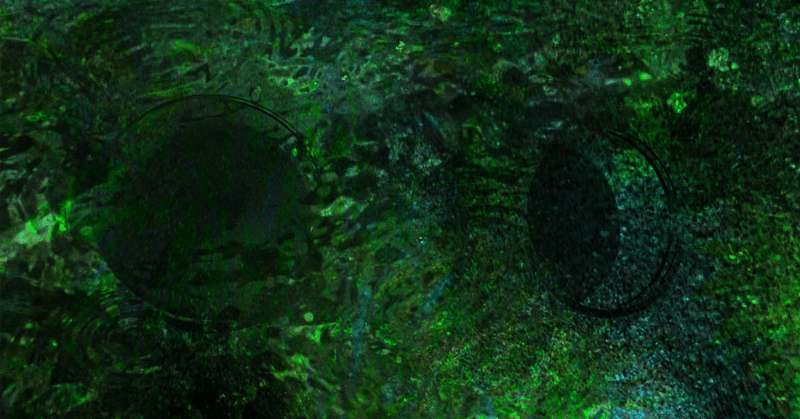
マッドパーティードブキュア 207
とりわけ暗い闇の塊とセエジの距離が縮まる。テツノは暗闇の塊が領域を広げるのを感じた。
「あぶない!」
咄嗟に、腕に実存を集めていた。テツノの腕がセエジの肩を掴む。セエジの境界を質量を持った暗闇が探るように掠めた。あと一歩、いや、半歩でも前に進んでいたら探りまわる暗闇がセエジを呑み込んでいただろう。
テツノはセエジを引き戻す。倒れ込むように下がるセエジを誰かが受け止める。老婆だ。セエジが確保されたのを感じて、テツノは暗闇に意識を向ける。
空を切った暗闇はやたらめったらにその触手を滅茶苦茶に振り回していた。その勢いは凄まじい。形を持たない暗闇のはずなのに、それは荒れ狂う奔流のように感じられる。
何も見えない。ただ気配だけだ。意思を持つかのように、あたりを探りまわるように、暗闇が蠢く。
「こいつ……生きてるでやすか!?」
「かもしれないねえ」
ズウラのとまどいの声に老婆が答える。苦々しい声色。暗闇の中で、暗闇と戦うことほど不利なことはない。どこまでが、敵の領域なのか視覚が封じられた状態で判別するのは非常に困難だ。
「でも、やるしかねえ」
マラキイが言った。ずしりと大地を踏みしめ、ぎゅっと拳を握る。
ぎらりと何かが煌く。老婆のナイフだ。戦うしかないようだ。テツノも覚悟を決めた。
「女神さんは下がってて」
小さくささやく。わずかに全身の密度を緩める。見えない敵との戦いでは、テツノの気配探知が鍵を握るだろう。
ゆっくりと慎重に感覚を伸ばす。自分の領域と暗闇の領域、その境界を探る。安全な位置、危険な位置、敵の形。探る。探る。
「え?」
テツノを掠めた暗闇の気配に声が漏れた。匂いだったのか、温もりだったのか、それとも手触りだったのか。一瞬の接触。そのときに感じたなにか。それをテツノが知っている感触だった。知りすぎている感触。戸惑いと混乱が頭の中で吹き荒れる。
だって、それは、その感触は
「メンチ?」
【つづく】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
