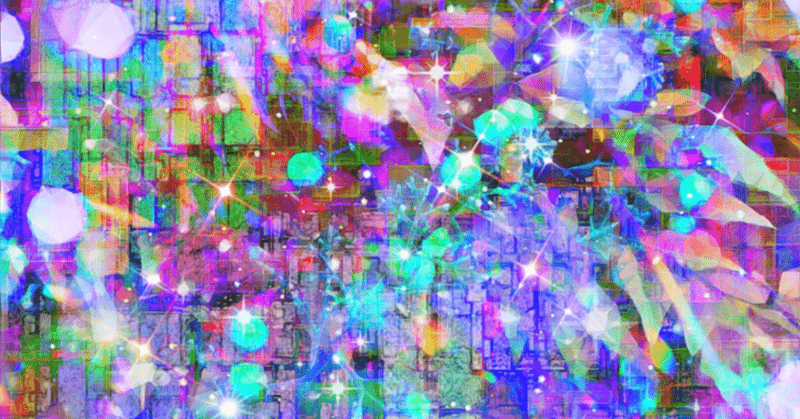
樹海ドロップ~短編小説~
たっぷりと水分を含んだ布地がふくらはぎに吸いつき、足枷のようになっている。濡れたズボンの裾から滴る雨雫。それが肌の表面を沿って流れ、靴下を重くさせるのを感じる。
足が思うように、前方へ進まない。もう歩けない。しかし、私があれを見つけないと。あの子が。私のかわいいあの子が——助からないのだ。
ふっふっ、と冷たい息の隙間から、諦めにも似た笑みが漏れた。見つかるわけないじゃない。もう30年も前の噂なのだから。だって、あの日だって、本物だったか分からないじゃない。そうして、私が無理を言ったから、お兄ちゃんはあれから——。
ズルッと濡れた草にすべり、私は仰向けにひっくり返る。地上を埋め尽くす草木や苔がクッションとなり、どうやら頭は強打しなかったみたいだ。つよく瞑った瞼に、優しくつき刺さってくる雨の糸。不思議とあたたかい。静寂をかき集めたような樹海の中。自分の息遣いすら聞こえない。もし、世界の底というのがあるならば、これほどまでに静かなのかもしれない。
【樹海に降る雨の中に〝樹海ドロップ〟というドロップがある。黄金色に輝くそれを舐めれば、どんな病や怪我でも治せるらしい】
私たちの村には、そんな噂が昔からあった。でも、学校の誰もそのドロップを見たことがないし、ただの噂だと思っていたけれど。私の祖父が昔、そのドロップを樹海で見つけ、自分の病が治ったというのだ。だから、私は今でもその〝樹海ドロップ〟の存在を信じている。
「茜、ま、待っててね……あなたの病を、わ、私が、治して、あげるから……」
仰向けのまま呟き、瞼を開ける。樹海の天井は、生い茂る樹木の先端が密集している。その隙間から、鼠色の空が少しだけ覗いている。針のように細い雨が、私の目玉めがけて落ちてくる。霧雨けむる背景の中、冷えきった手のひらに蘇る体温。感触。カランコロンと鳴るドロップの音。お兄ちゃんが好きだったあのドロップの——。
*
「もう、諦めよう! これ以上いたら、僕たちまで迷子になってしまうよ! また明日にしよう。なあ? 花梨」
「いやだっ! 今日じゃないといや! だって、次はいつ雨が降るのか分からないもん!」
私はお兄ちゃんの手を離し、樹海の中を走りだす。濡れそぼった草ですべりそうになりながらも、私は必死に樹海ドロップを探し回る。
「仕方ないなぁ……あと少しだけだよ」
お兄ちゃんのあたたかな手のひらが、私の小さな手のひらを包みこんだ。それだけで、私の心はホッとする。安心感でまるっと包まれる。
私たちはお父さんの病気を治すため、雨の日の樹海に来ていた。どうやら、治らない病気らしい。そんなものがあるのか。病気のことは私にはさっぱり分からないけれど……治らないなら樹海ドロップを見つけ、お父さんに舐めてもらえばいい。私たちの答えはそれに行きついた。だから、こうして雨の日には、樹海に来て探しているのだ。いつか見つかると信じて——。
カランコロン!
「花梨、ドロップ食べる?」
「うん、お腹空いた」
お兄ちゃんはポケットから、四角い缶を取りだす。深い緑色の缶だ。それの頭についた丸い形の蓋を、指先でくいっと押し開ける。
「さあ、花梨、手を出して」
私は手のひらを上向きで差しだす。お兄ちゃんが缶を逆さまにして、手の上で数回振ると。
ぽろん!
「わあ!」と私は声を上げる。手のひらに落ちてきたのは、桜色のドロップだった。透明感があって、表面には細やかな模様がある。キラキラと煌めく宝石のようだった。
「ありがとう!」
私はドロップを摘んで、口の中に放りこむ。いちご味。いちごの甘さが口内を駆け巡る。美味しい。一気に疲れがふっ飛んだ気がした。こんな簡単に樹海ドロップも手に入ったらいいなと、その時の私は思ったんだ。
しばらく探したけど、なかなか見つからない。樹海の中だと、時間の感覚も分からなくなる。わがままを言ったことを後悔していた頃、霧雨の中にキラキラと光るものを見つける。
「お兄ちゃん! あれ、絶対に樹海ドロップだよ!」と私は周りを気にすることなく、お兄ちゃんの手を離して走りだす。
「か、花梨!!」
私はキラキラしたものしか目に入っていなかった。目の前の谷に、全く気づかないままで。足がすべって前のめりになると、ひょいと体が軽くなった。生温かいぬくもりを感じる。硬い毛並みが肌にふれる。濡れた地上に置かれた私に、素早くかけ寄るお兄ちゃん。私たちの前には、巨大な黒い影が立っていた。
「花梨、逃げるんだ!」
どん、と押されると、カラン! と缶が落ちる音が鼓膜をゆすった。ドロップと金属がぶつかる音と。雨の音と。何か得体の知れないものの荒い息遣いと。そして、大きな気配と。
私はその後、樹海の入り口で目を覚ます。そこにお兄ちゃんはいなかった。それから今まで、ずっと行方不明のままなのだ。30年もの間も。あの日、あの後、お兄ちゃんがどうなったのか? あの日の記憶は、どうしても思い出せない。どうやって、樹海を抜けだしたのかも。
結局、お父さんはその後すぐに亡くなった。
*
雨と混じりあった涙を拭う。指先も腕も、足の付け根も、足の指も。もう、感覚がない。でも、あの日のお兄ちゃんの肌の温度は、はっきりと思いだせる。細胞がちゃんと記憶しているのだ。私は力ない手を握りしめる。
あの日、キラキラと輝いていたものは、果たして樹海ドロップだったのか? 今となっては分からないけれど、それでも今の私には……最後の砦のようなもの。なぜなら、私の5歳の娘は、難病に侵されている。治療法は、未だに見つかっていない。もう、これに頼るしかない。夫に何度も止められたけれど、私はどうしても諦めきれない。諦められるわけがない。だから、今日もこの樹海に——。
背中に染み入る水分すら、もう何なのか分からない。それぐらい、体の神経が、感覚が、消え失せている。文鎮のようにずっしりと重い体。それなのに、体の芯は軽い。浮遊感を感じる。意識が遠のいていくのを感じる。はははっ、私が死んでどうする?
「茜、茜……ごめん、ごめんね……」
助けてあげられないかもしれない。そんな弱音が、白い息の隙間から漏れる。どうにかして瞼を閉じ、自分の手らしきもので目玉を覆った。静寂の森には、絶望の時しか流れていかない。
……死ぬのかな……
カランコロン!
その時、瞼の裏に大きな闇が落ちた。ハッと皮膚神経が目を覚ます。研ぎ澄まされたようだった。懐かしい。懐かしいぬくもり。あの日の感覚が、今、私の頬を包んでいる。ああ、ああ、これは——。
「……お、お兄、ちゃん?」
開いた目玉の中に飛びこんできたのは、真っ暗な影だった。輪郭は丸くて、大きくて。獣の匂いに混じり、甘い匂いが鼻の奥に吸い込まれる。ドロップの匂いだ。お兄ちゃんも、私も大好きだったあのドロップの、甘い甘い匂い。毛むくじゃらの毛束の中に、懐かしい眼差しが隠れていた。私をいつも見つめていたあの、瞳。
『か、かりん、ごめんね。ずっと、あいたかった。でも、こんなすがたじゃ、あいにいけなかった。あのひのけもの。かれはこわいけものじゃなかった。かりんをたにからたすけた。そうして、ぼくはかりんとひきかえに、けもののともだちになったんだ。かれはずっと、ひとりぼっちだったから。ひとびとからはおそれられていたけれど、かれはやさしいけものだった。ぼくはかれとすごすうちに、けがはえ、おなじすがたになった。たべるものはくさや、きのこ、きのみなど。かれがなくなって、ぼくはこのじゅかいでひとりぼっちになった。さびしかった。でも、いつか、かりんがきてくれるって、そうしんじていた。だから、ぼくはずっと、ここで、きみをまっていたんだよ』
毛並みが肌にふれる。優しかった。お兄ちゃんの腕が私の体を浮かせ、抱きあげてくれた。あの日の獣と同じ気配がする。あの獣は、私を谷から救ってくれた。それなのに、私は怖かった。あの獣がお兄ちゃんを食べたのだと、子供ながらに思っていたんだ。だから、心の中で、お兄ちゃんは消えたのだと勝手に思いこんでいた。そう思いたかったのだ。そう思わないと、お兄ちゃんを失った悲しみから、逃れられそうになかったから。自分のわがままのせいで、お兄ちゃんがいなくなったのだと、思いたくなかったから。
カランコロン……
その時、一粒のドロップが、私の手の中に落ちた。それはあの日見た、キラキラと光るものに似ている。金色に色付いた丸いドロップ。
「お兄ちゃん、こ、これっ……」
宝石のようなドロップは、厚い毛に覆われたお兄ちゃんの瞳からこぼれ落ちたのだ。
『かりん、これをもっていきなさい』
毛むくじゃらの指先がそれを摘みあげる。深緑色の四角い缶を取りだすと、その中にコロン! とドロップを入れこんだ。差しだされたそれを、私は両手で受けとる。だいぶ錆びていたけれど、それはあの缶だった。お兄ちゃんの大好きなあのドロップの缶……。
「ありがとう!」と顔を上げると、もう獣の気配は消えていた。私はいつの間にか、樹海の入り口に戻ってきていた。あの日と同じように。雨はすっかり上がっていて、遠くの空があかね色に染まって滲んでいるのが見える。
不思議な感覚が、心の奥に残っている。
あの獣は何だったのか。
本当にお兄ちゃんだったのか。
あの日、獣なんて本当にいたのか。
口の中には甘い味が広がっている。あの大好きないちごの味が。手の中に感じる四角い金属の感触。片手で振ると、カランコロン! とドロップが音を鳴らした。
私は立ちあがり、茜のことを思いながら歩きだす。左手にはドロップの缶を抱え。右手の表皮にはあのあたたかなぬくもりが、今もまだ鮮明に取り残されている。
—end—
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
