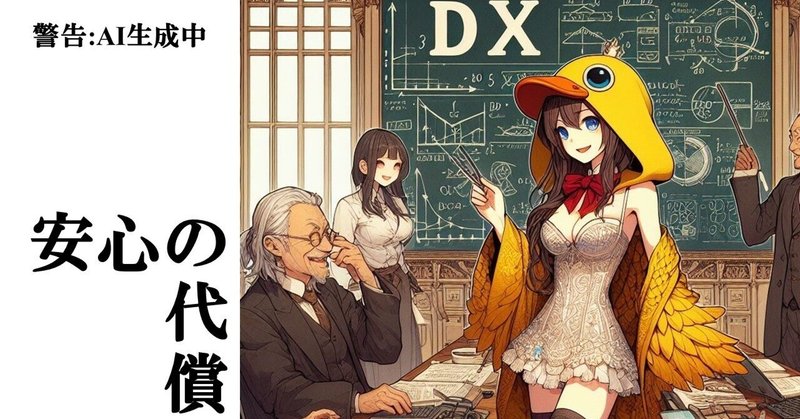
DX戦記6~XありDXの道筋を考える
前回、XありDXの構造として「パンテオンモデル」という独自の行動スキルを定義しました。今回はその続き。

パンテオンモデルで表す「いわゆる日本的企業(JTC)」
Japan Traditional Companyというネットスラング(日本語)を聞いたとき、ああ上手い事いうねぇ、と思いました。
いい感じに解説していたブログがあったのでリンク貼っておきます。
なお、私はこのブログで指摘されている通り、かつてJTCに務めていて、不思議な力が嫌になって辞めた派です。このあたりの分析も非常に優秀な記事ですね。
これに、「ビジョンが無い」「デザインが欠落」というのを追加すると、いかにも経営理論っぽく見えるので、採用して図にしてみます。

つまり「ビジネス」「サービス/商品」そして「業務」しかないのがJTCという事ですね。
変化(X)を忌避するので、「デザイン」の出る幕もないという状態です。
ただ、JTCにはメリット、デメリットがあります。
JTCのメリット=変化のない安心感
人類は昨今のようなスピードある情報技術の進展と、それに伴うプロセスの変化に向いていません。
人類のITでとてつもないインパクトを与えた発明は、「文字」「紙」「活版印刷」「電信」「インターネット」ですが、だんだんに早くなっています。
文字は、3000年くらい(異論は多々あり)かけてに広がり、地域レベルの経営を可能としました。
紙は、1500年くらいかけて広がり、地球レベルの広域経営を可能にしました。
活版印刷は、200年くらいかけて広がり、地球上の人文科学を含むあらゆる科学の促進を可能にしました。
電信は、30年くらいかけて広がり、地球規模で同期化された経営が可能になりました・
インターネットは、8年くらいかけて広がり、地球規模の経営に、集落経営と同等の容易性をもたらしました。
つまり、18世紀くらいまでは、下手すると数世代は変化のない経営を営むことができたんですが、今は数年単位で変化するという話です。
人は、そんなに便利になれませんので、変わらないことに安心感を持ちます。JTCはそんな人たちのよりどころとして、精神的安定を与えてくれます。
JTCのデメリット=相対的優位性の漸次的喪失
残念ながら、大なり小なりの変化が数年単位で訪れる中で、変化しないという事は相対的に生み出す価値が劣ってくるという事です。内部的な変化が結果として見えてくるまでに時間がかかるので、一見、そうではないように思いますが、誰にでもわかるようになった時には手遅れです。
しかし、インターネットが世界に普及した1990年から30年…つまり、失われた30年…たって、だいぶんと結果が出てきました。
変化を重ねてきた企業に対して、JTCは安い人件費で、生産性の低い長時間労働を行って対抗するしかありません。安心感を抱きしめながら、疲弊し、消え去っていくことになります。
そのうち、あと10年もすれば、誰にでも分かるような結果が出ることでしょう。
というわけで、次回からこのモデルを使って、どう変化をしていくかを考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
