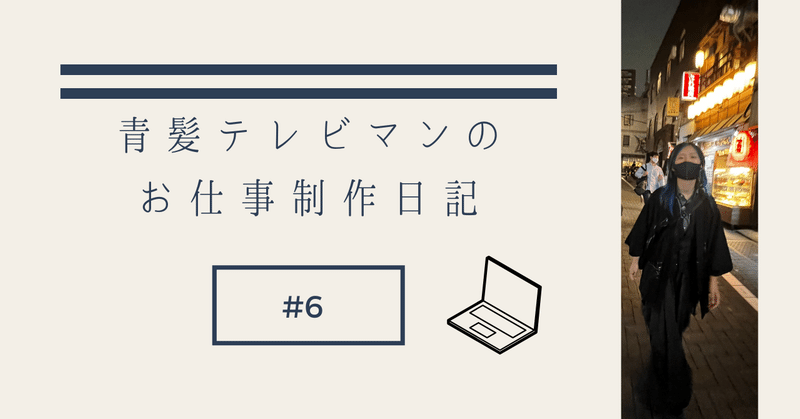
『The Signs~Asakawa Chieko: Changing Lives with Science and Technology~』(ディレクター)
下記、番組をディレクターとして担当させていただきました。
今回はその番組の編集後記。書いていこうと思います。
★The Signs
Asakawa Chieko: Changing Lives with Science and Technology
危機の時代から再び立ち上がっていく新しい時代の「兆し」をいち早くとらえ、世界へと伝えていく番組「The Signs」。
IBMの最高技術職・フェローであり、日本未来科学館2代目館長に就任した全盲の研究者・浅川智恵子さん。リアルワールド・アクセシビリティの実現を技術の力で解決してきた浅川さんのインタビューとともに未来のダイバーシティについて考察します。
NHK WORLD JAPAN 2021/12/4(土)12:40から 放送開始
NHKオンデマンド3年間放送
出会い、そして番組作り
今年度に入ってから「ズームバック×オチアイ」という番組のADを時より担当させてもらっているのだが、そのなかで実はずっと気になっていたことがある。
”落合さんの部屋やホームページでよく見かける
あのデジタル自然みたいな作品は何なのだろう”と…。
どこにある、何っていう作品なのかもわからず、
ただただ毎日ズームバックの期間は目の前のアーカイブ検索・権利処理…
毎日分室でお泊まり。そんな日々と戦ってた。
その答えは意外にもかなり早く、私は実体験として知ることになる。
10月、今回の番組のロケハン。ロケハンの場所にあった、それを見て、
私は耐えきれず「あっ…」と言ってしまった。「もしかしてこれ…落合さんの…」
落合さんが監修した『計算機と自然、計算機の自然』がある日本科学未来館。
お台場にある国立の科学館だ。
先端科学技術を体験的な展示を通して学ぶことができる。
この日本科学未来館の館長が2021年4月に変わった。
その方が今回メインで取材させていただいた、研究者の浅川智恵子さんだ。
(ちなみに前任(初代館長)は、宇宙飛行士の毛利衛さんである。)
(浅川さんのバックに写っている地球儀を見たことがある人もきっと多いはず。)
浅川さんは、14歳の時にプールの事故がきっかけで全盲になった。
しかし彼女は、目が見えなくなってしまった自身の体験をきっかけに、視覚障害者のアクセシビリティを科学の技術で解決する研究を長年取り組んできた。
浅川さんが全盲になった時は、1970年代前半。
インターネットはまだ普及していなかった。
今でこそ、音声合成システムなどによりネットで調べたものが
音で確認できるようになっているわけなのだが、
当時はそんな便利なものもなく、
さらに視覚障がいのある方の情報源というのはかなり限られていた。
(点字も当時は複製できず、1つ1つ人が打っていた。)
困難だったことの1つに 教科書があります。 当時は パソコンも インターネットも、スマートフォンもありません。それで2人いる兄弟のどちらかに 教科書を読み上げてもらい、点字で自分用の本を作る必要がありました。想像できますか?
私の兄弟にしても そんなの面白いわけもなく、頼みたい時にはいつもいなくなっていることに気が付きました (笑)
【中略】
私は 誰かに頼らずに済むようになりたいと強く思っていて、それがイノベーションを起こしたいという想いに繋がりました 。
私的 科学技術が社会とつながり、もたらすもの
今回、理系の大学に通う大学修士の学生さんが
番組制作のアシスタントとしてついてくれてました。
今回の番組をするにあたって、文系にもなれなかった私が
理系の楽しさ・希望とは何かを知りたいと思い、彼とはいろんな話をしました。
またこの日本科学未来館を青春の地だと言っていた
お世話になったプロデューサーさんは文系も理系も
関係ないよと教えてくれました。
数学や数字が苦手で理系は完全に範疇からはずれてしまっていた私ですが
化学は好きだったなぁという遠い記憶を思い出していました。
二人と話をしながら、そして番組を制作しながら思ったのは
”私が昔、理系って楽しいと思ったあの体験は
社会でどうやって生かすことができるのだろう”という問いでした。
私も理系的考え方を自分の仕事のなかで、人生のなかで
どこか実は生かせるのではないかという淡い期待もありました。
その問いを胸に
日本科学未来館に足を運んだ時、
私に見えたのは周りに見えたお台場の広大な開発都市と海、
そして未来館のなかの外とつながっていきそうな体験的な展示の数々でした。

私の得意分野はやはり情報で何か別の物語を伝えることですので
今回も以前からお世話になっているスーパーカメラマンのお二人にご協力いただき
たくさんの実景を撮影させていただきました。
見えてきたのは、この日本科学未来館がミニチュアな都市であり
ここからいろんなものがつながり、発信されていくということ。
科学技術の小さな想像と実験と成果の積み重ねで、
思いにもよらない広大な未来が作られていくこと。
それこそが理系の楽しみであり、希望であるのではないかと
私はその時考えました。
化学が好きだったけど、文系として進み、
あの時ワクワクした感触を将来にどう生かしていったらわからなかった日々。
一応文系だと思って生きてきた私としてはなかった新しい考え方だったので、
今後また自分が成長していくための大事な考え方になりそうです。

(でもなぜかできた)
”科学技術が世界を変えていく”
よく聞く文章ですが、私はこれを今回深く理解したように感じます。
自分の身内の話をすると、
私は弟が自閉症で今は実家で両親が一緒に暮らしていますが
何かと将来的に不安になることが最近ちょっとずつ出てきました。
将来、自分は弟とどう過ごしていくのか。
弟が自由に生き生きと暮らしていきたいように暮らすことができるのか。
そもそも自分がこの先一人で生きていくことは可能なのだろうか。
でももしかしたら各々に与えられてきた試練は
その人が、そしてその周りが動き出していくためのパワーを生み出す
大きな壁なのかも知れません。
壁がなければ人は試練をクリアしようとしないし、パワーも出さないのです。
不安と向き合っていた昨今。
今回の浅川さんの取材を通して、
科学技術が障がい者のアクセシビリティや生活・世界を変え、
そしてその技術がひいては高齢者や障がいを持っていない人をも支える
世界を変える技術になるという兆しを見たような気がします。
世界が変わる足音を聞いたような気がします。
皆さんにぜひ
この足音を聞いて欲しい。
そして科学技術に興味をもってほしい。
そんな想いでつくりました。
浅川さんは未来館で
どんな未来のダイバーシティを実現しようとしているのでしょうか。
一人でも多くの方に、
浅川さんや日本科学未来館の皆さんの思いが届くと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
