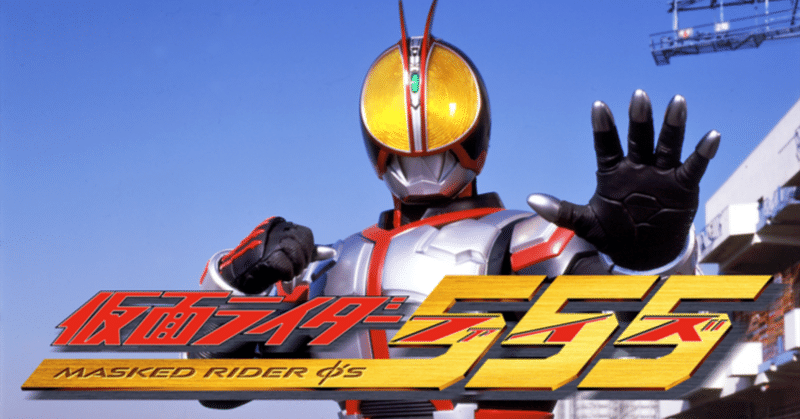
『仮面ライダー555』(2003)感想〜「滅び」の宿命から逃れられない者たちの無残な殺し合い〜
東映特撮YouTubeOfficialの『仮面ライダー555』(2003)のテレビ版の配信が終了したということで、簡潔ながら感想・批評をば。
評価:B(良作)100点中75点
概論

本作に関してはこれが二度目の視聴だったのだが、やはり思ったのは『仮面ライダー』はどこまで行こうと「映画ではなくテレビ文化の中でこそ成立するヒーロー」ということだ。
以前に劇場版「パラダイスロスト」を酷評した時に「テレビドラマの番外編としてならありだが映画としては厳しい」と書いたが、その理由は本作の土台が根っこにあるからこそである。
もう本作に関しては放送当時から様々な議論がなされてきたと思うが、今回の視聴で私の中で決定的だったのは本作はとにかく「この世という名のあの世」の世界での話であるということだ。
第一話から最終話まで一貫しているのだが、本作は脚本・演出・アクションなどあらゆるものが無機質にして冷徹・硬質なものであり、どこをどう見ても通常のヒーローフィクションの画面ではない。
井上敏樹がメインライターを務める作品は『鳥人戦隊ジェットマン』(1991)をはじめ、従来のヒーロー活劇や正義なるものに対して懐疑的・批判的なスタンスの下に物語が紡がれていた。
そんな中でも『仮面ライダーアギト』(2001)まではどこかに「救い」が残されていたし、驚愕の夢オチで打ち切り漫画のような幕の閉じ方をした『超光戦士シャンゼリオン』(1996)も一縷の望みがある。
しかし、本作に関しては徹底してそのような湿度というか抒情性のようなものが画面からは極力排されており、最終回まで見ても全くヒーローフィクションとしてのカタルシスが感じられない。
いわゆる、1970年代の漫画・アニメなどでよく見られた「黙示録」のような終末思想・聖戦のようなものではなく(それに近いのは「アギト」「パラロス」)、戦いにも温度がないのだ。
それは変身前の人間ドラマと変身後のライダー&オルフェノクの戦闘シーンの全てにおいて一貫しており、間違いなく『仮面ライダー』ではありながらその作風は徹底して飢え渇いている。
井上敏樹はよく「昼ドラ」だの「戦うトレンディドラマ」などとファンからは呼ばれ、物語も人物像も従来のヒーローフィクションとは異なる退廃的な文学的要素を好んで入れたがるエキセントリックな作家だ。
だが、その根底には「最後はなんだかんだ救われる」というある種の性善説のようなものがあり、どこかに「救い」というか「何だかんだ幸せにはなれる」という許しがあった。
翻って本作は最終回まで見終えても、表向きは大団円というかハッピーエンドの形を取っているようでいて、実は登場人物の誰にも、そして視聴者に対しても救いが残されていない。
かくして、本作は「仮面ライダー」という括りを超えた「ヒーローフィクション」の限界を露呈させた一作だが、果たしてそれがどのように画面の上で活写されたのだろうか?
乾巧=仮面ライダーファイズという「アンチヒーロー」がもたらした逸脱と破壊

本まず外せないのは第一話の乾巧=仮面ライダーファイズという「アンチヒーロー」が第一話でもう1人の主人公・木場勇治=ホースオルフェノクと対等の存在として演出されているカットだ。
『仮面ライダー』において大事なのはいかに「異形の怪人」が画面に象徴的に出てくる瞬間を印象付けるかだが、ファイズは既存のどのライダーにもなかった演出手法が取られている。
乾巧が変身するファイズは木場のホースオルフェノクの変身と同等であり、この時点で既に最終回までの結末がある程度紐付けされているといえるだろう。
だが、ここで示されているのは決して乾が実はオルフェノクだったという伏線とか、その前に園田真理がファイズギアを持っていて変身しようと試みて失敗するとかいう物語上のことだけではない。
仮面ライダーファイズの闇夜での登場がごく当たり前の日常風景として演出され、デザインにも戦い方にも「キャラクターとしての個性」なるものが完全に排されていることにある。
そもそも携帯電話で変身する上にデザインの配色も黒・銀・赤を彷彿させるメカニカルな「X」の延長線上にあるのも、必殺技のクリムゾンスマッシュの無機質なCGの演出もそれを助長していた。
これは前作「龍騎」によって「ライダーの敵はライダー」を踏まえた上でこそ成立するものだが、乾巧が仮面ライダーファイズに変身しても視聴者はちっとも気分が高揚しない。
最初は気だるそうに仕方なくの変身だったし、またファイズに変身するのは決して乾巧だけの特権でもなくオルフェノクであれば誰でも変身できるようになっている。
だからこそ、「ライダーベルト争奪戦」が画面の運動として象徴的に機能しているわけだが、カイザもデルタもスペックとしてはとんでもなく強力なのに、好んで変身する者はほとんどいない。
カイザギアはオルフェノクとしての適性が高い上位陣の者以外は変身を解除すると灰となって消えてしまい、デルタギアは使用者の潜在的な闘争本能を強制的に引き出し発狂させる中毒性の高いベルトだ。
ファイズギアにはそのようなデメリットこそないものの、使用する度に寿命を縮めてしまう点は変わらず、おいそれと変身できないように「制約と誓約」を設けているのである。
実際ライダーベルトがなくても草加雅人・園田真理・三原修二などの元流星塾のメンバーを除けば、オルフェノクに変身できる連中はそれだけで戦うことが可能となるのだ。
本作に登場するライダーベルト=ライダーズギアは後述する「オルフェノクの王」なるものを守るためにスマートブレイン社が開発・貸与しているものに過ぎない。
これだけを見ると「三種の神器」とも准えることはできるが(生身の人間では触れることすらできないのも含めて)、そのことが乾巧たちのヒーローたる所以にはならないのである。
しかも乾巧・木場勇治・草加雅人のいずれも部分的にはヒーローらしき性格はあったとしても、自らをヒーローたらんと望んでなったわけでも望まれてなったわけでもない。
それでありながら、石ノ森章太郎が提唱している「闇から生まれた正義」「異形の怪人による同族殺し」というエッセンスはきちんと押さえてある。
そのことを1話の仮面ライダーファイズとホースオルフェノクの同時進行の戦いとして示すことで視覚的に本作が「仮面ライダー」から「ヒーロー性」を排することに成功した。
情念のように見せかけた「論理」による殺戮ゲーム

本作をよくよく見ていくと、実は本作で繰り広げられる昼ドラのような複雑怪奇に満ちた罵詈雑言の応酬・権謀術数・殺し合いの数々は一見情念のように見せかけた冷たい「論理」による殺戮ゲームである。
こんなことをいうと「感情で動くキャラが多かったではないか」との反論が来そうだが、それはあくまでも「契機」に過ぎず、感情論で戦局や登場人物の悲喜交々が左右されるほど本作は甘くない。
表層に露呈する登場人物たちの濃密な情念の空回りとすれ違いとは対照的に、変身後の戦闘シーンにおける強さはシビアに序列が決まっていて、滅多なことではひっくり返らないのだ。
ラスボスの「オルフェノクの王=アークオルフェノク」を頂点として、北崎のドラゴンオルフェノク、木場のホースオルフェノク、巧のウルフオルフェノクが本作におけるオルフェノクの中でも特に強い。
そしてライダーズギアも単純な戦闘力のスペックはデルタ>カイザ>ファイズとなっており、ファイズは途中でスピード特化のアクセルフォームとチートのブラスターフォームで強化する必要があった。
また、オルフェノク側に殺される人間たちも、そして巧たちが私刑に処するオルフェノクたちも何かしらの「罪」を抱え「信賞必罰」として殺されることが前半では多く、無益な殺生はあまり行われない。
終盤で過激化していく中でも、例えば啓太郎と恋仲になった結花もそこだけを切り取ると悲劇のヒロインのように思われるが、その前に彼女は養父母と義妹・学校のいじめっ子たちを虐殺している。
それに加えてオルフェノクとして自分にとって気に入らない者を爪弾きにして殺して来たため、それが自業自得という形で跳ね返り、その思いが報われることはなく、啓太の初恋は実らなかった。
また、最終的に木場が変身するカイザの手にかかって首をへし折られて殺される草加雅人も、表向きは自身が乾巧共々権謀術数を働きかけた木場による因果応報という形で死んだようにも思われる。
だが、雅人を殺した時の木場の表情には全く人間味がなく、殺した理由も花形によって新社長に任命されたことで、自身の中にあった「オルフェノクに仇名する者は全員敵」という過激思想に陥ったからだ。
皮肉にも木場のその思想とスマートブレインの新社長に任命した花形の遺志とは真逆だったわけだが、要するによくある正統な嫡子が危険な傍流の二番手を粛清するという権力闘争の表れなのである。
この図式は『仮面ライダーBLACK』の剣聖ビルゲニアを粛清するシャドームーンの換骨奪胎というかセルフオマージュであるともいえ、決して木場は私怨で草加を殺したわけではない。
基本的に本作は主人公の乾巧が働きかけるいくつかの例外を除けば、表面上は情念で動いているように見せかけておきながら、戦いはあくまでオルフェノク側が仕掛けるゲームの論理で行われる。
そのことが終盤で次々と主人公にとって身近な者たちが殺されゆくシーンに凝縮されており、本作で殺される側も生き残る側も実は誰一人として明確な生殺与奪の権を持っていない。
そしてその理由は本作はあくまで「オルフェノクに覚醒した者」あるいは「オルフェノクに適合する記号を施された者」がひしめき合う世界だからであり、実は登場人物は大枠の部分で身動きを封じられている。
本作では「ヒーロー」も不在であれば「悪」もまた不在であり、「人類側に味方するオルフェノク」か「人類に取ってかわり種の繁栄を望む敵としてのオルフェノク」という「敵対敵」の戦いなのだ。
その意味で本作は「全員悪人」ならぬ「全員敵」のライダー版『アウトレイジ』と呼ぶにふさわしいかもしれない。
アークオルフェノクは絶対悪か?

本作では「人類と怪人の共存」が表向きのテーマとされているが、結論を述べると「部分集合(ミクロ)では可能だが、全体集合(マクロ)では不可能」というのが一貫している。
それは最終回までを待たずとも、序盤の4話までを見れば、そもそも人間に対して迫害されたり遺恨があったりする者たちがオルフェノクとして身勝手な人類を私刑に処していることからもわかるだろう。
上記したように何の敵意もない善意の塊である啓太郎ですら結花と和解することはできても、その思いが叶い結ばれることなど決してなく、またそれは巧と真理に関しても同様である。
劇場版では最終的に手を繋いで恋人のようにして自分たちの世界を求めてあてどなく彷徨う2人だが、テレビ版では決して男女の情愛ではなくまるで「気心知れた義兄妹」のような関係性だ。
だから本当に心底から分かり合えているわけではないのだが、それよりももっと重要な問いは本作のラスボスとして出てきたアークオルフェノクなる存在は絶対悪なのか?ということである。
オルフェノクの王=アークオルフェノクは「九死に一生を得た子供」の中から誕生するのだが、その目的は必ずしも人類にとって絶対悪といえるほどのものではない。
そもそも設定自体も「オルフェノクが永久機関として生きられるための救済措置」として作られたもので、そのために多くのオルフェノクを栄養分として吸収する必要があるというのもよく見かけた設定だ。
『ドラゴンボール』の人造人間・セルや『デジモンアドベンチャー02』のべリアルヴァンデモンを想起させる設定であり、かつデザインはバッタ人間のそれであることからも、視覚的に純粋悪とは判断しにくい。
最終的に乾巧たちが自分たちが「人間」として生き延びるためにオルフェノクの存在自体を否定する形としてアークオルフェノクは倒されることになったのだが、誰がそこにカタルシスを感じられようか?
確かに北崎=ドラゴンオルフェノクを食らうシーンがグロテスクであり、いずれ放っておけば人類そのものも駆逐されてしまうかもしれないという危険性は残っているだろう。
だが、それを乾巧たちが共闘して倒したところでアクションとしては相応の盛り上がりは担保されたとしても、それでこの世界に平和が訪れたかどうかは全くもって不明である。
ここにヒーローフィクションとしての格好良さを持たせるならば、もう少し乾巧たち3人のライダーの「ヒーロー性」とアークオルフェノクの「諸悪の根源」を確立するための仕掛けが必要であった。
だが、本作においては結局その辺りの問いに対する答えを曖昧にしたまま、巧たちライダーズギアの持ち主の判断によって叛逆を受ける形でアークオルフェノクは殺されることになってしまう。
白倉伸一郎も井上敏樹も決してそのことに無自覚であったとは思えず、だからこそもう1つの可能性として視聴者側の感情を救済するために「パラロス」を用意する必要があった。
徹頭徹尾、絶対的な正義も悪も不在な中で、一度死んで異形の怪人に覚醒した者たち同士の血で血を洗う仁義なき抗争は詰まる所「異形の怪人」である自分たちの存在をもこそ否定してしまったのだ。
これは「ヒーローフィクション」としての完全な敗北の瞬間であり、『仮面ライダーBLACK』が提示したメリーバッドエンド(ビターエンド)を遥かに超えるものといえるのではなかろうか。
「クウガ」「アギト」「龍騎」のいずれもギリギリのところで踏みとどまり超えなかった一線をとうとう本作は最終回にして超えてしまったという格好である。
黒い干渉縞でボカされた結末

このように、本作は物語の上でも、そして映像としても「ヒーローフィクション」としての限界を画面に露呈させ、それが敗北する瞬間をこれ以上ないまでに描出した作品である。
だからこそここで最後の問いになるのは、最終回で2回ほど出てきた黒い干渉縞だが、この干渉縞は乾巧VS木場勇治とEDのラストカットのところで出てくる。
これが何を意味するのかは当時から様々に論じられてきたと思うのだが、1回目のそれは明確に「人間」と「オルフェノク」の境界線として使われていた。
乾巧=仮面ライダーファイズはオルフェノク側について人類を見限ろうとした木場勇治=仮面ライダーカイザに「お前も人間だ」と言い放ち、真理たちのいる場所へ向かう。
しかし、その境界線を木場は激昂しながらも超えられずにいる、それは彼が「人間」として自らの罪と向き合うことから逃げ続けきた現実を巧にまざまざと突きつけられたからだ。
そして巧たちが河原で3人揃って寝そべったラストカットでは、引きのカットで巧たちだけをまるで一縷の望みのように照らしつつ、それを安易なハッピーエンドと見せないものとして機能している。
つまり同じ干渉縞のカットでもそれぞれが正反対の視点から撮られており、1回目はおそらく人類側の視点から見たオルフェノクの薄汚れた世界との境界線を示すかのように描かれていた。
そしてラストカットではオルフェノク視点から見た人間世界の眩しさを示しているわけだが、この干渉縞が反転として用いられるカットによって、実は結末が曖昧にボカされている。

表向きはアークオルフェノクの脅威が去り、オルフェノクだった者たちも含めて平和を享受しているように見えるが、それでも映像の淡いトーンに反して「平和」の象徴だという風には見えない。
実際、琢磨は井上敏樹演じる工事現場の監督に焼きを入れられながら働かされているし、海堂にしてもまだはっきりと目標は見つからず、三原たちも巧たちも見つかっていないのだ。
そして何よりアークオルフェノクが完全に滅んでおらずに保存されており、さらに影山冴子=ロブスターオルフェノクが生きていることから、まだオルフェノクの脅威は去っていない。
その上で巧は余命幾ばくもない己の生を啓太郎から継承する形で得た「みんなが幸せな世界」のために生きると口にするが、その言葉にはさほどの説得力もないのである。
要するに本作は映像・脚本共に卑近な視点での仕込みは完璧なのだが、もっと俯瞰して見た大局的な視点での仕込み・仕掛けが不完全であった。
ビターエンドにしたいのかハッピーエンドにしたいのかも不明であったし、そもそも人類とオルフェノクの戦いがはっきりと「ヒーローと悪」の戦いと定義されてもいない。
だからこそどんなに高く評価しようとしたとてB(良作)以上の評価は与えられず、序盤から仕掛けてきたものが今ひとつ終盤できちんと作品全体として昇華しきれず仕舞いだったと思う。
17話の乾巧=仮面ライダーファイズが成立する様が本作のピークであり、キャラ単位で見れば草加雅人をはじめ魅力的な人物が織りなす豊かな細部には恵まれていた。
しかし、やはり一方でいつもの白倉・井上コンビらしく終盤のまとめ方でいまひとつはっきりとした答えを出せずじまいで終わったという無念さもまた視聴後の印象に残ったであろう。
その意味では『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』(2022)は本作でうまく出し切れなかった「人間と怪物の共存」という要素に対して19年越しに挑もうとしたのかもしれない。
いずれにせよ、「滅び」の宿命から逃れられない上で無理難題に挑むという意欲は評価するが、そこに対する物語・人物描写・映像演出が今一つ追いついていなかった。
嫌いではないし擁護したいところだが、少なくとも東映特撮の歴史を完璧に塗り替えるには至らなかったというのが改めて視聴しての印象である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
