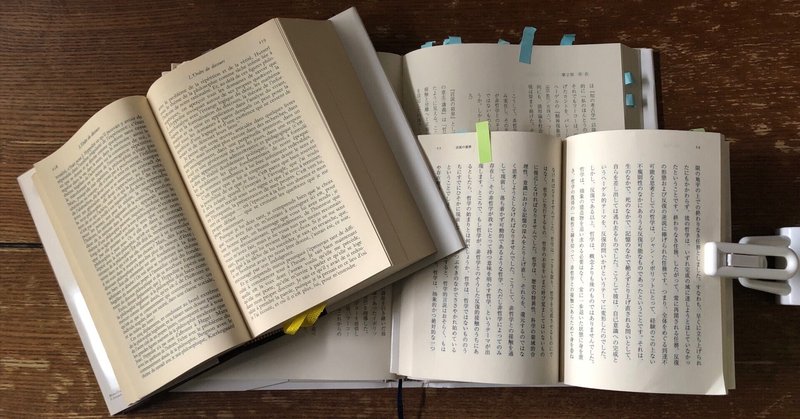
「フーコーのイポリット」に関する覚え書き
フーコーは、1970年に行われたコレージュ・ド・フランス講座の開講講義『言説の領界 L'ordre du discours』が終わるころ、〈哲学の非哲学を介した自己実現〉というヘーゲル的なテーマを「転倒 inversion」した〈哲学と非哲学の繰り返される接触〉というイポリット的なテーマをふまえ、そんな反復において「哲学のはじまり」はどのようなものでありうるかを問題にしはじめている。そこでフーコーは解答方針を2通り提起しているのだが、どういうわけか、『フーコーの〈哲学〉』の著者の市田良彦は2つのうち1番目の方針しか引いておらず、河出文庫版『言説の領界』の訳者の慎改康之は2番目の方針を誤訳している。しかし、これからみるように、フーコーがイポリットとともに選ぶ方針は2番目のものであり、それはヘーゲルから逸脱しハイデガーを放棄するような方針である。読解しなおさなければならない。問題と2つの解答方針が提起される箇所の原文と日本語訳を引いておこう。
Or, si elle est dans ce contact répété avec la non-philosophie, qu’est-ce que le commencement de la philosophie ? Est-elle déjà là, secrètement présente dans ce qui n’est pas elle, commençant à se formuler à mi-voix dans le murmure des choses ? Mais, dès lors, le discours philosophique n’a peut-être plus de raison d’être ; ou bien doit-elle commencer sur une fondation à la fois arbitraire et absolue ?
ところで、もし哲学が、非哲学とのそうした反復的接触のうちにあるとしたら、哲学の始まりとは何でしょうか。哲学は、哲学ではないもののうちにひそかに現前して、事物のつぶやきのなかでささやかれ始めているということでしょうか。しかしそうだとすると、哲学的言説はおそらく、もはや存在理由を持たないでしょう。それとも、哲学は、抽象的かつ絶対的な一つの創設にもとづいて始まらなければならないのでしょうか。
◆2番目の解答方針について:「抽象的かつ絶対的」?
市田が見限り慎改が見誤る2番目の方針を日本語訳で読んでみよう。「哲学のはじまり」問題への1番目の方針の帰結を示す「哲学的言説はおそらく、もはや存在理由を持たないでしょう」というセンテンスから続いて、「それとも、哲学は、抽象的かつ絶対的な一つの創設にもとづいて始まらなければならないのでしょうか」と書いてある。なぜ市田はここを省略したのか。
イポリット-フーコーがこちらの方針を選ぶことはないと判断したからだろう。フランス語原文を読んでいるはずの市田がどうやってそうした判断をしたのかはわからないが、少なくとも日本語訳の読者がそうした判断をするのはもっともなことだとおもう。というのも、哲学が「抽象的かつ絶対的な一つの創設にもとづいて始ま」るという言い方は、あまりにヘーゲル的だし、哲学が論理的に始まるというのは哲学が哲学的に始まるということであり、哲学のはじまり問題の前提をなす〈哲学と非哲学の反復的接触〉というイポリット-フーコー的なテーマに反してしまうからだ。やがては「絶対知」の高みから「哲学の終わり」を眺望することになるこのようなはじまりを、イポリット-フーコーが選ぶことはない。この日本語訳からそう判断して何もおかしくない。
しかし、少なくとも日本語訳の読者のそうした判断はある誤訳にもとづいている。慎改が「抽象的かつ絶対的な一つの創設」と訳している箇所の原文は‹ une fondation à la fois arbitaire et absolue ›となっている。「抽象的 abstraite」ではなく「恣意的 arbitaire」である。「抽象的かつ絶対的」と言えばヘーゲル的で論理学的だが、「恣意的かつ絶対的」とあるのだからぜんぜんヘーゲル的でも論理学的でもない。むしろフーコー的と言えないか。
じっさい、次の段落には、フーコーがイポリットとともにこんなふうに問うているのが読まれる。「ある特異な個体とともに、ある社会のなかで、ある社会階級のうちで、もろもろの闘争の只中で始まる」のでありながら「絶対的言説として始まる」のでもあるような、そんな「哲学」とはどのようなものなのか、と。「恣意的」でありながら「絶対的」である哲学のはじまりをイポリット-フーコーが問うているのがわかるだろう。フーコーは、イポリットとともに、慎改が見誤り市田が見限るこの2番目の方針を選び、「恣意的かつ絶対的」の「かつ」における哲学のはじまりを問うていく道を進んでいる。付言すると、この道はイポリットが「ヘーゲル哲学」に施した「ずらし déplacement」の操作によって開かれているのだとフーコーは語っている。その「ずらし」というのは、少なくともひとつには、ヘーゲル的な「抽象的かつ絶対的」をぜんぜんヘーゲル的でない「恣意的かつ絶対的」にずらしてしまうことではあったかもしれないと言えば少し皮肉っぽいだろうか。
◆1番目の解答方針について:‹ être déjà là ›
市田がイポリット-フーコーに帰する1番目の解答方針を見てみよう。「哲学的言説」の「存在理由」の消滅を帰結する方針である。
Est-elle déjà là, secrètement présente dans ce qui n’est pas elle, commençant à se formuler à mi-voix dans le murmure des choses ? Mais, dès lors, le discours philosophique n’a peut-être plus de raison d’être ; ou bien…
ここはこんなふうに訳してもいいのではないか。
哲学は、哲学ならざるものの内に密かに現前することですでに現に存在していて、諸事物の呟きの内に小声で形成されはじめているのだろうか。しかし、そうだとするならば、哲学的言説はもはや存在理由を失ってしまうかもしれない。それとも…
この翻訳が正当だとすると、この方針はずいぶんとハイデガー的な言葉遣いで語られているように見えないか。そしてこの方針は、2番目の方針が「哲学と非哲学」の「と」における「哲学のはじまり」を問うものであったことに比すると、「非哲学」における「哲学のはじまり」を問うものになっていることがわかる。おそらく「非哲学」の喃語めいた曖昧さにおいてすでにつねに開始されている哲学をそれとして言挙げする営みがそれ自体「哲学」であるということだろう。そうするとこの方針は、言葉遣いどころかその行論からしてハイデガー的な方針であるということになる。そしてすでに明らかにしてあるように、イポリット-フーコーはこの方針をとらない。「哲学的言説」の「存在理由」の消滅には向かわない。「哲学史の解体」にも「形而上学の完成」にも進まない。
◆哲学の終わりか哲学の再開か
まとめておこうか。フーコーはイポリットとともに「哲学のはじまり」をこんなふうに考えはじめている。哲学は、論理において哲学的にはじまっていたことになる(「絶対知」となった「終わり」の方から眺めて)のでもなければ、実存において非哲学的にもうはじまってしまっている(そしてやがて「解体」されて「消滅する」)のでもなく、「恣意的かつ絶対的に」、すなわち「哲学的かつ非哲学的に」、つまりそこでの「かつ」において、反復的にはじめられる、といったふうに。
ヘーゲルから逸脱してハイデガーを放棄するこのイポリット的な思考を、まさにイポリットから講座を引き継ぎつつあるフーコーが再開している。イポリットは自身の講座名を「哲学的思考の歴史」と命名していたが、これを引き継いだフーコーは講座名を「思考諸体系の歴史」と命名しなおしている。「哲学的」という措辞を取り去ることでフーコーは何をしているのか。「哲学」を終わらせていると見るべきだろうか。違うと言わねばならない。哲学がそこで再開されるかもしれない余白をイポリット的な仕方で開いていると見るべきだ。「哲学と非哲学」の「と」という余白を。
フーコーのイポリットの姿は1969年に行われた高等師範学校でのイポリット追悼演説「ジャン・イポリット1907-1968」にも見ることができる。『ミシェル・フーコー思考集成III』所収の廣瀬浩司訳から演説末尾を引く。
戦争の直後には、暴力と言説の関係を思考することを教えてくれた。つい最近は、論理と実存の関係を思考することを教えてくれた。そしてついこの前には、知の内容と形式的な必然性の関係を思考することを呼び掛けてもいた。要するに、哲学的思考とは、止むことのない実践であることを教えてくれた。
ここでもやはり「と」を問う師の姿が回想されている。そしてこの追悼演説はゲーテの『ファウスト』第1部のよく知られている一節で締めくくられる。
理論は灰色で、緑なのは生の黄金の樹だ。
理論の灰色と生命の緑の「と」が亡き師に捧げられていることになる。先ほど「「と」という余白」とは言ったものの、色彩には欠かないらしい。そしてフーコーは、師の思考を再開する理論をニーチェとともに練り上げる1971年の論考「ニーチェ、系譜学、歴史」をこうはじめている。『ミシェル・フーコー思考集成IV』所収の伊藤晃訳から引く。
系譜学は灰色の実践である。
こんな灰色がどんな緑との「と」において再開されているか、われわれが注視すべきはそこである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
