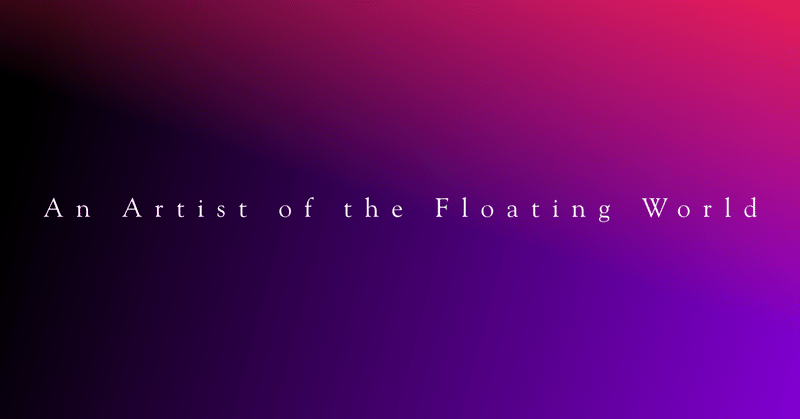
Kazuo Ishiguro『An Artist of the Floating World』:浮世を描いた画家は、やがて浮世に呑み込まれる
2019年3月、Kazuo Ishiguro(カズオ・イシグロ)の小説『An Artist of the Floating World』(邦題:浮世の画家、訳:飛田茂雄)がNHKでドラマ化されました(脚本:藤本有紀、主演:渡辺謙)。放送の数週間前にEテレの番組「日曜美術館」でドラマ化を知り、ドラマを観る前に原作を読んでみました。
彼の著作を読むのは『Never Let Me Go』(邦題:わたしを離さないで)、『Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall』(邦題:夜想曲集 ~音楽と夕暮れをめぐる五つの物語~)に続き3作目です。僕は新刊を常にチェックする熱心な読者ではありませんが、何かしらのきっかけで急に読みたくなって手に取る、そういう不思議な吸引力を持った作家です。
敗戦から数年後の東京。『An Artist of the Floating World』は、主人公である「小野益次」が、今の生活における家庭の問題を端緒に、自らの画家人生のさまざまな場面を回想する物語です。次女の縁談が成功するか否かは自らの過去が影響すると、遠回しに長女から忠告され、つらつらと過去を思い返したり、過去に親交のあった人々を訪ねる。その過程で読者は、彼が画家として考え成してきたこと、そして今もなお抱えているものに触れます。
「浮世」と訳された “floating world” とは一体何を指すのか。いわゆる浮世絵が示すような、小野の師匠「森山誠治」が描いた美しい世界と考えられ、そしてそれは小野が捨てた世界であります。その一方で、森山から離れて小野が描いた世界、すなわち小野が傾倒した軍国主義や国威発揚に加担する空気という解釈も可能です。“floating world” に翻弄されたのは、果たして森山なのか、それとも小野自身なのか。視点が違うと、物語から浮かび上がる陰影も変わり、異なる世界が姿を現わします。
芸術、それも絵画の世界を舞台にした物語ということもあり、ドラマは映像美に力を入れていました。「日曜美術館」が特集したのは、作中で重要な役割を担う三枚の絵です。小野、森山、そして小野の弟子である「黒田」、これらすべての画家が架空であり、小説では当然ながら言葉だけで絵の様子が描写されています。ドラマのために三人の画家が筆をとり、作中の言葉からイメージを膨らませて、三者三様の世界を立ち上げました。
僕が最も強く印象に残ったのが、宮﨑優という画家が描いた女性の絵です。彼女は、師匠としてさまざまな点で主人公の作風に影響を与えた森山の絵を描きました。その絵がドラマで映った時間はほんのわずかでしたが、刹那ともいえる時間の中で、僕はその絵が持つ美しさや儚さ、静謐さや脆さを感じました。漂うのは色気なのか諦観なのか、あるいは空虚なものに過ぎないのか。夜の闇は朝の光にとけますが、昼を照らす太陽も傾き夜に呑み込まれます。喰らい喰らわれ、巡り巡る。画家もまたその奇妙な循環の一部なのかもしれません。
できることなら、自分の目で直接その絵を観てみたい。テレビの画面越しに見るときとは異なる感覚が生まれるのではないでしょうか。印象的な絵を目の当たりにしたとき、その場に縛り付けられる感覚に陥ることがあります。眼前に広がる世界に呑み込まれ、心を奪われる。この絵についても、そういった印象的な体験が訪れるのかどうか興味があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
