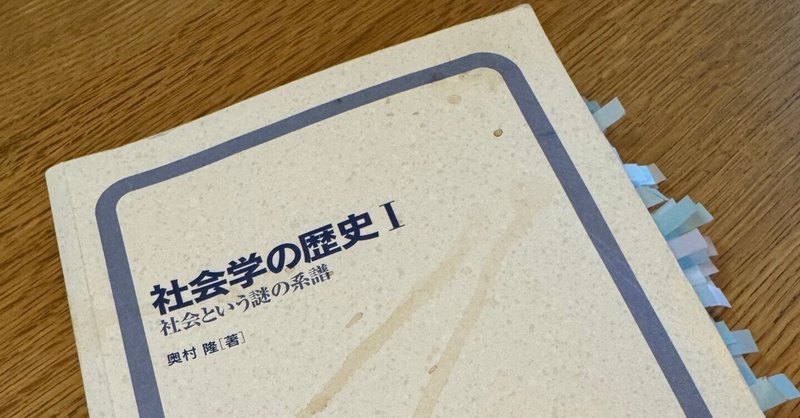
『社会学の歴史I 社会という謎の系譜』奥村隆
『社会学の歴史I 社会という謎の系譜』奥村隆、有斐閣アルマ
「面白くてためになる」というのは本書のような書物ではないでしょうか。講義スタイルの「ですます調」の文章も読みやすい。
社会学者の人物像、時代背景から理論や学説を説明してくれるので、学説史がスッと入ってきます。どんな入門書でも学説史が丁寧に説明されていると理解しやすいと思うのですが、そのためにはアンソロジーではなく、ひとりの筆者が書く必要があり、本書はそうした要件も満たしていると思います。
知り合いの子が大学生になったら、サル学の『人間の由来』河合雅雄か、長谷川宏訳の『法の哲学』ヘーゲルを贈っていたんですが、次はこれにしようと思うぐらい。
目次は以下の通りで、社会という謎に社会学者がいかに立ち向かっていったかをそれぞれの学者を1章ずつ解説していくというスタイル。
第1章 「社会学」のはじまり 社会という謎
第2章 カール・マルクス 資本という謎
第3章 エミール・デュルケーム 連帯という謎
第4章 マックス・ヴェーバー 行為という謎
第5章 ゲオルク・ジンメル 距離という謎
第6章 シカゴ学派とミード アメリカという謎
第7章 パーソンズとマートン 秩序という謎
第8章 亡命者たちの社会学 ナチズムという謎
マルクスが手をつけた資本主義の解明から抜け落ちた個々人の意識など「不純な」領域を後の社会学者は研究していく、という見立ても、個人的にはわかりやすい!
そしてそのマルクスだけでなくデュルケーム、ジンメルといった社会学の始祖たちをはじめ、ナチスからアメリカに逃れたアーレント、アドルノ、フロム、マンハイム、エリアスとなんとユダヤ系の多いことか。
エスタブリッシュメントといえるのはヴェーバー、パーソンズぐらい。そのパーソンズの弟子であるアメリカ生まれのマートンもフィラデルフィアの貧困地区で育ったユダヤ系というのですから驚きです!社会から疎外されていたユダヤ系研究者だからこそ、その謎といいますか、綺麗な建前とは裏腹の暗いタブーを暴いたということでしょうか。
《マートンは1938年(『社会的行為の構造』の1年後)の論文「社会構造とアノミー」で、「アメリカ文化」は3つの文化原理によって成り立つと指摘します。第1に、「同じ高遠な目標がすべての人々に開放されている以上、万人はこの目標に向って努力せねばならない」という原理。第2に、「現在失敗だと思われているものも、最後の成功にいたる中間駅であるにすぎない」という原理。第3に、「真の失敗とは、大望を手加減したり引っ込めたりすることにほかならない」という原理。こうした原理は、もし失敗したとき、「批判の眼を社会構造から転じて自己自身に向けるようにする」でしょう。そして、アメリカ社会では、この「文化的目標」が全員に強調されるが、実現の「制度的手段」は明らかに不平等にしか配分されていない。果たしてこの「共通の文化」を共有するほど社会は秩序づけられるのか。マートンは、このとき生じるのはデュルケームのいう「アノミー」ではないかと論じます》(p.225)というあたりは現代的な格差社会の根底的な批判にもなっていると感じます。
個人的に共感できるのはジンメル。貨幣は人間を自由にする、という考え方はいいな、と(p-136-)。公課が現物から貨幣に置き換わった段階で、人格は生産物から分離し、要求は人格に及ばなくなる、と。また、貨幣を使う際の「相手はこれぐらいで折り合ってくれるだろう」と客観的に類推することによって主観的な衝動を抑えることもできるようになる、と。貨幣を所有するものは祖国を含めてどんな集団からも自由でいられる、と(もちろん、貨幣はもっとも掠奪しやすいものだから土地を所有できず貨幣しか持てなかったユダヤ人は掠奪の対象となるのですが)。
また、社交に関する考え方も素晴らしいな、と。たとえ個人としては高尚な心を持っていたとしても、社会をつくる基本は原始的で低俗な欲求なので、個人は味気ない思をしながら、「終わりなき日常」をおくっています。本当はもっと生き生きと生きていきたいのですが、宗教的な高揚などは勘弁してほしい…。こうした悲劇を解消するのは「社交」だ、と。社交は「内容と形式の分離」「転回」「遊戯」が本質。社交には目的も内容もなく、瞬間の満足があればいい。もし目的や内容が入り込むと社交は台無しになる。それらを隠し続ける時、社交は遊戯になる、みたいな(p.146-)。
IIとなる第9章はシュッツとガーフィンケル、第10章はゴフマン、第11章はフーコー、第12章はジェンダーと社会学として主にミレット、第13章は周辺からの社会学として主にウォーラースタイン、第14章はブルデュー、第15章はルーマンをそれぞれ取り上げています。
こちらは今秋出たばかりですが、読むのが楽しみ!
以下は補足。
奥村さんのゼミに参加していた方から別なSNSでコメントをいただいたのですがそれは「レインとかエリアスについての授業でした。話は面白いし、ユーモアがあって優しい人でした」とのことでした。『文明化の過程』のエリアスはわかるけど、レインには驚愕。「ひょっとしてR.D.レインですか?」と聞いたら、そうだとのこと。奥村先生は東大で宮台の後輩だったらしいのですが、こうした世代のひとまわり上の精神科医のおそらく半分はレインの『引き裂かれた自己』を読んで、その道を志したと言われてます*1。中井久夫先生がどこかで書いていたと思いますが、なんか奥村先生の「心のうぶ毛」を感じさせていただきました。『社会学の歴史II』も買ってあるので、今読んでる『宗教の歴史』を読み終えたら、さっそく、とりかかりたいと思います。
*1 《英国においてはもちろん-といってよいそうだが-わが国にも『引き裂かれた自己』によって精神科医になった世代が確実に一世代分はあり、その影響は今日まで続いている》『家族の深淵』「R.D.レインの死」中井久夫、みすず書房、p.207
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
