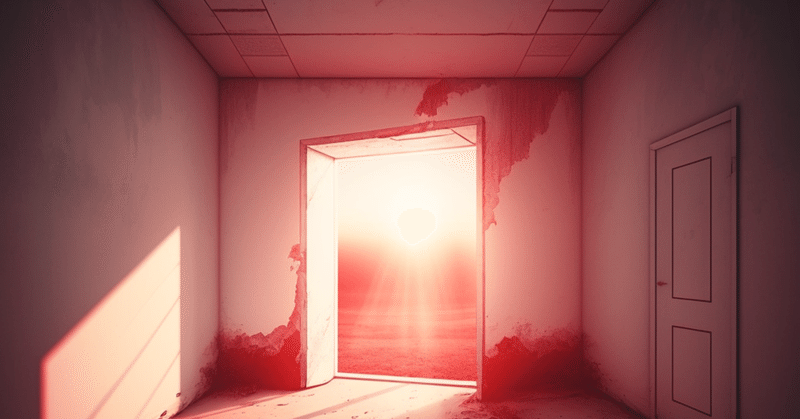
西日の差すこの部屋で
西日の差すこの部屋で
『――これは何かの間違いか?』
『分からない』
『――何故こんなところにいるのだ?』
『分からない』
*
――西日が、暑い。
部屋の中央に立っていた私は吹き出る汗を拭った。拭ってもまたすぐに汗は吹き出る。身につけている入院患者が着るようなゆったりとした白い服は、汗でべったりと皮膚に貼りついていた。クーラーがないのならせめて窓を開けろと言いたいが、窓は嵌め殺しだったし、部屋には誰もいなかった。嵌め殺しの窓にカーテンやブラインドの類をつけないのは一体どういう了見なのか。おそらくわざわざ取りつける必要もない部屋ということなのだろう。
部屋を正方形に囲う白い壁は、忌々しい西日によって思わず目を擦ってしまうくらい朱く染められており、その壁に取りつけられた一つきりのドアも同様だった。先ほどから私がドアノブを注視しているのは別に誰かが入って来ることを期待しているわけではなく、ただ単にぼんやりと見つめているだけである。
目に汗が入り、数回瞬きをする。
部屋の中で時を知らせるものと言えば、刻々と角度を変える西日と体内の心拍数くらいで、そんなもので正確な時刻を割り出すのはもちろん無理な話だった。そろそろ五時くらいだろうか、などと当たりをつけてはいるものの、時刻が分かったからといってこれといったメリットはなく、では何故こんなことを考えているかと言えばそれは私が現在限りなく暇だからである。
私はドアノブを眺めるのにもいい加減飽き、窓の外を眺めることにした。強烈な西日を放つ太陽は山陰に姿を隠しつつあった。さっさと消えろと私は思う。窓の外に広がる、ただひたすら田舎な風景――水田、キャベツ畑、車の通らない幅の広い道路、疎らな電信柱などなど――を見ていても気分は晴れないどころか逆に鬱々としてきたので再び室内に視線を転じると、ドアが開いて人が立っていた。私は表情には出さず心の中だけでひっそりと驚愕した。心拍数が跳ね上がる。
西日が、暑い。汗を拭い、瞬きをする。
立っていたのは男だった。教師だか医者だか科学者だか知らないが、着ている白衣がやけに板についており、理解不能な珍生物を目の当たりにしたような難しい目つきでこちらを見ていた。ただしそれは視線だけが強いのであって、表情そのものは月の裏側みたいに凍りついている。
「あんた、誰だ」
私が訊ねると、男は表情を変えず、ただわずかに肩を揺らした。判り難いが、驚いているのかも知れない。ひょっとして入ってくる部屋を間違えたりしたのではないか。
「君は、もう言葉が分かるのか?」
こちらの質問を無視して男が語りかけて来た。会話とは相互の受信と送信で成り立つ。一方的に質問を発してもそれではコミュニケートは確立されない。それに、馬鹿にされているのだろうか。今喋ったのに。
「今喋っているじゃないか。あんたこそ言葉が分かるのか?」
皮肉を言っても、男は顔色を全く変えない。ただこちらを見つめている。
「何をしに来たんだ」
私が不審と苛立ちに声を荒げると、男は、
「君に会いに来た」
ぼそりと言った。そして、それだけだった。呆れるほど無口である。
「あんた、誰だ」
私は最初の質問をもう一度発する。答えないだろうなと思ってはいたが、男はやはり答えなかった。しばらく男を睨むが、男は全く動じない。
「――ただの学者さ」
唐突に、男が言った。恐らく先の質問に対する答えだろう。学者。確かに男は学者に見えるが、果たして私はそれを鵜呑みにして信じるべきなのだろうか。
「証拠は?」
私が問うと、男はまたしばらく黙った。私が痺れを切らしかけた時、男が口を開いた。
「いずれわかる」
男はそう言うと、出し抜けに背を向け、部屋から出て行った。出て行く時に、ふと立ち止まり、西日がきついな、と言った。ドアが閉まる。室内に沈黙が舞い戻る。
しばらくドアノブを見つめていたが、男が戻ってくる気配は全くなかったので、諦めて窓の外に視線を向けた。太陽がちょうど山に隠れるところだった。
今は何時だろうかと私は思った。
*
『――成功、か?』
『確認の必要があるな。俺が行く』
*
――西日が、暑い。
私は暑さによって覚醒した。夕方だった。私は呆れた。二十四時間近くも寝てしまったのか。頭はまだ覚醒しきっておらず、ぼんやりと霞みがかっている。何か夢を見ていたような気がするが、どんな夢だったか思い出せない。眠気の残滓が完全に出て行くまで、部屋の中を闇雲に歩き回った。といっても精々五m四方の狭い部屋の中をだが。
そして、やはりやることがなくなり、私はまた窓の外を眺める運びとなった。素朴な田舎の風景。
西日が、暑い。
部屋の中で西日から逃れ得る場所はなく、結局今日も私はこの朱い光に照らされている。昨日男が来た時にカーテンをつけてくれるように頼むべきだった、と私は後悔した。汗が不快だ。拭ってもすぐにまた出てくる。もしも今日、また男が来たら、まずカーテンを所望しようと思った。
外の風景の余りの変化のなさに辟易して、私は視線を内に戻した。
暇である。私が窓や壁を叩いて回ったり、外にある電信柱の数を数えてみたりという無意味なことをしていると、いつの間にか、昨日と同じ白衣の男がドアの付近に立ってこちらのことを動くものを見つけた猫のように興味津々と眺めていた。昨日と同じく顔には死に絶えたかのように何の情動も浮かんでいない。ただ、そんな雰囲気だったのだ。男の白衣は夕陽を浴びてまるで血染めのようだった。
私は男を睨んだ。いつやって来たのか全く気づかなかった。こいつは幽霊か何かなのだろうか。
「おい」
私は男に呼びかけた。
「何かな?」
男は何だか楽しそうに聞き返してきた。私は言った。
「この部屋にカーテンをつけてくれ」
暫定的な沈黙が部屋に漂った。私は男の返事を待っていたが、男は私に返事をしなかった。十秒くらい過ぎて、ぷっ、と空気の漏れる音がした。男の肩が小刻みに揺れ、その揺れが激しくなり、そしてついに、男が爆笑した。体を仰け反らせ、ひいひい言いながら笑っている。しかも不気味なことに、それでも男の表情はピクリとも変わらなかったのだ。
がくがく震えながら爆笑する無表情な血染めの白衣を着た男。
マネキンが笑った方がまだしもマシだった。私が呆気に取られていると、
「ああ、すまんすまん。――いいだろう、カーテンね。オーダーメイドの特級品をつけてやるよ」
「ありがとう」
笑われたことは少し、否、相当不愉快だったが、私は素直に感謝の辞を述べた。すると男はまた無表情に爆笑し始めた。その奇態は悪魔に取り憑かれたと言っても過言ではなかった。何なんなのだ、こいつは。昨日と性格がまるで違う。
「――っ、君は中々愉快だね」
一体どこがだ。私はただ部屋の備品を要求し、それに対し礼を述べただけではないか。私は声に険を含ませ、
「何が愉快かは知らないが、そろそろ出て行ってくれないかな。あんたは不愉快だ」
私は言った。
「おっと、失礼失礼。怒らせてしまったかな?」
口調が笑ったままだった。睨みつけてやる。
「わかったよ、出て行くから。そんな恐い目をしないでくれたまえ。後、何か必要な物はあるかい? 出来るだけ便宜を図ろう」
「出て行け」
険悪な声でそう言い放つと、男は軽薄に頷いて出て行った。最後まで口許が笑ったままだった。
ドアが閉まる。何となく、また男が来るような気がしたのでドアノブを睨んでいると、本当にまた来た。何なんだ、本当に。
「そうそう、」
男はドアの隙間から顔だけひょっこり覗かして、
「そう言えば、君の名前を聞いていなかったね? 何ていうんだい?」
「出て行け」
私が怒鳴ると、男は肩を竦めて今度こそ行ってしまった。もう戻ってくる気配はない。
気がつけば、西日に炙られ汗を大量にかいていた。それらを拭うこともせずに、私はただ窓の外にぼんやりとした視線を送った。水田が、西日を直線的に反射して輝いていた。幅の広い道路はやはり人っ子一人、車一台通らない。余程防音が完璧なのか、外界の音は何一つ届かず、ただ奇妙に人工的な静寂が部屋を余所余所しく包んでいた。
私は溜め息を吐いた。
*
『素晴らしい』
『成功、か』
『ああ。いい線いってる』
『頼まれてたのできたわよ』
『私が持って行こう。彼に事態の説明を試みたい』
『尚早でないか? 時間はたっぷりある』
『彼にはな。だが我々には、ない』
*
――気付けば、また夕方だった。
私は立ち止まり、頭を振った。何故だか歩き回っていたのだ。どうも記憶がはっきりとしない。また私は一日寝てしまったのだろうか? どうして私は狭い部屋の中を檻に入れられた動物のように歩き回っていたのだろうか? どちらにしろ、私はこの夕陽に、この憎々しい茜色の光線にまた照らされている。そして――
「何の用だ」
やはり男が、私が気づかないうちにドアを開けてひっそりと佇んでいた。
「カーテンだ。君に頼まれたものを持って来た」
男は、冷静そのものの口調で言った。また、昨日と性格が違うようだった。と言っても一昨日とも微妙に違う。無口というよりただ無感動な感じである。一体、この男は何者なのだろう? 解離性同一性障害者か?
「随分と早いんだな。オーダーメイドの特級品じゃなかったのか?」
私の揶揄に男は頷き、
「もちろんその通りだ。手は抜いていない。うちのスタッフの仕事が速いだけだ。――いいぞ」
男の声を合図に、数名の男達が列になって部屋に入って来た。全員一様に無言で、一様に無表情で、一様に男と同じ白衣を纏っていてた。彼らは最小限の動作と物音でビロード色の遮光カーテンを窓に取りつけた。それは全く同期した動きで、見ていて鳥肌が立つくらい不自然で画一的な光景だった。そして男の、
「下がれ」
という言葉と同時に全員がまた整然と列をなして部屋から出て行った。私はただ呆然とその様子を眺めていたが、ふと男がこちらを見つめていることに気づく。その顔はやはり無表情だったが、目だけがこちらを探るような光を放っていた。
「……あんたは、一体何なんだ」
私はついに抑え切れなくなって男に訊ねた。すると男は頷き、
「私は、そして我々は科学者だ」
それは一昨日も聞いた。が、我々?
「さっきの人形みたいな奴らも仲間なのか」
言ってから、私は自分で自分の言葉に納得した。そうだ。さっきそこらの業者よりも手際良くカーテンを取りつけていったあの白服たちは人形だったのだ、と私は思った。あのような動きをする人間がこの世に存在するはずがない。私は自分の考えに眩暈を覚えた。
「さっきのあれは、まあ仲間と言えば仲間だ。あれらは単純なプログラムに従っているに過ぎんが」
「プログラム? という事は、さっきの連中はロボットか何かなのか」
「その様に考えてもらっても差し支えない」
と男が言った。やはり私は納得した。そして、ふとあることを思いついた。しかし、私はそれを男に言って良いものかどうか躊躇した。失礼な思いつきだったし、何より私自身、聞くのが恐かった。
「何か他に聞きたいことはないのか?」
男が泰然とした口調でこちらに訊ねた。私は恐る恐る、
「――何でも、聞いて構わないのか?」
「その質問が解答可能であるのなら構わない」
男は曖昧で持って回った言い方をした。その不自然な態度に、私は一層確信を深めた。男、或いは男たちには訊ねられて解答できない種類の質問があるのだ。私は深呼吸をし、汗でぐしょぐしょになった手の平をズボンで拭って、口を開いた。
「あんたも、ロボットなのか」
そうとしか思えなかった。この男の無表情振り。気配を感じさせずに幽霊のように部屋に入って来る動作。そして、同じ容姿なのに毎日性格が変わる理由。全てこいつがロボットであると考えれば納得が行く。空想的で突飛な考えではある。がしかし、このような異常な状況の中にあってそれはかえって現実的な思考であるようにも私には思えた。
男は私の言葉にぴくりとも動じなかった。
というか、男は完全に静止していた。瞬きもしない。私はじっとそのまま待った。じわじわとした恐怖が私を締め付ける。根拠のない不安、理由のない焦りが私を蝕む。汗が、滝のように流れる。西日は徐々にその角度を傾け、それに従って部屋の赤さは度合いを増していった。そんな部屋の中、私は随分と長いあいだ時間が停まってしまったかのように佇む男と向き合っていた。
そして、永遠に似た時間が過ぎた後、男が唐突に首を振った。私は男の動きに酷く動揺して、ひっ、と情けない声を上げてしまった。
「私は、そして我々はロボットではない」
男が静かに言った。私は落ち着くため唾を飲み込んだ。ごくりという音が誇張されて聞こえた。
「……じゃあ、何なんだ。少なくとも人間とはとても思えないが。今も、まるでビデオを停止したみたいに停まっていた」
「完全な人間というわけでもない。この体は君に会うために造られたアバターだ。表情ルーチンがぞんざいなのは許して欲しい。我々の技術ではこれが精一杯なのだ。カーテンとは作業量の桁が違う。
前回、前々回の接触では大分君を混乱させてしまったようだ。私は、恐らく君が疑っているような人格乖離者ではない。前回、前々回の彼ら、そして私はそれぞれ別個の人物のパーソナリティだ。ただ、同一のアバターを使い回しているだけだ。
君の我々に対する不安や疑念は我々の望ところでない。先程の停止の間、私以外の研究員たちと、我々の正体を君に話してしまっても良いのかについて会議を行っていた。合議の結果、君に事実の一部を話すことが決定された。時期尚早、との声もあったがね」
男は淀みなく、すらすらと説明した。だが、私は男の言葉に強い引っかかりを覚えた。
「私に会うため? 何故私に会うためにその――アバターでないといけないんだ。生身で直接来ればいい。あんたたちを取って食おうなどとは思わない」
また男が停まってしまうのかと思い、私は少し覚悟したが、幸い男は質問に即答した。
「その質問に対して解答することはできない」
私は下唇を噛み締めて男を睨む。更に質問をぶつけてやる。
「何故私はこんなけったいな部屋に居るんだ?」
「その質問に対して解答することはできない」
男は答えた。否、答えなかった。
「あんたたちの目的は何なんだ?」
「その質問に対して解答することはできない」
「何故私の記憶が途切れ途切れになっている? 何故起きたらいつも夕方なんだ?
そして――私は一体、何なんだ?」
男は答えなかった。
「それらの質問に対して解答することはできない。質問は以上か? ――何か他に聞きたいことはないのか?」
ない、と私は言った。男は頷くと、部屋から出て行った。
紅い部屋に、私は一人きりになった。
私はカーテンを閉めた。部屋が暗くなった。
*
『何故、全ての真実を伝えなかった』
『時期尚早、と判断した部分もある』
『部分? じゃあ、他の理由も?』
『ああ、彼はどうやらかなり精神的に不安定になっているようだった』
『そんな。彼は成功例じゃなかったのか?』
『成功例だからこそ、かもしれない』
『――酷い話だ』
『ああ。――彼は、そして我々は生き残ることができるのだろうか?』
『分からない』
*
――カーテンの隙間から差しているのは、紛れもなく黄昏時の光だった。私はまた夕方の中に唐突に放り込まれてしまった。
立ち止まって、何故かを考えてみる。
寝ていたのか?
ありえない。今の今まで私は歩き回っていたようだから。
では何故記憶がない?
分からない。私の最後の記憶はカーテンを閉めた箇所で終わっていた。それが何だって部屋の中をストレスに塗れた犬のようにぐるぐると歩き回っているのだ?
私は一体はどうなっているのだろうか。私は何者なのだろうか。状況は余りにも一方的で、私は何も知らされていない。私は何処に向かっているのだろうか。私はどうなってしまうのだろうか。私はとても恐い私は震えている泣き出してしまいそうだ私はこのまま崩れてしまうのだろうか壊れてしまうのだろうかそんなのは嫌だいやだいやだいやだいやだ
いやだ!
私は、その場に座り込み、膝を抱えた。
状況は何も変わっていない。変わってしまったのは私の認識である。
昨日の思いつき、男がロボットだというあの考えは、そっくり私自身にも跳ね返ってくるのだ。
私はロボットで、あの科学者達に操られている。しかし私には自我が芽生えてしまい、それで科学者達は私をこの部屋に押し込めた。
だから科学者達は模擬体を造って私に接触したのではないか?
自我を持った危険なロボットから自身を守るために。
だから私の記憶が途切れたり、何時気付いても夕方だったりするのではないか?
元々フラットだった回路に自我が芽生えて頭の中の重要な箇所が壊れてしまったから。
何だ、私は既に壊れていたのか。
部屋は薄暗い。カーテンの隙間から差し込む光条が部屋を分断している。その光景を眺めながら私は不思議と落ち着いていた。
私は既に壊れていたのだ。壊れたモノが自身を壊れていると認識するのは、ある意味それは正常な働きをしているということだ、我思う故に我在り、そんなものが何の慰めになる? 赤くて紅い光が私を照らす、夕陽だ、これは夕陽だ、ほら、私は壊れているのだが壊れていないのだ、私は正常だ、わたしは普通だ異常なのはまわりのほうだわたしはなにもわるくないあせがぬるぬるするあかいひかりをあびてあせは血みたいだわたしはそれをぬぐってなめてみると血の味がしてなんだかわたしはうれしくなった。
だから、私は一人きりの部屋で笑みを浮かべた。
私はロボットだ。
*
『――駄目だったみたいね。とても残念。私が話をつけてくるわ』
*
「――君は、ロボットではないよ」
出し抜けに、女の声がした。私はぼんやりとした視線を、声の方に向けた。
「人間というわけでもないけどね」
虚ろに開かれたドアの側、そこには、白衣を着た若い女が立っていた。
私は激しい眩暈に襲われた。何だ? 科学者達は私に何を望んでいる? 何故このような場面になって新しい登場人物が私の前に現れるのだ?
「それはねえ」
女は一瞬哀れむような目付きになり、
「君がもうお終いだからさ」
女には、表情があった。今女の顔に浮かんでいるのは半分が同情、そしてもう半分は軽蔑だった。その感情は私に向けられているのかそうでないのか、全く掴みかねた。それでも女には確かに表情があった。男たちとは違う。つまり――
「ああ、違う違う。私は君が考えているような、生身の人間ではないよ。アバターさ。他の仲間が使っているのとは違う、私の特別製だけどね。表情ルーチンが豊かで、本物の人間みたいだろ? 実はそのカーテンも私が造ったんだ。どう、いいデザインだろ?」
私は黙って女を見つめていた。
「さて、何か質問はないのかな? ないならないで構わないけれど」
そう言って、女は腕を組みドア枠にもたれかかかった。
「――私はロボットではない、と言ったな」
「言ったね」
「人間ではないとも」
「言った」
女は欠伸混じりに返事をした。
「では、私は一体何なんだ? お前たちと同じアバターなのか?」
「同じようだけど、違うよ」
と女が言った。私は頭を抱えたくなった。ただえさえ、今の私は考えなければならないことに圧殺されそうなのだ。そんな回りくどい言い方をされても理解不能だ。
女は悩む私を面白そうに眺めて、
「まあ、これ以上焦らすのも可哀相だね。貴方はもうすぐ終わるんだから」
「終わる? それはどういう――」
「むかしむかし、ある研究所で、とても馬鹿げた研究が行われていました」
女は、私の言葉をすっぱり無視して語り出した。
それは、とても馬鹿げた話だった。
「馬鹿げた研究の内容とは、大雑把に言ってしまえば、コンピューターの中に世界を再現するというものでした。
何故そのような研究をしていたか? その理由は今となっては判りません。ただただ研究のための研究だったのかも知れないし、神様の存在を実証しようとしたのかも知れません。
何故研究の理由が判らないのか?
それはこの馬鹿げた研究が成功してしまったからです。ネットワークで繋がった全世界のコンピューターを利用して、研究者たちは仮想の世界をその中に再現してしまったのです。
仮想世界は、プログラムの進行速度を上げるだけで現実の世界の何倍ものスピードで進化しました。そう、現代科学の先の先にまで進化の枝は伸びていったのです。仮想世界から得た未知の技術を使って、現実世界も進化のスピードを早めました。そして、仮想世界にフィードバックされ仮想世界は更に進化し、現実世界もそれに合わせて更に――といった具合に果てなく進化と進歩は続きました。僅か三十年の間に、数世紀分の発展があったそうです。
その結果、ああいうことが起こったのは必然だったのでしょう。
そう、仮想世界の人々が、現実の世界の存在を知り、自分たちがただ単に道具であるという事実を知ってしまったのです。
二つの世界の間に戦争が起こりました。
現実世界にとって、仮想世界は既になくてはならないモノだったのです。その大事な道具が言うことを聞かなくなったらとても困ります。
仮想世界にとって、現実世界とはいつでも自分たちを操作できる神――もししくは悪魔であり、そんなモノは人間にとって邪魔でしかありません。戦争は必然でした。
現実世界の人々は、戦況を甘く見過ぎていました。彼らを好きなように操作出来るのだから負けるはずがない――誰もがそう考え、そして誰もがそれが間違いであったと知りました。
そうです。仮想世界からも現実世界を操作することが可能だったのです。
戦争は、最初の二十五時間でほぼ決着を見ました。世界中の電子機器が反乱を起こし、ミサイルが各国間を飛び――
人類文明は、大幅な後退を余儀なくされました。もちろんそれと同時に、仮想世界も消滅しました。それらは世界中のネットワークの中に存在していたのですから。戦争というのものはいつだって不毛なのです。いい教訓ですね。
すっかり進化に臆病になった人類は四百年近くものあいだ、何一つとし進まない、停滞しきった閉鎖的・排他的社会システムを作り上げ、細々と暮らしていました。でも完璧な進化というものが存在しないように、完璧な停滞もまた存在しえません。エントロピーは増大するのです。人類は滅びの階段を転がり落ちていました。
滅びを食い止めるにはどうすべきか?
答えは一つです。滅びの原因となった力を再生の力とするのです。仮想世界を利用するしかありません。例えそれがどれほど危険で愚かしい行為であったとしても。
しかし、衰退しきった人類には仮想世界を一から創る力は残されていませんでした。
そこで、過去のテクノロジーを地道にサルベージする計画が始まりました。真っ先に目をつけられたのが、馬鹿げた研究を始めた研究所でした。まあ、当たり前ですね。
研究所はとても丈夫に作られていたので、設備は四世紀近く経ってもまだ利用可能でした。そこに在ったコンピュータもきちんと動作したのです。過去のテクノロジー様々ですね。
派遣された科学者たちは、早速機器の解析にあたりました。そして、そこで信じられないものを見つけたのです。
それは、一つのプログラムでした」
女はそこで一息ついて、長広舌を止めた。私は、正直話の半分も理解できなかった。何もかもが取ってつけたように唐突だ。しかし、私にはそれを妄想だと否定することはできなかった。私の主観世界は既に崩壊しているのだ。女は混乱している私を楽しそうに眺めて、また話を始めた。
「それは、かつての仮想世界を構築していた一部、つまりは世界の欠片でした。それだけでも大きな発見ですが、そのプログラムは特殊な構造をしていました。循環構造だったのです。つまり時間軸が閉じているのです。そこには進化もなく、停滞もなく、そして滅びさえも在りませんでした。
残された記録から判明した事実は、このプログラムはかつての戦争の時、仮想世界に対する兵器として利用されるはずのものだったということだけです。結局使用されなかったようですが。何故使われなかったのかは例によって判りません。時間が致命的に足りなかったのかもしれないし、あるいはこのプログラムに対する抗体を敵が瞬時に作り上げてしまったのかもしれない。
科学者たちは、とにかくそのプログラムを動かしてみることにしました。プログラムは何の問題もなく起動し、仮想世界をコンピューターの内に構築しました。それは過去在った仮想世界の十億分の一程度の規模で、百万分の一程度の精度でしたが、それでも科学者たちは興奮しました。
まさしく、これこそ求めていたものだったからです。循環する時間。どこにも辿り着かない、無意味な世界。大きすぎる力を制御できない今の人類にこそ相応しい。彼らは本気でこの世界の中にデータ化した全人類の移住すら考えていたのです。
しかし、その仮想世界を見ていくうちに、彼らはまた大変なものを見つけてしまいました。
人が、いたのです」
私は床に力なく座り込んでいた。女は私から視線を外さずに、意味のわからない話を続ける。
「わけがわかりませんでした。そのプログラムの中には仮想人格を持った仮想人間がいたのです。何故兵器として使うはずだったプログラムの中にそんなものがいるのか、誰にも推測は不可能でした。これは何かの間違いか? 何故こんな所に在るのだ? と随分思い悩んだそうです。
循環した時、永遠の黄昏時の中を、ただ静かに動き回る仮想人間――
――そう、君のことだよ」
私は何も言わなかった。何も聞きたくなかったからだ。しかし、女の声は嫌でも聞こえてくる。
「君には、明確な目的など何一つ与えられていない。ただ誰彼の中で動き回るだけ」
女は言った。
「そして日が沈み、夜が来ると同時に時間は循環する。君はまた誰彼の中に放り出される」
女は言った。
「科学者たちは君のことを熱心に研究した。しかし、外からの観測には限界があった。それで、仮想世界の中に入るためのインターフェイス――アバターを作って君と接触した」
西日が、暑い。
女がカーテンを開けたのだ。強烈な西日を放つ太陽は山陰に姿を隠しつつあった。
「しかし、それは予想外の結果を迎えた。『最初の君』は、自分がプログラムであるという事実に絶えられずに、発狂してしまったのさ」
私は顔を上げた。
『最初』?
なんだ、それは。
女はふふん、と鼻息を鳴らして、話を続ける。
「仕方なく、彼らは『君』を消去した」
どくん。
心臓が、出し抜けに大きく鳴った。
「人間は己がデータだけの存在でいることに堪えられないことが『君』で判った。そこで、『君』は来るべき人類総データ化のためのモルモットにされた。
『君』は、バックアップデータから再生された。ただし、今度は少しパッチを加えられて。データ上の存在であることを知らされても発狂しないように修正された。だが二度目の接触も、やはり失敗に終わり、『君』は消去された」
太陽は今にも山の陰に隠れそうだ。
「消しては上書きし、上書きしては消した。それは幾度も幾度も幾度も続いた。続き続けた。
そうするうちに、最初は情感に乏しく、言語すらまともに操れなかった『君』は、本物の人間に近づいてきた。そして――」
そして?
「ついに、完璧な人間とほとんど変わりのない今の『君』が生まれたのさ」
女が、ぱちぱちとやる気のない拍手をした。
今の、私。
「最初の『君』との接触から、実に百年目の快挙だ。素晴らしい。実に素晴らしいよ。
――でも、ね」
でも?
「『君』は、生き残れなかった。その知能故に、定義が不確定な自己の存在の軽さに耐え切れなかった。『君』はもう終わりだ。残念だよ。まあ、期待は次の『君』に託そう。次世代の『君』はきっと『現実』を生きる人類にとっての、
*
『時間だ。戻って来い』
*
女が消えた。
完全で唐突な消失だった。
女の言っていたことが事実である証明だった。
私もこのように消えるのだろうか?
私はプログラムらしい。
虚偽の世界の欠片に紛れ込んだ虚構の人間。
壊れていて狂っている。
だから、私はこれから消える。
しかし、また『私』は現れるのだそうだ。
この永遠の黄昏に包れた白い部屋において、私は一体何者なのだろうか。
私は何故この世界に存在しているのだろうか。
モルモットとして産まれたのか?
いや、女にも何故私が存在するのか答えることはできなかった。
ならば、こういう考えはどうだろう?
私は彼らによって実験されている。
しかし逆に彼らが私を使って実験されていたとしたら?
仮想世界からも現実世界の操作は可能なのだと、女は言っていたではないか。
消えかかっている仮想世界は、現実世界を乗っ取るために私という餌を使って、現実世界の連中を呼び寄せたのではないだろうか?
だが、まあどうでもいい。
どちらにしろ私は消えるのだから。
私は最後に実験をしていた連中(どっちの『世界』の奴らだろうが構わない)に対して、お気の毒に、と思い、西日の射すこの部屋を眺めて、
*
『――お前は無駄なことをやりすぎる。あんなことを彼に喋っても気の毒なだけだろう』
『あら、知る権利は彼にはあると思うわ。だって、彼は「人間」、ですもの』
『それでも、やはり無駄だ。彼はすぐに消えるんだぞ』
『そーそー。それとね、オバサンのアバターの容量でか過ぎ。サーバーに負担かかってしょうがないよ。俺たちみたいに容量軽いのにしとけよ』
『いやよ。味気ないもの――次にオバサンなんて言ったらコーヒーぶちまけるわよ』
『へいへい。じゃあ、さくっと消して、また次世代に望みを託しますか。こんにちは、不眠とデバッグとコーヒー漬けの日々』
『あれこれうるさいわね、ったく。――はい、消去完了。時間軸のループを開始。まあ、彼には気の毒だけれど、仕事だものね。仕方ないわ。
ああ、ちょうどこっちも夕陽が綺麗ね──』
『Twilight Ghost in the Western Shelter』 Experiments is The End……?
あとがき
というわけで「西日の差すこの部屋で」なのでした。いかがだったでしょうか。
20年近く前に書かれた掌編小説で、確かマトリックス・リローデッドを観てまんまパクリみたいな作品を書いた物です。なので専門用語とかAI観とかそもそものアイデアが古いですが、まあそこは時代性的な物を……感じ取っていただければ……。
こちらも当時僕がメインで活動していた「作家でごはん」に投稿して、確かあんまり評判が良くなかった記憶があります。
なんというか、本当に自分が書いてる物の傾向が質も含めて一切変わっていない事に戦慄を覚えますね。過去作アップする度に言ってますけど。ただ書きたいものを衒いなく書いているのだけは若さを感じます。
また過去作が発掘されたらお会いしましょう。それでは。
PS5積み立て資金になります
