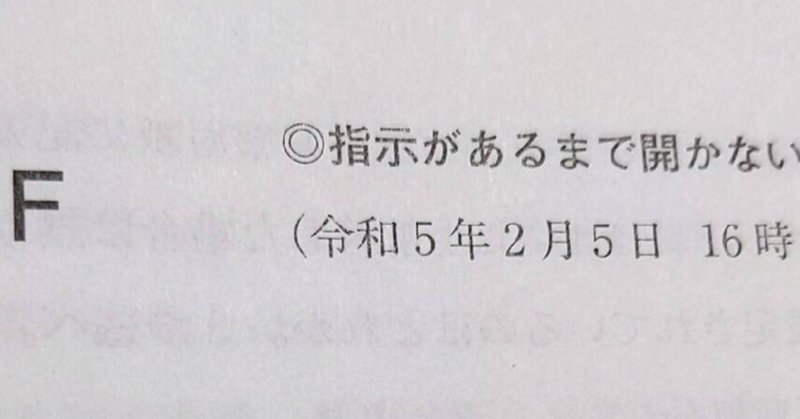
117回医師国家試験Fブロックの振り返り
最後のブロック、体力は残っているつもりだったが、手汗がでてきてたしアドレナリンで頑張ってた気がする。前日と違って公衆衛生がほぼ出題なく、おかげで体感の得点率は8割強、自己採点すると92%だった。禁忌を踏んでないかチェックと復習のために、このページにまとめます。
117F10 畜尿症状はどれか(65%)
尿意切迫感と夜間頻尿が正解。「畜尿症状」の意味が解せず、尿意切迫感と腹圧排尿を選んでしまった。押したら出るって畜尿の問題のように思えて。よく考えたら、尿意切迫感と夜間頻尿(夜間にも尿意)は元は同じなのでこれらを選べたはずの気もする。本番での思考不足とも言えそう(考えても答えが出ないと思ってこの問題に優先的に時間をかけなかったので、作戦の失敗とも解釈できそう)。
117F13 副腎腺腫によるCushing症候群で認めないもの(正答率86.3%)
正答は色素沈着。どうも内分泌の基本問題でありながら正答率が9割を下回っている問題が多く、「内分泌をはじめから捨てている」人が一部いるかもしれないと感じる。
117F14 出生後緊急で治療介入が必要な疾患(正答率89.7%)
一方この問題の正答率が意外と高い。正答は完全大血管転位症。ASDとVSDは多くの人が切れると思う。心内膜症欠損症が該当しないとは私は知らなかったが、正答選択肢のTGAが「生後間もないチアノーゼ」であることは記憶しており、なんとか正答できた。先天性心疾患は広く浅くの様相が強く対策しづらいと感じていたが、意外とみなやっている?
117F15 挫滅症候群で高値を示さないもの(正答率44.5%)
正答はカルシウム。自分はヘマトクリットと少し迷って正答していた。循環に問題は生じそうだから、ヘマトクリットは動きそう。カルシウムは腎不全が起こって低Caかもしれないという、かなり苦し紛れのこじつけ解釈をして、正解選択肢を選んでいた。
117F17 自我意識について(正答率49.5%)
かなり基本問題と思ったが、対策していない人が多かったのだろうか。文系的概念で理解しづらい人もいるのだろうか。予想外の正答率。
117F18 食思不振と体重減少(正答率70.4%)
副腎不全と副甲状腺機能亢進が正答。どちらも高カルシウム血症で説明付くと思ったら合っていた。褐色細胞腫では食欲低下のイメージはなかったが、自信は持てなかった。
117F19 待機的に行う全身麻酔化の手術で、術前に確保すべき絶飲時間(正答率94.5%)
2時間が正解、6時間は不正解。自分は4時間ほどだったと記憶しており、不正解のほうを選んでしまった。
117F25 末梢血好中球について(正答率27.8%)
減少症の原因は薬剤性が多い、副腎皮質ステロイドで増加する、の2つが正答。他が明らかな誤りだったが、そのうち「末梢血多核白血球の約60%を占める」は「末梢血白血球の約60%を多核球が占める」のひっかけだと気づいたのが見直しの時だった。FNは薬剤性(チアマゾールや放射線/抗癌剤)以外には思いつかなかったため、薬剤性が最多というのは正しいのかと予想したら合っていた。正答率が低いのは意外。
117F26 デルマドロームの問題(正答率54.5%)
今年は最後まで皮膚科が多いなと思った問題。日光角化症がデルマドロームでない。推測で当たった人も多いと思うが、それでも54%なのか。
117F31 迅速病理診断について(正答率51.9%)
2つの正答選択肢のうち、1つめ「切除範囲の決定が目的のひとつ」は手術見学をまじめにしていたら分かると思うが、2つめ「凍結してから切片を作成」は病理で実習していなければ難しいかもしれない。過去問か何かの解説で見たこともあるが、正答率が低いみたい。
117F35 カプセル内視鏡の計画の際に注意(正答率56.2%)
頭部MRAの検査予定日、が正答。思いのほか低い正答率で、みな疲れていたのかしら。さすがに内視鏡には金属が含まれているかなぁ、MRIにせずに「MRA」とするなんて嫌らしいよなあと思いつつ、これを選んだ。
117F42 オピオイドローテーション(正答率59%)
塩酸モルヒネを経鼻胃管から投与する、が正答で想定外。経鼻は余計しんどくするから不適切だと思ったんだが。自分は経口投与が無理なら点滴静注かと思ったのだが、経鼻胃管にするのがWHOの原則に合っているということか、、なるほど。
117F49 ポリファーマシー関連(正答率68.9%)
カルシウム拮抗薬が正答。ビスホスホネートと迷ったが、カルシウム拮抗薬は肝代謝であることと、血圧160/96はやはり高いのでこれを選んだら合っていた。腎障害と高K、活動性の低下があることからNSAID、ACE阻害、ベンゾジアゼピンは真っ先に除外、ビスホスホネートは高Ca血症(主訴食欲低下と関連?)への対処の必要性から切りづらかったが、むしろ主訴であるからこそ別の介入が必要なのかと解釈して、腎代謝なのかどうかわからなかった、こちらを選ばないことにしたら合っていた。
117F52 胎児発育不全で胎児の健常性評価(正答率82.8%)
推定胎児体重、羊水ポケット、胎児呼吸用運動が正答。子宮動脈血流速度波形を選んで間違えてしまったが、胎児MRAのひっかけだったのかもしれない。羊水ポケットも胎児自体ではないから、これと子宮動脈と迷ったのだが、血流自体の方が参考にはなると考えて羊水より子宮動脈の方を選んだら不正解だった。自信はなかったが、正答率82.8%あり、この問題は「設問者の意図を読む(ひっかけに気づく)」ことができるかどうかを問う問題だった(自分にとって)。
117F58 痛風発作の原因にならないもの(正答率85.9%)
スタチンはならない、が正答。降圧利尿薬と迷ったが、脱水が原因になるなら利尿薬も原因になると考えるべきだったのか。調べたところ、ループ利尿薬ではトランスポーターへの作用で尿酸排泄が低下する、らしい。設問がわざわざ「降圧利尿薬」と表記されており、出題者の何らかの意図を推察できてもよかったかもしれない。
117F64 II型呼吸不全の酸素管理(正答率52.9%)
NPPVが正答。過去問にかなり同じ状況の問題があり、この正答率は意外。酸素は低すぎず、かつ高い二酸化炭素が換気不十分を示唆しており、強制換気が妥当と感じた。
117F71 A-aDO2の計算(正答率68.9%)
FiO2の数値がなくて困った。FiO2=0.21とすると149.73となるところを150と近似し、150-(PaCO2/0.8)-(PaO2)=66Torrとなったが、正解は65Torrだった。FiO2を0.20とするべきだったのか、149.73のまま計算すべきだったのか、追及する気力がないが、医学知識や計算力を問うている問題ではなさそう。
117F75 推定細胞外液量の計算(正答率35.3%)
体重の60%が水で、内訳は40%が細胞内、20%が細胞外、という知識で解いたが、問題文中に身長やBMI、腹囲、体脂肪率の値も含まれており、最後に気を散らせる作戦か。仮に何か詳しい推定式があるとしても、誰も知らない問題は採点除外になるはずだから、あくまで素直に「体重の20%が細胞外液」の知識を基に計算したら合っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
